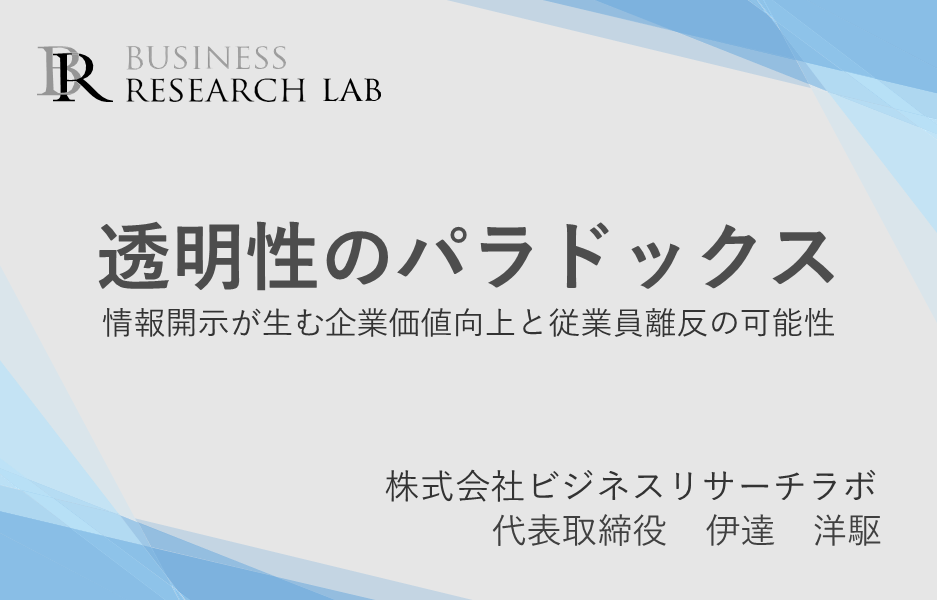2025年10月8日
透明性のパラドックス:情報開示が生む企業価値向上と従業員離反の可能性
社会や経済のあり方が変わろうとしている今、「人的資本」という言葉を耳にする機会が増えました。かつて企業価値を測る主な尺度は、工場や設備、製品といった「目に見える資産」でした。しかし、知識や情報が価値を生み出す現代において、企業の競争力の源泉として、そこで働く人々の持つ知識、スキル、経験、創造性、あるいは意欲といった「目に見えない資産」に関心が集まっています。
ただ、この「見えない価値」を、どのように捉え、どのように社内外に伝えていけば良いのでしょうか。この問いに答えるための一つの試みが「人的資本開示」です。企業が自社の人的資本に関する情報を、投資家や社会に向けて公開する動きが広がっています。
しかし、この人的資本開示、一口に言ってもその実態は様々です。どのような情報を開示すれば企業の価値は高まるのか。企業のどのような体制が情報開示を促したり、あるいは妨げたりするのか。開示された情報は、働く人々の心にどのような変化をもたらすのか。そして、そもそも「開示」という行為を、私たちはどのように客観的に評価できるのか。
本コラムでは、こうした人的資本開示をめぐる疑問に光を当てるべく、世界で行われている最新の研究動向を紹介していきます。それぞれの研究が、どのような問いを立て、どのような方法で答えを見つけようとし、そしてそこから何が見えてきたのか。各研究を丹念に見ていくことで、人的資本開示の複雑で奥深い世界を垣間見ることができるでしょう。
人的資本開示は保険企業の市場価値を高める
企業が持つ「人」という資源、すなわち人的資本に関する情報を外に向けて発信することが、その企業の経済的な評価、例えば株価のような市場での価値にどのような変化をもたらすのか。これは、人的資本開示を考える上で根源的な問いの一つと言えます。とりわけ、顧客との信頼関係や専門的な知識がビジネスの根幹をなすような業界では、従業員の質や能力が企業の成長に直結すると考えられます。その一例として、保険業界を取り上げ、人的資本に関する情報開示と企業の市場価値との関わりを調べた分析があります[1]。
この分析は、ナイジェリアの保険企業に着目して行われました。ナイジェリアの保険業界は、経済活動におけるリスク管理の担い手として、企業活動を支えています。こうした業界では、高度なスキルと専門知識を持つ人材の育成と維持が、事業運営の生命線となります。そこで、研究者たちは、企業が従業員のトレーニングや能力開発、健康と安全への配慮、キャリア形成の支援、退職後の生活設計への関与、そして障害を持つ人々の雇用といった人的資本に関する情報をどの程度開示しているか、そしてそれが企業の市場価値とどう関連しているのかを検証しました。
具体的には、ナイジェリア証券取引所に上場している保険企業の中から7社を選び出し、2014年から2023年までの10年間の年次報告書を調べました。年次報告書の中から、先に挙げた人的資本の各要素に関する記述を探し出し、その開示の度合いを評価したのです。そして、これらの開示度合いと、各企業の市場価値(株価などを基に算出される指標)との間に統計的な関連があるかどうかを分析しました。
分析の結果、いくつかの点が浮かび上がりました。従業員のトレーニングと開発に関する情報を開示している企業ほど、市場価値が高いという関連が見られました。この背景には、企業が従業員のスキルアップに投資していることを投資家が好意的に評価し、将来の収益性向上を期待することが考えられます。高度な専門性が求められる保険業務において、人材育成への注力は企業の競争力に直結するという認識が市場にあるのかもしれません。
従業員の健康と安全に関する情報の開示も、市場価値とプラスの関連があることが確認されました。従業員の心身の健康を守り、安全な労働環境を提供することは、生産性の維持向上だけでなく、企業の社会的評価や従業員の定着率にもつながる可能性があります。こうした取り組みを開示することが、投資家からの信頼獲得に寄与していると解釈できます。
従業員のキャリア開発に関する情報の開示についても、市場価値との間にプラスの関連が見られました。従業員が自身のキャリアパスを描き、成長できる機会を提供している企業は、優秀な人材を惹きつけ、維持しやすいと考えられます。これもまた、長期的な企業価値の向上につながる要素として、市場が評価しているのかもしれません。
障害者の雇用に関する情報の開示も、市場価値とプラスの関連が見いだされました。障害者雇用への取り組みは、企業の社会的責任(CSR)の一環として、あるいは多様な人材活用による組織活性化の観点から、企業イメージの向上や新たな価値創造につながると投資家が判断している可能性があります。
一方で、従業員の退職計画に関する情報の開示は、企業の市場価値との間に明確な関連が見られませんでした。これは、他の要素とは異なる結果です。この理由としては、退職計画に関する情報が、企業の将来の収益性や成長性に対する投資家の期待に結びつきにくい、あるいは開示されている情報の内容や質が、投資判断の材料としては不十分であるといった可能性が考えられます。
CEO兼任は人的資本開示を抑制するが独立取締役が緩和
企業の市場価値と人的資本開示の間につながりが見えてきましたが、そもそも企業がどれだけ人的資本に関する情報を開示するかという姿勢は、どのような要因によって左右されるのでしょうか。企業の意思決定、特に情報開示のような戦略的な判断には、経営トップのリーダーシップのあり方や、取締役会の構成といった企業統治の仕組みが関わっていると考えられます。スペインの企業を対象に行われたある分析は、この点に光を当てています[2]。
この分析では、企業の最高経営責任者(CEO)が取締役会の議長も兼任している状態、いわゆる「CEOデュアリティ」が、人的資本情報の開示にどのような作用を及ぼすのか、そして、取締役会における独立取締役の存在が、その作用にどう関わるのかを調べています。人的資本開示とは、企業が従業員の知識、スキル、経験、能力といった人的資源について、自発的に情報を公開することを指します。
研究者たちは、いくつかの理論的な枠組みを基に考察を進めました。例えば、資源依存理論は、企業が外部環境から必要な資源を獲得するために、取締役会のような仕組みを通じて外部との関係を構築すると考えます。また、ステークホルダー理論は、企業が株主だけでなく、従業員、顧客、地域社会といった多様な関係者の期待に応える責任があり、情報開示はその一環であると捉えます。正当性理論は、企業が社会的な規範や期待に沿った行動をとることで、その活動の正当性を獲得しようとすると説明します。
これらの理論的背景から、経営者の権限集中や取締役会の監視機能が、情報開示の姿勢に影響すると予想されました。
具体的には、次のような仮説が立てられました。第一に、CEOが取締役会議長を兼任している場合(CEOデュアリティ)、経営者の権力が集中しやすく、外部からの監視が働きにくくなるため、企業にとって必ずしも有利とは限らない情報(例えば、人的資本投資の不足など)の開示に消極的になるのではないか、つまり人的資本の開示は低下するのではないか、というものです。
第二に、取締役会における独立取締役の割合が多い企業ほど、経営陣からの独立性が保たれ、株主や他のステークホルダーの利益を代弁する形で、企業情報の透明性を高めるよう働きかけるため、人的資本の開示は増加するのではないか、と考えられました。そして第三に、もしCEOデュアリティが人的資本開示にマイナスの作用を及ぼすとしても、独立取締役の存在がそのマイナスの作用を和らげる、すなわち監視機能を果たすのではないか、という仮説です。
分析の対象となったのは、スペインの株式市場(IBEX35)に上場する代表的な企業21社で、2007年から2016年までの期間のデータが用いられました。各企業が公開しているCSR報告書や統合報告書から、人的資本に関する開示情報を集め、その内容を分析しました。人的資本開示の度合いを測るために、研究者たちは24項目からなる独自の指標を作成し、各項目について開示されていれば1、されていなければ0として点数化しました。
分析の結果、CEOデュアリティの状態にある企業では、人的資本の開示レベルが有意に低いことが明らかになり、第一の仮説が支持されました。これは、経営トップに権限が集中すると、情報の透明性よりも経営の自由度や裁量を優先する動機が働く可能性を示唆しています。企業にとって都合の悪い情報や、戦略的に秘匿しておきたい情報が人的資本関連事項に含まれる場合、開示を控えるという判断がなされやすいのかもしれません。
独立取締役の割合に関する第二の仮説については、予想とは異なる結果が出ました。独立取締役の割合が高い企業の方が、むしろ人的資本の開示レベルが低いという関係が見られたのです。これは、独立取締役が必ずしも人的資本情報の開示を推進するとは限らない可能性を意味しています。例えば、独立取締役が企業の競争戦略上の観点から、人的資本に関する詳細な情報の開示が競争相手に有利な情報を提供してしまうリスクを懸念したり、あるいは、開示コストや潜在的な法的責任を考慮して、慎重な姿勢を取ったりすることも考えられます。
しかし、第三の仮説、独立取締役がCEOデュアリティのマイナス作用を緩和するという点については、支持される結果が得られました。CEOが議長を兼任している企業であっても、独立取締役が多くいる場合には、CEOが議長を兼任していない企業との開示レベルの差が縮まる、あるいは、CEO兼任による開示抑制の度合いが弱まるという相互作用が確認されました。独立取締役が、経営者の独断を牽制し、一定の透明性を確保する上で、やはり何らかの役割を果たしていることを示唆しています。
たとえCEOに権力が集中していても、外部の視点を持つ独立取締役が存在することで、ステークホルダーへの説明責任を果たす必要性が認識されやすくなるのかもしれません。
人的資本開示は企業規模で内容差が少ない
企業統治の構造が人的資本情報の開示姿勢に影響を及ぼすことが分かってきましたが、それでは、企業の「大きさ」、企業規模によって、開示される人的資本情報の内容や量に違いは出てくるのでしょうか。一般的に考えれば、大企業の方が経営資源に余裕があり、社会的な説明責任もより強く求められるため、人的資本に関しても詳細かつ多岐にわたる情報を開示しているのではないかと予想されます。この疑問に答えるため、アメリカのS&P500指数を構成する企業を対象に、大企業と小企業とで人的資本開示にどのような違いがあるのかを比較した調査があります[3]。
この調査の背景には、2020年11月からアメリカ証券取引委員会(SEC)が上場企業に対し、年次報告書の中で人的資本管理に関する情報を開示するよう義務付けたという規制の変更があります。
この新しいルールでは、具体的に何を開示すべきかという詳細な項目は定められておらず、企業が自社にとって重要と判断する内容を裁量で開示するという「原則ベース」のアプローチが採用されました。そのため、企業ごとに開示する情報の内容や量にばらつきが生じる可能性が指摘されていました。この調査は、新しいルールが導入されて初めての開示状況を分析することで、実際にどのような情報が開示され、そこに企業規模による差が見られるのかを明らかにしようとしたものです。
研究者たちは、ステークホルダー理論を一つの理論的基盤としています。この理論では、企業は株主だけでなく、従業員、顧客、地域社会といった多様な利害関係者の期待に応える責任があるとされます。人的資本に関する情報の開示は、これらのステークホルダーに対して、企業が従業員をどのように扱い、育成し、評価しているかを透明に伝える手段となり得ます。大企業は一般により多くのステークホルダーを抱え、社会的な影響力も大きいため、より広範で詳細な情報開示を行う動機が強いと考えることもできます。
調査では、S&P500構成企業の中から、時価総額で上位100社を「大企業」、下位100社を「小企業」として抽出し、合計200社を分析対象としました。これらの企業が2020年11月9日から2021年5月31日までの間にSECに提出した年次報告書における人的資本開示の部分を収集し、その内容を分析しました。
分析の結果は、当初の予想とは少し異なるものでした。大企業と小企業とで、開示している人的資本テーマの数には、統計的に意味のある差は見られませんでした。大企業だからといって、必ずしもより多くの種類の人的資本情報を開示しているわけではなかったのです。
個別のテーマごとに見ても、一概に大企業の方が開示が多いとは言えませんでした。例えば、「人的資本の認識」(人的資本の重要性を明言しているかなど)や「多様性・公平性・包括性(DEI)」については、大企業の方が開示している企業の割合が高かった一方で、「雇用の安定性・定着率」や「労使関係」といったテーマでは、むしろ小企業の方が開示している企業の割合が高いという結果でした。
開示の詳細さ、具体的には文字数で比較しても、同様の傾向が見られました。多様性・公平性・包括性(DEI)に関する記述は、大企業の方が文字数が多い傾向にありましたが、他のテーマでは小企業の方が多い場合もあり、全体として企業規模による明確な差は認められませんでした。そして、総合的な開示の度合いを示す人的資本開示指数(HCDI)についても、大企業と小企業の間で統計的に有意な差はありませんでした。
これらの結果は、企業規模が人的資本開示の内容や量に決定的な違いをもたらすわけではないことを示唆しています。この背景には、SECの開示ルールが原則ベースであることが関連しているかもしれません。企業は自社の事業特性や経営戦略、あるいはステークホルダーからの関心が高いと判断する事項について、規模の大小に関わらず、ある程度自律的に開示内容を決定している可能性があります。小企業であっても、人材が特に重要な経営資源であると認識していれば、積極的に情報を開示するインセンティブが働くのかもしれません。
人的資本開示が進むと従業員の意欲は逆に低下する
これまでの議論では、人的資本開示が企業の市場価値や開示姿勢、あるいは企業規模によってどのように異なるかといった、主に企業側の視点や外部評価からの分析に着目してきました。しかし、人的資本開示がもたらす作用は、それだけにとどまりません。開示された情報を実際に目にし、受け止めるのは、企業の内部にいる「従業員」自身でもあります。
企業が自社の人的資本に関する情報を積極的に開示するようになると、そこで働く従業員の意欲や会社への思い入れ、いわゆる従業員エンゲージメントは、どのように変化するのでしょうか。直感的には、自社が従業員を大切にし、育成に力を入れているといった情報が開示されれば、従業員の士気は高まりそうに思えます。しかし、現実はそれほど単純ではないかもしれません。日本の上場企業を対象としたある研究は、この点に関して、一見矛盾するような結果を提示しています[4]。
この研究は、日本企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の仕組みが、人的資本情報の開示と、従業員のエンゲージメントにどのような関連を持つのかを分析しました。特に、情報開示による透明性の向上が、必ずしも従業員のエンゲージメントを高めるわけではなく、場合によっては逆に低下させてしまうかもしれないという「パラドックス(矛盾)」の可能性に焦点を当てています。
研究者たちは、エージェンシー理論やステークホルダー理論といった理論的枠組みを参考にしました。エージェンシー理論は、企業の経営者(エージェント)と株主(プリンシパル)の間には情報の非対称性や利益相反が生じやすく、取締役会の独立性などが経営者を規律し、情報開示を促進すると考えます。一方、ステークホルダー理論は、企業が株主だけでなく、従業員を含む多様な利害関係者に対して説明責任を負うべきであり、情報開示はその一環であると捉えます。
これらの理論に基づき、取締役会の構成(独立性や女性取締役の比率、規模など)が人的資本情報の開示レベルに影響し、そしてその開示レベルが従業員エンゲージメントに関わるとの仮説を立てました。具体的には、取締役会の独立性が高いほど、女性取締役が多いほど、取締役会の規模が大きいほど、また取締役会の活動(会議頻度)が多いほど、人的資本情報の開示が進むという仮説群と、人的資本情報の開示が多いほど従業員のエンゲージメントが高くなるという仮説を設定しました。
分析の対象となったのは、東京証券取引所のTOPIX100に選ばれている企業で、2019年度から2021年度までの3年間のデータが用いられました。各企業の統合報告書や企業統治報告書、Eikonデータベースから、人的資本情報の開示状況(独自のスコアで評価)、従業員エンゲージメントのスコア(企業が自主的に開示している値)、そして取締役会の属性に関する情報を収集し、パネルデータを用いた回帰分析を行いました。
人的資本情報の開示に影響する要因についての分析結果ですが、取締役会の独立性が高い企業ほど、また、女性の取締役比率が高い企業ほど、人的資本情報の開示スコアが有意に高いことが確認されました。取締役会に外部の視点や多様な意見が取り入れられることで、企業情報の透明性向上への意識が高まり、人的資本に関する情報開示も進みやすくなることを示唆しています。一方で、取締役会の規模や会議の頻度は、人的資本開示との間に明確な関連は見られませんでした。
そして、人的資本情報の開示と従業員エンゲージメントの関係についての分析結果は、予想とは反対のものでした。人的資本情報の開示スコアが高い企業ほど、従業員のエンゲージメントスコアが有意に低いという結果が得られたのです。企業が人的資本に関する情報を多く開示すればするほど、従業員の働く意欲や会社への帰属意識がむしろ低下してしまう可能性があるという、直感に反する現象を捉えています。
なぜこのような逆説的な結果が生じるのでしょうか。研究者たちは、いくつかの可能性を考察しています。一つは、開示される情報の内容に関連するものです。企業が開示する人的資本情報の中には、例えば、同業他社と比較して自社の従業員への待遇や投資が必ずしも十分ではないといった、従業員にとってはネガティブに受け取られかねない情報が含まれている可能性があります。
あるいは、企業が掲げる理想的な人材育成方針と、従業員が日常業務で実際に経験している現実との間に大きなギャップがある場合、開示情報がそのギャップを浮き彫りにしてしまい、かえって従業員の不満や失望感を招くことも考えられます。また、企業が「従業員は大切な資本である」と表明しつつも、実際の処遇改善や働きがい向上につながる取り組みが伴っていない場合、開示情報が形式的なもの、あるいは「建前」として従業員に受け止められ、シニカルな反応を引き起こすのかもしれません。
この研究結果は、人的資本情報の開示が、必ずしも従業員のポジティブな感情や行動に直結するわけではない、という論点を提起しています。透明性を高めること自体は企業統治の観点からは望ましいとしても、その情報が従業員にどのように受け止められ、どのような心理的な作用を及ぼすのかについては、慎重な配慮が必要であることを物語っています。情報開示は、単に情報を外に出せば良いというものではなく、その内容や伝え方、そして何よりも開示される情報と企業の実際の行動との一貫性が問われます。
人的資本開示を機械学習で定量的に測定できる
従業員の意欲という、人の内面に関わる側面にも人的資本開示が関わってくる可能性が見えてきましたが、ここで一度、視点を変えてみましょう。そもそも「人的資本開示」という、言葉で表現される情報を、私たちはどのように客観的に捉え、分析し、比較することができるのでしょうか。
企業が発行する報告書には、人材育成方針、ダイバーシティへの取り組み、従業員の健康増進策など、多種多様な情報が記述されています。これらの質的情報を、研究や実務で活用可能な形にするためには、何らかの方法で定量化する、要するに、数値で評価する必要が出てきます。この課題に対して、近年の情報技術の発展、特に機械学習の手法が新たな道を開きつつあります。ある研究では、機械学習アルゴリズムを駆使して、企業が開示する人的資本情報を体系的に分類し、定量的に測定するための新しいアプローチが提案されています[5]。
この研究の背景には、人的資本が企業価値創造における重要な資産であるとの認識が広まる一方で、その開示に関する会計基準や具体的なルールがまだ十分に整備されていないという現状があります。そのため、企業が開示する情報の内容や形式は多岐にわたり、研究者がそれらを一貫した基準で分析することが難しいという課題がありました。
従来の研究では、あらかじめ定義された少数のキーワードの出現頻度を数えたり、研究者が手作業で報告書の内容を読み解いて分類したりする方法が取られることがありましたが、これらの方法では、人的資本という多面的で複雑な概念の全体像を捉えきれない、あるいは分析に多大な時間と労力を要するといった限界がありました。
そこで、この研究では、Word2Vecという機械学習アルゴリズムを活用しました。Word2Vecは、大量のテキストデータの中から単語の意味や関連性を学習し、単語を数値のベクトルとして表現する技術です。この技術を用いることで、単語同士の意味的な近さや、文脈における使われ方の類似性を捉えることができます。
研究者たちは、アメリカの証券取引委員会(SEC)が2020年から企業に義務付けた人的資本開示に着目し、約4000社が開示したテキストデータを収集しました。そして、この大量のテキストデータをWord2Vecで学習させることにより、人的資本開示に関連するキーワードを網羅的かつ客観的に抽出し、それらを意味的に関連性の高いグループに分類するための包括的な「語彙リスト」を作成することを目指しました。
具体的には、人的資本の開示内容を、社会的な要請や企業戦略との関連性が高いと考えられる5つの主要なカテゴリーに分類しました。それは、「多様性、公平性、包括性(DEI)」、「健康と安全」、「労働関係と企業文化」、「報酬と福利厚生」、そして「人口統計およびその他(従業員数や構成など)」です。
各カテゴリーについて、核となるいくつかの初期キーワード(シードワード)を設定します。例えば、「多様性」のカテゴリーであれば「diversity」や「inclusion」といった単語です。そして、Word2Vecが学習した単語間の関連性情報に基づいて、これらのシードワードと意味的に類似している単語や、同じ文脈で使われやすい単語を次々と抽出していきました。
このプロセスを経て、最終的に1285個のキーワードから成る、非常に広範な人的資本開示関連の語彙リストを完成させました。このリストは、従来の手作業によるキーワード選定では見逃されがちだった多様な表現やニュアンスを捉えることができると期待されます。
この語彙リストの有効性を確かめるため、研究者たちは、リストを構成する各キーワードが、意味的な関連性に基づいて適切にグループ化されているかを視覚的に評価しました。主成分分析を用いて、各キーワードを3次元空間に配置し、関連性の高いキーワード群が実際に近くに集まっていることを確認しています。
この作成した語彙リストと収集した開示データを用いて、企業の人的資本開示の動向を分析する応用例も示しています。例えば、1994年から2022年までの長期間にわたるアメリカ企業の委任状(株主総会の招集通知などに含まれる情報開示書類)における人的資本関連の記述量の推移を分析したところ、特に2007年の役員報酬に関する開示規制の変更や、2010年の金融規制改革法による開示強化といった規制の変更があった時期に、人的資本に関する開示が顕著に増加していたことが明らかになりました。
求職者は人的資本開示で多様性を重視する
機械学習によって人的資本開示を客観的に測定する技術が開発されつつある一方で、実際に開示された情報、特にその中でも今日的な関心が高い「多様性(ダイバーシティ)」に関する情報は、これから企業で働こうと考えている人々、求職者の目にどのように映り、行動にどのような影響を与えるのでしょうか。企業が自社の多様性への取り組みを開示することは、社会的な要請に応えるだけでなく、優秀な人材を引きつけるための戦略として機能するのか。この問いに答えるため、アメリカで行われたフィールド実験と、企業の人的資本開示データを組み合わせた分析があります[6]。
この研究が生まれた背景には、企業におけるダイバーシティ&インクルージョンへの関心が世界的に高まっていることがあります。多くの投資家や規制機関が、企業に対して多様性に関する情報開示を求めるようになってきています。しかし、そうして開示された情報が、実際に求職者にとってどれほど価値のあるものとして認識され、就職活動という行動に結びついているのかについては、これまで十分な実証データがありませんでした。
そこで、この研究は、企業が提供する多様性に関する情報が、求職者の企業選択の意思決定にどのような変化をもたらすのかを、求職活動の場面で検証することを試みました。研究者たちは、アメリカのキャリアアドバイス企業「Zippia」と協力し、大規模なフィールド実験を行いました。2021年の6月から8月にかけての11週間にわたり、Zippiaのサービスを利用している17万8千人以上の求職者を対象としました。
実験の仕組みはこうです。求職者には、定期的に個人の希望や経歴に合った求人情報がメールで推薦されます。この推薦メールに、実験的な操作を加えました。求職者をランダムに2つのグループに分け、一方のグループ(ベースライン条件)には、従来通り、企業名、勤務地、提示される給与の情報のみを表示しました。もう一方のグループ(多様性条件)には、これらの基本情報に加えて、その企業の「多様性スコア」も表示しました。この多様性スコアは、企業の従業員の人種構成、男女比、学歴の多様性などを総合的に評価し、1から10の数値で示されるものです。
そして、それぞれの条件で、求職者がメール内のどの求人情報をクリックしたかを記録し、クリックされた求人の平均多様性スコアを比較しました。
実験の結果、求人情報に多様性スコアが表示されたグループの求職者は、そうでないグループの求職者と比較して、統計的に有意に高い多様性スコアを持つ企業の求人情報をクリックする傾向が見られました。ベースライン条件でクリックされた求人の平均多様性スコアが9.252だったのに対し、多様性条件では9.277と、わずかな差ではありますが、統計的には意味のある上昇が確認されました。これは、求職者が多様性に関する情報を目にすると、それを企業選択の一つの判断材料として活用し、より多様性の高い企業に目を向けるようになることを示唆しています。
この多様性情報の価値をより深く理解するために、別の実験条件(給与条件)との比較も行われました。この条件では、多様性スコアの代わりに、より詳細な給与情報(例えば、給与の中央値だけでなく、給与レンジなど)を追加で表示しました。その結果、多様性情報の提供は、求職者の注意を引くという以上の、実質的な価値を持つ情報として認識されていることが確認されました。
研究者たちは、理論的なモデルを用いて、求職者が多様性情報を知った場合に、給与の魅力と多様性の高さをどの程度相対的に評価するか(多様性情報への相対的感受性)を分析しました。その結果、多様性情報が提示されると、たとえ給与が多少低くても、多様性の高い企業を選ぶ傾向が強まることが明らかになりました。求職者にとって、企業の多様性が、金銭的な報酬とある程度トレードオフの関係になり得るほど、魅力的な要素として捉えられている可能性を示しています。
この研究は、2020年にアメリカ証券取引委員会(SEC)が導入した人的資本開示の義務化(HCD)との関連も分析しています。企業の実際の開示行動を調べたところ、求職者が多様性情報に敏感に反応する傾向のある産業(例えば、実験で多様性情報へのクリック率が高かった産業)に属する企業ほど、年次報告書において自社の多様性に関する情報を自主的に開示していることが分かりました。
脚注
[1] Tom, I. M., Okpo, S. A., and Simeon, U. (2025). Human resource factor disclosures and market value of insurance firms in Nigeria. Journal of Accounting and Financial Management, 11(2), 206-226.
[2] Tejedo-Romero, F., Tejada Ponce, A., Ramirez Corcoles, Y., and Lopez Perez, M. D. M. (2023). Board leadership structure and human capital disclosure: Role of independent directors. European Research on Management and Business Economics, 29, Article 100224.
[3] Pandit, G. M. (2023). The new human capital disclosures in Form 10-Ks of large and small S&P 500 companies. Journal of Applied Business and Economics, 25(6), 1-21.
[4] Elamer, A. A., and Kato, M. (2024). Governance dynamics and the human capital disclosure-engagement paradox: A Japanese perspective. Competitiveness Review: An International Business Journal, 35(1), 76-99.
[5] Demers, E., Wang, V. X., and Wu, K. (2024). Measuring corporate human capital disclosures: Lexicon, data, code, and research opportunities. Journal of Information Systems, 38(2), 163-212.
[6] Choi, J. H., Pacelli, J., Rennekamp, K. M., and Tomar, S. (2023). Do jobseekers value diversity information? Evidence from a field experiment and human capital disclosures. Journal of Accounting Research, 61(3), 695-735.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。