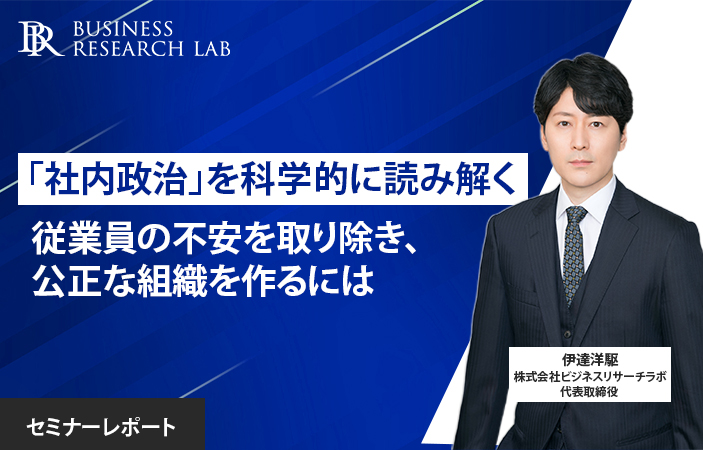2025年10月8日
「社内政治」を科学的に読み解く:従業員の不安を取り除き、公正な組織を作るには(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年9月にセミナー「『社内政治』を科学的に読み解く:従業員の不安を取り除き、公正な組織を作るには」を開催しました。
「優秀な若手が辞めてしまう」「部署間の連携がうまくいかない」といった組織課題の背景に、いわゆる「社内政治」が潜んでいることがあります。
本セミナーでは、こうした職場の“見えない力学”が、従業員の心理や生産性に与える影響を解き明かし、その対策をお話しました。実力よりも人間関係が優先されるといった非公式な力学がもたらす問題を直視し、人事が主導できる組織作りへのヒントを提供しました。
「社内政治」を従業員がどう感じ取るかが、会社への信頼を損ない、公正感を蝕む様子を具体的なデータで示しました。それが本音を言えない迎合的な態度や心理的な不安、さらには他者への攻撃性や離職意図へと繋がっていくメカニズムを解説しました。特に、組織の要である中間管理職がなぜ板挟みになり、ストレスに晒されやすいのか、その構造にも光を当てました。
しかし、本セミナーは問題点を指摘するだけではありません。こうした力関係の悪影響を和らげるためのアプローチも探っています。従業員の「自分も仕事に影響を与えられる」という感覚を高めたり、建設的な意見交換を促す「フィードバック環境」を構築したりする方法、あるいは社内で円滑に物事を進め、建設的に影響力を発揮するためのスキルとは何か。
組織に働く“見えない力”を理解し、従業員一人ひとりが安心して能力を発揮できる職場環境を築くための一歩として、本セミナーをご活用いただければ幸いです。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
「社内政治」という言葉には、どこかネガティブな響きがあります。実力よりも人間関係が重視される、一部の権力者に迎合しなければならない、といったイメージがつきまとうからでしょう。しかし、立場の異なる人々が集まる組織において、利害の対立や非公式な影響力の行使、すなわち政治的な力学が生まれるのは、ある意味で自然な現象です。
問題は、政治の存在そのものよりも、従業員一人ひとりが自社を「どれほど政治的か」と認識する、その「知覚」にあります。この知覚が、従業員の不安や不信感を増幅させ、組織全体の活力を蝕んでいくからです。本講演では、この「組織内政治の知覚」という概念を軸に、研究知見を紐解きながら、それが従業員の心理や行動に及ぼす影響、そしてその悪影響を緩和し、公正で健全な組織を築くための方策について探求していきます。
組織内政治の知覚とその悪影響
従業員が「この職場は政治的だ」と感じることは、組織にとって様々な悪影響の始まりとなります。それは個人の行動を歪め、組織への信頼を揺るがし、日々の業務に不安という影を落とします。最終的には、優秀な人材の流出という事態を招きかねません。ここでは、数々の研究が明らかにしてきた、組織内政治の知覚がもたらす深刻な影響について、そのメカニズムを見ていきます。
ある研究では、組織内政治の知覚を測定する尺度を開発する過程で、従業員が「政治」をどのように捉えているかを分析しました[1]。その結果、「一般的政治行動(他者を貶めて自分を利する)」「迎合行動(本音を言わずに権力者に同調する)」「報酬と昇進施策(評価や昇進が実力以外で決まる)」という三つの要素が浮かび上がりました。従業員はこのような行動や仕組みが蔓延していると感じた時に、職場を「政治的」だと認識するのです。
そして、このような認識は、従業員を自己防衛的な行動へと向かわせます。例えば、波風を立てないように当たり障りのない意見に終始したり、自分の評価を不当に下げられないよう上司の顔色をうかがったりする行動が増加します。これは、本来業務に向けるべきエネルギーが、内向きの人間関係対策に浪費されている状態と言えます。
組織内政治の知覚がもたらす深刻な影響の一つは、組織への信頼が覆されることです。4万人以上の従業員を対象とした118の研究を統合したメタ分析という手法を用いた研究では、組織内政治の知覚と「組織的信頼」の間に、強い負の関係があることが示されました[2]。政治的な駆け引きが横行していると感じる従業員ほど、「会社は自分たちの利益を真剣に考えてくれている」とは信じられなくなるのです。
この不信感は、評価や意思決定のプロセスに対する疑念、すなわち「手続き的公正」や「相互作用的公正」の認識を低下させます。ルールが公平に適用されず、評価基準が曖昧だと感じられる環境では、組織への信頼は生まれません。さらに、組織が自分の貢献を正当に評価し、幸福を気にかけてくれているという「組織的支援」の認識も、政治の知覚によって損なわれてしまいます。
信頼の欠如は、従業員の心に「不安」という毒を注入します。アメリカの大学職員822名を対象とした調査では、組織内政治の知覚と「職務不安」の間に正の相関関係が確認されました[3]。政治的な職場では、評価基準が曖昧で、失敗した場合の不利益が不当に大きいと感じられるため、従業員は予測不可能なリスクに晒されます。
自分のキャリアが、能力や努力といったコントロール可能なものではなく、自分ではどうにもならない「見えない力」によって左右されるという無力感が、慢性的な不安を引き起こすのです。とりわけ、権限が一部の管理職に集中し、明確なルールや手続きが欠如している組織では、この傾向が顕著になることも研究で示されています。
そして、不信と不安が積み重なった結果、従業員は最終的に「離職」という選択肢を考え始めます。複数の研究を統合した別のメタ分析では、職場を政治的だと強く感じる従業員ほど、その組織を去りたいと考える傾向、すなわち「離職意図」が高いことが一貫して示されています[4]。このメカニズムは、「嫌だから辞めたい」という単純なものではありません。
研究によると、組織内政治の知覚は、まず複雑な人間関係への対処といった「心理的負担」を増大させます。そして、この負担が職務満足度や組織への愛着といった「士気」を低下させます。この「心理的負担の増加」と「士気の低下」という二つのプロセスを経て、最終的に離職意図が高まることが証明されています。これは、政治的な職場が従業員の心を蝕んでいく過程を物語っています。
組織内政治が引き起こす対立と攻撃
組織内政治の知覚がもたらす悪影響は、個人の内面的な不安や不満にとどまりません。それはやがて、職場における人間関係を破壊する、目に見える「対立」や「攻撃」へと発展していきます。不公平感が蔓延し、誰もが自己防衛的になる環境は、従業員同士の信頼を失わせ、協力よりも敵対を、支援よりも妨害を選択させやすくなります。
イスラエルの多様な業種で働く540名以上の従業員を対象とした調査は、この危険なメカニズムを明らかにしました[5]。この研究では、組織内政治の知覚が、従業員の「職務ストレス」や「バーンアウト(燃え尽き)」を高め、それが最終的に同僚や上司に対する「攻撃的行動」につながるという経路を実証しました。政治的な職場がもたらす不公平感や心理的な緊張は、従業員にとって耐え難いストレスとなります。そのストレスのはけ口として、他者への批判、皮肉、無視といった、言葉や態度による攻撃が選択されやすくなるのです。
興味深いことに、この研究では、職務ストレスやバーンアウトが、政治の知覚と攻撃行動の関係を部分的に「媒介」していることが示されました。政治的な環境が直接的に攻撃性を生むだけでなく、ストレスというクッションを挟むことで、より根深く、じわじわと職場全体の攻撃性を高めていくのです。さらに、一度誰かが自己防衛のために攻撃的な態度を取ると、それが周囲の警戒心を煽り、さらなる攻撃を誘発するという、負のスパイラルに陥る危険性も指摘されています。
この問題は、より広範な「敵対的行動」という観点からも捉えることができます。ある研究では、職場環境を「政治的環境(競争的で自己利益を追求する雰囲気)」と「支援的環境(協力的で助け合う雰囲気)」に分け、それぞれが従業員の行動に与える影響を比較しました[6]。その結果、政治的環境の知覚は、同僚との衝突や悪口、嫌がらせといった「敵対的行動」や、仕事から精神的に離れて無気力になる「心理的離脱」と強い関連があることが判明しました。
研究者らはこの現象を「投資モデル」を用いて説明しています。政治的な環境は、従業員にとって自分の努力や貢献が正当に報われるかどうかわからない「リスクの高い市場」のようなものです。このような不確実な状況では、従業員は組織への長期的な貢献よりも、短期的な自己利益の確保や自己防衛に走りやすくなります。他者の足を引っ張ったり、協力を拒んだり、あるいは仕事への意欲を失って最低限の努力しかしなくなったりするのです。これは、組織内政治が、従業員から協力の精神を奪い、互いをライバルと見なす敵対的な文化を醸成することを示しています。
対話とフィードバックが政治を緩和する
組織内政治の知覚がもたらす数々の悪影響を前に、私たちは何から手をつけるべきでしょうか。幸いなことに、研究は絶望的な事実を突きつけるだけではありません。政治の知覚を低減させ、公正な組織文化を育むための処方箋も示唆しています。その鍵を握るのが、「対話」による役割の明確化と、「フィードバック」による透明性の確保です。これらは、政治が生まれる土壌である「曖昧さ」と「不信感」を取り除くための効果的なアプローチと言えるでしょう。
興味深いことに、組織内政治を最も強く認識するのは、一般職員でも上級管理職でもなく、「中間管理職」であることが分かっています。1600名以上の政府系研究開発機関の従業員を対象とした調査で、この事実が明らかになりました[7]。中間管理職は、上層部からの方針と現場からの要求の板挟みになる「サンドイッチ状態」にあり、常に複雑な調整を迫られます。また、限定的な権限しか持たない中で成果を出すことを求められ、同僚との昇進競争にも晒されるため、政治的な駆け引きの必要性を痛感しやすい立場にあるのです。
この研究は、政治の知覚を低減させる要因として「役割と責任の明確さ」と「部門間の良好な協力関係」が特に重要であることも突き止めました。この発見は、私たちが取り組むべき課題がどこにあるかを示しています。
そこでまず取り組むべきは、継続的な「対話」を通じて、従業員一人ひとりの役割と責任を明確にし続けることです。これは、年に一度の目標設定で終わるものではなく、日々のコミュニケーションの中に埋め込まれるべきプロセスです。
例えば、上司と部下の個人面談を、単なる進捗確認の場から「期待値のすり合わせ」の場へと変化させます。「今、チームから最も期待されている役割は何だと認識しているか」「どの範囲まで自分で判断して良いと考えているか」といった対話を通じて、お互いの認識のズレを定期的に修正します。これにより、部下は「上司の真意はどこにあるのか」といった疑心暗鬼から解放されます。
また、チームミーティングでは、プロジェクトの開始時に「誰が何に責任を持つのか」を全員で可視化し、確認し合う習慣をつけることも有効です。これによって、責任の押し付け合いや曖昧な指示による混乱を防ぐことができます。さらに重要なのは、業務の過程で役割が不明確になった際に、「少し役割分担を再調整しませんか」と誰もが気軽に提案できる文化を醸成することです。問題を放置せず、その都度コミュニケーションで解決する姿勢が、不満が政治的な動きに発展するのを未然に防ぎます。
次なる一手は、「フィードバック」によって組織の透明性を高めることです。150組の上司と部下のペアを対象とした調査では、上司や同僚から日常的に提供される非公式なフィードバックの質や頻度、すなわち「フィードバック環境」が良好であるほど、従業員の組織内政治の知覚が低減することが明らかになりました[8]。特に、上司からの質の高いフィードバックが強い影響力を持っていました。
なぜフィードバックが政治を抑制するのでしょうか。第一に、フィードバックは「何が評価され、どのような行動が期待されているのか」という基準を明確にし、評価の曖昧さを取り除きます。第二に、オープンなフィードバックは情報の非対称性をなくし、組織の透明性を高めます。第三に、建設的なフィードバックは上司や同僚との信頼関係を構築し、「この組織では公正に評価される」という安心感を与えます。これらはいずれも、政治が生まれる温床である「不確実性」「不透明性」「不信感」を直接的に解消する効果があります。
具体的な施策としては、年に数回の評価面談だけでなく、日々の業務の中で「今の行動は素晴らしかった」「この点は、こういう意図で修正してほしい」といった具体的でタイムリーなフィードバックを奨励することが挙げられます。また、管理職向けに効果的なフィードバック手法の研修を実施したり、多角的な視点を得られる360度フィードバックを導入したりすることも、評価の客観性を高め、「上司に気に入られているかどうか」といった政治的な懸念を払拭する上で有効です。
政治的な職場を「誠実性」で乗り切る
これまで見てきたように、対話やフィードバックを通じて組織内政治の知覚を緩和することは可能ですが、組織文化の変革には時間がかかります。もし、従業員が今まさに政治的な環境の渦中にいるとしたら、個人として、そして組織として、どのようにその荒波を乗り越えれば良いのでしょうか。ここにヒントを与えてくれるのが、「誠実性」という性格特性です。一見、政治とは無縁に思えるこの特性が、実は政治的な職場において個人のパフォーマンスを守り、組織が公正な評価を実現するための鍵となります。
「誠実性」とは、心理学において、自制心があり、責任感が強く、勤勉で、物事を計画的に進める傾向を指す性格特性です。一般的に職務成果と関連が深いことが知られていますが、ある研究がこの関係に「組織内政治の知覚」がどう影響するかを検証しました[9]。流通業からソフトウェア開発まで、4つの異なる業種の従業員813名とその上司を対象にした調査の結果は、示唆に富むものでした。
組織内政治の知覚が低い、要するに比較的健全な職場環境では、誠実性の高さと仕事のパフォーマンスにはほとんど関連が見られませんでした。しかし、組織内政治の知覚が中程度から高い環境、すなわち政治的な職場においては、誠実性が高い従業員ほど、上司からの職務遂行能力の評価も高くなるという関係が強まったのです。
この結果が意味するのは、政治的な混乱が渦巻く職場において、「誠実さ」が一種の羅針盤として機能するということです。政治的な職場では、方針が頻繁に変わり、評価基準は曖昧で、人間関係のノイズに溢れています。このような予測不能な環境では、多くの人が混乱し、パフォーマンスが低下してしまいます。しかし、誠実性の高い人は、持ち前の計画性や規律正しさによって、外部の混乱に惑わされることなく、自分がやるべきタスクに集中し、一貫した行動を維持することができます。彼ら彼女らは、周囲の雑音に振り回されず、黙々と責任を果たすことで、結果的に高いパフォーマンスを達成するのです。
この知見は、個人と組織の双方に具体的な戦略を示唆します。まず、従業員が個人でできる対策は、自身の「誠実性」を意識的に発揮することです。政治的な動きに気を取られるのではなく、自身の業務を計画・管理し、「自分が今やるべきこと」に集中します。そして、着実に成果を出し、そのプロセスと結果を客観的な事実として記録しておくことが重要です。これが「あの人は政治ではなく、仕事で貢献している」という揺るぎない評価を築き、不当な批判から身を守るための盾となります。
一方で、組織やマネジメントができることは、従業員の「誠実性」が正当に報われる環境を意図的に作ることです。例えば、採用や配置の段階で、候補者の誠実性を見極めることは一つの戦略です。特に政治的な影響を受けやすい部門や役職では、困難な状況をどう計画的に乗り越えたかといった具体的な行動経験を問うことで、この特性を評価できます。
さらに重要なのは、評価制度です。上司の主観や印象といった曖昧な要素の比重を下げ、「計画通りに業務を遂行したか」「責任を持って最後までやり遂げたか」といった、誠実な行動プロセスや客観的な成果をより重視する仕組みを導入します。これによって、真面目に働く従業員が政治的な動きに埋もれることなく、公正に評価される組織文化を醸成することができます。
悪ではない?職務成果を高める「政治的スキル」
これまで、組織内政治のネガティブな側面に焦点を当ててきましたが、最後に少し視点を変えてみましょう。「政治」という言葉が持つ、もう一つの側面についてです。それは、単なるゴマすりや足の引っ張り合いといった自己中心的な駆け引きではなく、組織の目標達成のために、他者に健全な影響を与え、円滑な人間関係を築くための高度な能力、すなわち「政治的スキル」です。政治的スキルは、ネガティブな組織内政治とは一線を画すものであり、むしろ現代の複雑な組織において、リーダーや従業員にとって不可欠な能力となりつつあります。
政治的スキルとは、学術的には「職場において他者を理解し、その知識を活用して、自分自身や組織の目標を促進する方向に他者に影響を及ぼす能力」と定義されています。この能力を測定する尺度を開発した研究では、政治的スキルが四つの異なる次元で構成されることを明らかにしました[10]。
第一に、他者や組織の力学を敏感に察知し、適切な行動を判断する「社会的洞察力」。第二に、説得力のあるコミュニケーションで相手から望ましい反応を引き出す「対人的影響力」。第三に、組織内外に協力的な人間関係のネットワークを築き、維持する「ネットワーク形成能力」。第四に、自分の行動が利己的ではなく、誠実で信頼できるものであると相手に感じさせる「見かけ上の誠実さ」です。
この研究は、大学生から様々な企業の従業員まで、幅広い対象者への調査を通じて、これらの政治的スキルが高い人ほど、職場での評価が高まる傾向があることを実証しました。具体的には、上司から見た職務遂行評価や、部下から見たリーダーとしての有効性の評価が、政治的スキルの高さと有意に相関していたのです。これは、政治的スキルが、単に世渡り上手というだけでなく、実際の業務成果やリーダーシップに直結する重要な能力であることを示しています。
特に、四つの次元の中でも、他者の意図や組織内のパワーバランスを的確に読み解く「社会的洞察力」が、職務遂行評価を予測する上で最も重要であることも分かりました。このスキルを持つ人は、誰に、いつ、何を話すべきかを的確に判断し、無用な対立を避けながら物事を前に進めることができます。社内政治を悪と見なして排除しようとするだけでは、組織は前に進みません。むしろ、この「政治的スキル」を健全な対人影響力スキルとして正しく理解し、従業員の育成テーマの一つとして捉える視点が、これからの人事戦略には求められるのかもしれません。
おわりに
本講演では、「組織内政治の知覚」をキーワードに、それが従業員の心理や行動に及ぼす多岐にわたる影響と、その対策について研究知見を基に解説してきました。職場が政治的だと感じられることは、従業員の信頼を損ない、不安を煽り、対立や攻撃行動を生み出し、最終的には離職につながるという、組織にとって看過できないリスクであることがお分かりいただけたかと思います。
しかし、同時に、そのリスクは決して手の打ちようがないものではないことも明らかになりました。重要なのは、社内政治をタブー視したり、個人の性格の問題として片付けたりするのではなく、その発生メカニズムを組織的な課題として理解することです。本講演で紹介した「対話」による役割の明確化や、「フィードバック」による透明性の確保は、政治が生まれる土壌を変えていくための具体的な手段です。これらのアプローチを通じて、従業員の不安を取り除き、誰もが公正に評価され、安心して能力を発揮できる組織文化の構築を目指していただきたいと願っています。
Q&A
Q:フィードバックの重要性は理解できましたが、私たちの会社には他者への指摘をためらう文化が根強く残っているように感じます。会社としてフィードバックを奨励しても、当たり障りのない表面的な内容に終始してしまい、なかなか本質的な改善につながりません。建設的で意味のあるフィードバックが活発に行われる組織になるためには、どのようなアプローチが有効でしょうか。
フィードバックの文化を根付かせることは多くの組織にとっての課題です。この状況を打開するには、「ポジティブ・フィードバック」から始めることが重要です。人はどうしても他者の欠点に目が行きやすいのですが、まずは日々の業務で同僚や部下が見せた良い行動や成果を捉え、褒め合う習慣を組織全体で奨励しましょう。例えば、「先日のプレゼン、データ分析が的確で説得力がありました」のように、事実を挙げて伝えることが大切です。
こうした肯定的なやり取りを重ねることで、職場内に信頼の土壌が育まれます。しっかりとした信頼関係があって初めて、人は厳しい指摘(ネガティブ・フィードバック)も「自分の成長のためだ」と前向きに受け入れられるようになります。ある研究では、ポジティブとネガティブの理想的な比率は「5対1」と言われます。この比率を目標に、意識的にポジティブな声かけを増やすことから始めてはいかがでしょうか。
また、「他者への指摘をためらう」背景には、心理的安全性の低さも考えられます。これを改善するには、特に管理職が率先して自らの弱みや失敗談を語る「自己開示」が有効です。上司が自身の経験をオープンにすることで、部下は「この職場では完璧でなくても良い」と感じ、安心して意見を言えるようになります。
Q:私の職場には、公式な役職についているわけではないものの、周囲に大きな影響力を持つ「非公式リーダー」のような人が存在します。彼らが時として社内政治の中心的な役割を担うこともあり、対応に苦慮しています。こうした影響力の強い人物に対して、人事としてはどのように関わっていくのが良いでしょうか。
非公式リーダーと関わる上で大切な心構えは、「問題人物」として敵視するのではなく、その影響力を認め、尊重し、「重要なパートナー」として捉えることです。彼ら彼女らは良くも悪も職場を動かす力を持っており、その力を組織にとってプラスの方向に導くことが人事の役割と言えます。
具体的な関わり方としては、会社のビジョンや方針といった公式な情報を丁寧に伝え、同時に「この方針について、現場の視点からどう思いますか」と彼ら彼女らの意見を真摯に求める姿勢が重要です。これによって、「会社から認められている」と感じ、組織への帰属意識を高めるでしょう。
さらに一歩進んだアプローチとして、彼らに「公式な役割」を担ってもらうことも有効です。例えば、部門横断プロジェクトのリーダーや若手のメンターといった責任ある役割を任せます。人は責任ある立場を与えられると、その役割にふさわしい行動を取ろうとします。彼ら彼女らの影響力を、組織の公式な目標達成という目的のために活用してもらう。このように、そのエネルギーを組織の発展へと向ける仕組みを整えることが、良い関わり方かと思います。
Q:会社として、時に従業員の意に沿わない異動や降格といった、厳しい人事判断を下さなければならない場面があります。その際、対象となった従業員から「上司に嫌われたからだ」「政治的に排除された」といった不満の声が上がり、トラブルに発展してしまうことがあります。こうした人事判断が、社内政治の結果であると受け取られないようにするためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
人事判断が「社内政治」の結果だと思われてしまうと、組織全体に不信感が広がりかねません。これを防ぐために重要なことは、その判断の「正当性」と「公平性」を、客観的な事実をもって担保することです。
例えば、対象者との面談記録、業務改善指示の経過、目標達成度を示す客観的データなど、判断の根拠となる事実を時系列で詳細に記録しておくことが求められます。これらの記録は、判断が上司の個人的な感情ではなく、あくまで本人のパフォーマンスという事実に基づいていることを証明する材料となります。
加えて、判断のプロセスも重要です。決定が直属の上司一人の考えで行われたとすれば、「好き嫌いで決められた」という疑念を招きやすくなります。厳しい人事判断は、人事部やさらに上位の役職者など、複数の視点を持つ人々が関与した上で下されるほうが良いでしょう。本人に伝える際には、「この件は、複数の目で慎重に検討を重ねた上での、組織としての正式な決定です」と伝えることで、個人の恣意性が排除された公平なプロセスを経た結論であることを示し、納得感を高めることができます。
Q:社内政治が横行する環境を、従業員が「リスクの高い市場」と捉えるという「投資モデル」のお話が興味深かったです。この観点に立った時、従業員が目先の利益にとらわれることなく、安心して自らの能力や時間を組織に「長期投資」できるような、つまり、長期的な視点で会社に貢献しようと思えるような環境を整備するために、人事として特に注力すべき施策は何だと思われますか。
「投資モデル」の観点は、健全な組織作りにおいて役立ちます。従業員が安心して「長期投資」(長期的な貢献)できる「安定した市場」を作る鍵は、「投資に対する見返りの予測可能性を高める」ことに尽きます。自分の努力や貢献が将来どのように報われるのか、その見通しが明確であればあるほど、人は安心して長期的な投資を行えます。
予測可能性を高めるために人事が取り組むと良いのは、評価制度の透明性を確保することです。どのような行動や成果が評価されるのか、その基準を開示し、一貫して運用することが求められます。「この会社では、基準に沿って誠実に努力すれば、正当に評価される」という安心感が、長期的な貢献意欲の基盤となります。
さらに、多様なキャリアパスを提示することも有効です。専門性を極める道やマネジメントに進む道など、従業員が自らのキャリアを長期的に設計できる選択肢を示します。これによって、従業員は「この会社で働き続ければ、成長できる」という希望的な見通しを持て、中長期的な視点での貢献、すなわち「長期投資」へと向かうことができるでしょう。
脚注
[1] Kacmar, K. M., and Carlson, D. S. (1997). Further validation of the Perceptions of Politics Scale (POPS): A multiple sample investigation. Journal of Management, 23(5), 627-658.
[2] Bedi, A., and Schat, A. C. H. (2013). Perceptions of organizational politics: A meta-analysis of its attitudinal, health, and behavioural consequences. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 54(4), 246-259.
[3] Ferris, G. R., Frink, D. D., Galang, M. C., Zhou, J., Kacmar, K. M., and Howard, J. L. (1996). Perceptions of organizational politics: Prediction, stress-related implications, and outcomes. Human Relations, 49(2), 233-266.
[4] Chang, C.-H., Rosen, C. C., and Levy, P. E. (2009). The relationship between perceptions of organizational politics and employee attitudes, strain, and behavior: A meta-analytic examination. Academy of Management Journal, 52(4), 779-801.
[5] Vigoda, E. (2002). Stress-related aftermaths to workplace politics: The relationships among politics, job distress, and aggressive behavior in organizations. Journal of Organizational Behavior, 23(5), 571-591.
[6] Cropanzano, R., Howes, J. C., Grandey, A. A., and Toth, P. (1997). The relationship of organizational politics and support to work behaviors, attitudes, and stress. Journal of Organizational Behavior, 18(2), 159-180.
[7] Parker, C. P., Dipboye, R. L., and Jackson, S. L. (1995). Perceptions of organizational politics: An investigation of antecedents and consequences. Journal of Management, 21(5), 891-912.
[8] Rosen, C. C., Levy, P. E., and Hall, R. J. (2006). Placing perceptions of politics in the context of the feedback environment, employee attitudes, and job performance. Journal of Applied Psychology, 91(1), 211-220.
[9] Hochwarter, W. A., Witt, L. A., and Kacmar, K. M. (2000). Perceptions of organizational politics as a moderator of the relationship between conscientiousness and job performance. Journal of Applied Psychology, 85(3), 472-478.
[10] Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., and Frink, D. D. (2005). Development and validation of the Political Skill Inventory. Journal of Management, 31(1), 126-152.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。