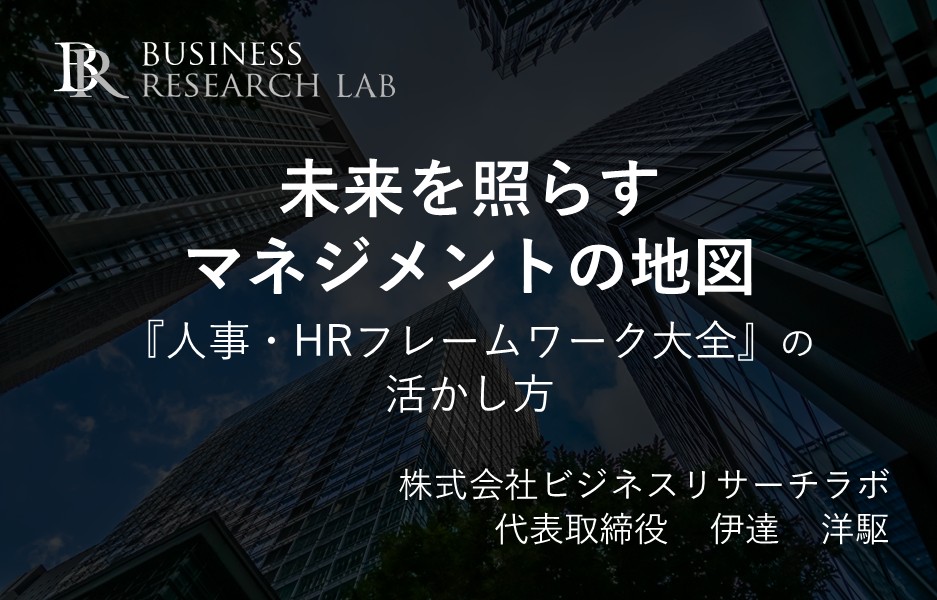2025年10月7日
未来を照らすマネジメントの地図:『人事・HRフレームワーク大全』の活かし方
現代のビジネス環境は複雑性を増しています。市場の変動は激しく、将来の予測は困難を極める時代。働き方はテレワークの普及などで多様化し、従業員一人ひとりが仕事に求める価値観も変化し続けています。こうした中で、企業がいかに持続的に成長していくかという問いに対し、近年「人的資本経営」という一つの切り口が提示されました。これは、人をコストではなく、価値創造の源泉となる「資本」として捉え、その価値を引き出すことで企業価値向上につなげようとする考え方です。人は、企業の持続的成長を支える重要な資本であるという認識が、広く共有されつつあります。
このような時代において、私たちは人と組織の問題にどう向き合えば良いのでしょうか。かつて多くの管理職が頼りにしてきた「勘」や「経験」は、今もなお、大事な役割を果たします。しかし、過去の成功体験が通用しない場面が増え、それだけでは立ち行かなくなっているのもまた事実です。特定の状況下で一度は成功した個人の経験則が、異なる背景を持つ部下や、変化した市場環境にも当てはまるとは限りません。個別の事象にその都度対処する「もぐら叩き」のようなマネジメントを続けていては、根本的な問題解決には至らず、リーダーもメンバーも疲弊していきます。
いま求められているのは、目の前で起きている問題の背後にあるメカニズムを理解し、より再現性が高く、有益な打ち手を考えるためのアプローチです。そのための思考の道具となるのが、長年の研究によって体系化されてきた先人たちの知恵の結晶、すなわち「フレームワーク」に他なりません。検証された知の体系を用いて、組織という複雑なシステムを読み解く。今回、私が上梓した『人事・HRフレームワーク大全』は、これからの時代を生きるビジネスパーソンにとって、思考のOSを更新するための、いわば「人と組織の科学」を実践するためのガイドブックとなることを目指しています。
管理職が陥る三つの罠
現場を預かる管理職は、日々、人と組織に関する無数の課題に直面します。その多くは、「良かれと思って」取った行動が、意図せず裏目に出てしまうケースです。フレームワークという視点を持たない場合、私たちは知らず知らずのうちに、いくつかの罠にはまってしまうことがあります。
一つ目の罠は、部下の主体性を引き出せないという問題です。「最近の若手は指示されたことしかやらない」と嘆くリーダーは少なくありません。しかし、その原因は、リーダー自身の過剰な管理にあるのかもしれません。部下の失敗を恐れるあまり、あるいは自分のやり方が最善だと信じるあまり、業務の進め方を細かく指示し、頻繁に進捗を確認する。こうしたマイクロマネジメントは、一見すると丁寧な指導のようですが、部下から「自分で考える機会」と「仕事をコントロールしている感覚」を奪い、結果的に彼らの自律的な成長を阻害してしまいます。
本書で紹介する「心理的エンパワーメント」というフレームワークは、人が内発的に動機づけられるためには、「仕事の意義」「有能感」「自己決定」「影響力」の四つの感覚が重要だと教えてくれます。
ただ作業をこなすのではなく、自分の仕事が組織や社会にとって価値がある(意義)と感じ、自分にはそれをやり遂げる能力がある(有能感)と信じられ、仕事の進め方をある程度自分で決められ(自己決定)、自分の行動が周囲に良い影響を与えている(影響力)と実感できること。部下の主体性を育むために必要なのは、管理を強めることではなく、むしろ適切な権限委譲と意味づけによって、部下がこれらの感覚を抱きながら自律的に動ける仕組みを設計することです。
二つ目の罠は、チーム内の対立を放置、あるいは悪化させてしまうことです。異なる専門性や価値観を持つ人間が集まれば、意見の衝突は避けられません。問題なのは、リーダーがその対立を見て見ぬふりをする(回避)、あるいは一方の意見を強引に押し通す(支配)といった対応を取ってしまうことです。これでは、一時的に対立が収まったように見えても、メンバー間にしこりを残し、チームの心理的安全性を損ないます。率直な意見交換が失われ、やがては組織全体の活力が削がれていくでしょう。
「コンフリクトマネジメント」のフレームワークは、対立を単なる問題としてではなく、より良い解決策を生み出すための機会として捉える視点を提供します。例えば、対立する両者の意見の背後にある関心事、すなわち「なぜその主張をしているのか」という根本的な欲求を理解し、双方にとって価値のある第三の案を共創する「統合」のアプローチがあります。これは時間と労力を要しますが、チームの課題解決能力を高め、メンバー間の信頼関係を深める上で有効な手法です。
三つ目の罠は、画一的な育成によって、かえって個性を潰してしまうことです。「すべての部下を公平に育てる」という考えから、全員に同じ研修を受けさせ、同じようなキャリアパスを提示する。一見すると公平なようですが、これは個人の多様な動機や強みを無視したアプローチと言えます。
本書で解説する「キャリア・アンカー」は、人がキャリアを選択する上で何を最も大切にするか、その価値観の軸が人それぞれ異なることを示しています。例えば、特定の分野の専門性を高めることに喜びを感じる「技術・職能別能力」をアンカーに持つ人もいれば、組織を管理し、人を動かすことにやりがいを感じる「経営管理能力」をアンカーに持つ人もいます。また、「HEXACOモデル」のような性格特性論は、人の行動傾向の個人差を理解する手がかりを与えてくれます。
すべての部下を同じ型にはめようとするのではなく、一人ひとりの価値観や特性に合わせた育成アプローチを設計すること、すなわち「分化」の視点を持つことが、個人の能力を引き出し、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
組織の「当たり前」を疑う
個々の管理職の行動だけでなく、組織全体に目を向けると、そこには変革を阻む、より根深く、見えにくい壁が存在します。多くの企業が「変わらなければ」と口にしながら、なぜ実際には変わることができないのか。フレームワークを用いることで、その構造を明らかにすることもできます。
第一の壁は、「同質性の罠」です。創業から長い年月が経ち、成功体験を積み重ねてきた組織に顕著なのが、「うちの会社は似たような考えの人ばかりで、新しいアイデアが出てこない」という停滞感です。
「ASAフレームワーク」は、組織が特別な意図なく同質化していくメカニズムを説明します。まず、組織の価値観や社風に惹かれた類似した特性を持つ人(Attraction)が集まり、次に組織が自らの文化に合う人(Selection)を選抜し、文化に合わない人(Attrition)が組織を去っていく。このサイクルが繰り返されることで、組織内の思考や行動の多様性は徐々に失われ、未知の課題や環境変化に対する脆弱性を高めてしまいます。この見えない力学を理解して初めて、私たちは多様性を確保するための採用や配置、異質な意見を歓迎する文化醸成の重要性に気づくことができます。
第二の壁は、「過去の成功体験という呪縛」です。「昔はこのやり方でうまくいった」という言葉は、変革に対する強力な抵抗勢力の一つです。しかし、成功体験に固執することは、未来の機会を逃すことにつながります。
本書で紹介する「両利きの経営」は、既存事業を磨き込み効率化する「深化」の活動と、新しい事業や市場を試行錯誤しながら開拓する「探索」の活動を、組織がいかに両立させるべきかを論じています。多くの組織は目先の収益を生み出す「深化」に偏りやすいのですが、持続的に成長するためには、不確実であっても未来への投資となる「探索」を怠ってはなりません。
また、「組織的忘却」というフレームワークは、新しいことを学ぶためには、時に古くなった知識や成功体験に根差した慣習を意図的に「忘れる」ことが戦略的に重要であるという、逆説的ながらも本質的な視点を提供します。過去の成功は守るべき資産であると同時に、未来を縛る足かせにもなり得ます。
第三の壁は、「理念と現場の乖離」です。経営層が朝礼で「我が社は挑戦を奨励する」と語る一方で、現場では一度の失敗も許されない空気が支配している。このような状況は、少なからぬ組織で見られます。
「組織文化の構造」に関するフレームワークは、文化を三つのレベルで捉えます。目に見える「人工物(制度やオフィス環境など)」、公式に語られる「価値観(企業理念など)」、最も深層にあり、人々の行動を無意識に規定する「基本的仮定(暗黙の前提)」です。企業理念という「価値観」を掲げるだけでは、組織文化は変わりません。「失敗は許されない」という「基本的仮定」が現場に根付いている限り、挑戦は生まれません。この深層の前提にまで働きかけ、それを変容させていくアプローチを取らない限り、掛け声だけの変革に終わってしまうでしょう。
知を力に変える
ここまで、個人と組織が陥りがちな罠や壁について、フレームワークという視点を通して見てきました。本書『人事・HRフレームワーク大全』は、こうした課題を特定するだけでなく、それを乗り越え、組織として学び、成長し続けるための方策を提示します。
組織における学習には、二つのレベルがあります。「シングルループ学習」と「ダブルループ学習」です。シングルループ学習とは、既存の目標や規則の範囲内で、やり方を改善していく学習です。これは日々の業務改善において求められますが、これだけでは環境の大きな変化に対応することはできません。
一方、ダブルループ学習とは、「そもそも、この目標設定は正しいのか」「この規則の背後にある前提は、今も有効なのか」といったように、既存の枠組みを問い直す、より深いレベルの学習を指します。本書で紹介する83のフレームワークは、このダブルループ学習を促すための思考の道具です。目の前の問題に対処するだけでなく、その問題を生み出している構造に目を向け、変革していくためのヒントを提供します。
この分厚い「知の道具箱」を、どのように使えばよいのでしょうか。本書の活用法は、単一ではありません。一つは、目の前に具体的な課題がある場合に、関連するフレームワークを目次や索引から探し出し、辞書のように引いて解決のヒントを得る使い方です。もう一つは、リーダーシップ、モチベーション、組織文化といった章立てに沿って体系的に読み進め、人と組織に関する知の全体像を、自身の頭の中にインストールしていく使い方です。
さらに、チームや部署内で輪読会を開くなどして、フレームワークを「共通言語」として導入することも有効です。例えば、「彼のモチベーションが低い」という曖昧な表現の代わりに、「彼の自己決定理論における『有能感』が満たされていないのではないか」と議論できるようになれば、感覚的な言葉によるすれ違いが減るでしょう。
明日から何を始めるか
知識を得るだけでは、現実は変わりません。重要なのは、学んだことを実践に移す一歩です。これは一例に過ぎませんが、例えば、来週予定されている部下とのミーティングで、「LMX(リーダー・メンバー交換理論)」を意識してみてはいかがでしょうか。この理論は、上司と部下の関係の質を「愛着」「忠誠」「貢献」「敬意」という四つの次元で捉えます。
ただ業務の進捗を確認するだけでなく、ミーティングの数分間を使って、「部下との間には、個人的な好意や信頼関係が築けているだろうか(愛着)」「部下のキャリアを本気で応援できているだろうか(忠誠)」「部下の努力や成果を公正に認められているだろうか(貢献)」「部下の専門性や意見に耳を傾けているだろうか(敬意)」と、心の中で自問自答してみる。その意識を持つだけで、問いかけの質、そして部下との関係性は、きっと少しずつ変わっていくはずです。
フレームワークは、複雑で捉えどころのない人と組織の問題に、構造と秩序を与えてくれます。それは、暗い夜道を照らす地図のようなものです。個人の感覚だけに頼るのではなく、「思考の補助線」を引くことで、私たちはより冷静に課題解決の道筋を描くことができるようになります。この一冊が、皆さんの「道具箱」に加わり、それぞれの現場で、より良い組織、より良い働き方を実現するための一助となることを願っています。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。