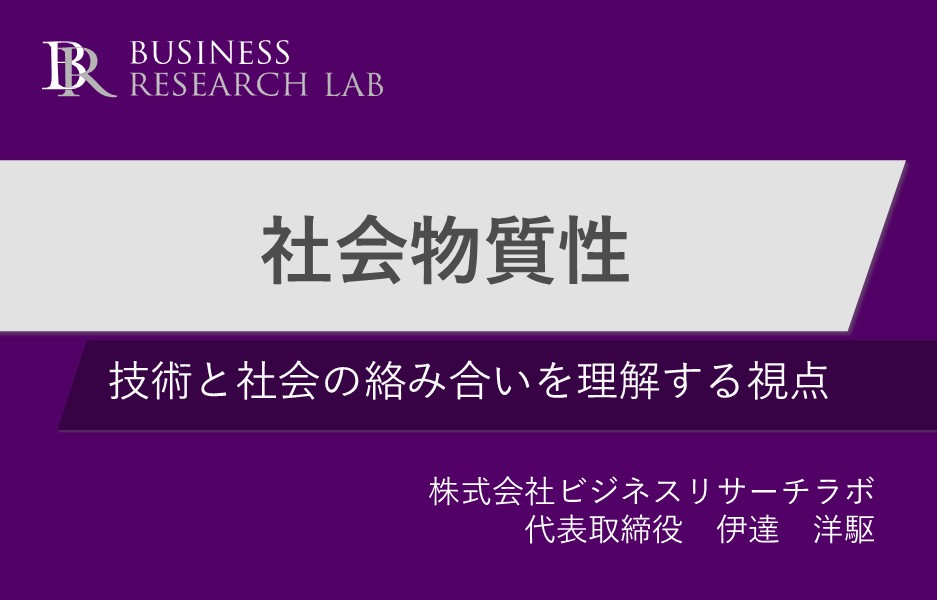2025年10月7日
社会物質性:技術と社会の絡み合いを理解する視点
私たちの日常生活や職場では、スマートフォン、パソコン、各種システムといった技術が当たり前のように存在しています。これらの技術は単純な道具として存在しているのでしょうか。それとも、私たちの行動や組織のあり方を変えているのでしょうか。
従来の考え方では、技術は人間が使う道具であり、社会は人間関係や制度によって構成されるものとして、両者を分けて考えてきました。しかし近年、この二分法的な見方に疑問を投げかける新しいアプローチが登場しています。それが「社会物質性」という考え方です。
この視点では、技術と社会は分離できないものとして絡み合っており、日々の実践の中で互いを形作っているとされます。例えば、メールシステムは情報伝達の道具ではなく、組織内のコミュニケーションパターンや権力関係を形成し、同時にそれらによって使われ方が決まるという相互関係にあります。
組織と技術は社会物質性を通じて相互構成される
技術と組織の関係について考える時、多くの人は技術が組織に何らかの変化をもたらすという一方向的な関係を想像するかもしれません。しかし、実際の関係は複雑で動的なものです[1]。
組織研究の分野では長い間、技術と社会を別々のものとして扱ってきました。一つ目のアプローチは、技術と人間や組織を独立した存在とみなし、技術が組織に一方向的に影響を与えるという見方です。このような研究では、新しい情報システムを導入した結果、組織の効率性がどの程度向上したかといった分析が中心となります。
二つ目のアプローチは、技術と組織が相互作用を通じて互いを形成するという視点です。この考え方では、技術は導入されるだけでなく、組織の文化や既存の業務手順と絡み合いながら活用されるものと捉えられます。
ところが、これらのアプローチにも限界があります。どちらも最終的には「社会」と「技術」を分離して考えているからです。実際の組織では、技術と社会的な要素が密接に絡み合い、どこからが技術でどこからが社会なのかを線引きすることは困難です。
そこで提案されたのが「社会物質性」という新しい視点です。この考え方では、社会的要素(人間関係、組織文化、業務慣行)と物質的要素(技術、システム、道具)が根源的に不可分であり、日々の実践を通じて相互に構成し合っているとされます。
例えば、ある企業で新しい顧客管理システムが導入された場合を考えてみましょう。従来の見方では、システム(技術)が営業活動(社会)に変化をもたらすと考えられていたかもしれません。しかし社会物質性の視点では、営業担当者がシステムを使う過程で、システムの機能と営業の実践が同時に形作られていくと捉えます。営業担当者はシステムの制約の中で新しい営業手法を編み出し、同時にその使い方がシステムの実際の機能を決定していきます。
この視点が重要なのは、技術と社会を分離して考える二元論から脱却し、両者の融合状態に着目することで、現代の複雑な組織現象をより正確に理解できる点にあります。技術は組織の実践そのものを構成する要素として位置づけられるのです。
情報システムは社会物質性を通じて構成される
情報システムの分野においても、社会物質性という概念は新たな理解の枠組みを提供しています。従来の情報システム研究では、システムを技術的な製品として捉え、それがユーザーや組織にどのような効果をもたらすかという視点が主流でした。
しかし、社会物質性の観点から見ると、情報システムは技術的な構成要素だけでなく、ユーザーの行動、組織の慣行、社会的な意味づけなどと不可分に結びついた存在として理解されます[2]。システムは使われる過程において、技術的機能と社会的実践が同時に形成されていく動的な存在です。
この考え方の中核にあるのは、根源的な絡み合いという考え方です。これは、社会的要素と物質的要素がそもそも別々に存在するのではなく、実践を通じて互いに生成し合っているという理解です。例えば、オンライン会議システムを考えてみましょう。これは単純な技術的道具ではありません。参加者の振る舞い、会議の進行方法、組織内の権力関係、コミュニケーションの文化などと密接に絡み合いながら、「会議」という現象を作り出しています。
別の核心的な考え方となるのが、行為的なリアリズムです。これは、人間だけでなく技術も能動的な主体(エージェント)として現実を構成するという考え方です。従来の人間中心主義的な見方を脱却し、技術もまた積極的に社会的現実の形成に参加していると捉えます。
この視点では、情報システムの研究において新たな課題も浮かび上がります。従来の研究手法は主に人間の視点(インタビューや観察)に依存していましたが、技術の能動性を理解するためには、技術そのものの「行為」を捉える新しい方法が必要になります。
研究者たちは、この課題に対応するため、局所的で詳細な分析と広域的で包括的な分析を組み合わせる手法を提案しています。これによって、技術と社会の動的で生成的な関係性をより深く理解できるようになります。
組織の現実は社会物質性を通じ実践的に構成される
組織で働く人々の日常を観察すると、技術と人間の活動が密接に絡み合っていることがわかります。例えば、営業会議では、売上データがスクリーンに表示され、参加者はそのデータを見ながら議論を展開します。この時、データそのものと人々の議論は切り離して考えることができません。データの表示方法、参加者の解釈、議論の進行、意思決定のプロセスなど、すべてが一体となって「営業会議」を作り出しています。
このような組織現象を理解するために、社会物質性の視点では「実践における絡み合い」を捉えようとします[3]。技術と社会的要素が実践の中で絡み合い、組織的な現実を構成しているという理解です。
この視点の発展において貢献をしたのが、技術研究における四つの異なるアプローチの整理です。
第一のアプローチは「技術の不在」です。これは、組織研究において技術が実質的に無視されている状況を指します。組織研究では、技術が常に存在しているにもかかわらず、その物質的な側面が軽視される傾向があります。
第二のアプローチは「外生的な力」という見方です。ここでは技術が組織に対して一方向的で決定的な変化をもたらすものとして扱われます。技術決定論的な研究がこの例で、技術の一般的な効果を測定しようとします。
第三のアプローチは「創発的プロセス」です。この視点では、技術が社会的に構築され、人々の解釈や行動によって動的に形成されるものと捉えられます。技術の意味や活用方法が、特定の社会的・歴史的文脈の中で生み出されることが強調されます。
第四のアプローチが「実践における絡み合い」であり、これが社会物質性の視点です。技術と社会を根源的に絡み合った現象として捉え、両者を明確に分離することなく、関係的に存在するものと考えます。
この理論的発展を示すために、バーチャルコラボレーション環境の事例が検討されています。従来の各アプローチがこの新技術をどのように研究するかを比較すると、それぞれの特徴が明確になります。技術を無視するアプローチではバーチャル環境の技術的性質は分析されません。外生的力として捉えるアプローチでは、バーチャル環境が生産性に与える効果が測定されます。創発的プロセスとして見るアプローチでは、利用者の解釈や行動に焦点が当てられます。
他方で、実践における絡み合いの視点では、バーチャル環境と人間の相互作用が実践の中でどのように組織的現実を構成するかが分析されます。バーチャル会議、共同作業、意思疎通など、具体的な実践がこの技術によってどのように可能になり、その結果どのような組織的現実が生み出されるかが分析対象となります。
プロジェクトの生存は社会物質性による交渉で決まる
組織に新しい情報システムを導入するプロジェクトは、様々な困難に直面します。理想的な計画通りに進むことは稀で、多くの場合、当初の想定とは異なる問題や抵抗が生じます。しかし、興味深いことに、一度問題に直面したプロジェクトの中には、完全に失敗するのではなく、何らかの形で「生き延び」、最終的に機能するシステムとして定着することがあります。
このような「プロジェクトの生存」現象を理解するために、ある大学における大規模システム導入事例が分析されました[4]。この大学は、研究助成金の管理方法を従来の方式から新しいシステムが推奨する「ベストプラクティス」に切り替えようとしました。
従来、この大学では研究者が自分の予算を柔軟に管理できる方式が採用されていました。研究者は必要に応じて予算を組み替えたり、年度をまたいで資金を活用したりすることが可能でした。しかし、新しいシステムでは、予算を事前に時期別に区分して管理する方式が求められました。
導入当初、この変更は現場の研究者や事務スタッフから強い抵抗を受けました。新しい方式では、研究の実情に合わない制約が多く、日常業務が煩雑になると感じられたからです。多くの研究者は新システムを使わず、独自のエクセルシートを作成して従来通りの管理を続けようとしました。
ここで注目すべきは、プロジェクトチームがこの抵抗に対してどのように対応したかです。彼らは「ベストプラクティス」に固執するのではなく、現場の要求を聞き入れて柔軟な対応を取りました。
例えば、新システムに従来の管理方式の機能を追加するカスタマイズを迅速に実施しました。これによって、研究者は慣れ親しんだ方法でも予算管理ができるようになりました。追加的な管理業務の負担を軽減するため、専門的なサポートセンターを設置し、複雑な処理を代行する体制を整えました。
これらの変更により、当初は抵抗を示していた研究者や事務スタッフも徐々に新システムを受け入れるようになりました。最終的に生まれたのは、理想的な「ベストプラクティス」でも従来の方式でもない、「交渉された実践」と呼べる新しい管理方法でした。
この事例から見えてくるのは、システム導入において技術的な理想と現場の実践の間で交渉と妥協が行われ、その結果、新しい実践が創発することです。重要なのは、この新しい実践が技術的な制約と社会的な要求の両方を考慮した、社会物質的な構成物であるということです。
プロジェクトの生存は、技術の一方的な押しつけでも、現場の要求への単純な屈服でもありません。むしろ、技術的な可能性と社会的な必要性が実践の中で交渉され、両者が妥協できる新しい形態が見つけられることによって実現されます。この過程では、技術も社会的実践も当初の形から変化し、相互に適応した新しい状態が生まれます。
匿名性は社会物質性を通じて構成される
インターネット上で情報を発信したり、商品やサービスについて評価を行ったりする際、多くの人が「匿名性」を活用しています。しかし、匿名性というものは単純に名前を隠すということ以上の複雑な現象です。社会物質性の視点から見ると、匿名性は技術的な仕組みと社会的な実践が絡み合って構成される現象として理解されます[5]。
この理解を深めるために、ホテル評価における二つの異なる匿名性の実践が比較検討されました。一つは従来からある専門機関による評価システム、もう一つは現代的なオンライン評価プラットフォームです。
従来の専門機関による評価では、訓練を受けた査察員が一般客として匿名でホテルに宿泊し、施設やサービスの質を評価します。この場合、匿名性は評価プロセスの一部として限定的に使用されます。査察員は宿泊中は身分を明かしませんが、評価後にはホテル経営者との直接対話を行い、改善点などについて詳細な説明を提供します。
この方式では、匿名性が品質保証と信頼性確保の手段として機能しています。査察員の専門性と組織的な責任体制により、評価の公平性と正確性が担保されます。匿名性は評価の信頼性を高めるための一時的な手段であり、評価プロセス全体の透明性を損なうものではありません。
一方、オンライン評価プラットフォームでは、一般利用者が匿名または仮名でホテルの評価を投稿します。この場合、匿名性は評価後の段階で実践され、評価者とホテル経営者の間に直接的な対話はありません。利用者の評価は即座に広範囲に公開され、多くの人の意思決定に活用されます。
しかし、この方式では評価の検証や信頼性の確認が困難です。匿名性によって、評価者の責任の所在が不明確になり、偽の評価や恣意的な評価が混入する可能性が高まります。同時に、ホテル経営者にとっては、不当な評価に対する反論や説明の機会が限られることになります。
これらの違いは、匿名性が実践される「タイミング」と「方法」によって生じています。専門機関では評価過程での一時的な匿名性が採用され、オンライン評価では評価後の永続的な匿名性が採用されています。この違いが、評価の意味、責任の所在、透明性、社会的な認知に異なる結果をもたらしています。
社会物質性の視点から見ると、匿名性は単純な社会的な現象ではありません。データベースの設計、アルゴリズムの動作、ユーザーインターフェースの構成など、技術的な要素が匿名性の実現方法に関わっています。技術的な設計の選択が、匿名性の社会的な意味や効果を決定しているのです。
例えば、評価の投稿システム、身元確認の方法、評価の表示方式、検索アルゴリズムなどの技術的な設計が、匿名性の機能を決定します。これらの技術的要素と社会的な実践が絡み合って、異なる形態の匿名性が構成されています。
社会物質性は技術の具体性や社会構造を捉えきれない
社会物質性というアプローチが組織研究や技術研究において新たな視点を提供している一方で、このアプローチに対する批判的な検討も重要な議論となっています。批判者たちは、社会物質性が本来目指していた社会的要素と技術的要素の統合的理解において、十分な成果を上げていないと指摘しています[6]。
批判の一つは、社会物質性の研究が技術の具体的な特性を十分に描写できていないという点です。社会物質性の理論では、技術と社会が絡み合っているという抽象的な記述にとどまることが多く、技術そのものが持つ機能や制約、設計上の特徴などが曖昧になってしまうという問題があります。
例えば、ある企業のコールセンターを分析した研究では、電話機、コンピューター、オペレーターが一体となって絡み合っているという描写がなされました。しかし実際には、オペレーターの視点からの分析に偏っており、技術システムの動作原理や設計思想については十分に説明されていませんでした。技術と社会の統合を目指したアプローチが、結果的に人間中心の分析に終始しています。
もう一つの批判は、社会物質性のアプローチが実践の局所的なレベルに焦点を絞るあまり、より広範な社会構造や権力関係を見落としてしまうという点です。組織や社会における技術の活用は、個々の実践レベルだけでなく、経済的な条件、政治的な権力関係、文化的な背景など、様々な構造的要因によって形作られています。
オンライン評価システムの分析においても、評価アルゴリズムの動作は商業上の秘密として明らかにされず、技術的な詳細が不明確なまま議論が進められました。こうした状況では、技術と社会の絡み合いを論じても、技術的メカニズムが理解されないまま、表面的な分析にとどまってしまいます。
これらの問題の背景には、社会物質性の理論的基盤となっている、行為的なリアリズムという立場の課題があります。この立場では、量子物理学の議論を社会領域に適用しようとしていますが、物理的現象と社会的現象では分析すべき階層や複雑さが異なります。
例えば、「コーヒーマグと手の境界が原子レベルでは曖昧である」という物理学的な事実を、そのまま社会的な現象に当てはめることには無理があります。社会的現象は、微視的な物理レベルとは異なる論理で構成されており、権力関係、制度的な制約、文化的な意味などの要素を無視して分析することはできません。
このような批判を受けて、代替的なアプローチとして「クリティカル・リアリズム」という立場が提案されています。この立場では、社会現象が複数の階層で構成され、上位レベルが下位レベルから創発することを認識します。心理的現象が生物学的基盤を持ちながらも、それに還元できないことを認めるように、社会的現象も物理的基盤を持ちながら独自の論理を持つと考えます。
クリティカル・リアリズムでは、社会構造と個人の行為を区別し、両者の相互作用を分析の中心に置きます。技術研究においては、技術が社会構造の一部を物質化するものと捉え、技術的な制約と社会的な条件の相互作用を分析することを重視します。
こうした批判的検討により、社会物質性アプローチの限界が明らかになると同時に、技術と社会の関係をより適切に理解するための新たな方向性が模索されています。技術の具体性を失わずに社会的文脈を考慮し、局所的な実践と広範な構造の両方を視野に入れた分析手法の開発が求められているのです。
脚注
[1] Orlikowski, W. J., and Scott, S. V. (2008). Sociomateriality: Challenging the separation of technology, work and organization. The Academy of Management Annals, 2(1), 433-474.
[2] Cecez-Kecmanovic, D., Galliers, R. D., Henfridsson, O., Newell, S., and Vidgen, R. (2014). The sociomateriality of information systems: Current status, future directions. MIS Quarterly, 38(3), 809-830.
[3] Orlikowski, W. J. (2009). The sociomateriality of organisational life: considering technology in management research. Cambridge Journal of Economics, 34(1), 125-141.
[4] Wagner, E. L., Newell, S., and Piccoli, G. (2010). Understanding project survival in an enterprise systems environment: A sociomaterial practice perspective. Journal of the Association for Information Systems, 11(5), 276-297.
[5] Scott, S. V., and Orlikowski, W. J. (2014). Entanglements in practice: Performing anonymity through social media. MIS Quarterly, 38(3), 873-893.
[6] Mutch, A. (2013). Sociomateriality – Taking the wrong turning? Information and Organization, 23(1), 28-40.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。