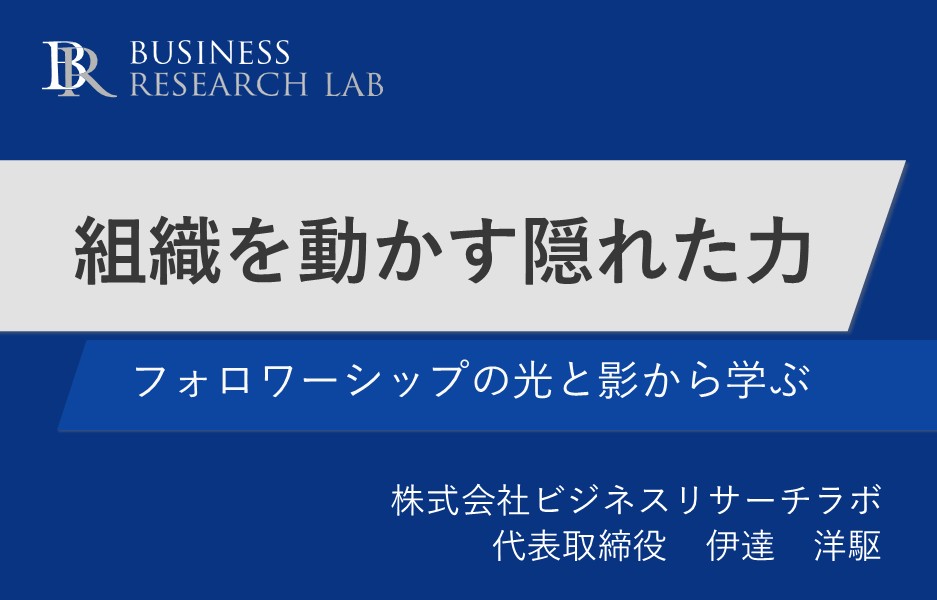2025年10月6日
組織を動かす隠れた力:フォロワーシップの光と影から学ぶ
組織の成功について語られる際、注目されるのは多くの場合、リーダーです。カリスマ性のある経営者、決断力に長けた管理職、革新的なアイデアを生み出すプロジェクトリーダー。こうした人物が注目される一方で、組織の大部分を占める部下や従業員の存在は軽視されがちです。
しかし、近年の研究では、リーダーの能力だけではなく、部下や従業員がどのような考え方を持ち、どのように行動するかも重要であることが示されています。フォロワーシップ、すなわち「部下としてのあり方」は、組織マネジメントにおいて影響力を持っています。
本コラムでは、フォロワーシップが職場にもたらす多面的な影響について紹介します。組織の成功を支える建設的な側面から、倫理的判断を左右する心理的メカニズム、さらには破壊的なリーダーを生み出す土壌となるリスクまで、フォロワーシップについて検討します。
効果的なフォロワーシップが組織を成功に導く
組織の成功において、リーダーの存在は確かに大事です。しかし、それと同程度に大事な要素がもう一つあります。それは、組織のメンバーが「部下」として果たす役割です。部下としてのあり方を研究する領域において、興味深い発見がありました。
ある銀行の事例が、この発見の出発点となりました。競争が激化する中で組織再編を迫られたこの銀行では、管理職が現場への対応に追われ、通常の業務指示を出すことができなくなりました。この状況で、部下たちは上司からの指示を待つことなく、自主的に業務を整理し、組織の再編を進めました。結果、リーダー不在の状況にもかかわらず、組織は危機を乗り越えることができました。
この事例は、従来の組織論に疑問を投げかけます。研究者たちは、部下の役割を見直す必要があると考えました。研究では、部下を5つのタイプに分類しています[1]。
- 第一に「羊型」と呼ばれるタイプです。これらの人々は指示されたことだけを実行し、自分で判断することを避けます。
- 第二に「イエスマン型」があります。行動力はあるものの、上司の意見に疑問を持たず、盲目的に従います。
- 第三に「疎外型」と名付けられたタイプは、批判的な思考力は持っているものの、組織に対して距離を置き、消極的な姿勢を示します。
- 第四に「生存者型」は、組織の変化に合わせて自分の安全を最優先に行動します。
- そして最後に、「効果的フォロワー」と呼ばれるタイプがあります。自発的に行動し、同時に批判的思考力も備えています。組織の目標達成に向けて貢献し、必要に応じて上司に意見することも厭いません。
この効果的フォロワーの特徴を検討すると、四つの要素が浮かび上がります。
- 自己管理能力:上司に依存することなく、自律的に仕事を進めることができます。階層関係に萎縮することなく、上司とも対等に議論を交わします。
- 組織コミットメント:ただし、これは上司個人への忠誠心とは異なります。組織の目標や価値観に対する献身的態度を指します。個人的な好き嫌いを超えて、組織全体の利益を考えて行動します。
- 能力と集中力:効果的フォロワーは自己研鑽を重ね、組織が期待する以上の成果を目指します。自分の強みと弱みを客観視し、チーム全体で最適な役割分担を実現しようとします。
- 勇気:これは単純な積極性ではありません。自分の信念を表明し、倫理的な判断に基づいて行動する勇気です。時には上司の決定に異議を唱え、組織の価値観を守るために立ち上がることも含まれます。
これらの特徴を持つ効果的フォロワーが組織に与える影響は大きなものです。監督コストの削減、意思決定の質の向上、組織の柔軟性の増大など、様々な恩恵をもたらします。リーダーが不在でも組織が機能し続ける、先ほどの銀行の事例も、このような効果的フォロワーの存在があったからこそ実現したと考えられます。
フォロワーシップの信念が倫理的行動を左右する
職場における不正や不祥事が断続的に発生する現状において、倫理的な行動の重要性が認識されています。従来、組織倫理の研究は主にリーダーの道徳的責任に焦点を当ててきました。しかし、実際の職場では、部下や従業員も日々の業務の中で道徳的な判断を迫られています。
ある研究では、部下が倫理的または非倫理的な行動を選択する際の心理的メカニズムが調査されています[2]。この研究は、エンロンやワールドコムといった企業不祥事を背景に、上司から非倫理的な指示を受けた部下がどのような反応を示すかを検討したものです。
研究者たちは、部下の行動を二つに分類しました。一つは「服従」で、上司からの非倫理的な要求に従ってしまうことを指します。もう一つは「抵抗」で、非倫理的な要求に対して異議を唱え、代替案を提示する行動です。
この選択を左右するのが、部下自身が持つ「フォロワーシップの信念」です。とりわけ注目されたのは、「リーダーシップの共同生成」という概念です。これは、組織の成功にはリーダーとフォロワーが協力して取り組むべきだという信念を意味します。
研究では、161名の社会人を対象に、二段階の調査が実施されました。最初の段階では、参加者のフォロワーシップに関する信念や、責任の所在に対する考え方が測定されました。四週間後の第二段階では、具体的な倫理的ジレンマのシナリオが提示されました。
提示されたシナリオは、自動車会社の従業員が上司からデータ改ざんを指示されるという状況でした。参加者は、この状況でどのような行動を取るかを選択しなければなりませんでした。
分析の結果、一定のパターンが明らかになりました。リーダーシップの共同生成という信念が弱い人ほど、上司の非倫理的な要求に従う可能性が高くなりました。これらの人々は、「責任は上司にある」として自分の責任を回避する傾向がありました。
一方、共同生成の信念が強い人々は、非倫理的な要求に対して抵抗を示す可能性が高くなりました。組織の倫理を維持することを自分の責任だと考え、上司に責任を転嫁することは少なくなりました。
ただし、研究では複雑な相互作用も発見されました。「リーダーシップのロマンス」と呼ばれる信念、すなわち組織の成果をリーダーの能力に帰する考え方が強い場合、共同生成の信念があっても責任転嫁が起こりやすくなることが分かりました。
この発見は、組織倫理における部下の役割を見直すきっかけとなります。倫理的な問題が発生した時、すべての責任をリーダーに求めるのではなく、部下にも主体的な責任があることを認識する必要があります。部下が組織倫理の維持に参加すべきという意識を持つことが、健全な組織文化の形成に重要です。
フォロワーシップへの無意識の偏見が関係を左右する
私たちは日常生活の中で、無意識のうちに様々な人々を分類し、評価しています。この心理的プロセスは職場においても作用します。上司が部下を見る時、部下が同僚を評価する時、私たちの頭の中では比較と判断が行われています。この評価システムが、職場の人間関係や組織の成果に影響を与えていることが明らかになりました。
この現象を理解するために、研究者たちは「フォロワーに対する暗黙の理論」という概念を挙げています。これは、人々が「部下とはこうあるべき」「従業員は一般的にこのような特徴を持つだろう」といった、フォロワーに対する前提や思い込みを指します。
1362名の参加者を通じて、この暗黙の理論の構造と影響が調査されました[3]。研究は5段階に分けて実施され、まず149名のリーダーからフォロワーの特徴について自由記述で意見を収集しました。その結果、1030項目の特徴が挙げられ、これを整理することで161項目に絞り込まれました。
続いて、428名のリーダーを対象とした分析により、フォロワーに対する暗黙の理論は6つの要因から構成されることが判明しました。「勤勉さ」「熱意」「良き市民性」という3つのポジティブな要因と、「従順性」「反抗性」「無能さ」という3つのネガティブな要因です。
さらに分析によって、これら6つの要因は2つの大きなカテゴリーに分かれることが明らかになりました。「フォロワープロトタイプ」と呼ばれる理想的なフォロワー像と、「フォロワーアンチプロトタイプ」と呼ばれる望ましくないフォロワー像です。
80名のリーダーとそれぞれの部下80名、計160名を対象とした調査では、リーダーが持つフォロワーへの暗黙の理論が、職場の人間関係に影響を与えることが実証されました。
具体的には、リーダーがフォロワーに対してポジティブな暗黙の理論(プロトタイプ)を持つほど、両者の関係性が良好になり、フォロワーの職務満足度も向上しました。相互の信頼関係が深まり、職場全体の雰囲気も改善されました。
反対に、リーダーがネガティブな暗黙の理論(アンチプロトタイプ)を持つ場合、フォロワーとの関係性は悪化し、職務満足度も低下しました。このような状況では、フォロワーは自分の能力を十分に発揮することができず、組織全体の生産性にも悪影響が生じました。
この研究が明らかにした洞察の一つは、リーダーの評価がフォロワーの実際の能力や行動よりも、リーダー自身の先入観に左右される場合があることです。リーダーがフォロワーをポジティブに捉えると寛大な評価をしやすくなり、ネガティブに捉えると厳しい評価を下しやすくなります。
フォロワーシップが破壊的リーダーを支える
歴史を振り返ると、破壊的なリーダーの台頭により多くの組織や社会が被害を受けてきました。独裁的な政治指導者、腐敗した企業経営者、権力を乱用する管理職など、その形態は様々です。従来、このような破壊的リーダーシップの研究では、リーダー個人の性格や能力に焦点が当てられてきました。しかし、近年の研究では、破壊的リーダーの台頭と維持には、リーダー以外の要因も関与していることが明らかになっています[4]。
この現象を説明するために、「毒のトライアングル」という理論的枠組みが取り上げられました。これは、破壊的なリーダーシップが「破壊的なリーダー」「影響されやすいフォロワー」「それらを促進する環境」という3つの要素の相互作用により生まれるとする考え方です。
破壊的リーダーの特性として、カリスマ性が挙げられます。一般的にカリスマは魅力的な特質とされますが、破壊的リーダーの場合、このカリスマ性は恐怖を煽ったり個人の権力増大を目的としたビジョンの推進に使われたりします。個人的な権力欲が強く、社会全体の利益よりも自分の地位や支配を優先します。
ナルシシズムも破壊的リーダーの特徴です。自己中心的で傲慢な態度を示し、他者の意見を軽視します。幼少期や過去の経験から生まれたネガティブな世界観を持ち、これが支配欲や攻撃性の源泉となります。特定の集団に対する憎悪や敵意を正当化するイデオロギーを掲げることも見られます。
しかし、破壊的リーダーだけでは組織や社会を支配することはできません。そこで重要な役割を果たすのが、「影響されやすいフォロワー」の存在です。研究では、このようなフォロワーを「追従者」と「共謀者」の2つのタイプに分類しています。
追従者は、基本的なニーズが満たされていない状況にある人々です。経済的困窮や社会的孤立により、現状を変えてくれる強力な指導者を求めています。自己評価が低く、心理的に未成熟な状態にあることもあります。これらの人々は、破壊的リーダーの約束に希望を見出し、批判的思考を放棄してしまいます。
一方、共謀者は野心的で、自分の地位や富を向上させることを主な目的としています。破壊的リーダーと共通の価値観や世界観を持ち、リーダーの成功が自分の利益につながると計算しています。利己的な動機により、意図的にリーダーの破壊的行動に協力します。
第三の要素である環境条件も、破壊的リーダーシップの発生に関与します。政治的、経済的、社会的な不安定性は、人々に強力な指導者への渇望を生み出します。脅威の認識が高まると、その脅威から守ってくれる強いリーダーを求める心理が働きます。
文化的な要因も見逃せません。不確実性を避けようとする文化、集団主義的な価値観、権力の格差を受け入れやすい文化では、強権的なリーダーが支持されやすくなります。制度的な監視体制が不十分な環境では、権力の乱用を防ぐメカニズムが機能せず、破壊的行動が野放しになります。
フォロワーシップの自覚は意欲や行動を低下させる
私たちは日常的に様々なラベルを使って自分自身や他者を定義しています。「リーダー」「管理職」「専門家」といったラベルがある一方で、「フォロワー」「部下」「従業員」といったラベルも存在します。これらのラベルは名称以上の意味を持ち、実際に人々の心理状態や行動に影響を与えます。
研究者たちは、「フォロワー」というラベルが持つ心理的効果について、実験的手法と現実の職場調査の両方を用いて検証しました[5]。従来のフォロワーシップ研究では、積極的で建設的なフォロワーの価値が強調されてきましたが、この研究では「フォロワー」という言葉そのものが持つ影響に着目しました。
最初の実験では、カナダの大学生154名を対象として、参加者に性格診断テストを受けてもらい、その結果に基づいて「リーダー」「フォロワー」のいずれかの役割を割り当てると伝えました。実際には結果は操作されており、参加者はランダムに役割を割り当てられました。比較対象として、どちらのラベルも与えられない統制群も設けられました。
実験の結果、「フォロワー」とラベル付けされた参加者は、「リーダー」やラベルなしの参加者と比較して、ポジティブな感情が低下しました。熱意や注意力といった肯定的な感情が有意に減少したのです。
この感情の変化は行動にも直接的な影響を与えました。フォロワーとラベル付けされた参加者は、グループに対する自発的な貢献意欲が低下しました。義務を超えてチームのために何かをしようという積極性が失われました。
この現象は実験室内だけのものではありません。第二の研究では、実際に働いている348名の社会人を対象に調査が実施されました。参加者は、自分自身をどの程度「フォロワー」だと認識しているかを評価し、同時に仕事に対するポジティブな感情と職場での自発的行動についても報告しました。
結果は実験結果と一致していました。自分をフォロワーとして強く認識している人ほど、仕事に対するポジティブな感情が低く、職場での自発的な行動も少なくなっていました。組織市民行動と呼ばれる、正式な職務には含まれないが組織にとって有益な行動を取る頻度が少なかったのです。
この現象が起こる理由について、研究者たちは、「フォロワー」というラベルに付随する社会的ステレオタイプに原因があると考察しています。多くの人にとって、フォロワーという言葉は「受動的」「従順」「独創性がない」「指示に従うだけ」といったネガティブなイメージと結びついています。
これらのステレオタイプは、個人の自己認識に影響を与えます。自分がフォロワーだと認識すると、無意識のうちにこれらのネガティブな特性を内面化してしまうのです。その結果、本来持っている能力や主体性を発揮することが難しくなり、消極的な行動パターンに陥ってしまいます。
脚注
[1] Kelley, R. E. (1988). In praise of followers. Harvard Business Review, 66(6), 142-148.
[2] Carsten, M. K., and Uhl-Bien, M. (2013). Ethical followership: An examination of followership beliefs and crimes of obedience. Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(1), 49-61.
[3] Sy, T. (2010). What do you think of followers? Examining the content, structure, and consequences of implicit followership theories. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 113(2), 73-84.
[4] Padilla, A., Hogan, R., and Kaiser, R. B. (2007). The toxic triangle: Destructive leaders, susceptible followers, and conducive environments. The Leadership Quarterly, 18(3), 176-194.
[5] Hoption, C., Christie, A., and Barling, J. (2012). Submitting to the follower label: Followership, positive affect, and extra-role behaviors. Zeitschrift fur Psychologie, 220 (4), 221-230.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。