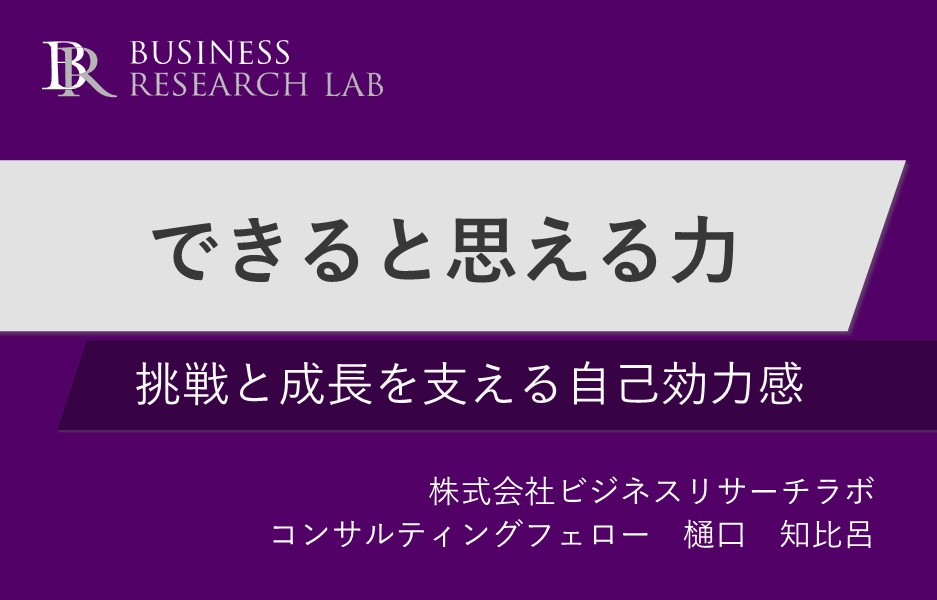2025年10月2日
できると思える力:挑戦と成長を支える自己効力感
人が行動を変えるとき、その背後にはどのような心理的プロセスがあるのでしょうか。新しい仕事に挑戦する、苦手なプレゼンに立ち向かう、あるいは学び直しを決意するというような行動の変化には、単なる「やる気」だけでは説明しきれない内面の動因が存在します。その中でも近年、注目を集めているのが「自己効力感(self-efficacy)」という概念です。これは「自分にはできる」という感覚、すなわち特定の行動を効果的に遂行できるという信念を指し、個人の選択、努力、継続、そして感情反応に広く影響を与えることが知られています。
自己効力感は、1970年代に心理学者アルバート・バンデューラによって理論化されて以来、教育・医療・スポーツといった分野で幅広く研究されてきました。中でも、行動療法の分野では、この信念が行動変容の重要な鍵を握っていることが明らかになっています。たとえば、強い恐怖を抱く被験者に対して段階的な行動課題を与えた研究では、「できる」と信じられるようになった被験者ほど、実際の行動に移せたという結果が示されています。過去の成功経験そのものよりも、「今の自分ができると信じられるかどうか」が未来の行動を予測するのです。
本コラムでは、この自己効力感という認知的要素に着目し、なぜそれが行動や成果に結びつくのか、そしてこの知見をビジネスや組織マネジメントにどう活かせるのかを探っていきます。社員の挑戦意欲を引き出すには何が必要か、マネージャーが部下の行動変容を促すにはどんな環境づくりが有効なのか。そのヒントは、心理学の研究成果の中にあります。具体的な実証研究の結果をもとに、自己効力感の形成メカニズムとその応用可能性について詳しく見ていきます。
自己効力感が行動変化を導く認知の力
行動の変化を引き起こす心理的な仕組みに注目し、その中心的な要素として自己効力感の概念を据えた理論を提案した研究を取り上げます[1]。自己効力感とは、自分がある行動を効果的に遂行できるという信念のことを指します。この研究では心理的な治療手法が効果を発揮する仕組みを明らかにするため、自己効力感という認知的要素が果たす役割を詳細に検討しています
この研究は、ヘビに対して強い恐怖心を抱える成人を対象に、異なる治療法(能動的モデリング、代理的モデリング、脱感作)によって自己効力感がどのように変化し、行動変容につながるかを調査したものです。
能動的モデリングは、本人自身が実際の行動に挑戦し、それを成功させることで「自分にもできる」という実感を得て、自己効力感を育むアプローチです。一方、代理的モデリングは、他者が課題を達成する様子を観察することで、自らの行動への自信を高めようとする方法です。脱感作は、不安や恐怖を伴う対象に対し、少しずつ接触機会を増やしていくことで、過剰な感情反応を緩和していく段階的な心理的介入です。
治療前後での自己効力感のレベルと行動テスト(ヘビへの接近・接触など)を比較し、それぞれの介入が自己効力感に与える影響と、その自己効力感が行動に与える予測力を評価しました。
調査の結果、治療後に自己効力感が高まった人ほど、行動テストにおいて恐怖の対象であるヘビに対し、より積極的に近づく傾向が見られたことが明らかになりました。特に、直接的な体験を通じて課題を克服する「能動的モデリング」による介入は、自己効力感と行動の変化を最も強く促す結果となり、代理的モデリングや脱感作と比べて、行動変容の程度も大きくなる傾向が見られました。
さらに興味深いのは、過去の成功体験があるかどうかよりも、「自分にはできる」という信念が、未知の課題においても行動の成否を予測する指標となっていた点です。つまり、自己効力感が高まることで、これまで回避してきた不安や緊張を引き起こす状況に対しても挑戦する力が生まれ、実際の行動へとつながるということです。
この理論の示唆は、心理的支援の枠組みに留まらず、ビジネスや人材開発の領域にも適用可能です。たとえば、新しい業務への挑戦に不安を感じる従業員に対しては、段階的に成功体験を積ませるような支援を行うことが、行動の変化を促す上で有効と考えられます。指導者やメンターの適切なロールモデル行動の提示、具体的な成功のフィードバック、本人が自信をもってタスクに取り組める設計を施すことで、自己効力感の向上を促しやすくなるでしょう。
また、失敗経験に過度にとらわれた社員に対しても、「これまでに克服できた課題がある」「成功のプロセスが再現可能である」といった認知的再評価を支援することによって、再挑戦への動機づけを支えることができます。これは、自己効力感が単なる希望的観測ではなく、行動結果に直結する信念として機能するという理論に基づいたアプローチといえます。
マネジメントの観点では、メンバーのパフォーマンスを引き出すためには、自己効力感を支える体験の設計が重要になります。単に成功を称賛するだけでなく、その成功が本人の努力によって達成されたものであることを明示し、自分の行動や努力によって結果が生じたと感じられるようにすることが求められます。また、代理経験をうまく活かすためには、ロールモデル(見本となる人物)の選び方が大切です。モデルとなる人とそれを見る人が、年齢やスキルのレベル、考え方などにある程度似ていると、「自分にもできそうだ」と感じやすくなり、自信を持ちやすくなるのです。
さらに、緊張や不安といった心理状態のマネジメントも自己効力感と関連します。状況に対する感情の反応をうまくコントロールできるようになると、自分の力に対する捉え方が前向きになり、難しい課題にも積極的に取り組めるようになります。たとえば、難易度の高いプレゼンテーションに向けたリハーサルを設け、安心して緊張を軽減する機会を提供することは、自己効力感を支える実践的な方法となり得ます。
集団の行動力を高める「自己効力感」のメカニズム
人は、自らの能力をどのように認識し、環境にどう働きかけるかによって、行動や感情、思考に大きな差が生まれます。この自己効力感の概念を心理学的に探究した研究を紹介します。この研究は、個人だけでなくが、いかに社会的行動や変革に影響を与えるかというテーマを、理論と実証の両面から掘り下げています[2]。
この論文では、恐怖症の被験者に対して、段階的に不安や緊張を引き起こす課題を与え、その達成度とそれに対する効力感の変化を測定する実験を行いました。その結果、自己効力感が高まるほど、被験者の行動はより積極的で、かつ感情的な覚醒(例:不安や恐怖)は減少することが明らかとなりました。
この研究から得られた最も重要な知見は、「人は成功したかどうかではなく、自分が成功できると信じているかどうかによって、その後の行動が左右される」という点です。実際に、過去の成功体験よりも、自己効力感の方が、未来のパフォーマンスを強く予測していました。また、この効力感は「他者の成功を観察する」「説得的なフィードバックを受ける」「生理的な状態をどう解釈するか」など、複数の情報源から形成されることが示されています。
加えて、この研究は個人の効力感だけでなく、集団全体としての「集団的効力感(collective efficacy)」にも注目しました。社会変革や組織改革のような大規模な課題においては、個人の努力だけでなく、「私たちなら変えられる」と集団が感じられるかどうかが、行動の持続性や戦略の選択に大きな影響を与えます。これは、組織マネジメントにおいて極めて実践的な示唆を持ちます。
たとえば、改革を推進するチームが高い集団的効力感を持っていると、困難に直面した際でも粘り強く取り組み続けやすくなります。逆に、組織内で「どうせやっても無駄だ」という空気が支配的になると、どれだけ優秀な人材が揃っていても行動は停滞します。
したがって、管理職やリーダーには、成功体験の共有、他者のモデルとなる行動の可視化、成功の明確なフィードバックといった工夫を通じて、環境づくりが求められるでしょう。高い集団的効力感を持つ組織では、困難なプロジェクトにも前向きに取り組む傾向があり、チーム全体の粘り強さや協力意識が強くなることが知られています。
また、この研究は、従業員の目標設定や自らの行動や思考をコントロールしながら進める自己調整のプロセスにも応用可能です。個人が大きな目標に向かって進むには、近接的な副次的ゴールの設定が有用であり、これによって「できた」という実感が蓄積され、自己効力感が強化されていきます。これは、モチベーションの持続や離職防止といった課題に対しても、実務的なアプローチを提供する理論となり得ます。
自己効力感が仕事成果に与える影響
自己効力感が実際にどれほどパフォーマンスに影響するのかを検討したメタ分析があります[3]。メタ分析とは、独立して実施された複数の研究結果を統合し、それらを解析する方法です。この研究では、、自己効力感と仕事関連のパフォーマンスの関連性を分析しました。
この研究によると、自己効力感と仕事上の成果との間には、が確認されました。これは、自己効力感の高い人ほど、そうでない人よりも平均的にやや優れた成果を上げる傾向があることを示しています。興味深いのは、この効果が、目標設定やフィードバックなど、他のよく知られた介入手法よりも大きい点です。さらに、性格特性などの他の個人要因に比べても、自己効力感はより有力なパフォーマンスの予測因子であることが明らかとなりました。
ただし、この効果は一様ではなく、タスクの複雑さによって左右されることも判明しました。分析によれば、単純なタスクでは自己効力感とパフォーマンスの関係が強く、タスクが複雑になるほどこの関係は弱まる傾向が見られました。複雑な業務においては、必要なスキルや戦略を学ぶまでに時間がかかるため、自己効力感の影響が直ちには表れにくいと考えられます。しかし、経験を積みタスクに慣れていく中で、その関係は再び強くなる可能性があるとも指摘されています。
また、実験室での模擬タスクと、実際の職場での実務タスクの間でも効果の出方に違いがあることが確認されました。自己効力感の影響は、模擬タスクでより強く表れ、実際の職場環境では相対的に弱くなる傾向があるのです。これは、実務の現場では、予測できない外部要因や複雑な人間関係、時間的制約などが自己効力感の効果を妨げるからかもしれません。
この研究の結果から、マネジメントにおいては自己効力感の重要性を認識し、それを高めるための環境整備や支援が有用であると考えられます。まず、マネージャーは従業員に対して、タスクの目標や目的、期待される成果を明確に伝えることが大切です。何をもって成功とするのかが不明確であれば、従業員は自らの能力を正しく見積もることができず、結果的にパフォーマンスが下がる恐れがあります。
また、複雑な業務に取り組む際には、単に技術的スキルを教えるだけでなく、その業務に成功するための戦略的なアプローチや考え方についてのトレーニングも必要です。たとえば、「この仕事を成功させるには、どういった段取りや情報収集が必要か」を自ら分析できるよう支援することは、自己効力感の向上に資するでしょう。
さらに、職場の環境自体が、集中力を妨げるような物理的・心理的ノイズからできるだけ隔離されていることも重要です。不要な中断や混乱が頻発する環境では、自己効力感は損なわれやすくなり、パフォーマンスにも悪影響を及ぼす可能性があります。
自己効力感を高める取り組みは、単発ではなく、タイミングや環境との連携が重要です。たとえば、トレーニングの実施時期が、実際の業務に直結していないと、学習内容が現場で活かされないまま忘れ去られてしまうこともあるでしょう。したがって、育成や研修の計画を立てる際には、実際の業務と連動させたスケジューリングが望ましいといえます。
健康行動を左右する「できる」という感覚
健康行動と自己効力感との関係をレビューした調査結果をもとに、ビジネスの現場にも通じる実践的示唆を探った研究を紹介します[4]。この研究は、痛みのコントロールや禁煙、摂食障害の対応、心臓リハビリ、治療計画の継続といった多様な健康行動を対象に、「自分にはできる」という感覚、すなわち自己効力感がどのように形成され、それが実際の行動や成果にどのように関係しているかを整理したものです。
この研究はこれまでの複数の実証研究を精査し、「自己効力感」が人の行動変容において中心的な役割を果たしていることを明らかにしました。たとえば、禁煙治療においては、再発を防ぐ決め手は“誘惑に耐えられる自信”であるとされ、痛みの管理では“痛みに耐えられる”という信念が実際の耐性に影響するという結果が示されています。
また、心臓発作からの回復では、患者だけでなく配偶者の「この人は回復できる」という認識も患者のや回復の度合いを左右するという興味深い知見が得られました。
こうした研究結果は、健康だけでなく、ビジネスや組織マネジメントにおいても有用です。自己効力感は、与えられた目標に向けて主体的に動くための“内発的な力”と捉えることができます。チームメンバーが自らの能力を信じられるとき、行動への移行がスムーズになり、成果も高まりやすくなります。
実務においては、単に知識やスキルを教えるだけではなく、成功体験を積ませる設計や、周囲の肯定的なフィードバック、本人が進捗を実感できる仕組みが、自己効力感を高めるうえで効果的です。
たとえば、業務改善プロジェクトの中で、初期段階から小さな成功を積み重ねる「スモールウィン」の設計は、心理的安全性の醸成にもつながります。また、他者の成功を観察することも有効です。組織内で成功体験を共有する文化は、メンバーの自信形成を支援します。
さらに、上司やマネージャーの関わり方も重要です。配偶者の認知が回復に影響を与えるように、マネージャーが部下の能力に対して肯定的な見立てを持ち、その姿勢を言葉や態度で表現することは、部下の行動意欲に直接影響します。「あなたならできる」「期待している」といった言葉は、単なる激励ではなく、心理的な土台づくりとして機能します。
この研究は、行動医学の視点から健康行動を分析していますが、その知見は組織行動の改善や人材育成の施策にも展開可能です。従業員の行動を変えるには、まず「やれる気がする」と思ってもらうこと、そしてその認識を支える環境を設計することが、行動変容と成果創出の第一歩になるでしょう。
学習成果を左右する自己効力感の影響力
自己効力感が、どのようにして学習の成果や動機づけに影響を与えるかについて、20年分のを紹介します[5]。
この研究は、アメリカの学生を対象にした複数の実験・調査結果を総括する形で実施されました。研究の焦点は、自己効力感がどのように学習行動や学業成績、そして感情反応と関連しているのかを明らかにすることにあります。
調査の結果、自己効力感の信念は、活動選択、努力、持続性、感情の安定性といった動機づけの中心的要素と強い関連を持つことが確認されました。特に、自己効力感の高い学生ほど、難しい課題にも積極的に取り組み、途中で諦めることなく継続し、結果として高い成績を収める傾向にあることが示されています。また、この信念は、学習における自己調整(自己目標の設定やモニタリング、学習方略の活用)とも密接に関係しており、自己効力感が高まることで、より高いレベルで学習をコントロールできるようになるという結果が得られています。
これらの知見は、教育現場に限らず、ビジネスの人材育成やマネジメントにおいても示唆に富んでいます。例えば、自己効力感の高い社員は、自分の能力に対する確信を持って業務に臨むため、新たなプロジェクトへの参加意欲が高く、困難な課題にも粘り強く取り組む傾向があります。また、達成経験やロールモデルの観察の要素が、効力感の形成に寄与することから、上司や教育担当者によるサポートの方法も再考される必要があるでしょう。
マネジメントの観点から見ると、評価制度や目標設定の運用にも工夫の余地があります。一例として、個人ごとに適した短期的に達成可能な目標を設定し、段階的に成功体験を積ませることで、自己効力感を高める設計が有効です。こうした働きかけが、結果的にパフォーマンスの最大化や離職防止にもつながる可能性があります。
自己効力感研究の現在地と今後の展望
自己効力感は、教育や心理学の領域で長く注目されてきた主要な研究テーマです。この概念がどのように展開されてきたのか、多くの研究成果を踏まえて整理・考察したレビュー論文を取り上げます[6]。レビュー論文とは、特定のテーマについて過去の研究成果を体系的に整理・分析し、現在の知見や研究動向を明らかにする論文です。
この論文は、特に学業環境における自己効力感という信念のあり方に焦点を当てています。調査の対象は、主に米国の児童・生徒・学生における自己効力感に関する既存の文献レビューであり、その方法としては実証的研究と理論的考察の両面から過去20年間の知見を総括しています。その結果、自己効力感は、学業成績や動機づけといった教育成果に強く関連していることが明らかになっています。
中でも重要な知見として、自己効力感は極めて文脈依存的であり、抽象的な自己評価よりも、課題や状況に特化した評価が、実際のパフォーマンスとより強い関連を持つことが示されています。これは、例えば「数学が得意」といった漠然とした自己評価よりも、「連立方程式を解ける」というような具体的なスキルに関する自己評価の方が、より行動や成果に直結するという意味です。
こうした知見は、自己効力感を測定・育成する際には、その特異性と対応性を重視する必要があることを示唆しています。特異性とは、自己効力感が「特定の課題や状況」に対してどれだけ限定的に生じるかを示す性質であり、たとえば「数学の計算」には自信があっても「作文」には自信がないというように、課題ごとに異なる自信の程度を指します。対応性とは、自己効力感の測定内容が実際のパフォーマンス課題とどれだけ具体的に一致しているかを示す概念で、実際に行う行動と評価項目のズレが小さいほど対応性が高いとされます。
また、自己効力感は単に「強ければよい」というものではなく、正確さ、すなわち自分の能力に関する認識が実際のパフォーマンスとどれだけ正確に一致しているかを示す精度も重要であるとされます。過剰な自信は不適切な課題選択や早期の失敗につながり、逆に過小評価は挑戦回避や学業意欲の低下を引き起こす可能性があります。したがって、学習者が自身のスキルや知識を客観的に理解するための支援は、教育現場において極めて有用です。
このような理論的示唆は、教育マネジメントにおいても応用が可能です。たとえば、従業員の職務に対する自己効力感を高めるために、業務ごとの達成体験を可視化し、小さな成功を積み重ねていくプロセスを設計することが効果的です。管理職は、部下の自己評価の正確性に目を配り、過剰な自信や不必要な自己卑下を見逃さず、適切なフィードバックや支援を提供することが求められます。
さらに、自己効力感は集団レベルでも形成されうるという点も、組織マネジメントにとって有意義です。学校現場における集団的効力感の概念を組織に応用することで、チーム全体のパフォーマンス向上に寄与する可能性があります。たとえば、部門全体で「私たちにはこのプロジェクトを成功させる力がある」という共通の信念を醸成することが、実際の行動や成果に好影響を与えることが期待されます。
教育・組織の現場では、単なる「やる気の問題」として片付けがちな動機づけのメカニズムに対して、このレビュー論文が提供する視座は、より精緻で実践的な指針となるでしょう。
自己効力感には小さな成功の積み重ねとフィードバックが重要
本コラムでは、自己効力感という認知的信念が、個人の行動選択や努力の持続、感情の安定、さらには学習成果や仕事のパフォーマンスに至るまで、広範な影響を及ぼすことを、心理学的研究知見をもとに検討してきました。
特に、能動的な成功体験や、他者の成功を観察することで形成される自己効力感は、個人だけでなく組織全体の行動力や変革推進力にまで影響を及ぼすことがわかっています。自己効力感の向上は、「やればできる」という前向きな心理状態を育み、結果として挑戦的な課題への積極的な関与や、失敗からの再起力を高めることにつながります。また、自己効力感は高すぎても低すぎても望ましくなく、実際の能力と釣り合った適切な調整が重要です。そのためには、日々の小さな成功体験の積み重ねと、適切なタイミングでのフィードバックが不可欠となります。
ビジネスの現場においては、こうした心理的資源を育成する環境設計が、パフォーマンスの最大化や離職防止、学習促進といった成果につながる可能性を秘めています。上司やリーダーは、部下の自己効力感を的確に支える存在となることが求められます。そのためには、達成可能な目標設定、成功の意味づけ、挑戦を歓迎する組織風土の醸成といった取り組みが有用です。
自己効力感という目に見えない資源をいかに育むか。それは、今後の人材育成やマネジメントの質を大きく左右するテーマといえるでしょう。
脚注
[1] Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191.
[2] Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American psychologist, 37(2), 122.
[3] Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (1998). Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 124(2), 240–261. https://doi.org/10.1037/0033-2909.124.2.240
[4] O’Leary, A. (1985). Self-efficacy and health. Behaviour research and therapy, 23(4), 437-451.
[5] Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary educational psychology, 25(1), 82-91.
[6] Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Advances in motivation and achievement, 10(149), 1-49.
執筆者
 樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
樋口 知比呂 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー
早稲田大学政治経済学部卒業、カリフォルニア州立大学MBA修了、UCLA HR Certificate取得、立命館大学大学院博士課程修了。博士(人間科学)。国家資格キャリアコンサルタント。ビジネスの第一線で30年間、組織と人に関する実務経験、専門知識で、経営理論を実践してきた人事のプロフェッショナル。通信会社で人事担当者としての経験を積み、その後、コンサルティングファームで人事コンサルタントやシニアマネージャーを務め、さらに銀行で人事部長などの役職を歴任した後、現在はFWD生命にて執行役員兼CHROを務める。ビジネスと学術研究をつなぐ架け橋となることを目指し、実践で役立つアプローチを探求している。