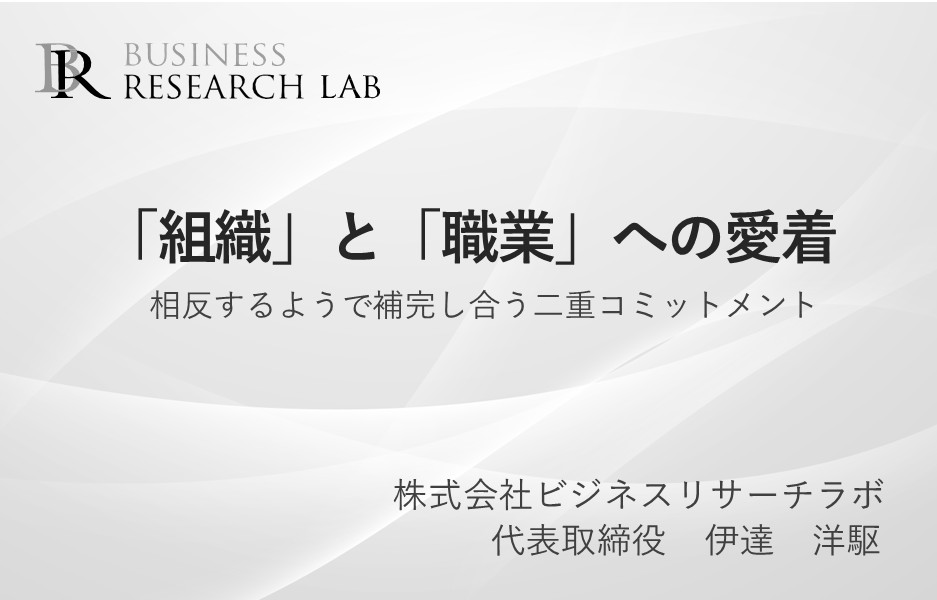2025年10月2日
「組織」と「職業」への愛着:相反するようで補完し合う二重コミットメント
私たちは様々な対象に対して献身を求められています。会社に尽くすべきか、それとも自分の専門性を磨くことに注力すべきか。こうしたジレンマを感じたことがある方も多いのではないでしょうか。この二つの方向性は、時に私たちを引き裂くように感じられることもあります。
本コラムでは、「二重コミットメント」について掘り下げていきます。組織へのコミットメントと職業へのコミットメント、この二つがどのように関連し、私たちの働き方や意識にどう関わってくるのかを探ります。
長い間、これらのコミットメントは相反するものとして考えられてきました。「会社人間」になれば専門性が犠牲になり、「プロフェッショナル」を追求すれば会社への忠誠心が低下するという具合です。しかし、近年の研究は、この二つが必ずしも対立するものではなく、むしろ相互に補完し合う関係にあることを明らかにしています。
入社してからの時間経過とともに変化する二つのコミットメントの関係、それぞれのコミットメントが持つ異なる側面、生産性への影響経路、そして職務関与との関係。これらの観点から「二重コミットメント」の様相を描き出していきます。
二つのコミットメントは入社後に補完関係となる
新しい会社に入社するとき、多くの期待と熱意を抱いています。組織への献身と自分の専門性を高めたいという思いの両方を持っていることが多いかもしれません。この二つの思いは、時間の経過とともにどのように変化していくのでしょうか。
韓国の大手電子企業で働く研究開発専門職を対象にした調査では、入社後の時間経過によって組織コミットメントと専門職コミットメントがどう変化するかが明らかになりました[1]。組織コミットメントとは所属する会社に対する心理的な愛着や一体感を、専門職コミットメントとは自分の職業や専門分野に対する愛着や一体感を指します。
この調査では、204名の研究開発専門職が対象となり、在職期間は1ヶ月から12年と幅広く、平均では22ヶ月でした。
調査結果から、変化のパターンが見えてきました。入社後すぐの段階では、組織コミットメントも専門職コミットメントも高い水準にありました。しかし、3ヶ月から6ヶ月が経過すると、専門職コミットメントがやや減少し始めます。そして7ヶ月から12ヶ月の間に大きな変化が起こります。
ここで「リアリティショック」と呼ばれる現象が発生します。入社前に抱いていた期待と実際の職場環境や仕事内容とのギャップに直面するのです。この時期に組織コミットメントが大きく低下する一方で、専門職コミットメントは増加に転じます。会社への期待が裏切られると感じると、その心理的な埋め合わせとして、専門分野への思いを強めるという補完的な関係が生まれるのです。
13ヶ月から36ヶ月の期間では、組織コミットメントは低い水準が続きますが、37ヶ月以降になると再び上昇傾向を見せます。一方、専門職コミットメントは大きな変動を見せなくなります。
このような変化のパターンから、入社後6ヶ月から1年の期間が特に重要であることがわかります。この時期にリアリティショックを経験し、組織への期待と現実のギャップを感じ、専門職コミットメントを高めることで心理的な安定を図ろうとします。
この補完関係の発見は、組織と専門職の間の二重コミットメントが単純に対立するものではないことを示しています。両者の間に動的な相互作用があり、時間の経過とともに変化していくことを理解することが大切です。
情緒的コミットメントが組織への態度を最も強く予測
組織へのコミットメントというと一つの概念のように思えますが、いくつかの異なる側面から構成されています。感情的な愛着なのか、単に離れるコストが高いからなのか、それとも道徳的な義務感なのか。その性質によって、私たちの行動や態度に与える影響は異なります。
組織や職業に対するコミットメントを構成する三つの要素について、カナダの看護師を対象にした研究で調べられました[2]。三つの要素を見てみましょう。
- 情緒的コミットメント:組織や職業に対する感情的な愛着や同一視の強さに基づくコミットメント
- 継続的コミットメント:組織や職業から離れることの損失への認識や、代替選択肢の少なさから生じるコミットメント
- 規範的コミットメント:組織や職業に対する道徳的な義務感や恩義として感じるコミットメント
この研究では、学生看護師と登録看護師という二つの異なるグループを対象に調査が行われました。学生看護師は入学時と1年後の2回、登録看護師は1回のアンケート調査を通じて、組織と職業それぞれに対する三つのタイプのコミットメントが測定されました。
分析の結果、組織へのコミットメントと職業へのコミットメントの間には関連性があるものの、それぞれが区別できる構造を持つことが確認されました。会社への思いと専門性への思いは、関連しつつも別物だということです。
さらに、三つのタイプのコミットメントの中で、情緒的コミットメントが最も強く仕事の満足度や離職意図と関連していました。心から組織や職業に愛着を感じている人ほど、仕事に満足し、辞めようとは思わないということです。
一方、継続的コミットメントは、代替的な仕事がないことや経済的な損失への懸念と関連しています。「他に選択肢がない」「辞めると損をする」という理由で組織に留まる場合です。このタイプのコミットメントも離職意図とは負の相関を示しましたが、情緒的コミットメントほど強いものではありませんでした。
規範的コミットメントは、組織に対する道徳的な義務感を示し、特定の行動(例えば欠勤やパフォーマンスの低下)とは中程度の関係を示しました。「恩義があるから」「辞めるべきではないという価値観があるから」という理由で組織に留まる場合です。
これらの結果から、組織や職業に対する情緒的な愛着や同一感が、ポジティブな職場行動や態度に最も強い影響力を持つことが明らかになりました。自分の仕事や組織に対して感情的に結びついていると感じている人は、より満足感を得やすく、意欲的で、パフォーマンスも高い傾向があります。
継続的コミットメントや規範的コミットメントも重要な役割を持ちますが、これらは情緒的コミットメントとは異なる動機づけのメカニズムを通じて組織に影響を与えます。例えば、継続的コミットメントが高い場合、「辞められないから仕方なく」という消極的な理由で組織に残るため、必ずしも高いパフォーマンスには結びつかないかもしれません。
職業へのコミットメントが生産性を高める動機となる
組織と職業の両方に同時にコミットする「二重コミットメント」は、生産性にどのような影響を与えるのでしょうか。この問いに答えるため、アメリカの大学に勤務する経営学の教授を対象にした研究が行われました。
この研究では、テニュア(終身在職権)を取得した教授237名を対象に、組織(大学)へのコミットメントと職業(学術研究職)へのコミットメントが、研究生産性にどのように影響するかを調査しました[3]。研究者たちは次のような仮説を立てました。
- 職業へのコミットメントは「内発的動機づけ」(活動自体が楽しいから行う動機)を高め、「外発的動機づけ」(報酬や評価のために行う動機)を低下させる
- 組織へのコミットメントは逆に、外発的動機づけを高め、内発的動機づけを低下させる
分析の結果、職業(学術研究職)へのコミットメントは内発的動機づけを有意に向上させることが明らかになりました。そして、この内発的動機づけが高い目標設定や目標へのコミットメント、研究への努力を促進し、結果として研究生産性を向上させました。
一方、組織(大学)へのコミットメントは内発的動機づけを低下させ、外発的動機づけを向上させました。しかし、外発的動機づけは研究目標や研究時間、生産性に対して統計的に有意な影響を与えませんでした。結果的に、組織コミットメントは研究生産性と直接関連しませんでした。
このことから、少なくとも研究活動のような創造的な知識労働においては、職業へのコミットメントが内発的動機づけを通じて生産性を高めることが示されました。「研究が好きだから研究する」という内発的な動機が、高い研究目標を設定し、その目標に対するコミットメントを高め、より多くの時間と努力を投入することにつながり、高い生産性をもたらすのです。
この結果は自己決定理論とも整合しています。自己決定理論によれば、内発的動機づけは自律性、有能感、関係性という基本的な心理的欲求が満たされたときに高まります。職業へのコミットメントが高まると、自分の仕事に対する自律性や有能感が強化され、内発的動機づけが促進されると考えられます。
職務関与が他のコミットメントを強く媒介する
これまで、組織コミットメントと職業コミットメントの関係や、それぞれがどのように生産性に影響するかを見てきました。しかし、職場における私たちの心理的な関与はもっと多面的です。様々なコミットメントがどのように関連し合い、影響し合っているのでしょうか。
カナダ西部の病院に勤務する看護師238名を対象にした調査では、5つの異なる形態のコミットメントの関係性が検証されました[4]。この5つとは、情緒的組織コミットメント、継続的組織コミットメント、キャリア・コミットメント、職務関与、そして勤労倫理です。
情緒的組織コミットメントと継続的組織コミットメントはすでに説明した通りです。キャリア・コミットメントは自分のキャリア全体に対する関与、職務関与は現在の職務への心理的な没入度、勤労倫理は仕事そのものに価値を置く考え方を指します。
この研究では、これら5つのコミットメントが実際に区別可能かどうかを確かめました。確認的因子分析という統計手法を用いた結果、これらは確かに別々の概念として識別できることが確認されました。継続的組織コミットメントは、「個人的犠牲」と「低代替案」という二つの下位次元に分かれることもわかりました。
これらのコミットメント間の関係性について、二つの理論モデルを検証しました。一つ目のモデルは、コミットメントが同心円状に並び、中心にある「勤労倫理」から外側に向かって他のコミットメントが位置するというものです。このモデルでは、内側にあるコミットメントほど安定的で、外側にあるコミットメントほど状況依存的だと考えられていました。
もう一つのモデルでは、「職務関与」が中心的な媒介変数として機能し、それが他のコミットメントを直接的に規定するというものでした。
分析の結果、二つ目のモデル、すなわち職務関与を中心に据えるモデルの方がデータによく合致することがわかりました。職務関与が情緒的組織コミットメントとキャリア・コミットメントに強い正の影響を与えていることが確認されました。
この結果は、職務関与が他のコミットメントを形成する上で媒介的な役割を果たしていることを意味しています。現在の仕事に心理的に没入している度合いが、組織への感情的な愛着や自分のキャリアへのコミットメントにつながるということです。
例えば、自分の仕事に深く関わり、それに意味を見出している人は、その仕事を提供している組織に対しても感情的な愛着を持ちやすくなります。同時に、その仕事を含む専門分野やキャリア全体に対するコミットメントも高まりやすいのです。
この研究から学べる点は、現在の職務に対する深い関与が、組織へのコミットメントやキャリアへのコミットメントを高める鍵となり得るということです。自分の日々の仕事に意味を見出し、心理的に没入できる環境を整えることが、結果的に組織やキャリアへの愛着を高めることにつながるかもしれません。
これまでの検討を通じて、二重コミットメントの様々な側面を見てきました。入社後の時間経過による変化、情緒的コミットメントの重要性、職業コミットメントが内発的動機づけを通じて生産性に与える影響、そして職務関与の中心的な役割まで、多角的な視点から二重コミットメントのイメージが見えてきました。
脚注
[1] Chang, J. Y., and Choi, J. N. (2007). The dynamic relation between organizational and professional commitment of highly educated research and development (R&D) professionals. The Journal of Social Psychology, 147(3), 299-315.
[2] Meyer, J. P., Allen, N. J., and Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78(4), 538-551.
[3] Becker, T. E., Kernan, M. C., Clark, K. D., and Klein, H. J. (2018). Dual commitments to organizations and professions: Different motivational pathways to productivity. Journal of Management, 44(4), 1202-1225.
[4] Cohen, A. (1999). Relationships among five forms of commitment: An empirical assessment. Journal of Organizational Behavior, 20(3), 285-308.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。