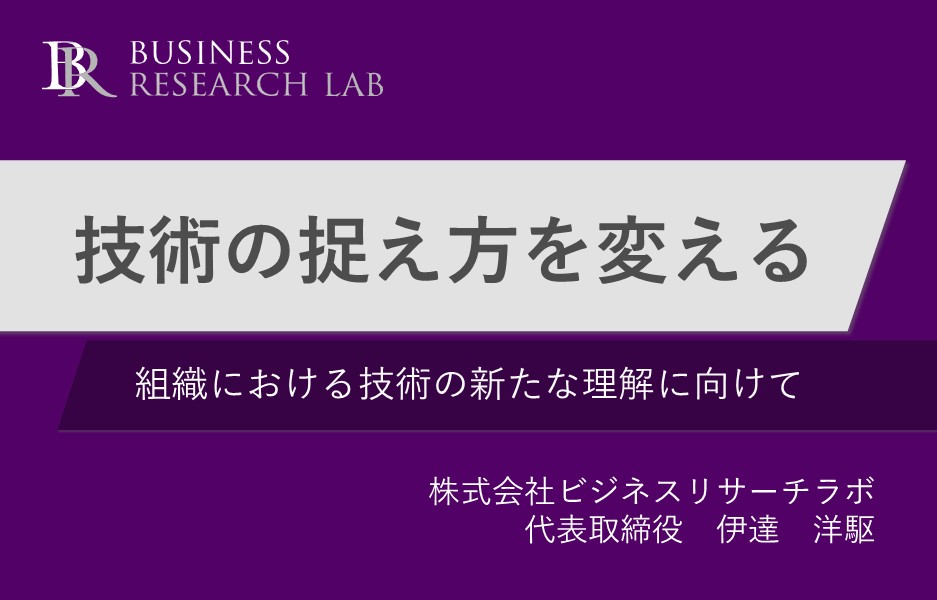2025年10月1日
技術の捉え方を変える:組織における技術の新たな理解に向けて
私たちの職場には数多くの技術があふれています。パソコンやスマートフォンから、最新のAIやロボットまで、これらの技術は日々の業務を支える存在となっています。しかし、技術をどのように理解し、活用していくかについて、どれほど本当に深く考えているでしょうか。
技術を「便利な道具」として捉える見方が一般的かもしれません。新しいシステムを導入すれば生産性が向上し、ロボットを配置すればコストが削減できる。このような発想は決して間違いではありませんが、技術と人間の関係はもっと複雑で動的なものでしょう。
本コラムでは、技術を取り巻く研究成果を通じて、従来とは異なる技術の捉え方を探求します。技術が単純な道具を超えて、私たちの働き方や組織のあり方を形作っていく存在であることを、事例とともに見ていきましょう。
情報システム研究はIT自体を理論化すべき
情報技術が組織の中核を担う現代において、研究者たちが直面している問題があります。それは、情報技術そのものについての理解がそこまで深まっていないということです。
情報システム分野の権威ある学術誌に掲載された論文を詳細に検討した研究では、情報技術を専門とする研究でありながら、技術それ自体がどのようなものかについて、十分に掘り下げて考察されていない論文が多数を占めていることが明らかになりました[1]。
この研究では、研究者たちが情報技術をどのように捉えているかを、五つのパターンに分類しています。最も多く見られたのは「道具観」と呼ばれる捉え方です。これは技術を労働の代替手段や生産性向上のための単純な道具として見る視点で、設計者が意図した通りに機能する固定的な存在として技術を理解します。
二番目に多かったのは「代理観」という捉え方でした。これは技術を何らかの数値や指標で表現し、ユーザーの満足度や導入コストといった測定可能な要素のみに着目する視点です。技術の特性や複雑さは抽象化され、数字として置き換えられています。
一方で、技術をより豊かに理解する視点も存在していました。「集合観」と呼ばれるこの捉え方では、技術を社会的・技術的な要素が複雑に絡み合ったシステムとして理解します。技術は使用される環境や歴史的な文脈に深く埋め込まれており、人々の使用と開発の相互作用によって絶えず形作られていく存在として捉えられます。
残りの二つのパターンは「計算観」と「名目的観」でした。計算観は技術の計算処理能力に特化した視点で、アルゴリズムやモデル構築といった計算機科学的なアプローチを取ります。名目的観は最も問題視される捉え方で、技術が論文中で名前だけ登場し、理論的にも実践的にもほとんど検討されていない状態を指します。
この研究が浮き彫りにしたのは、情報技術研究の多くが技術そのものを「ブラックボックス」として扱ってしまっている現実です。技術の多様性や社会との相互作用について考察せず、表面的な理解にとどまっているケースが目立ったのです。
研究者たちは、技術をより深く理解するために五つの前提を提示しました。
- 技術は自然でも中立でもなく、特定の価値観や利益が組み込まれているということです。
- 技術は常に歴史的・文化的文脈の中に位置しているということ。
- 技術は多数の部分から構成されており、その結合はしばしば不完全であるということ。
- 技術は固定的ではなく社会・経済的な実践から生み出されるということ。
- 技術は静的でなく動的であり、常に変化し続けているということです。
これらの理解に基づけば、技術は道具を超えた存在として捉える必要があります。職場において情報技術を活用する際にも、その技術がどのような価値観を内包し、どのような文脈で使用され、どのように変化していくのかを考慮することが求められます。
技術の構造は人間の実践を通じて形成される
技術と人間の関係について、従来とは異なる理解の仕方が提案されています。新しい視点では、技術の意味や機能は、あらかじめ決まっているものではなく、人々が実際に技術を使う過程で初めて生み出されると考えられています[2]。
この理解を深めるために、「技術アーティファクト」と「実践としての技術」という二つの概念を区別することが重要です。技術アーティファクトとは、物理的・概念的に安定した属性を持つ技術装置のことで、ソフトウェア、ハードウェア、データベースなどが含まれます。開発者が特定の機能を想定して作り上げたものですが、利用者がそれをどのように実際に活用するかは、まだ決まっていない状態です。
一方、実践としての技術とは、利用者が特定の場面で技術と実際にどのような相互作用を行うかを指します。人々の実践の中で、技術が持つ可能性や制約が行動やルールとして現れます。実践が繰り返されることで、ルーティン化され、組織に定着していきます。
この視点の有効性は、実際の企業における技術利用を調査した事例からも明らかになります。同じ協働支援技術(Lotus Notes)が導入された複数の組織で、全く異なる利用パターンが生まれました。
技術開発企業では、開発者グループが協働的な設計・開発のために積極的に技術を活用し、協働性を促進する構造を作り上げていました。彼ら彼女らは技術を通じて情報共有と創造的な問題解決を実現していました。
しかし、コンサルティング会社では三つの異なる利用パターンが同時に存在していました。一部のコンサルタントは技術に対して懐疑的で、限定的にしか利用していませんでした。これは競争的な企業文化や、非課金時間への抵抗感が背景にありました。別のコンサルタントたちは個人の生産性向上のために技術を活用していました。一方、技術サポート部門では協力的で問題解決志向の技術利用が行われていました。
別の企業では、顧客サポート部門がトラブル記録や解決方法の共有に技術を活用する一方で、同じ組織内でも技術を使って予期しない問題に迅速かつ創造的に対処し、新たな業務プロセスを開発する即興的な利用が生まれていました。
これらの事例が教えてくれるのは、技術の意味や利用方法が、ユーザーの実践を通じて動的に再構成されているということです。同じ技術であっても、組織の文化、個人の価値観、業務の性質によって異なる姿を現します。
この理解は、職場での技術導入や活用戦略を見直す必要性を示唆しています。技術を「導入すれば効果が出る」ものとして捉えるのではなく、「実践を通じて意味が生まれる」ものとして理解することで、より効果的な技術活用が可能になるでしょう。
技術の物質性は組織変化の社会的過程と絡み合う
組織における技術の理解をさらに深めるために、「物質性」という概念に着目すると良いでしょう。技術の物質性とは、技術が持つ具体的で物理的な特性のことですが、これが組織の変化にどのような影響を与えるかについて、誤解が存在しています[3]。
従来の技術研究では、物質性を強調することが技術決定論を意味するという混同が生じていました。技術決定論とは、技術が人間や組織の行動を一方的に決定するという考え方です。しかし、技術の具体的な特性を認識することは、必ずしも技術が全てを決定するということを意味するわけではありません。
実際には、技術の物質性と人間の主体的な行動は複雑に絡み合いながら、組織の変化を生み出しています。この複雑な関係を理解するために、四つの研究課題が提示されています。
第一の課題は、物質性の関連性を認識することです。多くの研究が技術の物質的側面を無視して社会的プロセスのみに焦点を当ててきましたが、物質的要素は制約や機会を提供し、人々が新たな活動や作業方法を可能にする基盤となっています。例えば、情報技術は情報を伝達・保存するだけでなく、従来不可能であった新しい種類の情報を生成することができるため、組織の役割や構造そのものを変化させる可能性があります。
第二の課題は、制約と機会の類型化を進めることです。技術が持つ制約や可能性の違いを分類・体系化し、それらが組織や業務の性質にどのような影響を及ぼすかを明らかにする必要があります。技術ごとに異なる特性を持っているため、その違いを理解することが重要です。
第三の課題は、技術開発と利用の連結を図ることです。従来の研究では技術の開発段階と実際の使用段階が分離されて研究されていましたが、これを統合的に研究することで、利用者の実践がいかに技術を再形成していくかを捉えることができます。技術の「社会的な形成」と「物質的な変容」の過程が交互に繰り返される様子を理解することが求められています。
第四の課題は、構成主義的研究への移行です。これまでの研究は「同一技術が異なる組織で異なる結果をもたらす理由」に焦点を当ててきましたが、今後は「異なる組織が同一技術を用いて似たような結果に至る理由」を問う研究が重要になります。この視点では、社会的相互作用を通じて共通の現実や認識が形成されるプロセスを重視し、制度化や正当化、技術の物質的制約といった要因が、特定の技術の使い方の定着にどう関わるかを解明します。
これらの課題が示すのは、技術の物質性を決定論的要素としてではなく、社会的かつ主体的な実践の一部として捉える必要があるということです。職場において技術を導入・活用する際には、技術の物質的特性を理解し、それを社会的・主体的な実践の文脈でどのように組織活動に活かせるかを考えることが求められます。
ロボットは分散した業務の調整方法を変える
近年、職場にロボット技術が導入される機会が出てきていますが、ロボットが業務にもたらす変化について、興味深い研究結果が得られています。ある病院の術後集中治療室での調査は、ロボットによる遠隔プレゼンスが、分散した複雑な業務の調整方法をどのように変えるかを明らかにしています[4]。
この調査が行われた病院では、重症患者の術後ケアが24時間体制で行われており、夜間巡回が患者の容体を安定させる上で重要でした。夜間巡回では、レジデント医師(新人医師)、指導医(経験豊富な専門医)、看護師が共同で患者状態を確認し、治療方針を調整していました。
研究者たちは14ヶ月間にわたって、従来の電話を使った夜間巡回と、遠隔操作ロボット(RP-7)を用いた巡回の効果を比較しました。合計424名の患者を観察し、準備段階(夜間巡回前の情報収集)と巡回実践という二つの連結した活動を分析しました。
電話による巡回では、二つの異なるパターンが観察されました。第一のパターンでは、レジデントがベッドサイドで患者を観察し、看護師と共に小さな調整を実施していました。巡回時には指導医とレジデントが短時間で患者状態を口頭で確認し、安定した患者の報告は受け入れられやすくなっていました。この方式では看護師も納得しやすく、その後の夜間ケアの協調が円滑に進みました。
第二のパターンでは、レジデントが患者のベッドサイドから離れて医療記録のみを軽く確認し、巡回時には曖昧な報告をすることが多くなっていました。指導医は口頭指導を通じて患者情報を引き出そうとするため巡回時間が長くなり、その後の看護師との協調も困難になるという問題が生じていました。
ロボット(RP-7)による巡回でも、同様に二つのパターンが見られましたが、その結果は電話の場合と異なっていました。第一のパターンでは、レジデントが事前にベッドサイドで綿密に準備を行い、巡回時には看護師、指導医とともにベッドサイドで共同で患者の状況を探求していました。この方法では、患者の状態に対する異なる見解が一時的に増加するものの、最終的には統一された認識に達しやすく、その後の夜間協調が円滑となっていました。
第二のパターンでは、レジデントが事前に十分な準備をせずに巡回を行い、巡回時には看護師と指導医が直接患者情報をやり取りし、レジデントが迂回されてしまうことが多くなっていました。結果、レジデントは合意形成から外れ、夜間のケアで調整が困難になるという課題が浮き彫りになりました。
この研究から明らかになったのは、事前の準備の仕方(ベッドサイドでの情報収集)が、その後の調整に重要であるということです。そして、ロボットを使った遠隔プレゼンスは、準備の内容次第で調整効果を向上させることもあれば、逆に低下させることもあるということでした。
重要なのは、ロボットという技術が効率化ツールではなく、業務の実践そのものを構成する要素として機能していたということです。ロボットの存在により、医療スタッフの行動パターンが変化し、情報共有の方法が変わって、患者ケアの質が左右されていました。
ロボットの物質性が職業間の境界を再構成する
ロボット技術の導入は、単に業務を効率化するだけでなく、職場における異なる職業グループ間の関係性を変化させることがあります。病院薬局でのロボット導入事例は、この複雑な変化の過程を明らかにしています[5]。
調査が行われた病院薬局では、薬剤師、技術者、助手という三つの職業グループが調剤業務に従事していました。調剤ロボットの導入により、これらのグループ間の境界関係がどのように変化するかが、20日間の参与観察と41回のインタビューを通じて追跡されました。
ロボットは二つの特性を併せ持っていました。デジタル物質性として、バーコード識別や在庫管理の自動化などが可能で、ソフトウェアの修正により業務プロセスを迅速に調整できる特性を備えていました。機械的物質性として、調剤業務を物理的に実行するアームや搬送システムなどを持ち、故障時には専門的なメンテナンス作業が必要でした。
薬剤師と技術者の間では、協力的な境界関係が形成されました。ロボット導入により、薬剤師は従来の調剤作業から解放され、研究活動や患者対応といったより高度な業務に集中できるようになりました。一方、技術者はロボットの管理・修理といった新たな専門スキルを獲得し、薬局内での地位が向上しました。両者は共にプロフェッショナリズムを推進する立場として、協力的な関係を築いていました。
しかし、薬剤師と助手の間では、境界の無視という問題が生じました。助手はロボット導入の意思決定から排除され、彼ら彼女らの仕事である在庫管理やロボットへの薬品充填などは困難で断片化されたものになりました。助手の業務はロボットにより後回しにされ、作業空間が乱雑で非効率になるなど、作業環境が悪化しました。薬剤師が助手の苦境に無関心であったため、この境界の無視が続いていました。
技術者と助手の間では、境界の緊張が生まれました。ロボット管理の権限を持つ技術者が助手の業務を頻繁に監視・指導するようになり、助手は自律性と独立性を失いました。助手はロボット使用に関する問題解決のために技術者への依存を強め、両者の間に緊張関係が生じていました。
このように、同じロボット技術の導入であっても、職業グループの組み合わせによって異なる境界変化が生じていました。これは「抵抗と適応」の相互作用として理解することができます。各職業グループがロボットの特性に対してどのような抵抗を示し、どのような適応を行うかが、境界関係を決定しているのです。
薬剤師にとってロボットは、より専門性の高い業務への移行を可能にする解放的な存在でした。技術者にとっては、新たな専門性を発揮できる機会を提供する存在でした。しかし助手にとっては、既存の業務を困難にし、他の職業グループへの依存を強める制約的な存在となっていました。
この事例が示すのは、技術の導入が職場の権力関係や職業的地位を再編する可能性があるということです。技術を効率化ツールとして捉えるのではなく、組織における職業的地位や権限を再構築する要素として理解する必要があります。
脚注
[1] Orlikowski, W. J., and Iacono, C. S. (2001). Desperately seeking the “IT” in IT research: A call to theorizing the IT artifact. In J. L. King and K. Lyytinen (Eds.), Information Systems: The State of the Field (pp. 19-42). Chichester, UK: Wiley.
[2] Orlikowski, W. J. (2000). Using technology and constituting structures: A practice lens for studying technology in organizations. Organization Science, 11(4), 404-428.
[3] Leonardi, P. M., and Barley, S. R. (2008). Materiality and change: Challenges to building better theory about technology and organizing. Information and Organization, 18(3), 159-176.
[4] Beane, M., and Orlikowski, W. J. (2015). What difference does a robot make? The material enactment of distributed coordination. Organization Science, 26(6), 1553-1573.
[5] Barrett, M., Oborn, E., Orlikowski, W. J., and Yates, J. (2011). Reconfiguring boundary relations: Robotic innovations in pharmacy work. Organization Science, 23(5), 1448-1466.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。