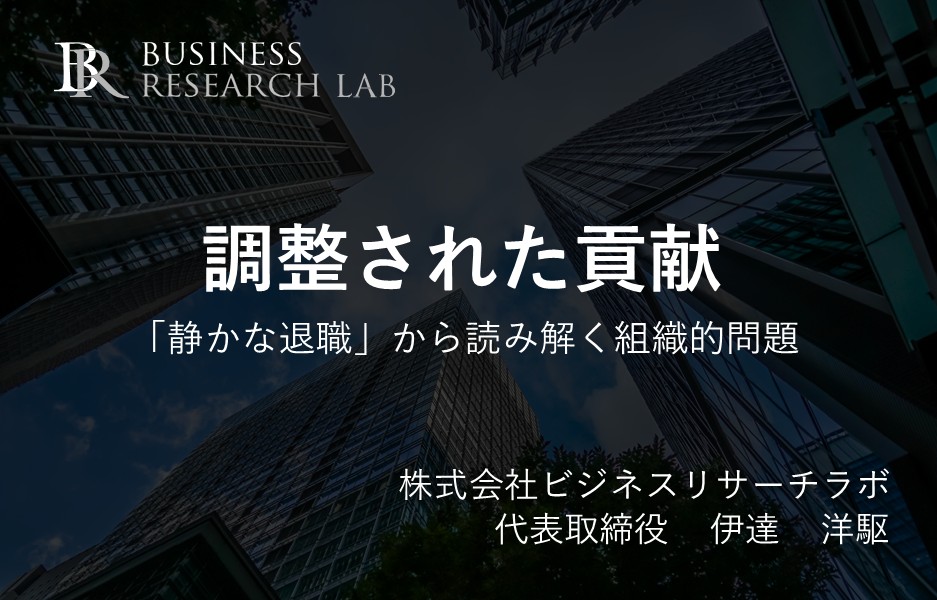2025年9月30日
調整された貢献:「静かな退職」から読み解く組織的問題
皆さんは「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。この概念は、2022年頃からSNSを中心に話題となった新しい働き方を表す言葉です。「静かな退職」とは、実際に会社を辞めるわけではなく、職務記述書に明記された範囲内で最低限の業務のみを行い、それ以上の追加的な労力を投入しないという態度や行動を指します。
長時間労働や自己犠牲を厭わない働き方をしてきた人もいるかもしれません。しかし、新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックを契機に、多くの人々が自分の働き方や人生の優先順位を見直す機会を得ました。「人生において仕事とは何か」「自分の時間や健康はどれほど価値があるのか」という問いに向き合った結果、「静かな退職」という選択肢を選ぶ人が世界中で増えたとされています。
本コラムでは、「静かな退職」を怠慢や責任放棄としてではなく、現代社会における合理的な心理的反応として捉え直します。複数の研究を紹介しながら、この現象が生じる背景や要因、そして人々がこの選択をする際の心理について掘り下げていきます。
「静かな退職」は、表面的には消極的な行動のように見えるかもしれません。しかし、それは実のところ、不公平感や過重労働、組織への不信感など、様々な要因に対する人間の自然な心理的反応とも言えるのです。労働環境や価値観が変化する現代において、この現象を深く理解することは、私たち一人ひとりのワークライフバランスを考える上でも、組織のマネジメントを考える上でも意義深いことです。
静かな退職は組織的信頼の低下から生じる
新型コロナウイルスのパンデミック後、職場環境は変化しました。テレワークの普及や働き方の多様化が進み、人々の仕事に対する価値観も変わりつつあります。そうした中で見られるようになった「静かな退職」という現象について詳しく見ていきましょう。
「静かな退職」とは、従業員が会社を辞めることなく、職場で必要最低限の仕事だけを行い、追加的な貢献を控える態度や行動を指します。形式的には在職していながら、心理的には仕事に対する積極性を失っている状態とも言えます。
なぜ人々は「静かな退職」を選ぶのでしょうか。研究ではいくつかの要因が述べられています[1]。一つ目は「組織的信頼の低下」です。従業員が組織や経営陣に対して信頼感を失うと、仕事への意欲も自然と低下します。例えば、パンデミック時に企業が従業員の健康よりも利益を優先したと感じた場合、組織への信頼は揺らぎます。
二つ目の要因は「自律性の欠如」です。自分で仕事のやり方や進め方を決められない環境では、従業員の内発的な動機づけが損なわれます。いつも上司の指示を仰ぎ、自分のアイデアを実現する余地がない状況は、仕事への熱意を失わせます。
三つ目は「従業員の孤立感」です。例えばテレワークが普及する中で、職場での人間関係が希薄化し、孤独感を抱く従業員が増えています。チームとしての一体感や同僚との交流が減少すると、仕事に対する意識も低下します。
四つ目は「キャリア開発への支援不足」です。自分の成長やスキルアップが実感できない環境では、従業員は将来に対する希望を失います。キャリアパスが不明確で、学習機会が乏しい職場では、現状維持の姿勢が強まり、仕事への積極性が失われていきます。
五つ目の要因として「従業員の価値の軽視」が挙げられます。自分の貢献や存在が組織から正当に評価されていないと感じると、従業員は「なぜ余分な努力をする必要があるのか」と考えるようになります。長時間労働や追加業務に対して適切な評価や報酬がない場合、このような感覚は強まります。
そして最後に「ワークライフバランスの崩壊とバーンアウト」があります。過重な業務負担やデジタル技術による「常に仕事モード」の状態は、従業員の心身を疲弊させます。バーンアウトに陥った従業員は、自己防衛的に仕事への関与を最小限に抑える傾向があります。
これらの要因が複合的に作用することで、「静かな退職」という現象が生じると考えられます。例えば、ある従業員がキャリア開発の機会がなく、自律性も制限され、さらにバーンアウト状態にあれば、その従業員が仕事への最小限の努力しか払わなくなるのは自然な反応でしょう。
静かな退職は仕事の目的や価値観の喪失で生じる
「静かな退職」を「大辞職(Great Resignation)」と並ぶ現代の労働市場における二大パラダイムシフトとして位置づける研究もあります[2]。「大辞職」と「静かな退職」はどのように関連し、どのような心理的背景があるのでしょうか。
「大辞職」とは、2021年春頃から顕著になった現象で、多くの労働者が自発的に仕事を辞めるという動きを指します。研究によれば、2021年末までにアメリカだけで4,700万人以上が自発的に離職したとされています。ホスピタリティ業界での離職率は高く、2021年11月には6.9%、2022年7月時点でも約6%と高い水準を維持していました。
一方、「静かな退職」は形式的には在職しながらも、職務記述書に明記された範囲内の業務のみを行い、それ以上の努力を控えるという態度を指します。ギャラップ社の調査(2022年)では、アメリカの労働人口の約半数がこの「静かな退職」状態にあり、特にZ世代や若いミレニアル世代に多いことが分かっています。
研究者らは、これらの現象がCOVID-19によって突如として生まれたわけではなく、従来から存在していた問題(低賃金、長時間労働、職場の文化的問題など)がパンデミックを契機に表面化し、加速したものだと分析しています。
「大辞職」や「静かな退職」という現象の背後には人間が持つ3つの要素の不足があると指摘しています。
一つ目の要素は「ニーズ(Needs)」です。これは職場で評価されている感覚や尊重されている感覚など、基本的な心理的欲求を指します。例えば、上司からフィードバックを受けられない、あるいは同僚から尊重されていないと感じる場合、従業員のニーズは満たされません。パンデミック期間中、多くの従業員が自分の健康が企業によって軽視されていると感じ、このニーズの不足が顕在化しました。
二つ目は「価値観(Values)」です。これは個人の信念や大切にしていることと、職場環境や文化との整合性を意味します。例えば、ワークライフバランスを重視する人が、常に残業を求められる環境にいると、価値観の不一致が生じます。パンデミックを経て、多くの人が自分の価値観を再評価し、それが職場の価値観と合致しないことに気づいたのです。
三つ目は「目的意識(Purpose)」です。仕事に意味や目的を感じられるかどうかが、従業員の満足度や帰属意識に影響します。自分の仕事が社会にどのように貢献しているのか、あるいは自己成長にどうつながるのかが見えない場合、従業員は目的意識を失います。パンデミックは多くの人に「人生で本当に大切なものは何か」を考えさせ、仕事における目的意識の欠如を際立たせました。
この研究では、「静かな退職」があらゆる意味で否定的な現象ではなく、従業員が自らの幸福や健康を守るための合理的な選択でもあることを示唆しています。例えば、職場でのストレスが高まり、バーンアウトのリスクが増す中、「静かな退職」を選択した従業員は、精神的健康を維持し、仕事と私生活のバランスを取り戻すことができるかもしれません。
静かな退職は報われない努力への反応である
「静かな退職」を人的資本管理(Human Capital Management)の視点から検討した研究を紹介しましょう[3]。この研究の特徴は、SNS(特にTikTok)上のコメント分析や関連文献のレビューを通じて「静かな退職」の実態を明らかにし、その上で従業員、管理職、さらには政策レベルでの含意を導き出している点にあります。
研究によれば、「静かな退職」という用語が広く知られるようになったのは、TikTokユーザーが2022年に投稿した動画がきっかけでした。この概念は「明示的に退職はせず、職務記述に定められた範囲内で最低限の業務のみを行い、それ以上の追加的な労働を控える」という態度や行動を指します。
研究者はTikTok上の2,000件のコメントから有効な672件を抽出し分析しました。その結果、「静かな退職」者の典型的な行動パターンとして、次のような特徴が浮かび上がってきました。
- 職務範囲以上の仕事は断る
- 定時を守り、残業を避ける
- 自発的なタスクに手を挙げない
- 仕事よりも自分の健康や生活を優先する
多くの投稿者が「静かな退職」を実践していることを認めており、これはCOVID-19以降に顕著になったことが指摘されています。一方で、一部の従業員はこうした態度に道徳的な疑問を呈し、昇進の機会を逃すリスクを懸念する声もありました。
この研究では、「静かな退職」の主な要因を3つ挙げています。
一つ目は「外的動機付けの不足」です。これは追加業務や残業に対する報酬やインセンティブが不十分である状況を指します。例えば、ある従業員のコメントには「私は週に60時間働いていたが、会社からの感謝や報酬は何もなかった。だから今は40時間だけ働き、それ以上は一切しない」というものがありました。こうした報酬と労力の不均衡感が、「静かな退職」を促しています。
二つ目は「心理的負担(バーンアウト)」です。長時間労働やストレスの多い職場環境は、従業員の心身に負担をかけます。多くの「静かな退職」者が以前はバーンアウト状態にあり、自らの健康を守るために労働投入量を調整しています。ストレス状態からの自己防衛として、「静かな退職」が選択されるのです。
三つ目は「管理職や組織への不満や不信感」です。不公平な評価制度や透明性のない昇進プロセス、さらには上司との関係悪化などが、従業員の組織への不信感を高めます。「自分がどれだけ努力しても評価されない」「会社は簡単に従業員を使い捨てにする」といった認識を持つ従業員は、意図的に職務範囲以上の努力を控えるようになります。
研究ではさらに、「静かな退職」と類似する他の概念との比較も行われています。例えば「Anti-work(反労働思想)」「Cyberloafing(勤務中のネットサーフィン)」「Clock-watching(時間管理に過敏な行動)」「Work-to-rule(規則厳守の抗議行動)」などとの違いが検討されています。最大の違いは、「静かな退職」が組織への意図的な妨害ではなく、自らの健康や公平性を守る個人的選択であることだと結論づけています。
静かな退職は合理的な貢献度の調整である
ある研究は、「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉自体に問題があると指摘し、より実態に即した「調整された貢献(Calibrated Contributing)」という概念を提案しています[4]。この研究は、現在の労働環境における構造的な不均衡を批判的に分析しながら、労働者の行動をより肯定的に捉え直そうとする試みです。
論文の冒頭では、事例が紹介されています。例えば、パンデミック中も対面で顧客対応を続けた薬剤師は、自らの健康を危険にさらしながらも、その報酬は会社CEOの給与の1%以下でした。またITサポートは、彼の提案が繰り返し無視され続けたことで、業務に対する積極性を失っていきました。研究者によれば、彼ら彼女らのような労働者は「静かな退職者」としてラベル付けされていますが、実際には労力に見合った待遇を得ていないと感じ、自発的に労働投入量を調整(Calibrate)しているだけです。
「静かな退職」という言葉は、労働者に対して怠惰で自己中心的であるという否定的なニュアンスを与えます。しかし研究者は、労働者が努力量を合理的に調整することは自然な行動であり、特に批判されるべきではないと主張しています。例えば衡平理論によれば、人は自分の投入する努力とそれに対する報酬を他者と比較し、不公平感を感じれば、報酬を増やすよう求めるか、あるいは労力を減らしてバランスをとろうとするものです。
この研究では、労働者の行動を「職務内(In-role)」と「職務外(Extra-role)」に分類しています。職務内とは、雇用契約や職務記述書に明確に記載された仕事内容を指します。一方、職務外とは、正式な職務範囲を超えて自発的に行う貢献を意味します。従来の職場文化では、このextra-roleの行動を積極的に行う労働者が高く評価される傾向がありました。しかし、本来extra-roleとは義務ではなく自発的なものであるはずなのに、それをしないことが道徳的な欠陥や非難の理由となるべきではないと指摘します。
企業側が職務外の仕事を当たり前に要求する「職務の肥大化(Job creep)」が進んでいることが、「静かな退職」という誤った表現が広がる原因になっていると考察しています。労働者が契約上の義務を果たしているにもかかわらず、それを超える貢献をしないというだけで否定的なラベルを貼られるのは不当だというわけです。
デタートは「静かな退職」という表現をやめ、「調整された貢献(calibrated contributing)」というより適切な言葉を使うことを提案しています。これは労働者が公平性の感覚に基づき、合理的に自らの労働投入量を調整しているというニュアンスを持つ用語です。こうした再定義により、労働者を不当に批判することなく、より正確に問題の原因(不公平感、待遇の悪さなど)を認識し、対策を講じることが可能になると述べられています。
例えば、ある企業で多くの従業員が「調整された貢献」の状態にあるとすれば、それは従業員の怠慢ではなく、組織の報酬体系や評価制度、労働環境に問題があるというシグナルと捉えたほうが良いということです。
この研究は、言葉の使い方が社会や労働者に与える影響がいかに大きいかを示しています。「静かな退職」という表現は、労働者を暗に非難し、真の問題(労働条件の悪化、報酬の不均衡など)から目を背けさせます。一方、「調整された貢献」という表現は、労働者の行動を合理的で理解可能なものとして認識し、より建設的な対話の道を開くものです。
脚注
[1] Pevec, N. (2023). The concept of identifying factors of quiet quitting in organizations: An integrative literature review. Izzivi prihodnosti (Challenges of the Future), 8(2), 128-147.
[2] Formica, S., and Sfodera, F. (2022). The great resignation and quiet quitting paradigm shifts: An overview of current situation and future research directions. Journal of Hospitality Marketing & Management, 31(8), 899-907.
[3] Serenko, A. (2024). The human capital management perspective on quiet quitting: Recommendations for employees, managers, and national policymakers. Journal of Knowledge Management, 28(1), 27-43.
[4] Detert, J. (2023). Let’s call quiet quitting what it often is: Calibrated contributing. MIT Sloan Management Review. https://sloanreview.mit.edu/article/lets-call-quiet-quitting-what-it-often-is-calibrated-contributing/
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。