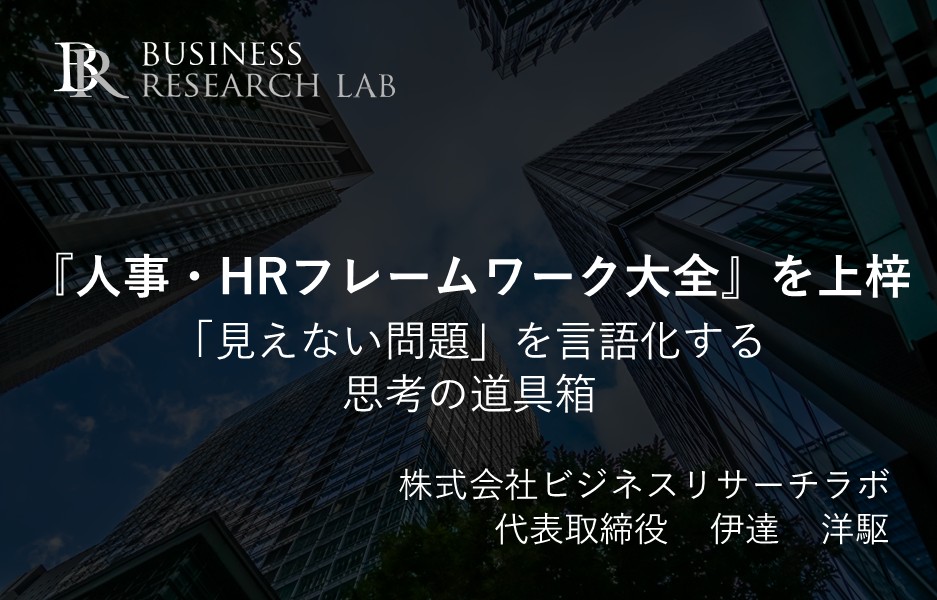2025年9月30日
『人事・HRフレームワーク大全』を上梓:「見えない問題」を言語化する思考の道具箱
人と組織をめぐる問題は、複雑に絡み合った糸のようです。一つの問題を解きほぐしたかと思えば、また別の結び目が現れる。若手社員が定着しない、チームの雰囲気がどこかギクシャクしている、部門間の連携がうまくいかずプロジェクトが停滞する。こうした無数の課題は、役職や立場に関わらず、組織で働くすべての人にとって、終わりなき問いとして立ちはだかります。
なぜ、これほどまでに人と組織の問題は厄介なのでしょうか。その難しさの本質は、問題の「見えにくさ」にあると私は考えています。例えば、「若手の定着率が低い」という一つの事象。その背後には、給与や待遇といった目に見える条件だけでなく、上司との人間関係、仕事の与え方への不満、評価制度への不信感、あるいは採用段階でのミスマッチなど、様々な要因が隠されています。これらの要因は、それぞれが独立しているわけではなく、互いに影響し合い、さらに問題を複雑にしています。多くの方が、このような状況に頭を抱えた経験をお持ちではないでしょうか。
私たちは、この見えない問題に、どう立ち向かえば良いのでしょう。ビジネスの現場では、問題解決のために「フレームワーク」が活用されます。しかし、不思議なことに、人と組織という重要な領域において、フレームワークはこれまで十分に活用されてきたとは言えません。人の心は一般化できない。組織の問題は個別性が高く、ケースバイケースだ。そうした考え方が根強くあったからかもしれません。
しかし、それは誤解です。この度、『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』を上梓しました。本書で紹介するフレームワークは、どんな料理も作れる「万能のレシピ」ではありません。むしろ、優れた料理人が最高の料理を生み出すために包丁やまな板を使いこなすように、複雑な問題を整理し、構造を可視化するための切れ味を持つ「思考の道具」です。本書が、皆さんの「道具箱」に新たな光をもたらし、明日からの景色を変える一助となることを願っています。
具体例で見る「思考の道具」
多くの管理職やリーダーが抱える悩みの一つに、「最近、若手の意欲が低い気がする」という漠然としたものがあります。朝礼で元気がなかったり、会議で発言が少なかったり、以前のような活気が感じられない。このような状況に直面したとき、私たちはどのような手を打つでしょうか。
フレームワークという「思考の道具」を持たない場合、そのアプローチは往々にして場当たり的になりやすいものです。「もっと主体性を持ちましょう」「プロ意識が足りません」と精神論を語ってみたり、一体感を醸成するつもりで飲み会を開いてみたり。もちろん、こうした働きかけが功を奏することもあるでしょう。しかし、多くの場合、問題の本質に触れることができず、空回りしてしまうのではないでしょうか。なぜなら、「意欲の低下」という、霧のように掴みどころのない現象の正体を見極められていないからです。
『人事・HRフレームワーク大全』で紹介する「思考の道具」を使うと、この状況はどう変わるでしょう。私たちは、この漠然とした問題に対して、複数の角度から光を当て、その輪郭を浮き彫りにすることができます。
一つ目の道具として、「目標設定理論」というレンズを覗いてみましょう。この理論は、人が目標によっていかに動機づけられるかを解き明かすものです。
このレンズを通してチームを見渡すと、問いが具体的になります。「チームの目標は、若手メンバーにとって明確で、挑戦しがいのあるものになっているだろうか?」「ただ『頑張れ』と言うだけでなく、具体的な行動と成果の基準は示されているか?」「彼ら彼女らの努力や進捗に対して、適切なフィードバックは機能しているだろうか?」もし、目標が曖昧であったり、達成しても何の反応も得られなかったりすれば、意欲が湧かないのは当然かもしれません。
二つ目の道具、「自己決定理論」のレンズをかけてみましょう。この理論は、人の内側から湧き出るモチベーションの源泉として、「自律性」「有能感」「関係性」という三つの基本的な欲求を提示します。
この視点からチームを観察すると、また新たな問いが生まれます。「若手メンバーは、仕事の進め方についてある程度の裁量を与えられ、自分の意志で動けているだろうか(自律性)?」「日々の業務を通じて、自分は成長している、能力を発揮できていると感じられているだろうか(有能感)?」「上司や同僚と良好な関係を築き、チームの一員として受け入れられていると感じられているだろうか(関係性)?」もし、マイクロマネジメントでがんじがらめにされていたり、自分の仕事が評価されず無力感に苛まれていたりすれば、意欲は枯渇してしまうでしょう。
三つ目の道具として、「職務特性理論」というレンズも有効です。この理論は、仕事そのものが持つ特性が、人のやる気にどう影響するかを分析します。
このレンズを手にすると、問いは仕事内容そのものへと向かいます。「彼ら彼女らが担当している業務は、単調な作業の繰り返しになっていないか?多様なスキルを活かす機会はあるか?」「自分の仕事が、一つの製品やサービスの完成にどう貢献しているのか、全体像を把握できているか?」「その仕事が、社内の誰かや社会にとって、どれほど重要なのかを実感できているか?」自分の仕事の意義や社会への影響を感じられないままでは、魂を込めて取り組むことは難しいはずです。
このように、複数のフレームワークという道具を使い分けることで、「若手の意欲低下」というぼんやりとした問題が、次第にその姿を現します。それはもはや掴みどころのない現象ではなく、「目標設定の曖昧さ」「フィードバックの不足」「自律性の欠如」「職務の単調さ」といった、輪郭のはっきりした具体的な課題群なのです。これが、「見えない問題を言語化する」という、本書が提供する価値です。問題の正体が見えれば、私たちはようやく次の一手を考えることができるようになります。
フレームワークは“掛け算”で真価を発揮する
一つの問題に対して、複数の視点から光を当てる。それだけでも、問題解決の精度は格段に上がります。しかし、本書が目指したのは、単なるフレームワークの羅列ではありません。現実の組織課題は、より複雑で、一つのアプローチだけでは太刀打ちできないことが少なくないからです。そこで重要になるのが、フレームワーク同士を組み合わせる、「掛け算」の思考です。本書の応用編では、その実践例をいくつか紹介しています。
ここでは、その中から「繁忙期における負荷を、個人と組織の両面でケアする」というケースを取り上げてみましょう。年末商戦のコールセンターを舞台に、クレーム対応に追われるオペレーターたちが次々と心身の不調を訴え、離職していく。深刻な問題です。
この問題に対して、まず組織という「環境」にアプローチするための道具として、「JD-Rモデル」が有効です。このモデルは、職場のストレスを「仕事の要求度」と「仕事の資源」の組み合わせとして捉えます。このコールセンターの場合、繁忙期にはクレーム件数や対応の難易度といった「要求度」が跳ね上がります。一方で、それを乗り越えるための「資源」、すなわち、分かりやすい対応マニュアル、上司や同僚からのサポート、あるいは一時的な人員増強といったものが不足していれば、バランスは崩れ、従業員は心身を消耗してしまいます。
まずはこのバランスシートを改善すること、すなわち、組織として対応マニュアルを整備したり、上申のルールを明確にしたり、支援体制を強化したりすることで、ストレスの発生源を減らしていくアプローチが考えられます。
しかし、組織的な対策を講じても、一度疲弊してしまった個人の心がすぐに回復するとは限りません。理不尽なクレームを受けた後、「もっとうまく対応できたはずなのに」と自分を責め続けてしまう。そんな個人の内面的な苦しみに寄り添うために、もう一つの道具、「セルフ・コンパッション」が力を発揮します。これは、困難な状況に直面した際に、過度に自己批判するのではなく、自分自身に対して優しさや思いやりを向ける、という考え方です。
研修などを通じて、「失敗は誰にでも起こりうること(共通の人間性)」と捉え直したり、「よくやっているよ」と自分を労ったり(自分への優しさ)する術を身につけることで、個人の心の回復力を高めることができます。
このように、組織という「環境」への働きかけ(JD-Rモデル)と、個人という「内面」への働きかけ(セルフ・コンパッション)を掛け合わせることで、私たちは問題の解決へと近づくことができます。どちらか一方だけでは、対症療法に終わってしまうかもしれません。組織の仕組みを整えるだけでなく、そこで働く一人ひとりの心の強さを育む。本書が提示するのは、そうした多角的で、人間的な問題解決のアプローチです。
この本の「使い方」
本書には、83ものフレームワークを収録しました。これだけ多くの道具が詰まった「道具箱」を前にして、どこから手をつければ良いかと戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。そこで、皆さんがこの本を最大限に活用するための「使い方」を少しだけ紹介させてください。
本書では、各フレームワークをただ解説するだけでなく、現場で「使える」ことを意識しました。それぞれの項目は、「どのような場面で有効か」という課題設定から始まります。次に、「どんなフレームワークか」で理論の要点を、図解を交えて平易に解説し、「どう使えば良いか」で実践的なステップを提示します。さらに、「理解のための例題」でビジネスシーンを想定した活用イメージを掴んでいただき、「何に注意すべきか」でフレームワークを万能薬と誤解しないための注意点にも触れています。この構成によって、理論を学び、実践し、振り返るというサイクルを自然に回せるように設計しました。
この道具箱の使い方は、大きく分けて二つあると考えています。
一つは、初めから順に読み進めていただく「通読」スタイルです。リーダーシップから始まり、モチベーション、組織文化、キャリア開発と、人と組織に関するテーマを体系的に学ぶことができます。これまで断片的に得てきた知識が、章を読み進めるごとにつながり、整理されていく感覚を味わっていただけるはずです。時間をかけてじっくりと、人と組織に関する知の全体像を掴みたい方におすすめです。
もう一つは、日々の業務で課題に直面した際に、必要な部分を参照する「逆引き」スタイルです。いわば、組織課題に対応するための「辞書」や「百科事典」として、この本を使っていただくのです。「最近、チーム内の対立が多いな」と感じたら、コンフリクトマネジメントのページを開いてみる。「新技術の導入に現場が抵抗している」と悩んだら、技術受容モデルの項目を読んでみる。目次や索引から、今まさにあなたが直面している問題に対応するフレームワークを探し出し、解決のヒントを得る。多忙なビジネスパーソンにとっては、こちらの使い方もあり得ます。
そして、この本は人事や人材開発に携わる方々のためだけのものではありません。部下の育成に悩むすべての管理職、チームを率いるプロジェクトリーダー、将来リーダーを目指すすべての方々にとって、強力な武器となるはずです。人と組織の問題は、もはや専門家だけの課題ではないからです。この本が、皆さんの思考のOSをアップデートし、課題解決の精度を高める一助となれば、著者としてこれ以上の喜びはありません。
明日からの景色を変えるために
ここまで、本書に込めた想いと、その活用法についてお話ししてきました。人と組織の問題に、唯一絶対の「正解」はありません。だからこそ、私たちは途方に暮れ、時に感情的な対立に陥ってしまう。しかし、本書で紹介したような、拠り所となる「思考の道具」を手にすることで、状況は変わり得ます。問題の本質を見抜くための「解像度」が上がるからです。
フレームワークという共通言語は、組織内の対話をより生産的なものに変えてくれます。「やる気がない」というレッテル貼りの代わりに、「彼の自己決定感を高めるにはどうすれば良いか」という建設的な問いが生まれる。感情的なぶつかり合いの代わりに、それぞれの立場を尊重した上での解決策の模索が始まる。そうしてチームは、同じ未来を描くことができるようになります。
本を閉じた瞬間から、皆さんの新たな挑戦が始まります。まずは一つで構いません。今、最も気になっている課題に対して、使えそうな道具を一つ、試してみてください。きっと、昨日までとは景色が少しだけ違って見えるはずです。問題の背後にある構造が見え、解決への新たな一歩を踏み出す勇気が湧いてくるかもしれません。この一冊が、皆さんの「道具箱」に加わり、皆さんがそれぞれの現場で、より良い組織、より良い働き方を実現するために用いられることを願っています。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。