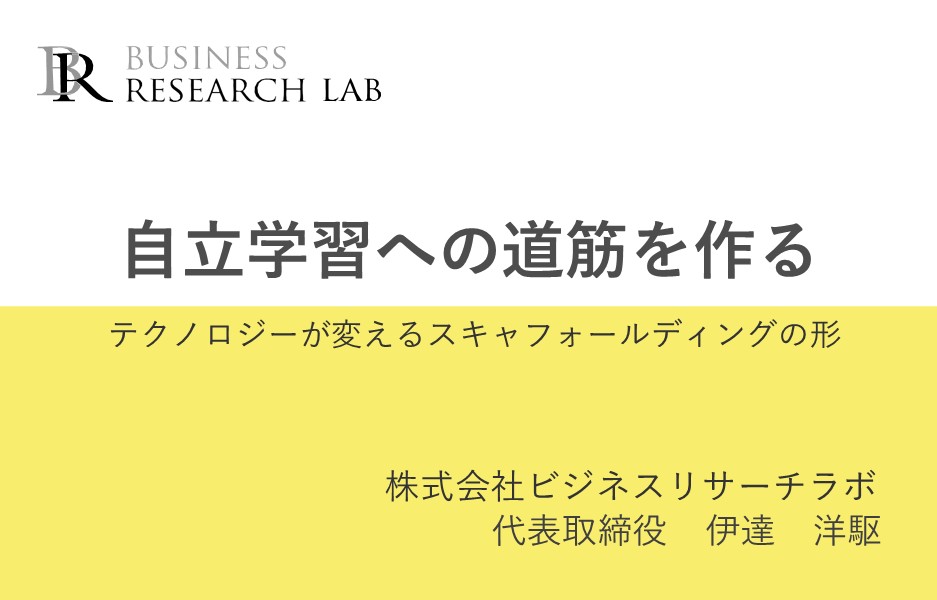2025年9月29日
自立学習への道筋を作る:テクノロジーが変えるスキャフォールディングの形
デジタル技術が教育や職場環境に浸透する現代において、私たちの学び方や問題解決の方法は変化しています。オンライン空間でのコラボレーションや学習が以前より日常的になりました。このような環境変化の中で注目されているのが「スキャフォールディング」という概念です。
スキャフォールディングとは、直訳すると「足場かけ」を意味します。建設現場で高所作業を可能にする足場のように、学習者が自力では到達できない課題に取り組めるよう支援する手法です。教師やシステムが初めは多くの支援を提供し、学習者のスキルが向上するにつれて徐々にその支援を減らしていくことで、最終的には自立した問題解決者へと成長することを目指します。
テクノロジーの発展は、このスキャフォールディングの実践にも変化をもたらしました。人間の教師だけでなく、コンピューターが学習者をサポートする「テクノロジー媒介型スキャフォールディング」が登場し、個別最適化された学習体験を提供できるようになったのです。
テクノロジーを活用したスキャフォールディングは、実際にどのような効果をもたらすのでしょうか。問題解決能力の向上、メタ認知スキルの発達、チームコラボレーションの効率化など、様々な側面から検証した研究が蓄積されています。本コラムでは、テクノロジーとスキャフォールディングの関係性に着目し、研究知見から見えてくる可能性と課題について考察します。
スキャフォールディングは技術を使った問題解決を促進
現代社会では、ビジネス環境であれ教育現場であれ、複雑な問題を解決する能力が求められています。しかし、テクノロジーを活用した学習環境において、学習者は様々な困難に直面することがあります。特に自己調整学習の場面では、適切な支援がなければ期待通りの学習成果が得られないことも少なくありません。
ドイツの大学で行われた研究では、テクノロジーを活用した学習環境でのスキャフォールディングが問題解決能力の向上にどのように寄与するかを検証しました[1]。この研究は、経営学部の学生72名を対象に、「反転授業」の形式で実施されました。反転授業とは、従来の講義を自宅で動画などで学び、教室では演習や議論に時間を使う形式です。
実験では、学生を2つのグループに分け、一方にはテクノロジーによるスキャフォールディングを提供し、もう一方には提供しませんでした。具体的には、Moodleという学習管理システムを使用し、企業のビジネスプロセスを分析・改善するという課題に取り組みました。
実験の結果、スキャフォールディングを受けたグループは、問題解決能力が統計的に有意に向上しました。学習プロセスに対する満足度も高まりました。適切に設計されたスキャフォールディングが、学習者の認知的負荷を管理するのに役立ったと考えられます。
認知的負荷とは、人間の脳が情報を処理する際にかかる負担のことです。学習理論では、認知的負荷は主に3種類に分類されます。「内在的負荷」は学習内容そのものの複雑さからくるもの、「付随的負荷」は学習方法や教材の設計による不必要な負担、そして「本質的負荷」は深い理解や知識の構築に関わる生産的な負荷です。
この研究では、スキャフォールディングが特に「付随的負荷」を減らし、「本質的負荷」を高めることが分かりました。言い換えれば、スキャフォールディングは学習者が無駄なことに頭を悩ませる時間を減らし、本当に考えるべき問題に集中できるようにするわけです。
オンラインではスキャフォールディングがメタ認知を向上
オンライン学習が高等教育の形態の一つとして定着しつつある今日、その教育的な質をいかに保証するかは課題です。対面授業と異なり、オンライン環境では学習者が孤立感を覚えたり、自己管理に困難を感じたりすることがあります。こうした課題に対して、スキャフォールディングという手法が有効であることが、近年の研究で明らかになってきました。
2010年から2019年までの10年間に発表された研究を対象に行われたメタ分析によると、オンライン学習環境におけるスキャフォールディングは、学習成果に大きな効果をもたらすことが分かりました[2]。このメタ分析では、8か国の18の学術論文に記載された64の効果量が分析され、スキャフォールディングの効果が統計的に検証されました。
スキャフォールディングの基本的な特徴として、次の3つが挙げられます。
- 1つ目は「コンティンジェンシー」で、学習者の能力に応じた支援をタイミングよく提供することを意味します。
- 2つ目は「相互主観性」で、学習者間で共通認識や理解を形成することです。
- 3つ目は「責任の移譲」で、支援者が徐々にサポートを減らし、学習者が最終的に自立的に課題をこなせるようになることを指します。
このメタ分析の発見は、オンライン学習環境におけるスキャフォールディングが、特に「メタ認知的領域」で高い効果を示したことです。メタ認知とは、自分自身の思考プロセスを認識し、調整する能力のことです。簡単に言えば、「学び方を学ぶ」能力とも言えるでしょう。オンライン学習においては、このメタ認知能力が成功の鍵を握ることが多いのです。
なぜオンライン学習においてメタ認知的スキャフォールディングが効果的なのでしょうか。それは、オンライン環境では学習者が自分のペースで学ぶ自由がある反面、自己調整の責任も大きくなるためです。メタ認知的スキャフォールディングは、学習者に「今自分は何を理解していて、何が分かっていないのか」「どのような学習戦略が効果的か」といった気づきを促し、学習プロセスを自ら最適化する手助けをします。
メタ認知的スキャフォールディングの例としては、自己評価のプロンプト、振り返りの機会の提供、学習日記の作成支援などが挙げられます。これらは学習者に自分の学習状況を客観的に見つめる機会を提供し、必要に応じて軌道修正を行うことを促します。
メタ分析ではさらに、スキャフォールディングの種類別にも効果を比較しています。その結果、メタ認知的スキャフォールディングに次いで、概念的スキャフォールディングも大きな効果を示しました。概念的スキャフォールディングとは、重要な概念を整理して提示する支援方法です。一方、戦略的スキャフォールディングと手続き的スキャフォールディングは、相対的に効果が低いことが分かりました。
もう一つ興味深いのは、スキャフォールディングを提供する主体による効果の違いです。最も効果が高かったのは、同級生(ピア)による支援でした。次いで教師、そしてコンピューターによる支援の順でした。ただし、ピアによる支援の研究例は少ないため、この結果の解釈には注意が必要です。
スキャフォールディングはオンライン協働を効率化する
プロジェクトベースの学習やチームでの協働作業は、現代の教育や職場環境で広く取り入れられています。とりわけオンライン環境でのチーム協働は、場所や時間の制約を超えた柔軟な働き方を可能にする一方で、コミュニケーションの困難さやプロジェクト管理の複雑さといった課題も抱えています。
このような課題に対して、プロジェクトマネジメントの知識体系をスキャフォールディングとして活用する試みが行われています。米国の大学院レベルのオンライン教育テクノロジーコースで実施された研究では、「プロジェクトマネジメント知識体系(PMBOK)」を用いたスキャフォールディングが、オンライン環境でのチーム協働にどのような効果をもたらすかが検証されました[3]。
PMBOKとは、プロジェクトマネジメントの国際的な標準として広く認知されている知識体系で、プロジェクトの開始から終結までの段階的な手法や、各段階で使用するツールを体系化したものです。この研究では、PMBOKの手法やツールをスキャフォールディングとして活用し、オンラインでのプロジェクトベース学習における効果を調査しました。
研究では、社会人大学院生14名を対象に、PMBOKを使用するグループと使用しないグループに分け、両者のプロジェクト遂行プロセスを比較しました。具体的には、チーム内の非同期掲示板でのコミュニケーション、最終成果物の質、そして学習者のプロジェクト経験に関するアンケート調査を通じて評価が行われました。
顕著な違いが見られたのは、チーム内コミュニケーションの効率性でした。PMBOKを使用したチームの掲示板投稿数は、使用しなかったチームの約3分の1と少なかったものの、内容はより焦点が絞られ、効率的なものでした。PMBOKのツールを活用したチームは、プロジェクトの初期段階でより明確な分析と計画を行い、後半ではスムーズな実行と管理ができていました。一方、PMBOKを使用しなかったチームでは、プロジェクト全体を通じて設計やスケジュール調整に関する議論が散発的に続き、非効率な面が見られました。
最終成果物の質については両グループ間で有意な差は見られませんでした。PMBOKを使用したグループの成果物の平均スコアは、使用しなかったグループとほぼ同等の結果となりました。学習者の主観的なプロジェクト経験についても、統計的に有意な差は認められませんでした。
これらの結果から、PMBOKを用いたスキャフォールディングはオンライン環境でのチームコミュニケーションを効率化する効果がある一方で、成果物の質や学習者の主観的体験には大きな影響を与えないことが分かりました。この背景には、参加者が経験豊富な社会人学生であったことも影響していると考えられます。彼ら彼女らはすでにある程度のプロジェクト経験を持っており、スキャフォールディングがなくても一定の成果を出せる能力があったと推測されます。
コンピューターのスキャフォールディングは固定的解除で効果低下
教育におけるテクノロジーの活用が進む中、「コンピューターによるスキャフォールディング」は、STEM(科学・技術・工学・数学)教育において広く取り入れられるようになりました。しかし、コンピューターによるスキャフォールディングが実際にどの程度効果的なのか、またどのような条件下で最も効果を発揮するのかについては、まだ多くの疑問が残されています。
これらの疑問に答えるため、STEM教育におけるコンピューターを用いたスキャフォールディングの効果を検証するメタ分析が行われました[4]。メタ分析とは、複数の研究結果を統計的に統合し、より信頼性の高い結論を導き出す手法です。この研究では、厳密な基準で選ばれた7件の研究が分析対象となりました。
全体的な結果として、コンピューターによるスキャフォールディングは、STEM教育において中程度の効果があることが確認されました。これは統計的に有意な結果であり、コンピューターによるスキャフォールディングが学習成果の向上に寄与することを示しています。
しかし、この研究で興味深かったのは、スキャフォールディングの「フェーディング(足場外し)」に関する発見です。教育理論において、スキャフォールディングは学習者のスキル向上に伴って徐々に減らしていく(フェーディングする)ことが理想とされています。これは、建設現場の足場が建物の完成とともに徐々に撤去されていくのに似ています。
しかし、この研究では予想に反する結果が出ました。フェーディングがないスキャフォールディングは、固定的にフェーディングするものよりも効果が高かったのです。要するに、コンピューターによるスキャフォールディングにおいては、一定のスケジュールで自動的に支援を減らしていく「固定的フェーディング」よりも、支援を継続して提供する方が学習効果が高いことが分かりました。
研究者たちは、コンピューターによる固定的フェーディングは、学習者の実際の進捗や理解度に関わらず機械的に支援を減らしてしまうため、学習者が十分に準備できていない段階で支援が取り去られてしまう可能性を指摘しています。理想的には、学習者の状態に応じて適応的にフェーディングを行うべきですが、現状のシステムではそれが難しい場合があります。
もう一つの発見は、スキャフォールディングのタイプによる効果の違いです。「概念的スキャフォールディング」は、「メタ認知的スキャフォールディング」よりも効果が高いことが示されました。概念的スキャフォールディングとは、学習内容の重要な概念を整理して提示する支援方法で、メタ認知的スキャフォールディングは学習者の自己調整や内省を促す支援方法です。
この結果は、先ほど紹介したメタ分析結果と一見矛盾するように見えるかもしれません。先ほどは、オンライン学習環境においてメタ認知的スキャフォールディングが特に効果的だと報告されていました。この違いは、研究対象の違い(一般的なオンライン学習 vs. STEM教育)や、スキャフォールディングの実装方法の違いによるものと考えられます。また、メタ認知的スキルの育成は長期的な取り組みを要するため、短期間の実験では効果が十分に現れにくい可能性もあります。
コンピューターによるスキャフォールディングをデザインする際は、固定的なフェーディングスケジュールを避け、可能であれば学習者の進捗に応じた適応的なフェーディングを検討すべきでしょう。それが技術的に難しい場合は、フェーディングなしでも一定の効果が期待できることを認識しておくと良いと言えます。
脚注
[1] Janson, A., Sollner, M., and Leimeister, J. M. (2020). Ladders for learning: Is scaffolding the key to teaching problem solving in technology-mediated learning contexts? Academy of Management Learning & Education, 19(4), 439-468.
[2] Doo, M. Y., Bonk, C., and Heo, H. (2020). A meta-analysis of scaffolding effects in online learning in higher education. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 21(3), 60-80.
[3] van Rooij, S. W. (2009). Scaffolding project-based learning with the project management body of knowledge (PMBOKR). Computers & Education, 52(1), 210-219.
[4] Belland, B. R., Walker, A. E., Olsen, M. W., and Leary, H. (2015). A pilot meta-analysis of computer-based scaffolding in STEM education. Educational Technology & Society, 18(1), 183-197.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。