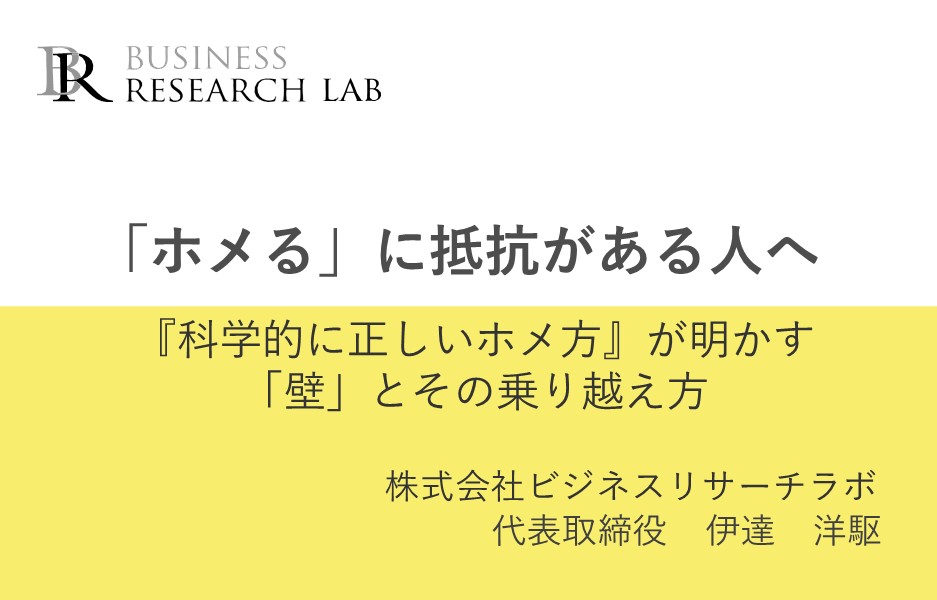2025年9月29日
「ホメる」に抵抗がある人へ:『科学的に正しいホメ方』が明かす「壁」とその乗り越え方
後輩や部下をもっとうまく勇気づけたい。そう願いながらも、いざ「ホメる」という行為を前にすると、言葉に詰まってしまった経験はないでしょうか。「気恥ずかしさが先に立ってしまう」「部下のためにならないのではないかと、効果を疑ってしまう」「どうせお世辞だと思われるのが関の山だ」。こうした内心の葛藤を抱えるリーダーや先輩社員もいます。善意とは裏腹に、かけた言葉が相手を萎縮させたり、見えない壁を作ってしまったりすることもあります。
なぜ私たちは、人を「ホメる」ことに、ためらいを感じてしまうのでしょうか。抵抗感の正体は、個人の性格や経験だけに起因するものではありません。その根底には、少なからぬ人が無意識のうちに囚われている、いくつかの「誤解」や「思い込み」という「壁」が存在するのです。
この度、『科学的に正しいホメ方:ポジティブ・フィードバックの技術』という本を上梓しました。本書は、感覚論や精神論に陥りがちだった「ホメる」という行為を、心理学や組織論といった科学的な知見の光で照らし出し、誰もが実践可能な「技術」として再構築することを試みたものです。本コラムでは、拙著で探求した内容に触れながら、多くの人が直面する5つの「壁」の正体を解き明かし、科学の力でそれを乗り越えるための道筋を示していきたいと思います。
第1の壁:「ホメすぎは甘やかし」という信念の壁
最初にぶつかるのが、「ホメすぎは、相手を甘やかすだけではないか」という信念です。とりわけ、自身が厳しい指導の中で成長してきた経験を持つ人ほど、この考えは強固かもしれません。規律を緩ませ、言うべきことを言えなくなり、結果的に本人の成長を阻害してしまうのではないか。その懸念は、育成への真摯な責任感の裏返しでもあります。
しかし、科学的な視点から見ると、「甘やかし」につながる危険性をはらんでいるのは、特定の種類のホメ方に限られます。それは、個人の才能や資質といった、固定的で変えられないと見なされるものを称賛する「能力ホメ」です。例えば、「本当にセンスがある」といった言葉がそれに当たります。
一見、相手を勇気づけているように思える「能力ホメ」ですが、実は副作用を伴います。ドゥエックの研究によれば、能力をホメられた人は、成功の要因を自らの不変の「才能」に結びつけて考えやすくなります[1]。その結果、一度失敗を経験すると、「自分には才能がなかった」という証明だと捉えてしまい、次なる挑戦への意欲を失ってしまうのです。これは、知能や才能は固定的であると考える「固定マインドセット」が強化されるためです。失敗を恐れ、本来持っていたはずの可能性の芽を、ホメ言葉自身が摘んでしまうという皮肉な事態を招きかねません。
一方で、拙著で一貫して推奨しているのが、「プロセスホメ」というアプローチです。これは、「今回の提案に至るまでの、あの粘り強い情報収集が素晴らしかった」「困難な状況で、複数の選択肢を冷静に検討した工夫が見事だった」というように、具体的な行動や努力の過程、試行錯誤のプロセスに光を当てるホメ方です。
「プロセスホメ」は、人の能力は固定的ではなく、努力や工夫次第で伸ばせると信じる「成長マインドセット」を育みます。このマインドセットを持つ人は、失敗を能力の欠如の証明ではなく、成長のための学習機会として捉えることができます。挑戦する心を支え、困難からの回復力を育みます。要するに、「プロセスホメ」は、相手の自律的な成長を促す「育成」行為であり、「甘やかし」とは次元の異なるアプローチなのです。この違いを理解し、意識的に言葉を使い分けることが、信念の壁を乗り越えるための第一歩となります。
第2の壁:「お世辞だと思われる」という信頼の壁
続いて立ちはだかるのは、「本心ではないお世辞だと受け取られ、かえって信頼関係を損なうのではないか」という、人間関係に関わる壁です。この不安は、少なからぬ人が感じるところでしょう。心のこもっていない言葉が相手に見透かされ、白々しい空気が流れる。そんな気まずい状況を想像すると、ポジティブな言葉を発する意欲も萎えてしまいます。
実際、その懸念は的を射ています。真実味のないホメ言葉は、相手のモチベーションを削ぐだけでなく、関係性にひびを入れることもあります。では、「お世辞」と「心に響く称賛」とを分かつものは、何なのでしょうか。その答えは、「具体性」にあります。
「素晴らしい仕事でしたね」「さすがですね」といった漠然とした言葉は、何を評価されているのかが不明確なため、受け手にとっては社交辞令に聞こえてしまいます。これに対し、本書が提唱する「具体化」の技術は、ホメ言葉に客観性と信頼性をもたらします。その核となるのが、「数値」「行動」「状況」という三つの事実に基づいて語るという手法です。
例えば、「今月の顧客満足度が前月比で15%向上しました(数値)。これは、○○さんがお客様一人ひとりの問い合わせに対して、解決策だけでなく代替案まで丁寧に提示していた(行動)結果です。特に、システムトラブルでクレームが殺到し、チーム全体が混乱する中で(状況)、冷静に優先順位をつけてチームを導いてくれた貢献は、計り知れないものでした」。
このように事実をベースに語ることで、ホメ言葉は主観的な感想ではなく、客観的な事実に基づく「評価」として機能します。相手は自身のどの行動が成果に結びついたのかを理解でき、その成功体験を再現しようと努めるようになるでしょう。
この「具体化」をさらに一歩進め、相手の心に深く刻み込む方法が、心に響く「エピソード」として語る手法です。私たちの脳は、ただの情報の羅列よりも、背景や登場人物、そして感情の動きを含む物語を記憶しやすいようにできています。
事実を報告するだけではなく、「あの時、プロジェクトが暗礁に乗り上げかけて、誰もが諦めかけていました。そんな中で、○○さんだけが顧客の元へ何度も足を運び、小さな要望の中から本質的な課題をすくい上げてきてくれました。あの粘り強さがなければ、この成功はあり得なかったと思います」。このように物語として語ることで、相手は自分の行動が持つ意味や価値を、感情を伴って理解することができます。それはもはや「お世辞」ではなく、相手の奮闘をすぐそばで見ていたからこそ語れる、真実味のこもったメッセージとなります。
第3の壁:「叱る方が即効性がある」という経験則の壁
「結局のところ、重要な局面では厳しく叱責する方が、手っ取り早く行動を変えさせられる。自分もそうやって育てられてきた」。こうした経験則は、無視できない実感かもしれません。確かに、厳しい言葉は相手に強いインパクトを与え、その場では行動が修正されたかのように見えることもあります。この「即効性」への信頼が、ポジティブなアプローチへの移行を妨げる壁となっています。
しかし、ここにも人間の脳に組み込まれた、二つの「不都合な真実」が横たわっています。一つは、私たちがポジティブな情報よりもネガティブな情報に、より強く迅速に反応してしまう「ネガティビティ・バイアス」です。これは、危険を察知し生存確率を高めるための本能的な傾向です。このバイアスのために、私たちはよほど意識しない限り、例えば、同僚のプレゼンテーションの優れた点よりも、些細なミスといった欠点の方に自然と目が行きやすくなります。
もう一つのメカニズムが「記憶無視」です。研究によれば、人は自己肯定感を維持するために、自分に関する否定的なフィードバックを選択的に思い出しにくくなる、という性質を持っています。「何度注意しても直らない」という現場の嘆きは、相手の意欲や態度の問題だけでなく、この認知システムに起因する可能性があります。叱責というネガティブ・フィードバックは、伝えた側の強い意図とは裏腹に、そもそも相手の記憶に定着しにくいという科学的根拠は、「叱る」指導法の限界を示唆しています。
では、改善点を指摘したり、厳しいフィードバックを伝えたりする必要がある場面では、どうすれば良いのでしょうか。その答えは、拙著で紹介する「ホメの黄金比 5:1」にあります。これは、安定した人間関係を築いているチームやカップルに見られるコミュニケーションの比率で、ポジティブなやりとりが5に対して、ネガティブなやりとりが1の割合で交わされている状態を指します。
この比率が意味するのは、日頃から称賛や感謝といったポジティブなフィードバックを積み重ねておくことで、信頼関係という「心理的な貯金」が蓄えられるということです。この貯金が十分にあれば、いざ改善点を指摘しなければならない場面でも、相手はそれを人格否定や批判としてではなく、「自分の成長を願ってくれているからこその言葉だ」と建設的に受け止めることができるのです。
日常的な「ホメ」は、いざという時の「叱責」の効果を最大限に高めるための土台です。即効性があるように見える叱責も、この土台なくしては砂上の楼閣に過ぎません。この逆説的な真実が、経験則の壁を打ち破る鍵となります。
第4の壁:「ホメるのは上の立場から」という役割の壁
「ホメるという行為は、本質的に評価する側、すなわち上司から評価される側である部下への一方的なものではないか」。この「役割」意識は、ホメるという行為に付きまとう気恥ずかしさや、上下関係の硬直性を助長する壁となります。評価者として相手を見定めるような、どこか「上から目線」に感じられることへの抵抗感が、自然な称賛の言葉を妨げてしまいます。
この壁を乗り越えるためには、「ホメる(ポジティブ・フィードバック)」を、評価ではなく、組織の風通しを良くし、活性化させるための「双方向のコミュニケーション」だと再定義する必要があります。その実践は、決して上司から部下への一方通行である必要はありません。
まずは、「同僚をホメる」こと。同じ立場で業務にあたる同僚だからこそ気づける貢献があります。「あの時の的確な情報共有のおかげで、プロジェクトの遅れを防ぐことができました。ありがとうございます」。日々の業務で助けられた場面で、具体的な貢献を認め合う言葉は、チームワークを強固にします。
そして、多くの人が実践をためらいがちですが、実は効果的なのが「部下から上司をホメる」ことです。「部長が示してくださった方針のおかげで、チームとして迷わず業務に集中できました」「先日の面談でいただいたアドバイスが、課題解決の大きなヒントになりました」。こうした部下からの具体的なフィードバックは、上司に自らのリーダーシップや支援が正しく伝わっているという確信を与えます。それは上司自身の行動を省察する機会となり、より良いマネジメントへとつながる好循環を生み出します。
ポジティブなコミュニケーションの力は、当事者間にとどまりません。研究によれば、二者間で感謝の言葉が交わされる場面を第三者が目撃すると、その第三者も、当事者たちに対してより協力的になる傾向があることが示されています。いわば「感謝の目撃効果」です。
一人のリーダーが部下のプロセスを称賛し始めれば、その部下もまた、同僚の小さな工夫に気づき、感謝を伝えるようになるかもしれません。そのようなポジティブなやりとりが組織の隅々にまで「伝播」し、目撃され、模倣されていく。この連鎖が、トップダウンのスローガンだけでは実現できない、ボトムアップからの組織文化を形作っていくでしょう。
第5の壁:「そもそもホメるネタがない」という観察眼の壁
最後の壁は、おそらく最も実践的で、多くの人が日々直面している悩みでしょう。「日常業務をこなしているだけで、称賛に値するような特別な行動や、目を見張るような大きな成果はそうそう見つからない」。ホメる重要性は理解できても、その対象となる「ネタ」が見つからなければ、行動に移すことはできません。この観察眼の壁は、ポジティブ・フィードバックの実践を断念させる、最大の障壁かもしれません。
この壁を突破する鍵は、私たちの視点を「特別な成果」から「日常のプロセス」へとシフトさせることにあります。称賛の対象は、大きな成功体験だけではありません。人が成長する上で重要なのは、日々の業務の中に無数に散りばめられた「小さな進歩」です。昨日より今日できたこと、先週よりスムーズになったこと、前回よりも工夫が見られたこと。この成長のプロセスに価値を見出し、光を当てることが、相手のモチベーションを持続させ、着実な成長を支えます。
どうすれば「小さな進歩」に気づくことができるのでしょうか。それには、観察の「解像度」を上げるための技術が役立ちます。例えば、「時間軸での比較」です。朝のミーティングでの発言と、午後のミーティングでの発言を比べる「即時比較」。週の初めと終わりでの変化を見る「週単位の比較」。先月との違いを振り返る「月単位の比較」。時間軸の目盛りを使い分けることで、見過ごしやすい変化を捉えることができます。
また、「領域別の観察」も有効です。技術面での進歩、コミュニケーション面での進歩、時間管理といったマネジメント面での進歩など、観察の切り口を複数持つことで、その人の多面的な成長に気づきやすくなります。
こうした観察眼を養うと同時に、ホメる機会を意識的に増やすための「環境づくり」も大事です。例えば、社内SNSやチャットツールといったデジタルツールを活用し、良い行動を見かけたら即座に称賛や感謝のメッセージを送る。あるいは、自分自身のカレンダーに「1日の振り返り」として10分間をブロックし、その日に見つけたメンバーの「小さな進歩」を記録する習慣をつける。いわば、ホメの「スケジューリング」です。こうした小さな仕組みづくりが、私たちの無意識的な観察の癖を乗り越え、ポジティブなフィードバックを組織の日常へと変えていきます。
ホメることを組織のOSへ
本コラムでは、「ホメる」という行為を前に、私たちが直面する5つの心理的な壁について、拙著『科学的に正しいホメ方』の知見を基に、その乗り越え方を論じてきました。「甘やかしになる」という信念、「お世辞だと思われる」という不安、「叱る方が手っ取り早い」という経験則、「ホメは上から下へ」という役割意識、「ホメるネタがない」という観察眼の限界。これらの壁は、個人の能力の問題ではなく、科学的なアプローチによって乗り越えることが可能な、構造的な課題です。
5つの壁を乗り越えた先には、ポジティブ・フィードバックが組織の隅々まで行き交う、新たな景色が広がっています。そこでは、メンバーが安心して失敗を恐れずに挑戦し、互いの貢献から学び合い、自律的に成長していく「学習する組織」の姿が現れるでしょう。
その意味で、「科学的に正しいホメ方」は、部下育成やモチベーション向上のための対症療法的なマネジメント手法の一つではありません。個人の成長と組織の発展という、時に相反するように見える二つの目標を両立させるための、戦略的かつ持続可能なコミュニケーションの基盤、いわば組織のOS(オペレーティング・システム)なのです。
このOSが組織にインストールされた時、私たちが日々交わす何気ない一言一言が、人と組織の未来を創造する力へと変わります。本書を手に取っていただくことで、皆さんの日々のコミュニケーションを見つめ直し、その一言の持つ計り知れない力を再発見するきっかけとなれば、これに勝る喜びはありません。まずは、皆さんが最も高く感じている一つの「壁」からで構いません。その壁を乗り越えるための、小さな一歩を今日から踏み出してみてはいかがでしょうか。
脚注
[1] 本コラムで紹介している研究知見の詳細および出典は、拙著『科学的に正しいホメ方:ポジティブ・フィードバックの技術』をご覧ください。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。