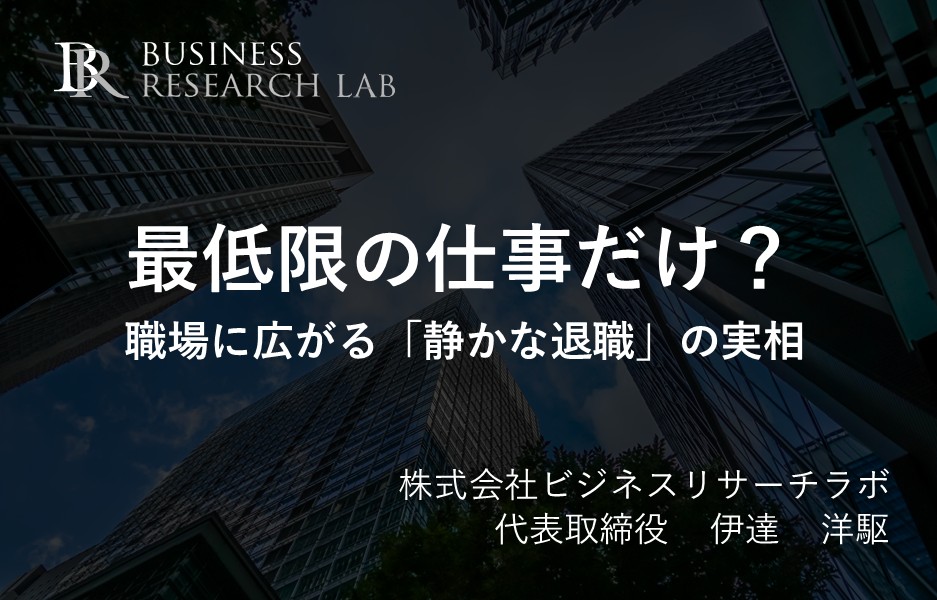2025年9月26日
最低限の仕事だけ?:職場に広がる「静かな退職」の実相
近年、「静かな退職(Quiet Quitting)」という現象が世界中で関心を集めています。静かな退職とは、定められた最低限の仕事のみを行い、それ以上の努力や仕事をしないという働き方を指します。これは物理的に職場を離れることではなく、心理的に仕事から距離を置く現象です。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを経て、多くの人々が仕事と生活のバランスや自分の健康について見直すようになりました。その結果、従来の「会社のために全てを捧げる」という働き方に疑問を持ち、自分の境界線を明確にする人が増えたという見方もあります。
静かな退職は、単純な個人の怠惰や責任放棄ではありません。むしろ、組織の構造的問題や管理方法、社会経済的要因など、複雑な背景が絡み合った現象です。様々な職場において、従業員が静かな退職に至る過程やその結果には共通点と固有の特徴があります。
本コラムでは、病院、学校、公的機関、そして一般企業における静かな退職に焦点を当て、その実態と背景要因を探ります。医療従事者、教師、公務員、そして民間企業の従業員が、なぜ静かな退職という選択をするのか、それぞれの職域における研究結果を基に考察していきます。
静かな退職は病院の安全や医療の質を脅かす
医療現場における静かな退職は、職場環境の問題にとどまらず、患者の安全や医療サービスの質に関わる課題です。ある研究グループは、病院環境における医療従事者の静かな退職に関する概念分析と包括的文献レビューの研究プロトコルを提示しました[1]。この研究は、医療現場特有の静かな退職を理解するために重要な取り組みです。
COVID-19パンデミックの期間中、医療従事者は過酷な状況に置かれました。長時間労働、感染リスク、人員不足、そして時に患者や家族からの理解不足など、様々なストレス要因が重なりました。一般的な職場とは異なり、医療現場では従業員が「最低限の仕事」だけを行うことが、直接的な人命や健康に関わる可能性があります。
医療現場における静かな退職の表れとして、必要最低限の患者ケアのみを提供し、それ以上の追加的な支援や観察を行わない、チームの協力体制から自分を切り離す、患者とのコミュニケーションを必要最低限に抑えるなどの行動が見られます。こうした行動は、患者の安全性を脅かすだけでなく、医療の質全体を低下させる恐れがあります。
静かな退職が医療現場で広がる原因として、過重労働による身体的・精神的疲労が挙げられます。医療従事者は、シフト勤務や長時間労働によって慢性的な疲労状態に陥りやすく、その結果、燃え尽きに苦しむことがあります。この状態が長期間続くと、自己防衛として静かな退職という行動を取ることがあります。
病院組織の硬直的な構造や階層的な人間関係も要因の一つです。医師と看護師、あるいは管理職と現場スタッフの間に存在する権力格差は、コミュニケーション不全や不公平感を生み出す可能性があります。自分の意見や提案が無視される経験を重ねると、医療従事者は積極的な関与を諦め、必要最低限の業務のみを行うようになります。
医療現場の静かな退職は、患者ケアの質に悪影響を及ぼします。患者の細かな変化に気づかなくなる、必要な情報共有がなされない、チーム内の連携が弱まるなどの問題が生じます。こうした状況は、医療ミスや患者の不満、入院期間の長期化などにつながる可能性があります。
静かな退職が蔓延する医療現場では、優秀な医療従事者の離職率も高まります。熱心に働く医療従事者が周囲の静かな退職者の負担を背負うことになり、結果的に彼ら彼女らも燃え尽きてしまうという悪循環が生じるかもしれません。
静かな退職は教師への不公平な管理で深刻化する
教育現場における静かな退職もまた、深刻な問題として浮上しています。ある研究チームは、トルコの教育現場を対象に、教師の静かな退職について調査を行いました[2]。この研究では、混合研究法(質的調査と量的調査の組み合わせ)を用いて、教師が静かな退職に至る要因やその結果について分析しています。
教師の静かな退職とは、教師が学校環境の中で一定の努力を続けながらも、自分の職業に対する帰属意識や積極的な関与を感じられなくなる状態を指します。具体的には、授業の準備を最小限に抑える、課外活動や学校行事への参加を避ける、生徒や保護者とのコミュニケーションを必要最低限に留めるなどの行動が見られます。
この研究では、教師32名へのインタビューと484名へのアンケート調査を通じて、教師の静かな退職を引き起こす要因を4つのカテゴリーに分類しています。その中でも特に深刻なのが「管理的要因」です。
管理的要因として顕著だったのは、学校管理者からの不公平な扱いです。多くの教師が、仕事の配分が偏っていると感じており、一部の教師に過剰な負担がかかる一方で、他の教師は比較的楽な仕事を任されるという不公平感が広がっていました。管理者からの脅迫的な言葉遣いや心理的圧迫も、教師の職務へのモチベーションを低下させる要因となっています。
教師の静かな退職を促す二つ目の要因は「社会的要因」です。社会全体から教師の仕事が過小評価される風潮があり、教師としての尊厳が損なわれているという感覚が広がっています。教師は高い教育を受け、子どもたちの未来を形作る仕事をしているにもかかわらず、その価値が社会的に認められないと感じる教師がいるのです。
三つ目の要因は「経済的要因」です。多くの国で教師の給与水準は他の専門職と比較して低く、生活を十分に支えるレベルにありません。トルコの例では、教師の給与はOECD諸国の平均を大きく下回っています。このような経済的な不安定さが、将来への見通しを暗くし、職務へのコミットメントを弱めています。
四つ目の要因は「健康的要因」です。教師は日々、多くのストレスや精神的プレッシャーにさらされています。生徒の問題行動への対応、保護者からの要求、管理者からの業績評価などが重なり、心身の健康を損なうことが少なくありません。こうした健康問題が蓄積すると、自己防衛として静かな退職という選択をすることがあります。
教育は国の将来に関係する営みです。教師が静かな退職に陥ると、次世代を担う子どもたちの成長や発達に支障をきたす恐れがあります。教師の職業満足度や働きがいは、教師個人の問題ではなく、社会全体の問題として捉える必要があるでしょう。
静かな退職は公務員の絶望感から生じる
公的機関における静かな退職は、民間企業とは異なる特徴を持っています。ある研究では、トルコの公務員を対象に、静かな退職を選択する理由やその結果について分析しています[3]。この研究は、13名の公務員へのインタビューを通じて、公的機関特有の静かな退職の実態を明らかにしました。
公務員の静かな退職は、「システム上の問題と絶望感」が大きな要因であることが明らかになりました。公的機関は一般的に官僚的な組織構造を持ち、変化に対して抵抗が強い傾向があります。このような環境の中で、公務員は自分の努力や創意工夫が組織に受け入れられないという絶望感を抱きやすくなります。
公的機関特有の静かな退職の要因として、「業績評価と報酬制度の欠如」も挙げられています。公的機関では、業績に基づいた評価や報酬体系が整備されておらず、頑張っても頑張らなくても給与や昇進に大きな差がつかないことがあります。そのため、公務員は「なぜ余計な努力をする必要があるのか」と考えるようになります。
「同一労働同一賃金制度による不公平感」も公務員の静かな退職を促進する要因です。公的機関では、年功序列や学歴に基づいた画一的な給与体系が採用されています。そのため、実際の業務量や責任の重さに関わらず、同じ職位であれば同じ給与となります。この状況が、より多くの責任を負ったり、複雑な業務を担当したりすることへの意欲を削ぐのです。
公務員の静かな退職における特徴的な点は、「雇用保障が強すぎて怠惰が生じやすい」ことです。公務員は強い雇用保障を持っており、よほどのことがない限り解雇されることはありません。この安定性は一方で、積極的に努力する動機を弱める原因ともなります。
公務員の静かな退職に伴う感情的側面として、最も強いのは「価値を認められていない感覚」です。公務員の中には、自分の仕事や貢献が上司や組織から適切に評価されていないと感じる人もいます。「不幸感」「絶望感」「疲労感」「不安」なども、静かな退職にある公務員に共通して見られる感情です。
公的機関における静かな退職の問題点は、それが公共サービスの質に影響することです。公務員が最低限の業務しか行わなくなると、市民に提供されるサービスの質が低下し、行政に対する信頼感も損なわれます。一部の公務員が静かな退職になると、責任感の強い公務員がその負担を背負うことになり、組織全体の機能低下につながります。
静かな退職は組織の不公平感への反応である
静かな退職を理論的観点から分析した研究では、この現象の背景にある心理的・社会的メカニズムを明らかにしています[4]。静かな退職を理解するための理論的枠組みを構築し、特に「社会的交換理論」「資源保存理論」「世代理論」という3つの理論を中心に考察しています。
社会的交換理論の観点からみると、静かな退職は組織と従業員の間の「互恵性」のバランスが崩れた時に生じます。従業員は組織に対して労力、時間、スキル、献身などを提供する一方、組織からは報酬、評価、成長機会、尊重などが得られることを期待します。しかし、この交換関係が不公平だと感じると、従業員は自分の投資(インプット)を減らして均衡を取ろうとします。これが静かな退職として表れるのです。
この研究では、組織における不公平感が静かな退職の強い誘因の一つであることが指摘されています。不公平感は様々な形で生じますが、特に昇進や給与に関する不公平、上司による偏った評価、仕事の負担の不均衡などが従業員の不満を高めます。
例えば、自分と同じような能力や貢献をしている同僚が、より高い評価や報酬を得ていると感じる場合、従業員は「なぜ自分だけが一生懸命働く必要があるのか」という疑問を持つようになります。あるいは、組織への貢献に対して適切な認識や評価が得られない場合も、従業員のモチベーションは低下します。
資源保存理論の視点からは、静かな退職は従業員が自分の資源(エネルギー、時間、健康など)を守るための防衛的な反応と理解できます。現代の職場では、従業員は常に高いパフォーマンスを求められる一方で、十分な回復時間や支援が得られないことがあります。このような状況が続くと、従業員は自分の資源が枯渇するのを防ぐために、仕事へのコミットメントを意図的に削減します。
特にワークライフバランスの崩壊が静かな退職を促進する要因であると指摘されています。長時間労働や休日出勤が常態化している職場では、従業員は自分の健康や私生活が犠牲になっていると感じます。そのような状況での静かな退職は、自己保存のための合理的な戦略と言えるかもしれません。
世代理論の観点からは、静かな退職は特にZ世代(1990年代後半から2010年代初頭に生まれた世代)やミレニアル世代(1980年代から1990年代半ばに生まれた世代)に顕著であることが示されています。新しい世代は、「仕事のために生きる」のではなく「生きるために仕事をする」という価値観を持ち、ワークライフバランスや個人の幸福を重視する傾向があります。
これらの若い世代は組織への帰属意識が比較的弱く、自分の価値観や目標に合わない職場環境では、積極的に関与することを躊躇しません。研究によれば、Z世代の従業員は職場での不公平や意味のない業務に対して敏感であり、そのような状況には静かな退職で応じる傾向があるとされています。
静かな退職の具体的な表れ方としては、最低限の業務のみを行う、自発的な提案や改善活動を控える、会議での発言を避ける、時間外の仕事を拒否する、組織の社交行事に参加しないなどが挙げられます。これらの行動は一見すると消極的ですが、従業員の視点からは自己防衛的で合理的な選択であることがあります。
この研究は、静かな退職が怠慢や無責任さの表れではなく、組織的な問題に対する反応であることを強調しています。特に組織内での不公平感、過度なストレス、意味を見いだせない仕事などが、従業員の静かな退職を促進します。
静かな退職がもたらす結果として、組織内での生産性低下、欠勤や形式的な出勤(プレゼンティーズム)の増加、職務上の退屈感や疲弊感、同僚との対立、組織全体の業績低下などが指摘されています。個人レベルでも、スキル開発の停滞や成長機会の喪失といった悪影響があります。
静かな退職は企業が従業員を軽視する結果である
企業環境における静かな退職に焦点を当て、その原因と対応策について分析した研究があります[5]。研究によれば、静かな退職は新しい現象ではなく、以前から存在していた働き方が近年になって注目されるようになったものです。特に「Great Resignation」と呼ばれる2021年以降の大量離職の背景にある問題と関連しています。
静かな退職を引き起こす主な要因として、5つの項目が挙げられています。
- 第一に「キャリア開発へのコミットメント不足」があります。企業が従業員の成長やキャリア開発に十分な投資をしていない場合、従業員は自分の仕事に将来的な希望を持てなくなります。専門的なスキルを向上させる機会やキャリアパスが示されないと、従業員は現状維持の姿勢に陥りやすくなります。
- 第二の要因は「従業員を大切に扱わない組織文化」です。従業員を「消耗品」として扱う企業文化が依然として多くの組織に根付いています。従業員の意見や感情に対する共感や配慮が欠如した管理スタイルは、職場への帰属意識や積極的な貢献意欲を低下させます。
- 第三に「従業員の孤立感・疎外感の増大」が挙げられます。特にCOVID-19パンデミック以降、テレワークの普及により物理的な職場コミュニティが希薄化しました。オンライン会議やデジタルコミュニケーションでは、対面での交流から得られる帰属意識や人間関係の深さを完全に代替することは難しいものです。従業員が企業の意思決定プロセスから排除されていると感じる場合、組織への疎外感はさらに強まります。
- 第四の要因として「従業員の自律性の欠如」があります。自律性は従業員のモチベーションとパフォーマンスに影響を与えます。過度なマイクロマネジメントや柔軟性の欠如は、従業員の創造性や主体性を損ない、仕事に対する情熱を失わせます。
- 第五の要因は「組織への信頼感の低下」です。従業員の組織や管理職への信頼度が年々低下していることが報告されています。企業が約束を破ったり、従業員の期待を裏切ったりする経験が積み重なると、従業員は組織に対して懐疑的になり、最低限の努力しか投じなくなります。
この研究では、企業がこれらの問題に効果的に対処できていない理由として、5つの管理的失敗を指摘しています。「約束を守れない管理」「職場文化の軽視」「従業員のウェルビーイングへの無関心」「多様性と包摂性の欠如」「意味のある仕事の創出の失敗」です。
注目したいのは「意味のある仕事の不足」です。多くの従業員は、自分の仕事が何らかの形で意義や目的を持っていることを求めています。しかし、日々の業務が単調で機械的なものになり、自分の貢献が大きな目標や価値にどうつながっているのかを見失っている人もいます。この状況では、最低限の努力で日々をやり過ごすことが合理的な選択になります。
静かな退職は、従業員が組織から正当に評価されていないと感じた時の自然な反応であることが強調されています。従業員が自分の貢献や存在が尊重されていないと感じると、従業員も同様に組織に対して最低限の関与しか示さなくなります。
脚注
[1] Kang, J., Kim, H., and Cho, O. H. (2023). Quiet quitting among healthcare professionals in hospital environments: A concept analysis and scoping review protocol. BMJ Open, 13, e077811.
[2] Ozen, H., Korkmaz, M., Konucuk, E., Ceven, B., Sayar, N., Mensan, N. O., and Chan, T. C. (2024). Evaluation of quiet quitting: Is the bell ringing? Journal of Qualitative Research in Education, 38, 108-142.
[3] Esen, D. (2023). Quiet quitting in public institutions: A descriptive content analysis. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 13(1), 296-326.
[4] Arar, T., Cetiner, N., and Yurdakul, G. (2023). Quiet quitting: Building a comprehensive theoretical framework. Akademik Arastirmalar ve Calismalar Dergisi, 15(28), 122-138.
[5] Mahand, T., and Caldwell, C. (2023). Quiet quitting: Causes and opportunities. Business and Management Research, 12(1), 9-19.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。