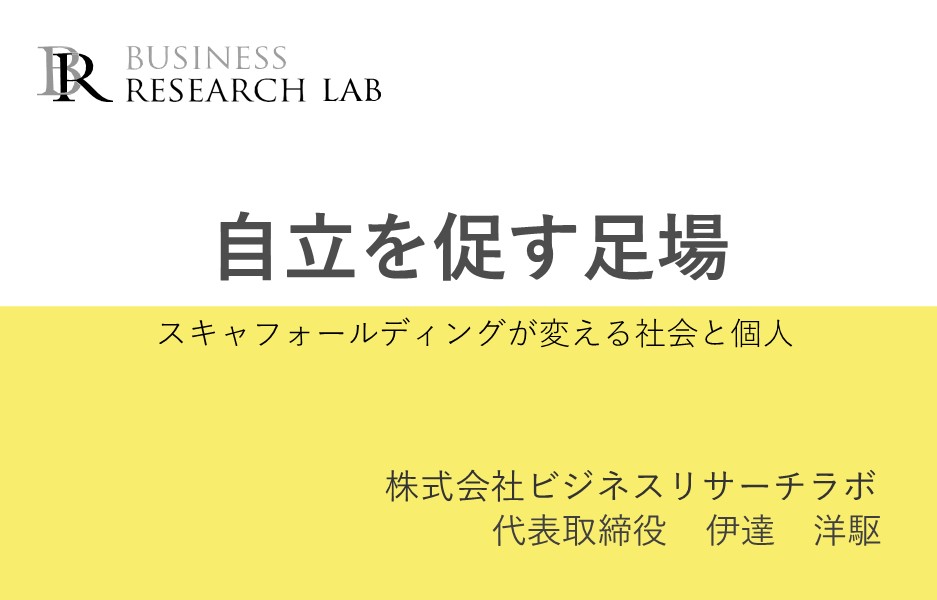2025年9月25日
自立を促す足場:スキャフォールディングが変える社会と個人
職場環境を見渡すと、ある人が別の人を支援する場面が見られるかもしれません。例えば、先輩社員が新入社員に業務を教える際、最初は手厚くサポートし、徐々に自立を促していくことがあります。このように、学習者や実践者が次第に自立できるよう一時的な足場を設ける支援方法を「スキャフォールディング」と呼びます。建設現場の足場(スキャフォールド)が建物の完成とともに取り外されるように、スキャフォールディングも相手が自立したら徐々に取り外されることが特徴です。
この概念は教育分野から生まれましたが、現在では組織マネジメント、国際開発、地域振興など幅広い分野で応用されています。スキャフォールディングが持つ多様な可能性と独自の価値は、現代社会が直面する複雑な課題への対応において新たな視点を提供してくれます。
本コラムでは、スキャフォールディングがもたらす様々な効果について、農村開発、女性の起業支援、学習環境、国際開発、社会的不平等の是正といった多様な文脈から探っていきます。それぞれの分野での実証研究を紹介しながら、スキャフォールディングがどのように人々の行動や関係性を変容させ、新たな可能性を開くのかを考察します。
スキャフォールディングは農村の知識共有を間接的に促す
農村地域では長年にわたって培われてきた知恵や技術が存在しますが、それらが広く共有されず埋もれてしまうことがあります。インド中央部のマディヤプラデシュ州で約9年間実施された調査では、農村の知識をどのように発掘し、共有するかという観点からスキャフォールディングの効果が明らかになりました[1]。
この地域では「FarmScreen」という社会的仲介組織が中心となり、農民たち自身が持つ農業知識を映像で記録・共有する活動を行っていました。しかし、農村社会特有の課題もありました。例えば、カースト制度による身分差別やジェンダーによる制約から、知識を持つ農民が自ら発信することをためらうケースです。農業の実践知は言葉だけでは伝えにくく、映像でも完全に捉えることが難しいという技術的な問題もありました。
これらの課題に対して、FarmScreenは二つのアプローチを採用しました。一つは「テクノフィシング」と呼ばれる手法で、最新の高度な技術ではなく、現地の状況に合わせた簡易なビデオ撮影技術を用いることです。もう一つが「スキャフォールディング」で、これが特に興味深い結果をもたらしました。
スキャフォールディングのアプローチでは、社会的不平等を直接的に批判するのではなく、「多様な農業知識を集める」という別の魅力的な目標を掲げることで、間接的に社会変革を促していました。例えば、低カーストの農民や女性農民の知識を積極的に記録することで、彼ら彼女らの社会的地位を間接的に向上させる効果が見込めます。
実際の知識共有プロセスは、5つの段階に分けられます。
- 「知識の気づき」の段階では、農民自身が気づいていない自分の知恵の価値を第三者が発見し顕在化させます。
- 「知識の勧誘」では、社会的制約によって発言をためらう農民に、名誉や社会的評価を動機づけとして共有を促します。
- 「知識の符号化」では、農作業の複雑さや身体知を映像で記録します。
- 「知識の検証」では記録された内容の実用性や理解可能性を確かめます。
- 「知識の整理」では、他の農民が活用しやすいように情報を構造化します。
このプロセス全体を通じて、スキャフォールディングは二つの機能を果たしていました。一つは、知識提供者(農民)自身が自立して知識を表現できるよう徐々に支援する点です。もう一つは、社会的障壁を直接攻撃せず、別の目標を通じて間接的に乗り越えていく点です。
スキャフォールディングが女性起業家の曖昧さを支える
デジタル時代の到来により、伝統的な職場から離れ、オンライン空間で自分のビジネスを展開する女性たちが増えていますが、この移行過程にはさまざまな心理的・社会的な課題が存在します。ここで、スキャフォールディングが重要な役割を果たすことが、健康・フィットネス業界の女性デジタル起業家を対象とした研究で明らかになりました[2]。
この研究では、女性たちがデジタル起業家として活動する際に経験する「リミナリティ」に焦点を当てています。リミナリティとは、明確な立場を持たない「どちらでもない」状態を指し、この場合は従来の雇用関係から抜け出し、まだデジタル起業家としての確固たるアイデンティティを確立していない中間的な状態を意味します。
女性たちの語りから浮かび上がってきたのは、このリミナリティが三つの段階で展開することでした。
- 「分離」の段階では、従来のキャリアからの離脱を経験します。多くの女性たちは組織内での不満や制約から、新たな可能性を求めてデジタル起業の道を選びました。
- 「リミナリティ」の段階では、経済的不安定さ、仕事の不確実性、社会的孤立感、オンライン上での自己表現の圧力など、多くの困難に直面します。
- 「統合」の段階では、デジタル空間での新たなコミュニティ形成、専門知識の構築、そして起業家としての新しいアイデンティティを確立していきます。
これらの移行過程において、スキャフォールディングが女性起業家の曖昧さを支える役割を果たしていました。例えば、オンラインコミュニティの存在は女性起業家たちに情報的・感情的サポートを提供し、不確実な状況での心理的安定をもたらしていました。メンターや同業者とのネットワークは、新たなビジネスモデルの開発や専門性の向上を支援する足場となっていました。
デジタル空間で起業家として活動することの「自由」という一般的なイメージとは裏腹に、実際には様々な社会的プレッシャーや心理的ストレスが存在します。例えば、「完璧な姿」をソーシャルメディアで見せなければならないという圧力や、プライベートとビジネスの境界が曖昧になることによる葛藤などです。スキャフォールディングはこうした困難に対して、女性起業家たちが自分自身のペースで新たなアイデンティティを構築できるよう支援する枠組みとなっていました。
リミナリティの時期は不安定ではありますが、同時に創造的な可能性を秘めた時期でもあります。女性起業家たちはこの時期に、従来の規範や制約から自由になり、新しい自己表現や職業的アイデンティティを模索することができます。スキャフォールディングはその模索の過程を支え、女性たちが自分自身の声を見つけて、独自のビジネスモデルを確立するための土台となります。
複合型スキャフォールディングは調整戦略に有効
教育現場において、学習者が自分自身の学習過程を管理・調整する能力は重要です。この能力は「自己調整学習」と呼ばれ、学習者の生涯にわたる学びの基盤となります。近年では、複数の学習者が共同で学習プロセスを調整する「社会的に共有された調整学習」の重要性も認識されるようになっています。これらの調整能力を高めるためのスキャフォールディングの効果について、46件の研究を対象としたメタ分析から結果が報告されています[3]。
この研究では、学習調整を支援するスキャフォールディングを四つのタイプに分類しています。一つ目は「スクリプト」で、学習タスクの手順や協調的な役割分担を明示するものです。二つ目は「グループ認識ツール」で、グループメンバーの活動状況を可視化し協調学習の認識を高めるものです。三つ目は「知的教育エージェント」で、仮想的なエージェントが学習者の行動に応じてフィードバックを提供します。そして四つ目は「複合ツール」で、上記の要素を複数組み合わせたものです。
分析の結果、調整型学習スキャフォールディング全体としては中程度の正の効果が確認されました。自己調整学習に対する効果と社会的に共有された調整学習に対する効果はどちらも中程度でした。
スキャフォールディングのタイプによって効果は異なります。総合的に最も効果が高かったのは「複合ツール」でした。ただし、自己調整学習に対しては「グループ認識ツール」が最も効果的であり、社会的に共有された調整学習に対しては「複合ツール」が最も効果的でした。また、学業成果への効果と調整戦略への効果を比較すると、調整戦略への効果の方が学業成果への効果よりも大きいことが分かりました。
スキャフォールディングの効果は様々な条件によって異なることも明らかになりました。例えば、学校段階では初等教育の生徒に対して最も効果的であり、学習形態では個別学習よりも協調学習の方が効果を高めました。教科領域では工学やコンピューター科学よりも、社会科学、自然科学、語学分野での効果が高い結果となりました。
国際開発では構造的スキャフォールディングが協働を促す
国際開発の分野では、複雑な社会問題に取り組むために異なる専門領域や組織間のコラボレーションが不可欠です。しかし、政策立案者、研究者、資金提供者、現地実施者など多様な関係者が効果的に協働することは容易ではありません。そこで重要になるのがスキャフォールディングです。インド、メキシコ、南アフリカ、ガーナにおける8つの国際開発プロジェクトを対象とした研究では、スキャフォールディングがどのように異分野間の協働を促進するかが分析されました[4]。
この研究が独自性を持つのは、スキャフォールディングを「構造的スキャフォールディング」と「プログラム的スキャフォールディング」の二つに分類した点です。これらは相互補完的に機能し、異なる専門家集団間の協働プロセスを支えています。
構造的スキャフォールディングは協働の基盤となる枠組みを提供するもので、三つの要素から成り立っています。一つ目は「保護された空間」の創出です。これは関係者が日常業務や組織の制約から離れ、自由に意見交換できる環境を指します。国際開発の現場では、こうした空間が異なる視点や知識の共有を促し、創造的な解決策の模索を可能にしていました。
二つ目は「マルチボーカルな調整」で、多様な声を調和させるファシリテーションのプロセスです。例えば、ある開発プロジェクトでは、専門用語を使う研究者と現場の言葉を使う実務者の間で通訳的役割を果たす「ブローカー」の存在が、コミュニケーションギャップを埋めていました。
三つ目は「適応的資金調達」で、プロジェクトの進展に応じて柔軟に資金配分を調整できる仕組みです。従来の厳格な予算管理ではなく、学習と実験を奨励する資金提供方法が、予測不可能な状況での創造的対応を可能にしていました。
一方、プログラム的スキャフォールディングはプロジェクトの各段階で必要となる具体的な活動を支援するもので、五つの要素があります。「共通問題の交渉」では、異なる利害関係者が共通の問題定義を作り上げるプロセスを促進します。「学習志向の確立」では、プロジェクトを結果ではなく学習のプロセスとして捉え直すことを奨励します。「分散型専門知識の活用」では、各専門家の独自知識を認識し効果的に統合します。「交換通貨の評価」では、専門知識や資金、政治的支援など各参加者が持つ資源の価値を評価し交換可能にします。「学習ピッチのマッピング」では、プロジェクトを小さな課題に分割し段階的に解決することで不確実性を管理します。
これら二種類のスキャフォールディングが相互に作用することで、国際開発プロジェクトにおける大きな課題の一つである「エビデンスの統合」が促進されていました。例えば、ある公衆衛生プロジェクトでは、医学研究者の科学的知見と現地コミュニティの文化的知識を組み合わせることで、より効果的な介入方法が開発されました。
構造的スキャフォールディングが協働の基盤を整え、プログラム的スキャフォールディングが具体的な協働活動を支援するという二重の支援体制により、多様な関係者間の信頼構築と知識統合が実現していました。
スキャフォールディングは不平等を隠れた目標で変える
小規模な社会において長年にわたって根付いた不平等のパターンを変えることは、困難な課題です。インドの農村地域で活動するNGO「Gram Vikas」の10年間に及ぶ事例研究では、スキャフォールディングが社会的不平等の変革に果たす独自の役割が明らかになりました[5]。
インドの農村社会では、カースト制度やジェンダーによる不平等が日常生活の行動パターンや相互作用の中に深く埋め込まれています。例えば、異なるカーストの人々が同じ場所で水を汲むことは禁忌とされ、女性は公の場での発言が制限されるなど、不平等が行動規範として現れています。こうした不平等に直接挑戦することは、しばしば強い抵抗や対立を生み出します。
そこでGram Vikasが採用したのが、「スキャフォールディング」というアプローチでした。このプロセスは三つの相互関連したメカニズムから成り立っています。
一つ目は「資源の動員」です。組織は地元の規範や信念といった制度的資源、自助グループや村落委員会などの社会的・組織的資源、資金や材料・労働力といった経済的資源を動員し、村人たちが新たな相互作用のパターンを構築できるよう促しました。例えば、村全体で共同管理する水道システムの建設に必要な資金や労働力を集めることで、従来は交流のなかった異なるカーストの村人たちが協力する機会が生まれました。
二つ目は「安定化」です。新しい相互作用のパターンを定着させるために、公式・非公式な統治構造やルールを構築しました。例えば、水道管理委員会には全カーストと女性の代表者を含めることを義務付け、維持管理費の支払いルールを明確化するなど、新しい関係性を制度化する仕組みを作りました。これによって、一時的な変化ではなく持続的な変革を実現する土台が形成されました。
三つ目は「目標の秘匿」です。これが最も興味深いメカニズムかもしれません。Gram Vikasは社会秩序の変革という本来の目的を前面に出さず、安全な水と衛生施設の整備という全員が合意できる別の目標に焦点を当てました。これによって、直接的な抵抗を避けながらも、結果として社会的相互作用のパターンを再構築することに成功しました。
例えば、全世帯(上位カーストも下位カーストも)がプロジェクトに参加しない限り水道システムを建設しないという原則を導入しました。これは、表向きは技術的・経済的理由(全世帯が参加することでコスト効率が上がる)で正当化されていましたが、実際には異なるカースト間の協力と平等なサービス提供を実現するための戦略でした。
女性の発言権を高めるために、水道管理委員会での女性代表の参加を義務付けましたが、これも水管理における女性の役割(水汲みや家庭での水使用)という実用的な理由で導入されていました。こうした間接的なアプローチにより、直接的な社会規範への挑戦では生じたであろう抵抗を最小限に抑えながら、実質的な変化を促すことができました。
脚注
[1] Qureshi, I., Bhatt, B., Parthiban, R., Sun, R., Shukla, D. M., Hota, P. K., and Xu, Z. (2022). Knowledge commoning: Scaffolding and technoficing to overcome challenges of knowledge curation. Information and Organization, 32, 100410.
[2] Kelly, G., and McAdam, M. (2022). Scaffolding liminality: The lived experience of women entrepreneurs in digital spaces. Technovation, 118, 102537.
[3] Shao, J., Chen, Y., Wei, X., Li, X., and Li, Y. (2023). Effects of regulated learning scaffolding on regulation strategies and academic performance: A meta-analysis. Frontiers in Psychology, 14, 1110086.
[4] Canales, R., Bradbury, M., Sheldon, A., and Cannon, C. (2024). Evidence in practice: How structural and programmatic scaffolds enable collaboration in international development. Administrative Science Quarterly, 1-56.
[5] Mair, J., Wolf, M., and Seelos, C. (2016). Scaffolding: A process of transforming patterns of inequality in small-scale societies. Academy of Management Journal, 59(6), 2021-2044.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。