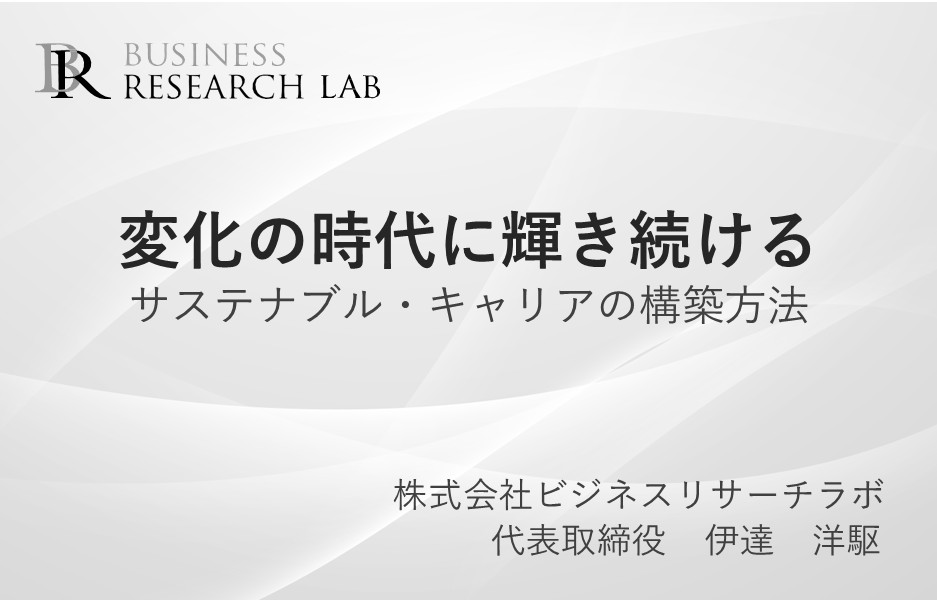2025年9月25日
変化の時代に輝き続ける:サステナブル・キャリアの構築方法
「一つの企業で定年まで働く」というキャリアパス以外も認められるようになり、多様な働き方や職業選択が可能になった一方で、不確実性も高まっています。変化の激しい環境の中で、個人が長期にわたって満足感や経済的安定を保ちながらキャリアを継続するには、何が必要なのでしょうか。
サステナブル・キャリアとは、個人の幸福、健康、生産性を現在から将来にわたって維持しながら発展させるキャリアのあり方を意味します。これは単純に長く働き続けることではなく、自分らしさを保ちながら、社会的にも経済的にも充実した職業生活を送ることを指します。
本コラムでは、様々な立場の人々のサステナブル・キャリアについて検討します。個人事業主、研究者、芸術家、子育て中の母親、そして大学卒業生といった異なる背景を持つ人々のキャリアに焦点を当て、それぞれがどのようにして持続可能なキャリアを構築しているのかを探っていきます。
個人事業主のキャリアは自己管理で持続可能になる
日本でも「フリーランス」「独立コンサルタント」「ギグワーカー」といった形で活躍する人々が出てきています。こうした働き方は、自由度が高く、自分の裁量で仕事ができるというメリットがありますが、同時に不安定さやストレス、孤独感といった課題も抱えています。個人事業主として長く安定したキャリアを築くためには、何が必要なのでしょうか。
オランダで行われた研究では、102名の個人事業主を対象に、持続可能なキャリアの構築方法について調査しました[1]。参加者は様々な職種、年齢、教育背景を持ち、キャリアステージも多様なメンバーで構成されていました。インタビュー形式で各事業主のキャリア形成プロセスや課題、対処法を聞き取り、質的に分析しました。
この調査における興味深い発見は、個人事業主のキャリア自己管理に4つの異なるパターンが存在することでした。
第一のパターンは「積極的なクラフター」と呼ばれるタイプで、長期的な視野を持ち、計画的に自分のキャリアを設計する人々です。自己実現や成長を意識し、市場の変化を先読みして自分のスキルを更新していました。
第二のパターンは「適応的なクラフター」と呼ばれるタイプです。このタイプの個人事業主は、その場の状況に応じて柔軟にキャリアを調整する能力に長けています。市場や顧客のニーズが変わればすぐに対応し、新たな機会を見つけることを得意としています。
第三のパターンは「生存者」と呼ばれるタイプで、キャリア自己管理に対する取り組みが最小限にとどまり、日々の業務をこなすことに精一杯の状態です。長期的な計画よりも、目の前の仕事を確保することに主眼を置いています。
第四のパターンは「受動的バランサー」と呼ばれるタイプです。このタイプは積極的なキャリア管理を避け、仕事と私生活のバランスを保つことを最優先します。キャリアの発展よりも、安定した生活リズムを保ち、ストレスを減らすことを重視しています。
調査の結果、持続可能なキャリアを構築できている個人事業主は、「積極的なクラフター」や「適応的なクラフター」に多く見られました。それらに共通する特徴として、高い自己認識、積極的な学習姿勢、強いネットワーク構築能力が挙げられます。
一方で、「生存者」や「受動的バランサー」のタイプは、しばしば経済的な不安定さや将来への不安を抱えていました。目先の収入確保に追われるあまり、自己投資の時間を確保できず、結果的にスキルの陳腐化や市場価値の低下に苦しむ場合が見られました。
持続可能なキャリアを構築する上で、個人事業主を支えるものとして「個人的な幸福感」「柔軟な働き方」「社会的支援」が挙げられています。特に社会的支援に関しては、家族や友人からの精神的サポートだけでなく、同業者とのコミュニティ形成や相互支援が重要であることが分かりました。
この研究では、個人事業主のキャリア持続可能性を高めるためには、個人が積極的かつ戦略的にキャリア自己管理を行うことの重要性が強調されています。しかし、すべての人が生まれながらにして「積極的なクラフター」になれるわけではありません。自己管理のスキルを徐々に学び、発展させていく過程が必要です。
データサイエンスへの移行が研究者のキャリアを安定化
科学・技術・工学・数学(STEM)分野のアカデミックキャリアが不安定になりつつあることが問題視されています。博士号を取得しても、安定したポジションを得ることが難しく、多くの研究者が短期契約の連続や将来の不確実性に悩まされています。このような状況下で、アカデミアから民間企業へと活躍の場を移す研究者もいますが、その移行プロセスやその後のキャリアの持続可能性については十分に理解されていませんでした。
英国で行われた研究では、アカデミアからデータサイエンス分野へキャリアを移行した研究者28名を対象に、その移行過程や移行後のキャリア状況についてインタビュー調査を実施しました[2]。対象者は物理学、生物学、電子工学、神経科学など幅広い分野出身で、博士号取得後間もない人から10年以上の研究経験を持つ人まで様々な経歴の持ち主でした。
この調査では、なぜ研究者たちがアカデミアを離れてデータサイエンスの道を選んだのか、その移行を可能にした要因は何か、そして新たなキャリアパスでどのような持続可能性を見出しているのかを明らかにすることを目的としていました。
調査から明らかになったアカデミアを離れる主な動機は、キャリアの不確実性と仕事の意義の欠如でした。多くの研究者は、任期付きポジションの更新の難しさや、テニュアのポストが限られていることへの懸念を抱えていました。また、学術研究の進展の遅さや、論文を発表することが実社会に直接的な影響を与えないことへの失望感を抱いていました。
これらの研究者たちはどのようにしてデータサイエンスへの移行を成功させたのでしょうか。調査によると、キャリア移行を可能にした要因は「個人的な努力」と「キャリア触媒(career catalysts)」でした。
個人的な努力としては、「自己省察」が挙げられます。多くの研究者は、自分の価値観や興味、強みを見つめ直す時間を意識的に取っていました。次に「自己学習」があります。オンライン講座やプログラミングの自習、データサイエンスのコンペティションへの参加など、新たなスキルセットを獲得するための努力を惜しみませんでした。さらに「社会的資本の活用」も重要でした。既存の人脈を活かして、データサイエンス分野で働く友人や知人から情報やアドバイスを得るという方法です。
「キャリア触媒」としては、特に「データサイエンスブートキャンプ」のような集中型トレーニングが効果的でした。これらのプログラムはスキルを教えるだけでなく、参加者のマインドを変え、企業文化への適応を促し、実際の就職に結びつける役割を果たしていました。
データサイエンスへの移行後、研究者たちはどのようなキャリアの持続可能性を見出しているのでしょうか。調査によると、多くの元研究者たちは新たな職場で「研究者としての自己イメージの再確認」を経験していました。データサイエンスの仕事でも、科学的手法を用いた問題解決を継続できることで、研究者としてのアイデンティティを維持・強化できていました。
「キャリア期待と実際のキャリア結果の調和」も見られました。アカデミアでは満たされなかった社会的影響力の実感や、能力や努力が正当に評価される機会がデータサイエンスの職場では充実していたのです。
この研究は、研究者からデータサイエンティストへのキャリア移行が「分野の転換」ではなく、個人の価値観や期待に合致した「持続可能なキャリアの再構築」であることを示しています。多くの元研究者たちは、データサイエンスの仕事において安定性と意義を見出し、長期的なキャリア展望を描けるようになったと感じていました。
芸術家のキャリアは危機時にデュアル化で安定する
パフォーミングアーティスト(俳優、ダンサー、歌手、演奏家など)のキャリアは、その性質上、特殊です。そのキャリアは短期間で身体的制約に直面しやすく、雇用も不安定であることが多いため、長期にわたる持続可能性が課題となっています。特に新型コロナウイルスのパンデミックは、この問題をより深刻なものにしました。公演の中止や延期が相次ぎ、多くのパフォーミングアーティストが収入源を失ったのです。
このような状況下で、パフォーミングアーティストはどのようにしてキャリアの持続可能性を確保できるのでしょうか。ポーランドで行われた調査では、111名のパフォーミングアーティストを対象にアンケート調査を実施し、パンデミック下での職業状況やキャリアに対する意識、将来への展望について分析しました[3]。
調査対象者は俳優、ダンサー、音楽家(歌手・器楽奏者)など、舞台上で観客と接する職業に従事する人々でした。パンデミックによる職業状況の変化、キャリア終了への考え方、代替キャリアの可能性、特に「デュアルキャリア」(芸術分野と非芸術分野の両方でキャリアを同時に進行させること)に対する評価について質問しました。
調査結果によると、回答者の56.7%がパンデミックにより芸術キャリアの不安定さを強く意識するようになったと答えています。また、43.2%が芸術キャリアだけでは十分な生活水準を確保できないと認識していました。こうした認識に基づき、約半数(47.7%)が代替キャリアの計画の必要性を強く感じていたのです。
しかし、非芸術的な教育や仕事を積極的に追求しようとした割合はやや低く、33.3%から44.1%程度でした。これは、多くの芸術家が自分のアーティストとしてのアイデンティティを強く持ち、別のキャリアへの移行に対して心理的抵抗を感じていることを示唆しています。
芸術キャリアの終了に対する態度も興味深い結果が出ました。芸術キャリアの終了を失敗と考える人とそうでない人が同数程度存在したのです。また、男性の方が、キャリアが身体的健康や生活水準を害する場合にキャリアを放棄する傾向が強かったことも分かりました。これは伝統的な家庭モデルに起因すると考察されています。男性は稼ぎ手としての責任を感じ、経済的安定を優先していたということです。
調査で注目されたのが「デュアルキャリア」の実践です。デュアルキャリアとは、芸術活動を続けながら同時に別の職業(教師、コーチ、事務職など)も持つというキャリア戦略です。この戦略はもともとスポーツ選手のキャリア研究から着想を得たもので、選手としての短いキャリア期間を考慮して早期から別のキャリアの準備を始めることを推奨するものです。
調査によると、すでにデュアルキャリアを実践している芸術家は、教育者(教師)としてのキャリアが芸術キャリア終了後の仕事に有利であると認識していました。また、デュアルキャリアが現実的で有益なキャリア形成方法であると感じていました。
この調査が示唆するのは、パフォーミングアーティストがキャリアの持続可能性を高めるためには、芸術活動に関連した代替キャリアや補完的なキャリアを早い段階から準備することが効果的だということです。特に、教育活動(教師やコーチ)や関連技術分野(音響、照明、デジタルコンテンツ制作など)でのスキル獲得が、芸術家のキャリアの安定性を高める可能性があります。
働く母親のキャリアは職場の理解があると持続可能になる
科学、工学、技術分野(SET)は伝統的に男性が多数を占める分野で、女性、特に母親がキャリアを継続することが難しいとされてきました。これらの分野では「理想の労働者」として職場での存在感(可視性)や時間的・地理的柔軟性が求められる文化が強く、それが母親としての役割と両立しにくいためです。このような環境でキャリアと子育てを両立させるには、どのような条件が必要なのでしょうか。
イタリア、フランス、オランダのSET企業で働く女性を対象とした研究では、主に30名の母親と8名の父親に対してインタビューを行い、出産後のキャリア形成や勤務時間短縮に関する決定、職場の文化や支援策に関する認識などを調査しました[4]。
この調査で明らかになったのは、多くの母親が勤務時間の短縮を「個人の選択」として表現しつつも、実際には社会的・組織的圧力を感じていたことです。例えば、職場で「良い母親ならば子どものために時間を割くべき」という暗黙の期待があったり、逆に「キャリアを真剣に考えているならフルタイムで働くべき」という考えが根強かったりするのです。
国による違いも見られました。フランスではパートタイム勤務が広く認められていましたが、それでもキャリア上の不利益を避けるためには長時間労働が求められていました。イタリアではパートタイム勤務自体が珍しく、母親は主に家族や祖父母の支援を受けてフルタイム勤務を継続していました。オランダでは育児休暇制度が充実していましたが、それを利用することでキャリアの停滞を招くことも少なくありませんでした。
多くの母親は、勤務時間を短縮するとキャリアアップや昇進が難しくなると感じており、この状況を「交換条件」(取引)として受け入れていました。一方、男性従業員は家庭のために勤務時間を短縮することが一般的ではなく、職場文化の中でそれが規範として認められていませんでした。父親の多くは、育児に積極的に関わりたいという意思を持ちながらも、実際にはフルタイム勤務を続けていました。
しかし、この研究では例外的に、時短勤務をしながらもキャリアを継続・昇進できた3人の女性の事例も紹介されています。彼女たちの成功要因を分析すると、特に上司の理解と支援が大きな役割を果たしていたことが分かりました。
時間や場所よりも結果を重視する職場環境が、母親のキャリア継続を可能にしていました。しかし、それでもなお、彼女たちは「例外的な存在」であることを認識しており、自分たちのケースが一般的なものではないと感じていました。
この研究が示すのは、SET分野の母親が持続可能なキャリアを構築するためには、制度があるだけでは不十分だということです。柔軟な勤務形態が「特別な配慮」ではなく「当然の権利」と見なされるような職場文化の変革が必要です。管理職の態度や行動が、部下のキャリアと家庭の両立にとって影響を持つことが明らかになりました。
卒業生のキャリアは雇用可能性で持続可能になる
大学を卒業して労働市場に参入する若者たちは、皆が皆「入社すれば定年まで」という安定したキャリアパスを期待するわけではありません。雇用形態の多様化、テクノロジーの急速な進化、グローバル競争の激化などにより、卒業生のキャリアは複雑で予測困難なものになっています。このような環境で、卒業生はどのようにして持続可能なキャリアを構築できるのでしょう。
英国の研究者たちによる概念的研究では、卒業生の持続可能なキャリアについて、個人(卒業生)と組織(雇用主)の観点から総合的に分析しています[5]。この研究では「キャリア・エコシステム」と「新しい心理的契約」という二つの理論的枠組みを用いて、卒業生と雇用主が互いにどのように相互作用し、それぞれの目標を達成できるかを探求しています。
「キャリア・エコシステム」とは、卒業生(個人)、大学(教育機関)、企業(雇用主)、政府(社会)などが相互依存的に結びついた労働市場を生態系のように捉える考え方です。一方、「新しい心理的契約」とは、組織と個人の関係が従来の長期雇用を前提とした安定的なものから、能力ベースで個人が主体的にキャリアを管理し、組織との関係も流動的かつ短期的なものへと変化していることを示す概念です。
研究者たちは、卒業生のキャリアの持続可能性に寄与する要素として、三つのテーマに注目しています。第一のテーマは「キャリアマネジメント」です。これには「キャリア所有意識」「キャリア満足度」「人材の惹きつけと保持」が含まれます。
「キャリア所有意識」とは、個人がキャリア形成に関与し、自律的にキャリアを管理することを指します。不確実な労働環境では、自分のキャリアは自分で管理するという意識が特に重要になります。例えば、定期的に自分のスキルや市場価値を見直し、必要に応じて新たな知識や経験を獲得するといった行動が、キャリア所有意識の表れといえます。
「キャリア満足度」は、給与や昇進機会だけでなく、仕事と生活のバランスや自己実現の可能性なども含む総合的な満足度を指します。持続可能なキャリアのためには、経済的な成功だけでなく、心理的な充実感も不可欠です。
一方、雇用主側の視点では、「人材の惹きつけと保持」が競争優位を維持するための要素となります。優秀な卒業生を獲得し、彼らが長く活躍できる環境を整えることが、企業の持続的な発展につながります。
第二のテーマは「人材開発」です。ここには「人的資本」「移転可能なスキル」「組織特有の資本と職務特化スキル」という要素が含まれます。
「人的資本」とは、個人が持つ知識、スキル、経験の総体を指します。卒業生がキャリア全体を通じて継続的に自身の人的資本を高めることが、持続可能なキャリアの基盤となります。具体的には、専門知識の更新、新たな技術の習得、異なる職務経験の蓄積などが挙げられます。
「移転可能なスキル」は、特定の職種や業界に限らず、様々な場面で活用できる汎用的なスキルを指します。コミュニケーション能力、問題解決能力、チームワーク、リーダーシップなどがこれに該当します。これらのスキルは、雇用環境が変化しても価値を保ち続けるため、卒業生の雇用可能性を高める上で重要です。
「組織特有の資本と職務特化スキル」は、特定の組織や職務に関連した知識やスキルを指します。企業はこれらを社員に提供することで、組織の競争力を高めると同時に、人材の定着も図ることができます。
第三のテーマは「技術革新」で、「柔軟な労働環境」と「自動化と人工知能」という要素が含まれます。
「柔軟な労働環境」とは、テレワークやフレックスタイムなど、時間や場所にとらわれない多様な働き方を可能にする環境を指します。卒業生に柔軟な働き方を提供することで、幸福感や生産性が向上し、持続可能なキャリアにつながるとされています。
「自動化と人工知能」は、労働市場を変えつつある技術革新を指します。企業がこれらの技術を効果的に活用することで競争優位を高める一方、卒業生も新たな技術に適応し、それを活用するスキルを身につけることが求められています。
脚注
[1] van den Groenendaal, S. M. E., Akkermans, J., Fleisher, C., Kooij, D. T. A. M., Poell, R. F., and Freese, C. (2022). A qualitative exploration of solo self-employed workers’ career sustainability. Journal of Vocational Behavior, 134, 103692.
[2] Ruiz Castro, M., Van der Heijden, B. I. J. M., and Henderson, E. L. (2020). Catalysts in career transitions: Academic researchers transitioning into sustainable careers in data science. Journal of Vocational Behavior, 122, 103479.
[3] Mizera-Peczek, P., Krasnova, A., Sasin, M., and Sieczych-Kukawska, A. (2024). Dual careers as sustainable careers for performing artists in times of crisis: A contextual approach to the construct of a sustainable arts career. PLOS ONE, 19(12), e0314933.
[4] Herman, C., and Lewis, S. (2012). Entitled to a sustainable career? Motherhood in science, engineering, and technology. Journal of Social Issues, 68(4), 767-789.
[5] Donald, W. E., Ashleigh, M. J., and Baruch, Y. (2020). Striving for sustainable graduate careers: Conceptualisation via career ecosystems and the new psychological contract. Career Development International, 25(2), 90-110.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。