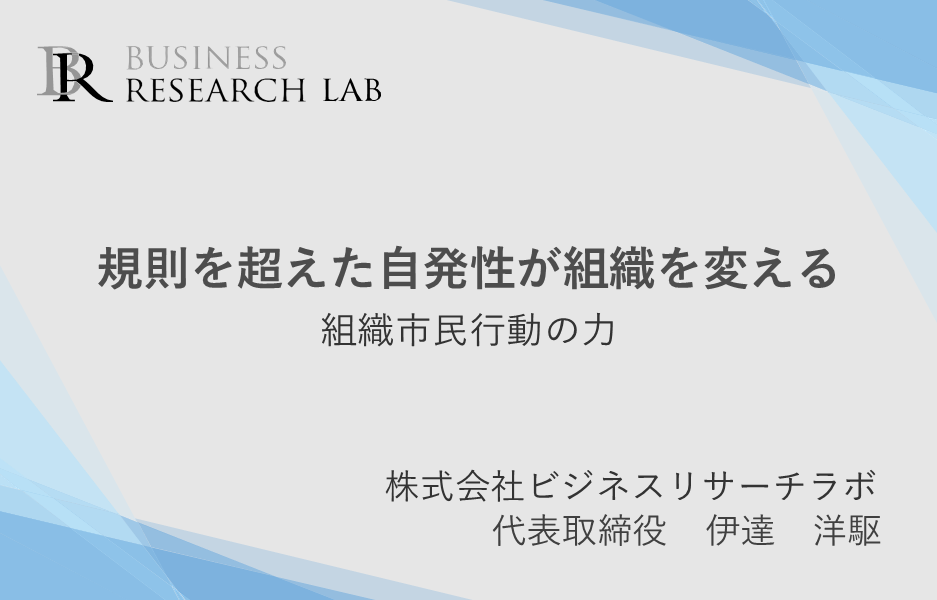2025年9月24日
規則を超えた自発性が組織を変える:組織市民行動の力
職場での人間関係や業務の遂行において、給料のためだけに働く人と、それ以上の貢献をする人がいることに気づいたことはありませんか。自分の仕事が途中でも同僚を助ける人、新入社員に進んで助言をする先輩、会社の規則を率先して守る部下など、職務として明確に定められていないにもかかわらず、自発的に組織のために行動する姿を見かけることがあるでしょう。このような行動は、「組織市民行動」と呼ばれています。
組織市民行動とは、職務として正式に求められていない自発的な行動であり、直接的な報酬を期待せずに行われるものです。それにもかかわらず、このような行動は組織全体の効率性や生産性を高めることが知られています。例えば、同僚を助ける、会社の規則を守る、組織の改善に積極的に関わるといった行動が挙げられます。
組織市民行動は、現代の組織マネジメントにおいて価値ある行動として認識されています。なぜなら、公式の職務記述書には記載されていない自発的な行動こそが、組織の柔軟性を高め、予測不可能な状況への対応力を向上させるからです。しかし、この組織市民行動はどのような要素から構成されているのでしょうか。
本コラムでは、組織市民行動の構成要素について検討していきます。服従・忠誠・参加という三つの次元から捉える見方、利他主義と一般的遵守という二つの側面から理解する視点、さらには複数の次元に分ける意義についての批判的検討、そして最終的に組織市民行動が組織成果にどのように貢献するのかを解説します。
組織市民行動は服従、忠誠、参加の多次元である
組織市民行動の捉え方は研究者によって様々ですが、その見方の一つに「服従」「忠誠」「参加」という三つの次元から構成されるという考え方があります[1]。これらの次元は、組織における市民としての異なる側面を表しています。それぞれの次元について見ていきましょう。
「服従」とは、組織の規則や手続きを守る行動を指します。例えば、時間通りに出勤する、会社の資源を大切に使う、無駄な休憩を取らないといった行動です。この次元は組織のルールに対する責任感や規範意識を反映しており、基本的な組織市民としての義務を果たす側面といえるでしょう。
服従行動は、一見すると当たり前のように思えるかもしれませんが、実際には全ての従業員が同じように規則を遵守しているわけではありません。組織のルールを厳格に守る従業員とそうでない従業員の間には差があります。
次に「忠誠」の次元ですが、忠誠とは、組織の利益を促進するような行動や態度を示し、組織外部に対しても自分の所属する組織を好意的に表現する行動です。例えば、組織を批判する声に対して組織を擁護したり、組織の良い点を外部の人に積極的に伝えたりする行動が挙げられます。
忠誠行動の背景には、組織への強い一体感や愛着があります。組織への忠誠心が高い従業員は、困難な状況においても組織への貢献を続けます。例えば、組織が危機的状況にあっても前向きな態度を維持し、組織の回復に向けて積極的に行動するのです。
三つ目の次元は「参加」です。参加とは、組織の意思決定に関与し、自発的に改善を提案するなど、組織運営に直接貢献する行動を指します。参加はさらに「社会的参加」「提唱的参加」「機能的参加」の三つに細分化されることがあります。
「社会的参加」は、組織内の社会活動に関わることを意味します。例えば、職場のイベントに参加したり、同僚との交流を大切にしたりする行動です。社会的参加が活発な職場ほど、従業員間のコミュニケーションが円滑で、情報共有が促進されます。
「提唱的参加」は、組織内の変革や改善を促進し、新しいアイデアや方法を提案する行動です。例えば、業務プロセスの非効率な部分を指摘し、改善案を出すといった行動が含まれます。提唱的参加は組織の革新や進化に欠かせません。
「機能的参加」は、自発的に職務や業務上の役割を超えて追加の責任を果たす行動です。例えば、自分の専門分野以外の仕事も進んで引き受けたり、チームの目標達成のために余分な労力を注いだりする行動が挙げられます。この行動は、組織の柔軟性を高め、人的資源の有効活用につながります。
これら三つの次元は互いに関連していますが、それぞれ異なる側面から組織市民行動を捉えています。服従は基本的な義務の履行、忠誠は組織への愛着と擁護、参加は積極的な関与と貢献という形で表れます。
組織市民行動は利他主義と一般的遵守に分かれる
組織市民行動を理解するための別の視点として、「利他主義」と「一般的遵守」という二つの次元から捉える考え方があります[2]。この二分法は、組織市民行動の本質をより簡潔に理解するための枠組みを提供してくれます。
「利他主義」とは、具体的な個人を助ける行動を指します。例えば、業務負担の大きい同僚を手伝う、病気で欠席した人の仕事をカバーする、新入社員に業務の進め方を丁寧に教えるといった行動が挙げられます。特定の人物に対する直接的な援助行動であり、個人間の相互支援の関係に基づいています。
利他主義的な組織市民行動が職場でどのように表れるのでしょうか。利他主義的行動は主に従業員の感情状態、特に職務満足度と強く関連しています。職務に満足している従業員ほど、同僚を助ける行動を取ります。ポジティブな感情状態が他者を助けたいという動機につながるという心理学的知見があります。
他方で、「一般的遵守」は組織に対する一般的な忠実性や規範遵守行動を指します。例えば、時間厳守、余計な休憩を取らない、会社の資源を無駄にしないといった行動です。これは特定の個人ではなく、組織全体に対する義務感や責任感に基づく行動と言えます。
一般的遵守行動の予測因子は利他主義とは異なります。職務満足度は一般的遵守に直接的な影響を与えません。代わりに、リーダーの支援性(上司がどの程度部下を支援しているか)や出身地域(農村部出身者の方が遵守行動が多い)、そして社会的承認欲求(他者からの承認や評価を求める傾向)が直接的に影響していました。
利他主義と一般的遵守という二つの次元は異なるメカニズムで生じます。利他主義は主に感情的な要因(職務満足、ポジティブな気分)により促進される一方、一般的遵守は規範への同調や社会的承認欲求によって促進されやすいと考えられます。
研究者たちは、利他主義的行動は対人関係に基づく自発的な行動であり、感情的なつながりや満足感から生まれやすいと考えています。一方、一般的遵守行動は社会規範や期待に応えようとする意識から生まれやすく、社会的な承認や評価と関連していると解釈されます。
例えば、ある従業員が職場で非常に満足感を得ている場合、その感情状態から同僚を自発的に助けるという行動につながりやすいでしょう。一方、社会的な承認を重視する従業員は、組織のルールをしっかりと守り、模範的な社員として認められたいという意識から一般的遵守行動を示すかもしれません。
組織市民行動は複数の次元に分ける意味が薄い
組織市民行動を複数の次元から捉える考え方を見てきましたが、ここで一度立ち止まって考えてみましょう。組織市民行動を複数の次元に分けることには本当に意味があるのでしょうか。この疑問に対する研究も行われています。
ある研究グループは、メタ分析という手法を用いて、組織市民行動の次元の妥当性を検証しました[3]。メタ分析とは、多くの研究結果を統合して分析する手法です。この研究では、過去に行われた数多くの組織市民行動に関する研究を集めて分析することで、次元間の関連性や予測因子との関係を検証しました。
この研究では133の研究から条件に合った37の研究(合計サンプルサイズ16,330人)を抽出し、分析を行いました。分析対象となったのは、利他主義、誠実性、スポーツマンシップ、礼儀正しさ、市民的美徳という5つの次元です。これらはそれぞれ、同僚を助ける行動、規律的に責任をもって行動すること、些細なことで文句を言わない態度、トラブルを未然に防ぐための配慮、組織運営への積極的な関与を表しています。
分析の結果、これらの次元間には非常に高い相関があることが判明しました。特に利他主義、誠実性、礼儀正しさ、市民的美徳は互いに強く関連していました。スポーツマンシップだけがやや他の次元との相関が低めでしたが、それでもかなりの関連性が見られました。
高い相関係数とは何を意味するのでしょうか。それは、ある次元で高い評価を受ける人は、他の次元でも高い評価を受けるということです。例えば、同僚をよく助ける人(利他主義が高い人)は、規則もしっかり守る傾向(誠実性が高い)があり、トラブルを未然に防ぐための配慮(礼儀正しさ)もしっかりしているということです。
さらに、研究者たちは組織市民行動の予測因子との関連性も検討しました。職務満足、組織コミットメント、公正感、リーダー支援、性格特性の誠実性といった代表的な予測因子が、組織市民行動の各次元とどのように関連しているかを調べたのです。
その結果、これらの予測因子は組織市民行動のどの次元ともほぼ同程度の関連性を示すことが分かりました。ある要因(例えば職務満足)が高まると、利他主義も誠実性も礼儀正しさも同じように高まります。各次元によって予測因子との関連性が大きく異なるということはありませんでした。
これらの結果は、組織市民行動を複数の次元に分けることの意義に疑問を投げかけるものです。次元間の相関が高く、予測因子との関連パターンも似ているということは、これらの次元が実質的には同じものを測定している可能性があります。
この結果を踏まえ、研究者たちは組織市民行動を「単一の潜在的な概念」として再定義することを提案しました。表面上は異なる行動に見えても、その根底には共通の心理的基盤があるのではないかという考え方です。この考え方に従えば、組織市民行動は多様な行動の表れ方を持つ単一の概念として理解することができます。
実際、この研究では、組織市民行動を全体として測定した尺度と各次元を別々に測定した尺度の予測力を比較したところ、全体尺度で測定した方が若干ではありますが予測力が高い場合もあることが分かりました。
他方で、研究者たちは別の可能性も示唆しています。それは、組織市民行動を「集合モデル」として捉える考え方です。この見方では、組織市民行動は様々な行動の集合体であり、各行動が組織に与える影響は異なる可能性があります。職務特性や組織環境に応じて各次元の意義が変わる可能性があり、状況に応じた測定が必要になるかもしれません。
例えば、チームワークが重視される職場では利他主義的行動が特に価値を持つかもしれませんし、厳格な規律が求められる職場では一般的遵守行動が特に重要かもしれません。このように、組織の文脈によって各行動の意義が変わる可能性は否定できません。
組織市民行動は職務外でも組織成果を高める
組織市民行動が複数の次元から構成されるか、単一の概念として捉えるべきかという議論はありますが、肝心なのは、このような行動が組織にとってどのような意味を持つのかという点です。組織市民行動は、職務外の自発的な行動でありながら、組織全体の成果にどのように貢献するのでしょうか。
組織市民行動が組織成果に与える影響についても、多くの研究が行われています。ある包括的なレビュー研究では、組織市民行動が組織にもたらす効果として、次のような点が挙げられています[4]。
組織レベルでの効果として、全体的な生産性の向上が挙げられます。組織市民行動が活発な職場では、同僚間の協力や支援が円滑に行われるため、業務の効率性が高まります。例えば、経験豊富な従業員が新入社員を自発的に指導することで、新入社員の習熟度が早く高まり、チーム全体の生産性が向上します。
顧客満足度の向上も組織市民行動の効果です。サービス業において、従業員の組織市民行動は顧客体験に影響を与えます。例えば、自分の担当外の質問にも丁寧に対応する従業員(利他主義的行動)や、顧客の問題を未然に防ごうとする従業員(礼儀正しさ)は、顧客満足度を高めます。
また、組織市民行動は組織の適応力や変化対応能力を高めることも知られています。自発的に組織の問題点を指摘したり、改善案を提案したりする従業員(市民的美徳や提唱的参加)が多い組織では、環境変化に対する適応が素早く行われます。
組織市民行動は従業員の離職率低減にも寄与します。組織市民行動が活発な職場では、従業員同士の関係性が良好で、互いに助け合う文化が形成されるため、職場への帰属意識が高まります。その結果、離職意図が低下し、人材の定着率が向上します。
このように、組織市民行動は様々な形で組織成果に貢献することが実証されています。職務として正式に求められていない自発的な行動が、組織全体の効率性や生産性、顧客満足度、適応力、人材定着率などの向上に寄与しているのです。
脚注
[1] Van Dyne, L., Graham, J. W., and Dienesch, R. M. (1994). Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 37(4), 765-802.
[2] Smith, C. A., Organ, D. W., and Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(4), 653-663.
[3] LePine, J. A., Erez, A., and Johnson, D. E. (2002). The nature and dimensionality of organizational citizenship behavior: A critical review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(1), 52-65.
[4] Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., and Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 513-563.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。