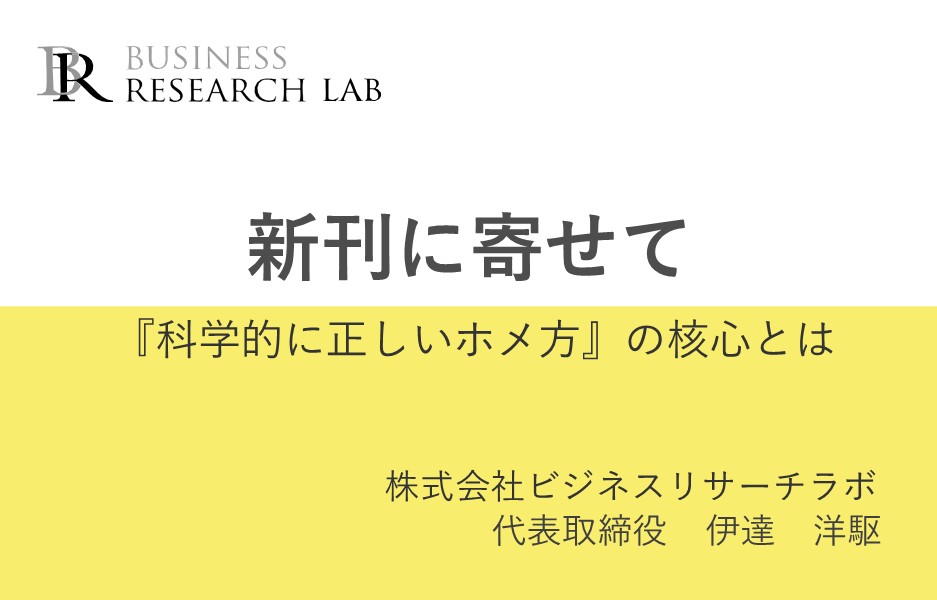2025年9月22日
新刊に寄せて:『科学的に正しいホメ方』の核心とは
『科学的に正しいホメ方:ポジティブ・フィードバックの技術』という本(共著)を上梓しました。この出版を記念し、本書で探求したテーマの核心に触れながら、なぜ今「ホメる」という行為を科学の目で見つめ直す必要があるのか、その一端を伝えるコラムをお届けします。
「良かれと思ってかけた言葉が、かえって相手を萎縮させてしまった」「励ましているつもりでも、相手との距離が縮まらない」。こうした経験は、役職や立場にかかわらず、多くの人が一度は直面する悩みではないでしょうか。組織で働く私たちにとって、円滑な人間関係の構築と、それを通じた相互の成長は尽きることのない課題です。多くのリーダーや先輩は、自らの経験則に基づき、誠実に他者と向き合い、言葉を尽くしていることでしょう。しかし、その熱意が必ずしも相手の意欲向上やチームの活性化に結びつくとは限りません。
ここに、職場でよく見られる一つの場面があります。あるチームメンバーが、顧客への提案資料を非常に優れたデザインで仕上げてきました。その出来栄えに感心したリーダーや先輩は、最大限の賛辞として、こう伝えます。「〇〇さんは本当にセンスがありますね。この分野は安心して任せられます」。この言葉は一見、相手を勇気づけ、自信を持たせるための、最良の声かけに聞こえるかもしれません。
しかし、不思議なことに、この言葉を境に、そのメンバーは以前のような自由な発想を出しにくくなり、資料作成において、失敗を過度に恐れるようになってしまいました。言葉をかけた側のポジティブな意図とは裏腹に、その言葉は相手にとって重いプレッシャーとしてのしかかってしまったのです。
なぜ、このようなすれ違いが起こるのでしょうか。言葉をかける側の熱意や人柄、あるいは善意が不足しているからではありません。これは、効果的なフィードバックに関する体系的な知識、すなわち「技術」が共有されてこなかったという問題なのです。私たちは、コミュニケーション、特に「ホメる」という行為を、個人の感覚や経験則に委ねてきました。しかし、その一言が持つ影響の大きさを考えれば、そろそろ私たちは、この行為を科学の目で捉え直し、誰もが学び、実践できるスキルとして身につけるべき時に来ているのかもしれません。
本コラムでは、このたび上梓した拙著『科学的に正しいホメ方』で提示した知見を基に、この問題について考えていきます。
なぜ善意はすれ違うのか
先ほど挙げたようなコミュニケーションのすれ違いは、決して特殊な例ではありません。その背景には、人間の心理に関する科学的なメカニズムが存在します。本書では、こうしたメカニズムを数多くの研究成果を基に解き明かしていますが、ここではその核心に触れてみましょう。
まず、「〇〇さんは本当にセンスがありますね」という言葉がなぜ意図せぬ副作用を生んだのかを考えてみます。心理学の研究では、このような個人の固定的な資質を対象とするホメ方を「能力ホメ」と呼びます[1]。この種のホメ言葉は、成功の要因をその人の生まれ持った「能力」や「才能」に帰属させます。短期的には相手の自尊心を高めるかもしれませんが、長期的に見ると、一つの罠を仕掛けることになります。
それは、一度失敗を経験した際に、「自分にはセンスがなかったのだ」「能力が足りなかったのだ」という証明だと受け止めてしまいやすくなるというリスクです。成功の理由が不変の「能力」にあると信じていると、失敗は自身の限界を意味するように感じられ、次の挑戦への意欲を削いでしまいます。スタンフォード大学のドゥエックの研究では、知能や才能は固定的であると考える「固定マインドセット」を持つ人は、失敗を恐れて挑戦を避ける傾向が示されています。「能力ホメ」は、意図せずしてこの固定マインドセットを強化してしまう可能性があるのです。
その一方で、本書で推奨しているのが「プロセスホメ」です。これは、「どのような過程を経てそのデザインに至ったのか」「特に工夫した点はどこか」といった、具体的な行動や努力の過程、試行錯誤のプロセスに焦点を当てるアプローチです。このホメ方は、人の能力は固定的ではなく、努力や工夫次第で伸ばせるという「成長マインドセット」を育みます。失敗は能力の欠如の証明ではなく、次なる成長のための学習機会として捉えられるようになり、挑戦を支えます。
コミュニケーションの効果は、言葉の内容だけでなく、それを受け取る相手との関係性の質にも左右されます。ある研究では、メンバー間の信頼関係が十分に築けていない場合、たとえ上司から部下へであっても、ポジティブ・フィードバックが、かえって相手の責任感を低下させるという逆説的な結果が示されています。信頼していない相手からのホメ言葉を、「何か裏があるのではないか」「本心から評価しているわけではない」と表面的に受け止め、その真意を探ろうとすることで余計な心理的負担が生じるためと考えられます。
これらの知見が示すのは、コミュニケーションはただの「気持ち」の問題ではないということです。その効果は、科学的なメカニズムに裏付けられています。だからこそ、個人の経験則だけに頼るのではなく、客観的で再現可能な「技術」としてポジティブ・フィードバックを捉え直し、習得していくアプローチが有効です。
関係性を構築するスキルとしてのポジティブ・フィードバック
『科学的に正しいホメ方』で提示する「ホメる」技術は、ただ相手の行動を短期的に変えたり、その場のモチベーションを高めたりするためだけのものではありません。より高度な目的、すなわち、長期的で良好な「関係性」の構築に応用できるスキルです。
組織論の研究によれば、上司と部下の関係は、多くの場合、「他人」の関係から始まります。この段階では、仕事上の役割に基づいた、いわば取引的なやりとりに留まります。しかし、コミュニケーションの質と量を重ねることで、やがて互いの人となりを理解する「知人」の関係へと進み、最終的には互いの強みを理解し、補完し合える「パートナー」の関係へと深化していくとされます。この関係構築の原則は、上司と部下という縦の関係だけでなく、同僚同士の横の関係においても同様に重要です。互いにポジティブ・フィードバックを重ねることが、チーム全体の結束力を高めます。
このプロセスを加速させ、形式的な関係から相互に貢献し合える協力関係へと深化させる上で、ポジティブ・フィードバックは計画的に活用できる有効な技術となります。日々の業務の中で、相手の貢献や工夫を見つけ出し、それを言語化して伝えるという行為の繰り返しが、少しずつ信頼を築き上げていくのです。例えば、同僚が忙しい中で自分の業務を手伝ってくれた際に、「先ほどはサポートいただき、ありがとうございました。おかげで、無事に締め切りに間に合いました」と伝える。こうした小さな実践の積み重ねが、関係性を深めます。
この関係構築の技術を考える上で、一つの重要な指標となるのが「ホメの黄金比 5:1」です。これは、安定した人間関係を築いているチームやカップルに見られるコミュニケーションの比率で、ポジティブなやりとりが5に対して、ネガティブなやりとりが1の割合で交わされている状態を指します。
この比率は、意図的に信頼関係という「心理的な貯金」を蓄えるための指標と捉えることができます。日常的に称賛や感謝といった肯定的なフィードバックを積み重ねておくことで、信頼関係という「心理的な貯金」が蓄えられます。そして、この貯金が十分にあるからこそ、いざ改善点を指摘したり、厳しいフィードバックを伝えたりしなければならない場面でも、相手はそれを「自分の成長を願ってくれているからこその言葉だ」と受け止めることができるのです。
要するに、効果的なフィードバックとは、その場限りの一言で完結するものではありません。日々のコミュニケーションを通じて、いかに良好な関係性という土台を構築しておくか。その積み重ねがあって初めて、人の成長を促す言葉が機能し始めるのです。本書では、この比率を意識するための具体的な記録方法など、さらに踏み込んだ実践スキルも紹介しています。
文化を醸成するコミュニケーション戦略
個人間で関係性を構築するスキルは、さらに組織全体へと展開することで、その効果を増幅させることができます。それは、組織の「文化」を醸成するという、より高度な技術です。
この点を考える上で興味深いのが、本書でも紹介している「感謝の目撃効果」に関する研究です。ある実験によれば、二者間で感謝の言葉が交わされる場面を目撃した第三者は、その当事者たちに対してより協力的になり、関係を深めたいと感じる傾向が高まることが示されています。
これは、一個人が実践したポジティブなコミュニケーションが、周囲の人々の行動や認識にまで影響を及ぼす、つまり「伝播する」メカニズムを裏付けています。一人のリーダーやメンバーが、ある同僚の貢献に対して誠実な感謝を伝える。その光景が、チーム全体にポジティブな波紋を広げていくのです。例えば、営業担当者が社内チャットで、技術サポート担当者の迅速な対応に感謝を述べたとします。それを見た他の営業担当者も、技術サポートの価値を再認識し、感謝を伝えやすくなるかもしれません。同時に、技術サポート担当者は自分の仕事の貢献度を実感し、モチベーションを高めるでしょう。
この波及効果を意図的に活用するマネジメント技術が、「ホメ言葉の共有」です。例えば、チームミーティングの場で、あるメンバーの優れた行動や工夫を成功事例として取り上げ、チーム全体で共有します。これは、単にそのメンバーを称賛することに留まりません。その行為は、「私たちのチームでは、このような行動や価値観が評価される」というメッセージを組織全体に発信することになります。
個人のファインプレーが言語化され、共有されることで、それは個人の成功体験からチームの「ベストプラクティス」へと昇華します。成功の再現性が高まり、チーム全体のスキルが底上げされるだけでなく、そのプロセスを通じて、組織の知的資産が蓄積されていきます。
このように、個人間の関係構築スキルとして始まったポジティブ・フィードバックは、組織内での共有と波及を通じて、やがては組織全体の「当たり前」、すなわち「文化」を形作っていきます。それは、トップダウンでスローガンを掲げるだけでは実現できない、ボトムアップからの有機的な組織変革のプロセスと言えます。本書の後半では、こうした個人間のスキルが、いかに組織全体の文化へと昇華していくのかを、さらに多くの事例と共に論じています。
「ホメ方」が拓く、人と組織の可能性
本コラムを通じて一貫してお伝えしたかったのは、「ホメる」という行為を、個人の経験や勘といった属人的なアートの世界から、誰もが学び、実践できる「科学的なスキル」へと転換することの重要性です。
デザイン資料を見て「センスがありますね」と感覚的に反応するのではなく、「このデザインに至るまでに、どのようなプロセスを辿ったのですか」と問いかけ、その努力と工夫に光を当てる。それは、相手の成長を促すための、意図を持った技術的な介入です。
このスキルは、部下育成やモチベーション向上といった、目の前の課題に対処するためだけの手法ではありません。チーム内に安心して失敗し、自由に意見を交わせる「心理的安全性」を醸成し、一人ひとりの挑戦する心を育み、ひいては組織全体の学習能力と創造性を高めるためのコミュニケーション技術なのです。この技術を習得することは、自分自身の観察眼や他者への理解を深めることにもつながり、結果的に自身の成長にも寄与します。
私たちが日々交わす何気ない一言一言が、組織の文化を形作り、その未来を方向づけています。しかし、その一言も、技術として意識的に用いることで、人と組織の未来を創造する確かな力へと変わります。このスキルは、上司、部下、同僚といった立場にかかわらず、誰もが実践することで組織をより良く変えていく可能性を秘めています。
本コラムでご紹介したのは、拙著『科学的に正しいホメ方』で展開している内容のほんの一部に過ぎません。本書では、ここで触れた理論的背景に加え、「感謝」の伝え方、フィードバックの「具体化」の方法、相手や状況に応じた「使い分け」など、明日から使えるさらに多くの実践的スキルを解説しています。本コラムで紹介した視点に少しでも共感いただけたなら、ぜひ本書を手に取ってみてください。
脚注
[1] 本コラムで引用している研究の詳細は、拙著『科学的に正しいホメ方:ポジティブ・フィードバックの技術』をご参照ください。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。