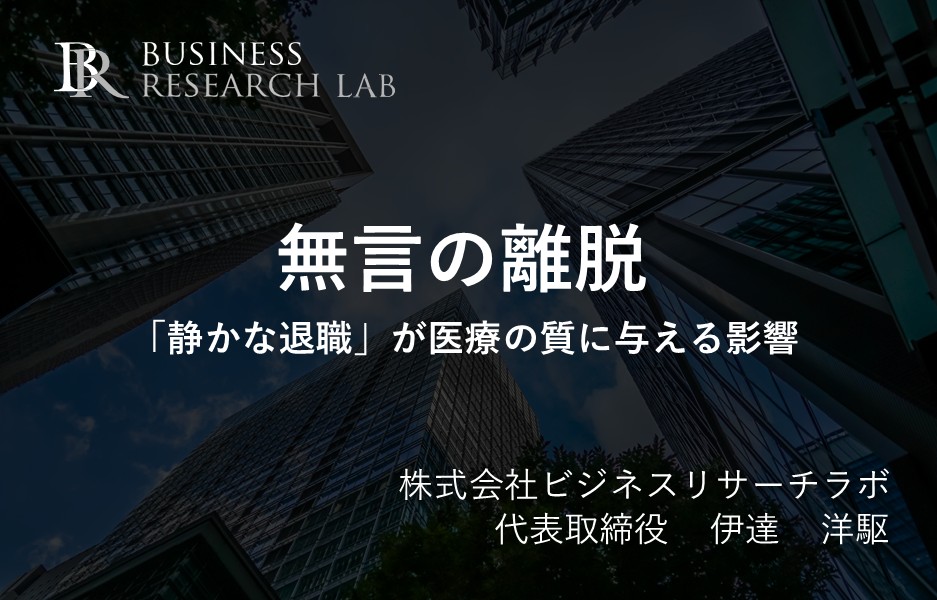2025年9月19日
無言の離脱:「静かな退職」が医療の質に与える影響
私たちの社会を支える医療現場。そこで働く人々の姿勢や心持ちは、患者の安全と健康に関わる問題です。近年、医療従事者、特に看護師の間で「静かな退職」という現象が広がりを見せているという指摘があります。「静かな退職」とは、実際に職場を去るのではなく、必要最低限の仕事だけを行い、それ以上の努力や貢献を意図的に控える行動を指します。心はすでに職場を離れているのに、身体だけがそこに残っている状態と言えるでしょう。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、医療従事者に前例のない負担をかけました。長時間労働、感染リスク、人手不足、精神的プレッシャー。これらの要因が重なり、多くの医療従事者がバーンアウトを経験し、その結果として「静かな退職」という選択をする人が増えています。
この現象は個人の問題ではなく、システム全体に関わる課題でしょう。「静かな退職」が進めば、患者ケアの質が低下し、残された職員の負担が増え、さらなるバーンアウトや離職を招く悪循環に陥る可能性があります。
本コラムでは、医療現場、特に看護師における「静かな退職」の実態と背景について研究知見を基に見ていきます。なぜこの現象が看護師に多いのか、どのような要因が関連しているのか、そして「静かな退職」がもたらす影響とは何か。これらの問いに向き合いながら、医療現場における「静かな退職」について考えていきましょう。
静かな退職は看護師に特に多く起きている
医療の最前線で患者ケアに従事する看護師。その彼ら彼女らに「静かな退職」が見られることが、ギリシャで行われた調査で明らかになりました[1]。調査は2023年6月に実施され、看護師946名、医師390名、その他の医療従事者424名の計1760名を対象としていました。
この調査では、「静かな退職」を測定するために特別に開発された尺度が使用されました。この尺度は「離脱」「主体性の欠如」「動機づけの欠如」という3つの要素で構成されています。仕事から心理的に離れ、自ら進んで行動することなく、仕事への意欲も失っている状態を測定するものです。
調査対象となった医療従事者全体の57.9%が「静かな退職」状態にあることが判明しました。職種別に見ると、看護師の「静かな退職」割合は67.4%と最も高く、医師(53.8%)やその他の医療従事者(40.3%)と比べて統計的に有意に高い結果となりました。
なぜ看護師に「静かな退職」が多いのでしょうか。いくつかの要因が浮かび上がってきます。
看護師は他の医療従事者と比べてバーンアウトの度合いが高く、職務満足度が低いことが分かりました。バーンアウトとは、長期的なストレスによって心身が疲れ果てた状態を指します。患者との直接的な接触時間が長く、感情労働の度合いが高い看護師は、バーンアウトに陥りやすい職種と言えます。
勤務形態も一因となっています。シフト勤務をしている看護師は、規則的な勤務をしている看護師よりも「静かな退職」の割合が高いことが分かりました。シフト勤務は生活リズムを乱し、十分な休息を取ることが難しくなります。心身の疲労が蓄積し、仕事への意欲が低下すると考えられます。
勤務する医療機関の種類も関係していました。民間セクターで勤務経験がある看護師は、公立病院のみで勤務してきた看護師よりも「静かな退職」の傾向が強いことが示されました。民間医療機関では、収益性を重視するあまり、看護師の労働条件が厳しくなる場合があるのかもしれません。
経験年数も見逃せません。臨床経験が少ない若手看護師ほど「静かな退職」を選択する割合が高いという結果が出ました。理想と現実のギャップに直面した若手看護師が、キャリアの早い段階で挫折感を味わっている可能性を示唆しています。
もちろん、COVID-19パンデミックの影響も大きいでしょう。パンデミック期間中、看護師は感染リスクにさらされながら、増加する患者ケアの負担を背負い続けました。このような極限状態での勤務経験が、多くの看護師のメンタルヘルスに深刻な影響を与えたことは想像に難くありません。
静かな退職は看護師の離職意図を高める
「静かな退職」を選択した看護師は、やがて実際の退職へと向かう可能性が高いことが分かってきました。ギリシャで行われた調査は、看護師629名を対象に「静かな退職」と離職意図の関係を調べました[2]。
この調査では、看護師の60.9%が「静かな退職」をしていると分類されました。そして、離職意図が「やや高い」または「非常に高い」と回答した看護師は全体の40.9%に達しました。
「静かな退職」を選択している看護師のうち、49.9%が高い離職意図を持っていました。一方、「静かな退職」を選択していない看護師で高い離職意図を持っていたのはわずか26.8%でした。統計分析の結果、「静かな退職」状態にある看護師は、そうでない看護師と比べて離職意図を持つ可能性が約3倍も高いことが明らかになりました。
「静かな退職」は一時的な状態ではなく、実際の退職へとつながる前段階である可能性が高いのです。言い換えれば、「静かな退職」は離職予備軍を見分けるサインと言えるかもしれません。
どのような看護師が特に離職を考えやすいのでしょうか。調査結果によると、次のような属性を持つ看護師が高い離職意図を示していました。
- 女性の看護師は男性よりも離職を考える傾向にありました。これは、家庭と仕事の両立という課題を抱えやすい女性看護師の現実を反映しているのかもしれません。
- シフト勤務をしている看護師も離職意図が高いことが分かりました。不規則な勤務時間は、プライベートの時間確保や健康維持を難しくし、仕事への不満を高める要因となります。
- 民間医療機関に勤務する看護師も公立病院の看護師よりも離職を考える傾向が強いことが示されました。これは、民間医療機関における労働条件や職場環境に課題があることを示唆しています。
- 職場が「慢性的に人手不足である」と感じている看護師も離職意図が高いことが分かりました。人手不足は一人あたりの業務量増加につながり、看護師の心理的・身体的負担を大きくします。
- 意外かもしれませんが、臨床経験が豊富なベテラン看護師ほど離職意図が高いという結果も出ています。通常、経験年数が増えるほど職場への適応度は高まると考えられますが、この調査では逆の結果となりました。研究者たちは、COVID-19による長期的な負担の蓄積が、ベテラン看護師の心身に特に大きな影響を与えた可能性を指摘しています。
この結果から見えてくるのは、「静かな退職」が一過性の現象ではなく、看護師のキャリア選択に関わる問題であるということです。「静かな退職」を選択した看護師の中には、より良い職場環境を求めて実際に職場を去る準備をしている人もいると考えられます。
懸念されるのは、経験豊富なベテラン看護師の離職意図が高いことです。ベテラン看護師は豊富な知識と経験を持ち、新人看護師の教育や複雑な医療ケースへの対応において重要な役割を担っています。そうした人材が職場を去ることは、看護ケアの質の低下につながる可能性があります。
静かな退職は看護師の道徳的レジリエンスで減少する
医療現場で「静かな退職」に歯止めをかける要素として、「道徳的レジリエンス」という概念に注目してみましょう。道徳的レジリエンスとは、倫理的な困難や葛藤に直面したときに、自分の価値観や信念を保ちながら対処する能力を指します。ギリシャで実施された調査では、この道徳的レジリエンスが看護師の「静かな退職」やバーンアウト、離職意向にどのような作用をもたらすかを調べました[3]。
調査対象となったのは、2年以上の勤務経験を持つ現役看護師957名です。平均年齢は36歳、勤務経験の平均は10.9年でした。調査の結果、看護師の71.9%が「静かな退職」状態にあり、バーンアウトの平均も10点満点中7.29点と高く、51.8%が高い離職意向を持っていることが判明しました。
この調査で使用された道徳的レジリエンスの尺度は、4つの要素から構成されています。「道徳的困難への反応」「個人的誠実性」「関係性の誠実性」「道徳的効力感」です。道徳的困難への反応とは、倫理的な課題に直面したときの対処方法を指します。個人的誠実性は、自分の価値観や信念を守る力です。関係性の誠実性は、他者との関係において誠実さを保つ能力です。そして道徳的効力感は、倫理的な行動をとる自信を表します。
調査の結果、これらの道徳的レジリエンスの要素が高い看護師ほど、「静かな退職」の度合いが低いことが明らかになりました。詳しく見ていきましょう。
「道徳的困難への反応」と「道徳的効力感」が高い看護師は、「離脱」「主体性欠如」「動機付け欠如」といった「静かな退職」の全ての側面が低くなりました。倫理的な課題に適切に対応できる力と、倫理的行動への自信を持つ看護師は、仕事から心理的に離れることなく、自発的に行動し、仕事への意欲も維持できるということです。
「個人的誠実性」が高い看護師は、特に「離脱」の傾向が低いことが示されました。自分の価値観や信念をしっかりと持ち、それを守る力のある看護師は、困難な状況でも仕事から心理的に離れることが少ないようです。
「関係性の誠実性」が高い看護師は、「離脱」と「主体性欠如」が少ないことが分かりました。他者との関係において誠実さを保つ能力は、職場での人間関係を良好に保ち、仕事への関与を維持することにつながるのでしょう。
さらに、「道徳的困難への反応」の高さは、バーンアウトや離職意向の低下にも関連していました。倫理的な課題に適切に対応できる能力を持つことは、心理的な消耗を防ぎ、職場への定着意欲を高めます。
看護師は日々、生命に関わる判断や倫理的な葛藤に直面します。例えば、限られた医療資源をどう配分するか、患者の自律性と安全性のバランスをどうとるかなど、簡単に答えが出ない問題に向き合うことが少なくありません。
道徳的レジリエンスの高い看護師は、こうした葛藤にうまく対処する方法を持っています。自分の価値観や信念を明確に持ち、それに基づいて行動することができます。また、困難な状況でも他者との関係を大切にし、チームとして問題に取り組む姿勢を持っています。そして、「自分は倫理的に正しい行動をとることができる」という自信を持っています。
これらの特性は、看護師が日々の業務の中で意義を見出し、困難に立ち向かう力となります。道徳的レジリエンスの高い看護師は、仕事の困難さや負担を感じても、それに価値を見出し、前向きに取り組むことができるのです。
一方、道徳的レジリエンスが低い看護師は、倫理的な葛藤に直面したとき適切な対処方法を見つけられず、無力感や疲労感を抱きやすくなります。その結果、心理的に仕事から離れ、最低限の業務だけをこなす「静かな退職」の状態に陥りやすいのでしょう。
静かな退職は職務満足度が低い医療者に多い
「静かな退職」という現象は、単純に個人の性格や気質の問題ではなく、職場環境や職務満足度と関係していることが明らかになってきました。トルコで実施された調査は、医療従事者445名(看護師や医師を含む)を対象に、「静かな退職」と職場での幸福感や個人と組織の価値観の一致度との関連を探りました[4]。
この調査では、「静かな退職」を測定する尺度と同時に、「静かな解雇」という概念も測定されました。「静かな解雇」とは、雇用主や管理職が従業員の業務負担を増やしつつも、昇進や賃上げの機会を与えないなど、間接的に離職を促す行為を指します。組織側からの「静かな退職」の誘発とも言えるでしょう。
調査結果によると、医療従事者の「静かな退職」と「静かな解雇」の平均得点は、5点満点中3.28点でした。これは、調査対象となった医療従事者の間で、これらの現象が中程度に広がっていることを示しています。
注目すべき発見は、職務満足度と「静かな退職」の強い関連性でした。職務満足度が低い医療従事者ほど、「静かな退職」の程度が高いという相関が見られました。職務満足度は、仕事内容そのものだけでなく、給与や昇進の機会、同僚や上司との関係、職場の環境や方針など、多岐にわたる要素から構成されます。これらの要素に対する満足度が低いと、仕事へのモチベーションも低下し、「静かな退職」につながりやすいのです。
個人と組織の価値観の一致度も重要でした。自分自身の価値観や目標と、勤務する組織の価値観や目標が合っていると感じる医療従事者ほど、「静かな退職」の度合いが低いことが分かりました。逆に言えば、自分の価値観と組織の価値観にズレを感じる医療従事者は、仕事に対する意義を見出しにくく、「静かな退職」の状態に陥りやすいのでしょう。
この調査では、医療従事者の属性と「静かな退職」との関連も調べられました。その結果、次のような特徴を持つ医療従事者ほど「静かな退職」の度合いが高いことが明らかになりました。
- 婚姻状況と「静かな退職」には関連が見られ、未婚の医療従事者の方が「静かな退職」の程度が高いという結果が出ました。家族からのサポートや家庭での充実感が仕事へのモチベーションにも良い影響を与える可能性が示唆されます。
- 子どもの有無も関連要因でした。子どもがいない医療従事者の方が「静かな退職」の程度が高いという結果が得られました。子育ての経験が何らかの形で仕事への取り組み方に反映されるのかもしれません。
- 居住地域による違いも見られました。トルコの東アナトリアや中央アナトリア地域で働く医療従事者は、他の地域と比べて「静かな退職」の度合いが高いことが分かりました。これらの地域では、医療資源や労働条件に地域格差があることが考えられます。
トルコの医療現場では、医療従事者1人あたりの患者数が多く、給与や労働条件の問題が「静かな退職」の主な要因であると研究者たちは指摘しています。特に看護師は患者との接触時間が長く、厳しい労働条件に置かれていることが多いため、「静かな退職」の危険性が高いと言えるでしょう。
静かな退職は医療現場の質を低下させる
「静かな退職」が広がることで、医療現場はどのような影響を受けるのでしょうか。世界的な医療の課題を分析した研究によれば、「静かな退職」は医療サービスの質を低下させるリスク要因であることが指摘されています[5]。
医療の質は、患者と医療提供者の協力関係や職場環境に強く依存しています。医療従事者が仕事に対する情熱やコミットメントを失えば、患者ケアの質も低下します。「静かな退職」状態の医療従事者は、必要最低限の業務だけをこなし、患者との関わりや、医療チームでの協力、新しい知識や技術の習得に消極的になります。その結果、患者の満足度低下、医療ミスの増加、医療チームの士気低下など、様々な問題が生じる可能性があります。
特に看護師の「静かな退職」は、患者ケアに直接的な影響を及ぼします。看護師は患者の最も身近にいる医療従事者であり、その態度や行動は患者の回復や満足度に関わります。「静かな退職」状態の看護師は、患者の些細な変化に気づきにくくなったり、患者の心理的ニーズに十分に応えられなくなったりする恐れがあります。
「静かな退職」は職場全体の雰囲気にも影響します。ある看護師が「静かな退職」の状態になると、その消極的な姿勢は同僚にも伝染しやすく、職場全体のモチベーション低下を招きます。「静かな退職」状態にある看護師の仕事を他の看護師がカバーしなければならず、それが新たな負担となって、さらなるバーンアウトや「静かな退職」を生み出すという悪循環に陥ります。
近年、医療現場では若い世代、特にZ世代(1995年以降に生まれた世代)の割合が増加しています。研究によれば、このZ世代は従来の世代と比べて、働き方に対する価値観が異なる傾向があります。彼ら彼女らは柔軟性、評価されること、自律性、ワークライフバランスを求め、伝統的な「仕事中心」の価値観に疑問を投げかけることがあります。
この世代間の価値観の違いが、「静かな退職」の広がりに関連している可能性もあります。若い世代の医療従事者が増える中で、従来の医療現場の厳しい労働環境や階層的な組織文化に不満を感じ、「静かな退職」を選択する人が増えているのかもしれません。
COVID-19パンデミックは、こうした問題をさらに悪化させました。感染リスク、劣悪な労働環境、経済的困難、不公平な業務負担、職場での暴力の増加など、パンデミック下で医療従事者は多くの困難に直面しました。その結果、不安、抑うつ、バーンアウトが増加し、「静かな退職」や実際の離職につながっているのです。
脚注
[1] Galanis, P., Katsiroumpa, A., Vraka, I., Siskou, O., Konstantakopoulou, O., Katsoulas, T., Moisoglou, I., Gallos, P., and Kaitelidou, D. (2024). Nurses quietly quit their job more often than other healthcare workers: An alarming issue for healthcare services. International Nursing Review, 71(4), 850-859.
[2] Galanis, P., Moisoglou, I., Malliarou, M., Papathanasiou, I. V., Katsiroumpa, A., Vraka, I., Siskou, O., Konstantakopoulou, O., and Kaitelidou, D. (2024). Quiet quitting among nurses increases their turnover intention: Evidence from Greece in the post-COVID-19 era. Healthcare, 12(1), 79.
[3] Galanis, P., Moisoglou, I., Katsiroumpa, A., Vraka, I., Siskou, O., Konstantakopoulou, O., and Kaitelidou, D. (2024). Moral resilience reduces levels of quiet quitting, job burnout, and turnover intention among nurses: Evidence in the post COVID-19 era. Nursing Reports, 14(1), 254-266.
[4] Karadas, A., and Cevik, C. (2025). Psychometric analysis of the quiet quitting and quiet firing scale among Turkish healthcare professionals. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 31(3), e14136.
[5] Boy, Y., and Surmeli, M. (2023). Quiet quitting: A significant risk for global healthcare. Journal of Global Health, 13, 03014.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。