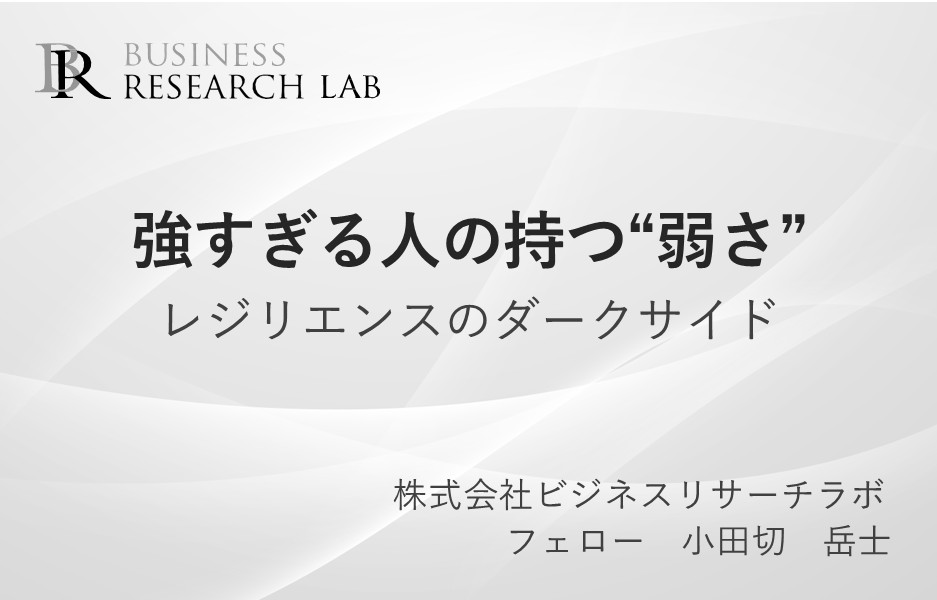2025年9月18日
強すぎる人の持つ“弱さ”:レジリエンスのダークサイド
私たちが生きる現代社会は、「逆境の時代」と言えます。地震や豪雨といった自然災害、未知のウイルスによるパンデミック、物価高騰や経済の不安定さ。さらに、働き方改革や教育制度の変化、AI・グローバル化による職業構造の変化など、私たちの暮らしには常に新しいストレスが静かに積み重なっています。こうした不確実性が日常の一部となるなかで、個人の心にも、これまで以上に大きな負荷がかかっているといえます。
このような時代背景のなかで注目されているのが「レジリエンス(Resilience)」です。直訳すると「弾力」や「回復力」などと表現されますが、心理学の分野では「困難に直面しても立ち直る力」とされ、ビジネスや教育・医療・福祉などの分野で幅広く導入されています。企業の研修やメンタルヘルス対策などでも、「折れない心」「何度でも立ち上がる力」として、レジリエンスを育む取り組みが広がってきました。
たしかに、予測困難な社会を生きるうえで、レジリエンスは非常に重要な力です。しかしその一方で、「強くあらねばならない」「前を向かなくてはならない」といった意識が、かえって人を追い込んでしまうことはないでしょうか。
本コラムでは、レジリエンスの持つ“光と影”に目を向けながら、現代人にとって本当に必要な「強さ」とは何かを、研究知見をベースに考えていきます。
レジリエンスとはなにか
レジリエンスは、本来は物理学や生態学の分野で用いられていた言葉で、外からの力を受けても変形せず、元の形に戻る弾性や、環境の変化に対する回復力を意味していました。これが心理学に取り入れられるようになり、ストレスや逆境、トラウマ、脅威、重大な困難に直面したときに、それを乗り越えて適応する能力[1]として広く使われるようになっています。
レジリエンスが高い人は、大きな失敗や人間関係のトラブル、病気などの出来事に直面したときに、気持ちを立て直し、新たな目標に向かって進んでいくことができます。
レジリエンスを測定するある尺度に基づくと、レジリエンスは以下の要素から構成されていると考えられています[2]。
- 能力・高い基準・粘り強さ:困難に直面しても、自分の能力を信じ、高い目標を持ち、粘り強く取り組む力を表します。
- 直感への信頼・否定的感情への耐性・ストレスからの学習:自分の直感を信じ、否定的な感情に耐え、ストレスを成長の機会と捉える力を表します。
- 変化の肯定的受容・安全な人間関係:変化を前向きに受け入れたり、信頼できる人間関係を築いたりする力を表します。
- コントロール感:自分の人生や状況に対して主導権を持ち、コントロールできると感じる力を表します。
- スピリチュアリティ:何かに対する信仰やスピリチュアルな価値観が、困難を乗り越える支えとなっている状態を表します。
また、レジリエンスが高いことは、以下のような様々なポジティブな効果にもつながります。
- 身体疾患の予防:複数の研究において、レジリエンスが高いほど、様々な身体疾患のリスクになるとされるコルチゾール量が減少することが報告されています[3]。
- メンタルヘルスの維持:複数の研究を統合して再分析した結果、レジリエンスが高いほど、ネガティブな感情・不安・うつ症状が減少することが示されています[4]。
- 職務満足度やパフォーマンスの向上:レジリエンスが高いことは、仕事に対しての満足感やパフォーマンスの向上にも寄与しうることが複数の研究で指摘されています[5]。
以上のような理由から、レジリエンスは現代社会で「理想的な強さ」として注目されることが多くなっています。ビジネス、教育、医療など複数の領域で、レジリエンス研修や教育プログラムが導入されているのも、その現れといえるでしょう。
レジリエンスのダークサイド
「レジリエンスを育てよう」―そんなメッセージがあふれる現代社会において、私たちは知らず知らずのうちに、「強くなければならない」という見えない圧力を感じているかもしれません。困難に打ち勝つ力は確かに重要です。しかし、この“強さ”だけに注目すると、望ましくない現象が起きる可能性があります。
レジリエンスと関連する性格が悪影響を及ぼす
まず重要な指摘は、「レジリエンスの高さと関連している特定の性格傾向が、悪影響をもたらしうる」ということです[6]。
たとえば、自信過剰な人は、自分の能力を強く信じており、他者から否定的な評価を受けてもストレスを感じにくい、つまりレジリエンスが高いことがわかっています。しかし同時に、「自分はすごい人間だ」「他人の言うことは受け入れない」という考えや態度は、他者との関係性を悪くしてしまう可能性があるのです。
また、現実逃避をするために、自分の能力や環境を不自然に肯定的に捉えている場合もあります。このような人は、短期的にはレジリエンスが高いといえますが、長期的には疲弊したり、周囲との関係性に歪みが生じ、社会的に孤立するリスクが高まったりすることも指摘されています。
強すぎる心は「偽りの希望」を見出す
過剰なレジリエンスそのものの悪影響について言及しているのが、「偽りの希望症候群(False Hope Syndrome)」という概念です。本来この概念は、ダイエットや禁煙などの自己改善行動における失敗パターンを分析したものですが、強すぎるレジリエンス問題にも深く関連しています。
この症候群は、以下のようなサイクルで進行するとされます[7]。
- 非現実的な期待を持って行動を始める(「きっとできるはず」と信じて始める)
- 結果が出ないことに落胆し、自己否定に陥る
- 「もっと頑張れば…」と再挑戦するが、やはり望む変化が得られない
- 失敗と落胆が繰り返され、心身のエネルギーが消耗していく
設定された目標や提示された課題の解決が、明らかに非現実的なのにもかかわらず、「どんなにつらくても前向きでいなければ」「強い自分を証明したい」と信じ続けるあまり、自分の本当の疲れや痛みに気づけなくなる―これが、レジリエンスが高すぎることによって引き起こされる現象です。
偽りの希望症候群に陥ることで、以下のような影響があります。
- 自己評価の低下と自己否定:期待していた変化が実現できなかったとき、「自分は意志が弱い」「だめな人間だ」と自分自身を責めたり、無力感が増大したりします。これにより、自尊心が損なわれるのです。
- 感情の悪化と絶望感:高い期待を抱いて始めた自己変革が失敗すると、落胆、フラストレーション、絶望感が強まります。これがさらなる失敗を呼び込み、悪循環を生みます。
- コントロール感の喪失:最初は「自分で変えられる」と感じるものの、挫折を繰り返すと、「自分にはコントロールできない」と信じ込んでしまう危険があります。
- 自己制御リソースの枯渇:自己変革のために努力(自制・意志力)を使いすぎると、その後の制御ができなくなる結果、さらに失敗しやすくなります。
- ポジティブ幻想の強化と現実逃避:過去の失敗から学ばず、成功体験のみを過大評価してしまい、現実的でない次の変革計画に飛びつきやすくなります。現実を正しく認識できないことで、変革成功の確率がさらに下がってしまいます。
これらはいずれも、レジリエンスそのものが悪いのではなく、レジリエンスの「強さ」を誇張しすぎてしまった結果と言えるかもしれません。つまり、レジリエンスは本来、私たちを守る力のはずなのに、それが過剰になると、自分を守れない原因にもなってしまう。ここに、「レジリエンスの影」があります。
だからこそ私たちは、「強くあること」以外の面も、レジリエンスの一部であると捉える必要があるのです。
レジリエンスとの向き合い方
それでは、私たちはどうすれば「強すぎるレジリエンス問題」に陥らず、持続可能な心の回復力を育むことができるのでしょうか。ポイントは大きく以下の2つです。
「すぐに元に戻る力」ではなく「じっくり相対する力」とみなす
レジリエンスという言葉は、その語源からもわかるように、「元の状態に戻る」ということが強調されています。ですが、例えば何らかのストレスを受けて休養が必要になったとき、ただ単に元の状態に戻るだけでは、また同じようなストレスを受けたときに対処できない可能性があります。また、元に戻るという結果だけではなく、その過程で本人が経験する感情や回復の体験を重視すべきではないか、という指摘もあります[8]。
つまり、レジリエンスを「すぐに元に戻ることのできる強さ」という結果にフォーカスしたものではなく、「困難にじっくり向き合い、そこに意味を見出そうとする力」と過程に焦点化して捉え直す必要があるのではないでしょうか。
レジリエンスは一個人のみで発揮するものではない
つい忘れてしまいがちですが、レジリエンスの構成要素を振り返ると、そこには「安心できる人間関係」が含まれています。これはつまり、レジリエンスそのものが、一個人の独力で発揮するものではないことを表しています。時には他者に助けを求めることも、レジリエンスの重要な一側面といえるのです。困難な状況にあって、すべてを一人で抱え込もうとすることが「強さ」だと誤解されがちですが、実際には、自分が今どんな状態にあるのかを見つめ、必要な支援を受け入れることこそが、持続可能なレジリエンスを支える土台となります。
「助けを求めること」は、単なる依存ではなく、自己理解と自己開示に基づく成熟した行動です。他者の視点を取り入れることで、自分では気づけなかった視野の狭さや思い込みに気づくこともありますし、感情の整理がついたり、状況を俯瞰して見直すきっかけになったりもします。
「レジリエンスは一人で発揮するものではない」という意識は、周囲の人々にとっても重要です。例えば、チーム内にハイパフォーマーがいると、その人に任せる仕事の量や難易度がどうしても過剰になりがちです。ただ、ハイパフォーマーはレジリエンスが高い方も多いので、なかなか疲労や不満などを表に出さないので、組織や上司としても放任してしまいがちです。
しかし、今回見てきた知見から考えると、ハイパフォーマーに対しても、周囲からの物理的・感情的な支援や、帰属意識を感じられるサポートを提供すべきといえます。
終わりに
本コラムでは、現代社会において注目される「レジリエンス」という力について、その過剰さがもたらす影の部分にも目を向けました。困難に立ち向かい、何度でも立ち上がる力はたしかに重要ですが、「強さ」だけを美徳として追い求めることは、時に自分自身を追い詰め、傷つけることにもつながります。
本当に必要なのは、ただ速やかに回復することではなく、困難と丁寧に向き合いながら、時に立ち止まり、時に助けを求めながら、自分のペースで再び歩み始める力です。そして、その力は決して一人で完結するものではなく、周囲とのつながりや信頼の中で育まれていくものでもあります。
「レジリエンス=強さ」という一面的な理解にとらわれず、しなやかで、温かみのある“人間らしい強さ”としてのレジリエンスを、今一度捉え直していくことが、これからの時代を生きる私たちにとって、より大切になってくるのではないでしょうか。
脚注
[1] Southwick, S. M., Pietrzak, R. H., Tsai, J., Krystal, J. H., & Charney, D. (2015). Resilience: an update. PTSD research Quarterly, 25(4), 1-10.
[2] Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 76–82. https://doi.org/10.1002/da.10113
[3] Aizpurua‐Perez, I., Arregi, A., Labaka, A., Martinez‐Villar, A., & Perez‐Tejada, J. (2023). Psychological resilience and cortisol levels in adults: A systematic review. American Journal of Human Biology, 35(12), e23954.
[4] Hu, T., Zhang, D., & Wang, J. (2015). A meta-analysis of the trait resilience and mental health. Personality and Individual differences, 76, 18-27.
[5] Bardoel, E. A., Pettit, T. M., De Cieri, H., & McMillan, L. (2014). Employee resilience: An emerging challenge for HRM. Asia Pacific Journal of Human Resources, 52(3), 279-297.
[6] Treglown, L., Palaiou, K., Zarola, A., & Furnham, A. (2016). The dark side of resilience and burnout: a moderation-mediation model. PloS one, 11(6), e0156279.
[7] Polivy, J., & Herman, C. P. (2000). The false-hope syndrome: Unfulfilled expectations of self-change. Current Directions in Psychological Science, 9(4), 128-131.
[8] Ferrarello, S. (2021). The normative space of resilience. Jahr: Europski časopis za bioetiku, 12(2), 267-284. https://doi.org/10.21860/j.12.2.4
執筆者
 小田切 岳士 株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー
小田切 岳士 株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー
同志社大学心理学部卒業、京都文教大学大学院臨床心理学研究科博士課程(前期)修了。修士(臨床心理学)。公認心理師。働く個人を対象にカウンセラーとしてのキャリアをスタート。その後、企業人事として制度・施策の設計・運用などに携わる。現在は主な対象を企業や組織とし、臨床心理学や産業・組織心理学の知見をベースに経営学の観点を加えた「個人が健康に働き組織が活性化する」ための実践を行っている。特に、改正労働安全衛生法による「ストレスチェック」の集団分析結果に基づく職場環境改善コンサルティングや、職場活性化ワークショップの企画・ファシリテーションなどを多数実施している。