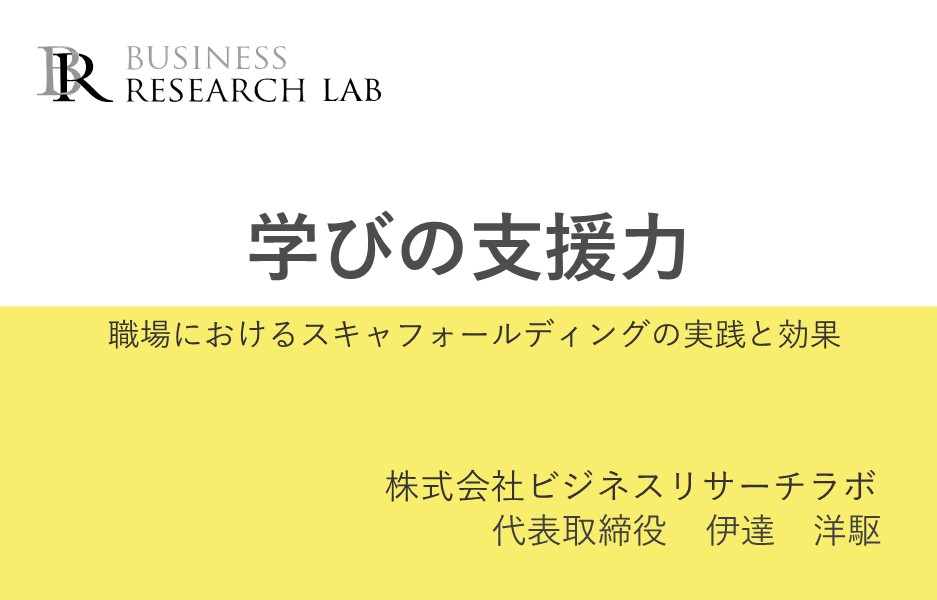2025年9月18日
学びの支援力:職場におけるスキャフォールディングの実践と効果
私たちの働く環境は、速いペースで変化しています。デジタル技術の発展や世界的な競争の激化により、職場で継続的に学び、適応する能力は、個人にとっても組織にとっても欠かせないものとなりました。こうした状況の中で注目されているのが「スキャフォールディング」という概念です。
スキャフォールディングとは、直訳すると「足場かけ」を意味し、元々は教育心理学の分野でヴィゴツキーやブルーナーらによって提唱・発展された概念です。学習者が新しい知識やスキルを獲得する過程で、一時的な支援や足場を提供し、徐々にその支援を減らしていくことで、最終的には自立した学習者へと成長を促します。
この概念は近年、学校教育だけでなく職場学習の領域にも応用され始めています。職場におけるスキャフォールディングは、同僚、上司、テクノロジーによって提供される多様な形態の支援を通じて、従業員の自己調整学習を促進し、組織全体の知識創造や革新を支えるものです。
本コラムでは、職場におけるスキャフォールディングの役割と可能性について、研究成果をもとに探っていきます。テクノロジーを活用したスキャフォールディングが自己調整学習に与える影響、社会的相互作用の価値、グローバルな知識移転における応用、そして医療現場でのリーン導入事例など、多角的な視点から職場でのスキャフォールディングの実態に迫ります。
職場のスキャフォールディングは社会的要素が重要
知識主導型社会において、職場での継続的な学習は不可欠です。自己調整学習は、学習者が主体的に学習目標を設定し、学習プロセスをコントロールし、自己評価する能力を指します。この能力は職場環境では特に価値がありますが、多くの従業員はこれを自然に身につけているわけではありません。ここで重要となるのが、職場におけるスキャフォールディング(足場かけ)です。
ヨーロッパの大手自動車メーカーと教員の職能団体という2つの組織を対象とした調査では、テクノロジーを活用したスキャフォールディングが職場での自己調整学習にどのような影響を与えるかが検証されました[1]。この研究では、「Learn-B」という学習支援ソフトウェアを用いて、53名の従業員が2か月間にわたり学習活動を行いました。
自己調整学習は、大きく分けて「計画」「遂行」「評価・内省」という3つのプロセスから成り立っています。「計画」のフェーズでは、学習目標の設定や学習計画の立案が行われます。「遂行」のフェーズでは、課題に取り組み、適切な学習戦略を用います。そして「評価・内省」のフェーズでは、学習の成果を振り返り、次の学習に生かします。
Learn-B環境には、これらの自己調整学習を支援するための様々な技術的介入が組み込まれていました。例えば、利用情報の提供、ソーシャルウェーブ(同僚の活動や学習リソースの共有を可視化するもの)、進捗メーター(自分と他者の進捗状況を比較できるもの)、学習目標の推奨機能、組織が推奨する学習経路の提案、知識共有プロファイルなどです。
調査では、アンケートとソフトウェア利用のログデータ(トレースデータ)という2種類のデータを収集しました。アンケートでは参加者が各介入をどのように評価しているかを測定し、トレースデータでは実際の利用行動を分析しました。
この2つのデータの間には食い違いがありました。アンケートでは、利用情報の提供、システム推奨能力、システム推奨学習パスという組織的な要素が「計画」フェーズで特に有効だと評価されていました。一方、社会的要素(ソーシャルウェーブやユーザー推奨目標)は、参加者自身の認識では補助的な要素に過ぎないと位置づけられていました。
しかし、実際の行動を示すトレースデータを分析したところ、「ソーシャルウェーブ」という社会的な要素が、自己調整学習の全てのプロセス(計画・遂行・評価)と最も強く関連していることが明らかになりました。参加者は自分でそれほど重要だと認識していなくても、実際には同僚の活動や共有情報に影響を受けて学習を進めていたのです。
この結果は、職場での学習において社会的相互作用の力を裏付けるものです。人は他者との関わりの中で学ぶものなのです。同僚が何を学んでいるか、どのような情報を共有しているかを知ることが、自分自身の学習に強い動機づけをもたらします。
職場のスキャフォールディングを考える上で、価値の高い発見は、私たちが思っている以上に社会的な要素が学習に影響を与えているという点です。これは単に「他者から学ぶ」という意味ではなく、他者の存在や活動そのものが私たちの学習行動を形作っているということを意味します。
職場のスキャフォールディングは社会的介入が効果的
職場での自己調整学習において社会的要素が重要であることを見てきました。さらに詳しく、どのような技術的スキャフォールディング介入が職場の自己調整学習に効果的なのかを掘り下げていきます。
ここで紹介する研究は、先ほどと同じく、ヨーロッパの大手自動車メーカーと教員の職能団体を対象とした調査ですが、分析手法をさらに精緻化し、マイクロレベルの学習プロセスに焦点を当てています[2]。
職場での学習は、フォーマルな教育環境とは異なります。学校教育では明確なカリキュラムや評価基準があり、教師が学習を導きます。一方、職場学習は多くの場合、非公式でありながらも自己主導的です。しかし、だからこそ適切な支援や構造が必要とされます。この研究では、そうした支援の中でも特にどの技術的介入が効果的かを明らかにすることを目指しました。
研究者たちは、自己調整学習をマクロレベルの3つのプロセス(計画、遂行、評価・内省)に分類し、さらにそれぞれをより細かなマイクロレベルのプロセスに分解して分析しました。例えば、「計画」には目標設定や個人的な学習計画の作成といったマイクロプロセスが含まれます。
この研究の特徴的な点は、「遷移グラフ」という手法を用いて、参加者の行動を時系列で分析したことです。遷移グラフとは、ある行動から次の行動へどのように移り変わっていくかを視覚的に表現するものです。また、重回帰分析も用いて、各介入がマイクロレベルのSRLプロセスにどの程度影響を及ぼしているかを測定しました。
分析の結果、「ソーシャルウェーブ」という介入が中心的であり、すべてのマイクロレベルの自己調整学習プロセスにおいて高い影響力を示していることが判明しました。ソーシャルウェーブとは、同僚の学習活動や共有されたリソースを可視化するツールです。学習者は組織内の他のメンバーが何を学んでいるのか、どのようなリソースを活用しているのかを知ることができます。
「システム推奨の学習経路・活動・資産」も、特に目標設定や個人計画の作成といった「計画」プロセスにおいて高い効果を示しました。この機能は、組織が推奨する学習コンテンツや活動を提示するものです。
参加者の職務経験やコンピューター技能の差異を考慮した上でも、ソーシャルウェーブの利用頻度が高い参加者は、自己調整学習プロセスの遂行頻度が高いことが見えてきました。社会的介入の効果が個人の属性を超えて一般化できることを示唆しています。
人は本質的に社会的な存在であり、他者との関わりの中で学び、成長していくものです。テクノロジーによるスキャフォールディングは、そうした人間の社会的な学習プロセスを支援し、促進する役割を担っているのです。
スキャフォールディングで海外知識を組織に定着させる
グローバル化が進むビジネス環境において、海外で得た知識や経験を自国の組織に持ち帰り、効果的に活用することは、競争優位を確立するための鍵となります。しかし、情報を伝えるだけで、組織内で知識移転が起こるとは限りません。文化的背景や組織風土の違いにより、海外の知識をそのまま取り入れることが難しい場合も少なくありません。国際経験を持つ帰国幹部がスキャフォールディング(足場かけ)を通じて海外の知識を組織に定着させる過程を探ります。
韓国の金融企業に勤務する国際帰国幹部45名を対象とした2年間にわたる質的研究では、彼ら彼女らがどのように組織内で「バウンダリー・スパナー」として機能し、海外の知識を組織に根付かせたのかが調査されました[3]。バウンダリー・スパナーとは、異なる知識や文化の領域間を仲介し、双方を結びつける役割を担う人物を指します。
この研究では、帰国幹部がバウンダリー・スパナーとして活動するための条件と、彼らが実践するスキャフォールディング活動の両面から分析が行われました。
まず、バウンダリー・スパナーとして機能するためには、3つの条件が必要であることが明らかになりました。第一に「能力」、つまり外国の実践知識や人的ネットワーク、そして組織の長期的ビジョンを持っていることです。第二に「持続的意欲」、すなわち長期間にわたり外国の知識を組織に導入し続ける強い意欲です。そして第三に「機会」、組織内で実際に境界スパニング活動を行うためのポジションや組織文化の受容性が求められます。
これらの条件を備えた帰国幹部たちは、3種類のスキャフォールディング活動を通じて海外の知識を組織に定着させていました。
1つ目は「認知的スキャフォールディング」です。これは組織のメンバーが外国の知識や実践を理解できるよう、言語や文化的背景の解説、概念枠組みの構築、メンタリングを通じて支援する活動です。例えば、ある帰国幹部は、海外で学んだ金融モデルの基本概念を組織のメンバーが理解できるよう、現地の文化的背景や導入経緯も含めて説明しました。専門用語の翻訳や解説も重要な役割となりました。
2つ目は「関係的スキャフォールディング」です。これは組織のメンバーが外国の企業や専門家と直接関係を構築できるよう支援する活動です。例えば、海外視察の企画・引率、外国人パートナーの招聘、直接的な関係構築のサポートなどが含まれます。ある帰国幹部は、組織のメンバーを海外に連れていき、現地のビジネス実践を直接体験させることで、文書だけでは伝わらない暗黙知の共有を促進しました。
3つ目は「物理的スキャフォールディング」です。これは学習資料やマニュアルの提供、学習空間の設置、概念実証の提示など、物理的または組織的なリソースを提供する活動です。例えば、海外で使用されていた業務マニュアルを自社向けにカスタマイズしたり、新しい業務プロセスを試験的に導入して効果を実証したりする取り組みが行われました。
これらのスキャフォールディングの特徴は、段階的かつ反復的なプロセスとして展開されることです。最初は帰国幹部が多くの支援を提供しますが、組織メンバーの理解が深まるにつれて徐々に支援を減らし、最終的にはメンバー自身が海外の知識を活用し、さらには発展させられるようになることを目指します。
この過程はヴィゴツキーの「最近接発達領域」の概念に基づいています。最近接発達領域とは、学習者が現在持っている能力と、支援があれば到達できる潜在的な能力の間の領域を指します。スキャフォールディングはこの領域をターゲットとし、学習者が少しずつ自分の能力を拡張していくことを可能にします。
病院のリーン導入はスキャフォールディングで実践化する
医療機関は高度に専門化された複雑な組織であり、変革の導入は容易ではありません。とりわけ、製造業に起源を持つリーンマネジメントのような概念を病院に導入する際には、様々な抵抗や課題が生じます。ノルウェーの病院におけるリーン思想導入の事例から、スキャフォールディングが実践的な変革をどのように支援するかを検討してみましょう。
リーンマネジメントとは、元々トヨタ生産方式を起源とする経営手法で、顧客価値の特定、プロセスマッピング、価値創出、無駄の排除、継続的な改善という原則に基づいています。医療現場では、患者の待ち時間の短縮や医療プロセスの効率化、医療ミスの削減などを目指して導入されることが増えていますが、医療従事者からの抵抗に直面することも少なくありません。
ノルウェーの病院を対象とした研究では、人材開発部門がどのようにスキャフォールディングを通じてリーン導入を支援したかが調査されました[4]。データは、医師、看護師、マネージャー、HR担当者など合計10名のインタビュー、リーン活動の観察、関連文書の分析を通じて収集されました。
研究者たちは、リーン導入プロセスを3つのフェーズに分類しています。
第1フェーズは「認知的スキャフォールディング」です。このフェーズでは、人材開発部門がリーンの基本的知識を医療従事者に伝え、共通の理解を促進することに焦点を当てていました。しかし、知識を伝えるだけではなく、医療現場の文脈に合わせた言葉選びや説明方法の工夫が重要でした。例えば、医師の抵抗感を軽減するために、「コスト削減」といった言葉を避け、代わりに「患者の安全性や治療の質向上」を強調することで、医療従事者の価値観に沿った形でリーンの概念を紹介する必要があります。
この段階では、医療従事者がリーンを経営用語やコスト削減の手段ではなく、患者ケアを向上させるための方法として理解することが求められます。人材開発担当者は、医療従事者の既存の知識体系や価値観を尊重しながら、新しい概念をどう位置づけるかを慎重に考慮していました。
第2フェーズは「ピアツーピア・スキャフォールディング」です。このフェーズでは、抽象的な概念を具体的な体験へと転換することが目指されました。興味深い試みの一つが、「紙飛行機作成活動」です。この活動では、参加者はまず従来の方法で紙飛行機を作ります。次に、リーンの原則(ムダの排除、フロー創出、標準化など)を適用して再度作成します。そして、両者のプロセスと結果を比較することで、リーンがもたらす改善を実感するのです。
この活動の特徴は、参加者に意図的に「失敗」を体験させた後、リーンを適用して成功を経験させることで、その有効性を実感させる点にあります。チームで活動を行うことで、同僚同士の対話や知識共有が促進され、集団的な学習が起こりました。人は概念的な説明だけでなく、身体的・感覚的な経験を通じて深く学ぶものです。
第3フェーズは「スキャフォールディングの段階的削減(フェーディング)」です。このフェーズでは、人材開発部門が徐々に支援を削減し、責任を病院の現場スタッフに移譲していきました。当初は人材開発部門が主導していたリーン活動も、少しずつ医療従事者自身が計画・実行するようになります。これによって、リーンが現場のものとして定着していくのです。
しかし、このフェーズは必ずしも順調に進んだわけではありません。一部のスタッフは、人材開発部門のサポート撤退が早すぎると感じ、支援の継続を望む声もありました。学習者によって理解度や自信の獲得速度は異なるため、支援の削減タイミングを見極めることの難しさがここに表れています。それでも、支援の削減は学習者の自立に不可欠です。初めは戸惑いや不安を感じても、自ら考え実践することを通じて、本当の意味でリーン思考を身につけることができるからです。
脚注
[1] Siadaty, M., Gasevic, D., and Hatala, M. (2016). Associations between technological scaffolding and micro-level processes of self-regulated learning: A workplace study. Computers in Human Behavior, 55, 1007-1019.
[2] Siadaty, M., Gasevic, D., and Hatala, M. (2016). Measuring the impact of technological scaffolding interventions on micro-level processes of self-regulated workplace learning. Computers in Human Behavior, 59, 469-482.
[3] Roberts, M. J. D., and Beamish, P. (2017). The scaffolding activities of international returnee executives: A learning-based perspective of global boundary spanning. Journal of Management Studies, 54(4), 511-539.
[4] Haukasen, O. A., and Hermanrud, I. (2023). Creating a lean mind-set: Change of practice towards early treatment. Management Learning, 54(5), 777-801.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。