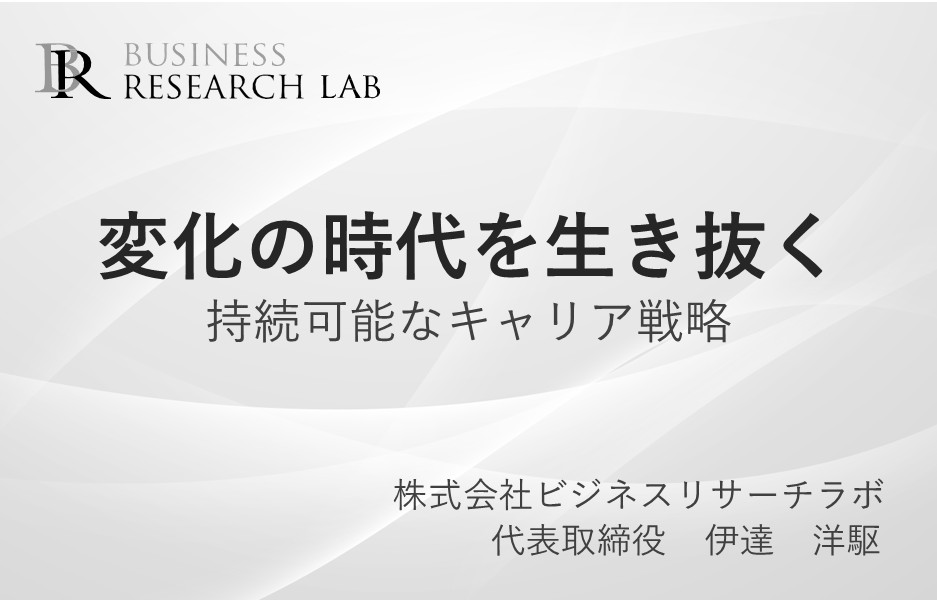2025年9月17日
変化の時代を生き抜く:持続可能なキャリア戦略
私たちのキャリアは多くの変化や不確実性に直面しています。長期雇用は当たり前のものではなく、働き方が多様化し、テクノロジーの急速な発展により求められるスキルも変わっています。こうした変化の中で、長期にわたり健康や幸福を保ちながら、仕事の生産性も維持できる「サステナブル・キャリア(持続可能なキャリア)」という考え方が生まれてきました。
サステナブル・キャリアとは、単純に同じ仕事を長く続けるということではありません。自分自身の価値観や目標に合致し、心身の健康を保ちながら、変化する環境に適応し続けられるキャリアのあり方です。しかし、このようなキャリアを築くのは容易ではありません。何が私たちのキャリアを持続可能なものにするのでしょうか。
本コラムでは、サステナブル・キャリアを形成する要因について考えていきます。家庭と職場からの支援、仕事と家庭の相互作用、自分自身のキャリアに対する語り、キャリアに対する意味づけや環境認識、そして研修や上司の支援など、いくつかの観点からサステナブル・キャリアの要素を探っていきましょう。
私たちがキャリアを通じて何を得たいのか、どのように仕事と生活のバランスを取るのか、そして変化する社会の中でいかに自分のキャリアを持続させていくのか。これらの問いについて解説していきます。
キャリアの持続性は家庭と職場の支援で高まる
仕事の負担増加や技術革新、社会・経済的変化によって、個人のキャリアが不安定になりやすい状況が生まれています。こうした背景から、健康や幸福、生産性を維持しながらキャリアを追求する「サステナブル・キャリア」の考え方が広がっています。
サステナブル・キャリアを支える要因として、仕事と家庭という二つの領域からの支援が挙げられます。トルコ北西部の様々な組織で働く412名を対象とした調査では、職場と家庭からの支援がキャリアの持続性にどう関わるかが調べられました[1]。
この調査では、参加者に対して2回の質問紙調査が行われました。1回目では職場や家庭の状況について、2週間後の2回目では個人のキャリアへの取り組みや仕事と家庭のバランスなどが測定されました。
調査結果から見えてきたのは、家庭を支援する上司の存在と、仕事を支援する家庭環境が、個人のキャリアの持続性に良い影響を与えることでした。例えば、上司が従業員の家庭生活に理解を示し、必要に応じて柔軟な働き方を認めるような環境では、従業員は自分のキャリアを主体的に形作る「キャリア・クラフティング」という行動を取りやすくなります。
キャリア・クラフティングとは、自分自身のキャリアを積極的に形成し、必要なリソースを獲得しようとする行動です。例えば、新しいスキルを学んだり、仕事上の人間関係を構築したり、自分の仕事の意義を見出したりする活動が含まれます。
調査では、このキャリア・クラフティングが、ワーク・ファミリー・バランスやエンプロイアビリティ(雇用され続ける能力)、仕事への熱意を高め、仕事によるストレスを軽減することが分かりました。さらに、キャリア・クラフティングは「個人とキャリアの適合性」を高めることも明らかになりました。これは自分の価値観やスキルとキャリア経験との整合性を指します。
このプロセスを見ると、職場や家庭からの支援が、個人のキャリア・クラフティングを促し、それが個人とキャリアの適合性を高め、最終的にはキャリアの持続可能性につながるという連鎖的な関係が浮かび上がってきます。
この研究から学べることは、キャリアの持続性を高めるためには「全人生(whole-life)」の視点が重要だということです。仕事だけでなく家庭生活も含めた総合的な視点でキャリアを考える必要があります。個人の主体性(キャリア・クラフティング)がキャリアの持続性に影響を与えることも明らかになりました。
この研究結果は、キャリアの持続性が個人の努力だけでなく、それを取り巻く環境との相互作用によって形成されることを示しています。家庭と職場という二つの領域が調和することで、個人は自分らしいキャリアを長期にわたって維持できるようになります。
キャリアは仕事と家庭の相互作用で形成される
現代社会におけるキャリアを理解するためには、仕事と家庭という二つの領域が互いにどのように影響し合っているかを考える必要があります。従来のキャリア研究では仕事の領域に焦点が当てられてきましたが、家庭や個人生活との関係性を無視してはキャリア全体を把握することはできません。
特に現代では、経済のグローバル化やテクノロジーの進展、共働き世帯の増加、人口の高齢化など、様々な社会変化が起きています。これらの変化は私たちのキャリアの形成に影響を与えています[2]。
仕事と家庭の関係性には、主に二つの側面があります。一つは「仕事と家庭の葛藤」です。これは仕事と家庭の役割が互いに干渉し合い、どちらか一方、あるいは両方の役割遂行が難しくなる状況を指します。例えば、仕事の残業が家族との時間を奪ったり、子どもの病気で仕事を休まなければならなかったりする場合です。
もう一つの側面は「仕事と家庭の相互強化」です。これは一方の領域で得られたスキルやリソースが、他方の領域にもプラスの影響を与える状況です。例えば、仕事で培ったコミュニケーション能力が家庭での対話を円滑にしたり、家庭での経験が仕事における人間関係の理解を深めたりすることがあります。
現代のキャリアを理解する上で重要なのは、次の四つのテーマです。
- キャリアの自己管理:雇用の不安定化が進む中、組織に頼るだけでなく、個人が主体的にキャリアを管理することが求められています。特に配偶者のキャリア、子育て、親の介護など、家庭生活を考慮したキャリア決定が重要になってきています。
- キャリア成功:従来は給与や昇進といった客観的な指標でキャリアの成功が測られてきましたが、現在では個人の価値観や満足感といった主観的な指標も重視されています。例えば家庭責任によって昇進などの客観的成功が制限されることがありますが、一方で自分の価値観に合ったワークライフバランスを実現できれば、主観的な成功感は高まる可能性があります。
- グローバルなキャリア:異なる文化圏で働く場合、家庭と仕事の調整はより複雑になります。海外赴任や国際的な仕事に就く場合、自分だけでなく家族全体への影響を考慮する必要があります。
- 持続可能なキャリア:これは長期的に健康や幸福感を維持できるキャリア形成を指します。キャリアの柔軟性や個人の価値観との適合、そして仕事と家庭の間でエネルギーやリソースをうまく配分することが、キャリアの持続可能性には求められます。
社会の変化に伴い、キャリアのあり方も変化しています。組織内でのキャリアだけではなく、組織の境界を越えた「境界のないキャリア」や、個人のニーズに合わせた「カスタマイズされたキャリア」が増えています。柔軟な勤務形態の普及や女性の労働市場への参入拡大、高齢者の雇用継続なども、キャリアの多様化を促進しています。
キャリアの持続性は自分の語りで構築される
キャリアの持続可能性を考える上で、私たち自身がキャリアをどのように捉え、語るかという視点も重要です。イタリアのプロジェクトマネージャー50名を対象にした質的研究では、個人がどのように自分のキャリアを語り、意味づけるかによって、キャリアの持続可能性が構築されることが明らかになりました[3]。
この研究では、参加者にインタビューを行い、キャリアの意味、成功、個人と組織の相互作用などについて聞き取りが行われました。そして、その「語り」を分析することで、キャリアの持続可能性がどのように構築されるかを探っています。
研究の理論的背景には、キャリアの持続可能性を4つの要素で説明する枠組みがあります。一つ目は「時間性」で、キャリアが生涯を通じてどのように展開していくかを指します。二つ目は「社会的空間」で、職業だけでなく個人の私生活も含めた様々な社会的文脈を意味します。三つ目は「主体性」で、キャリア形成において個人が積極的に関与することを示します。そして四つ目は「意味」で、自身のキャリアがどれほど個人的な価値観や目標に合致しているかを表します。
インタビューの分析から、プロジェクトマネージャーたちは自分のキャリアを「プロジェクトのようなもの」や「旅」といった比喩で表現することが多いことが分かりました。これらの表現は、キャリアが固定されたものではなく、動的で発展していくものだという認識を反映しています。
多くの参加者が「主体性」を重視し、キャリアを自分自身で設計し管理するものだと語りました。一方で、「組織がキャリアを認めて報酬を与える」という側面も強調され、個人と組織の相互作用の重要性も指摘されました。
持続可能なキャリアについては、「個人の満足感や充実感」と「客観的な成功指標(報酬や昇進)」のバランスが重要だという見方が示されました。ただし多くの場合、給与や地位といった外的な要素よりも、個人の満足感やチーム・関係者との良好な関係構築など、内的な要素がより重視されていました。
キャリアの持続可能性を支える鍵として、いくつかの要素が挙げられました。初めに「主体的行動」ですが、主体的にスキルを獲得し、人間関係を管理し、自分を高め続けることが大切です。続いて「意味」においては、自分の価値観や目標との一貫性があり、充実感を持って取り組めることが重要です。三つ目は「社会的空間」で、職場環境が支援的であり、プロジェクトが個人のキャリア発達に寄与することが求められます。最後に「時間性」で、継続的なキャリア発達が見込める機会や、キャリアの一貫性が必要です。
この研究は、キャリアの持続可能性がただ外部の条件によって決まるのではなく、個人がそれをどう解釈し意味づけるかという「語り」によって構築されることを示しています。同じような職場環境や経験であっても、それをどのように自分のキャリアストーリーに組み込むかによって、キャリアの持続可能性は変わるということです。
プロジェクトマネージャーの例では、プロジェクトの短期的・限定的な性質をキャリアの不安定要素と捉えるのではなく、多様な経験を積み重ね、スキルを向上させる機会として肯定的に語ることで、キャリアの持続可能性を高めていました。
この研究から学べることは、持続可能なキャリアの形成には個人の主体性と意味づけが重要であり、自分自身のキャリアストーリーを積極的に構築していくことが大切だということです。組織側には、従業員のキャリア形成を支援するために、明確で透明性のあるキャリアパスを提供することが求められます。
キャリアの持続性は意味や環境への認識で決まる
キャリアの持続性を実現するためには、自分のキャリアに対する意味づけや、取り巻く環境をどう認識するかが重要になります。韓国の研究チームは、中堅期(40~55歳)の従業員を対象に、キャリアの持続可能性を測定する尺度を開発しました[4]。この研究を通じて、持続可能なキャリアを支える要素が明らかになっています。
不確実な労働市場では、長期雇用よりも生涯にわたるキャリアやエンプロイアビリティ(雇用され続ける能力)を追求することが現実的になっています。キャリアの転換期を迎える中堅期の従業員にとって、自分のキャリアを持続可能にするための指標が必要とされています。
この研究では、韓国の中堅期従業員を対象に、キャリアの持続可能性を測定する尺度を段階的に開発しました。文献レビューと専門家の意見を取り入れた概念モデルを構築し、尺度項目を作成。その後、韓国企業のオフィス勤務者を対象に調査を実施し、最終的な尺度を完成させました。
完成した尺度は、4つの次元から構成されています。
- 一つ目は「意味認識」です。これは自分のキャリアが人生の価値観やアイデンティティと合致していると認識し、その方向性を明確にする能力を測ります。
- 二つ目は「スキル獲得」です。継続的な学習を通じて競争力のあるスキルを習得し、キャリアを持続的に成長させる能力を測ります。
- 三つ目は「関係構築」です。キャリアの成長に必要な専門的な人脈やネットワークを構築し維持する能力を測ります。
- 四つ目は「環境認識」です。自身のキャリアを取り巻く環境の変化を理解し、それを反映してキャリアを発展させる能力を測ります。
この研究の結果から、中堅期従業員のキャリア持続可能性を高めるためには、これら4つの要素をバランスよく発展させることが重要だと分かりました。単に職業スキルを高めるだけでなく、自分のキャリアに意味を見出し、人間関係を構築し、環境の変化に敏感であることが、キャリアの持続可能性に寄与することが見えてきました。
キャリアの持続性は研修と上司の支援で高まる
キャリアの持続可能性を高めるためには、スキルや知識の更新が求められます。企業が提供する研修は、そのための重要な機会となります。香港のサービス業に従事する334名の営業担当者を対象にした研究では、研修がキャリアの持続可能性にどのような影響を与えるか、またその効果を高める要因は何かが調べられました[5]。
この研究では、キャリアの持続可能性を「長期間にわたり、雇用とエンプロイアビリティを維持する能力」と定義しています。キャリアの持続可能性を測る指標として、「仕事のパフォーマンス」と「エンプロイアビリティ(雇用され続ける能力)」の二つが用いられました。
研究は、企業が提供する2日間の顧客サービス品質向上研修を受講した営業担当者を対象に行われました。データは研修前、研修直後、そして研修から2ヶ月後の3時点で収集されました。
この研究で注目されたのは、「経験への開放性」と「上司によるサポート」という二つの要素です。「経験への開放性」とは、新しい経験や知識を受け入れ、学習する個人の性格特性を指します。「上司によるサポート」は、研修で得た知識やスキルを職場で活用する際に、上司が提供する支援やフィードバックを意味します。
研究の結果、研修自体が仕事のパフォーマンスとエンプロイアビリティを向上させることが確かめられました。研修を通じて新しい知識やスキルを習得することで、業務遂行能力が高まり、労働市場での価値も向上したのです。
さらに、「経験への開放性」が高い従業員ほど、研修からより多くを学び取り、それが結果的にパフォーマンスとエンプロイアビリティの向上につながることが分かりました。新しいことに対して積極的で、好奇心が強く、学習意欲の高い人ほど、研修の効果が高まるということです。
同様に、「上司によるサポート」も研修効果を高めることが明らかになりました。上司が研修内容に関心を示し、研修で学んだことを実践する機会を提供し、適切なフィードバックを与えることで、従業員は研修で得た知識やスキルを実際の業務に活かしやすくなります。
当初の予想では、「経験への開放性」と「上司のサポート」の間に相互作用効果があると考えられていましたが、実際の調査ではそのような効果は見られませんでした。両者は独立してそれぞれ研修効果に貢献しているということです。
この研究からの学びとしては、企業がトレーニングを提供する際には、個人の性格特性(特に経験への開放性)を考慮することで、トレーニングの効果を最大化できるということです。例えば、新しい経験に対してオープンな従業員には、より挑戦的な内容の研修を提供するなどの工夫が考えられます。
上司による継続的な支援が、研修効果を職場で定着させる要因となることも分かりました。上司自身が研修内容を理解し、部下が学んだことを実践できるようにすることが大切です。
脚注
[1] Kilic, E., and Kitapci, H. (2024). Contextual and individual determinants of sustainable careers: A serial indirect effect model through career crafting and person-career fit. Sustainability, 16(7), 2865.
[2] Greenhaus, J. H., and Kossek, E. E. (2014). The contemporary career: A work-home perspective. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1, 361-388.
[3] Lo Presti, A., Manuti, A., De Rosa, A., and Elia, A. (2022). Developing a sustainable career through discourse: A qualitative study on a group of Italian project managers. International Journal of Managing Projects in Business, 15(8), 1-18.
[4] Kim, S., Lee, H., and Jin, S. (2024). Development and validation of a career sustainability scale for mid-career employees. Frontiers in Psychology, 15, 1442119.
[5] Bozionelos, N., Lin, C.-H. V., and Lee, K. Y. (2019). Enhancing the sustainability of employees’ careers through training: The roles of career actors’ openness and supervisor support. Journal of Vocational Behavior, 117, 103333.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。