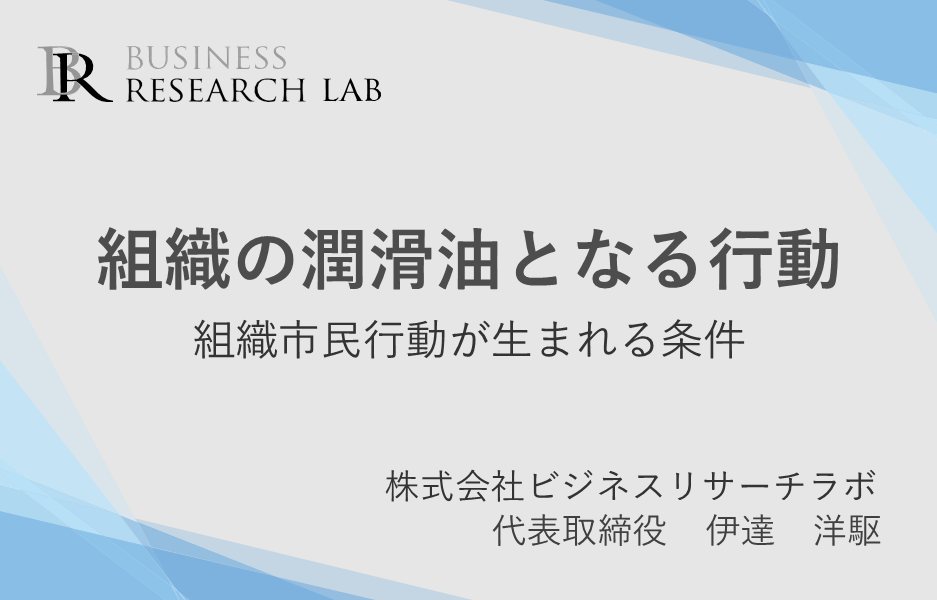2025年9月17日
組織の潤滑油となる行動:組織市民行動が生まれる条件
職場で同僚が困っていたら手を差し伸べる、期限に間に合わせるために尽力する、会社の評判を高めるような行動をとる。これらの行動は、仕事の正式な役割の中には書かれていないけれども、組織の円滑な運営には欠かせないものです。
このような自発的な行動は、学術的には「組織市民行動」と呼ばれています。組織市民行動とは、従業員が職務上の義務を超えて自発的に行う、組織の効率性や生産性に寄与する行動のことです。例えば、新人の手助けをする、不在の同僚の仕事をカバーする、組織の評判を高める発言をする、などが含まれます。
組織市民行動は組織の生産性向上、顧客満足度アップ、離職率低下など、様々な好ましい結果をもたらすことが明らかになっています。そのため、多くの企業がこうした行動を促進する方法を模索しています。しかし、組織市民行動はその性質上、強制できるものではありません。どのような条件や環境が、従業員の自発的な組織市民行動を引き出すのでしょうか。
本コラムでは、組織市民行動を促進する要因について見ていきます。リーダーの行動スタイル、従業員の心理状態、組織からの支援、個人の価値観など、多岐にわたる促進要因を紹介します。
変革型リーダー行動は組織市民行動を促進する
リーダーのあり方が変われば、組織全体は変わります。どのようなリーダーが部下の組織市民行動を高めるのでしょうか。ここで注目したいのが「変革型リーダー行動」です。変革型リーダー行動とは、部下の意識や価値観に働きかけ、彼ら彼女らのモチベーションを高め、期待以上の成果を出せるよう促すリーダーシップスタイルです。
アメリカの大手石油会社で988名の従業員を対象に行われた調査では、変革型リーダー行動が従業員の職務満足、組織へのコミットメント、リーダーへの信頼、そして組織市民行動に良い効果をもたらすことが示されました[1]。
変革型リーダー行動には、いくつかの要素があります。まず、「明確なビジョンの提示」です。組織の未来像や目標を分かりやすく伝え、部下に方向性を示します。次に「適切なロールモデル」として、自らが模範となる行動を示します。また、「集団目標の促進」として、個人の利益より集団の目標達成を優先する価値観を育みます。そして「高いパフォーマンスへの期待」を伝え、部下の可能性を信じて高い目標設定を促します。さらに「個別的配慮」として、部下一人ひとりのニーズや関心に目を向け、個々に合わせたサポートを提供します。最後に「知的刺激」によって、部下の創造性や問題解決能力を引き出します。
この調査では、変革型リーダー行動の中でも、特にビジョンを明確に示し、従業員一人ひとりをサポートするという二つの行動が、従業員の態度や行動に大きなプラス効果をもたらすことが見えてきました。リーダーが組織の進むべき方向を明確に示し、同時に個々の従業員に寄り添うサポートを提供することで、従業員は自発的に組織に貢献しようとするのです。
一方、この研究では「リーダーシップの代替要因」についても調査されています。これは、リーダーの直接的な指導がなくても、従業員の態度や行動に良い影響を与える要素のことです。例えば、仕事の自己完結性(一人で完結できる仕事の度合い)、集団の凝集性(チームの結束力)、従業員の職務への熟練度などがあります。調査結果では、これらの代替要因も従業員の満足度やコミットメントに独自の影響を持つことが分かりました。
特に仕事が構造化され、自己完結性が高い場合は、リーダーのガイダンスがそれほど必要ではなくなることも示されました。しかし、総じて変革型リーダー行動は、こうした代替要因の存在にかかわらず、従業員の態度や行動に独自の良い影響を及ぼすことが確認されました。
変革型リーダーは信頼を高め、組織市民行動を促す
変革型リーダー行動が組織市民行動を促進することを見てきましたが、そのメカニズムはどうなっているのでしょうか。変革型リーダー行動は、どのようにして従業員の自発的な貢献を引き出すのでしょうか。
アメリカのある石油化学企業に勤務する988名の社員を対象とした研究では、変革型リーダーシップと組織市民行動の間にある要因が解明されました[2]。この研究によると、変革型リーダーシップは直接的に組織市民行動を促すのではなく、「リーダーへの信頼」と「満足度」という二つの心理的要素を通じて間接的に影響することが分かりました。
研究では、変革型リーダーシップを6つの要素(ビジョンの明確化、適切な模範の提示、集団目標の受容促進、高い成果の期待、個別的な支援の提供、知的刺激)に分け、これらがリーダーへの信頼、従業員の満足度、そして組織市民行動にどう影響するかを分析しました。
分析の結果、変革型リーダーシップは従業員のリーダーに対する信頼および満足度に強い良い影響を与えることが明らかになりました。リーダーが明確なビジョンを示し、個々の従業員に配慮を示すと、従業員はそのリーダーを信頼し、職場での経験に満足感を覚えます。そして、この信頼と満足という心理状態が、組織市民行動を促します。
この「信頼」と「満足」の媒介的役割は重要です。研究データを分析すると、変革型リーダーシップは組織市民行動に直接的な影響はほとんど見られませんでした。しかし、リーダーへの信頼と職場での満足度を通じた間接的な経路では、明らかに組織市民行動に良い影響を与えていました。
リーダーが部下の組織市民行動を促したいなら、リーダーとしての信頼を築き、部下の職場での満足度を高めることが大切です。例えば、一貫性のある行動で信頼性を示し、公正な評価や意思決定を心がけることで信頼を高めることができます。従業員の意見に耳を傾け、個々の強みや関心に合った仕事の機会を提供することで満足度を向上させることができるでしょう。
組織の長期的な成功には、業績管理だけでなく、リーダーと従業員の信頼関係の構築や、従業員の満足度向上が欠かせません。変革型リーダーシップは、こうした信頼と満足を育む土壌を作り、組織全体の自発的な協力体制を強化します。
組織市民行動は一時的なポジティブ気分で高まる
リーダーの行動が従業員の信頼や満足度を通じて組織市民行動を促進することを見てきました。もっと日常的な要素、例えば従業員の「気分」は組織市民行動にどのような影響があるのでしょうか。
アメリカ南西部の小売店で働く221名の販売員を対象にした調査では、職場における「ポジティブな気分」が組織市民行動を促す要因になることが分かりました[3]。この研究は特に、その場の「状態としての気分」と個人の「性格特性としての気分傾向」を区別し、どちらが組織市民行動により強く関連するかを検討しました。
組織市民行動は二つのタイプに分けられました。一つは「役割内行動」で、顧客サービスのように職務として期待される支援的行動です。もう一つは「役割外行動」で、同僚を自発的に助けるといった、職務記述書には明記されていない自発的な行動です。
研究者はさらに、「状態としてのポジティブ気分」(最近1週間の職場での気分)と「特性としてのポジティブ気分」(普段からの気分の良さ、つまり性格的な明るさ)を測定し、これらが組織市民行動とどう関連するかを調べました。
組織市民行動を促進するのは、性格としての明るさではなく、その瞬間に感じる「状態としてのポジティブ気分」でした。普段は無口で控えめな人でも、その日の気分が良ければ、同僚を助けたり、顧客に親切にしたりする可能性が高まります。
状態としてのポジティブ気分は、同僚を助ける行動および顧客サービス行動と、共に有意な正の相関を示しました。この関連性は、職場における公平感(上司や経営層の公正さ、給与の公平性など)を調整した後でも維持されました。職場が公平か不公平かにかかわらず、その日の気分の良さが組織市民行動を促進するということです。
さらに、顧客サービス行動(役割内の組織市民行動)が実際の販売業績とも良い関連があることが確認されました。気分が良い日に顧客に対して親切にすることは、気分の表れにとどまらず、実際の業績向上にもつながります。
この研究から、職場でのポジティブな気分が組織市民行動の促進に重要であることが分かります。職場の雰囲気を明るくする、適度な休憩を取り入れる、従業員同士の良好な交流を促すなど、従業員の気分を良くする工夫が組織市民行動の促進につながる可能性があります。
組織市民行動は組織的支援によって促進される
リーダーの行動スタイルや従業員の気分が組織市民行動に与える影響について取り上げてきました。組織全体からの支援はどうでしょうか。従業員が組織からどのように扱われていると感じるかは、その従業員の行動に影響を与えるのでしょうか。
アメリカの大手企業に勤める252組の上司と部下を対象にした研究では、「知覚された組織支援(Perceived Organizational Support: POS)」が組織市民行動を促進することが明らかになりました[4]。POSとは、従業員が「組織が自分の貢献をどれだけ価値あるものと見なし、自分の幸福にどれだけ配慮しているか」と感じる程度を表すものです。
この研究は社会的交換理論に基づいており、人々は互恵的な関係を築く傾向があるという前提に立っています。社会的交換理論によれば、人は自分に良くしてくれる相手に対して、何かを返したいと感じるものです。職場に当てはめると、組織から支援を受けていると感じる従業員は、組織に恩返しをしたいと思い、その結果として組織市民行動が促進されると考えられます。
研究では、POSとLMX(Leader-Member Exchange)を区別しています。LMXは部下と上司の個別の関係の質を指し、先ほど扱った内容に近いものです。この研究の独自性は、組織全体からの支援(POS)と上司からの支援(LMX)を区別し、それぞれが従業員の行動に与える影響を分析した点にあります。
分析の結果、POSは組織へのコミットメントを高め、離職意図を減少させることが分かりました。そして何よりも、POSは組織市民行動に良い影響を与えることが確認されました。組織から支援されていると感じる従業員は、自発的に組織に貢献する行動を取りやすいのです。
一方、LMXは上司に対する好意的行動や高い業績評価に関連することが分かりました。POSとLMXは互いに区別される概念であり、それぞれが独立して従業員の態度や行動に影響を与えることが分かりました。
この研究結果は、組織市民行動を促進するには、リーダー個人の行動だけでなく、組織全体からの支援が感じられる環境づくりも重要であることを意味しています。従業員の貢献を認め評価する制度の導入、従業員の福利厚生への配慮、公正な評価制度の確立などが考えられます。
この研究はPOSとLMXを区別することの重要性も強調しています。両者は異なる社会的交換関係に基づいており、それぞれが異なる結果をもたらします。POSは組織全体への貢献意欲を高め、LMXは上司個人との関係を強化します。組織全体の支援環境と個々のリーダーシップの両方が、効果的な職場づくりには求められます。
組織市民行動は集団主義的な価値観で促される
ここまで見てきた要因は、主に組織やリーダーからの働きかけに関するものでした。しかし、組織市民行動を促進する要因は、従業員の内面にも存在します。中でも個人の持つ価値観は、行動に影響を与える可能性があります。
アメリカ南東部の金融サービス企業で155名の従業員を対象にした研究では、「個人主義–集団主義」という価値観が組織市民行動に与える影響が調査されました[5]。個人主義とは自分の利益や個人的な目標を優先し、独立性を重視する価値観です。一方、集団主義とはグループの利益を自分の利益よりも優先し、集団の一員であることを高く評価する価値観です。
この研究の特徴は、異なる文化間の比較ではなく、同一文化(アメリカ)内での個人の価値観の違いに焦点を当てた点です。同じ文化に属していても、個人の持つ価値観には違いがあり、それが行動の違いを生み出す可能性があります。
研究では、組織市民行動を4つの次元に分類しています。一つ目は「対人的援助」で、同僚の仕事を手伝うような行動です。二つ目は「個人のイニシアティブ」で、組織改善のための積極的な提言などが含まれます。三つ目は「個人の勤勉さ」で、職務を超える範囲での責任感ある行動です。四つ目は「組織への忠誠的支援」で、組織のイメージを対外的に高めるような行動です。
研究の仮説では、集団主義的な価値観を持つ従業員は、「対人的援助」「個人のイニシアティブ」「組織への忠誠的支援」の3つの次元で高い組織市民行動を示すと予測されました。一方、「個人の勤勉さ」は直接的な報酬に結びつきやすいため、集団主義とは関係が弱いと予想されました。
調査結果は、概ねこの仮説を支持するものでした。集団主義的な「価値観」を持つ従業員は、対人的援助、個人のイニシアティブ、組織への忠誠的支援といった組織市民行動を積極的にとりました。集団主義的な「規範」も対人的援助、個人のイニシアティブ、個人の勤勉さと関連していました。
この結果は、集団主義的な価値観を持つ従業員が集団の利益のために自発的に行動するという理論的予測と一致しています。集団主義者は自分の利益より集団の利益を優先するため、組織全体のために自発的に貢献しようとします。
一方、「個人の勤勉さ」が集団主義と弱い関係しか持たなかったのは、この次元の行動が個人の評価や報酬に直接結びつきやすいためと考えられます。個人主義者も自分の利益のためにこうした行動を取る可能性があるのです。
脚注
[1] Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., and Bommer, W. H. (1996). Transformational leader behaviors and substitutes for leadership as determinants of employee satisfaction, commitment, trust, and organizational citizenship behaviors. Journal of Management, 22(2), 259-298.
[2] Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., and Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly, 1(2), 107-142.
[3] George, J. M. (1991). State or trait: Effects of positive mood on prosocial behaviors at work. Journal of Applied Psychology, 76(2), 299-307.
[4] Wayne, S. J., Shore, L. M., and Liden, R. C. (1997). Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective. Academy of Management Journal, 40(1), 82-111.
[5] Moorman, R. H., and Blakely, G. L. (1995). Individualism-collectivism as an individual difference predictor of organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 16(2), 127-142.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。