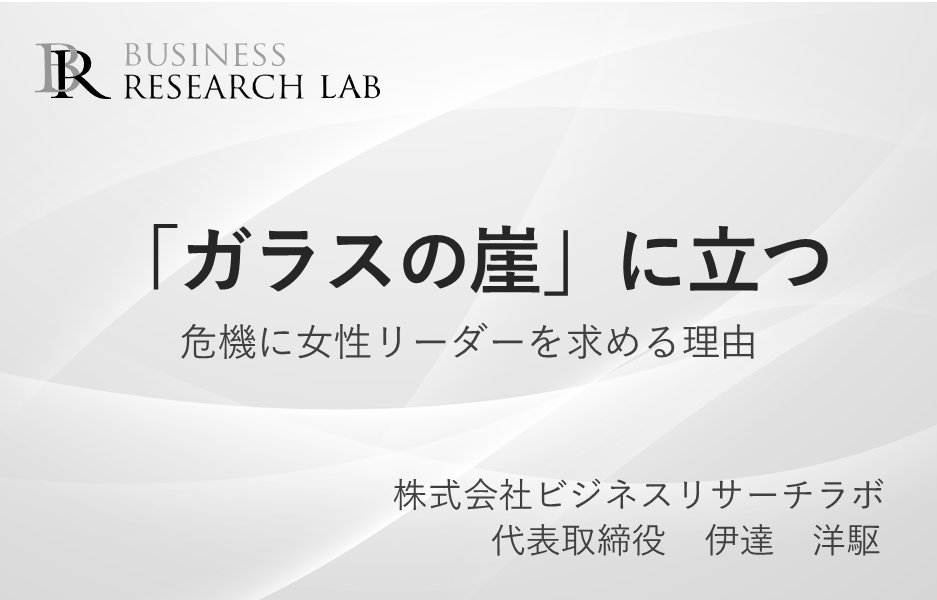2025年9月16日
「ガラスの崖」に立つ:危機に女性リーダーを求める理由
組織における女性の活躍は、多様な視点やスキルをもたらすことが期待されています。政府や企業も女性の登用を進める動きを強めていますが、その実態や効果については、私たちの直感や期待と異なる側面がないわけではありません。
例えば、企業のトップ層に女性が増えると業績が向上すると考えがちですが、本当にそうなのでしょうか。もしそうだとしても、それはどのような条件下で起こるのでしょうか。また、女性リーダーが登用される状況には特徴があるのでしょうか。昇進における男女差別は実際に存在するのでしょうか。さらに、女性が少数派である職場環境は、女性自身の行動や自己認識にどのような変化をもたらすのでしょうか。
本コラムでは、こうした問いに対する実証研究の結果を紹介します。時に私たちの予想と異なる結果が見られることもありますが、女性活躍の実態と効果について深く掘り下げていければと思います。
女性役員は革新的な企業ほど業績を向上させる
「女性が経営層に入ると企業業績が上がる」という主張を耳にしたことがあるでしょうか。この主張はあらゆる企業に当てはまるわけではありません。どのような条件で女性役員の存在が企業業績を高めるのかを見ていきましょう。
1992年から2006年の間の米国の大企業(S&P1500企業)を対象に、女性役員の存在が企業業績にどのような効果をもたらすかを検討した研究があります[1]。この研究では「女性役員がいる企業といない企業では業績に違いがあるのか」「それはどのような企業でより顕著なのか」という点を分析しています。
企業業績の指標としては「トービンのQ」という値を使いました。これは企業の市場価値を資産の簿価で割った値で、企業の将来性や市場からの評価を表します。分析の結果、女性役員がいる企業ではこの値が約1.19%高いことがわかりました。
ただし、この効果はすべての企業で同じように現れるわけではありません。女性役員の存在が企業価値を高めるのは、主にイノベーションに力を入れている企業でした。具体的には、研究開発費の比率が高い企業ほど、女性役員の存在による業績向上効果が大きくなっていました。
イノベーションを重視する企業で、女性役員の効果がより顕著に表れるのは、なぜでしょうか。研究者たちはいくつかの可能性を挙げています。
第一に、多様な視点が意思決定の質を高める効果です。経営層に多様な背景を持つ人々がいると、問題解決の際に幅広い視点が生まれ、創造的な解決策が生まれやすくなります。イノベーションを追求する企業では、固定観念にとらわれない新しい発想が必要とされるため、この効果が大きくなると考えられます。
第二に、女性特有のリーダーシップスタイルの効果です。一般的に女性は参加型のリーダーシップを取る傾向があり、チーム内での情報共有や協力を促進します。イノベーションの創出には、組織内の異なる部門間での情報交換や協力が不可欠であるため、こうしたリーダーシップスタイルが有効に機能するのでしょう。
第三に、組織内の女性社員全体へのモチベーション効果です。トップに女性がいることで、中間管理職や一般社員の女性たちのモチベーションや帰属意識が高まり、組織全体のパフォーマンスが向上する可能性があります。イノベーションには社員の積極的な参加が欠かせません。この効果も革新的な企業でより大きくなるでしょう。
女性は企業が危機的状況の時に登用されやすい
女性が企業のトップポジションに就くことが少しずつ増えてきましたが、そのタイミングや状況には特徴があるようです。女性がリーダーシップポジションに登用される際の状況に着目した研究を紹介しましょう[2]。「ガラスの崖(Glass Cliff)」と呼ばれる現象を発見した研究です。
この研究では、イギリスのFTSE100指数(ロンドン証券取引所の主要企業100社)に含まれる企業を対象に、女性が新たに取締役に登用された19件と、男性が登用された19件を比較分析しました。そして株価の変動に着目して、女性と男性がそれぞれどのような企業状況で取締役に登用されているかを調べました。
結果、男性が取締役に就任した企業では、就任前から就任後まで株価が比較的安定していました。一方、女性が取締役に就任した企業では、特に市場全体が下落している時期において、就任の数か月前から株価が顕著に下落する傾向がありました。
要するに、女性役員は企業が業績不振や危機的状況にある時に登用されることが明らかになりました。これが「ガラスの崖」という現象です。女性はリーダーシップポジションに到達できたとしても、そのポジションは非常に不安定で、失敗するリスクが高い状況であることが多いのです。
このような現象が起こる理由を考えてみましょう。研究者たちはいくつかの可能性を指摘しています。
一つ目の可能性は、「スケープゴート理論」です。企業が困難な状況にあるとき、その責任を取らせる「生贄」として女性が選ばれる可能性があります。男性中心の組織文化の中で、女性は「外部者」と見なされやすく、失敗した場合に責任を負わせやすい存在だと認識されているのかもしれません。
二つ目は、「危機における女性的リーダーシップへの期待」です。困難な状況では、従来の男性的な強硬なリーダーシップよりも、女性的とされる共感力や関係構築能力が価値を持つと考えられるかもしれません。危機を乗り越えるには新しいアプローチが必要であり、女性リーダーに期待が寄せられるのです。
三つ目は単純に「チャンスの不均衡」です。安定した好調な企業では、男性が優先的に選ばれるため、女性にはリスクの高いポジションしか残されていない可能性があります。
女性は政府機関の昇進で差別されていなかった
「ガラスの天井」という言葉をご存知でしょうか。これは女性が組織内で一定レベル以上の昇進を阻まれる見えない障壁を表す言葉です。多くの研究や報道が、この「ガラスの天井」現象の存在を指摘してきました。しかし、アメリカの研究者たちが連邦政府機関を対象に行った調査では、予想外の結果が明らかになりました。
この研究は、アメリカ連邦政府の上級管理職(Senior Executive Service, SES)への実際の昇進データを分析したものです[3]。1987年から1992年にかけて行われた32のポジションに対する438名の応募者の昇進過程を調査しました。
連邦政府のSESへの昇進プロセスは、専門の評価パネルによる審査があり、そこで推薦リストが作成されます。その後、最終的な採用責任者がリストから人物を選んで任命します。この研究では、応募者の性別が直接的あるいは間接的に昇進決定に影響を与えるかどうかを検証しました。
研究者たちは当初、「女性は昇進において直接的または間接的に不利に扱われるだろう」という仮説を立てていました。しかし、分析結果はその仮説を覆すものでした。むしろ女性であることは評価パネルの評価や推薦決定において、プラスの効果をもたらしていたのです。同じ条件であれば、女性の方が評価パネルから高い評価を受ける傾向がありました。そして最終的な採用決定においては、性別による有意差は認められませんでした。
職務経験の短さという点では女性は男性よりも不利な条件にあったにもかかわらず、評価においては不利に働いていませんでした。経験不足にもかかわらず女性は高く評価される傾向があったということです。
この結果について、研究者たちはいくつかの説明を試みています。第一に、連邦政府は昇進決定プロセスにおいて公正性や透明性を重視しており、その結果として性差別的な決定が抑制されている可能性があります。
第二に、連邦政府は「ガラスの天井」問題への意識が高く、女性の昇進を積極的に支援する方針を持っていた可能性があります。実際、調査期間中、連邦政府には女性や少数派の昇進を促進するプログラムが存在していました。
第三に、昇進に応募する女性自体が、男性に比べて優れている可能性も指摘されています。「ガラスの天井」を意識している女性は、応募する前に自己選別を行い、非常に高い能力を持つ女性だけが応募している可能性があります。同じレベルの男性に比べて、応募する女性の質が平均的に高かったのかもしれません。
この研究の重要な意義は、適切に設計された昇進プロセスにおいては、女性が差別されない、あるいはむしろ優遇される可能性があることを示した点でしょう。「ガラスの天井」は不変の現象ではなく、組織の制度設計や方針によって変化し得るものです。
女性は職場で少数派だと男性的な行動をとりやすい
皆さんは職場で少数派の立場になったことがありますか。その経験は皆さんの行動や自己認識にどのような変化をもたらしましたか。特に女性が男性中心の職場で働く場合、彼女たちの行動パターンや自己認識にはどのような影響があるのでしょうか。
法律事務所という職場環境において、女性弁護士たちの行動パターンや自己認識に関する研究が行われています[4]。この研究では、女性弁護士の割合が非常に低い「男性支配型事務所」(女性比率5%以下)と、ある程度の女性弁護士がいる「ジェンダー統合型事務所」(女性比率15%〜40%)を比較しています。
研究者は両タイプの事務所で働く女性弁護士たちにインタビューとアンケート調査を行い、彼女たちの職場における経験や自己認識について調査しました。その結果、組織内の女性比率の違いによって、女性たちの自己認識や行動パターンが異なることが明らかになりました。
男性支配型事務所で働く女性弁護士たちは、男性との違いを非常に強く意識する傾向がありました。彼女たちは男女の職業的能力の差異を明確に認識し、職場における男女の役割や特性について固定的なイメージを持ちやすい傾向がありました。例えば「男性は分析的で論理的」「女性は感情的で協調的」といったステレオタイプをより強く受け入れていたのです。
一方、ジェンダー統合型事務所で働く女性弁護士たちは、男女間の違いをそれほど強調せず、むしろ個人差を重視する傾向がありました。彼女たちは性別によるステレオタイプを超えて、個々の弁護士の能力や特性に注目していました。
「成功するために必要な特質」に関する認識にも大きな違いがありました。男性支配型事務所の女性たちは、成功するためには「男性的な特徴(競争的、攻撃的、長時間労働など)」が必要だと考えていました。彼女たちは自分が成功するためには「男性のように振る舞う」必要があると感じていたということです。
これに対して、ジェンダー統合型事務所の女性たちは、成功に必要な特質について、男性的特質だけでなく女性的とされる特質(協調性やコミュニケーション能力など)も含めた多様な要素を認める傾向がありました。「女性らしさ」を維持しながらも成功できると認識していたのです。
自己認識についても違いが見られました。男性支配型事務所の女性たちは、自分自身を「同化者(Accommodator)」として認識する傾向がありました。これは、男性中心の組織文化に適応するために、自分の女性としてのアイデンティティを抑制し、男性的な行動様式を採用することを意味します。例えば、攻撃的なコミュニケーションスタイルを採用したり、感情を表に出さないよう努めたりするなど、「男性的」と見なされる行動を意識的に取り入れていました。
一方、ジェンダー統合型事務所の女性たちは、自分自身を「統合者(Integrator)」として認識していました。これは、男性的特質と女性的特質の両方を状況に応じて柔軟に取り入れ、自己を多面的に統合して表現するスタイルです。彼女たちは自分の「女性らしさ」を抑圧する必要はなく、むしろそれを強みとして活かしていました。
この結果は、組織内のジェンダー構成が女性の自己概念や行動パターンに影響を与えることを示しています。男性支配型組織では女性が「男性化」しなければ成功できない環境が作られ、それが女性たちの自己表現を制限して、ストレスを増加させる可能性があります。
一方、ジェンダー統合型組織では、女性がジェンダーにとらわれず自由な自己表現が可能になり、多様な強みを発揮できる環境が整います。これは女性個人のキャリア発達だけでなく、組織全体のパフォーマンスにもプラスの効果をもたらす可能性があります。
脚注
[1] Dezso, C. L., and Ross, D. G. (2012). Does female representation in top management improve firm performance? A panel data investigation. Strategic Management Journal, 33(9), 1072-1089.
[2] Ryan, M. K., and Haslam, S. A. (2005). The glass cliff: Evidence that women are over-represented in precarious leadership positions. British Journal of Management, 16(2), 81-90.
[3] Powell, G. N., and Butterfield, D. A. (1994). Investigating the “glass ceiling” phenomenon: An empirical study of actual promotions to top management. Academy of Management Journal, 37(1), 68-86.
[4] Ely, R. J. (1995). The power in demography: Women’s social constructions of gender identity at work. Academy of Management Journal, 38(3), 589-634.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。