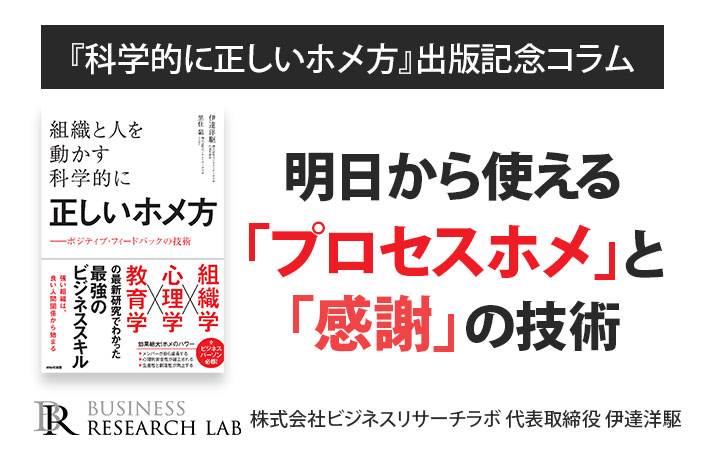2025年9月16日
『科学的に正しいホメ方』出版記念コラム:明日から使える「プロセスホメ」と「感謝」の技術
「思うように成長しない後輩がいる」「チームの一体感がなかなか醸成されない」「同僚や上司との間に見えない壁を感じる」。いつの時代も、組織で働く私たちにとって、円滑な人間関係の構築と、それを通じた相互の成長は尽きることのない課題です。多くの人は、自らの経験に基づいて、誠実に他者と向き合い、言葉を尽くしていることでしょう。しかし、その熱意が必ずしも相手の意欲向上やチームの活性化に結びついているとは限りません。「良かれと思ってかけた言葉が、かえって相手を萎縮させてしまった」「励ましているつもりでも、相手との距離が縮まらない」。こうしたコミュニケーションのすれ違いは、なぜ起こるのでしょうか。
この問いに対する答えを探求する中で執筆したのが、このたび上梓した拙著『科学的に正しいホメ方:ポジティブ・フィードバックの技術』です。その鍵は、私たちが日常的に、そして無意識的に行っている「ホメる」という、シンプルでありながら奥深い行為に隠されています。本書で私たちが提示するのは、心理学、教育学、組織論といった領域で積み重ねられてきた、数多の学術研究の成果に基づいた、客観的で再現可能な「技術」としてポジティブ・フィードバックを捉え直すアプローチです。
なぜ、あるホメ言葉は人の可能性を引き出し、あるホメ言葉は逆にその芽を摘んでしまうのか。本コラムでは、本書のエッセンスを凝縮し、なぜ今「科学的に正しいホメ方」が必要なのか、その理由と実践のヒントをお伝えしたいと思います[1]。
「ホメる」ことへの誤解と葛藤
働く人々の中には、「ホメる」という行為に対して、ある種の誤解や心理的な抵抗感を抱いている人もいます。「ホメすぎると相手を甘やかすことになるのではないか」「お世辞だと思われて、かえって信頼を失うのではないか」「そもそも、何をどうホメれば良いのかわからない」。こうした考えは、決して珍しいものではありません。これまで「ホメる」という行為は、個人の感覚や経験則が主な拠り所とされ、その技術が体系的に語られることは多くありませんでした。特に、自身が厳しい指導の中で成長してきた経験を持つ人ほど、「ホメる」ことの有効性に懐疑的であったり、その実践に気恥ずかしさを感じたりする傾向が見られます。
しかし、一見簡単そうに見えるこの行為には、実は複雑なメカニズムが働いています。効果的なホメ言葉は相手の意欲を高め、組織全体に活気をもたらしますが、その方法を誤れば、相手に不要なプレッシャーを与え、挑戦する心を奪い、かえってパフォーマンスを低下させる危険すら伴います。
例えば、ある営業マネージャーが、大型契約を獲得した若手社員に対して「◯◯さんは天才ですね。まさに営業の申し子です」と最大限の賛辞を送ったとします。この言葉は、一見すると若手社員の自信を高めるように思えます。しかし、この社員が次に担当した案件で思うような成果を上げられなかった時、この言葉は重い呪縛となって彼にのしかかります。「天才のはずなのに、なぜ失敗したんだ」「周りの期待を裏切ってしまった」。成功を自らの固定的な「才能」に結びつけてしまった結果、失敗を恐れ、次第に難易度の高い挑戦を避けるようになってしまった、というケースもあり得ます。
「とりあえずホメればいい」という安易な考え方は、このようなコミュニケーションにおける事故を引き起こしかねません。私たちが直面しているのは、個人の資質の問題ではなく、効果的なフィードバックに関する体系的な知識、すなわち「技術」が共有されてこなかったという構造的な問題です。もちろん、経験から得られる知見は貴重です。しかし、それだけに頼ったフィードバックは、時として効果が不安定になり、意図せぬ誤解を生む可能性も秘めています。そこで本書では、経験則に科学的な視点を加えることで、より確実で再現性のあるアプローチを提案しています。
フィードバックを技術にする
この課題を乗り越えるために、コミュニケーションという曖昧な領域に、客観性と再現性をもたらす「科学」の光を当てる必要があります。このたび上梓した書籍で私たちが提示する中核的な知見の一つが、「能力ホメ」と「プロセスホメ」の違いです。例えば、「◯◯さんには才能がありますね」「本当に優秀です」といった、個人の固定的な資質を対象とする「能力ホメ」は、短期的には相手の自尊心を高めるかもしれません。
しかし、スタンフォード大学のドゥエックらによる一連の研究をはじめ、近年の心理学研究は、この種のホメ言葉が副作用を持つことを明らかにしています。それは、成功を自分の「能力」に帰属させた人は、一度失敗を経験すると、「自分には能力がなかったのだ」という証明だと捉えてしまい、次なる挑戦を恐れるようになるというリスクです。才能があるはずなのに失敗したらどうしよう、というプレッシャーが、本来持っているはずの可能性の芽を摘んでしまうのです。
一方で、「今回の提案に至るまでの、粘り強い情報収集のプロセスが素晴らしかったです」「困難な状況で、複数の選択肢を検討された工夫が見事でした」といった、具体的な行動や努力の過程に焦点を当てる「プロセスホメ」は、異なる効果をもたらします。このホメ方は、人の能力は固定的ではなく、努力や工夫次第で伸ばせるという「成長志向」を育みます。失敗は能力の欠如の証明ではなく、次なる成長のための学習機会として捉えられるようになります。プロセスを評価する言葉が、人の挑戦する心を支え、困難からの回復力を育むのです。この違いを理解し、意識的に言葉を使い分けることは、効果的なフィードバックを実践する上での第一歩と言えるでしょう。
さらに、私たちがホメ方を実践する上で障壁となる、人間の脳に組み込まれた「不都合な真実」についても知っておく必要があります。その一つが「ネガティビティ・バイアス」です。これは、人間がポジティブな情報よりもネガティブな情報に、より強く、そして迅速に反応する傾向を指します。私たちの祖先が生存競争を勝ち抜く過程で、捕食者や毒のある植物といった危険を察知する能力が重要だったことの名残とも言われています。このバイアスは現代の職場においても作用し、私たちは意識しない限り、同僚のプレゼンテーションの優れた点よりも、些細な誤字脱字や言い淀みといった欠点や改善点に自然と目が行きやすくなります。だからこそ、ポジティブな側面に意識的に注意を向け、それを言語化する「技術」が不可欠です。
もう一つの重要なメカニズムが「記憶無視」です。サウサンプトン大学のセディキデスらの研究によれば、人は自己肯定感を維持するために、自分に関する否定的なフィードバックを選択的に思い出しにくくなるという性質を持っています。「何度注意しても直らない」という現場の嘆きは、相手の意欲や態度の問題だけでなく、この認知システムに起因する可能性があるのです。
叱責というネガティブ・フィードバックは、そもそも相手の記憶に定着しにくいという科学的根拠は、「叱る」指導法の限界を示唆しています。これらの知見は、「ホメる」という行為が、ただの気分の問題や対人関係の潤滑油にとどまらず、人間の学習と行動変容の原理に基づいた、合理的な育成手法であることを教えてくれます。これらの脳のメカニズムと、それを乗り越えるための思考法については、本書で詳しく解説しています。
明日から使える「ホメ方」の実践スキル
どのような技術を用いれば、有効なホメ方を実践できるのでしょうか。本書では、こうした科学的知見を現場で即座に活用できる具体的なスキルへと落とし込んでいますが、ここでは特に重要で、かつ汎用性の高い三つの技術を紹介します。これらは単独で機能するだけでなく、相互に組み合わせることで、さらにその効果を高めることができます。
一つ目は、「感謝」というポジティブ・フィードバックです。「ホメる」という行為に気恥ずかしさや上下関係を意識してしまう抵抗を感じる人でも、「ありがとう」という言葉であれば、ごく自然に、そして対等な立場で口にすることができるはずです。「先日の会議資料、非常に助かりました。あのデータがあったおかげで、クライアントへの提案に説得力が増しました」といった感謝の言葉は、単純な礼儀作法ではありません。「あなたの行動が、チームや組織にとって価値を生み出した」という明確な承認のメッセージです。
ペンシルベニア大学のグラントらの研究では、感謝の言葉を受け取った人は、その後の協力行動が顕著に増加することが示されています。感謝は、相手の「自分は他者や社会の役に立っている」という感覚、すなわち「社会的価値」を満たし、内発的な動機づけを刺激します。重要なのは、「ありがとうございます」と伝えるだけでなく、「何に対して、なぜ感謝しているのか」を添えることです。これによって、感謝は効果的な「プロセスホメ」として機能し、相手の自己効力感を高め、さらなる貢献意欲を引き出すのです。
二つ目は、人間関係における「心理的な貯金」を築く、「ホメの黄金比 5:1」という指標です。これは、ワシントン大学のゴットマンやノースカロライナ大学のフレドリクソンの研究などで示されている、安定した人間関係を築いているチームやカップルに見られるコミュニケーションの比率で、ポジティブなやりとりが5に対して、ネガティブなやりとりが1の割合で交わされている状態を指します。
日常的に称賛や感謝といったポジティブなフィードバックを積み重ねておくことで、信頼関係という「心理的な貯金」が蓄えられます。この貯金があるからこそ、いざ改善点を指摘しなければならない場面でも、相手はそれを人格否定や批判としてではなく、「自分の成長を願ってくれているからこその言葉だ」と建設的に受け止めることができるのです。この比率は、上司と部下の関係だけでなく、同僚同士のコミュニケーションにおいても同様に重要です。
この比率を意識するためには、自身のコミュニケーションを客観的に把握することから始めるのが有効です。例えば、手帳やメモアプリを使い、1週間、身近な同僚や上司、部下など、相手一人ひとりに対して行ったポジティブな声かけ(P)とネガティブな声かけ(N)を記録してみる。このシンプルな実践だけでも、自身のコミュニケーションの癖や、特定の相手に対する関わりの偏りなどが可視化され、行動変容への一歩となるはずです。
三つ目は、ホメ言葉に説得力をもたらす「具体化」の技術です。「素晴らしいですね」「見事な成果でした」といった漠然とした言葉は、相手の心に響きにくく、何を評価されているのかが不明確なため、次の行動にもつながりません。ポジティブ・フィードバックの効果を最大化するためには、その内容を具体化する必要があります。
そのためのフレームワークの一つが、「数値」「行動」「状況」という三つの事実に基づいて語ることです。例えば、「今月の顧客満足度が前月比で15%向上しました(数値)。これは、◯◯さんがお客様一人ひとりの問い合わせに丁寧に対応し、解決策だけでなく代替案まで提示していた(行動)結果です。特に、システムトラブルでクレームが殺到し、チーム全体が混乱する中で(状況)、冷静に優先順位をつけてチームを導いてくれた貢献は、非常に大きいものでした」といった形です。
このように事実をベースに語ることで、ホメ言葉は主観的な感想ではなく、客観的で信頼性の高い評価となり、相手は自身のどの行動が成果に結びついたのかを理解して、その成功体験を再現しようと努めるようになります。これは、個人の成長を促すだけでなく、チーム全体にとっての「ベストプラクティス」を共有する上でも有効な手法です。本書では、ここで紹介した3つの技術以外にも、すぐに実践できる多様なスキルを紹介しています。
ホメ方を使い分ける
これまで紹介してきた実践スキルは強力ですが、その効果を最大限に発揮するためには、もう一つの重要な視点が加わります。相手の特性や置かれた状況に応じて、ホメ方を柔軟に使い分けるという「最適化」の視点です。万能なホメ言葉というものは存在せず、同じ言葉であっても、受け取る相手や文脈によってその意味合いは変わります。
まず考慮すべきは、相手の経験や習熟度です。例えば、新しい業務に挑戦し始めたばかりの新人社員に対しては、完璧な成果を求めるのではなく、試行錯誤のプロセスそのものを肯定的に評価することが重要です。小さな成功体験を積み重ねられるよう、「まずはやってみよう」という挑戦する姿勢や、昨日より今日できた「小さな進歩」に光を当て、「前回よりも手順の確認がスムーズになりましたね」「質問の意図が的確になってきましたね」といった成長ポイントを頻繁にフィードバックすることが、自信と学習意欲を育みます。
一方で、高度な専門性を持つベテラン社員に対しては、行動の承認だけでは物足りないかもしれません。彼ら彼女らにとっては、その専門的な判断が組織全体にどのような戦略的価値をもたらしたのか、あるいは、彼ら彼女らの持つ暗黙知が後進の育成にどう貢献しているのかといった、より大局的で本質的な貢献を言語化して伝えることが、プロフェッショナルとしての誇りとモチベーションを高める上で効果的です。
相手との関係性の質も、ホメ方の選択に影響します。立命館大学の山浦氏らの研究では、上司と部下の信頼関係が希薄な場合、上司からのポジティブ・フィードバックが、かえって部下の責任感を低下させるという逆説的な結果が示されています。信頼関係が構築されていない相手からのホメ言葉を、「何か裏があるのではないか」「本心から評価しているわけではない」と表面的に受け止め、その真意を探ろうとすることで余計な心理的負担が生じるためと考えられます。
したがって、関係性がまだ構築できていない相手に対しては、まずはこちらが相手の貢献に助けられているという「感謝」のメッセージを伝えることから始めるのが有効です。感謝は、評価という上下関係のニュアンスが薄く、純粋な協力関係を築くための第一歩となり得ます。
本書が特に強調したいのは、ホメるという行為が、決して上司から部下への一方通行のものではない、という点です。同僚や、時には上司に対してポジティブ・フィードバックを行うことも、風通しの良い組織文化を創る上で重要です。
同僚に対しては、日々の業務で助けられた場面を取り上げ、「あの時の的確な情報共有のおかげで、プロジェクトの遅れを防ぐことができました」と貢献を認め合うことが、チームワークを強化します。上司に対しては、そのリーダーシップや支援をホメることが有効です。「部長が示してくださった明確な方針のおかげで、チームは迷わず業務に集中できました」「先日の面談でいただいたアドバイスが、課題解決の大きなヒントになりました」。こうした部下からの具体的なフィードバックは、上司自身の行動を省察する機会を与え、より良いマネジメントへとつながる好循環を生み出します。
本書の後半では、こうした相手や状況に応じた使い分けのバリエーションを、さらに豊富なケーススタディと共にお届けしています。
言葉で、人と組織の未来を創造する
本コラムでご紹介したのは、拙著『科学的に正しいホメ方』で展開している内容のほんの一部です。本書を通じて一貫してお伝えしたいのは、「科学的に正しいホメ方」とは、部下育成やモチベーション向上のための対症療法的なマネジメント手法の一つではないということです。組織で働く一人ひとりの挑戦する心を育み、チーム内に安心して失敗し、自由に意見を交わせる「心理的安全性」を醸成し、ひいては組織全体の学習能力と創造性を高めるための、戦略的なコミュニケーション技術です。
言葉は、使い方一つで人の可能性を無限に広げることもあれば、いとも簡単に閉ざしてしまうこともあります。私たちが日々交わす何気ない一言一言が、組織の文化を形作り、その未来を方向づけています。ポジティブ・フィードバックの実践は、個人の行動変容から始まります。しかし、その影響は波紋のように広がり、やがて組織全体を巻き込むうねりとなります。一人のリーダーが部下のプロセスを称賛し始めれば、その部下もまた、同僚の小さな工夫に気づき、感謝を伝えるようになるかもしれません。そのようなポジティブな相互作用が組織の隅々にまで浸透した時、そこには失敗を恐れず、互いに学び合い、自律的に成長していく「学習する組織」の姿が現れるはずです。
「ホメる」という行為を、経験や勘といったアートの世界に、科学の視点というサイエンスを融合させること。その先に、個人の成長と組織の発展が両立する、持続可能な未来が待っています。本書を手に取っていただくことで、皆さんの日々のコミュニケーションを見つめ直し、その一言の持つ計り知れない力を再発見するきっかけとなれば幸甚です。
脚注
[1] 本コラムの中で引用している研究の論文情報は、『科学的に正しいホメ方:ポジティブ・フィードバックの技術』を参照してください。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。