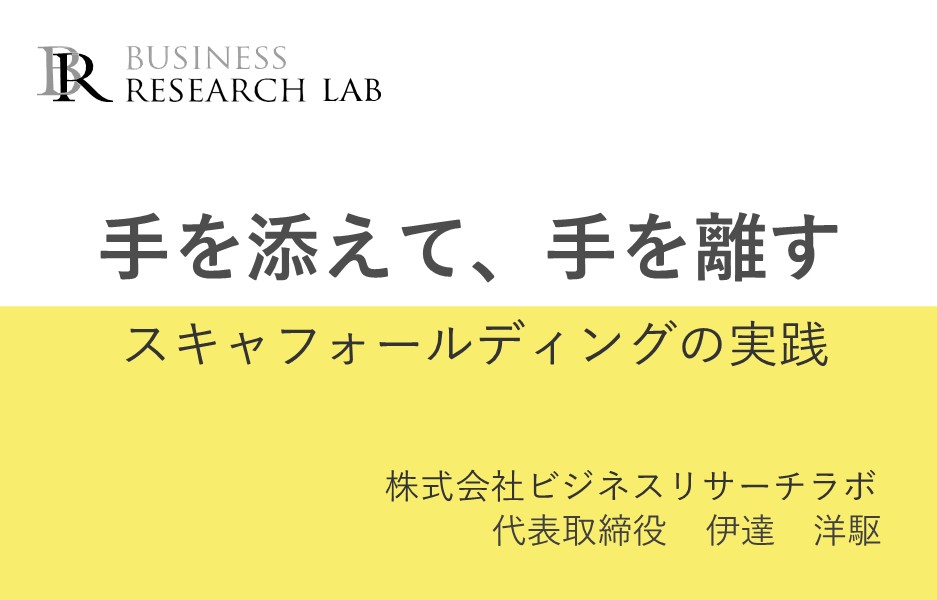2025年9月12日
手を添えて、手を離す:スキャフォールディングの実践
教育や人材育成の現場において、学習者が自分の力だけでは到達できない高みへと導くための支援方法として「スキャフォールディング」という概念があります。スキャフォールディングとは、直訳すると「足場かけ」を意味し、建築現場の足場のように、一時的な支援を提供しながら、徐々にその支援を減らしていくことで学習者の自律性と能力を高めていく手法です。
この概念は、ロシアの心理学者ヴィゴツキーが提唱した「最近接発達領域」という理論に基づいています。最近接発達領域とは、学習者が現在一人でできることと、支援があればできることの間にある領域のことです。スキャフォールディングは、この領域において支援を提供することで、学習者の潜在能力を引き出し、次第に自律的な学びへと導いていく過程です。
環境が複雑化し、学習者に求められる能力も高度化しています。知識の習得だけでなく、批判的思考力、問題解決能力、自己調整能力など、より高次のスキルが求められています。そのような状況において、スキャフォールディングは学習者の自律的な成長を促進するための手段として注目されています。
本コラムでは、スキャフォールディングの多様な側面と育成効果について探っていきます。高等教育における反省的ジャーナリングを通じた高次思考力の育成、体育教育における生徒コーチの自律的指導力の育成、スキャフォールディングの認知的能力向上への効果、そして学校改善におけるビジョンの役割に関する研究知見を見ていきます。
スキャフォールディングで高度な思考力を身につける
高等教育、特に看護教育の現場では、卒業後に臨床現場で直面する複雑な状況に対応できる思考力が求められます。そこで着目されているのが、反省的ジャーナリングとスキャフォールディングの組み合わせです。
反省的ジャーナリングとは、学生が自らの経験や学びを内省的に文章化し、それを分析することで理解を深める手法です。しかし、高次の思考スキルを要するこの活動を学生が自力で行うことは簡単ではありません。そこで教育者によるスキャフォールディングが必要となります。
ある研究では、看護学部の4年生を対象に、反省的ジャーナリングにおけるスキャフォールディングの効果を調査しました[1]。この研究では、精神看護の臨床実習を履修している学生たちが対象となりました。研究者たちは質的アプローチを採用し、学生の反省的ジャーナルの内容分析とフォーカスグループディスカッションを通じてデータを収集しました。
スキャフォールディングのプロセスは4つの段階で構成されていました。反省プロセスへの導入、初回ジャーナルへのフィードバック、継続的なフィードバックとコーチング、そして最後に徐々に支援を減らしていくフィードバックです。このように段階的に支援を調整することで、学生の自律的な思考力を育成することを目指しました。
研究結果は主に3つのカテゴリーに分類されます。1つ目は「意識的無能力」です。学生たちは最初、高次思考力を使って反省的ジャーナルを書く能力が不足していることを自覚していました。しかし、この自覚こそが成長の第一歩となりました。
2つ目は「介入条件」です。教員のスキャフォールディングによる支援、具体的なフィードバック、そして仲間からのサポートが学習を促進する条件として挙げられました。とりわけ、教員の継続的な支援とフィードバックが高次思考能力を高めるために大切だったと報告されています。
3つ目は「同時発生した意図せざる成果」です。反省的ジャーナリングを通じて、副次的に学術的ライティング能力の向上や発見学習という効果が生まれました。学生たちは継続的なジャーナリングとフィードバックにより、自分たち自身で新たな知識を発見する経験を得ていたのです。
この研究では、スキャフォールディングが学生の成長において2つの点で見逃せない役割を果たしていることがわかりました。一つは、学生が「無意識の無能力」の状態から「意識的能力」へと進むことを可能にする点です。最初は自分が何をどう考えれば良いかもわからない状態から、徐々に自分の思考プロセスを意識的にコントロールできるようになるということです。もう一つは、ヴィゴツキーの最近接発達領域理論に基づくスキャフォールディングにより、学生が段階的に高次思考スキルを習得できる環境が創出される点です。
スキャフォールディングで生徒コーチが自律的に指導する
高等教育における反省的ジャーナリングを通じたスキャフォールディングの効果を見てきましたが、次に中等教育、特に体育教育の場面におけるスキャフォールディングの活用事例を見ていきましょう。
体育教育では「スポーツ教育モデル」という教育アプローチがあります。これは運動技能を習得するだけでなく、生徒自身がチーム運営やコーチングなどの役割を担うことで、より包括的なスポーツの理解と社会的スキルの発達を目指すモデルです。このモデルでは、生徒がコーチ役を務め、仲間の学習をリードする機会が提供されますが、そのプロセスにおいて教師によるスキャフォールディングがどのように生徒コーチの指導力を育成するかを調査した研究があります[2]。
この研究は1年間にわたるアクションリサーチとして実施され、ポルトガルの中学校に通う7年生26名(12〜14歳)が参加しました。これらの生徒たちは、1年間を通じてバスケットボール、ハンドボール、サッカー、バレーボールという4つの種目を順に体験しました。研究者は教師として実際の指導を行いながら研究を進め、各種目で「計画→実施→観察→反省」というサイクルを繰り返し、その成果を次の種目の指導に反映させました。データ収集は授業観察、映像・音声記録、教師の日誌、半構造化インタビュー、コーチ役の生徒とのセミナーなど、多様な方法で行われました。
その結果、1年間を通じて段階的に生徒コーチの能力が発達していく様子が観察されました。最初のバスケットボールのシーズンでは、生徒コーチは教師の指示なしでは戦術的な問題を認識・解決できず、教師によるガイドが不可欠でした。
第2シーズンのハンドボールでは、コーチ役の生徒は徐々に戦術的な問題を自ら発見し、仲間と共同で解決策を見出すようになりました。この時期に効果的だったのが「誘導観察」と呼ばれる手法で、教師の指導のもとで映像分析を活用した指導が行われました。
第3シーズンのサッカーになると、生徒コーチの自主性がさらに高まり、自ら問題を特定し、仲間に質問しながら、より高度な戦術的理解を促進することができるようになりました。顕著だったのは、なぜそうするのかという理由付けや議論を行う能力の向上でした。
最終シーズンのバレーボールでは、生徒コーチが仲間にも責任を委譲し、仲間同士のピア・ティーチングが活発になりました。生徒たちは自己監視や相互評価を行うようになり、より高度な自己調整能力が見られるようになりました。
この研究からは、教師のスキャフォールディングは単純に支援を減らしていくだけの直線的なプロセスではないことが分かります。生徒の認知的・メタ認知的な進展や取り組む種目の特性に応じて、動的に調整していく必要があります。例えば、最初は教師が主導して明確な指導を行い、その後、徐々に探究型・発見型の学習へと移行することが効果的であることが明らかになりました。
スキャフォールディングは認知的能力を効果的に高める
具体的な教育場面におけるスキャフォールディングの実践と効果について見てきましたが、ここではスキャフォールディングに関する過去の研究を体系的に整理した知見をもとに、その効果と課題について考えてみましょう。
教師と生徒のインタラクションにおけるスキャフォールディングについて、過去10年間(1998年〜2009年)の研究を系統的にレビューした研究があります[3]。この研究では、スキャフォールディングの概念化、実際の教育現場での実践方法、そしてその効果に焦点が当てられました。
スキャフォールディングの特徴として3つの要素が挙げられています。1つ目は「コンティンジェンシー」と呼ばれるもので、教師が生徒の能力や状況に応じて支援を柔軟に調整することを指します。2つ目は「フェーディング」で、生徒が自律性を高めるにつれて、支援を段階的に減少させることです。3つ目は「責任の移譲」で、教師が次第に生徒に対して課題遂行や学習への責任を移していくことです。このように、スキャフォールディングは生徒と教師が共に積極的に参加する相互作用であり、生徒が自律的に学習を進められるよう支援するための教育的手法として位置づけられています。
このレビューでは、スキャフォールディングを「意図(目的)」と「手段」の二つに分類する分析の枠組みが提示されています。スキャフォールディングの意図としては、メタ認知的活動の支援、認知的活動の支援、感情的活動の支援の3つがあります。一方、スキャフォールディングの手段としては、フィードバック、ヒント提示、指示、説明、モデリング(手本を示すこと)、質問をすることなどが挙げられています。教師はこれらの手段を様々な意図と組み合わせて用いることで、生徒の学習を支援しています。
実際の授業を観察した記述的研究の分析からは、多くの教師が「モデリング」と「質問すること」を広く活用していることが明らかになりました。しかし、授業の規模や状況によって、教師の支援がどの程度「コンティンジェント」(生徒に合わせて調整されているか)であるかは異なることも分かりました。
スキャフォールディングの効果を検証した研究は比較的少ないものの、行われた研究の多くはスキャフォールディングが生徒の認知的・メタ認知的な能力向上に効果的であることを示しています。しかし、動機づけや関心といった感情的側面への効果については、結果が一貫していないことも明らかになりました。
ビジョンは学校改善を支えるスキャフォールディング
ここまで主に教室内での教師と生徒の相互作用におけるスキャフォールディングに焦点を当ててきましたが、学校組織全体のレベルでも「スキャフォールディング」という概念は有用です。学校改善とリーダーシップの文脈における「ビジョン」の役割に焦点を当て、それがいかに学校改善を支えるスキャフォールディングとして機能するかを考察します。
学校改善やリーダーシップの研究において、「ビジョン」という言葉が使われますが、その具体的な内容や実践方法については曖昧なままです。ある研究では、教育リーダーシップと学校改善に関する文献(1995年から2012年)を分析し、「ビジョン」という概念を「使命」「目標」「期待」という3つの要素に分解し、教育現場で実践可能な形で提示しています[4]。
この研究では、「ビジョン」を構成する3つの要素が説明されています。「使命」は学校の根本的価値観や目的を示すものです。「目標」は使命を達成するための方向性を示すものです。そして「期待」は目標達成のための基準や達成水準を示すものです。この3つの要素が互いに連動し、学校改善やリーダーシップの効果を支えるための「足場(スキャフォールディング)」として機能するのです。
研究では、「使命」には8つの要素が含まれると分析しています。改善が可能だという希望、成功へのコミットメント、生徒やコミュニティの強みに焦点を当てる考え方、生徒中心の考え方、学術的基盤、成果志向、継続的改善、そして共同責任です。これらの要素が組み合わさることで、学校の方向性が形作られます。
「目標」については、具体的で明確な学術的方向性を持ち、挑戦的だが達成可能であること、生徒全員を対象としていること、そして教職員がオーナーシップを持てるよう設定されることが大事であると指摘されています。目標設定のプロセスにおいては、教職員が主体となり、コミュニケーションを通じて、目標達成のための継続的なモニタリングと評価が行われる必要があります。
「期待」は、目標を実践へと変換する要素です。学術的基準を定めることで、教職員が目標を認識できるよう支援します。また、教職員や生徒の行動基準を示すことで、生徒の学力向上や学校文化の形成に貢献します。この研究では、低所得家庭の生徒に対して「期待」が特に良い結果をもたらすことも指摘されています。
ビジョン(使命、目標、期待)が学校改善において機能するためには、学校リーダーが一貫したコミュニケーションを通じて教職員全体の共通理解やコミットメントを形成することが求められます。学校リーダーが自ら模範を示すこと(モデリング)、さらに進捗状況を定期的に評価する(モニタリング)ことも有効です。
このように、ビジョンの3要素(使命・目標・期待)は、学校改善において「足場」として機能します。それは教職員に対して行動の指針を与え、学校全体が一貫した方向性を持って改善に取り組むための支えとなります。そして、リーダーがコミュニケーション、共通理解の形成、モデリング、モニタリングを通じてビジョンを運用することで、学校全体の能力向上が促進されるのです。
脚注
[1] Jarvis, M. A., and Baloyi, O. B. (2020). Scaffolding in reflective journaling: A means to develop higher order thinking skills in undergraduate learners. International Journal of Africa Nursing Sciences, 12, 100195.
[2] Farias, C., Hastie, P. A., and Mesquita, I. (2018). Scaffolding student-coaches’ instructional leadership toward student-centred peer interactions: A yearlong action-research intervention in sport education. European Physical Education Review, 24(3), 269-291.
[3] van de Pol, J., Volman, M., and Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher-student interaction: A decade of research. Educational Psychology Review, 22(3), 271-296.
[4] Murphy, J., and Torre, D. (2015). Vision: Essential scaffolding. Educational Management Administration & Leadership, 43(2), 177-197.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。