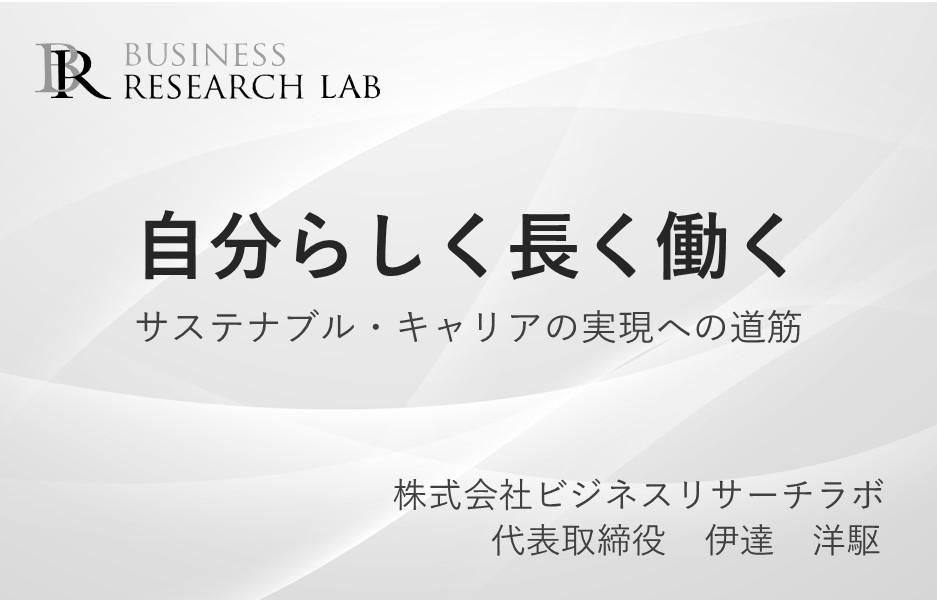2025年9月11日
自分らしく長く働く:サステナブル・キャリアの実現への道筋
かつては「一つの会社で定年まで勤め上げる」というキャリアは珍しくありませんでしたが、現在ではそのような安定したキャリアを築くことは簡単ではなくなっています。転職への心理的障壁が下がり、働き方も多様化する中で、「サステナブル・キャリア(持続可能なキャリア)」という考え方が脚光を浴びています。
サステナブル・キャリアとは、人生全体を通じて満足感や幸福感を維持しながら、長期にわたって健康で生産的に働き続けることができるキャリアを意味します。それは職業生活の長さだけでなく、その質にも着目した概念です。どうすればサステナブル・キャリアを実現できるのでしょうか。
本コラムでは、サステナブル・キャリアに関する研究知見を紹介しながら、その意味するところについて解説します。組織と個人の関係性、新自由主義的社会の課題、年齢による変化、そしてキャリア選択の動機など、多角的な視点からサステナブル・キャリアを考察します。
誰もが、自分のキャリアをどう形作るべきか迷うことがあるでしょう。本コラムを通じて、読者の皆さんがキャリアを持続可能なものにするためのヒントを得ていただけると嬉しいです。
キャリアは組織との共生的な調整で持続可能に
個人のキャリア形成と組織の要求が一致しないことがあります。このような状況で、どのようにサステナブル・キャリアを実現できるのでしょうか。経営コンサルタントを対象とした調査によれば、キャリアの持続可能性を高めるには、個人と組織の利害を調整することが必要です[1]。
サステナブル・キャリアは4つの要素から成り立っていると考えられています。
- 時間性:これは現在だけでなく、将来にわたってキャリアが持続することを意味します。
- 社会的空間:キャリアは職場だけでなく、私生活を含む様々な場所で形成されるということです。
- 主体性:自分自身がキャリアを選択し構築していく力を指します。
- 意味:キャリアが個人の価値観や目的に合っているかどうかという点です。
4つの要素を踏まえたうえで、経営コンサルタントのキャリアを調査した結果、彼ら彼女らが組織との関係をどのように語るかには4つのパターンがあることがわかりました。
一つ目は「過剰な同一化」と呼ばれるパターンです。このタイプのコンサルタントは組織と自分を強く一体化させています。組織の価値観や文化に共感し、キャリアにおける問題があっても、それを成長の機会として捉えることができます。例えば、長時間労働や高いプレッシャーも「自分を磨くチャンス」と前向きに解釈します。組織に対する強い帰属意識があるため、会社への貢献に喜びを感じます。
二つ目は「順応」のパターンです。このタイプは組織が設定した昇進システムやキャリアパスに沿って自分を合わせていきます。例えば、「マネージャーになるには何が必要か」という組織の基準を理解し、それに合わせて行動します。社内の人間関係や権力構造を上手く利用して自分のキャリアを前進させようとします。ただし、社内政治の複雑さに疲れを感じることもあります。
三つ目は「共生の創出」です。このタイプは最もサステナブルなキャリアを実現しています。自分の価値観や目標を組織の要求と積極的に調和させ、新しい役割や機会を自ら創り出します。例えば、既存のキャリアパスにはない新しいプロジェクトを提案し、自分の専門性を活かしながら組織にも価値をもたらします。このような人は内的な充実感と組織への貢献を両立させており、長期的なキャリアの持続可能性を高めています。
四つ目は「転職・離脱」のパターンです。このタイプは組織内でキャリアの持続可能性を見いだせず、別の場所で新たな機会を探そうとします。社内の人間関係がうまくいかなかったり、自分の価値観と組織の方向性が合わなかったりすることで、不満や緊張を感じます。そのため、転職によって問題解決を図ろうとするのです。
これらの結果からわかることは、サステナブル・キャリアを実現するには、単純に組織に従うのではなく、自分の価値観や目標を組織のニーズと調和させる「共生的な調整」が必要だということです。経営コンサルタントという厳しい環境でも、自分のキャリアに意味を見出し、組織と共存する道を探った人たちがキャリアの持続可能性を高めることができました。
このような調整は一度だけ行うものではなく、キャリアの各段階で繰り返し行われるプロセスです。例えば、キャリア初期では組織の方針に順応することがあるかもしれませんが、経験や専門性が増すにつれて、より主体的に組織との関係を構築できるようになります。
個人主義的な競争でキャリアが不安定化する
「自分のキャリアは自分で管理すべき」という考え方が広まっています。一見すると自由で魅力的に思えるこの考え方ですが、実はキャリアの持続可能性を脅かす側面もあります。このような個人主義的な考え方の背景には、新自由主義というイデオロギーが存在すると指摘する研究があります[2]。
ここにおける新自由主義とは、個人の経済的自由を最大化することが人間の幸福を高めるという考え方です。一人ひとりが自由に競争し、能力や努力に応じた報酬を得ることを理想とします。このイデオロギーは職場にも浸透し、私たちのキャリア観にも作用しています。
新自由主義の特徴は、三つの要素で説明できます。一つ目は「個人主義」です。これは自分の人生やキャリアは自分自身の責任であるという考え方です。例えば、スキルアップや資格取得は個人の責任とされ、失敗した場合も自己責任として片付けられます。自己啓発書が人気を集め、「自分を高める」ことが奨励される社会的風潮もこれに関連しています。
二つ目は「道具的」な観点です。これは人間関係を取引関係として捉える見方です。会社と従業員の関係も、お互いに利益をもたらす限りにおいて継続される契約関係とみなされます。例えば、従業員は会社の利益に貢献する限りにおいて価値があり、貢献度が低下すれば容易に解雇されるという考え方が強まります。その結果、従業員は自分の市場価値を高めるために努力し続ける必要に迫られます。
三つ目は「競争主義」です。様々な事柄が市場原理に基づいて決まるという考え方で、職場においても競争が奨励されます。評価制度も個人の成果に基づいて設計され、同僚との競争が促進されます。例えば、成果に応じた賞与や昇進制度は、組織内での競争を激化させます。
新自由主義的な考え方が職場にどのような形で現れているのでしょうか。典型的な例は、成果主義の評価システムです。個人の業績を数値化して評価し、それに基づいて報酬や昇進を決定する仕組みが多くの企業で導入されています。非正規雇用の増加や個別交渉型の雇用契約も、労働を取引と見なす考え方の表れです。
新自由主義的なイデオロギーがなぜ多くの人々に受け入れられているのかも考える必要があります。この研究によれば、それは「自由の幻想」「能力主義の幻想」「成長と進歩の幻想」といった心理的要素が関わっています。
「自由の幻想」とは、個人が自分の意思で自由にキャリアを選択できるという考え方です。しかし実際には、社会経済的な背景や教育機会の格差によって、選択肢は制限されています。例えば、高度な専門教育を受ける経済的余裕がない人は、自ずと選べるキャリアが限られてしまいます。
「能力主義の幻想」とは、努力と能力があれば誰でも成功できるという考え方です。しかし、スタート地点の不平等や社会的ネットワークの差異など、成功には個人の努力だけでは説明できない側面が存在します。
「成長と進歩の幻想」とは、経済や個人は常に成長し続けるという考え方です。この考えの下では、停滞は失敗とみなされ、前進し続けることが求められます。しかし、人生には様々な段階があり、常に成長し続けることは現実的ではありません。
新自由主義的な環境がキャリアの持続可能性に与える問題点は何でしょうか。研究によれば、絶え間ない競争や自己管理のプレッシャーは心理的・身体的な健康を害する恐れがあります。自分の市場価値を証明し続けるストレスは、燃え尽きやメンタルヘルスの問題を引き起こします。
短期的な成果が重視される環境では、長期的なキャリア発達が阻害される可能性があります。例えば、短期的な数字を上げるために必要な能力と、長期的なキャリア形成に必要な能力は必ずしも一致しません。競争が激化すると、同僚との協力関係が損なわれ、組織全体のパフォーマンスも低下する恐れがあります。
サステナブル・キャリアの視点から見ると、新自由主義的なキャリア観は多くの課題を内包しています。個人が自由に選択し競争するという理想は魅力的に映りますが、その裏で多くの人々のキャリアが不安定化している現実があります。
キャリアの将来的な適合性は中高年ほど重要に
キャリアの持続可能性を考える上で、「労働適応能力」という概念は大切です。ここでいう労働適応能力とは、現在の仕事を今後も継続して行えるという個人の認識を指します。労働適応能力を高め、サステナブル・キャリアを実現するためには、何が必要なのでしょうか。
ベルギーで行われた調査からは、現在の仕事が自分に合っているという「適合性」と、将来に向けた展望を持つという「未来志向性」が重要であることがわかりました[3]。この調査は5205名の労働者を対象に行われ、様々な年齢層や職種の人々が参加しました。
調査では「自律性」「強みの活用」「ニーズ供給適合性」「未来志向性」という四つの要素が労働適応能力とどのように関連するかを検証しました。「自律性」とは仕事の進め方を自分で決められる程度、「強みの活用」とは自分の得意なことを仕事で活かせる程度、「ニーズ供給適合性」とは仕事が自分のニーズや価値観に合っている程度、「未来志向性」とは仕事が将来的な成長や発展につながる程度を意味します。
調査の結果、予想に反して「ニーズ供給適合性」だけが労働適応能力と直接的に関連していることがわかりました。仕事が自分の価値観やニーズに合っていると感じる人ほど、将来も働き続ける能力があると認識する傾向があったのです。
さらに、年齢によって「未来志向性」の重要度が異なりました。若い世代(20-34歳)では未来志向性と労働適応能力の関連はあまり見られませんでしたが、中高年層(35-49歳、50歳以上)では、未来志向性が高いほど労働適応能力も高いという関連が表れました。これは、キャリアの後半になるほど、仕事の将来性や成長機会が労働適応能力の認識に関わることを示しています。
この理由はどこにあるのでしょうか。若い世代は、キャリアの初期段階にあり、様々な可能性が開かれています。新しい分野に挑戦する機会も多いため、現在の仕事の将来性だけがキャリアを決定づけるわけではありません。
一方、中高年になると状況は変わります。専門性が高まり、特定の分野でのキャリアが確立されてくると、急激な方向転換は難しくなります。そのため、現在の仕事が将来も通用するかどうか、学び続ける機会があるかどうかが、労働適応能力の認識に影響するのです。
もう一つ予想外だったのは、「強みの活用」が労働適応能力と負の関連を示したことです。これは一見矛盾しているように思えますが、強みを発揮することで短期的には高いパフォーマンスを発揮できても、長時間の過酷な労働につながり、長期的な労働適応能力を損なう可能性があることを示唆しています。
「労働の意味深さ」が労働適応能力に直接影響しないという結果も得られました。仕事に意味を見出すことは大切ですが、それだけでは長期的に働き続ける能力の認識には結びつきません。
これらの結果から、サステナブル・キャリアを実現するためには、年齢や状況に応じた異なるアプローチが必要だと考えられます。若い世代では、様々な経験を通じて自分のニーズや価値観に合った仕事を見つけることが大切です。中高年では、学び続ける機会や将来的な展望を持てる環境が特に重要になります。
キャリア選択の動機は自己評価の維持と関連する
サステナブル・キャリアを考える上で、私たちがなぜ特定のキャリアを選ぶのかという「動機」も重要です。ポルトガルで行われた調査では、観光・ホスピタリティ産業を専攻する大学生のキャリア動機と教育へのコミットメントの関係が明らかになりました[4]。
この調査では、自己決定理論という枠組みを用いて、学生の動機を分類しています。自己決定理論によれば、人間の動機は大きく「内発的動機」と「外発的動機」に分けられます。内発的動機とは、活動そのものが楽しく、自己満足につながるために行動する動機です。例えば、「ホテル業界で働くのが楽しそうだから」という理由です。
一方、外発的動機はさらに細かく分類されます。「同一化動機」があります。これは個人の価値観に合致するために行動する動機です。例えば、「ホスピタリティの価値観が自分の人生観と合っているから」という理由でキャリアを選ぶ場合が該当します。
続いて「取り入れ動機」があります。これは自己評価を維持するため、つまり恥や罪悪感を避けるために行動する動機です。例えば、「このキャリアを選ばなければ自分は失敗者だと感じてしまうから」といった理由です。
さらに「外的物質的動機」があります。これは給料や福利厚生といった具体的な報酬を求める動機です。「ホテル業界は給料が良いから」という理由でこの分野を選ぶ場合がこれに当たります。
最後に「外的社会的動機」があります。これは他者からの承認を得たり、批判を避けたりするための動機です。例えば、「両親や友人から認められたいから」という理由でキャリアを選ぶ場合です。
ポルトガルの調査では、ホスピタリティを専攻する学生305名を対象に、これらの動機と教育プログラムへのコミットメントとの関連を調べました。コミットメントは「情緒的コミットメント」(学部やプログラムへの愛着)、「継続的コミットメント」(学部を辞めることのコストを考慮した継続)、「規範的コミットメント」(道義的な理由での継続)の三種類に分けて測定されました。
調査結果では、学生がホスピタリティ業界でのキャリアを選ぶ主な動機として、同一化動機(価値観との合致)、外的物質的動機(給料などの報酬)、内発的動機(楽しさや満足感)が多く見られました。これは、学生たちが観光業界を選ぶ際に、自分の価値観との一致や仕事の楽しさを重視する一方で、将来の経済的見返りも考慮していることを示しています。
興味深いのは、「取り入れ動機」(自己評価の維持)が、すべてのタイプのコミットメントに最も強く関連していたことです。これは、自分の能力を証明したい、失敗したくないという感情が、教育プログラムへの関与を促進することを示しています。例えば、「このプログラムを途中で辞めたら自分は弱い人間だと思われるかもしれない」という気持ちが、困難があってもプログラムを継続する原動力になっているのです。
この結果は、心理学で知られている「自己一貫性の原理」とも合致します。人は一度決めた選択を正当化し、自分の決断が間違っていなかったと思いたい傾向があります。そのため、自分が選んだプログラムに価値を見出し、コミットメントを高める傾向があるのです。
「同一化動機」(価値観との一致)は、特にプログラムに対する情緒的コミットメントを高めることもわかりました。プログラムの内容や理念が自分の価値観と合致していると感じる学生ほど、そのプログラムに愛着を持つようになります。例えば、「おもてなしの心」を大切にする学生が、ホスピタリティプログラムに強い親近感を抱くような場合です。
「外的社会的動機」(他者からの承認や批判の回避)も継続的および規範的コミットメントに関連していました。社会的評価を維持するために、プログラムを継続するということです。
これらの結果から、サステナブル・キャリアを形成する上で動機の多様性を考慮することが重要だと考えられます。楽しさや収入だけでなく、価値観との一致や自己評価の維持といった心理的要素も、長期的なキャリアコミットメントに影響するのです。
脚注
[1] Chudzikowski, K., Gustafsson, S., and Tams, S. (2020). Constructing alignment for sustainable careers: Insights from the career narratives of management consultants. Journal of Vocational Behavior, 117, 103312.
[2] Bal, P. M., and Doci, E. (2018). Neoliberal ideology in work and organizational psychology and its implications for career sustainability. European Journal of Work and Organizational Psychology, 27(5), 536-548.
[3] Stuer, D., De Vos, A., Van der Heijden, B. I. J. M., and Akkermans, J. (2019). A sustainable career perspective of work ability: The importance of resources across the lifespan. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(14), 2572.
[4] Cesario, F., Sabino, A., Moreira, A., Portugal, M., and Correia, A. (2022). Students’ motivation for a sustainable career in the hospitality industry in Portugal. Sustainability, 14(11), 6522.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。