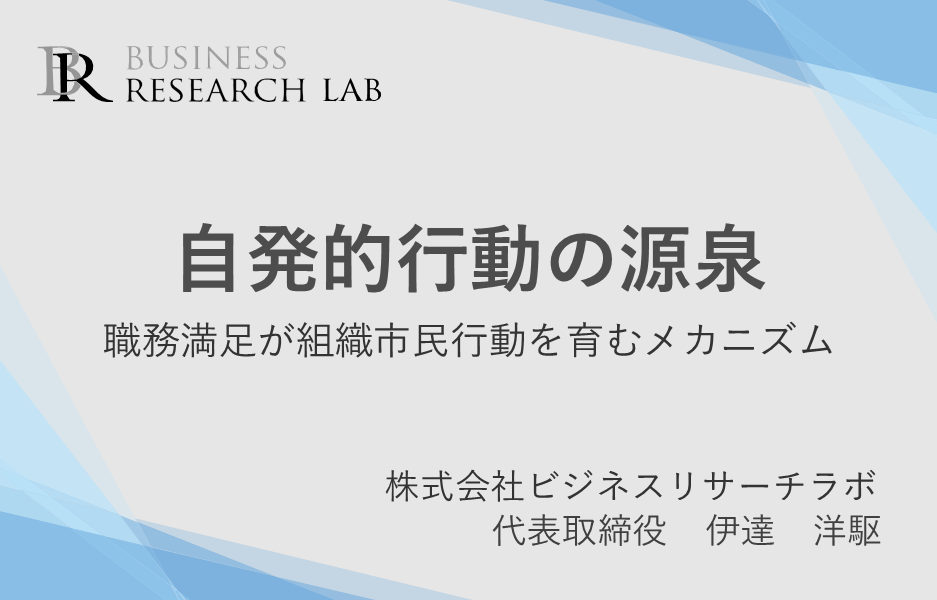2025年9月11日
自発的行動の源泉:職務満足が組織市民行動を育むメカニズム
職場における人間関係や仕事への取り組み方において、多くの人が経験したことがあるのではないでしょうか。同僚が困っているときに手を貸したり、自分の担当でなくても組織のために一歩踏み出して行動したりすること。このような行動は、正式な仕事の一部ではなく、評価されなくても自発的に行われることが多いものです。
こうした行動は専門的には「組織市民行動」と呼ばれます。組織市民行動とは、公式の職務記述には含まれていないけれども、組織全体の効率や有効性を高める自発的な行動のことです。例えば、同僚を助ける、会社の備品を大切に使う、不平不満を言わないなどが含まれます。
どのような人がこうした組織市民行動を取りやすいのでしょうか。その鍵の一つが「職務満足」です。職務満足とは、自分の仕事や職場環境に対する肯定的な感情や態度を指します。
本コラムでは、職務満足と組織市民行動の関係について、その結びつきから、対象による違い、背景にある動機や価値観まで、多角的に掘り下げていきます。これらの知見は、職場環境や人間関係を理解する上で、新たな視点を提供するものになるでしょう。
職務満足は組織市民行動を最も強く予測する
職場で自発的に同僚を助けたり、組織のために進んで行動したりする人は、どのような特徴を持っているのでしょうか。多くの研究によれば、仕事に満足している人ほど、このような組織市民行動を取る可能性が高いことが分かっています。
組織市民行動は、職務記述書には明記されていない自発的な行動を指します。具体的には、同僚への援助、組織のルールの遵守、組織の評判を守ろうとする行動、建設的な提案、自己啓発などが含まれます。これらの行動は強制されたものではなく、従業員の自発的な意思によるものです。
組織市民行動の要因については、様々な研究が行われてきました。それらを総合的に分析した結果、職務満足が組織市民行動を最も強く予測する要因であることが明らかになっています[1]。
この分析では、多数の研究データを統合するメタ分析という手法が用いられました。メタ分析では、個々の研究の限界を超えてより一般的な傾向を見出すことができます。この手法を用いて、職務満足や組織への取り組み、公正さの認識といった態度的要因と、協調性や誠実性などの性格的要因が組織市民行動にどう関連するかが調べられました。
調査の結果、職務満足度は組織市民行動と強い相関関係があることが確認されました。特に、同僚を助けるような「利他的」な行動や、組織のルールを守る「遵守」的な行動との関連が顕著でした。
職務への満足度が高い従業員は、自分の仕事環境に満足しているため、その環境を支える組織や同僚に対して恩返しをしたいという気持ちが生まれやすいと考えられます。職務満足は肯定的な感情状態を表すため、このような状態にある人は他者を助けるような行動を取りやすくなるという説明もあります。
認知された公正さや組織への取り組みも組織市民行動と正の相関を示しましたが、これらの要因は職務満足ほど強い予測力を持っていませんでした。
性格要因に関しては、協調性と誠実性が組織市民行動に対して最も強い関連性を持っていました。協調性が高い人は他者を助けやすく、誠実性が高い人は組織のルールを守る傾向があるためと考えられます。
これらの結果は、態度的要因(とりわけ職務満足)が性格要因よりも組織市民行動をより強く予測することを示しています。しかし、性格も一定の予測力を持っていることから、両方の要因が組み合わさって組織市民行動に影響していると言えます。
組織市民行動は職務満足と強く結びついている
なぜ職務満足と組織市民行動の間に結びつきがあるのでしょうか。その関係を掘り下げてみましょう。
伝統的に、職務満足と職務遂行の関連について多くの研究が行われてきましたが、生産量や仕事の質といった従来の職務遂行の指標では、職務満足との関連が弱く、曖昧な結果が報告されてきました。そこで、研究者たちは「組織市民行動」という概念を導入し、職務遂行の定義を拡張しました。
アメリカ中西部の州立大学で働く非教員の管理職・専門職・技術職従業員77名を対象に実施された調査では、職務満足と組織市民行動の関係が検証されました[2]。この調査では、従業員自身が自分の職務満足度を評価し、組織市民行動については各従業員の直属の上司が評価するという方法が取られました。
組織市民行動の測定には、規則遵守、利他主義、協力性、批判の回避、時間の厳守などの幅広い項目が含まれる30項目の尺度が使用されました。職務満足については、仕事自体、上司、同僚、給与、昇進機会という5つの側面から評価する標準的な尺度が用いられました。
調査の結果、全体的な職務満足と組織市民行動との相関が認められました。とりわけ、上司に対する満足および昇進機会への満足が、組織市民行動と強く関連していることが分かりました。
この結果は、職務満足と組織市民行動の間に確かに強い関係があることを示しています。この関係性が見られた理由としては、次の2点が考えられます。
1つ目は、組織市民行動の自発的・裁量的な性質です。組織市民行動は従業員がより自由に選択できる行動であるため、職務満足などの内的な要因(態度や感情)の影響を受けやすいと考えられます。強制されない分、自分の感情や態度がより直接的に行動に表れやすいのです。
2つ目は、測定尺度のマッチングです。組織市民行動という広範囲の行動を総合的に測定した尺度と、職務満足という一般的な態度測定の間に、より良い対応があったことが考えられます。従来の研究では、特定の業績指標(例えば生産量など)と職務満足という広範な態度との間にずれがあったため、関連性が弱く出ていた可能性があります。
ただし、この調査では交差遅延分析という手法も用いられましたが、職務満足が組織市民行動を引き起こすという一方向の関係は検証されませんでした。これについては、調査期間が短すぎた可能性(6週間)や、組織市民行動が比較的安定した行動であったことが理由として考えられています。
このほか、「上司の支援的態度」や「個人の性格(気質)」など、他の変数が満足と組織市民行動の間の共通原因として働いている可能性も指摘されています。上司のサポートが良ければ職務満足も高まるし、組織市民行動も増えるという関係性です。
組織市民行動は対象により満足とコミットで異なる
職務満足と組織市民行動の間に関連があることを見てきましたが、組織市民行動にも様々な種類があり、その種類によって予測要因が異なる可能性があります。組織市民行動を「対象」という観点から分類し、それぞれに影響を与える要因の違いについて検討します。
組織市民行動は、その行動が向けられる対象によって、「個人指向型(OCBI)」と「組織指向型(OCBO)」の2つに分けることができます。個人指向型の組織市民行動は、同僚を助けるなど特定の個人に向けられた行動であり、組織指向型は組織全体に利益をもたらす行動(例:組織のルールの遵守、組織の評判を守る行動など)を指します。
この区別に基づいて、様々な組織に属するフルタイム従業員461名を対象に実施された調査では、職務満足と組織コミットメント(組織への心理的な愛着や一体感)が、これら2種類の組織市民行動にどのように影響するかが検証されました[3]。
調査では、参加者から職務満足や組織コミットメントに関するデータを収集し、組織市民行動については参加者の上司からの評価を得ることで、自己評価バイアスを最小限にする工夫がなされました。
因子分析の結果、組織市民行動が「個人指向型」と「組織指向型」という異なる因子に分かれることが示されました。さらに、これらは通常の職務遂行である「役割内行動」とも区別されることが確認されました。
職務満足と組織コミットメントがこれらの行動をどのように予測するか分析した結果、次のような傾向が明らかになりました。
個人指向型の組織市民行動(同僚への援助など)には、職務満足が有意に強い予測因子となっていました。仕事に満足している人ほど、同僚を助けるような行動を取る傾向が強いということです。
他方で、組織指向型の組織市民行動(組織への忠誠を示す行動など)には、組織コミットメントがより強く影響していました。組織に対して強い愛着や一体感を持つ人ほど、組織全体のために行動する傾向が強いのです。
役割内行動(正式な職務として求められる行動)については、職務満足も組織コミットメントもそれぞれ有意な予測力を持っていましたが、組織コミットメントの方がより強い予測力を持っていました。
これらの結果は、組織市民行動の種類によって、それを促進する心理的要因が異なることを示しています。個人を助けるような行動は主に職務満足に基づいており、組織全体のために行動することは主に組織コミットメントに基づいているということです。
このような違いが生じる理由としては、行動の対象と心理的要因の間に一種の対応関係があるためと思われます。職務満足は主に職場での人間関係や仕事自体に関する感情であるため、個人に向けられた行動と関連しやすいのでしょう。一方、組織コミットメントは組織全体への愛着であるため、組織に向けられた行動につながりやすいと言えます。
向社会的行動は対象により動機や要因が異なる
より広い概念である「向社会的行動」という観点から、行動の対象による動機や要因の違いについてさらに掘り下げていきます。
向社会的行動とは、他者や集団に利益をもたらすことを目的とした自発的な行動のことです。組織市民行動はこの向社会的行動の一種と考えることができます。従来、職場における向社会的行動と職務満足の関連については、2つの理論的アプローチから説明されてきました。
1つは「社会的交換理論」です。この理論によれば、組織が従業員に対して公平な待遇などの好意的な行動を示すと、従業員はその恩返しとして組織に役立つ行動(向社会的行動)を示すとされています。
もう1つは「気分理論」です。この理論では、職務満足は従業員の肯定的な気分を表しており、このような肯定的な気分が向社会的行動を促進すると考えられています。
しかし、これらの理論は向社会的行動が「誰を対象にしているか」という点を明確に区別していませんでした。そこで、アメリカ南東部の大学に勤務する女性秘書100名を対象に実施された調査では、個人向けと組織向けの向社会的行動を区別した上で、それぞれにどのような心理的プロセスが働いているかが検討されました[4]。
この調査では、各秘書の向社会的行動について、直属の上司と複数の同僚から評価を収集し、併せて秘書自身の職務満足度や価値観、共感性、報酬の公平性に対する認識なども測定されました。
因子分析の結果、向社会的行動は次の3つの次元に分けられました。
- 組織向け向社会的行動(例:組織への忠誠、改善提案)
- 職務内の向社会的行動(役割上当然とるべき行動)
- 個人向け向社会的行動(例:同僚への個人的な配慮や支援)
調査の結果、職務満足は個人向けと組織向けの双方の向社会的行動と正の相関を示しました。しかし、それぞれの行動に影響を与える他の要因には違いが見られました。
個人向けの向社会的行動は、「他者への配慮の価値観」と「共感性」と相関を示しました。他者への配慮を大切にする価値観を持っている人や、共感性の高い人ほど、同僚など特定の個人を助ける行動を取りやすいということです。一方、これらの価値観や共感性は、組織向けの向社会的行動とは有意な相関を示しませんでした。
対して、組織向けの向社会的行動は、「報酬の公平性」と「上司による承認・評価」と相関を示しました。組織内で報酬が公平に分配されていると感じている人や、上司が望ましい行動を認め評価していると感じている人ほど、組織全体に利益をもたらす行動を取っていました。これらの要因は個人向けの行動とは関連がありませんでした。
職務満足の影響を検討したところ、個人向けの向社会的行動については、職務満足が価値観や共感性と並んで独自の影響を示しました。一方、組織向けの向社会的行動においては、職務満足の影響は報酬の公平性や上司からの評価によってほぼ完全に説明されました。
これらの結果から、向社会的行動の対象によって、その発生プロセスが異なることが示されました。個人向けの行動は主に個人の価値観や共感性など性格的・内在的要因に基づいているのに対し、組織向けの行動は主に職場環境における報酬の公平感や上司からの評価といった外部的要因に依存していることが明らかになりました。
組織市民行動は内在化された価値観で高まる
組織市民行動を促進する要因として、「組織コミットメント」の質的な側面に焦点を当てます。組織コミットメントとは、組織に対する心理的な愛着や一体感のことですが、このコミットメントには異なる種類があることが分かっています。組織コミットメントを心理的な愛着という観点から検討した研究によれば、コミットメントには次の3つの異なる次元があります。
- コンプライアンス:外的な報酬を得るために組織に従うという表面的な愛着です。「この会社にいると給料が良いから」という理由で組織に留まるケースが該当します。
- アイデンティフィケーション:組織との一体感や所属感を得るために、組織の価値や態度を受け入れる愛着です。「この会社の一員であることに誇りを感じる」という気持ちに基づくコミットメントです。
- 内在化:組織の価値観や目標が個人の価値観と一致することから生じる、深く本質的な愛着です。「この会社の理念や方向性に共感できる」という理由で組織に貢献するケースです。
これらの3つの次元が従業員の向社会的行動(組織市民行動)や離職にどのように影響するかを分析するため、2つの調査が行われました[5]。1つは大学職員82名を対象にしたもの、もう1つは大学を卒業する学生162名を対象にしたものです。
両方の調査で因子分析を行った結果、コンプライアンス、アイデンティフィケーション、内在化の3つが独立した次元として抽出されました。また、「役割内行動」(正式に求められる行動)と「役割外行動」(自発的な組織市民行動)も2つの次元に分かれることが確認されました。
相関分析の結果、内在化とアイデンティフィケーションは、役割外の向社会的行動(組織市民行動)や組織に留まる意図と強く関連していました。特に内在化は組織に留まる意図を強く予測し、実際の向社会的行動(学校への寄付など)も予測することが分かりました。
一方、コンプライアンスは向社会的行動にはほとんど影響せず、むしろ離職の意図と関連していました。外的な報酬のために組織に留まっている人は、組織市民行動をあまり取らず、場合によっては組織を離れる可能性もあるということです。
これらの結果から、組織コミットメントは単一の概念ではなく、異なる基盤から構成されることが示されました。そして、向社会的行動(組織市民行動)を予測する上で、特に内在化とアイデンティフィケーションが強く影響を与えることが明らかになりました。
この研究は、組織市民行動を促進するためには、外的な報酬によってコンプライアンス型のコミットメントを高めるだけでは不十分であることを示唆しています。むしろ、従業員が組織の価値観に共感し、それを内在化できるような環境づくりが大切です。
脚注
[1] Organ, D. W., and Ryan, K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology, 48, 775-802.
[2] Bateman, T. S., and Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee “citizenship.” Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
[3] Williams, L. J., and Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17(3), 601-617.
[4] McNeely, B. L., and Meglino, B. M. (1994). The role of dispositional and situational antecedents in prosocial organizational behavior: An examination of the intended beneficiaries of prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 79(6), 836-844.
[5] O’Reilly III, C., and Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492-499.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。