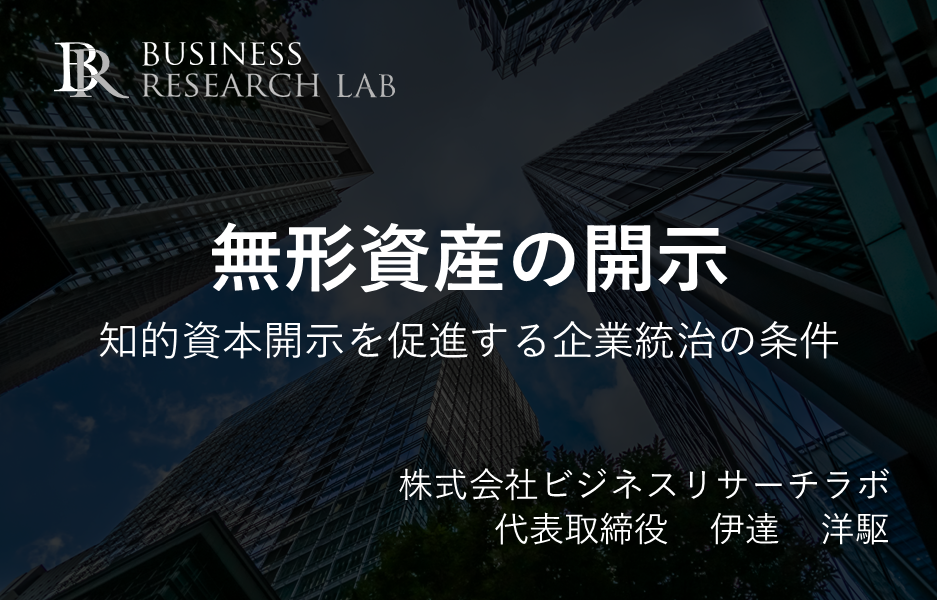2025年9月10日
無形資産の開示:知的資本開示を促進する企業統治の条件
企業の価値は目に見える有形資産だけでなく、知識やブランド、人材といった目に見えない無形の資産(知的資本)によっても左右されるようになりました。知的資本は企業の競争力の源泉の一つであり、持続的な成長を支えます。しかし、これらの見えない資産は従来の財務諸表には十分に反映されておらず、企業の価値を評価する上で課題となっています。
こうした背景から、企業が自発的に知的資本に関する情報を開示する動きが広がっています。投資家や市場関係者にとって、企業の知的資本に関する情報は、将来の成長性や価値創造の可能性を判断する上で手がかりとなります。しかし、すべての企業が積極的に知的資本情報を開示しているわけではありません。どのような条件が整った時に、企業は知的資本の情報を積極的に開示するのでしょうか。
本コラムでは、企業の知的資本開示を促進する要因について、様々な国や地域での実証研究を基に解説します。とりわけ、取締役会の構成や規模、独立性、株主構成などの企業統治(コーポレート・ガバナンス)の仕組みが、知的資本の情報開示にどのように関わっているかを探ります。
知的資本の開示は取締役会規模と非線形の関係
企業の取締役会の規模と知的資本の開示量には、どのような関係があるのでしょうか。この問いに答えるために、メキシコの上場企業を対象とした研究結果を見ていきましょう。
メキシコ証券取引所に上場する100社を対象に、2005年から2007年までの3年間の年次報告書を分析した研究があります[1]。この研究では、企業統治の仕組みの中でも、特に取締役会の特性(規模、独立性、監査委員会の規模、CEO兼任の有無)と所有構造(経営者や家族による持株比率、大株主、機関投資家の持株比率)が知的資本の情報開示にどう関連しているかを調査しました。
メキシコ企業の特徴として、取締役会の規模には大きなばらつきがあることがわかりました。最小で4名、最大で34名と差が大きく、平均的な取締役会の規模は約12名でした。また、家族の持株比率が高く平均約31%であり、CEOと取締役会議長を兼任している企業が44.3%存在することも明らかになりました。
この研究の興味深い発見は、取締役会の規模と知的資本開示の間に非線形の関係が存在することです。具体的には、取締役会の人数が15名までは規模が大きくなるほど知的資本の開示量が増加する傾向がありましたが、15名を超えると逆に開示量が減少していくことが判明しました。
このような非線形の関係が見られるのは、なぜでしょうか。取締役会の規模が適度であれば、多様な専門知識や経験を持つメンバーが集まり、幅広い視点から知的資本の重要性を認識し、その開示を推進する力になります。しかし、取締役会が過度に大きくなると、意思決定の調整が難しくなり、効率的な監視機能が低下することで知的資本開示への積極性も弱まるのかもしれません。
この非線形の関係は、メキシコのコーポレート・ガバナンス基準で推奨されている「取締役会の最大人数は15名程度が望ましい」という指針を支持する結果となりました。実証研究によって、理論的に望ましいとされていた取締役会の規模が、実際に知的資本開示の観点からも合理的であることが裏付けられたということです。
この研究では機関投資家の持株比率と知的資本開示の間に負の関係が見られました。機関投資家の持株比率が高い企業ほど、知的資本の情報開示が少ない傾向がありました。この結果は一見矛盾しているように思えますが、機関投資家が企業に直接アクセスして情報を得られる立場にあるため、公開文書での情報開示の必要性が低下する可能性を示唆しています。
さらに、CEOと取締役会議長を同一人物が務める場合(CEO兼任)については、非線形分析を行った場合にのみ知的資本開示に正の影響が見られました。これは、CEO兼任によってリーダーシップが一本化され、迅速な意思決定や効率的なコミュニケーションが可能になり、結果として知的資本開示が促進されるケースがあることを示唆しています。
この研究結果から、取締役会の規模を考える際には「大きければ良い」「小さければ良い」という単純な二元論ではなく、組織の効率性と多様性のバランスを考慮した「最適な規模」があることがわかります。メキシコ企業の場合は約15名という数字が示されましたが、この数字は国や地域、業種によって異なる可能性があります。
知的資本の開示は取締役会の独立性で促進
取締役会の独立性は、知的資本の開示にどのような影響を与えるのでしょうか。この問いを検討するために、ヨーロッパのバイオテクノロジー企業を対象とした研究結果を見ていきましょう。
2002年から2004年にかけてヨーロッパの証券市場に上場していたバイオテクノロジー企業54社を対象とした研究では、取締役会の特徴が知的資本の自発的開示に与える影響を調査しています[2]。バイオテクノロジー業界が選ばれた理由は、この業界が特に知的資本(研究開発能力、特許、専門知識など)に依存しており、投資家にとってこれらの情報が企業価値を判断する上で重要だからです。
この研究では、知的資本を「内部資本」(例:組織構造、プロセス、研究開発)、「外部資本」(例:顧客関係、ブランド、提携関係)、「人的資本」(例:従業員のスキル、知識、経験)の3つのカテゴリーに分類しました。そして、年次報告書の内容分析を通じて、これらの情報がどの程度開示されているかを測定しました。
研究の結果、取締役会の独立性と知的資本開示の間に正の関係がありました。独立取締役(会社の経営陣から独立した立場で監視・助言を行う取締役)の割合が高い企業ほど、知的資本に関する情報開示が充実していました。特に「内部資本」に関する情報開示が多い傾向が見られました。
独立取締役が多いと知的資本の開示が促進される理由が気になるところです。独立取締役は、経営陣から独立した立場で企業活動を監視するため、情報の透明性や株主への説明責任を重視します。また、外部からの視点で企業を見ることで、知的資本の重要性をより客観的に評価し、その情報開示を推進する役割を果たすことができるのでしょう。
対照的に、取締役会の規模については、大きくなるほど知的資本の総開示量が減少する傾向が見られました。これは先ほど見たメキシコ企業の研究と一部整合する結果です。ただし、外部資本や人的資本に関する開示については、取締役会の規模が大きい企業の方が多いことが見えてきました。取締役会の規模が大きくなると、様々な専門性を持つメンバーが増え、特定の分野(この場合は外部資本や人的資本)に関する情報の重要性が認識されやすくなる可能性を示唆しています。
CEOが取締役会議長を兼務する企業では、特に将来志向の知的資本情報の開示が減少しました。CEOと取締役会議長の役割が分離されていると、経営陣に対する監視機能が強化され、より透明性の高い情報開示が促進される可能性があります。
予想に反する結果として、監査委員会や指名委員会、報酬委員会などの委員会が独立取締役中心に構成されている場合、知的資本の情報開示量はむしろ減少しました。しかし、この結果は情報開示の「質」の向上と関連している可能性が指摘されています。独立性の高い委員会は情報の質を重視し、量よりも質の高い開示を促進する可能性があるのです。
ヨーロッパのバイオテクノロジー企業の研究から得られた知見は、取締役会の独立性が知的資本開示の促進に一定の役割を果たすということです。経営陣から独立した立場で企業活動を監視できる独立取締役の存在が、情報の透明性を高め、知的資本の開示を促進することが明らかになりました。
知的資本の開示は独立取締役と監査委員会で促進
これまで、メキシコ企業とヨーロッパのバイオテクノロジー企業における知的資本開示と企業統治の関係を見てきました。今度は、英国の上場企業を対象とした研究を通じて、知的資本開示を促進する要因について理解を深めていきましょう。
英国のロンドン証券取引所に上場する企業の中から、知的資本が重要視される業種(製薬・バイオ、IT、通信、金融、メディア、食品・飲料など)から100社を選定した研究では、企業統治の構造が知的資本の開示にどのような影響を与えるかを分析しました[3]。
この研究の特徴は、知的資本開示を「人的資本」「構造資本」「関係資本」の3つに分類し、さらに開示の「量」だけでなく「質」も測定したことです。具体的には、開示された項目数の比率(開示指数)、開示に使用された単語数(量的指標)、年次報告書全体に占める知的資本記述の割合(フォーカス)という3つの指標を用いて評価しました。
研究の結果、英国企業の知的資本開示指数の平均は36%で、企業間にかなりのばらつきがあることがわかりました(最低16%から最高56%まで)。また、開示は主にテキスト形式で行われており、数値データや図表の使用は限定的でした。
顕著な発見は、取締役会における独立非執行役員(independent non-executive directors)の割合と知的資本開示の間に正の関係があることでした。独立取締役の割合が高い企業ほど、知的資本に関する情報を多く開示していました。これは先ほど見たヨーロッパのバイオテクノロジー企業の研究結果と一致しており、取締役会の独立性が知的資本開示を促進することを改めて確認できます。
独立取締役が多い企業で知的資本開示が促進される理由としては、独立取締役が経営陣と株主の間の情報の非対称性を低減しようとする動機を持っていることが考えられます。独立取締役は外部からの視点で企業を評価し、投資家にとって価値のある情報(財務諸表に表れない知的資本に関する情報)の開示を推進する役割を果たしているのかもしれません。
対照的に、CEOが取締役会議長を兼務している企業(CEO兼務)については、知的資本開示に統計的に有意な影響は見られませんでした。これはヨーロッパの研究結果とは異なる点です。
この研究では株式所有構造の影響も検証されました。その結果、株式が一部の大株主に集中して保有されている企業では、知的資本開示が抑制されました。特に関係資本(顧客関係、ブランド、提携関係など)に関する情報の開示量が少なくなりました。大株主が企業と直接的な関係を持ち、公開情報以外の経路で情報を得ることができるため、公式な開示の必要性が低くなるためと解釈されています。
英国企業の研究で興味深いのは、監査委員会の規模と開催頻度が知的資本開示に正の影響を与えていたことです。監査委員会のメンバー数が多く、会議の開催頻度が高い企業ほど、知的資本の情報開示が充実していました。
監査委員会は企業の財務報告や情報開示の質を監視する役割を持っており、その活動が活発である企業では、知的資本に関する情報開示も促進されると考えられます。定期的な会議を通じて、監査委員会は経営陣に対して透明性の高い情報開示を促し、知的資本に関する情報の質と量を高める役割を果たしているのです。
さらに、企業規模や企業年齢、収益性などの要因も考慮されています。その結果、企業規模(売上高)が大きいほど知的資本開示が多いことが分かりました。大企業ほど情報開示のリソースが豊富であり、また市場からの情報開示への期待も高いためでしょう。
一方、企業年齢(上場期間)は知的資本開示指数と負の関係を示しました。若い企業ほど知的資本の開示に積極的である可能性を示唆しています。新しく上場した企業は、市場での認知度を高め、投資家の信頼を得るために、積極的に情報開示を行うのかもしれません。
収益性(総資産利益率)は知的資本開示指数と正の関係を示しました。収益性の高い企業は、その成功の背景にある知的資本の価値を開示することで、投資家に対して持続的な競争優位性をアピールしている可能性があります。
英国企業の研究から得られた知見は、独立取締役の存在と監査委員会の活動が知的資本開示を促進する要因であるということです。監査委員会の規模と開催頻度が開示に与える正の影響は、企業統治の中でも監査機能の充実が情報の透明性向上に寄与することを表しています。
脚注
[1] Hidalgo, R. L., Garcia-Meca, E., and Martinez, I. (2011). Corporate governance and intellectual capital disclosure. Journal of Business Ethics, 100(3), 483-495.
[2] Cerbioni, F., and Parbonetti, A. (2007). Exploring the effects of corporate governance on intellectual capital disclosure: An analysis of European biotechnology companies. European Accounting Review, 16(4), 791-826.
[3] Li, J., Pike, R. H., and Haniffa, R. (2008). Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms. Accounting and Business Research, 38(2), 137-159.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。