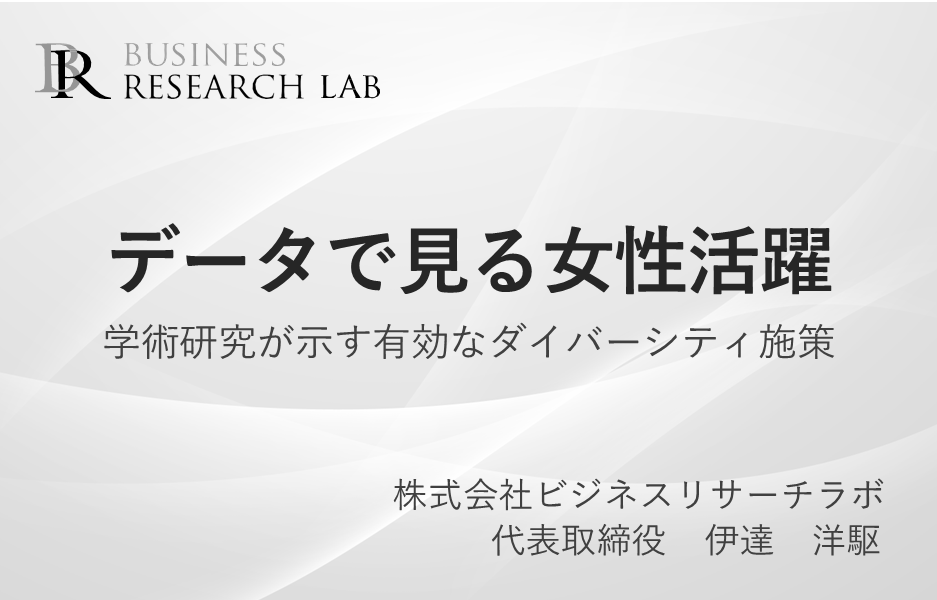2025年9月9日
データで見る女性活躍:学術研究が示す有効なダイバーシティ施策
現代社会において、女性の社会進出や職場における活躍は広く議論されているテーマです。その背景にある実態や要因について、実証的な研究に基づいた理解もまた求められます。女性の働き方や昇進、賃金などに関する課題は、個人の選択や能力の問題ではなく、組織や社会の構造にも深く根ざしています。
本コラムでは、女性活躍に関する学術研究から得られた知見を紹介します。第一に、企業における女性役員の増加が、企業の人員削減にどのような変化をもたらしたのかを見ていきます。第二に、女性管理職を増やすために効果的な施策は何かについて、実証研究から明らかになった事実を解説します。第三に、日本企業における女性の継続就業と育児支援の関係性について検証します。第四に、高学歴女性の所得格差がキャリアの過程でどのように拡大していくのか、その動態を探ります。
女性役員の増加は企業の人員削減を抑制した
企業の取締役会における女性の存在は、経営判断にどのような違いをもたらすのでしょうか。この問いに対して一つの答えを提供している研究があります[1]。2006年にノルウェーで導入された取締役会のジェンダークオータ制に着目しました。ジェンダークオータ制は、上場企業の取締役会に最低40%の女性を登用することを義務付けるものでした。
この制度導入によって、ノルウェーの上場企業の取締役会における女性の割合は、平均で約18%から40%へと増加しました。研究者たちは、このような女性役員の急増が企業の意思決定にどのような変化をもたらしたのかを調査するため、ノルウェーの上場企業と非上場企業、さらには他の北欧諸国の企業を比較しました。
調査では2003年から2009年の期間のデータを分析し、企業の財務状況や雇用状況などを調べました。分析に用いられたのは「差分の差分法」と呼ばれる手法です。これは、クオータ制度の対象となった企業群と対象外の企業群を比較することで、制度導入の効果を測定します。
分析から明らかになったのは、女性役員が増えた企業では、短期的な収益性は若干低下したものの、従業員の雇用が比較的安定していたという事実です。具体的には、クオータ制導入後の企業では、従業員を削減する頻度が減少しました。企業が1%、3%、5%以上の人員削減を行う確率が、他の企業と比べて低くなったのです。
この結果はどのように解釈できるでしょうか。研究者たちは、女性役員が男性役員と異なる価値観や経営スタイルを持っている可能性を指摘しています。女性役員は短期的な利益よりも、従業員の雇用安定性を守ることに価値を置くのかもしれません。
この解釈を裏付けるため、研究者たちは他の可能性も検討しました。例えば、女性役員の増加によって取締役会の機能が低下したのではないか、あるいは経験不足の役員が増えたのではないかという仮説です。しかし、データを分析した結果、役員の平均年齢や経験に大きな変化はなく、取締役会の活動性も低下していないことが確かめられました。人員削減の減少は、取締役会の機能不全ではなく、女性役員特有の経営判断によるものと考えられます。
女性役員がレイオフを避ける理由としては、いくつかの可能性が考えられます。一つは、女性役員が「利他的」または「ステークホルダー志向」であり、株主だけでなく従業員など様々な関係者の利益を考慮しているという点です。もう一つは、短期的なコスト削減よりも、長期的な企業価値を高めるために従業員の士気を保つことを優先する判断かもしれません。
女性役員の増加は、取締役会の構成員の多様化をもたらします。多様な背景や価値観を持つメンバーが意思決定に参加することで、幅広い視点からの検討が可能になります。この研究は、そうした多様性が象徴的な意味を持つだけでなく、実際の企業行動に変化をもたらすことを示しています。
女性管理職は研修より組織責任の明確化で増加する
企業が女性管理職を増やすために取り組んでいる様々な施策は、どれほど効果があるのでしょうか。この問いに答えるために、米国企業が導入している多様性促進施策の効果を分析した研究を見ていきましょう[2]。
この研究の特徴は、多様性促進のための施策がマネジメント層における白人女性、黒人女性、黒人男性の割合にどのような影響を与えるかを、1971年から2002年までの期間において大規模かつ定量的に評価した点にあります。708の民間企業のデータを用いて、各種の多様性施策の効果を検証しました。
分析においては、企業が採用した施策と、実際の管理職層の多様性の変化との関係を調べています。用いられたデータは、米国雇用機会均等委員会が収集した年次報告書と、研究者たちが実施したサーベイを組み合わせたものです。サーベイでは、企業がどのような多様性施策を、いつから導入したかを把握しています。
研究者たちは、企業が採用する多様性促進施策を3つのタイプに分類しました。第一は「組織責任を明確化する施策」で、アファーマティブ・アクション計画、ダイバーシティ委員会、ダイバーシティ担当部署の設置などが含まれます。第二は「管理者のバイアスを減少させる施策」で、ダイバーシティ研修や管理者のダイバーシティ評価などです。第三は「社会的孤立を緩和する施策」で、ネットワーキングやメンタリングプログラムがこれに当たります。
分析の結果、最も効果的だったのは「組織責任を明確化する施策」でした。アファーマティブ・アクション計画の導入は、白人女性と黒人男性の管理職への昇進を有意に促進しました。また、ダイバーシティ委員会や専門スタッフの設置も、白人女性、黒人女性、黒人男性のいずれの管理職比率も高める効果がありました。
一方、「管理者のバイアスを減少させる施策」の効果は限定的でした。例えば、ダイバーシティ研修は黒人女性に対して逆効果となるケースもありました。「社会的孤立を緩和する施策」も効果は限られていました。ネットワーキングは主に白人女性に効果があり、メンタリングは黒人女性にのみ効果を示すという結果でした。
多様性を促進するためには、責任の所在を明確にし、その責任を果たす権限を持った部署や人材を設置することが必要です。組織の構造や責任者を明確に設定することが、個人の偏見を直接的に対象とする施策よりも効果的だということです。
例えば、ダイバーシティ研修は参加者の意識や態度に一時的な変化をもたらすかもしれませんが、それが組織の実践や構造の変化につながらなければ、長期的な効果は期待できません。むしろ、表面的な対応に終わり、かえって反発を招くリスクもあります。
対照的に、ダイバーシティ委員会や専門スタッフの設置は、多様性促進に対する組織的なコミットメントを示し、それを実行する責任と権限を明確にします。これによって、多様性に関する問題が組織の日常的なプロセスや意思決定に組み込まれ、持続的な変化が生じやすくなるのです。
女性管理職の増加を図るためには、個々の管理者の意識改革も大切ですが、それだけでは不十分です。多様性促進の責任を組織的に位置づけ、その取り組みが持続的に行われるような仕組みを構築することが必要です。
女性の継続就業は企業の育児支援で促進される
日本では長年、女性の労働参加率がM字カーブを描くことが知られています。これは、出産・育児期に一度仕事を離れる女性が多いためです。こうした状況の中、日本企業のワークライフバランス(WLB)政策が女性の継続雇用にどのような影響を与えているかを調査した研究を紹介しましょう[3]。
この研究は、日本における男女雇用機会均等法(以下、均等法)施行以降のWLB政策の展開と、その効果を実証しています。均等法は1986年に施行されましたが、同法自体は差別的取り扱いを排除するための法律であり、企業に積極的な措置を求めるものではありませんでした。そこで重要になるのがWLB政策です。
日本におけるWLB政策の展開を振り返ると、1987年に労働基準法が改正され、法定労働時間が週40時間に短縮されました。この背景には主に海外との貿易摩擦への対応がありました。1991年には育児休業法が制定されましたが、これは1990年の合計特殊出生率1.57ショックによる少子化への危機感から生まれたものでした。
その後、エンゼルプラン(1994年)、新エンゼルプラン(1999年)、次世代育成支援対策推進法(2003年)などが制定され、主に少子化対策として育児支援政策が推進されました。また、1999年には男女平等推進の一環として「ファミリー・フレンドリー企業表彰」が開始され、2007年に「男女共同参画・仕事と家庭の両立推進企業表彰」へと統合されました。
この研究によれば、企業がWLB措置を導入する理由として最も多かったのは「企業の社会的責任(CSR)」でした。しかし、女性社員の定着率向上やモチベーション向上を期待する企業も少なくありませんでした。
実際にWLB政策は女性の継続就業に効果があったのでしょうか。分析によれば、マクロ統計からいくつかの変化が見られます。結婚や出産を理由とした女性の離職率は大幅に低下しており、1991年から2009年の間に、結婚による離職率は1.66%から0.69%へ、出産育児による離職率は1.07%から0.62%へと減少しました。
就業構造基本調査によれば、2000年代以降、特に未就学児を持つ女性の就業率は上昇しました。企業内での女性の長期勤続者割合も年々増加傾向にあり、特に20代後半から30代前半の女性の定着率が向上しています。女性の相対賃金や女性管理職割合も上昇傾向にありますが、特に相対賃金の上昇速度は緩やかでした。
しかし、これらの変化がWLB政策の効果なのか、それとも他の要因によるものなのかを判断するためには、より詳細な分析が必要です。そこで、労働政策研究・研修機構による『仕事と家庭の両立支援に関する調査』(2006年)のデータを用いて、次の2つの仮説を検証しました。
- 企業がWLB措置を熱心に実施するほど、女性の企業内定着率が高まる
- 女性の企業内定着率が高いほど、女性管理職割合が高まる
分析の結果、経営トップのWLB指向が強く、育児支援措置が多く実施されるほど、女性の継続雇用年数や離職時期に関する指標は改善することが確かめられました。また、女性の定着率(継続勤務年数)が高い企業ほど、女性管理職の存在や比率が高いことも確認されました。
一方で、男女平等の促進策(ポジティブ・アクション)は、女性の定着率自体には大きな影響を与えなかったものの、管理職割合にはプラスの影響を与えていました。これは、女性の継続就業と管理職登用は別の課題であり、それぞれに対応した施策が必要であることを意味しています。
この研究は、WLB政策、特に育児支援措置が女性の継続就業を促進し、企業内でのジェンダー平等達成に貢献していることを実証的に示しました。企業が積極的にWLB措置を推進し、それが実際に利用されている環境では、女性が出産後も仕事を続け、キャリアを積み重ねていく可能性が高まります。
女性の所得格差は出産後のキャリア中断で拡大する
高学歴の女性にとって、キャリアと出産・育児の両立は課題です。アメリカの金融および企業セクターで働く高学歴のプロフェッショナルを対象に、男女間の賃金格差がどのように形成されるかを分析した研究に注目しましょう[4]。
この研究は、1990年から2006年の間にシカゴ大学ブース経営大学院(MBA)を卒業した男女のキャリアを追跡調査したものです。MBAという同じ高度な教育を受けた男女を比較することで、教育格差以外の要因で生じる賃金差の実態とその原因を解明しようとしました。
研究では、各卒業生が卒業後に就いた職務やキャリア中断の有無、就労時間、所得(賞与を含む)、家族の状況(結婚や子供の有無、配偶者の収入)などを尋ねるオンライン調査が実施されました。このデータを用いて、男女のキャリアと所得の差を経年で追跡する個人単位のパネルデータが構築されました。
分析の結果、MBA卒業直後の所得水準は男女でほぼ同等ですが、卒業5年後には男性が女性より約30%高くなり、10年以上経つとその差は60%近くに達することが明らかになりました。所得の差は、特に金融業界(投資銀行業務等)やコンサルティング業界に進んだ人々で顕著でした。
なぜこのような所得格差が生じるのでしょうか。研究者たちは、その要因として次の3つを特定しました。
- 第一に、MBA取得時のコース選択と成績の違いです。男性はファイナンス関連科目を多く履修し、成績(GPA)も高い傾向があり、これが卒業後の所得に有利に働いていました。
- 第二に、キャリア中断の頻度とその影響の違いです。女性は出産や育児を理由とするキャリア中断が多く、一度でも半年以上のキャリア中断があると所得が大きく下がります(平均で約37%低下)。この影響は長期間にわたって続きます。
- 第三に、週あたりの労働時間の違いです。女性は卒業後の経過年数とともに労働時間が短縮される傾向が強く、特に子供を持つ女性は労働時間が男性より24%少なくなっていました。
研究者たちは、これら3つの要素が、観察された男女間の所得格差の84%を説明すると述べています。同じMBAを取得しても、コース選択、キャリア中断、労働時間の違いによって、所得格差が生じるのです。
女性は出産後、労働市場から離れる傾向があり、特に配偶者の収入が高い場合にその傾向が顕著になることが分かりました。子供が生まれると、女性はフレキシブルな勤務形態や労働時間が短い職種に転職する傾向があり、その結果、所得が著しく減少します。
研究者たちは、観察された男女格差は主に「女性がキャリアよりも家庭や育児を優先すること」によるものと解釈しています。一方で、職場環境の柔軟性の欠如や労働時間の長さという職務特性が、女性のキャリア継続を困難にしている可能性も指摘しています。
興味深いのは、MBA取得者と他の専門職(医師、弁護士、PhD取得者)を比較した分析結果です。MBA取得者の女性は、他の専門職の女性に比べて、キャリア中断や時短勤務の影響を大きく受けることが明らかになりました。その理由として、ビジネスや金融業界特有の競争的なキャリア構造が挙げられています。これらの業界では、長時間労働や継続的なキャリア構築が高い報酬につながるため、出産・育児によるキャリア中断が大きなペナルティとなるのです。
この研究から、高学歴女性の所得格差を縮小するためには、出産・育児期のキャリア中断を最小限に抑える環境づくりが重要であることが分かります。特に、金融やコンサルティングなどの高収入職種では、仕事と育児の両立を可能にする柔軟な勤務形態や、キャリア中断後の円滑な復帰を促す仕組みが求められます。
脚注
[1] Matsa, D. A., and Miller, A. R. (2013). A female style in corporate leadership? Evidence from quotas. American Economic Journal: Applied Economics, 5(3), 136-169.
[2] Kalev, A., Dobbin, F., and Kelly, E. (2006). Best practices or best guesses? Assessing the efficacy of corporate affirmative action and diversity policies. American Sociological Review, 71(4), 589-617.
[3] Kawaguchi, A. (2013). Equal Employment Opportunity Act and work-life balance: Do work-family balance policies contribute to achieving gender equality? Japan Labor Review, 10(2), 35-56.
[4] Bertrand, M., Goldin, C., and Katz, L. F. (2010). Dynamics of the gender gap for young professionals in the financial and corporate sectors. American Economic Journal: Applied Economics, 2(3), 228-255.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。