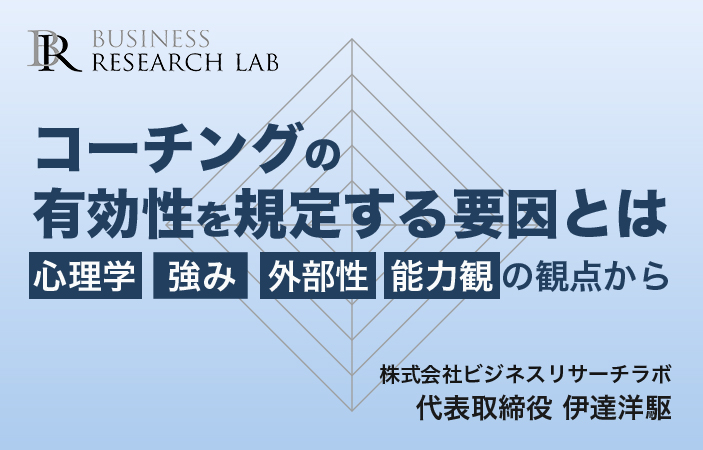2025年9月9日
コーチングの有効性を規定する要因とは:心理学、強み、外部性、能力観の視点から
コーチングは個人の能力開発や組織のパフォーマンス向上に有効な手法として認識されています。指示を与えるのではなく、対話を通じて相手の気づきや行動変容を促すコーチングは、多くの企業で採用されるようになりました。しかし、すべてのコーチングが等しく効果を発揮するわけではありません。コーチングの品質や成果には差があり、その差を生み出す要因を理解することは、組織における人材開発の質を高める上で大事です。
本コラムでは、「どのようなコーチングが特に有効か」という問いについて、いくつかの研究知見を紹介します。コーチングの効果を高める要素として、コーチの持つ心理学的知識、強みに焦点を当てるアプローチ、コーチの立場(外部か内部か)、そして能力観(人間の能力は変化するという信念)の4つの側面に焦点を当てます。
コーチングは心理学知識があると成功する
コーチングの効果を高める要素として、コーチの持つ心理学的知識の重要性が指摘されています。エグゼクティブ・コーチング(経営幹部向けのコーチング)の成果について検討した研究があります。この研究では、1985年から2001年にかけて著者自身がコーチングを担当した経営幹部を対象にアンケート調査を実施し、コーチング成功の要因や効果的なコーチの特徴を探りました[1]。
調査は106人の幹部に送付され、そのうち87人から回答を得ています。この調査では、コーチを選ぶ際の基準、コーチングに対する反応、コーチング成功の指標などについて尋ねています。
幹部たちがコーチを選ぶ際に最も重視した要素は何だったのでしょうか。調査結果によると、「心理学の大学院レベルの教育」が最も高く、次いで「ビジネスやマネジメントの経験」となっています。コーチとしての評価や経験はそんなに高くありませんでした。このことから、幹部たちは深い行動変容を目指す場合には、心理学的背景を持つコーチを高く評価していることがわかります。
この調査では、優れたコーチの資質についても質問しています。回答者の多くが「クライエントとの強い信頼関係」を挙げ、「プロフェッショナリズム」も重視されていました。コーチングの主な目的としては、「個人的な行動変容」、「リーダーシップの効果性向上」、「人間関係の強化」、「個人の成長やキャリア発展」が挙げられました。
幹部たちが評価した効果的なツールとしては、「実際のコーチングセッション」、「360度フィードバック」、「コーチとの関係性」が挙げられています。これらの結果から、個人的接触を重視するコーチングの有効性が強調されています。
コーチングが成功したと考える指標としては、「持続的な行動変容」、「自己理解の深まり」、「より効果的なリーダーシップ」が挙げられました。これらは感情的能力の向上とも密接に関連していました。
この研究から得られた知見として、心理学の知識を持ち、ビジネス経験のあるコーチが特に効果的であることが明らかになりました。幹部はデータに基づいた個人的な洞察を好むため、心理測定ツールも重要です。そして、持続的な学習や行動変容がコーチング成功の大切な指標となっています。
心理学的知識の重要性が強調されるのは、コーチングが単なるスキル伝達ではなく、個人の深い部分での理解や変容を促す過程だからです。心理学の知見を持つコーチは、クライアントの思考パターン、感情、行動の背後にある要因を理解し、それに基づいた効果的なアプローチを取ることができます。
コーチングは強みに注目すると効果が高まる
コーチングの効果を高める2つ目の要素として、「強み」に焦点を当てるアプローチが挙げられます。ある研究では、強みベースのエグゼクティブ・コーチングがリーダーシップの発達にどのような影響を与えるかを、統制群を用いた準実験的デザインで検証しています[2]。
この研究では、リーダーシップ理論として「フルレンジ・リーダーシップ・モデル(FRLM)」を採用し、特に「変革型リーダーシップ」に焦点を当てています。変革型リーダーシップとは、共通のビジョンを通じて部下を鼓舞し、革新的な変化や個別の配慮を通じて部下に影響を与えるリーダーの能力のことです。
研究はオーストラリアの大規模な非営利組織の幹部・管理職37名を対象に実施されました。参加者はコーチング群と待機群(統制群)に分けられ、コーチング群には3ヶ月間(計6セッション、各90分)の強みベースのコーチングが提供されました。その後、両群は役割を交代し、待機群にも同様のコーチングが行われました。
使用されたコーチング手法は、リーダーの強みに関するインタビューとフィードバック、リーダーシップに関する360度評価、そして強み診断ツールを用いた個人の強みの評価に基づく目標設定と行動計画の策定でした。
研究の結果、コーチング群は、待機群に比べて、変革型リーダーシップが顕著に増加したことが判明しました。一方、待機群も一部の下位尺度で若干の向上を示しましたが、コーチング群ほどではありませんでした。
長期的効果についても検証が行われ、両群とも最終的にはコーチング後に顕著なリーダーシップの向上を示しました。コーチング終了後も改善効果が継続し、さらなる改善が見られたことは注目に値します。
さらに、強みベースのコーチング手法に忠実に従った参加者ほど、変革型リーダーシップが大きく向上したことも明らかになりました。プロトコル遵守は、変革型リーダーシップの変化の予測要因となっていました。
強みに焦点を当てるコーチングが効果的である理由はいくつか考えられます。人は自分の弱みよりも強みを伸ばす方が、より早く大きな成長を遂げることができます。強みはすでに持っている能力の土台であり、それを意識的に活用することで、より効果的な行動パターンを築くことができます。
強みに焦点を当てることで、ポジティブな感情が生まれ、学習意欲や挑戦意欲が高まります。弱みに焦点を当てると防衛的になりがちですが、強みに焦点を当てると前向きなエネルギーが生まれます。
強みを意識することで自己効力感が高まり、自信を持って行動できるようになります。自分の強みを理解し、それを活かす方法を知ることで、困難な状況でも自分の能力を発揮できる可能性が高まるのです。
コーチングは外部コーチが効果的
コーチングの効果を高める三つ目の要素として、コーチの立場(外部か内部か)が挙げられます。外部コーチ、ピアコーチ、自己コーチングの相対的な効果性を比較検証した研究を見てみましょう[3]。
この研究は、コーチングの効果が、コーチが誰であるかによってどのように異なるのかを実証的に明らかにすることを目的としています。研究はカナダとオーストラリアで実施された2つの実験から構成されています。
第1研究はカナダのMBA学生30名を対象に行われ、参加者は無作為に外部コーチ群、ピアコーチ群、自己コーチング群の3つに割り当てられました。コーチングは2回実施され、チーム行動を定量的に評価する行動観察尺度が用いられました。外部コーチは経験豊富な教員とMBAプログラムの責任者が務め、ピアコーチは同級生が担当しました。自己コーチングでは、自身で行動目標を立て改善計画を作成しました。
第1研究の結果、外部コーチ群がピアコーチ群よりもチーム行動で顕著に高いパフォーマンスを示しました。コーチの信頼性についても外部コーチが最も高く評価されました。自己コーチングはピアコーチより高い評価を得ましたが、外部コーチには及びませんでした。
第2研究はオーストラリアのEMBAプログラム在籍の管理職者23名を対象に実施され、第1研究の結果を別の国・状況で追試することを目的としていました。測定指標として授業成績という客観的な評価が用いられました。外部コーチはプログラム修了生でコーチングの訓練を受けた人物が務め、ピアコーチは同一人物が担当して質を統一しました。自己コーチングでは明確な行動目標設定が行われました。
第2研究の結果、外部コーチおよび自己コーチング群がピアコーチ群よりも顕著に高い成績を獲得しました。外部コーチはピアコーチよりも顕著に高い信頼性評価を受け、自己コーチングもピアよりも信頼性が高いと評価されました。コーチングプロセスに対する満足度も外部コーチが最も高い結果となりました。
これら2つの研究から、外部コーチが最も効果的であり、その理由としてコーチの信頼性の高さが関係していることが明らかになりました。自己コーチングの有効性は、本人が既に十分なスキルや知識を持っている場合に高まる傾向があります。一方、ピアコーチングは、ピアの知識やスキルに関する認識が不足している場合には有効性が低下する傾向が見られました。
外部コーチが効果的であったのは、なぜでしょうか。外部コーチは組織内の力関係や政治的配慮から自由であり、よりオープンで率直なフィードバックを提供できます。外部コーチは新鮮な視点をもたらし、組織内で当たり前と思われている前提や習慣に疑問を投げかけることもできます。「部外者」であることが、むしろ価値ある洞察をもたらすのです。さらに、外部コーチは多様な組織での経験から得た知見を活かすことができ、より広い文脈での助言を提供できます。
能力が伸びるという信念でコーチングは増える
コーチングの効果を高める4つ目の要素として、能力観(人間の能力は変化するという信念)の影響が挙げられます。ある研究では、管理職が持つ「暗黙の人間観(Implicit Person Theories; IPT)」が部下へのコーチング行動にどのような影響を与えるかを探求しています[4]。
IPTとは、人間の能力や性格が変化可能(増大理論、Incremental Theory)か、固定的(固定理論、Entity Theory)かという個人が持つ暗黙の信念のことです。
研究者たちは、管理職が持つ「増大理論」が部下に対するコーチング行動にプラスの影響を与えるという仮説を立てました。増大理論とは、人間の属性(能力や性格)は努力や経験により変化可能であるという信念です。一方、固定理論とは、人間の属性は基本的に変わらないものであり、努力や経験による変化は限定的だという信念を指します。
この研究は3つのパートから構成されています。第1研究は縦断的フィールド研究で、MBA受講中の管理職45名を対象に行われました。管理職が持つIPTを事前に測定し、約6週間後に部下170名が管理職のコーチング行動を評価する匿名のフィードバック調査が実施されました。
第1研究の結果、IPTは管理職のコーチング行動を予測することが明らかになりました。増大理論を持つ管理職ほど、部下に対するコーチング行動が活発であることが示されたのです。
第2研究は追加のフィールド研究として、管理職92名とその部下105名(MBAプログラム受講者とその直属上司)を対象に行われました。第1研究と異なり、この研究では管理職が評価者を選ばず、評価のフィードバックも受け取らない条件で実施されました。その結果、IPTが管理職のコーチング行動をさらに強く予測することが確認されました。
第3研究は実験的研究で、IPTが管理職のコーチングへの意欲とコーチングの質に影響するかを検証することを目的としていました。MBAプログラムを受講中の管理職115名(そのうち62名が「固定理論」保持者として分類)が参加し、固定理論を持つ管理職を2群に無作為に割り当てました。一方の群には「増大理論」への転換を促すワークショップが提供され、もう一方の群にはプラセボコントロールとしてのワークショップが提供されました。
介入後6週間後に、仮想的な部下のパフォーマンスをビデオで見せ、管理職のコーチング意欲、提供する改善提案の量と質を測定しました。その結果、増大理論の介入を受けた群は、コーチングの意欲、提供した改善提案の量および質のすべてがプラセボ群より顕著に高いことが明らかになりました。
これら3つの研究から、増大理論を持つ管理職は部下をより積極的にコーチングすることが示されました。重要なことに、実験的研究によって、固定理論を持つ管理職であっても、適切な介入によって増大理論に転換することが可能であり、それによって実際にコーチング行動が促進されることが明らかになりました。
増大理論を持つ管理職は、部下の能力は努力や学習によって向上すると信じているため、コーチングという成長支援活動に意義を見出しやすいと思われます。「この人は変わらない」と思ってしまえば、コーチングに時間やエネルギーを投資する動機は低下してしまうでしょう。
増大理論を持つ管理職は、失敗やミスを学習の機会と捉える傾向があります。そのため、部下がミスをおかした際も、批判するのではなく、その経験から学ぶことを促すコーチング的なアプローチを取りやすいのです。逆に、固定理論を持つ管理職は、ミスを能力不足の証拠と見なし、指導よりも評価的なフィードバックに傾く可能性があります。
脚注
[1] Wasylyshyn, K. M. (2003). Executive coaching: An outcome study. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 55(2), 94-106.
[2] MacKie, D. (2014). The effectiveness of strength-based executive coaching in enhancing full range leadership development: A controlled study. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 66(2), 118-137.
[3] Sue-Chan, C., and Latham, G. P. (2004). The relative effectiveness of external, peer, and self-coaches. Applied Psychology: An International Review, 53(2), 260-278.
[4] Heslin, P. A., Vandewalle, D., and Latham, G. P. (2006). Keen to help? Managers’ implicit person theories and their subsequent employee coaching. Personnel Psychology, 59(4), 871-902.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。