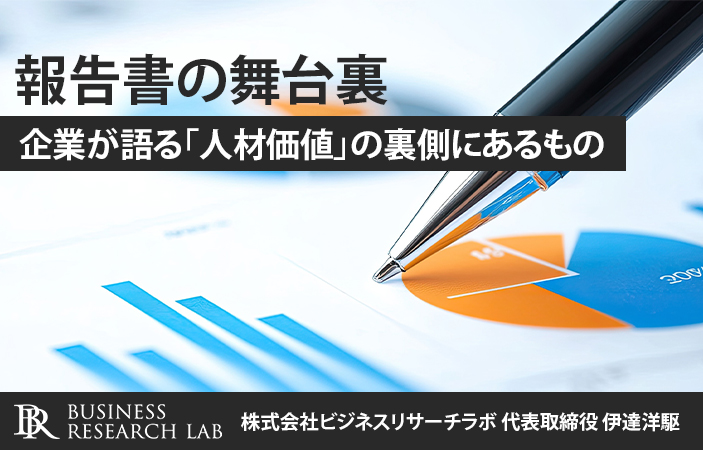2025年9月5日
報告書の舞台裏:企業が語る「人材価値」の裏側にあるもの
企業経営において「人」の価値が見直されています。従業員の知識やスキル、経験といった「人的資本」が企業の競争力を左右する要素となっているからです。知識経済の進展によって、企業価値の源泉が知的資産へとシフトしています。
このような中で、企業が持つ人的資本に関する情報を外部に開示する動きが広がっています。年次報告書やサステナビリティレポートなどで、従業員の教育訓練、多様性、満足度、生産性といった情報を自主的に公開する企業が増えているのです。しかし、人的資本の開示は企業によって内容や質にばらつきがあり、統一された基準も確立されていません。
なぜ企業は人的資本を開示するのでしょうか。開示することで企業にどのような利益があるのでしょうか。また、開示の実態はどのようになっているのでしょうか。本コラムでは、人的資本開示の背景にある理由を探り、現状と課題について記述します。人的資本の開示が情報提供の枠を超えて、企業の戦略的行動として機能している側面や、理想と現実のギャップについても掘り下げていきます。
人的資本の開示不足は企業固有性の軽視に起因
「人材が最も重要な資産である」と口にする企業は多いにもかかわらず、実際の情報開示の現場では人的資本に関する情報が十分に公開されていない矛盾が存在します。このパラドックスはなぜ生じるのでしょうか[1]。
多くの企業では、顧客関係やブランド価値などの外部資本や、社内のプロセスやシステムといった内部構造資本については比較的詳細な情報を開示していますが、人的資本に関する情報の開示は限定的であることが実証研究から明らかになっています。例えば、スペイン、イタリア、マレーシアなど世界各国での調査結果を見ると、知的資産の中でも人的資本は最も開示が少ないカテゴリーとなっています。この現象は世界的に共通しており、一部のスリランカやニュージーランドなどを除いて広く観察されています。
この開示不足の原因は、従来の人的資本の概念化にあると考えられます。これまでの知的資産研究では、人的資本を主に個人が持つ知識やスキルの「ストック」(在庫)として捉えてきました。従業員の能力や経験、専門知識などを「企業が所有する資産」として静的に見る視点です。この見方は、従業員個人の一般的な能力やスキルを中心に考えるため、それらが企業間で比較的容易に移転可能であることを暗黙のうちに前提としています。
しかし、この概念化には問題があります。それは「企業固有性」の視点が欠けていることです。企業固有性とは、ある企業に特有の文脈や環境の中でのみ価値を発揮する知識やスキルのことを指します。実際の企業活動では、一般的な知識やスキルよりも、その企業特有の業務プロセスや文化、システムと結びついた知識やスキルこそが競争優位の源泉となるケースが多いのです。
例えば、ある技術者が持つプログラミングスキルは一般的には他社でも活用できる汎用的な能力ですが、その技術者が特定の企業の独自システムや開発文化の中で培った知識や経験は、他社に移っても同じ価値を発揮するとは限りません。こうした企業固有の文脈に埋め込まれた人的資本こそが、企業の競争力の核心部分です。
リソース・ベースド・ビューの視点から人的資本を捉え直すと、その本質が見えてきます。この理論によれば、企業の持続的な競争優位は、次の特性を持つ資源から生まれます。
- 稀少性:他社が持っていない
- 模倣困難性:簡単に真似できない
- 代替不可能性:他の資源で代替できない
- 価値創造能力:顧客価値を生み出せる
人的資本をこの視点で捉えると、従業員の知識やスキルの集合体ではなく、企業特有の文脈の中で形成され、機能する資源であることが分かります。従業員が持つ知識が企業固有の仕組みや文化と結びつき、他社が容易に模倣できない形で価値を創出するプロセス全体が人的資本です。
このような企業固有の人的資本の形成には、人的資源管理(HRM)の施策や組織文化が関わっています。いかに優秀な人材を採用しても、それを企業の競争優位につなげる組織的な仕組みがなければ、個人の能力は十分に発揮されません。従業員の潜在能力を引き出し、企業特有の価値創造につなげるためには、評価制度、教育研修システム、組織文化の形成などが必要です。
ここに人的資本開示の難しさがあります。従来の開示アプローチでは、従業員数や平均勤続年数、資格保有者数といった一般的で測定しやすい指標に焦点が当てられがちでした。これらの指標は確かに人的資本の一側面を表しますが、企業固有性という核心部分を捉えきれていません。企業固有の文脈の中での人的資本の価値や、それを形成するHRM施策の効果を数値化して外部に説明することは容易ではありません。
さらに、企業固有の人的資本は競争優位の源泉でもあるため、詳細な情報を開示することで競合他社に模倣される可能性も考慮する必要があります。どこまで開示するかのバランスも難しい判断となります。
このように考えると、人的資本の開示不足は、従来の概念化が企業固有性という本質的な側面を軽視してきたことに起因すると言えます。人的資本を個人の能力やスキルのストックとしてではなく、企業固有の文脈の中で機能する戦略的資源として捉え直す必要があります。その上で、人的資本がどのように企業価値の創出につながるのかを説明できる新たな開示フレームワークの構築が求められているのです。
人的資本の開示は企業が社会的批判を避ける手段
企業はなぜ人的資本に関する情報を自主的に開示するのでしょうか。その背景には、情報を提供するという表面的な理由以上に、複雑な社会的・政治的動機が存在しています。
スリランカで行われた研究は、企業が年次報告書で人的資本情報を開示する動機を浮き彫りにしています[2]。この研究では、コロンボ証券取引所に上場する時価総額上位30社の年次報告書を分析し、さらに人事担当役員や上級管理職へのインタビューを実施しました。その結果、人的資本開示が企業と社会・政府・投資家との間の緊張関係を緩和するための戦略的ツールとして機能していることが明らかになりました。
最も頻繁に開示された人的資本情報は「従業員関係」に関するものでした。企業が従業員の功績を称える表彰制度や、社内活動の様子を報告するといった内容です。一見すると従業員の士気向上が目的のように見えますが、その背後には別の意図がありました。この時期に、調査対象企業の多くが技術革新を進める過程で半熟練労働者の削減を行っていたのです。従業員との良好な関係を強調することで、人員削減に対する社会的批判を和らげる狙いがあったと考えられます。
次に多かったのは「従業員の生産性測定」に関する情報でした。従業員一人当たりの付加価値といった指標を示すことで、企業が社会全体の利益に配慮していることをアピールする狙いがありました。同時に、雇用水準を明示することで政府からの規制圧力を回避する目的もありました。
対照的に、「公平性」と「安全管理」に関する情報は極めて少ないことが分かりました。公平性(性別・民族・障がい者雇用など)に関する開示が少なかった理由には、テロの脅威による特定民族の雇用リスク、女性雇用に関する文化的背景、障がい者雇用のコスト増加懸念などがありました。また安全管理については、内戦状態にあった当時のスリランカ社会が「安全の欠如」を当たり前と受け止めていたため、積極的な開示が社会や政府からの支持獲得につながらなかったと考えられます。
この調査から見えてくるのは、企業が人的資本情報を選択的に開示することで、自社の利益追求を円滑に進めようとする戦略的行動です。企業が利益最大化を図るためには、様々な関係者からの支持や協力が必要です。社会(労働者やコミュニティ)、政治(政府)、経済(資本提供者)との関係を良好に保つための手段として、人的資本情報の開示が利用されています。
人的資本開示のもう一つの特徴は、企業が自社に有利な情報を選択的に開示する傾向があることです。従業員教育への投資額やトレーニングプログラムのような肯定的な側面は積極的に開示される一方、労働問題や雇用の不安定性のような否定的な側面はあまり開示されません。情報開示が中立的な事実提供ではなく、企業イメージの向上や批判回避を目的とした戦略的コミュニケーションであることを意味しています。
開示される人的資本情報の選択は、各国の社会的・文化的背景によっても異なります。例えば、労働者の権利が強く保護されている国では、雇用の安定性や労働条件に関する情報がより詳細に開示されるでしょう。一方、労働市場の流動性が高い国では、従業員の能力開発や成果に関する情報が中心となります。こうした違いは、各社会における企業と利害関係者との力関係を反映していると考えられます。
人的資本開示が企業の戦略的行動であるという視点は、開示情報の解釈にも影響を与えます。企業が公開する人的資本情報は必ずしも実態を正確に反映しているとは限らず、企業と利害関係者との関係調整という文脈の中で理解する必要があります。投資家や分析家は、開示された情報の背後にある企業の動機を考慮し、批判的に評価することが求められるでしょう。
人的資本の開示と企業の実際の管理活動は乖離する
企業が年次報告書などで外部に開示する人的資本情報は、企業内部で実際に行われている人的資本管理活動を正確に反映しているのでしょうか。この問いに答えるために、スウェーデンの企業を対象とした研究が行われました[3]。この研究では、企業の年次報告書における人的資本開示内容と、企業内部の人的資本管理実務との関連性が検証されました。
調査はストックホルム証券取引所に上場する27社を対象とし、実際に回答を得た16社のデータを分析しています。研究者たちは、各企業の年次報告書を内容分析して人的資本開示項目を抽出すると同時に、各企業のCFOにアンケートを送付して人的資本管理の実際の重要性に関する評価を収集しました。分析対象となったのは、従業員構成(年齢、性別、国籍など)、従業員の健康と満足度、教育とトレーニング、採用・キャリア・報酬、従業員一人当たりの収益・付加価値といった項目です。
この調査から得られた結果は示唆に富むものです。全体的には人的資本の開示情報と内部管理活動との間に統計的な相関関係が認められましたが、個別企業や産業ごとの詳細な分析では、この相関関係は限定的で弱いことが明らかになりました。一部の企業や業種では比較的強い相関が見られましたが、統計的に有意な相関が確認されなかった業種もありました。
さらに、企業が内部で重要視している人的資本の項目と、実際に年次報告書で開示する項目には必ずしも一致が見られないことも分かりました。これは、企業内部で重要だと認識されている人的資本管理活動が、必ずしも外部への情報開示に反映されていないことを意味します。
なぜこのような乖離が生じるのでしょうか。研究者たちはいくつかの理由を指摘しています。一つ考えられるのは、戦略的情報が競合企業に漏れるリスクです。人的資本管理の具体的な方法や成果は、企業の競争優位の源泉となる場合があります。こうした情報を詳細に開示することで、競合企業に模倣される可能性があるため、企業は戦略的に重要な情報の開示を控える傾向があります。
例えば、ある企業が独自の人材育成プログラムを通じて高い生産性を実現しているとします。このプログラムの詳細な内容や成果を開示することで、競合企業が同様のアプローチを採用し、競争優位が失われる可能性があります。そのため、企業は一般的な情報のみを開示し、本当に差別化につながる要素については開示を控えることになります。
二つ目の理由は、開示に伴う追加コストの存在です。人的資本情報を収集、分析、検証して開示するためには、相応の人的・金銭的コストがかかります。詳細な情報を正確に開示するためには、社内の様々な部門からデータを収集し、整合性を確認する必要があります。このコストが便益を上回ると判断される場合、企業は必要最低限の情報開示にとどめる可能性があります。
三つ目の理由として、人的資本指標の測定や報告のフレームワークが不明確であることが挙げられます。物理的資産や財務情報と異なり、人的資本は目に見えない無形資産であり、その価値や効果を客観的に測定することは容易ではありません。統一された測定基準や報告フレームワークが存在しないため、企業は自社にとって都合の良い指標や数値を選択的に開示することが可能です。
これらの要因により、企業内部で実際に行われている人的資本管理活動と、外部に開示される情報との間にギャップが生じると考えられます。この乖離は、人的資本開示の信頼性や有用性に疑問を投げかけるものです。投資家や分析家が企業評価の材料として人的資本情報を活用する際、この点に留意する必要があります。
脚注
[1] Abhayawansa, S., and Abeysekera, I. (2008). An explanation of human capital disclosure from the resource-based perspective. Journal of Human Resource Costing and Accounting, 12(1), 51-64.
[2] Abeysekera, I. (2008). Motivations behind human capital disclosure in annual reports. Accounting Forum, 32(1), 16-29.
[3] Ax, C., and Marton, J. (2008). Human capital disclosures and management practices. Journal of Intellectual Capital, 9(3), 433-455.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。