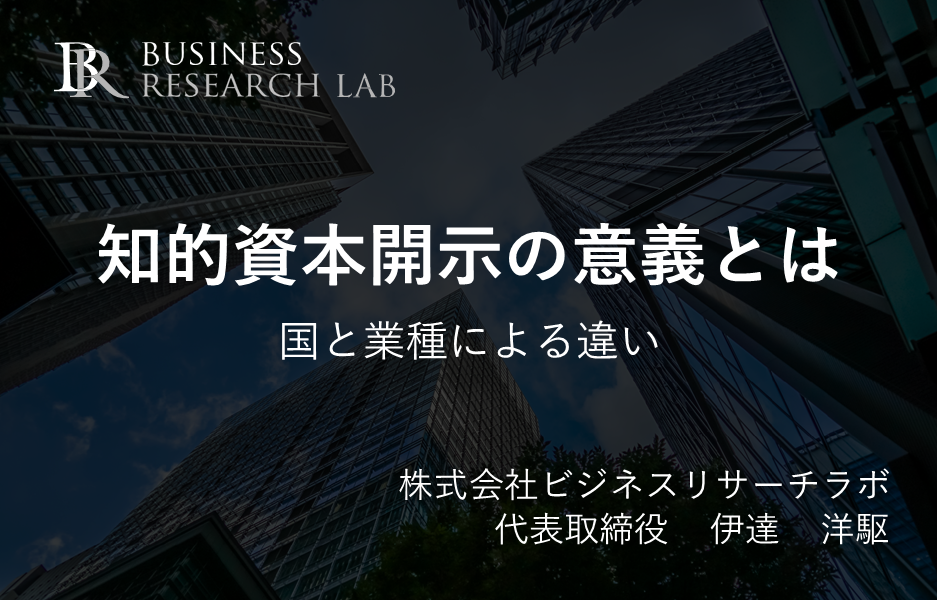2025年9月4日
知的資本開示の意義とは:国と業種による違い
企業の価値を決める要素として、物的資産だけでなく、無形資産がますます重要になっています。「知的資本」と呼ばれる無形資産には、企業が持つ知識やブランド力、顧客との関係性、組織内の仕組みなど様々な要素が含まれます。こうした目に見えない資産こそが企業の競争力の源泉となっているケースが見られます。
しかし、これらの知的資本は従来の会計基準では十分に評価されず、財務諸表に反映されにくいという課題があります。そのため、投資家や利害関係者が企業の価値を理解するためには、企業が自主的に知的資本に関する情報を開示しなければなりません。
各国の企業は、年次報告書やIPO(新規株式公開)の目論見書などを通じて、知的資本に関する情報を自主的に開示していますが、その実態は国や地域、業種によって異なります。この違いはなぜ生じるのでしょうか。
本コラムでは、知的資本の開示に関する国際的な動向として、オーストラリアと香港の事例を紹介します。また、様々な業種における知的資本開示の違いや、特にハイテク企業における知的資本開示の実態について見ていきます。
知的資本の開示はオーストラリアが香港より活発
知的資本の開示については、国や地域によって違いがあることが分かります。例えば、オーストラリアと香港の上場企業における知的資本の開示状況の差を見てみましょう[1]。
オーストラリアの企業は香港の企業と比較して、知的資本に関する情報をより積極的に開示する傾向にあります。オーストラリアの上場企業の年次報告書における知的資本の開示項目数は平均31.6項目であるのに対し、香港の企業では平均13.2項目にとどまっています。オーストラリア企業が香港企業の2倍以上の情報量を開示していることが分かります。
この違いが生まれる理由は何でしょうか。一つは、オーストラリアと香港では企業文化や情報開示に対する姿勢が異なることが考えられます。オーストラリアでは企業の透明性や情報開示が社会的に高く評価される文化がある一方、香港では伝統的に情報の非公開性がより許容される環境にあるとされています。
さらに、開示される知的資本の種類にも違いがあります。知的資本は一般的に「内部資本」「外部資本」「人的資本」の3つに分類されますが、オーストラリア企業ではこれらの割合に偏りが見られます。オーストラリア企業の知的資本開示の内訳は、外部資本が49%、内部資本が41%、人的資本が10%となっています。要するに、顧客関係やブランドなどの外部資本と、組織構造や業務プロセスなどの内部資本に関する情報が大部分を占め、従業員のスキルや知識に関する人的資本の情報はあまり開示されていないのです。
一方、香港企業の開示内容は比較的バランスが取れており、外部資本37%、人的資本35%、内部資本28%とほぼ均等に分布しています。香港企業は人材に関する情報をオーストラリア企業よりも多く開示する傾向にあり、これは人材重視の経営姿勢を反映している可能性があります。
オーストラリア企業が開示する知的資本項目を見ると、「ビジネス提携」や「経営哲学」が最も多く報告されています。次いで「経営プロセス」が続きます。こうした項目が多く開示される背景には、企業が自社の経営方針や戦略的パートナーシップについて投資家や利害関係者に伝えたい意図があると思われます。
知的資本情報は年次報告書のどの部分に記載されているのでしょうか。オーストラリア企業では、知的資本に関する情報は主に「ビジネス・運営」セクションで報告されており(695回)、財務セクションでの報告は少ない(53回)ことが分かっています。このことは、知的資本が企業の財務活動というよりも、ビジネスモデルや事業戦略の一部として捉えられていることを示唆しています。
企業規模による差異も見られます。大規模な企業ほど知的資本に関する情報を多く開示する傾向があり、これはオーストラリアと香港の両国に共通しています。大企業は一般的に情報開示に費やせるリソースが多く、また社会的責任の観点からも積極的な情報開示が求められることが多いため、このような結果になっているのでしょう。
時間的変化に目を向けると、オーストラリアでは1998年から2002年にかけて知的資本の開示量が増加しています。これは企業が徐々に知的資本の重要性を認識し、その情報を積極的に外部に伝えるようになったことを表しています。
しかし、両国に共通する課題もあります。それは、開示される知的資本情報のほとんどが定性的であり、定量的な情報が少ないことです。知的資本を定量的に測定することは難しいという現実がありますが、この定量化の不足は投資家が企業間の比較を行う際の障害となりえます。
知的資本の開示に関する統一的な基準やガイドラインがないため、企業間で開示内容や量にばらつきが見られます。これは投資家が企業の知的資本を評価する際の一貫性や比較可能性を損なう要因となっています。
知的資本の開示は業種によって異なる
企業による知的資本の開示は、国や地域による違いだけでなく、業種によっても異なります。この違いはなぜ生じるのでしょうか。また、どのような業種で知的資本の開示が活発に行われているのでしょうか。
オーストラリアの上場企業を対象とした調査によると、知的資本の開示量には業種間で顕著な差異があることが判明しています[2]。「ヘルスケア」と「情報技術(IT)」業種の企業が最も多く知的資本に関する情報を開示しており、一方で伝統的な製造業や資源産業などでは比較的少ない傾向にあります。
この業種間の違いが生じる理由としては、業種ごとのビジネスモデルや競争優位の源泉の違いが挙げられます。ヘルスケアやIT業種では、企業価値の多くが特許や技術力、研究開発能力などの無形資産に依存しています。そのため、これらの業種の企業は自社の知的資本の価値を投資家や市場に伝えることに高い優先順位を置いているのでしょう。
例えば、製薬企業にとっては新薬の開発パイプラインや研究能力が将来の収益を左右します。同様に、IT企業にとってはソフトウェア開発力や技術革新能力が競争力の源泉となります。これらの業種の企業は、自社の無形資産の価値を市場に認識してもらうために、積極的に知的資本に関する情報を開示します。
開示される知的資本の種類にも業種間で違いが見られます。調査によると、オーストラリア企業全体では「構造資本」(組織の構造やプロセス、知的財産など)に関する開示が最も多く、「人的資本」(従業員のスキルや知識など)や「関係資本」(顧客との関係性など)の開示は比較的少ないことが分かっています。
とりわけ頻繁に開示される項目として「知的財産(Intellectual Property)」が挙げられます。これは特許や商標、著作権などの法的に保護された知的資産を指し、年次報告書内で最も多く言及される知的資本関連用語となっています。知的財産は他の知的資本の要素と比べて比較的定義が明確で測定しやすい特性があり、企業が開示しやすい項目であると言えるでしょう。
業種による知的資本開示の差異を説明するための検証も行われています。オーストラリアの125社を対象とした分析の結果、業種タイプ(特にヘルスケアとIT)は知的資本開示に対して有意な正の影響を及ぼしていることが確認されました。ヘルスケアやIT業種に属している企業は、他の業種の企業と比較して統計的に有意に多くの知的資本情報を開示していると言えます。
業種以外の要因としては、企業規模も知的資本開示に対して有意な影響を持つことが確認されています。企業規模(総資産の規模)が大きいほど、知的資本に関する情報を多く開示します。大企業ほど情報開示のためのリソースを多く持ち、また市場や規制当局からの期待も高いためと考えられます。
一方で、理論的には知的資本開示の重要な動機と考えられていた「情報の非対称性」(企業と投資家間の情報格差)は、期待に反して知的資本開示を促進する要因ではないことが明らかになりました。情報の非対称性が大きい企業ほど知的資本を多く開示するという仮説は支持されなかったのです。
この結果は、企業の知的資本開示が必ずしも情報格差の解消を主目的としているわけではなく、むしろ業界の慣習や競争環境、企業規模などの要因によって決定される部分が大きいことを意味しています。
知的資本の開示はハイテク企業で特に活発
知的資本の開示パターンを詳しく見ていくと、ハイテク企業において知的資本の開示が活発であることが明らかになります。これはなぜでしょうか。デンマークの新規株式公開(IPO)企業を対象とした調査から、ハイテク企業における知的資本開示の実態とその背景について探ってみましょう。
デンマークのコペンハーゲン証券取引所に1990年から2001年の間に上場した68社のIPO目論見書を分析した調査によると、ハイテク企業(IT企業やバイオテクノロジー企業など)はローテク企業と比較して、統計的に有意に多くの知的資本情報を開示していることが分かりました[3]。
ハイテク企業が知的資本開示に積極的な理由はいくつか考えられます。第一に、ハイテク企業のビジネスモデルは本質的に知識や技術、イノベーション能力などの無形資産に依存しています。例えば、ソフトウェア企業にとっては、物理的な設備よりも、プログラミング技術や知的財産、顧客基盤などが企業価値の源泉となります。そのため、ハイテク企業は自社の価値を投資家や市場に理解してもらうために、これらの無形資産に関する情報を積極的に開示する必要性が高いわけです。
第二に、ハイテク企業、特にIPOを行う若い企業は往々にして従来の財務指標では評価が難しいという特徴があります。多くのハイテク・スタートアップは、設立から数年間は赤字経営であったり、売上が少なかったりすることが普通です。そうした状況で投資家から資金を調達するためには、将来の成長可能性や現在保有している技術的優位性などを積極的にアピールする必要があります。知的資本の開示はそのための有効な手段となります。
デンマークの調査では、知的資本の開示内容を6つのカテゴリー(従業員、顧客、情報技術、プロセス、研究開発、戦略的記述)に分類し、各カテゴリーの開示状況を時系列で分析しています。その結果、全体的に1990年代を通じて知的資本の開示量が増加する傾向が見られましたが、2000年以降はやや減少に転じていることも分かりました。
この増加傾向は、1990年代後半のITバブル期と重なっています。当時はインターネット関連企業を中心にハイテク企業への投資熱が高まり、多くのハイテク企業がIPOを行いました。そうした市場環境の中で、投資家の関心を引くために知的資本の開示が重視されたと考えられます。一方、2000年以降の不況期には、投資家がより慎重になり、財務的な堅実性を重視する傾向が強まったことが、知的資本開示の減少につながった可能性があります。
ハイテク企業における知的資本開示の特徴として、研究開発(R&D)に関する情報が多く含まれる点も挙げられます。研究開発投資は将来の製品やサービスの基盤となるため、バイオテクノロジーやIT企業などでは、研究開発パイプラインや技術的ブレークスルーなどの情報が開示されることがあります。
ハイテク企業では人的資本に関する情報も比較的多く開示されます。技術系の人材の質や量は、ハイテク企業の競争力を左右するため、従業員のスキルや知識、経験などに関する情報が重視されます。
デンマークの調査では、IPO前に経営陣が株式を保有している企業の方が知的資本開示が多いという結果も得られています。経営陣がIPOの利益を最大化しようとするインセンティブがある場合、企業の内在価値を市場に伝えるために知的資本開示を促進する可能性があるのかもしれません。
一方、企業規模(従業員数)と企業年齢(設立からの経過年数)は知的資本開示量に対して統計的に有意な影響を示さなかったことも分かっています。ハイテク企業における知的資本開示が、企業の規模や歴史よりも、業種特性や経営陣のインセンティブによって左右されることを示しています。
IPO目論見書における知的資本開示の意義は、通常の年次報告書での開示とは少し異なります。IPO目論見書は将来的な投資家に対する最初の公式な情報開示であり、企業の将来性や成長戦略、競争優位性などを伝えるための媒体です。ハイテク企業にとっては、財務実績がまだ限られている段階で、自社の潜在的価値を伝えるための知的資本開示が重要になります。
IPO時の知的資本開示は、企業の透明性を高め、投資家との情報の非対称性を減少させる効果もあります。これによって、企業は資本市場からより有利な条件で資金を調達できる可能性が高まります。新興のハイテク企業にとって、適切な知的資本開示は企業価値評価の向上につながる可能性があるのです。
脚注
[1] Guthrie, J., Petty, R., and Ricceri, F. (2006). The voluntary reporting of intellectual capital: Comparing evidence from Hong Kong and Australia. Journal of Intellectual Capital, 7(2), 254-271.
[2] Bruggen, A., Vergauwen, P., and Dao, M. (2009). Determinants of intellectual capital disclosure: Evidence from Australia. Management Decision, 47(2), 233-245.
[3] Bukh, P. N., Nielsen, C., Gormsen, P., and Mouritsen, J. (2005). Disclosure of information on intellectual capital in Danish IPO prospectuses. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 18(6), 713-732.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。