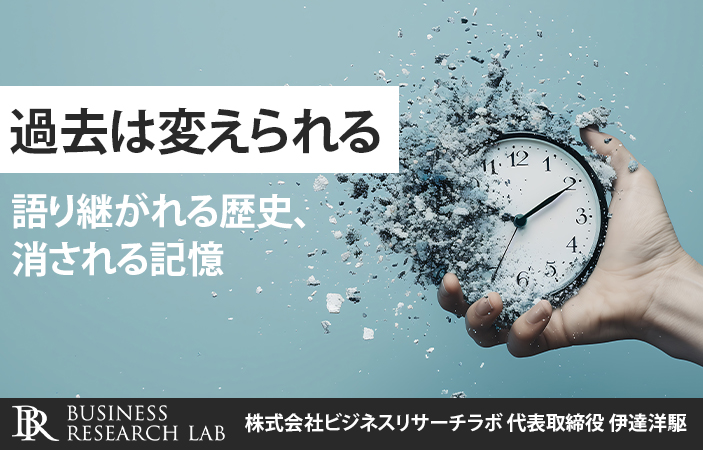2025年9月4日
過去は変えられる:語り継がれる歴史、消される記憶
私たちは歴史を不変の事実として受け止める習慣があります。過去は既に起きたことであり、変えることができないものだと考えます。しかし、組織における歴史とは、そのような固定的なものなのでしょうか。組織の歴史は、語り手によって解釈され、状況に応じて選択的に利用されるものであることが近年の研究で明らかになっています。経営者は自社の過去を語り直すことで、現在の戦略や将来の方向性を正当化します。また、ある時点では重要視されていた歴史の一部が、別の時点では意図的に忘れ去られることもあります。
「我々はこれまでこのように事業を展開してきたから、今後もこの方針を続けるべきだ」という主張を耳にしたことがあるでしょう。あるいは反対に「過去の失敗から学び、新しい方向に舵を切る時だ」という言葉も使われます。これらの言説は歴史的事実を述べているのではなく、現在の意思決定を正当化するために過去を解釈しているのです。
本コラムでは、組織における歴史の戦略的利用について、4つの視点から考察します。経営者による歴史の語り方、戦略策定における過去の再構築、組織変革を正当化するための歴史の再解釈、組織アイデンティティ維持のための意図的な忘却という観点から、歴史が経営においていかに活用されているかを探ります。
歴史は経営者によって戦略的に語られる
歴史とは過去の出来事の客観的な記録だと考えていませんか。しかし組織の中では、歴史は単純な過去の記録ではなく、経営者によって戦略的に語られる資源となっています。
スウェーデンの研究者が行った調査によれば、経営者は組織の歴史を自らの戦略的意図に応じて意識的に解釈し直し、利用していると言います。この研究では、スウェーデンの大手多国籍企業2社(トラックメーカーのスカニア社と銀行のハンデルスバンケン)を調査しました[1]。79回に及ぶ半構造化インタビューや会議・イベントへの参与観察、社内文書の分析などを通じて、組織内で歴史がどのように参照され、利用されているかを分析しました。
研究によると、組織における歴史の利用には5つの方法があります。
- 第一に「科学的利用」で、これは歴史的出来事を客観的に検証・解釈するものです。
- 第二に「実存的利用」で、これは組織メンバーが自分や組織のアイデンティティを過去に関連づけて再認識するためのものです。
- 第三に「道徳的利用」で、これは忘れ去られたり軽視されたりした過去の出来事や考え方を再評価・復活させることです。
- 第四に「イデオロギー的利用」で、これは経営層が自分たちの戦略を正当化するために歴史を再解釈して用いることです。
- 第五に「非利用」で、これは現在の戦略に不都合な過去をあえて無視・忘却することです。
このうち、戦略プロセスとの関連で見逃せないのは「道徳的利用」「イデオロギー的利用」「非利用」の3つです。事例を見ていきましょう。
1999年、スカニア社は競合企業ボルボ社から敵対的買収を受けました。この時、スカニア社の経営陣は過去の他社の合併事例(イベコ社など)を引用し、「合併すると市場シェアが低下する」という歴史的事実を強調して、合併の正当性を否定しました。これは典型的な「イデオロギー的利用」です。歴史を用いて自社の独立性を守る戦略を正当化したのです。
別の例では、ハンデルスバンケンの事例があります。同行は1970年代に分権型経営を導入して成功した歴史を持ちます。1990年代にインターネットバンキングを導入する際、集中型システムが分権主義に反すると考えられましたが、最終的には各支店が個別のウェブサイトを持つ独自方式を採用し、歴史的な分権哲学との連続性を主張しました。これもまた「イデオロギー的利用」であり、新技術を正当化するために歴史を戦略的に用いた例です。
「道徳的利用」の例としては、スカニア社のモジュラーシステムの再評価が挙げられます。スカニア社のモジュラー化生産は長年の伝統でしたが、若手エンジニアがそれを誤解したため品質低下が生じました。そこで経営者は、モジュラー化の本来の意味を、歴史を参照して復活させました。歴史の復活によって戦略の軌道修正を図った例です。
「非利用」の例としては、ハンデルスバンケンが1970年以前の期間をほとんど参照しないことが挙げられます。1970年代以降の成功した経営のみが語られ、それ以前の歴史はほぼ無視されています。これは特定の歴史期間を意図的に忘却することで、経営変革の断絶を強調する例です。
この研究が教えてくれるのは、歴史は経営者が戦略的に利用できる「資源」だということです。過去は固定された「制約要素」ではなく、状況に応じて解釈し直せる素材です。経営者が歴史を戦略的に用いることで、組織変革の抵抗を軽減できることも見えてきました。
戦略づくりでは歴史が都合よく再構築される
組織の戦略を考える場合、私たちは過去、現在、未来という時間の流れをどのように考えているでしょうか。過去は既に起きた固定的な事実であり、未来は予測するものだと考えられているかもしれません。しかし、組織の戦略づくりの場面では、過去も未来も現在の状況に合わせて柔軟に再構築されています。
ある技術企業の新規市場の参入戦略プロジェクトを詳細に観察した研究があります[2]。会議やミーティングの様子を記録し、関係者にインタビューを行い、組織内で時間がどのように扱われているかを分析しています。
その結果、「テンポラル・ワーク」という新しい概念を提示しました。これは、企業の戦略づくりに関わる人々が、時間をどのように構築し、再構築し、利用しているかという作業を指します。具体的には、過去の構築、未来の投影、現在の調整という3つの側面から成り立っています。
初めに、「過去の構築」について見てみましょう。戦略づくりの場面では、過去の出来事は選択的に再構築され、現在の意思決定を正当化するために利用されます。例えば、ある製品開発の失敗経験が「市場投入のタイミングが早すぎた」という教訓として語られることもあれば、別の場面では「十分な市場調査を行わなかった」という教訓として語られることもあります。同じ過去の出来事でも、現在の文脈によって異なる意味づけがなされます。
次に「未来の投影」について考えてみましょう。組織の中では、様々な未来シナリオが描かれ、それが現在の決定を促す材料として使われます。例えば「このまま行けば5年後に市場シェアが半減する」という悲観的なシナリオを描いて組織変革の必要性を訴えることもあれば、「新技術に投資すれば3年以内に業界リーダーになれる」という楽観的なシナリオを描いて投資を促すこともあります。未来予測は客観的な科学というよりも、戦略的な説得の道具として機能していることが多いのです。
さらに「現在の調整」についてですが、「現在」とは、過去と未来との整合性を保つために柔軟に調整される対象です。例えば、業績が悪化している状況で「現在は一時的な調整期間である」と解釈すれば、過去の成功と未来の成功の間の橋渡しとして現状を正当化できます。一方、同じ状況を「現在は危機的状況である」と解釈すれば、過去のやり方を否定し、未来に向けた抜本的変革の必要性を訴えることができます。
この研究が明らかにしたのは、戦略づくりの場面では、過去・現在・未来という時間の区分けが固定されたものではなく、組織内の対話と交渉を通じて再構築されているということです。例えば、ある会議で「我々の強みは品質へのこだわりだった」と過去が構築されれば、それに整合する形で「今後も品質を最優先する」という未来が投影されます。しかし別の会議で「我々は変化への適応が遅れてきた」と過去が再構築されれば、「今こそ変革のときだ」という異なる未来が描かれるでしょう。
こうした時間の再構築は、組織内の様々な利害関係者の間での交渉と説得のプロセスでもあります。各部門や階層の人々は、自分たちの立場を強化するような時間の語り方を試み、それが全体としての戦略形成に反映されていきます。
この研究で理解できるのは、時間とは客観的に存在する背景要素ではなく、「戦略を形成する際の構成要素」だということです。経営者やマネージャーは、過去・現在・未来をどのように構築し、語るかが、戦略の質や方向性に違いをもたらすことを認識すると良いでしょう。
この視点から考えると、戦略づくりとは客観的な環境分析や合理的な意思決定ではなく、組織内での「意味づくり」のプロセスだともいえます。過去の経験をどう解釈し、現在の状況をどう理解し、未来の可能性をどう想像するかという、集団的な意味づくりが戦略の中心にあるのです。
歴史の再解釈が組織変革を正当化する
組織は変化する環境に適応していく必要がありますが、同時に独自のアイデンティティを維持することも求められます。この「安定性」と「変化」という一見矛盾する要素をどのように両立させるのでしょうか。ある研究チームは、組織のリーダーが修辞的手法を用いて、過去の価値観を再解釈しながら変革を進めるプロセスを明らかにしました[3]。
組織アイデンティティとは、「中心的で継続的かつ特徴的な属性」として定義されます。しかし実際には、アイデンティティは固定的なものではなく、絶え間ない修辞的かつ実践的努力によって維持されています。組織のリーダーは、過去から引き継いだ価値や特徴を再解釈しつつ、現在の状況に適応させる必要があります。
研究では、日用品・化粧品大手のプロクター・アンド・ギャンブル(P&G)を対象として、1980年から2000年にかけての経営幹部による177回の内部向けスピーチを分析しました。特に「徹底性(thoroughness)」というP&Gの歴史的価値に関する発言に着目し、リーダーがこの価値をどのように再解釈しながら組織変革を推進したかを調査しました。
分析の結果、P&Gのリーダーは「徹底性」という歴史的価値を3つの修辞的手法を通じて再解釈し、変革を促進していたことがわかりました。
1つ目の手法は、「理想」と「現実」の分離です。リーダーは「徹底性」という理想(過去からの価値観)と、それが実際の業務でどれほど実践されているかとのギャップを指摘しました。例えば、「我々は徹底性を語るが、実際にはそれを十分に実践していない」と主張し、実務の改善を促したのです。これによって、変革は「本来の価値観への回帰」として提示されました。
2つ目の手法は、「目的」と「手段」の分離です。リーダーは徹底性を目的そのものではなく、別の目的を達成するための手段として再解釈しました。例えば「徹底性を完璧さそのものとして追求すると、新製品の開発が遅れる。徹底性は消費者の反応に即応するための手段であるべきだ」と主張し、イノベーションを促進したのです。これにより、徹底性の意味が柔軟に拡張され、新しい取り組みを正当化する根拠となりました。
3つ目の手法は、「文字通り」と「精神」の分離です。リーダーは徹底性を過去のやり方を文字通り踏襲することではなく、その精神を理解して現状に適応させるべきだと主張しました。例えば、新たな経営手法(統合品質管理など)を導入する際、「これも徹底性の精神に基づく新しい形態である」として正当化しました。過去の慣習の機械的な踏襲を避け、新しい状況に合わせて意味を拡張・再解釈することが促されました。
こうした修辞的手法を通じて、P&Gのリーダーは「徹底性」という歴史的価値を維持しつつも、その解釈を柔軟に変化させることで組織変革を推進しています。この事例から学べるのは、組織アイデンティティの安定性と変化という相反する要素は、リーダーの巧みな修辞によって調和できるということです。
歴史的価値観は固定的な制約ではなく、むしろ変革を支える資源となり得ます。組織のリーダーが過去から受け継いだ価値を維持しつつ、新しい状況に柔軟に対応するための手法として、修辞的な再解釈が有効です。
組織アイデンティティは、危機時だけでなく日常的に修辞的な手法を通じて再構築されています。リーダーは過去から受け継いだ価値を維持しつつも、その解釈を柔軟に変化させることで、組織の連続性を保ちながら変革を進めることができます。
この視点から考えると、組織変革とは過去との断絶ではなく、過去の再解釈を通じた連続的な進化として捉えることができます。歴史的価値観を否定するのではなく、その意味を拡張し再解釈することで、組織メンバーの抵抗を減らし、変革への支持を得やすくなるのです。
歴史を意図的に忘れることで組織は保たれる
私たちはこれまで、組織が歴史をどのように利用し、再構築し、再解釈するかを見てきました。しかし、組織の歴史の中には、意図的に「忘れられる」部分があることも見逃せません。ある研究では、組織がいかに自身の過去の一部を「意図的に忘却」することで、現在の組織アイデンティティを維持・形成しているかを明らかにしています[4]。
この研究においては、フランスの航空機エンジンメーカーであるスネクマ社を事例として取り上げ、企業が集団的記憶を操作する過程を分析しました。スネクマ社は1945年にフランス政府によって国有化され設立された企業ですが、ドイツの航空機エンジンメーカーであるノーム・エ・ローヌ社の施設・資産を接収して発足したという複雑な歴史を持っています。ノーム・エ・ローヌ社は第二次世界大戦中のナチス占領下のフランスにおいて、ドイツ軍のためにエンジンを製造していたため、その歴史には負の側面がありました。
研究者たちは、1945年から2000年代までの約60年間にわたるスネクマ社の年次報告書や社内刊行物、公式の歴史記述などの広範な文書資料を収集し、質的分析を実施しました。また、一部の関係者へのインタビューも行い、企業内での歴史記憶の形成過程を追跡しました。
その結果、スネクマ社が過去の特定の側面を意図的に「沈黙」させる、すなわち「積極的に言及しない」ことで組織アイデンティティを維持していたことが明らかになりました。具体的には次のようなプロセスが確認されました。
- 忘却の正当化:スネクマ社は、自らの設立を第二次世界大戦後のフランス航空産業の再生と位置づけることで、「負の歴史」について語らないことを正当化しました。「産業再建」や「国のため」という大義が忘却を促進しました。
- 沈黙の制度化:組織内外の公式文書や歴史記述において、負の過去に関する言及を避けるという行為が常態化され、制度化されました。組織内でこれらの過去に触れることは「タブー」となり、公式記録から除外され続けました。
- 代替的な記憶の提示:負の過去を語らない代わりに、組織は「フランスの技術的卓越性」や「国家への貢献」といった、肯定的で誇れる過去を選択的に記憶し、公式のナラティブとして強調しました。
このようにして、負の過去は積極的に忘れられ、組織アイデンティティを揺るがす要素として表舞台から排除されました。この「忘却」は記憶の欠如ではなく、「積極的な意味付け行為」だということです。
集団的記憶は組織アイデンティティの形成において大事である一方で、その記憶が必ずしも「真実」や「完全性」を伴わず、選択的かつ意図的に構成されます。組織が自身の過去の一部を意図的に忘却し続けることが、長期的にその組織アイデンティティを維持・強化する上で役割を果たしているのです。
脚注
[1] Brunninge, O. (2009). Using history in organizations: How managers make purposeful reference to history in strategy processes. Journal of Organizational Change Management, 22(1), 8-26.
[2] Kaplan, S., and Orlikowski, W. J. (2013). Temporal work in strategy making. Organization Science, 24(4), 965-995.
[3] Golant, B. D., Sillince, J. A. A., Harvey, C., and Maclean, M. (2015). Rhetoric of stability and change: The organizational identity work of institutional leadership. Human Relations, 68(4), 607-631.
[4] Anteby, M., and Molnar, V. (2012). Collective memory meets organizational identity: Remembering to forget in a firm’s rhetorical history. Academy of Management Journal, 55(3), 515-540.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。