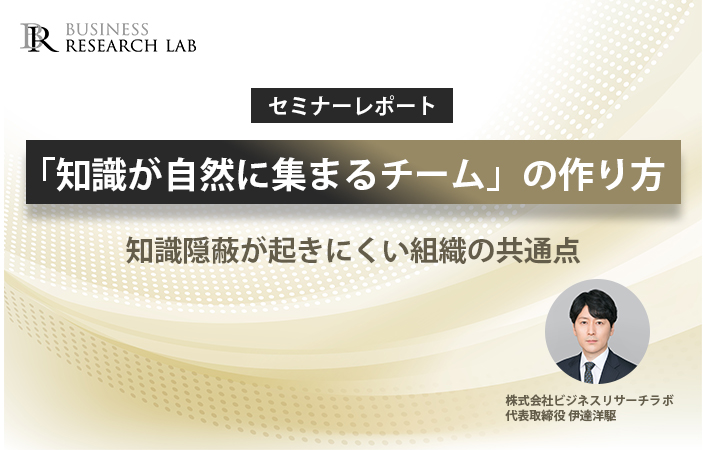2025年9月3日
「知識が自然に集まるチーム」の作り方:知識隠蔽が起きにくい組織の共通点(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年8月にセミナー「『知識が自然に集まるチーム』の作り方:知識隠蔽が起きにくい組織の共通点」を開催しました。
皆さんの職場では、従業員一人ひとりが持つ知識や経験が、円滑に共有されているでしょうか。チームの協力関係が損なわれ、新しいアイデアが生まれにくくなっているとしたら、その背景には「知識隠蔽」という問題が潜んでいるのかもしれません。
知識隠蔽とは、同僚から求められた情報を意図的に提供しない行動を指します。仮にそのつもりがなくても、結果的に知識の流れを止めてしまうことがあるかもしれません。
「忙しくて教える時間がなかった」「自分の専門領域だから安易に教えられない」「かえって相手を混乱させるかもしれない」。こうした一つひとつの配慮や判断が、意図せず知識の共有を妨げ、組織の活力を静かに奪っていくことがあるのです。
知識が共有されないのは、決して個人の意欲だけの問題ではありません。むしろ、職場の人間関係や評価制度、リーダーの振る舞いといった、組織の構造的な要因が影響しています。もし、良かれと思って取った行動や、見て見ぬふりをしてきた組織の慣習が、従業員の成長機会や組織全体のパフォーマンスを低下させているとしたら、どうでしょうか。
この問題を放置すれば、組織はじわじわと蝕まれてしまいます。大切なのは、この現象の本質を理解し、自らの組織で何が起きているのかを捉え直す視点です。
本セミナーでは、株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役の伊達洋駆が、この複雑な「知識隠蔽」のメカニズムについて解説しました。自社の課題を発見し、次の一手を考える上で実践的なヒントを得られる機会となれば幸いです。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
企業の持続的な成長とイノベーションの源泉は、従業員一人ひとりが持つ知識や経験にあります。それらが組織内で円滑に共有され、新たな価値創造へと結びつくことで、企業は変化の激しい時代を勝ち抜くことができます。しかし、多くの組織では、この理想的な知識共有がうまく機能していない現実があります。その根底に潜む問題が「知識隠蔽」です。知識隠蔽とは、従業員が意図的に同僚からの知識要求を拒む行為を指します。本講演では、なぜ知識隠蔽が起きてしまうのか、それが個人や組織にどのような影響を与えるのかを研究知見から紐解き、知識が自然に集まるチームを作るための方策について考えていきたいと思います。
知識隠蔽が個人に与える代償
知識隠蔽とは、同僚から求められた知識や情報を意図的に共有しない行為全般を指します。例えば、重要な情報を知っているにもかかわらず知らないふりをしたり、わざと曖昧な説明に終始したり、あるいは多忙を理由に協力を断ったりする行動が、これにあたります。このような行動は、短期的には自身の優位性を保つための戦略に見えるかもしれませんが、巡り巡って自分自身の首を絞めることになりかねません。
特に、個人の「創造性」にダメージを与えることが研究によって明らかになっています[1]。ある調査では、知識隠蔽を頻繁に行う従業員ほど、上司から創造性が低いと評価される傾向が確認されました。これは、知識を隠す行為が、周囲からの信頼を失うことにつながるためです。
別の実験研究では、知識隠蔽を行った人物はチームの他のメンバーから協力や助言を得られなくなり、結果的に、本人の創造的なパフォーマンスが低下するという負の循環が実証されています。ただし、この悪影響は職場の風土によって左右されることもわかっています。個人の学習や成長を重視する「熟達風土」が根付いた職場では、一度失った信頼を回復する機会が与えられやすく、創造性へのダメージが和らげられました。逆に、他者との競争を煽る「遂行風土」の職場では、知識隠蔽がもたらす不信感は根深くなり、創造性への悪影響が深刻化します。
知識隠蔽という行為は、実行した本人の心にも複雑な感情を呼び起こします。特に、知らないふりをして情報を隠す「無知を装う」というタイプの隠蔽は、本人に強い「罪悪感」と「恥」の感情を引き起こすことが研究で示されています[2]。この二つの感情は似ているようで、その後の行動に全く逆の影響を与えます。
罪悪感とは、「自分のとった行動は間違っていた」という行為そのものへの後悔です。この感情を抱いた人は、自身の行いを埋め合わせようとする意識が働き、本来の職務以上の貢献、例えば困っている同僚を自発的に手伝うといった行動を増やす傾向が見られました。一方で、恥とは、「そんな行動をとった自分はダメな人間だ」という自己そのものへの否定的な感情です。恥を感じた人は、他者からの評価を恐れて内向きになり、周囲との関わりを避けるようになります。その結果、組織への貢献行動はむしろ減少してしまうのです。
同じ知識隠蔽という一つの行動から出発しても、それが罪悪感につながるか、恥につながるかによって、組織への貢献意欲が正反対の方向へと分岐してしまう点は、興味深い知見と言えるでしょう。
知識隠蔽は常に悪意から行われるのでしょうか。実は、必ずしもそうとは限りません。ある調査によれば、従業員の約一割が日常的に何らかの知識隠蔽を行っていると報告されていますが、その動機は様々です[3]。会社の機密情報を守るためであったり、自身の知識が複雑すぎてうまく説明できない、あるいは不正確な情報を伝えてしまうことを恐れたりといった理由も含まれます。
しかし、様々なタイプの知識隠蔽を引き起こす最も強力な要因は、対人関係における「不信感」であることが明らかになっています。相手を信頼できないという気持ちが、自己防衛的な知識の出し惜しみにつながるのです。また、知識の性質も隠蔽のされやすさに関係します。特に専門的で複雑な知識は、誤解を招きたくないという思いから、意図的に説明を避ける「回避的隠蔽」につながりやすい傾向があります。
ただし、このような隠蔽は、組織の文化によって減らすことが可能です。日頃から知識を共有することが奨励され、オープンなコミュニケーションが根付いている職場では、この種の回避的な隠蔽行動が有意に減少することも確認されています。
意外に思うかもしれませんが、知識隠蔽の中には、むしろ人間関係に良い影響を与える可能性のあるものも存在します。知識隠蔽は、そのやり方によって大きく三つのタイプに分類されます。一つ目は、なぜ共有できないのか正当な理由を説明する「合理化した隠蔽」。二つ目は、嘘をついたり話をはぐらかしたりする「回避的隠蔽」。三つ目が、知らないふりをする「無知を装う」隠蔽です。
ある研究で、自分が知識を隠した経験と、逆に他者から隠された経験の両面から、それぞれの隠蔽タイプが関係性に与える影響を調査しました[4]。その結果、会社のルールや顧客のプライバシー保護といった正当な理由をきちんと説明する「合理化した隠蔽」は、隠された側もその状況に納得しやすく、相手への理解を深めるきっかけとなり、逆に関係性が強化されると感じることがありました。
一方で、嘘をつく「回避的隠蔽」は、隠した側も隠された側も関係が悪化したと感じており、「無知を装う」隠蔽に至っては、隠された側が将来的な報復を考えるきっかけになり得ることが示されました。知識を共有しないという行為そのものではなく、その伝え方や理由の示し方が、人間関係の行方を左右します。
知識を共有する組織の作り方
企業によっては知識共有を促進するために、高機能なナレッジマネジメントシステムを導入したり、知識共有に関する詳細な規則を設けたりしています。しかし、ある調査研究によると、こうしたシステムや規則といったハード面の対策は、従業員の知識隠蔽行動を減らす上で、残念ながら有意な効果が見られませんでした[5]。従業員は、規則の抜け穴を見つけたり、システムを形骸化させたりする方法を心得ているのです。
その一方で、明確な効果を示したのが、組織の「文化」でした。オープンで協力的な知識共有の文化が職場に根付いている組織では、従業員の知識隠蔽行動が明らかに低下します。逆に、経済的な不安が強い職場では、従業員は自分の立場を守るために知識を隠そうとする傾向が強まります。だからこそ、リーダーが率先して失敗談を語って挑戦を奨励したり、1on1個人面談等の場で他者貢献を賞賛したりするなど、知識を共有しても損をしないオープンな文化と心理的安全性を育むことが、重要な対策となります。
さらに、知識隠蔽は伝染する性質を持っており、誰かが隠蔽を始めると、その相手も報復として隠蔽で応酬するという負の連鎖が生まれやすいことも確認されています。このような環境が蔓延すると、従業員の組織に対するエンゲージメントは低下し、離職意向を高めることにつながってしまいます。
組織全体の風土を協力的に変えたとしても、特定の知識、特に個人の経験に根差したノウハウのような「暗黙的知識」の共有は、依然として難しい課題として残ります。ある学術界を対象とした調査では、論文などで文書化しやすい「明示的知識」よりも、教育や研究のコツといった個人の経験に依存する「暗黙的知識」の方が、より強く隠蔽される傾向にあることがわかりました[6]。
この背景には、個人の「競争心」が関わっています。もともと競争的な性格の持ち主は、たとえ周囲が協力的な雰囲気であっても、自身の優位性を維持するために、明示的・暗黙的を問わず多くの知識を隠そうとします。
もちろん、業務上、他者との協力が不可欠な環境を設計することには意味があり、マニュアル化できるような「明示的知識」の隠蔽を抑制する効果が確認されています。しかし、個人の競争心が強い場合、その競争力の源泉となる「暗黙的知識」の共有には、最後まで抵抗を示す傾向がありました。この課題に対処するには、個人目標だけでなくチーム共通の目標を設定したり、意図的にペアで取り組む業務体制を基本としたりするなど、過度な競争よりも協力を促す仕組みが効果的です。
知識隠蔽が起きてしまった組織では、もはやイノベーションは期待できないのでしょうか。必ずしもそうとは言えません。たとえ知識隠蔽が存在したとしても、それを乗り越えて革新を生み出すための鍵が、チームの「学習風土」と個人の「仕事の自律性」にあることが分かっています。
研究によると、知識隠蔽は、新しいアイデアを職場に導入し、実現させていく「革新的な仕事行動」を阻害する要因となることが確認されています[7]。しかし、チーム内に個人の学習や成長を支援し、挑戦を奨励する「熟達風土」が存在する場合、知識隠蔽が革新性へ与える悪影響が大幅に軽減されることが明らかになりました。たとえ同僚から知識を得られなくても、自ら学ぼうとする意欲と、それを支える環境があれば、別の方法で必要な情報を獲得し、アイデアを実現できるためだと考えられます。
さらに興味深いのは、この学習風土と、仕事の進め方との組み合わせです。学習を重視する風土があり、かつ、他者にあまり依存せずに独立して進められる仕事の場合、あるいは、自分で仕事の段取りや手法を決められる自律性が高い仕事の場合、従業員は知識隠蔽という制約をものともせず、むしろ高い革新性を発揮したのです。
他者からの情報提供に頼らずとも、自らの裁量と学習意欲で道を切り拓ける環境が、知識隠蔽という逆境を跳ね返す力になります。具体的には、本人の能力より少し上の挑戦的な業務(ストレッチアサイン)を任せて実践的な学びを促したり、目標達成のプロセスは個人の裁量に任せて権限移譲を進めたりすることが、この力を育む上で重要です。
知識隠蔽の根底にある心理的な要因として、「縄張り意識」の問題も指摘されています[8]。自分の知識やスキル、あるいは担当業務を「自分のテリトリー」とみなし、他者が関与することに抵抗を感じる心理状態です。縄張り意識が強い従業員は、同僚からの知識要求を自身の領域への侵入と捉え、知識隠蔽を行いやすい傾向があることが研究で示されています。
問題は、この意識が知識共有を妨げるだけにとどまらない点です。縄張り意識は他者との協力を拒絶するため、チームからのサポートを得られなくなり、本人の業務遂行能力そのものを低下させてしまうのです。深刻なのは、縄張り意識が、会社の規則を意図的に破ったり、同僚への協力を怠ったりといった、組織や対人関係における「逸脱行動」を増加させることまでわかっています。
そして、縄張り意識と逸脱行動との間を、知識隠蔽という行動が取り持っているという悪循環の構造も明らかになりました。要するに、縄張り意識が知識隠蔽を生み、その知識隠蔽という不誠実な行動が、他の様々な問題行動への心理的なハードルを下げるということです。
縄張り意識と密接に関連するのが、「心理的所有感」という概念です[9]。人は、自分が時間や労力を投じた対象に対して、「これは自分のものだ」という感覚を抱きます。この感覚が、個人の職務やそこで得た知識に向けられると、「これは私の仕事」「これは私の知識だ」という強い所有感が生まれ、知識を他者と共有することへの抵抗感、すなわち知識隠蔽につながりやすくなります。自分の領域を守ろうとする縄張り意識も、この個人レベルの所有感の表れと言えるでしょう。
しかし、この所有感にはもう一つの側面があります。それは、従業員が「組織そのもの」に対して抱く所有感です。従業員が「この会社は自分たちのものだ」と感じられるようになると、その関心は個人の利益から組織全体の利益へと向かいます。結果、組織の成功は自分自身の成功であると捉え、組織の発展のために自らの知識を積極的に共有しようとする動機が生まれます。
したがって、知識隠蔽という問題を解決するためには、従業員の意識を「個人の職務への所有感」から「組織全体への所有感」へと高めていくアプローチが有効です。例えば、会社のビジョンや経営状況を積極的に共有して当事者意識を育んだり、個人の手柄だけでなくチーム全体の成果として称賛したりすることで、「会社の成功が自分の成功だ」という組織への所有感を醸成できます。
知識隠蔽の防波堤
従業員の知識隠蔽行動は、本人の資質だけでなく、直属の上司であるリーダーの姿勢に影響されることがわかっています[10]。とりわけ、リーダーが知識の出し惜しみを容認したり、あるいは自ら実践したりするような態度を示すと、部下はそれを「この職場では知識を隠しても良いのだ」という暗黙のメッセージとして受け取ります。その結果、部下もリーダーの行動を模倣し、チーム全体に知識隠蔽が蔓延していきます。
この「リーダー示唆型知識隠蔽」がもたらす結末は深刻です。ある調査では、上司の態度を真似て知識隠蔽を行うようになった部下は、仕事に対する満足感が低下し、組織を去りたいと考える気持ちが強くなることが明らかにされました。
興味深いことに、隠蔽のタイプによって影響は少し異なります。嘘をついたり知らないふりをしたりする隠蔽は職務満足度を大きく下げましたが、正当な理由を説明する「合理化した隠蔽」は、本人の道徳的な葛藤が少ないためか、離職意向をむしろ減らす可能性も示唆されました。
いずれにせよ、リーダーの無意識の態度が、部下のエンゲージメントを蝕み、組織の活力を奪っていくという事実は、管理職にとって重い教訓と言えます。だからこそリーダーは、自ら情報をオープンにし、知識を求める部下を歓迎する姿勢を示すと共に、正当な理由なく知識を出し惜しむ態度を容認しないことが求められます。
チーム全体の協力意識が低く、どこかギスギスした雰囲気の職場であっても、知識隠蔽の蔓延を食い止める防波堤が存在します。それは、リーダーとメンバー一人ひとりとの間に築かれた「信頼関係」です。
ある実験研究と実際の職場調査を組み合わせた研究では、チーム全体の協力意識が高い場合に知識隠蔽が減少するのはもちろんのこと、たとえチームの協力意識が低い状況であっても、リーダーとメンバーの間に強い信頼関係が存在していれば、知識隠蔽は効果的に抑制されることが実証されました[11]。
これは、チーム全体の風土という大きな流れを変えることが難しくても、リーダーが個々のメンバーと真摯に向き合い、個人的な信頼を勝ち得ることができれば、知識共有の文化を局所的にでも育むことが可能であることを示しています。メンバーは、「チームの他の人は信頼できないかもしれないが、少なくともこのリーダーは信頼できる」と感じることで、安心して知識を開示できるようになるのです。
リーダーがメンバーとの関係性を丁寧に築き上げることが、チームの協力体制が未熟な段階においては重要な役割を果たすと言えます。そのために、チームミーティングだけでなく個々のメンバーと向き合う個人面談を重視するとともに、小さな約束でも確実に守って一貫性を示すなど、地道な信頼の積み重ねが不可欠です。
組織内での立場や評価をめぐる政治的な駆け引きは、多くの職場で起こり得ることです。このような環境では、従業員は自分の弱みを握られまいと、あるいは他者を出し抜こうと、自己防衛のために知識を戦略的に隠すようになります。しかし、こうした社内政治の濁流に飲み込まれることなく、自らの知識をオープンにし続ける人々もいます。彼ら彼女らを支えているのは、自身の専門分野に対する誇りや使命感、すなわち「専門職コミットメント」です。
ある研究では、専門職コミットメントが高い従業員は、たとえ組織内の政治的駆け引きが蔓延する環境に身を置いていたとしても、知識隠蔽に走りにくい傾向があることが明らかになりました[12]。彼ら彼女らにとって重要なのは、社内での短期的な政治的利益ではなく、自らが属する専門家コミュニティへの貢献や、専門性そのものの発展です。
その高い倫理観と専門家としての強いアイデンティティが、組織内の政治的な混乱に対する防波堤として機能し、目先の利害を超えて知識を共有するという行動を支えるのです。企業は、従業員の専門性を尊重し、そのコミットメントを育むことで、より健全な組織文化を築くことができるでしょう。具体的には、その人の専門性そのものを認め、称賛の言葉をかけるだけでなく、社外勉強会への参加を奨励し、専門家としてのアイデンティティを育む機会を提供することが有効です。
なお、「忙しい」という言葉は、同僚からの協力依頼を断る際の常套句になりがちです。実際に、迫り来る締め切りなど、強い時間的プレッシャーを感じている従業員ほど、他者に知識を教える時間的・精神的な余裕を失い、知識隠蔽を行いやすいことが研究で示されています[13]。自分の仕事を終わらせることで頭がいっぱいになり、他者を助けることを後回しにしてしまうのです。
しかし、同じように多忙な状況下でも、快く知識を共有する人々がいます。その行動を分けるものは何なのでしょうか。鍵は「向社会的動機」と「他者視点取得能力」にあります。向社会的動機とは、純粋に他者の役に立ちたい、助けたいという思いのことです。そして他者視点取得能力とは、相手がどのような状況にあり、何を求めているのかを、相手の立場に立って理解する力です。
この二つの要素を高いレベルで兼ね備えている人は、たとえ時間的なプレッシャーに晒されていても、知識隠蔽に走りにくいことがわかっています。他者の視点に立つことで、同僚が情報を求める背景にある切迫感や重要性を察知し、それを助けたいという動機が、自らの多忙さを乗り越えて協力行動を促すのです。
相手の身になる力が、知識の出し惜しみを防ぐための砦となります。この「相手の身になる力」を育むには、日頃から感謝を伝え合う文化が役立ちます。例えば、質問する側は「〇〇という目的のために」と背景を共有し、教えてもらった側は「おかげで〇〇が解決できました」と成果を伝え合う習慣が、互いの共感と協力を引き出します。
おわりに
本講演では、「知識隠蔽」という現象を多角的に分析し、それが起きにくい組織の共通点を探ってきました。見てきたように、知識隠蔽は個人の性格の問題ではなく、職場の風土、リーダーシップのあり方、仕事の進め方、従業員の心理状態が複雑に絡み合って生まれる課題です。
システムや規則を整えるだけでは、この問題を根本的に解決することはできません。知識が自然に集まり、活発に共有される組織とは、制度という器だけでなく、その中身である「文化」が成熟している場所です。そこでは、従業員間の信頼が醸成され、互いへの貢献が尊重され、挑戦と成長が奨励されています。
本講演で紹介した知見を参考に、自社の組織文化を見つめ直していただきたいと思います。従業員一人ひとりが安心して知識を開示し、共に成長できるような、生産的な職場環境を築くための一歩を踏み出すきっかけとなれば嬉しいです。
Q&A
Q:長年の経験を通じて、言葉で説明するのが難しい専門的な知識やノウハウ、いわゆる「暗黙知」を持つベテラン社員がいます。しかし、自身の職場での優位性を保ちたいという思いからか、若手社員への知識の共有にあまり積極的ではないケースがあるように感じます。組織にとって貴重な資産であるその暗黙知を、うまく次世代に継承してもらうには、どうすればよいのでしょうか。
多くの組織が直面する重要な課題かもしれません。まず、ベテラン社員の方々が長年かけて培ってこられた知識や経験に対し、組織として敬意を払う姿勢を示すことが不可欠です。彼ら彼女らの功績と専門性を公式に認め、その価値を明確にすることから始まります。
具体的なアプローチとして、彼ら彼女らが持つ専門性を認定し、知識共有を名誉ある役割だと位置づけることが有効です。例えば「マイスター制度」のように卓越した技術を持つ社員を認定したり、「技術顧問」といった特別な称号を付与し、若手への指導を公式なミッションとして定義したりする方法が考えられます。このように、彼ら彼女らの存在の重要性を目に見える形で示すことで、知識の伝承に新たな誇りややりがいを見出してもらえる可能性があります。
制度的な後押しも重要です。若手への指導実績や知識共有の成果を人事評価の項目に加えるなど、本人に具体的なメリットが感じられる制度設計もあると良いでしょう。称号による名誉と評価による実利を組み合わせることで、自発的な行動を促し、貴重な知識の継承を円滑に進めることができるでしょう。
Q:失敗した経験を組織全体で共有し、そこから学ぶ文化の重要性は理解できます。しかし、私の会社では昔ながらの減点主義が根強く残っています。失敗を報告することが自身の評価低下に直結するのではないかという恐れから、多くの社員が失敗を隠してしまう傾向にあります。このような状況で、人事部門として、何から着手するのが効果的でしょうか。
この問題の根幹には「心理的安全性」の不足があります。つまり、「この組織では、失敗を正直に話しても不利益を被ることはない」とメンバーが安心して感じられる環境がなければ、失敗の共有は進みません。
文化を一度に変えるのは困難ですので、まずは小さな一歩から始めることが重要です。最初に取り組むべきは、経営層や管理職から明確なメッセージを発信し続けることです。「私たちは失敗そのものを責めるのではなく、そこから何を学び、次にどう活かすかを共有することを評価する」という姿勢を繰り返し伝え、実際に学びを共有した社員を称賛するなど、行動で示すことが信頼につながります。
組織によっては「失敗報告会」のような場を設けていますが、「失敗」という言葉にはネガティブな響きがあります。そこで「挑戦共有会」のように、よりポジティブな名称で場を設定してみてはいかがでしょうか。成功事例だけでなく、そこに至る試行錯誤のプロセス全体を共有する文化が育てば、失敗を開示する心理的なハードルも下がり、組織全体で建設的に学んでいけるようになると考えられます。
Q:知識の共有を推進した結果、今度はあらゆる情報が共有されすぎて「情報過多」に陥り、かえって重要な情報が埋もれてしまって生産性が落ちるのではないか、という心配があります。組織として、効果的な知識共有と、情報過多の防止を、どのように両立させればよいのでしょうか。
鋭いご指摘です。知識共有は重要ですが、人間が処理できる情報量には限界があり、情報が多すぎるとかえって生産性が落ちることもあります。
この課題へのアプローチとして、知識や情報の種類を整理し、区分けすることが考えられます。そして、その種類に応じて共有範囲や使用するツールを戦略的に使い分けると良いでしょう。
例えば、全社的な重要事項はポータルサイト、部門内のノウハウはチャットツール、プロジェクトの知見は専用ツールで共有する、というように情報の性質に合わせて「場」を選ぶことで、必要な情報が必要な人に届きやすくなります。
受け手の負担を減らす工夫も有効です。チャットやメールで【共有のみ】【要確認】といったタグを件名につけるルールを設けるだけでも、受け手は情報の重要度を判断しやすくなります。
そしてもう一つ大切なのは、情報を一方的に共有する(プッシュ)だけでなく、必要な人が必要な時に検索して引き出せる(プル)環境を整備することです。これらの観点をうまく組み合わせることで、知識共有のメリットを活かしつつ、情報過多のデメリットを抑えることができるのではないでしょうか。
Q:セミナーの中で、正当な理由を説明する「合理化した隠蔽」は、人間関係を悪化させにくいという話がありました。しかし、この「正当な理由」が、単なる自己保身のための言い訳として悪用されてしまう恐れはないのでしょうか。マネージャーとして、部下が説明する理由が本当に正当なものなのか、それとも巧妙な言い訳なのかを、どう見極めれば良いのか悩んでいます。
部下の説明が本当に正当なものか、その真意を完全に見極めることは難しいでしょう。しかし、見極めとまではいかなくても、その確度を判断するための材料はあります。その一つが、「代替案を提示しているかどうか」という観点です。もし部下が、単に「できません」と拒絶するのではなく、建設的な提案を返してくれるのであれば、それは単なる自己保身ではない可能性があります。
例えば、「今は別の業務で手一杯ですが、来週であれば対応できます」「その資料は契約上お渡しできませんが、こちらのデータであれば共有可能です」といった提案です。このような代替案は、知識を共有したくないのではなく、制約がある中でも協力しようという前向きな姿勢の表れだと判断できます。
とはいえ、最終的に重要になるのは、その場限りの言動で判断するのではなく、日頃から部下と信頼関係を築き、彼ら彼女らの業務状況をきちんと把握しておくことです。普段からコミュニケーションを取り、部下の状況を理解していれば、その言葉がその場しのぎの言い訳か、事実に基づいた説明なのかは判断しやすくなります。
脚注
[1] Cerne, M., Nerstad, C. G. L., Dysvik, A., and Skerlavaj, M. (2014). What goes around comes around: Knowledge hiding, perceived motivational climate, and creativity. Academy of Management Journal, 57(1), 172-192.
[2] Burmeister, A., Fasbender, U., and Gerpott, F. H. (2019). Consequences of knowledge hiding: The differential compensatory effects of guilt and shame. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92(2), 281-304.
[3] Connelly, C. E., Zweig, D., Webster, J., and Trougakos, J. P. (2012). Knowledge hiding in organizations. Journal of Organizational Behavior, 33(1), 64-88.
[4] Connelly, C. E., and Zweig, D. (2015). How perpetrators and targets construe knowledge hiding in organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(3), 479-489.
[5] Serenko, A., and Bontis, N. (2016). Understanding counterproductive knowledge behavior: Antecedents and consequences of intra-organizational knowledge hiding. Journal of Knowledge Management, 20(6), 1199-1224.
[6] Hernaus, T., Cerne, M., Connelly, C. E., Poloski Vokic, N., and Skerlavaj, M. (2019). Evasive knowledge hiding in academia: When competitive individuals are asked to collaborate. Journal of Knowledge Management, 23(4), 597-618.
[7] Cerne, M., Hernaus, T., Dysvik, A., and Skerlavaj, M. (2017). The role of multilevel synergistic interplay among team mastery climate, knowledge hiding, and job characteristics in stimulating innovative work behavior. Human Resource Management Journal, 27(2), 281-299.
[8] Singh, S. K. (2019). Territoriality, task performance, and workplace deviance: Empirical evidence on role of knowledge hiding. Journal of Business Research, 97, 10-19.
[9] Peng, H. (2013). Why and when do people hide knowledge? Journal of Knowledge Management, 17(3), 398-415.
[10] Offergelt, F., Sporrle, M., Moser, K., and Shaw, J. D. (2019). Leader-signaled knowledge hiding: Effects on employees’ job attitudes and empowerment. Journal of Organizational Behavior, 40(7), 819-833.
[11] Babic, K., Cerne, M., Connelly, C. E., Dysvik, A., and Skerlavaj, M. (2019). Are we in this together? Knowledge hiding in teams, collective prosocial motivation and leader-member exchange. Journal of Knowledge Management, 23(8), 1502-1522.
[12] Malik, O. F., Shahzad, A., Raziq, M. M., Khan, M. M., Yusaf, S., and Khan, A. (2019). Perceptions of organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity: The moderating role of professional commitment. Personality and Individual Differences, 142, 232-237.
[13] Skerlavaj, M., Connelly, C. E., Cerne, M., and Dysvik, A. (2018). Tell me if you can: Time pressure, prosocial motivation, perspective taking, and knowledge hiding. Journal of Knowledge Management, 22(7), 1489-1509.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。