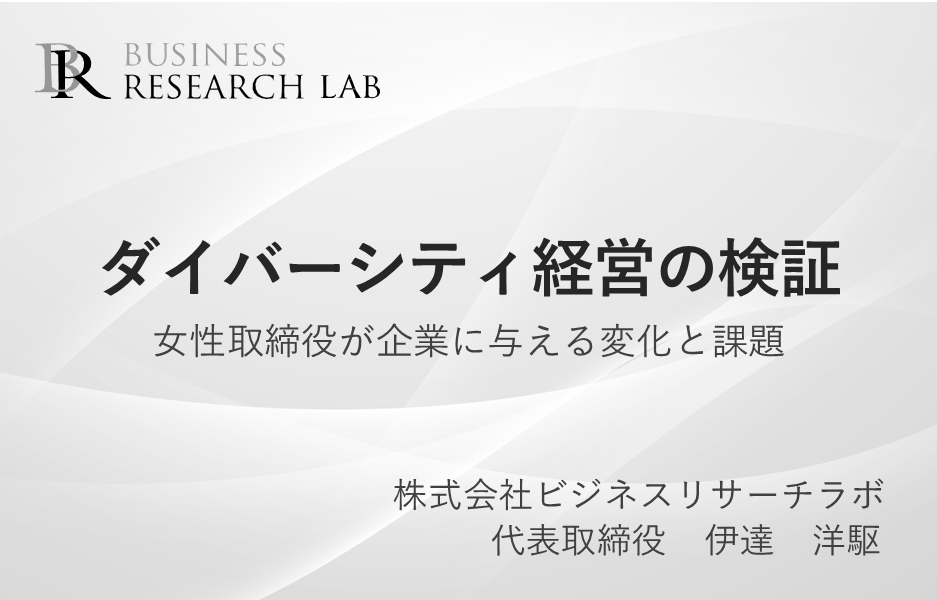2025年9月2日
ダイバーシティ経営の検証:女性取締役が企業に与える変化と課題
企業経営において、ダイバーシティの重要性が世界的に認識される中、日本でも女性の取締役会への登用が少しずつ広がりを見せています。取締役会における女性の存在は、多様性を示すシンボルとしてではなく、企業の意思決定や経営パフォーマンスに実質的な変化をもたらす可能性があると期待されています。女性役員の存在が企業にどのような変化をもたらすのか、その効果は世界各国で様々な研究が行われてきました。
女性取締役の登用は、企業統治の強化や経営監視機能の向上といった好ましい効果をもたらす可能性がある一方で、その財務的パフォーマンスへの影響については、研究者たちの間で見解が分かれています。ある研究では女性役員の比率が高いほど企業の短期的な収益性が向上するとされる一方、別の研究では市場評価(株価)との関連性は見られないという結果が出ています。
女性役員を増やすための施策として一部の国では導入されている数値目標や義務化については、それがかえって企業価値を低下させる可能性も指摘されています。女性役員の登用を考える際には、数値目標を達成することだけではなく、そのプロセスや背景にある社会的文脈も考慮する必要があります。
本コラムでは、女性役員が企業に与える影響について、企業統治、財務パフォーマンス、社会的評価、そして義務化政策の効果という多角的な視点から検討します。各国の先行研究から得られた知見を紹介しながら、女性役員の存在がもたらす魅力と、その限界について考察していきましょう。
女性役員は企業統治を改善するが業績向上は限定的
取締役会における女性役員の存在は、企業統治(コーポレート・ガバナンス)にどのような変化をもたらすのでしょうか。ある実証研究では、米国企業のデータを用いて、取締役会における女性の役割と影響力が検証されています。この研究では、特に取締役会の行動パターン、CEO交代、取締役の報酬設計、そして最終的な財務パフォーマンスという観点から分析が行われました[1]。
顕著な傾向として、女性取締役は男性取締役に比べて、取締役会の会議への出席率が総じて高いことが判明しました。出席率の問題(出席率が低いこと)を抱える割合は、男性役員に比べて約30%も低いという結果でした。この研究では、女性役員が増えると、男性役員の出席率も向上するという現象が確認されています。女性役員の存在が取締役会全体の参加意識を高め、会議の雰囲気や取り組み姿勢に好ましい変化をもたらしている可能性を表しています。
委員会活動においても、女性取締役の特徴的な行動パターンが見られました。女性取締役は監査委員会やコーポレート・ガバナンス委員会など、企業経営を監視する役割を担う委員会への参加率が高い傾向がありました。一方で、報酬委員会への参加率は男性よりも低いことが示されています。この結果は、女性取締役が企業の監視機能を高めるという理論的予測と一致しています。
CEOの交代に関しても、女性役員の存在は影響を及ぼすことが確認されました。女性役員の比率が高い企業では、業績不振(特に株価下落)時にCEOが交代する可能性が顕著に高まります。女性役員がCEOの業績に対してより厳格な評価を行い、監視機能を効果的に発揮していることを意味します。
取締役への報酬設計においても女性役員の影響が見られました。女性役員の比率が高い企業では、取締役に対する株式報酬(成果連動型報酬)の比率が高くなりました。報酬設計が株主の利益とより連動する形で行われることを意味し、企業統治の質の向上を示す一つの指標と考えられます。ただし、女性役員は報酬委員会にあまり参加しないため、CEO報酬設計に関しては男女比率による差異は見られませんでした。
このように、女性役員は取締役会の監視機能や企業統治の質を高める点で効果を示しましたが、財務パフォーマンスについてはどうだったのでしょうか。単純な統計分析では、確かに女性取締役比率が高い企業はトービンのQや資産収益率(ROA)が高い傾向がありました。しかし、この関係は見かけ上のものである可能性があります。
研究者たちが内生性(例えば、「業績の良い企業だから女性を登用する余裕がある」という逆の因果関係)を考慮した分析を行うと、女性比率と企業パフォーマンスの関係はむしろ負(ネガティブ)になる場合もあることが判明しました。特に買収防衛策が少なく、既に強力なガバナンス体制を持つ企業では、女性比率を増やすことが過度な監視をもたらし、かえってパフォーマンスを低下させる可能性があることが指摘されました。
一方で、買収防衛策が多くガバナンスが弱い企業では、女性役員が加わることで企業価値が向上しました。女性役員の存在価値がその企業の元々のガバナンス状況によって異なることを示唆しています。
女性役員は企業の短期利益を高めるが株価には無関係
個別の研究では相反する結果が報告されることもある中、過去の多数の実証研究を統合的に分析したメタ分析を行い、女性役員と企業パフォーマンスの関係についてより包括的な知見を提供している論文を紹介しましょう。この研究は1996年から2014年5月までに発表された140の独立した研究(世界35カ国、約9万社のデータ)を対象としており、その結果にはある程度の一般性があると考えられます[2]。
このメタ分析では、企業パフォーマンスを二つの側面から評価しています。一つは会計利益率(ROA、ROEなど)という短期的業績指標、もう一つは株価やトービンのQといった市場パフォーマンスという長期的評価指標です。
分析の結果、女性取締役比率が高い企業ほど、会計利益率は統計的に有意に高いことが確認されました。しかし、市場パフォーマンス(株価など)とは一般的には有意な関連性が見られませんでした。女性取締役の存在は企業の短期的な収益性には良い影響を与えるものの、市場からの評価(株価)にはあまり影響しないということが明らかになったのです。
この研究では、国の法的・社会的状況によって女性取締役の影響が異なることも示されました。株主保護が強い国(例えばニュージーランドやイスラエル)では、女性取締役と会計利益率の正の関係がより強く見られました。一方、株主保護が弱い国(オランダやドイツなど)では、その関係はほとんど見られませんでした。
男女平等度についても調整効果が確認されました。男女平等度が高い国(北欧諸国など)では、女性取締役が市場パフォーマンスに正の影響を与える傾向があったのに対し、男女平等度が低い国では逆に負の影響が見られたのです。これは、社会的文脈が女性取締役の効果を左右することを意味しています。
取締役会の活動に関しても、女性取締役比率が高い企業では、取締役会の監視活動(会議出席率や監査活動など)や戦略的関与活動がより活発になる傾向が確認されました。こうした活動の活性化が、最終的に企業の会計利益率向上につながっていると考えられます。特に株主保護が強い国では、女性取締役と取締役会の監視活動の関係がより強くなることも分かりました。
女性取締役は男性とは異なる経験や価値観を取締役会に持ち込むことで、意思決定プロセスを多角化・改善させ、結果的に企業利益(特に短期的利益率)の向上につながるため、このような結果が得られたと考えられます。
一方、市場パフォーマンスに関しては、外部評価や投資家の期待も影響します。そのため、社会全体のジェンダー平等の状況という文脈が重要になってくるのです。男女平等度が高い社会では、女性取締役の存在が投資家からも前向きに評価されます。
この研究から得られる重要な知見は、女性役員を取締役会に増やすことは一定の企業利益改善につながる可能性がありますが、それは数の問題ではなく、異質な意見を活かす組織文化や社会的文脈が重要だということです。ジェンダー平等度が高い社会では、女性取締役が市場評価にもプラス効果を持つため、社会全体の男女平等の推進も重要となります。
女性役員は企業統治の質と社会的評価を高める
取締役会における女性役員の価値は、財務的パフォーマンスだけで測ることはできません。2009年の広範な文献レビューでは、企業の取締役会における女性役員の存在がコーポレート・ガバナンスに与える影響について、個人、取締役会、企業、そして産業・外部環境という4つのレベルから多面的に検討しています[3]。
この研究では、女性役員に関する理論的視点を整理しています。個人レベルでは、「人的資本理論」に基づき、女性役員が持つ教育や経験の水準は男性と同等であるにもかかわらず、十分に評価されていない状況があることが指摘されています。「地位特性理論」からは、女性は男性よりも高い能力を証明しないと同等の評価を得にくいという現実が示されています。
取締役会レベルでは、「社会的アイデンティティ理論」により、同質な人々が集まりがちであり、異質な集団(女性)が排除される傾向があることが説明されています。「社会的ネットワーク理論」からは、取締役同士のネットワークが閉鎖的であると女性の参加が阻害されることが示されました。また、「ジェンダー化された信頼」という観点からは、男性が集団的信頼を重視するのに対し、女性は個人的信頼を重視する傾向があり、それが取締役会での役割遂行に影響することが説明されています。
企業レベルでは、「資源依存理論」から、女性役員が外部からの資源(知識・経験・多様性)を提供し、企業の資源依存関係を改善できることが示されています。「制度理論」からは、女性役員の存在が企業の社会的正当性を向上させ、内部の女性幹部登用も促進することが説明されています。「エージェンシー理論」の観点からは、取締役会のジェンダー多様性が株主利益を守るモニタリング機能を高める可能性が指摘されています。
女性取締役の特性に関する実証研究からは、女性取締役は男性よりも若く、MBAや高度な学位を持つことが多いことが明らかにされています。社会的資本(家族やネットワークなど)に基づく登用も見られます。取締役会内における役割としては、女性は非執行役員としての割合が高いものの、重要な委員会(指名・報酬委員会など)への参加率は男性と同程度になってきていることが示されています。業種別に見ると、女性取締役は大企業や特定業種(小売・金融など)に多い傾向があります。
女性取締役の存在はどのような影響を与えるのでしょうか。この研究では、様々なレベルでの影響を指摘しています。
個人レベルでは、女性取締役がロールモデルとなり、後輩女性のキャリア形成を促進する効果があります。取締役会レベルでは、女性の存在が意思決定プロセスを改善し、取締役会内のコミュニケーションや独立性を高める効果が指摘されています。
企業レベルでは、女性取締役が一定数存在すると、企業の社会的責任やガバナンスの質が向上し、場合によっては財務パフォーマンスも改善する傾向が見られました。外部環境レベルでは、女性取締役の存在が企業の社会的評判や正当性を高め、外部からの人材確保や企業ブランド向上に貢献することが示されています。
この研究は、取締役会のジェンダー多様性が企業統治の改善に貢献する可能性を強く示唆しています。とりわけ、女性取締役の存在は、取締役会の意思決定プロセスを改善し、企業の社会的責任や評判を高めるという点で価値があると言えるでしょう。
女性役員の義務化は経験不足で企業価値を低下させた
女性役員を増やすための政策として、一部の国では女性クオータ制度(女性比率の最低基準を定める制度)が導入されています。その先駆けとなったのはノルウェーで、2003年に世界で初めて企業取締役会における女性比率を最低40%とする法律を導入しました。このノルウェーの事例から、女性クオータの義務化が企業価値にどのような影響を与えたのかを実証的に分析した研究があります[4]。
この政策導入前、ノルウェー企業の取締役会における女性比率は約9%でした。その意味で、40%という基準は非常に大きな変化を意味します。この急激な変化が企業価値にどのような影響を与えたのかを検証するため、研究者たちはオスロ証券取引所に上場する248社の2001年から2009年までのデータを分析しました。
株価への即時的な影響を調べるため、法律が最初に発表された2002年2月22日のイベントスタディを実施しました。その結果、女性取締役がゼロだった企業は平均して3.54%という大きな株価下落を経験しました。一方で、女性取締役が既に1人以上いた企業では有意な株価下落は見られませんでした。この結果は、投資家たちが女性クオータ義務化を企業価値にとって負のショックとして捉えたことを示しています。
長期的な影響を調べるため、操作変数法を用いてトービンのQ(企業価値の指標)への影響を分析しました。その結果、女性取締役比率が義務化により10%増加すると、トービンのQは平均で12.4%低下するという関連性が見られました。この結果は、クオータ政策が企業価値に負の影響を与えた可能性を示唆しています。
なぜクオータ制度が企業価値を低下させたのでしょうか。研究者らはその原因を検証しています。
取締役の特性に大きな変化が見られました。義務化後に任命された女性取締役は、以前の男性取締役に比べてCEO経験が少なく、平均年齢も8歳以上若く、取締役としての経験や業務知識が乏しい傾向にありました。これらの要因は取締役会全体の経験値や専門知識の低下を招いた可能性があります。
経営意思決定にも変化が見られました。義務化後、企業は負債比率を増加させ、現金保有を減らし、M&A(企業買収)をより積極的に行うようになりました。これらの決定は、若く経験の浅い取締役が増えたことと関連付けられます。結果、企業の財務的リスクが高まり、資産効率(資産回転率)が低下し、運営費用が増加したことが示されました。
制度の導入は企業の行動にも影響を与えました。クオータ制度による負の影響を避けるため、一部の企業は公開企業から非公開企業への転換や、国外への移転を選択しました。実際、公開企業の数は法律導入後に30%以上減少し、非公開企業が増加しました。
この研究から得られる示唆は、取締役会の多様性促進政策は理論的には肯定的な影響が予測されるものの、現実の運用においては強制的な導入が企業価値を阻害する場合があるということです。経験豊富な人材が限られている状況で義務的に多様性を課すと、逆に企業のパフォーマンス低下を引き起こす可能性があります。
この結果は、女性役員の登用自体が悪いわけではなく、急激かつ強制的な変化がもたらす混乱や、経験豊富な女性人材の不足が問題であることを示唆しています。多様性推進のための政策設計においては、取締役候補者の経験や能力を考慮した柔軟な運用が必要であると言えるでしょう。長期的には女性管理職の育成や経験を積む機会の提供など、パイプラインの整備も課題となります。
脚注
[1] Adams, R. B., and Ferreira, D. (2008). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial Economics, 94(2), 291-309.
[2] Post, C., and Byron, K. (2015). Women on boards and firm financial performance: A meta-analysis. Academy of Management Journal, 58(5), 1546-1571.
[3] Terjesen, S., Sealy, R., and Singh, V. (2009). Women directors on corporate boards: A review and research agenda. Corporate Governance: An International Review, 17(3), 320-337.
[4] Ahern, K. R., and Dittmar, A. K. (2012). The changing of the boards: The impact on firm valuation of mandated female board representation. The Quarterly Journal of Economics, 127(1), 137-197.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。