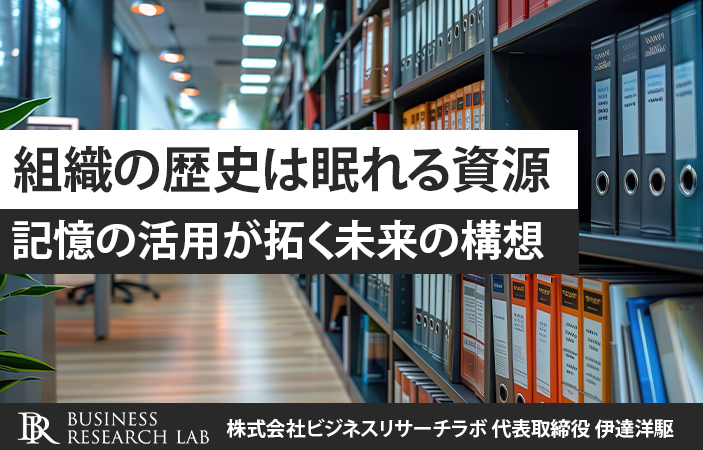2025年9月2日
組織の歴史は眠れる資源:記憶の活用が拓く未来の構想
組織の歴史は、単純な過去の出来事の記録ではありません。それは組織の未来を形作る資源であり、組織のアイデンティティや変化への対応力、ステークホルダーからの信頼構築、そして伝統と革新のバランスに関わっています。しかし、多くの組織では歴史を活かす視点が必ずしも十分ではなく、過去の経験や知恵を眠らせたままになっています。歴史は「過ぎ去ったもの」ではなく、現在と未来を照らす灯火となり得ます。
本コラムでは、組織における歴史の解釈と活用がいかに組織力の強化につながるかを、いくつかの角度から探ります。組織が自らの歴史をどう捉え、解釈し、語るかによって、未来への構想力や変化への適応力、ステークホルダーからの信頼、そして伝統の革新的継承が可能になることを見ていきましょう。
歴史の解釈は過去への回帰やノスタルジーではありません。それは現在の課題に取り組み、未来を切り拓くための行為となります。組織はどのように歴史を解釈し、それを組織力の源泉とすることができるのでしょうか。その鍵を研究成果とともに紐解いていきましょう。
歴史を活用すると組織の未来像が深まる
組織の歴史は、いわば未来を描くための絵の具です。過去の経験や記憶が、組織の将来像を描く際の素材となります。このことを如実に示す事例として、デンマークの玩具企業レゴ・グループの事例研究があります[1]。
レゴ・グループは2000年代初頭、デジタル玩具市場への急速な対応によりブランドの拡張を進めたものの、かえって自社のアイデンティティが曖昧になるという課題に直面しました。従来のブランド価値を再確認し、「創造性を刺激する」企業というアイデンティティを明確にしたいという意図から、同社は自社の歴史を振り返りました。
この振り返りでは、主に文書や口頭での記憶を活用し、「品質から信頼へ」「楽しさから能動的な楽しさへ」といった既存のブランド価値を再定義することに留まりました。その範囲と深さは限定的でした。
しかし、数年後の2005年から2007年にかけて、レゴは財政的危機に直面し、大規模なリストラが行われました。この時、新しいCEOの下で、レゴの存在理由を根本から再考する必要が生じました。第二期の振り返りでは、文書や口頭の記憶だけでなく、物質的な記憶、すなわち、初期の玩具そのものなども活用されました。
特に創業期(1930年代)の「最善のみが十分である」というモットーや初期の玩具の物理的な特徴に焦点を当て、「系統的創造性」という新たなアイデンティティを構築することができました。第二期の取り組みでは、再構築の範囲と深さが広がり、レゴのアイデンティティを再定義することに成功しました。
この事例から学べることは、組織が過去を想起する際の時間的な幅と深さが、未来へのアイデンティティの時間的視野と範囲に影響を与えるという点です。過去の想起期間が長いほど、未来へのアイデンティティの期間も長くなる傾向があります。
組織記憶の形態も重要です。「テキスト(文書)」、「物質的(製品など)」、「口述(語り継がれる話)」という3種類の組織記憶の形態があり、これらをどれほど多様に活用するかによって、未来のアイデンティティの範囲が広がります。とりわけ物質的記憶の活用は、アイデンティティの再構築において威力を発揮することがわかりました。
これらの記憶形態を相互に結合して使用することで、アイデンティティ再構築の深さが促進されることも判明しています。レゴの事例では、創業期の物理的な玩具(物質的記憶)とモットー(テキスト記憶)、そして古参社員の語り(口述記憶)を組み合わせることで、より深いレベルでのアイデンティティ再定義が可能になりました。
このように、組織が自身の過去を現在の資源として未来を構想する「進行中の時間的視点」を採用することが有益です。これは過去への回帰ではなく、組織の未来を創造するために過去を活用することを意味します。組織が危機や変化の局面に直面した際には、過去の多様な記憶形態を想起し、それを未来への構想に変換していくことが、組織のアイデンティティ再構築と未来像の明確化につながるのです。
歴史の解釈が企業の変化対応力を高める
歴史を活用して組織の未来像を深める方法を見てきましたが、歴史の解釈はさらに企業の変化対応力を高めます。急速に変化する環境において企業が生き残るためには、環境の変化に適応し、機会を捉え、資源を再構成する能力が必要です。この能力を「ダイナミック・ケイパビリティ」と呼びますが、この能力の基盤として、歴史の解釈が有効です。
従来、企業戦略における歴史は、企業が制約を受ける外部要因として捉えられてきました。しかし実際には、歴史は企業が戦略的に管理し活用できる内部資源と見ることができます。歴史の解釈の仕方によって、企業の変化対応力は変わるのです[2]。
歴史の解釈には大きく分けて三つの視点があります。一つ目は「客観的歴史」です。これは事実としての過去をデータとして収集・分析する能力で、技術の進化や市場の動向を予測するのに役立ちます。例えば、過去の技術革新パターンを分析することで、将来の技術変化を予測できます。
客観的歴史の認識には、二つの視点が含まれています。一つは「通時的認識」で、ある技術が長期間にわたりどのように発展してきたかを理解する能力です。もう一つは「共時的認識」で、複数の産業や製品ラインにわたる技術革新の波及を追跡し理解する能力です。これらの能力によって、企業は潜在的な技術変化から生じる機会をいち早く感知することができます。
二つ目の視点は「レトリカル・ヒストリー」です。これは過去を説得的な物語(ナラティブ)として再解釈し、ステークホルダーの支持を集めて変革を推進する能力です。企業が感知した機会を実際に獲得するためには、組織内外の関係者の協力が必要です。そのためには、変化の必要性を説得的に示し、関係者の動機づけを高めなければなりません。
レトリカル・ヒストリーの活用方法としては、いくつかの手法があります。例えば「連続性としての変化の提示」は、変化を過去からの自然な継続と位置づけることで、人々の抵抗感を軽減します。また「歴史的瞬間としての変化の提示」は、変化を決定的な歴史的な転換点として強調し、緊急性を高めます。「意図的な忘却」という手法もあり、これは変化の障害となる過去の要素を意図的に省略することで、変化への抵抗を弱める効果があります。
三つ目の視点は「想像的歴史」です。これは過去の解釈を基に、理想的な未来像を構築し、それを説得的に提示する能力です。新たな製品や市場を創出するためには、望ましい未来を描き、それに基づいて資源や組織構造、市場そのものを再構成する必要があります。
想像的歴史の活用には「未来完了形思考」が鍵となります。これは、未来のある時点から現在を振り返るような思考法です。この思考法を用いて、企業は製品の再構成(技術の系譜を想像的に拡張し、新しい製品用途を発見する)、組織の再構成(未来のシナリオを想定し、組織の戦略的選択を現在の行動に落とし込む)、市場の再構成(新製品を中心とした新たな市場秩序を構想し、市場参加者を説得する)を行うことができます。
歴史の認識方法によって、企業のダイナミック・ケイパビリティの基盤が形成されます。客観的歴史の認識が高い企業ほど、市場の変化を早く感知できます。レトリカル・ヒストリーの認識が高い企業ほど、変革のための資源動員が効果的になります。そして想像的歴史の認識が高い企業ほど、製品・組織・市場の再構成能力が高まります。
企業が競争環境の急激な変化に適応するには、歴史を多面的に捉える能力を育成する必要があります。歴史を「過去の制約」ではなく「未来を切り開くための資源」として捉え直すことで、企業は環境変化に対応し、存続と成長を実現することができます。
歴史を正直に語る企業は信頼されやすい
歴史の解釈が企業の変化対応力を高める仕組みを見てきました。ここでは視点を変えて、企業がどのように歴史を語るかが、企業の信頼性にどう影響するかという側面に焦点を当てましょう。
企業の中には自社の歴史をマーケティングやブランディングの手法として活用するところがあります。しかし、その歴史の「真正性(authenticity)」が問われることになります。表面的あるいは一面的な歴史の活用は、かえって企業のアイデンティティや社会的正統性を損なう可能性があります。
企業が真正に歴史を語るとはどういうことでしょうか。デンマークの醸造会社カールスバーグ・グループの事例から考えてみましょう[3]。カールスバーグでは、過去の歴史を語る際に、三つの異なるプロセスを用いていることが明らかになっています。
一つ目は「誘発的歴史化」です。これは過去の出来事や遺産を自然発生的に解釈し、それが現在の企業活動やアイデンティティに影響を与えるプロセスです。カールスバーグでは、創業者の理念や初期の企業精神が、経営陣や従業員の自己理解や意思決定の指針として無意識的に作用していました。彼ら彼女らは企業の過去から自然と学び、その価値観や実践を現代に活かしていました。
二つ目は「演繹的歴史化」です。これは現在の戦略や目的に基づいて意識的に歴史を再解釈し、それを積極的に語り直すプロセスです。例えば企業のブランディング活動の中で、創業時の理念やビジョンを現代の文脈に合わせて再構築するといった取り組みが、これにあたります。カールスバーグでは、マーケティングやコミュニケーション活動において、自社の長い歴史や伝統を強調し、製品の品質や信頼性を裏付ける要素として活用していました。
三つ目は「反省的歴史化」です。これは過去の歴史に対して批判的・反省的に取り組むプロセスで、過去の過ちや問題点を認識し、それを現在の倫理的立場から再評価するプロセスです。カールスバーグがかつて取った差別的な方針や植民地的な慣習を振り返り、それを現代の価値観から批判的に検証する取り組みが該当します。
研究によれば、企業が歴史を真摯に取り扱うためには、これら三つの歴史化プロセスをバランスよく行うことが重要だと指摘されています。一方的な歴史化、例えば演繹的な(戦略的に再構成された)歴史の強調のみでは、企業の真正性や社会的信頼は維持できません。誘発的および反省的な歴史化を取り入れることで、企業のアイデンティティや信頼性を高めることができます。
都合の良い成功物語だけを強調し、失敗や問題点には触れない企業があるかもしれません。しかし、そのような一面的な歴史語りは、長期的には信頼を損なう恐れがあります。信頼される企業は、自社の歴史に誠実に向き合い、良い面も悪い面も含めて包括的に語ることができます。
例えば、カールスバーグは創業者の科学的精神や社会貢献だけでなく、第二次世界大戦中のナチスドイツとの関係や植民地での事業展開における問題点なども隠さず語ることで、却って信頼を獲得しています。過去の過ちを認め、そこから学んだことを示すことが、ステークホルダーの共感や尊敬を生み出します。
歴史を真正に語ることは、過去を美化するのではなく、その複雑さや矛盾を含めて扱うことを意味します。そうすることで、企業は自己批判的かつ正直に歴史と向き合い、アイデンティティの深みや持続可能性を高めることができます。これによって、顧客や社会からの信頼が培われ、長期的な関係構築が可能になります。
企業の歴史を語る際には、単一の「正しい」物語を押し付けるのではなく、多様な解釈や視点を許容する姿勢も大切です。過去は常に再解釈され、現在の文脈に合わせて意味づけられます。この過程を開かれたプロセスとして捉え、様々なステークホルダーの声を取り入れることで、豊かで信頼性の高い企業のアイデンティティが形成されます。
歴史を語ることで家族企業は伝統を再創造する
企業が歴史を正直に語ることで信頼を獲得できる点を議論しました。ここでは家族企業に焦点を当て、世代という概念を通じて歴史がどのように語られ、伝統が再創造されるかを考えます。
家族企業は社会の中でも独特の存在です。所有と経営が家族という紐帯で結ばれ、世代を超えた事業継承が行われるという特徴があります。従来、家族企業研究では「世代」を主に血縁関係による系譜として理解してきました。しかし実際には、「世代」という概念はより豊かな意味を持ち、戦略的に活用されています。
ドイツの老舗印刷出版企業「Bagel社」(1801年設立、7世代にわたる家族経営)の事例をもとに検討を加えてみましょう[4]。同社の文書を分析すると、「世代」という言葉が様々な文脈で語られ、その都度異なる意味を持って使われていることがわかります。
初めに、「系譜としての世代」という使い方があります。これは家族の血統として連続性を強調し、過去から未来へのつながりを示すものです。Bagel社では、家族の価値観が代々受け継がれてきたことを強調し、先祖への感謝や尊敬の念を表しています。時には先祖との象徴的な対話が語られることもあります。例えば、創業150周年記念式典でのスピーチでは、現経営者が創業者の精神に思いを馳せ、その指針が現在でも会社の決断に影響していると述べています。
系譜としての世代という概念は、家族企業特有の強みを表しています。血のつながりによる価値観の継承は、長期的な視点や安定性をもたらします。しかし、これだけでは家族企業の生存と発展は説明できません。
そこで二つ目の「神話としての世代」という使い方が登場します。これは家族企業を社会的に認知された大きな物語に結びつけ、社会的文脈の中での企業の永続性を主張するものです。Bagel社の場合、自社をグーテンベルク以来の印刷文化の伝統の一部として位置づけ、単なる一家族の事業を超えた社会的意義を強調していました。これによって、企業は社会の中での正統性や権威を獲得します。
しかし、伝統的な家族企業が生き残るためには、変化する環境に適応する必要もあります。ここで三つ目の「再創造としての世代」という使い方が重要になります。これは各世代が新しい課題に直面して家業を刷新し、自らの役割を再定義することを強調するものです。
Bagel社では、各世代が単に伝統を守るだけでなく、時代の変化に応じて伝統を再解釈し、革新を取り入れてきました。例えば、第5世代の経営者は戦後の再建期に新しい技術を導入し、第6世代は国際化戦略を進めるなど、各世代が独自の貢献で会社を発展させてきました。過去の伝統を否定するのではなく、その本質を現代に適応させる形で革新を行ったのです。
四つ目の「批判としての世代」という使い方もあります。これは社会的変化を認識し、それに応じて家族企業がどのように変わらねばならないかを指摘するものです。Bagel社では、第二次世界大戦後の再建期など、社会の大きな変動期に、既存の慣行やアイデンティティを批判的に見直す議論が行われました。こうした批判的視点が、企業の変革を促す原動力となりました。
これら四つの「世代」の語り方は、状況に応じて使い分けられています。例えば、企業の周年記念行事では「系譜としての世代」と「神話としての世代」が前面に出され、経営危機の際には「再創造としての世代」や「批判としての世代」の語りが増える傾向があります。
このように、家族企業は「世代」という概念を、血縁関係を超えて、戦略的かつレトリカルに活用しています。世代間の連続性を強調しつつも、各世代が新たな視点や価値観をもたらすことで、伝統が静的なものではなく、動的に再創造されていきます。これこそが、家族企業が何世代にもわたって存続できる秘訣の一つと言えるでしょう。
脚注
[1] Schultz, M., and Hernes, T. (2013). A temporal perspective on organizational identity. Organization Science, 24(1), 1-21.
[2] Suddaby, R., Coraiola, D., Harvey, C., and Foster, W. (2019). History and the micro-foundations of dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 41(3), 530-556.
[3] Hatch, M. J., and Schultz, M. (2017). Toward a theory of using history authentically: Historicizing in the Carlsberg Group. Administrative Science Quarterly, 62(4), 657-697.
[4] Lubinski, C., and Gartner, W. B. (2023). Talking about (my) generation: The use of generation as rhetorical history in family business. Family Business Review, 36(1), 119-142.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。