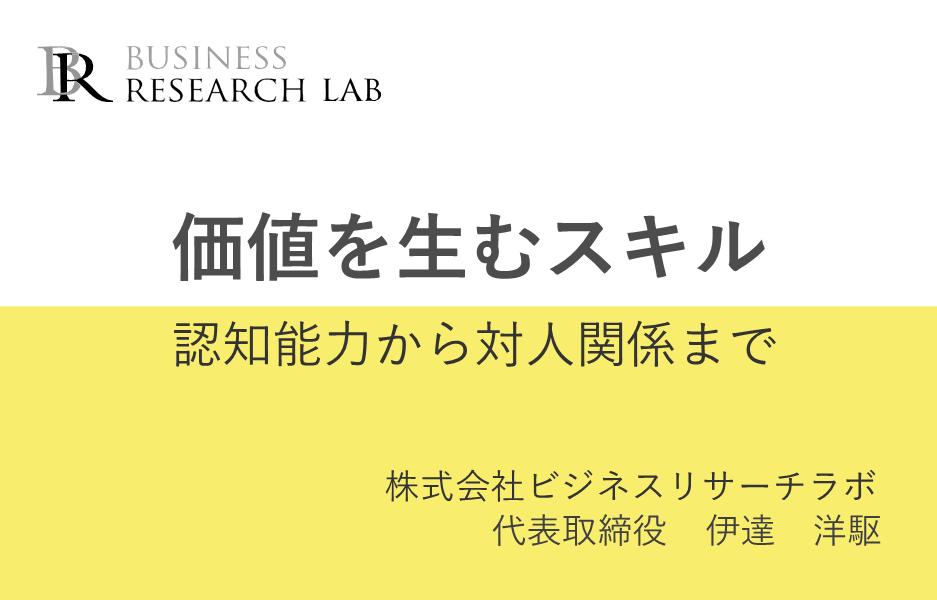2025年8月29日
価値を生むスキル:認知能力から対人関係まで
個人が持つスキルの質や種類が、私たちの仕事における成功に影響を与えるようになっています。かつては学歴や知的能力が将来の成功を予測する指標と考えられていましたが、近年の研究ではそれらよりも実際の仕事で発揮される多様なスキルこそが、職業的成功に関わることが明らかになってきました。
技術の急速な発展とグローバル化によって、求められるスキルの内容も変化しています。単純作業は自動化され、代わりに創造的思考や対人関係能力といった人間ならではの能力が重視されるようになりつつあります。組織内では個人プレーよりもチームでの協働が増え、多様な背景を持つ人々との効果的なコミュニケーション能力が求められています。
本コラムでは、スキルに関する様々な研究知見を紹介します。リーダーシップに必要な認知的スキル、チームワークに欠かせない対人関係スキル、実務的能力の重要性、そして労働市場における社会的スキルの価値の高まりなど、多角的な視点からスキルについて考察します。
これらの研究を通じて見えてくるのは、単一のスキルではなく、多様なスキルのバランスが求められているという事実です。皆さんはどのようなスキルを磨いてきましたか。そして、これからどのようなスキルを身につけていくべきでしょうか。自分自身のスキルポートフォリオを見直す機会として、本コラムをお読みいただけると良いかもしれません。
複雑な社会問題の解決には高度な認知的スキルが必要
組織が直面する課題は複雑さを増しています。市場の急速な変化、テクノロジーの進化、グローバル化による競争の激化など、組織のリーダーは前例のない中で意思決定を迫られることが多くなっています。このような状況において、リーダーシップの本質は何なのでしょうか[1]。
従来、リーダーシップは人間関係に焦点を当てて理解されてきました。カリスマ性や部下への影響力といった側面が強調され、「人を動かす力」としてリーダーシップが語られることが一般的でした。しかし、複雑化する社会において、優れたリーダーには人間関係を構築する能力だけでなく、高度な認知的スキルが必要となります。
認知的スキルとは、複雑な問題を理解し、情報を分析し、創造的な解決策を生み出す能力のことです。具体的には、問題を多角的に捉える思考力、情報を適切に収集・整理する能力、曖昧さや不確実性に対処する判断力などが含まれます。
組織においては、リーダーは3つの矛盾に直面しています。1つ目は安定性と変化のバランスです。組織は一定の安定を保ちながらも、環境変化に適応する必要があります。2つ目は組織内の異なる部門や機能の目標の不一致です。例えば、営業部門は売上を最大化したいと考える一方、品質管理部門は品質基準を厳格に守りたいと考えるでしょう。3つ目は組織全体の目標と個人のニーズの調和です。これらの矛盾は、組織内に複雑さと対立を生み出します。
こうした状況において、優れたリーダーは単純な問題解決ではなく、「複雑な社会的問題」に対処する能力を発揮します。複雑な社会的問題の特徴として、問題自体が構造化されておらず、情報が曖昧で、解決策も一つではないことが挙げられます。さらに、問題が相互に関連しており、一つの解決策が別の問題を引き起こす可能性もあります。
調査によれば、効果的なリーダーは主に3つの認知スキル領域を通じて複雑な問題を解決します。第一に「問題解決スキル」です。問題の定義から始まり、情報収集、問題の構造化、そして創造的な解決策の生成までの一連のプロセスを含みます。第二に「社会的判断スキル」です。これは解決策の実行可能性を社会的文脈の中で評価し、実行計画を形成する能力です。第三に「社会的スキル」です。他者と協力して解決策を実行するためのコミュニケーション、説得、調整の能力が含まれます。
これらのスキルの基盤となるのが知識です。タスクに関する専門的知識、組織の仕組みに関する知識、人間の行動や心理に関する知識が、問題解決の質を左右します。知識は情報の集積ではなく、過去の経験に基づいて形成された認知構造であり、リーダーシップの効果を高める要素です。
リーダーシップ能力は生まれつき決まるものではありません。個人の特性(能力、動機、人格)、キャリア経験、環境の影響が相互に作用して発達します。一定の潜在能力を持つ人が、適切な経験を積むことでリーダーシップスキルを身につけていくのです。
チームワークには対人関係スキルが特に重要
現代の組織では、個人の力だけで成果を上げることは困難になっています。多くの企業がチーム制を採用し、多様な専門性や視点を持つメンバーが協働することで複雑な課題に取り組んでいます。組織の成功は、こうしたチームがどれだけ効果的に機能するかに依存しています。
何がチームの成功を左右するのでしょうか。メンバー個人の技術的な専門知識や能力も確かに重要ですが、それだけでは十分ではありません。調査の結果、チームの効果性を高める上で重要なのは、メンバーが持つ対人関係スキルであることが明らかになっています[2]。
対人関係スキルとは、他者と効果的にコミュニケーションを取り、良好な関係を構築・維持する能力のことです。具体的には、コンフリクト(対立)を解決する能力、他者と協力して問題を解決する能力、明確かつ効果的に情報を伝達・受信する能力などが含まれます。
調査では、チームワークに必要な知識・技能・能力(KSA: Knowledge, Skill, Ability)を5つのカテゴリーに分類しています。1つ目は先に述べた対人関係スキルです。2つ目は自己管理スキルで、適切な目標を設定し自律的に行動する能力や、自身のパフォーマンスを自己評価・改善する能力が含まれます。3つ目は計画・調整スキルで、チーム内の業務割り当てや進捗管理を行う能力です。4つ目はコミュニケーションスキルで、情報を正確かつわかりやすく伝え、他者の意見に耳を傾ける能力です。5つ目は協力・支援スキルで、個人よりもチームを重視し、メンバーが困難に直面したときに支援を提供する能力が含まれます。
実験では、これらのスキルを持つメンバーで構成されたチームと、そうでないチームのパフォーマンスを比較しました。その結果、対人関係スキルの高いメンバーで構成されたチームは、そうでないチームと比較して、より良い意思決定を行い、効率的に作業を進め、メンバー間の満足度も高いことがわかりました。
技術的な専門性が高いメンバーだけで構成されたチームよりも、専門性が中程度でも対人関係スキルに優れたメンバーが含まれるチームの方が、総合的なパフォーマンスが高いことも見えてきました。チームの成功において対人関係スキルが如何に重要であるかを物語っています。
対人関係スキルがチームパフォーマンスを高める理由は何でしょうか。対人関係スキルの高いメンバーはコミュニケーションを円滑に行い、情報の共有を促進します。情報共有が活発に行われると、チーム全体の知識が拡大し、創造的な解決策が生まれやすくなります。
対人関係スキルはチーム内の対立を解決することを可能にします。意見の相違は避けられませんが、対人関係スキルが高いメンバーは、対立を個人攻撃ではなく問題解決の機会として捉え、対話を促進します。
対人関係スキルはチームの心理的安全性を高めます。心理的安全性とは、自分の意見や懸念を表明しても、拒絶されたり批判されたりしないという信頼感のことです。この環境があると、メンバーは新しいアイデアを提案したり、失敗を恐れずに挑戦したりすることができます。
成功の予測には知能より実務的スキルが重要
私たちの社会では長い間、知能テストや学力テストが人材の価値を測る指標とされてきました。学校では試験の点数が評価の中心となり、就職活動では学歴や資格が重視されます。しかし、こうした「知能」や「学力」は、実際の社会での成功をどれほど正確に予測できるのでしょうか。
1970年代初頭に実施された研究では、従来の知能テストが実際の職業的成功とほとんど関連していないことが明らかになりました[3]。この研究では、高い学業成績を収めた人々の多くが必ずしも社会的・経済的成功を収めているわけではないことが示されました。
知能テストや学力テストが成功を予測できない理由はいくつか考えられます。こうしたテストは主に学校の成績や入学試験の成績を予測するために設計されており、実際の職場で求められるスキルとは異なる能力を測定しています。学校では個人の記憶力や抽象的思考力が評価されますが、職場では対人関係能力や問題解決能力など、より実践的なスキルが求められます。
知能テストは時に社会的に恵まれた層に有利に働くという問題もあります。知能テストの得点と職業的地位の間に相関が見られる場合でも、それは能力そのものというよりも、社会階層や教育機会といった外部要因の影響を反映している可能性があります。
こうした問題を踏まえ、研究では「知能」ではなく「実務的スキル(コンピテンス)」を測定することの重要性が提案されました。コンピテンスとは、実際の仕事や生活の場面で効果的に行動できる能力のことです。知能が抽象的な概念であるのに対し、コンピテンスは具体的な行動として観察可能であるという特徴があります。
研究者は従来の知能テストに代わる新たな評価方法として、6つの原則を提案しています。1つ目は「基準サンプリング」で、実際の仕事で行う具体的な課題に基づいて能力を評価するというものです。例えば、管理職の評価なら、実際の会議運営や部下の指導場面を観察して評価します。
2つ目は「学習による変化の反映」です。能力は訓練や経験で向上するものであり、評価もそうした変化を捉えられるべきだと考えます。3つ目は「評価基準の明確化と公開」で、何が評価されるのか、どうすれば改善できるのかを受験者に明らかにするというものです。
4つ目は「幅広く役立つ能力のクラスター測定」です。特定の仕事だけに通用するスキルではなく、コミュニケーション能力や目標設定能力など、様々な状況で役立つ一般的能力を評価します。5つ目は「自発的行動の測定」で、与えられた選択肢から選ぶのではなく、自ら適切な行動を生み出す能力を測定します。
最後の原則は「自発的な思考パターンの測定」です。行動の背後にある思考プロセスや動機を評価することで、様々な状況での適応能力をより包括的に把握しようというものです。
社会的スキルの価値が近年の労働市場で高まった
この20年ほどの間に、労働市場において求められるスキルの内容が変化してきました。「社会的スキル」と呼ばれる、他者と効果的に協働・コミュニケーションする能力の価値が急速に高まっています。
社会的スキルとは、チームメンバーと協力する能力、共感力、交渉力、説得力など、人間関係の構築と維持に関わる能力の総称です。かつてはあまり注目されなかったこれらのスキルが、なぜ現代の労働市場でこれほど重視されるようになったのでしょうか。
米国の1980年から2012年までの労働市場データを分析した調査によると、社会的相互作用を必要とする職種の割合が増加したことがわかりました[4]。特に、数学的能力と社会的スキルの両方を高いレベルで要求する職種(例えば、管理職、教師、医師、弁護士など)の雇用と賃金が増加しています。
一方で、数学的能力は高いものの社会的相互作用をあまり必要としない職種(典型的には理工系の技術職)は相対的に縮小しました。この傾向は、単に高度な技術的スキルを持つだけでは不十分であり、それを他者とのコミュニケーションを通じて活かす能力が求められていることを示しています。
社会的スキルの重要性が高まっている背景には、情報通信技術(ICT)の発達があります。コンピュータ技術の進化により、定型的で予測可能な作業は機械によって自動化されるようになりました。その結果、人間に求められる業務は、より非定型的で柔軟な対応を要するものにシフトしています。
チームに基づく働き方が拡大する中で、メンバー間の効果的な協働が生産性を左右するようになっています。調査では、チーム内での「タスク交換」を円滑に行う能力が生産性向上の鍵であることが示されました。タスク交換とは、各メンバーが得意とする業務を担当し、相互に補完し合うことです。社会的スキルが高い労働者は、他者との調整やコミュニケーションのコストが低く、タスク交換を効率よく進めることができます。
技術進歩で非定型的認知スキルの需要が高まった
コンピュータやロボット技術の急速な発展は、私たちの仕事のあり方を変えつつあります。1980年代以降、技術革新が労働市場で求められるスキルの内容にどのような影響を与えてきたのか、その変化の実態とメカニズムを探る研究が行われました。
この研究では、職業を遂行するために必要な作業(タスク)の種類に着目し、それが技術革新によってどのように変化したかを分析しています[5]。研究者たちは職場のタスクを大きく2つのカテゴリーに分類しました。1つは「定型的(ルーチン)タスク」で、明確なルールやパターンに従って行われる作業です。もう1つは「非定型的タスク」で、状況に応じた判断や創造性を要する作業です。
データ分析の結果、1960年から1998年までの間に、アメリカの労働市場では定型的タスクの需要が減少し、非定型的タスクの需要が増加したことが明らかになりました。特に1980年代以降、このトレンドは加速しています。
非定型的タスクはさらに「認知的タスク」と「手作業タスク」に分けられます。認知的タスクは分析的思考や対人コミュニケーションを含み、手作業タスクは身体的な器用さや状況適応を要する作業です。調査では、特に非定型的認知タスクの需要が増加していることがわかりました。
この変化はなぜ起きたのでしょうか。研究者たちはコンピュータ技術の進歩に着目しています。コンピュータは、ルールに従って処理を行うことが得意です。そのため、定型的なタスク、つまり「もしAならBを行う」というようなルールで記述できる作業は、コンピュータによって代替されやすいのです。
一方、コンピュータが苦手とするのが非定型的タスクです。分析的思考、創造性、他者との交渉や説得といった作業は、明確なルールで記述することが難しく、人間特有の能力を要します。さらに、コンピュータ技術は非定型的認知タスクを代替するのではなく、むしろ補完する役割を果たします。
この変化は学歴による影響の差としても現れています。大卒労働者は非定型的認知タスクの需要増加から恩恵を受け、定型的認知タスクの減少の影響は比較的小さいものでした。一方、高卒以下の労働者は定型的手作業タスクの需要減少の影響を大きく受け、非定型的手作業の需要は若干増えたものの、全体としての労働需要は減少しました。
この研究からわかるのは、技術の進歩によって単に仕事が減るというよりも、仕事の内容が変化するということです。定型的な作業は機械に置き換えられる一方で、人間にしかできない非定型的な作業の価値は高まっています。
職業スキルを体系化したO*NETは実務に有効
労働市場は変化しており、新たな職業が生まれる一方で、古い職業が消えていきます。このような環境の中で、各職業にどのようなスキルや知識が必要なのかを理解することは、キャリア選択や人材育成において重要です。しかし、職業の内容は多様かつ複雑で、それを体系的に把握することは容易ではありません。
そこで開発されたのが、「職業情報ネットワーク(Occupational Information Network;O*NET)」です[6]。O*NETは米国労働省が開発した職業情報を体系化したデータベースで、従来の職業辞典に取って代わる包括的な職業情報システムとして機能しています。
O*NETの特徴は、職業を「職務」としてではなく、より広範で統合的な情報として捉えていることにあります。このシステムでは、「仕事をする人」「仕事の内容」「仕事の文脈」という3つの視点から職業を理解するアプローチが取られています。
具体的に、O*NETは6つの主要な領域に分類されています。「働く人の特性」には、認知能力、運動能力、身体能力といった個人の能力や、職業的興味、仕事に関する価値観が含まれます。そして「働くために必要な要件」として、基礎的・複合的スキル、専門的・一般的知識、必要な教育・訓練・経験が挙げられています。
「経験の要件」では、過去の職務経験や関連業務経験、組織特有の経験が含まれます。「職務の要件」には具体的な業務活動や、必要な機器・技術・資材が含まれます。「職業の特性」としては、労働市場における職業の位置づけや雇用の動向、成長性などが示されています。さらに「職業固有の情報」として、特定の職業に特化した情報や、ライセンス要件、業界特有の規制などが提供されています。
脚注
[1] Mumford, M. D., Zaccaro, S. J., Harding, F. D., Jacobs, T. O., and Fleishman, E. A. (2000). Leadership skills for a changing world: Solving complex social problems. The Leadership Quarterly, 11(1), 11-35.
[2] Stevens, M. J., and Campion, M. A. (1994). The knowledge, skill, and ability requirements for teamwork: Implications for human resource management. Journal of Management, 20(2), 503-530.
[3] McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for “intelligence.” American Psychologist, 28(1), 1-14.
[4] Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. The Quarterly Journal of Economics, 132(4), 1593-1640.
[5] Autor, D. H., Levy, F., and Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. The Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279-1333.
[6] Peterson, N. G., Mumford, M. D., Borman, W. C., Jeanneret, P. R., and Fleishman, E. A. (1999). Understanding work using the Occupational Information Network (O*NET): Implications for practice and research. Personnel Psychology, 52(2), 451-492.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。