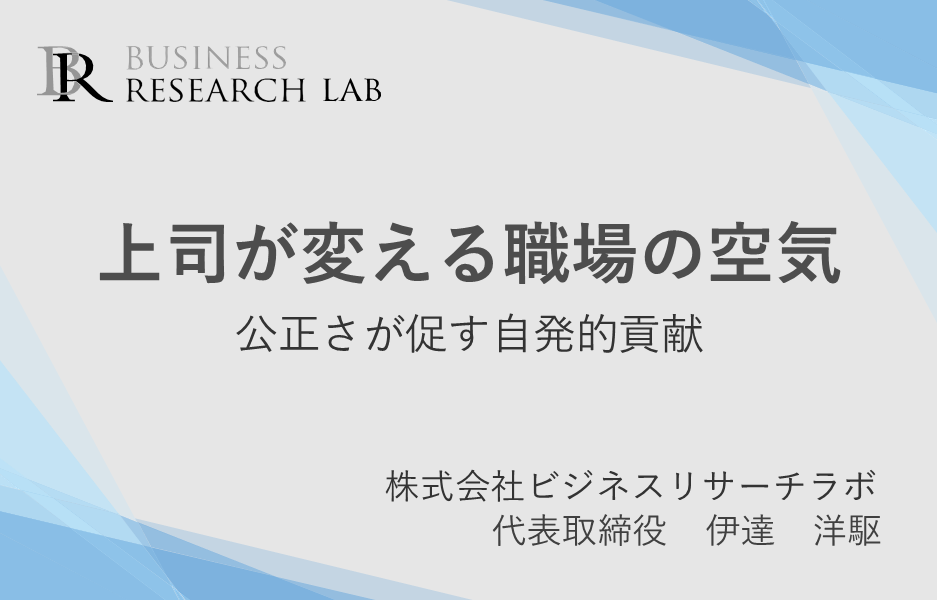2025年8月28日
上司が変える職場の空気:公正さが促す自発的貢献
職場において、給与や昇進といった報酬を得るために定められた仕事をこなすのは当然のことです。しかし、多くの組織では、業務記述書には明記されていない自発的な行動も日常的に見られます。例えば、困っている同僚を手助けしたり、会社の備品を大切に扱ったり、会議で建設的な提案をしたりする行動です。こうした自発的な行動は「組織市民行動」と呼ばれ、組織の効率性や生産性を高めています。
なぜ人は報酬が得られない行動をわざわざ行うのでしょうか。その鍵の一つとなるのが「公正感」です。職場における扱いが公正だと感じられるとき、私たちは組織に対して自発的に貢献しようという気持ちが生まれます。逆に不公正を感じると、最低限の仕事だけをして、それ以上の努力はしなくなる可能性が高まります。
本コラムでは、組織市民行動と公正感の関係について掘り下げていきます。リーダーの公正さがどのように部下の行動に変化をもたらすのか、上司との信頼関係はどう関わるのか、監視方法や対人的な関わり方はどう影響するのかなど、様々な角度から考察します。
組織市民行動にはリーダーの公正さが効く
組織の中で、業務として明確に求められていないにもかかわらず、自発的に行われる行動があります。例えば、同僚が困っているときに手を差し伸べたり、組織のルールをきちんと守ったりする行動です。こうした行動は「組織市民行動」と呼ばれ、組織全体の機能を高める上で欠かせない存在となっています。
どのような条件が整った時に、人はこのような自発的な行動を取るようになるのでしょうか。台湾の大手通信企業3社に勤務する従業員195名を対象にした調査では、リーダーの公正さが組織市民行動を促すことが分かりました[1]。
この調査では、リーダーの公正さを測るために、支持的リーダー行動(部下を支援する行動)、報酬の公正性(成果に応じた公平な報酬付与)、参加型リーダー行動(部下の意見を取り入れる行動)という3つの側面から評価しました。また、組織市民行動については、「利他主義」(他者を助ける行動)と「一般的遵守」(ルールや規範を自発的に守る行動)の2つの側面から測定しました。
調査結果から見えてきたのは、リーダーの公正さが「利他主義」的な組織市民行動に強い関係を持つということでした。とりわけ、支持的なリーダー行動が、部下の利他的な行動を促進することが明らかになりました。リーダーが部下に対して公正で支持的な態度を示すと、部下は同僚を助けるなどの利他的な行動をとる可能性が高まるのです。
一方、「一般的遵守」という側面の組織市民行動に対しては、職務の特性が大きな影響を持っていました。職務の多様性や自律性、意義、フィードバックなどの特性が豊かであるほど、ルールや規範を自発的に守る傾向が増加することが分かりました。仕事そのものに意味を見出せる場合、組織のルールを守るという行動にもつながりやすいわけです。
この調査の意義は、従来の研究で重視されていた「職務満足度」という要因が、実は組織市民行動を完全には説明できないことを明らかにした点にあります。職務に満足しているからといって、必ずしも組織市民行動をとるとは限りません。むしろ、リーダーの公正さや職務の特性そのものが組織市民行動に結びついていることが分かりました。
リーダーの公正さが組織市民行動を促す理由としては、次のような心理的なメカニズムが考えられます。リーダーが公正に振る舞うと、部下は組織や上司に対する信頼感を抱きやすくなります。そして、その信頼感が、見返りを期待しない自発的な貢献行動へとつながっていきます。
職務の特性が組織市民行動に影響する理由としては、内発的動機づけが考えられます。多様性や自律性、意義のある仕事は、外からの報酬がなくても、仕事そのものに価値を見出す気持ちを高めます。そうした内発的動機づけが、組織への自発的な貢献につながるのでしょう。
組織市民行動は上司への信頼を通じ公正さから生まれる
リーダーの公正さが組織市民行動を促すことを見てきました。この関係性をより深く理解するために、リーダーの公正さと組織市民行動の間には、どのような心理的なプロセスが働いているかを見てみましょう。
退役軍人省病院の従業員126名を対象にした研究では、上司への信頼が、リーダーの公正さと組織市民行動をつなぐことが明らかになりました[2]。この研究では、「リーダーの公正さ」→「上司への信頼」→「組織市民行動」という流れのモデルを検証しました。
リーダーの公正さは、「手続き的公正」と「分配的公正」の2種類に分けて測定されました。手続き的公正とは、意思決定の過程が公平かどうかを指します。一方、分配的公正とは、報酬や結果の分配が公平かどうかを指します。
結果、手続き的公正は上司への信頼を高めることが分かりました。分配的公正も上司への信頼に良い影響を与えましたが、手続き的公正の方がより強い影響力を持っていました。従業員は結果(報酬や待遇)そのものよりも、それらを決める過程の公正さをより重視するということです。
そして、上司への信頼は組織市民行動に強く結びついていました。信頼できる上司の下では、従業員は自発的に組織に貢献する行動を取りやすくなります。
この研究で興味深いのは、手続き的公正や分配的公正が組織市民行動に及ぼす影響は、信頼を媒介することで完全に説明される点です。要するに、リーダーの公正さだけでは直接的に組織市民行動を促すわけではなく、あくまでも「上司への信頼」を通じて間接的に影響していると考えられます。
社会的交換理論の観点から考えると、リーダーが公正な判断をしていると従業員が感じれば、その上司に対する信頼が生まれます。信頼関係が構築されると、従業員は上司や組織との間に社会的な交換関係を感じ、その関係性を維持・発展させるために自発的な貢献を行います。
これは、先ほど見たリーダーの公正さと組織市民行動の関係をより深く説明するものです。リーダーの公正さは直接的に組織市民行動を促すわけではなく、上司への信頼という心理的なプロセスを経て間接的に影響するのです。
特に手続き的公正が重要であるという点は、管理職の日常行動に関わる発見です。結果や報酬の分配を全員が満足いくように行うことは難しいかもしれませんが、少なくともその決定プロセスを透明で一貫性のあるものにすることは可能です。意思決定の過程において従業員の意見を聞く機会を設けたり、決定理由を明確に説明したりすることで、手続き的公正を高めることができるでしょう。
組織市民行動は上司の監視方法による公正感で高まる
上司への信頼がリーダーの公正さと組織市民行動をつなぐことを見てきました。上司が日常的に行う監視活動は、どのように従業員の公正感や組織市民行動に関係しているのでしょうか。
米国南西部の映画館チェーンで働く213名の従業員とその上司11名を対象にした研究では、上司の監視方法が組織市民行動に及ぼす影響を調査しました[3]。この研究では、監視方法を「観察」(上司が部下の仕事を直接見て確認する)、「非公式なディスカッション」(上司が部下と仕事について非公式に話し合う)、「公式な会議」(正式な会議や報告の機会を通じて進捗を確認する)の3つに分類しました。
調査結果から、「観察」と「公式な会議」という監視方法が組織市民行動に直接的な良い影響を持つことが分かりました。また、すべての監視方法(観察、非公式なディスカッション、公式な会議)が、従業員の公正感を高めることも明らかになりました。
ここにおける公正感は、「分配的公正」(結果や報酬の分配が公正であるという感覚)、「手続き的公正」(意思決定プロセスが公平であるという感覚)、「対人的公正」(上司とのやりとりが敬意と配慮に満ちているという感覚)の3つの次元から測定されました。そして、これら3つの公正感はいずれも組織市民行動を高める効果がありましたが、特に手続き的公正と対人的公正の影響が大きいことが分かりました。
直接的に観察すること、および公式な会議で進捗を確認することは、組織市民行動に直接つながりますが、それだけでなく公正感を媒介して間接的にも影響します。一方、非公式なディスカッションは直接の影響は弱く、公正感を媒介することによってのみ組織市民行動に関係していました。
「観察」という監視方法は、上司が部下の仕事ぶりを直接見ることで、部下の努力や成果を正確に把握できます。そのため、評価や報酬が公正に行われる可能性が高まり、部下の公正感が高まると考えられます。また、上司が部下の仕事を直接見ていることで、部下は自分の貢献が認識されていると感じ、それが組織市民行動の動機づけになるのかもしれません。
「公式な会議」では、全員が同じ情報を共有し、進捗を報告する機会が平等に与えられるため、手続き的公正が高まりやすいでしょう。会議という公の場で自分の貢献を示すことができるため、それが組織市民行動を促す動機になることも考えられます。
「非公式なディスカッション」は、上司と部下の間で個別にコミュニケーションが取られるため、対人的公正感を高める効果があります。しかし、それだけでは直接的に組織市民行動を促すには不十分です。公正感を通じて間接的に組織市民行動に結びつくというわけです。
組織市民行動は上司の対人的な公正さで高まる
米国中西部の2つの中規模企業(鉄鋼加工会社と塗料製造会社)の従業員225名とその上司を対象にした研究では、組織的公正と組織市民行動の関係が調査されました[4]。この研究では、組織的公正を「分配的公正」(結果や報酬の分配が公正かどうか)と「手続き的公正」(意思決定過程が公正かどうか)に分類し、さらに手続き的公正を「正式な手続き」と「相互作用的公正」(上司との対人的なやりとりの公正さ)の2つに細分化しました。
調査の結果、相互作用的公正(上司との対人的な公正さ)が、組織市民行動の5つの次元(利他主義、礼儀正しさ、スポーツマンシップ、良心性、市民的美徳)のうち4つ(利他主義、礼儀正しさ、スポーツマンシップ、良心性)を予測する強力な要因であることが明らかになりました。上司が部下に対して公正に接する、具体的には敬意を持って接する、意見を聞く、説明をする、といった対人的な行動が、部下の組織市民行動を促す上で重要だということです。
この研究では、組織的公正と職務満足度の関係も調査されました。分配的公正、正式手続き、相互作用的公正のすべてが職務満足度に良い影響を与えていました。しかし、職務満足度と組織市民行動の間には直接的な関係は見られませんでした。公正感を考慮に入れると、職務満足度自体は組織市民行動を直接予測しないのです。
この発見は興味深いものです。従来の研究では、職務満足度と組織市民行動の間に関連があると考えられてきましたが、この研究は、その関係性の裏には公正感が媒介として存在することを示しています。従業員は単に仕事に満足しているから組織市民行動をとるわけではなく、職場での扱いが公正だと感じるからこそ、自発的な貢献を行うのです。
とりわけ相互作用的公正(上司との対人的な公正さ)が組織市民行動に強く関連していたという点は、管理職の普段の行動の重要性を示唆しています。組織の正式な手続きや制度がどれほど公正に設計されていても、それを実行する上司の対人的な振る舞いが不公正であれば、従業員の組織市民行動は抑制されてしまうかもしれません。
上司との日常的なやりとりは、従業員にとって最も直接的で具体的な公正さの経験となります。制度やルールは抽象的で遠い存在ですが、上司の言動は毎日の仕事の中で直接体験するものです。そのため、上司がどれだけ敬意をもって接してくれるか、説明をしてくれるか、意見を聞いてくれるかといった対人的な公正さが、従業員の行動に影響を及ぼすのでしょう。
組織市民行動はリーダーとの関係が良いほど高まる
ここまで、リーダーの公正さ、上司への信頼、監視方法、対人的な公正さなど、様々な角度から組織市民行動の促進要因を見てきました。最後に、これらをより包括的に捉える視点として、リーダーと部下の関係の質(Leader-Member Exchange:LMX)に着目します。
質の高いLMXでは、信頼、サポート、報酬の交換レベルが高くなります。このLMXと組織市民行動の関係を、50のサンプル(総数9,324名)を対象にしたメタ分析の結果から見ていきましょう[5]。
このメタ分析では、LMXと組織市民行動の間に中程度に強い正の関係があることが確認されました。リーダーと部下の関係の質が高いほど、部下は組織市民行動を行うということです。
LMXは「個人指向型の組織市民行動」(同僚への援助行動や礼儀正しさなど、特定の個人を直接支援する行動)と「組織指向型の組織市民行動」(組織全体の利益に寄与する行動)のどちらにより強く関連するのでしょうか。分析の結果、LMXは個人指向型の組織市民行動とより強く関連していることが分かりました。
LMXは基本的に人間関係に基づく社会的交換を意味します。そのため、特定の個人(同僚など)に対する直接的な援助行動の形で組織市民行動が現れやすいのです。上司との良好な関係が、職場の他のメンバーに対する援助行動にも波及します。
先ほど見た対人的な公正さの重要性とも関連しますが、LMXはより包括的に上司と部下の関係の質を捉えています。対人的な公正さはLMXの一部ではありますが、LMXには信頼、尊敬、相互の責任感など、より幅広い要素が含まれます。
脚注
[1] Farh, J. L., Podsakoff, P. M., and Organ, D. W. (1990). Accounting for organizational citizenship behavior: Leader fairness and task scope versus satisfaction. Journal of Management, 16(4), 705-721.
[2] Konovsky, M. A., and Pugh, S. D. (1994). Citizenship behavior and social exchange. Academy of Management Journal, 37(3), 656-669.
[3] Niehoff, B. P., and Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 36(3), 527-556.
[4] Moorman, R. H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship? Journal of Applied Psychology, 76(6), 845-855.
[5] Ilies, R., Nahrgang, J. D., and Morgeson, F. P. (2007). Leader-member exchange and citizenship behaviors: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92(1), 269-277.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。