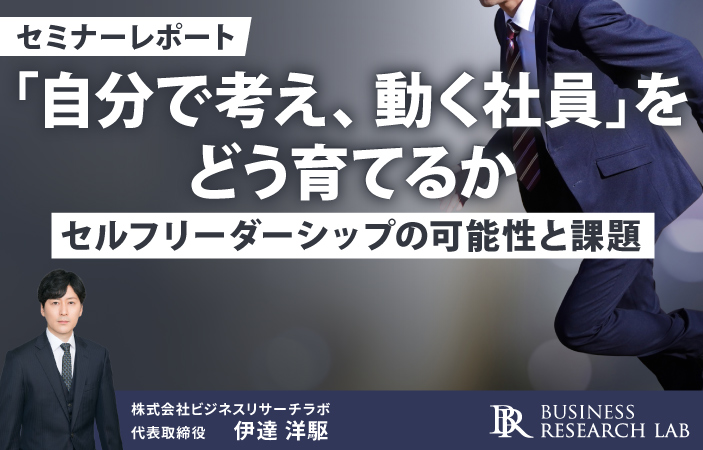2025年8月27日
「自分で考え、動く社員」をどう育てるか:セルフリーダーシップの可能性と課題(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年8月にセミナー「『自分で考え、動く社員』をどう育てるか:セルフリーダーシップの可能性と課題」を開催しました。
先行きが不透明で、変化の速い時代において、組織が成長するためには、社員一人ひとりが自分で考え、動く力が欠かせません。上司からの指示を待つだけでは乗り越えられない課題が増えているからです。そこで今、「セルフリーダーシップ」という考え方が注目されています。
セルフリーダーシップとは、自分自身をリーダーとして導く力のことです。自分を管理するだけでなく、自ら目標を立て、自分の考えや行動を良い方向に導きながら、主体的に仕事を進めていく能力を指します。
セルフリーダーシップは、個人の仕事の成果や満足感を高めるだけでなく、新しいアイデアを生み出し、組織の変革を後押しする力にもなります。例えば、テレワークのように上司や同僚と離れて働くときには、自分でやる気を保ち、成果を出すために、セルフリーダーシップがますます重要になることが研究で示されています。
しかし、セルフリーダーシップは誰にでも、いつでも同じように効果を発揮するわけではありません。その効果は、本人の「自分で決めたい」という意欲の強さや、仕事の進め方の自由度、職場の雰囲気など、様々な条件によって変わってきます。また、一般的に良い面ばかりが語られますが、あまり知られていない一面や課題も存在します。
本セミナーでは、株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役の伊達洋駆が登壇し、セルフリーダーシップについて、国内外の研究で分かってきたことをお伝えしました。セルフリーダーシップが「どんなときに力を発揮するのか」、そして「組織として、どうすればその力を育て、活かせる環境をつくれるのか」を、様々な角度から考えました。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
予測不可能な変化が続く状況下で組織が持続的に成長するためには、社員一人ひとりが指示を待つのではなく、自らの意思で考え、主体的に行動することが求められます。「自分で考え、動く社員」をいかにして育てるかという問いは、多くの企業にとって重要な人事課題となっています。その解決の鍵を握る一つが、本講演で探求する「セルフリーダーシップ」です。本講演では、このセルフリーダーシップの可能性と、育成における課題について、研究知見を交えながら多角的に考察します。
自分で自分を導く技術
セルフリーダーシップとは、自分自身の思考や行動に影響を与え、自身を動機づけ、目標達成へと導くための一連の思考と行動の戦略です。セルフリーダーシップは自己管理とは一線を画し、より能動的に自分自身をリードしていく技術と言えます。この概念は、大きく三つの次元からなる構造で理解することができます[1]。
第一の次元は「行動中心戦略」です。これは、自身の行動を管理し、目標達成の確率を高めるための方法です。例えば、自ら挑戦的かつ具体的な目標を設定する「自己目標設定」や、日々の行動や進捗を記録・観察する「自己観察」がこれにあたります。目標を達成した際に自分自身にご褒美を与える「自己報酬」や、逆に達成できなかった際に自らを律する「自己処罰」といった方法も、行動を望ましい方向へ導くための要素です。これらの戦略は、いわば自分自身のマネージャーとして、行動を計画し、実行し、評価するプロセスを自律的に行うことに他なりません。
第二の次元は「自然報酬戦略」と呼ばれます。これは、仕事そのものに内在する楽しさや満足感、意義を見出し、それを内発的動機づけの源泉とするアプローチです。私たちは、外部からの報酬や評価がなくとも、活動自体に喜びを感じることで、より高い集中力と持続力を発揮できます。例えば、困難な課題をゲームのように捉えて攻略する楽しみを見出したり、一見単調に見える作業の中に社会への貢献や自己成長といった意義を見出したりする工夫がこれに該当します。この戦略は、仕事の「やらされ感」を払拭し、自発的なエンゲージメントを引き出す上で重要です。
第三の次元は「建設的思考パターン戦略」です。これは、思考の質そのものを改善し、パフォーマンスを高めるための認知的なアプローチです。目標を達成した姿を心に描く「成功の視覚化」や、「自分ならできる」「この失敗は次への糧になる」といった前向きな言葉を自身に投げかける「肯定的な自己対話」がその代表例です。また、「自分にはこの仕事は向いていない」といった非生産的な思い込みや固定観念を客観的に見つめ直し、より建設的なものへと修正していくプロセスも含まれます。思考は感情や行動の源泉であり、この内なる対話をコントロールすることが、困難な状況を乗り越えるための基礎となります。
これらの三つの戦略は、それぞれ独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。これらの戦略を意識的に学び、日々の業務の中で実践していくことが、セルフリーダーシップの基本となります。例えば、難しい課題に対して、まずはそれを小さなステップに分解して一つずつ達成していく(行動中心戦略)ことで成功体験を積み重ねる。その経験が「自分はできる」という自信、すなわち「自己効力感」を育み、それがさらなる挑戦への意欲(自然報酬戦略)や、前向きな思考(建設的思考パターン戦略)へとつながっていくのです。このように、セルフリーダーシップとは、自分自身を導くための技術の集合体であり、意識的な訓練によって誰もが高めていくことのできる能力です。
なぜセルフリーダーシップは重要か
セルフリーダーシップは、個人の生産性を高めるだけでなく、組織全体の活性化や従業員のウェルビーイングにも関わることが、学術研究によって示されています。
セルフリーダーシップは職場の心理的負担を予防する効果があります。ある公的機関の従業員を対象に行われたトレーニング実験では、セルフリーダーシップの研修を受けたグループは、受けていないグループに比べて心理的負担が有意に減少するという結果が示されました[2]。このメカニズムを分析すると、セルフリーダーシップはストレスそのものを直接取り除くのではなく、「自分は物事をうまくやり遂げられる」という自信(自己効力感)や、仕事に対する喜びや誇りといったポジティブな感情を増やすことで、結果的にストレスへの耐性を高めていることが分かりました。
これは、心理学の「資源保存理論」で説明できます。この理論では、ストレスとは、自信や前向きな感情、良好な人間関係といった個人が持つ「心理的資源」が脅かされたり失われたりする際に生じると考えられています。セルフリーダーシップは、この心理的資源を内側から豊かにすることで、外部からのストレスに対する防波堤を築きます。
セルフリーダーシップは組織の革新を促す原動力ともなります。タイの地域特産品を生産する小規模生産者グループを対象とした調査では、興味深い関係性が見出されました[3]。当初の予測とは異なり、セルフリーダーシップは直接的に組織の革新行動に結びつくわけではなく、個人の「創造性」を高めることを通じて、間接的に革新を促進していました。
セルフリーダーシップが高い人は、自己管理能力に長けているため、新しいアイデアを生み出す過程で困難に直面しても、粘り強く思考を続けることができます。セルフリーダーシップは創造性を発揮するための土台となり、その創造性が革新という果実を生みます。もちろん、革新の実現には、リスクテイクを許容する組織文化や知識を共有する仕組みといった環境要因も不可欠ですが、その根底には個人の創造性を支えるセルフリーダーシップが存在すると言えます。
また、セルフリーダーシップは、上司から評価される形での革新性を高めることも分かっています。イスラエルの様々な組織で働く従業員とその上司を対象にした研究では、従業員の革新的行動を「自己評価」と「上司からの評価」の両面から測定しました[4]。その結果、特に目標達成に向けた計画的な行動を促す「行動中心戦略」や、困難を乗り越えるための「建設的思考戦略」が高い従業員ほど、上司からも「革新的である」と評価される傾向が強いことが確認されました。
一方で、仕事の楽しさを見出す「自然報酬戦略」は、本人の内面的な動機づけにはつながるものの、必ずしも上司から評価される革新行動とは直接関連が見られませんでした。これは計画性や粘り強さといった要素が、他者から見て分かりやすい成果として認識されやすいことを示唆しています。
セルフリーダーシップは「自己効力感」を介して成果を高めることも実証されています。ある大学で行われた研究では、学生たちのセルフリーダーシップが、直接的に学業成績を向上させるわけではないことが示されました[5]。その代わりに、セルフリーダーシップが高い学生は「自分ならできる」という自己効力感が高まり、その高まった自己効力感が、高い学業成績へとつながるという連鎖反応が確認されました。目標設定や自己観察といった戦略が、自分の行動をコントロールできているという感覚を強め、それが自信となって実際の行動を支えるという、心理的なメカニズムが働いています。
そして、セルフリーダーシップはチームのパフォーマンス向上にも貢献します。オーストラリアの製造企業を対象とした調査では、行動中心型のセルフリーダーシップが高い従業員ほど、仕事内容そのものから得られる内発的な満足感と、給与などから得られる外発的な満足感の両方が高いことが分かりました[6]。この高まった職務満足が、チーム全体の財務的・非財務的なパフォーマンスに好影響を与えていました。自分で自分を律することができるという自律性の感覚が、仕事への満足度を高め、それがチームへの貢献意欲や協調性を促して、組織全体の成果を底上げするという好循環を生み出していたのです。
これらの研究結果は、セルフリーダーシップが個人、チーム、組織全体に多岐にわたる利益をもたらす能力であることを示しています。
セルフリーダーシップを活かす環境の作り方
社員がどれほど高いセルフリーダーシップのスキルを身につけたとしても、それだけでは十分な効果を発揮することはできません。個人の能力が組織の力として結実するためには、その能力を存分に活かすことのできる「環境」が不可欠です。ここでは、セルフリーダーシップの効果を最大化するための環境要因について探っていきます。
第一に、セルフリーダーシップが創造性として開花するためには、職場からの支援が決定的な役割を果たします[7]。セルフリーダーシップは、あくまで創造性の「潜在能力」を高めるものです。この潜在能力を、実際にアイデアを形にする「実践的創造性」へと転換できるかどうかは、周囲の環境に左右されます。
研究によれば、支援の源は「チーム」「上司」「組織全体」の三つに大別されます。例えば、革新的なアイデアを思いついても、上司が聞く耳を持たなかったり、チームメンバーが非協力的であったりすれば、そのアイデアは実行に移されることなく消えてしまいます。組織全体としても、情報共有が円滑に行える仕組みや、失敗を恐れずに挑戦できる文化、公正な評価制度などが整っていなければ、社員は革新的な行動を躊躇するでしょう。企業はセルフリーダーシップ研修といった人材育成だけでなく、その能力を安心して発揮できる土壌を耕す努力を同時に進める必要があります。
第二に、セルフリーダーシップの効果は、仕事の進め方における個人の自由裁量、すなわち「職務自律性」の高さに影響されます。中国の複数の組織を対象とした調査では、職務自律性が高い環境で働く従業員の場合、セルフリーダーシップと職務成果の間に強い正の関係が見られました[8]。しかし、逆に職務自律性が低く、厳格なルールやマニュアルに縛られた環境では、その関係性は弱まることが判明しました。
この現象は「状況強度理論」によって説明できます。この理論は、規則が厳格で個人の裁量が小さい「強い状況」では個人の性格や能力といった特性が行動に現れにくく、逆に自由度が高い「弱い状況」では個人の特性が発揮されやすいと説明します。セルフリーダーシップという個人の能力を最大限に引き出すためには、スキルを教えるだけでなく、社員に一定の裁量権を与え、自らの判断で仕事を進められるような「弱い状況」を作り出すことが必要です。
第三に、セルフリーダーシップは、テレワークなどのバーチャルな労働環境において、その重要性を一層増すことが分かっています。複数の企業を対象とした調査によると、リーダーと部下が物理的に離れた場所で働くほど、リーダーが部下に与える直接的な影響力は弱まる傾向にありました[9]。その一方で、従業員がバーチャルな環境で働く度合いが高まるほど、個人のセルフリーダーシップが仕事のモチベーションに与える影響は、より一層強くなることが確認されました。
オフィスにいれば、上司からの声かけや同僚との雑談といった外部からの刺激によってモチベーションが維持されることもありますが、在宅勤務などではそうした機会が減少します。その分、自分自身で目標を設定し、進捗を管理し、内側からやる気を引き出すセルフリーダーシップの役割が、パフォーマンスを維持・向上させる上で重要になるのです。
第四に、セルフリーダーシップの効果的な育成方法は、全ての部下に一様に通用するわけではなく、個人の「自律性欲求」の度合いによって調整する必要があります。ある米国の企業を対象とした研究では、部下の自主性を重んじる「エンパワリング型リーダーシップ」は、もともと自律的に行動したいという欲求が強い部下のセルフリーダーシップを促進する一方で、そうした欲求が低い部下には必ずしも響かないことが示されました[10]。さらに、自律性欲求が強い部下に対して、上司が細かく指示を出す「指示型リーダーシップ」を取った場合、かえって部下のセルフリーダーシップの発揮が抑制されてしまうという結果も出ています。
このことは、全ての社員が権限委譲を望んでいるわけではないという事実を示唆しています。人によっては、明確な指示があった方が安心して業務に取り組める場合もあります。部下一人ひとりの特性を見極め、ある時には背中を押し、ある時には具体的な道筋を示すといった、柔軟な関わり方が求められます。
部下のセルフリーダーシップを育む支援策
これまでの考察を踏まえ、管理職や人事担当者が部下のセルフリーダーシップを育むために実践できる支援策を、三つの柱で整理します。これらの支援は、個人のスキル開発と、それを活かす環境整備の両輪で進めることが重要です。
第一の柱は「自律性を引き出す関わり方」です。これは、部下が自らの能力を発揮する機会を創出することに主眼を置きます。まず、可能な範囲で仕事の進め方や意思決定を部下に任せてみましょう。研究が示すように、職務自律性が高い環境では、個人が持つセルフリーダーシップのスキルが成果に結びつきやすくなります。裁量を与えることは、部下に対する信頼の証であり、責任感を育みます。
同時に、部下一人ひとりの「自律性欲求」を見極め、関わり方を変える視点も不可欠です。全ての部下が同じレベルの自律を求めているわけではありません。自律を求める部下には積極的に権限を委譲し、一方で明確な指示を求める部下には丁寧なガイドを提供するといった個別のアプローチが、部下の心理的な適合性を高め、自発的な行動を引き出します。
第二の柱は「自ら手本となり、動機づける」ことです。上司自身の姿勢やチーム運営のスタイルは、部下のセルフリーダーシップに影響を与えます。特に効果的なのは、上司自身が仕事を楽しむ姿、すなわち「自然報酬戦略」を実践して見せることです。リーダーが内発的に動機づけられ、仕事に喜びを見出している姿は、その熱意が部下にも伝播し、チーム全体のエンゲージメントを高めます。
また、トップダウンで物事を決定するのではなく、部下がチームの意思決定に参加できる機会を設けることも重要です。このような参加型のマネジメントスタイルは、部下に当事者意識を芽生えさせ、組織からの支援として認識されるため、創造性や革新性の発揮を後押しします。
第三の柱は「成長をデザインし、支援する」というアプローチです。これは、部下の自信と能力を施策で高めていくことを目指します。セルフリーダーシップを成果につなげる鍵は、「自分ならできる」という自己効力感です。自己効力感を育むためには、いきなり大きな課題を与えるのではなく、挑戦的な課題を達成可能な小さなステップに分解し、一つずつ成功体験を積ませることが効果的です。小さな成功の積み重ねが、やがて大きな自信へとつながります。
さらに、チーム内で知識や成功事例、失敗から得た教訓などを共有できるミーティングを定期的に設けることも支援策です。個人の持つ知がチームの知へと昇華するプロセスは、個人の創造性を組織全体の革新へと結びつけるに重要です。これらの支援を通じて、部下が安心して挑戦し、成長できる環境を整えることが、セルフリーダーシップを育むことにつながるでしょう。
おわりに
本講演では、「自分で考え、動く社員」を育てるための鍵として、セルフリーダーシップの概念、その重要性、育成のための環境と支援策について考察してきました。セルフリーダーシップは、行動を管理する技術、仕事の捉え方を変える技術、思考を改善する技術から成り立っており、個人の成果やウェルビーイング、さらにはチームや組織の革新性にまで好影響を及ぼすことが明らかになりました。
しかし重要なのは、セルフリーダーシップは個人のスキルのみで完結するものではないという点です。社員がその能力を最大限に発揮するためには、裁量権のある職務環境、挑戦を後押しする組織文化、一人ひとりの特性に合わせた上司の支援が求められます。
最後に、ある研究では、セルフリーダーシップが高いリーダーほど、部下にビジョンを示し成長を促すといった、より積極的で望ましいリーダーシップを発揮する傾向があることが示されています[11]。自分自身を正しく導く能力は、他者を導く優れたリーダーシップの基盤となり得ます。セルフリーダーシップの育成は従業員教育に留まらず、次世代のリーダーを育てるための第一歩であると言えます。
Q&A
Q:高いレベルでセルフリーダーシップを発揮している社員に対して、会社は報酬という形で報いるべきでしょうか。
セルフリーダーシップと報酬の関係は、社員のモチベーションを考える上で重要な論点です。結論から言うと、給与やボーナスといった金銭的な報酬と直接結びつけることは、慎重になるべきだと考えます。セルフリーダーシップの本質は、仕事そのものへの興味や成長意欲といった内発的動機づけにあるため、金銭という外発的動機づけを結びつけると、かえって純粋なやる気を損なう危険性があるからです。
そこで、報酬をより広い意味で捉え、非金銭的な報酬を充実させることをお勧めします。例えば、より大きな裁量権を与えたり、本人の成長につながる挑戦的なプロジェクトを任せたりすることです。また、本人が希望する研修への参加を支援することも、成長意欲に応える報酬となります。このような形で報いることが、セルフリーダーシップをさらに強化し、組織全体の力にもなっていくでしょう。
Q:上からの指示で物事が決まる、いわゆるトップダウンの文化が強い組織風土の中で、社員一人ひとりのセルフリーダーシップを根付かせるには、何から手をつければよいでしょうか。
トップダウン文化が根強い組織でセルフリーダーシップを育むには、多くの方が悩む点かと思います。組織全体の文化を一度に変えるのは困難です。そこで提案したいのが、スモールスタートで成功事例を作ることです。組織の中にも、比較的、現場の自律性が高い部門やプロジェクトがあるはずです。まずはそうした環境を「パイロットケース」として選び、そこで集中的にセルフリーダーシップを高める取り組みを試します。
自律性が認められている環境であれば、セルフリーダーシップの向上は目に見える成果につながりやすくなります。その成功事例を社内で共有することで、「セルフリーダーシップは成果につながる有効なスキルだ」という認識が広がり、他の部門へも良い影響が波及していくでしょう。限定的な範囲で確実に成果を出すアプローチが現実的かつ効果的です。
Q:常に自分を律して主体的に行動することを求められると、かえって真面目な社員ほど燃え尽きてしまわないか心配です。セルフリーダーシップの推進が、社員にとって新たな精神的負担とならないようにするには、どのような配慮が必要でしょうか。
重要な指摘です。セルフリーダーシップが「常に完璧でなければならない」というプレッシャーになり、燃え尽きにつながるのではないかという懸念ですね。本来、セルフリーダーシップは仕事へのコントロール感を高め、ストレスを軽減する効果があります。しかし、それが過剰に求められたり、完璧主義と結びついたりすると、精神的な負担になりかねません。
これを避けるために重要な配慮は、心理的安全性の高い環境を同時に整えることです。心理的安全性とは、誰もが「失敗しても大丈夫だ」「挑戦が歓迎される」と感じられる状態を指します。マネージャーは部下の挑戦を奨励し、結果だけでなくプロセスを評価する姿勢が求められます。失敗を責めるのではなく、チームの学びとして次に活かす文化があって初めて、社員は安心してセルフリーダーシップを発揮できます。
Q:セルフリーダーシップという言葉は、モチベーション、オーナーシップ、主体性といった他の言葉と、どのように違うのでしょうか。定義が広いように感じます。
これらの言葉は関連が深く、違いが分かりにくいかもしれません。まず、モチベーションを高めることは、セルフリーダーシップの重要な構成要素の一つですが、それが全てではありません。オーナーシップ(当事者意識)や主体性は、主に「仕事に対する姿勢」や「精神的なあり方」を指します。一方で、セルフリーダーシップは、そうした姿勢にとどまらず、それを実現するための具体的な「技術」や「行動」の集合体であるという点が特徴です。技術として体系化されているため、誰もが学び、実践しやすいという利点があります。
Q:全社的にセルフリーダーシップを育成することは、将来の経営幹部候補の育成、いわゆるサクセッションプランにも貢献するように感じました。
セルフリーダーシップの育成は、次世代リーダーを育てるためのサクセッションプランにおいて、重要な土台となり得ます。「自分自身を導くことができない人に、他者や組織を導くことはできない」という考え方が根底にあります。キャリアの早い段階から、自ら目標を設定し、モチベーションを管理し、物事を前に進めていく経験を積むことは、将来リーダーに求められる資質やスキルを自然と身につけていくことに他なりません。全社的なセルフリーダーシップの育成は、将来の組織を担うリーダー候補者層を厚くする、有効な人材開発投資であると言えるでしょう。
Q:正直なところ、どうしても好きになれない、退屈だと感じてしまう業務があります。そのような仕事に対して、講演にあった自然報酬戦略を適用し、楽しみや意義を見出すためのコツや思考法があれば教えてください。
多くの方が共感するお悩みだと思います。退屈だと感じる作業に、内側からのやる気を見出すコツを2つ紹介します。
一つは、「ゲーミフィケーション」という考え方です。退屈な業務をゲームのように捉え直し、例えば、「昨日の自分より1分早く終わらせる」「ミスをゼロにする」といった自分だけの小さな目標を設定します。自己ベストの更新を目指すことで、退屈な作業にゲーム性が生まれ、達成感や楽しさを見出しやすくなります。
もう一つは、その仕事が持つ社会的な意義を改めて想像してみることです。自分の仕事が組織の中でどのような役割を果たし、最終的に誰の役に立っているのかをイメージします。仕事に対する見方が変わり、意味や誇りを見出す手助けになることがあります。
脚注
[1] Houghton, J. D., and Neck, C. P. (2002). The revised self-leadership questionnaire: Testing a hierarchical factor structure for self-leadership. Journal of Managerial Psychology, 17(8), 672-691.
[2] Unsworth, K. L., and Mason, C. M. (2012). Help yourself: The mechanisms through which a self-leadership intervention influences strain. Journal of Occupational Health Psychology, 17(2), 235-245.
[3] Pratoom, K., and Savatsomboon, G. (2012). Explaining factors affecting individual innovation: The case of producer group members in Thailand. Asia Pacific Journal of Management, 29(4), 1063-1087.
[4] Carmeli, A., Meitar, R., and Weisberg, J. (2006). Self-leadership skills and innovative behavior at work. International Journal of Manpower, 27(1), 75-90.
[5] Prussia, G. E., Anderson, J. S., and Manz, C. C. (1998). Self-leadership and performance outcomes: The mediating influence of self-efficacy. Journal of Organizational Behavior, 19(5), 523-538.
[6] Politis, J. D. (2006). Self-leadership behavioural-focused strategies and team performance: The mediating influence of job satisfaction. Leadership & Organization Development Journal, 27(3), 203-216.
[7] DiLiello, T. C., and Houghton, J. D. (2006). Maximizing organizational leadership capacity for the future: Toward a model of self-leadership, innovation and creativity. Journal of Managerial Psychology, 21(4), 319-337.
[8] Ho, J., and Nesbit, P. L. (2014). Self-leadership in a Chinese context: Work outcomes and the moderating role of job autonomy. Group & Organization Management, 39(4), 389-415.
[9] Andressen, P., Konradt, U., and Neck, C. P. (2012). The relation between self-leadership and transformational leadership: Competing models and the moderating role of virtuality. Journal of Leadership & Organizational Studies, 19(1), 68-82.
[10] Yun, S., Cox, J., and Sims Jr, H. P. (2006). The forgotten follower: A contingency model of leadership and follower self-leadership. Journal of Managerial Psychology, 21(4), 374-388.
[11] Furtner, M. R., Baldegger, U., and Rauthmann, J. F. (2013). Leading yourself and leading others: Linking self-leadership to transformational, transactional, and laissez-faire leadership. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(4), 436-449.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。