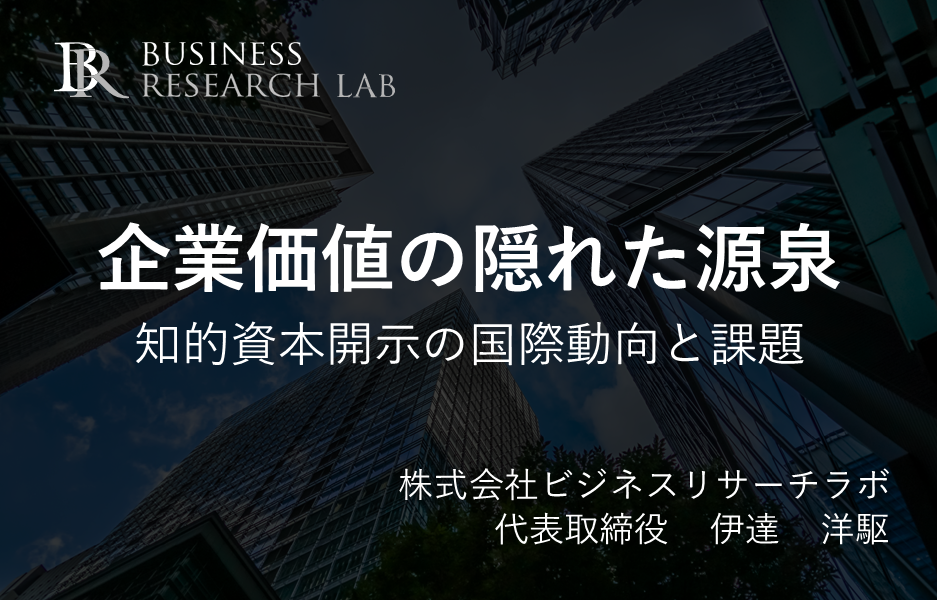2025年8月27日
企業価値の隠れた源泉:知的資本開示の国際動向と課題
企業の価値を決める要素が変化しつつあるという指摘があります。かつては「目に見える資産」が企業価値の中心でしたが、今日では技術やノウハウ、顧客との関係、従業員の能力といった「目に見えない資産」が企業の競争力に影響を与えるようになりました。この「目に見えない資産」は知的資本(Intellectual Capital)と呼ばれます。
知的資本は一般的に、企業内の経営プロセスやシステムなどの「内部資本」、顧客や取引先との関係などの「外部資本」、そして従業員のスキルや知識を示す「人的資本」の三つに分類されます。これらは財務諸表には現れにくいものの、企業の持続的な成長や競争優位性の源泉となります。
しかし、この知的資本をどのように測定し、開示すべきかという点については、世界中の企業や研究者が試行錯誤を続けています。企業によって開示の内容や方法は様々で、統一された基準や枠組みが十分に確立されているわけではありません。
本コラムでは、各国における知的資本開示の実態を紹介しながら、その現状と直面している課題について考えます。南アフリカ、スリランカ、イタリア、オーストラリア、アイルランドなど、異なる経済環境や文化背景を持つ国々における企業の開示事例を通じて、知的資本開示の多様性と共通点を探ります。
知的資本の開示は人的資本を中心に急増
南アフリカの企業における知的資本開示の実態を調査した研究によると、2002年から2006年にかけて知的資本に関する情報開示は大幅に増加しました。この研究では、南アフリカのトップ20企業を対象に5年間にわたる年次報告書を分析し、知的資本情報の開示状況を調べています[1]。
目を引くのは、5年間で開示量が約2倍に増加したという事実です。開示される項目の数も、各項目についての記述量も増えました。これは企業が徐々に知的資本の価値を認識し、その情報を積極的に公開するようになったことを意味します。
特徴的なのは、開示される知的資本の中で「人的資本」が最も多く、全体の約69%を占めていたことです。次いで「外部資本」が22%、「内部資本」が9%という結果でした。これは他の国々の研究結果とは異なる傾向を示しています。多くの国では、顧客関係やブランドといった外部資本の開示が中心となる傾向がありますが、南アフリカでは人材に関する情報が多かったのです。
人的資本の中でも特に「公平性」に関する開示が目立ちました。具体的には「黒人経済的エンパワーメント(Black Economic Empowerment;BEE)」に関する記述が多く見られました。これは南アフリカの歴史的背景、例えばアパルトヘイト後の社会的課題を反映したものと言えるでしょう。企業は人種間の経済格差を是正するための取り組みや方針を積極的に開示していました。
また「地域社会への関与」や「研修プログラム」に関する情報も頻繁に報告されていました。これらも人的資本の一部として分類されています。
知的資本の開示場所についても発見がありました。多くの企業は「コーポレート・ガバナンス」セクションや「取締役会報告書」の中で知的資本情報を開示していました。財務諸表の中で数値として示されることは少なく、主に定性的な記述として報告されていました。
業種別に見ると、鉱業企業は全般的に知的資本の開示が少ない傾向がありました。これは鉱業が伝統的に物理的資産を中心とする産業であることが関係しているかもしれません。
南アフリカで人的資本の開示が多い背景には、いくつかの要因が考えられます。まず、前述した人種問題やHIV/AIDSといった社会的課題があります。これらの問題に企業がどう対応しているかを示すことが、社会的責任を果たす上で重要視されていました。
規制対応という側面も見逃せません。南アフリカでは「BEE法」や「キングレポート」といった制度が企業に社会的責任を求めており、これらへの対応状況を示すために人的資本の情報が積極的に開示されていたと考えられます。
企業が開示を行う動機としては「正当性理論」の視点から解釈することができます。これは企業が社会的期待に応えることで自らの存在を正当化しようとする行動を説明する理論です。南アフリカの企業は、人種問題などの社会的課題に対する取り組みを示すことで、社会からの信頼を得ようとしていたと考えられます。
スリランカ企業は知的資本の報告で外部資本を重視
スリランカの企業における知的資本報告の実態を調査した研究では、南アフリカとは異なるパターンが見られました。この研究では、スリランカのコロンボ証券取引所に上場する時価総額上位30社を対象に、1998年から2000年の年次報告書を分析しています[2]。
全体的な傾向として、スリランカでも調査期間中に知的資本報告の量が増加したことが確認されました。企業が徐々に知的資本の重要性を認識し、情報開示に積極的になっていった様子がうかがえます。
南アフリカとの違いは、開示される知的資本のカテゴリーです。スリランカでは「外部資本」に関する情報が最も多く報告されており、次いで「人的資本」、そして最も少なかったのが「内部資本」でした。これは南アフリカの傾向(人的資本が最多)とは異なります。
外部資本の中で特に多く報告されていたのは「ブランド構築」と「企業イメージ構築」に関する情報でした。スリランカ企業がこれらの項目を重視した背景には、グローバル市場との競争環境があると考えられます。国際競争が激化する中で、企業のブランドやイメージが競争要素になっているためです。
人的資本の開示についても特徴がありました。スリランカでは「従業員関係」が人的資本の中で最も多く報告されていました。具体的には、従業員の貢献に対する感謝の表明や労働組合との関係に関する記述が目立ちました。一方で、公平性に関する報告は少なく、南アフリカで公平性(特に人種問題)に関する報告が多かったこととは対照的です。
内部資本については、プロセスやシステムに関する情報が比較的多く報告されていましたが、知的財産や財務関係について報告は少ない状況でした。
スリランカ企業の知的資本報告の特徴を理解するために、研究者たちは先行研究(オーストラリア、スウェーデン、アイルランドの事例)との比較分析も行っています。その結果、スリランカ企業は人的資本の報告において、「企業家精神」よりも「従業員の社会的価値や関係性」を重視することが判明しました。
この違いはどこから来るのでしょうか。研究者たちは文化的・社会的要因を挙げています。スリランカの文化的背景では、個人の起業家精神よりも集団の調和や関係性が重視されるのかもしれません。また、スリランカ企業が研究開発を海外から取り入れている実態も関係している可能性があります。自社で新たな技術やビジネスモデルを生み出すよりも、既存の技術やモデルを導入・適応させることに重点を置いているため、企業家精神があまり強調されていないことが考えられます。
スリランカの事例で見えてくるのは、知的資本報告が各国の経済状況や文化的背景、そして国際的な位置づけによって形作られる点です。グローバル市場と競争するスリランカ企業にとって、ブランドや企業イメージといった外部資本が競争優位性の源泉となるため、それらの情報が重視されたのでしょう。
知的資本の開示は外部構造が最も多い
イタリアの上場企業における知的資本開示に関する研究では、さらに別の傾向が見られました。この研究では、イタリア証券取引所に上場する非金融企業から30社をサンプルとして選び、2001年の年次報告書に記載された知的資本情報を分析しています[3]。
イタリア企業は平均して51項目の知的資本情報を開示していました。そのうち、「外部構造」に関する情報が最も多く、全体の49%を占めていました。次いで「内部構造」が30%、「人的資本」が21%となっていました。これはスリランカの傾向(外部資本が最多)と似ていますが、南アフリカ(人的資本が最多)とは異なります。
外部構造の中で特に多かったのは「顧客」に関する情報で、次いで「流通チャネル」、そして「業務提携」が続きました。顧客との関係性やビジネスパートナーとの協力関係が重視されていることがわかります。
人的資本に関しては、従業員の基本情報(平均年齢や離職率など)が最も多く報告されていました。しかし、この割合は全体から見ると比較的少なく、イタリア企業は人的資本よりも外部関係を重視することが示唆されます。
知的資本開示に影響を与える要因について分析も行われています。研究者たちは「業種」と「企業規模」という2つの要因を検証しました。
「業種」については、ハイプロファイル企業(高度な技術を要する業界の企業)とロープロファイル企業(伝統的産業の企業)で比較しました。結果、ハイプロファイル企業はロープロファイル企業よりも有意に多くの知的資本情報を開示していることがわかりました。特に外部資本に関する情報が多い傾向がありました。技術志向の企業が無形資産の重要性をより強く認識していることを示しています。
「企業規模」については、企業規模(売上高、総資産、時価総額などで測定)が大きいほど知的資本情報の開示量が多いという関係が確認されました。大企業はより多くのリソースを持ち、情報開示に投資できることや、より多くのステークホルダーからの期待に応える必要があることがその理由として考えられます。
業種と企業規模は、知的資本開示量を説明する主な要因でした。企業がどの業種に属しているか、そしてどれだけの規模があるかによって、知的資本開示の量がかなりの程度予測できるということです。
研究者たちはオーストラリア企業の知的資本開示との比較も行っています。その結果、イタリア企業はオーストラリア企業よりも平均して多くの知的資本情報を開示していることがわかりました。この違いの理由として、イタリアでは政府主導の知的資本推進政策が影響している可能性が示唆されました。
知的資本の開示は体系化されず定性的
オーストラリアの企業における知的資本開示の実態を調査した研究では、開示が体系化されていない状況が明らかになりました。この研究ではオーストラリアの時価総額上位19社および知的資本開示の優良事例として知られる1社の合計20社をサンプルとして、年次報告書における知的資本情報の開示状況を分析しています[4]。
知的資本に関する情報開示は企業間で大きな差があり、統一された方法で体系的に報告されていない実態が明らかになりました。サンプル企業は平均して約9項目の知的資本情報を開示していましたが、その数は企業によって異なり、最も多い企業では17項目、最も少ない企業では2項目の開示に留まっていました。
最も体系的な開示を行っているとされた企業でも、知的資本を完全に体系的に示すフレームワークを確立しているとは言い難い状況でした。これは知的資本開示の枠組みがまだ発展途上であることを示しています。
開示される知的資本の項目にも特徴的なパターンがありました。「人的資本」では、「起業家精神」が最も頻繁に報告され、調査企業20社中19社が何らかの形でこれに言及していました。また「職務関連の知識」も多くの企業で報告されていました。
「外部構造」では、「顧客」との関係に関する情報が16社で記載され、最も多く報告されていました。また「ビジネス協力関係」も多くの企業で取り上げられていました。
「内部構造」については、「経営プロセス」が15社で記載され、「経営哲学」は12社が報告していました。
一方、ほとんど記載がなかった項目としては、「知的財産」「財務関係」「フランチャイズ契約」「職業資格」などが挙げられます。これらは企業が重要視していないか、あるいは開示することのメリットを感じていない項目と考えられます。
特筆すべきは、知的資本に関する情報がほぼすべて定性的であり、数値を用いた定量的な表現が限られていた点です。定量的に報告されていた例外的な事例としては、ある企業が新たに導入または再設計した経営プロセスの数を報告した例が挙げられます。
カテゴリー別の開示量を見ると、外部資本が最も多く(全体の40%)、次いで内部資本と人的資本がそれぞれ30%となっていました。これは南アフリカ(人的資本が最多)とは異なる傾向ですが、スリランカやイタリア(外部資本が最多)に近いパターンです。外部資本が多く報告されているのは、競争の激化により顧客関係の重要性が高まっていることを反映しているのでしょう。
この研究から導き出された主な結論として、オーストラリア企業における知的資本開示は体系化されておらず、一貫した開示フレームワークが未整備であるという点が挙げられます。また、知的資本に関する情報は定性的表現が主体であり、定量的評価はまだ発展途上であることも明らかになりました。
企業は知的資本の重要性を認識しているものの、これを外部に効果的に伝える方法を確立できていない状況が浮き彫りになっています。このことは、知的資本開示のための標準化された枠組みや指針が必要であることを示唆しています。
知的資本の開示は不十分で定性的な情報が中心
アイルランドの上場企業における知的資本開示に関する研究では、企業価値に占める知的資本の割合が高いにもかかわらず、その開示が限定的であることが明らかになりました。この研究では、アイルランド証券取引所に上場する97社の中から知識集約型企業(技術志向・人材志向の企業)11社を対象に、知的資本の開示状況を調査しています[5]。
対象企業のほとんど(11社中9社)において市場価値が簿価価値を大幅に上回っていました。この隠れた価値(hidden value)は市場価値の57%から93%にも及び、知的資本が企業価値に占める割合が高いことを示しています。言い換えれば、これらの企業の価値の大部分は財務諸表に表れない無形資産(知的資本)から来ているということです。
しかし、このように重要な知的資本に関する情報開示の実態は限定的でした。開示されていたとしても、多くの場合は定性的で簡単な記述にとどまっており、具体的な数値や定量的な評価はほとんど見られませんでした。
開示されていた知的資本情報のカテゴリーを見ると、「外部構造(顧客・取引先との関係)」が最も頻繁に開示されていました。「人的資本(従業員のスキルや教育)」や「内部資本(経営哲学・情報システム)」に関する開示は限定的でした。特に人的資本に関する開示は少なく、例えば「起業家精神」などの項目はほとんど報告されていませんでした。
具体的な開示事例としては、例えば特定のプロジェクトに専門チームを割り当てる経営モデルについて報告していた例(内部資本に関する開示)や、重要な取引相手との長期的パートナーシップを強調していた例(外部資本に関する開示)が挙げられています。人的資本に関しては、従業員トレーニングとマネジメントの質を企業の成功要因として報告していた例があります。
脚注
[1] Wagiciengo, M. M., and Belal, A. R. (2012). Intellectual capital disclosures by South African companies: A longitudinal investigation. Advances in Accounting, 28(1), 111-119.
[2] Abeysekera, I., and Guthrie, J. (2005). An empirical investigation of annual reporting trends of intellectual capital in Sri Lanka. Critical Perspectives on Accounting, 16(3), 151-163.
[3] Bozzolan, S., Favotto, F., and Ricceri, F. (2003). Italian annual intellectual capital disclosure: An empirical analysis. Journal of Intellectual Capital, 4(4), 543-558.
[4] Guthrie, J., and Petty, R. (2000). Intellectual capital: Australian annual reporting practices. Journal of Intellectual Capital, 1(3), 241-251.
[5] Brennan, N. (2001). Reporting intellectual capital in annual reports: Evidence from Ireland. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 14(4), 423-436.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。