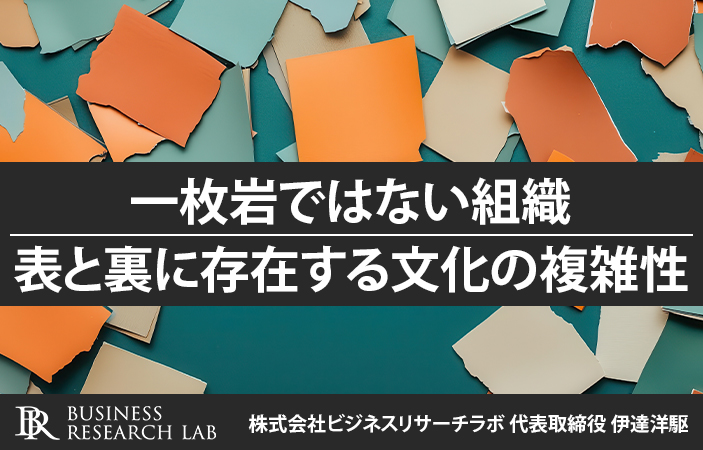2025年8月25日
一枚岩ではない組織:表と裏に存在する文化の複雑性
職場に一歩足を踏み入れたとき、そこには目に見えないけれども確かに存在する「雰囲気」を感じ取ることがあります。ある企業では活気あふれる会話が飛び交い、別の企業では静かで整然とした環境が広がっています。このような違いは、長い年月をかけて形成された「組織文化」の一つの表れです。組織文化とは、組織の中で共有される価値観、信念、行動様式などの総体であり、いわば組織の「個性」や「性格」に相当するものです。
組織文化は、職場の雰囲気以上の意味を持ちます。企業の意思決定、社員のモチベーション、イノベーションの創出、さらには組織の存続そのものにまで関わります。経営学の分野では、組織文化への関心が高まり、多くの研究が行われてきました。
本コラムでは、「組織文化はどのように形成されるのか」「組織文化はどのような複雑性を持っているのか」という問いを中心に探求していきます。一見シンプルに見える組織文化ですが、その実態に迫ると複雑で多層的な様相が見えてきます。具体的には、日常の実践による文化形成、創業者の価値観の継承プロセス、表面的な公式文化と多様な下位文化の関係、そして組織物語の共通性と独自性のパラドックスという4つの側面から考察します。
文化は価値観より日常の実践によって形成される
組織文化を語るとき、「我が社の理念」といった言葉を思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。確かに理念は、組織文化の構成要素になり得ます。しかし、実際の組織文化はそれだけで形成されるわけではありません。20の異なる組織ユニットを対象にした大規模な調査による研究を見てみましょう[1]。
この研究では、組織文化を「玉ねぎモデル」として概念化しました。組織文化は外側から内側に向かって「シンボル」「英雄」「儀式」「価値観」という層から構成されています。
- シンボルとは、組織内で特別な意味を持つ言葉や物、行動のことです。例えば、企業特有の専門用語や、オフィスのレイアウト、服装のコードなどが該当します。
- 英雄とは、組織内で尊敬され、模範とされる人物です。創業者や歴代のカリスマ的リーダーがこれに当たることが多いでしょう。
- 儀式とは、朝礼や定例会議、社内イベントなど、組織内で繰り返される形式的な活動を指します。
- そして最も内側にあるのが価値観、すなわち善悪や正誤についての基本的な感覚です。
この研究はオランダとデンマークの10の組織における20のユニットを対象に行われ、質的調査と量的調査を組み合わせた包括的なものです。各ユニットから9名ずつの代表者に対してインタビューを行い、組織文化に関する基本情報を収集しました。その上で、各ユニットからおよそ65名ずつ、合計1,295名に対してアンケート調査を実施し、組織文化を測定する135の質問項目に回答してもらいました。これらの質問は、仕事の目標や信念に関する「価値観」の項目と、日常の業務における「実践」に関する項目から構成されていました。
データを分析した結果、組織文化には6つの次元が存在することが判明しました。これらの次元は、次のような対照的な特性として現れます。
- 1つ目は「プロセス志向か結果志向か」という次元です。プロセス志向の組織では、「どのように仕事をするか」が重視され、結果志向の組織では「何を達成するか」が重視されます。
- 2つ目は「従業員志向か職務志向か」という次元です。従業員志向の組織では従業員の福祉や感情に配慮する一方、職務志向の組織では仕事の完遂が最優先されます。
- 3つ目は「ムラ的かプロフェッショナルか」という次元です。ムラ的な組織では従業員のアイデンティティが組織に依存し、プロフェッショナルな組織では職業的な専門性がアイデンティティの基盤となります。
- 4つ目は「開放的か閉鎖的か」という次元です。これは組織内外のコミュニケーションの開放度を表します。開放的な組織では情報共有が活発で、新メンバーの受け入れもスムーズです。一方、閉鎖的な組織では情報は限られた人にしか共有されず、新メンバーが内部に溶け込むまでに時間がかかります。
- 5つ目は「緩い管理か厳格な管理か」という次元です。緩い管理の組織ではルールや規則が少なく柔軟性がある一方、厳格な管理の組織では詳細なルールと厳しい時間管理があります。
- 6つ目は「規範的か実用主義的か」という次元です。規範的な組織では定められた手順や原則を守ることが重視され、実用主義的な組織では結果や顧客満足を重視します。
また、組織文化を形成するのは一般に考えられている「価値観」よりも、「日常の実践」の方が影響力を持つということがわかりました。価値観は主に人が幼少期から青年期にかけて家庭や学校で身につけるものであり、成人して組織に入ってからは大きく変わりにくいものです。一方、実践とは組織での日々の活動や行動パターンのことであり、これは組織に入ってから学習されます。
創業者の価値観が歴史的過程で共有される
組織文化が日常の実践によって形成されることを見てきましたが、では誰がその実践を最初に作り出すのでしょうか。その答えの一つは「創業者」です。組織文化の形成における創業者の役割に焦点を当てた研究が行われています[2]。組織を現在の姿としてではなく、過去から未来へと連続する時間的なプロセスとして捉え、特に創業期における文化形成の仕組みを解明しようとした研究です。
この研究では、組織文化を研究するには「長期間にわたるプロセス分析」が必要だと主張しました。組織の歴史的な経緯や時間的な変化を詳細に追跡することで、文化がどのように形成され、維持され、変化するかを理解しようとするものです。そして、ある学校を対象に、1934年の創立から1975年までの約40年間にわたる歴史を調査しました。特に「ソーシャル・ドラマ」と呼ばれる、組織内の重要な出来事(リーダーの交代、組織構造の変化、危機的状況など)に着目し、それらの出来事を通じて組織文化がどのように形作られてきたかを分析しました。
研究によれば、組織文化は次のような要素から構成されます。
- まず「シンボル」があります。これは物理的な対象物、行動、言語など、多義的な意味を含み、感情を喚起し行動を促す象徴的な要素です。例えば会社のロゴ、オフィスデザイン、制服などが該当します。
- 次に「言語」です。組織内の経験を体系化し、意味を安定化させる働きを持ちます。特に新しい組織が自己認識や共有理解を形成する際に重要な役割を果たします。組織特有の専門用語や表現が、メンバー間の共通理解を促進します。
- 「イデオロギー」は、組織の社会的位置づけに関する正当性を示し、行動を動機づける信念の体系です。組織が「なぜ存在するのか」「社会にどのような価値を提供するのか」という問いに対する答えを与えます。
- 「信念」は、行動を方向づける基本的な前提や価値観です。「良いサービスとは何か」「どのような行動が評価されるべきか」といった判断の基準となります。
- 「儀式」は、象徴的な身体の動きやジェスチャーを用いて意味を表現し、社会関係を定型化し規定する行為です。例えば入社式、定例会議、表彰式などが該当します。これらの儀式は組織の価値観を視覚的、体験的に伝える機能を持ちます。
- 最後に「神話」です。これは組織の歴史や特定の出来事に関する物語を提供し、現在の正当性を過去に結びつける機能を持ちます。創業エピソードや危機を乗り越えた物語などが典型的な例です。
創業者(起業家)がこれらの文化的要素を形成する過程の分析が行われています。創業者は組織の構造や技術的側面を作り出すだけでなく、組織内で共有される価値観、言語、神話などの象徴的な要素を形作ります。創業者のビジョンや信念は、初期の組織文化の核となり、その後の発展に影響を与えます。
例えば、ある企業の創業者が「顧客の問題解決を最優先する」という強い信念を持っていた場合、その信念は初期のメンバーに共有され、日々の業務の中で実践されます。やがてそれは「うちの会社では顧客のためなら何でもする」という形で言語化され、「創業者がある顧客のために徹夜で問題解決に取り組んだ」といった神話として語り継がれることになります。そして、顧客からの感謝状を掲示する、顧客満足度の高いスタッフを表彰するといった儀式が生まれ、それがさらに文化を強化していきます。
創業者の価値観はどのようにして組織メンバーに浸透し、共有されるのでしょうか。この研究ではこれを「コミットメントのメカニズム」として説明しています。
- 初めに「ビジョンの共有」があります。創業者の明確かつ魅力的なビジョンが組織内で共有されることで、メンバーの意識や行動が方向づけられます。
- 次に「言語の役割」です。組織特有の言語や用語が形成されることで、メンバー間の一体感が醸成されます。専門用語や略語、内輪の表現などは、それを理解し使用することで組織への所属感を高める効果があります。
- 「犠牲と投資」も重要です。メンバーが他の選択肢を断念し、組織に時間や資源を投資することで、組織との結びつきが強化されます。
- 最後に「境界の管理と排他性」があります。組織が外部との接触を一定程度制限し、内部の団結を強めることで、コミュニティ感覚が高まります。「私たちは特別だ」という意識は、組織アイデンティティを強化する効果があります。
このように創業者の価値観は、ビジョンの共有、組織特有の言語の発展、メンバーの投資と犠牲、そして境界管理といったメカニズムを通じて組織全体に浸透し、時間の経過とともに組織文化として根付いていきます。
公式文化の裏には多様な下位文化が存在する
組織文化が日常の実践によって形成され、創業者の価値観が歴史的過程で共有されることを見てきました。しかし、組織文化はそれほど単純で一枚岩的なものなのでしょうか。「公式文化の裏には多様な下位文化が存在する」という重要な観点を提示した研究を見てみましょう[3]。
具体的には、「ソフトな官僚制」と呼ばれる組織形態に着目しています。これは伝統的な官僚制の枠組みを保持しながらも、一定の柔軟性を持つ組織のことです。この種の組織では表面的な「公式文化(Official Culture)」と、実際に存在する多様な「下位文化(Subcultures)」の間にズレが生じていることを発見しました。
研究対象となったのは、「パシフィック州警察(PSP)」という仮名で呼ばれる警察組織でした。この組織では、上層部が推進する模範的な警察官像、倫理規定、勤務態度などからなる明確な公式文化が存在していました。しかし、現場レベルではこの公式文化が現実から乖離した「神話的」存在と見なされ、表面的なものに留まっていました。
研究者たちは質的手法を採用し、警察官や管理者へのインタビュー、参与観察、文書分析などを通じてデータを収集しました。そのデータを分析した結果、PSP内には少なくとも3つの異なる下位文化が存在していることが明らかになりました。
1つ目は「指揮官文化(Command Culture)」です。これは上層部の規範を忠実に遵守し、公式文化の維持を最優先とする文化です。この文化を持つ人々は、組織の権威や階層構造を強調し、公式的なルールや手続きを重視します。良い警察官とは規則に従い、組織の方針を忠実に実行する人です。この文化は主に上層部や管理職に見られ、彼らは公式文化を組織全体に浸透させようと努力します。
2つ目は「伝統主義文化(Traditional Culture)」です。これは現場の警察官によって支持される文化で、実践的で伝統的な警察活動を重視します。彼らは公式文化の非現実的側面を否定的に捉え、「現場の経験」や「実際に効果がある方法」を優先します。例えば、公式には「コミュニティとの協働」が強調されていても、現実には「犯罪者の取り締まり」や「秩序維持」といった伝統的な警察の役割を重視するのです。この文化は公式文化への消極的抵抗を示し、表面上は従いながらも、実際の行動では異なる価値観に基づいて行動します。
3つ目は「対抗文化(Counter Culture)」です。これは最も公式文化に反する立場を取り、公式文化を公然と批判・拒否する文化です。この文化を持つ人々は、非公式的な規範や行動基準を積極的に推進し、対抗行動を示します。例えば、上層部が推進する書類作業や報告義務を意図的に怠ったり、公式の指示に反する独自の行動方針を持ったりします。公式文化を「現実離れした理想論」として嘲笑し、「本当の警察の仕事」は別にあると考えています。
これらの下位文化の違いは、警察署内での世代間・階層間・部署間の緊張関係を生み出していました。例えば、若手警察官が訓練で学んだ公式的な方法を実践しようとすると、「伝統主義文化」を持つベテラン警察官から「それは理論だけで、現場では通用しない」と教えられることがあります。また、上層部の指示が現場レベルで変質したり無視されたりすることで、政策の意図した効果が得られないこともあります。
なぜこのような下位文化が生まれるのでしょうか。次のような理由が挙げられます。
組織内の異なる職位や部署には、異なる業務内容、責任、権限があり、それに伴って異なる価値観や行動様式が発達します。また、外部環境の変化に伴い、組織文化も変化することがありますが、その変化は均一ではありません。新しい価値観や行動様式が一部の部署や個人に先に取り入れられ、他の部分では古い文化が残存することで、文化の多様性が生まれます。個人のバックグラウンドや経験も下位文化の形成に寄与します。異なる教育歴、職業経験、社会的背景を持つ人々が組織に加わることで、多様な視点や価値観が持ち込まれます。
組織は文化の独自性を語るが物語は共通している
うちの会社の文化は他社とは違う。多くの組織の経営者や従業員はこのように語るかもしれません。確かに各組織には固有の歴史があり、独自の価値観や行動様式があります。しかし、組織文化に関する興味深いパラドックスを明らかにした研究があります[4]。それは「組織は文化の独自性を語るが、実際に組織内で共有される物語には共通性がある」というものです。これは「ユニークネスのパラドックス(uniqueness paradox)」と名付けられています。
この研究においては、組織文化の研究において「物語(stories)」が分析対象であることに着目しました。物語とは、組織内で語られるエピソードや出来事の説明のことで、これらは組織の価値観や規範を伝える媒体となります。例えば「創業者がどのように会社を始めたか」「危機的状況をどう乗り越えたか」「どのような行動が評価されるか」などの物語は、組織の歴史、価値観、規範を伝えます。
研究者たちは様々な組織の物語を収集・分析した結果、組織が自らの文化をユニークだと主張する一方で、実際に語られる物語には類似したパターンがあることを発見しました。研究で特定された典型的な組織物語のパターンには次のようなものがあります。
1つ目は「ルールを破る英雄の物語」です。この物語では、組織内の規則や慣習を破ることで成功した人物が英雄として描かれます。例えば「CEOが突然工場の現場に現れて、作業員と一緒に働いた」「管理職が顧客のために通常の手続きを飛ばして特別対応をした」などの話です。こうした物語は、組織が柔軟性を持ち、時には規則よりも結果や人間関係を重視することを示します。
2つ目は「低位者がトップに上り詰める物語」です。組織内で低い地位から出発し、能力や努力によって高い地位に昇進した人物の物語です。「配達員から始めて社長になった」「掃除スタッフから始めて店長になった」などの話がこれに当たります。この種の物語は、組織が公平で機会均等であることを象徴し、努力が報われる場所であるというメッセージを伝えます。
3つ目は「解雇や雇用リスクに関する物語」です。組織が厳しい経済状況や危機的状況に直面した際に、どのように社員が解雇を免れたか、または逆に解雇されたかを伝える物語です。例えば「不況時でも社員を解雇せず、経営陣が給与カットで乗り切った」「業績不振の責任を取って幹部全員が辞任した」などの話です。これらの物語は、組織の危機対応や社員に対する姿勢を示します。
4つ目は「転勤や移動を伴う物語」です。転勤や配置転換が個人や家族にとって困難や犠牲を伴うものであることを示しつつ、組織がその苦難を乗り越えるために社員を支援した事例が語られます。「海外転勤を命じられた社員の家族のために特別な支援プログラムを用意した」「急な転勤で困った社員に対して柔軟な勤務体制を認めた」などの話です。これらの物語は、組織が社員の個人的事情に配慮し、支援する姿勢を持っていることを伝えます。
5つ目は「上司が部下の失敗にどう対応するかの物語」です。部下の失敗に対して上司がどのように反応するかを示し、組織のリーダーシップのあり方を伝える物語です。「新人が大きなミスをしたとき、上司は責めるのではなく一緒に解決策を考えた」「失敗した社員に対して学びの機会を与え、成長を促した」などの話が該当します。これらの物語は、組織がどのように失敗や間違いを扱うかという姿勢を示します。
6つ目は「組織が障害を乗り越える物語」です。組織が内部または外部の困難を乗り越えた事例が物語として語られ、組織の柔軟性や回復力を示します。「大きな災害で工場が被災したが、社員全員の努力で驚くほど早く復旧した」「強力な競合の参入で危機に陥ったが、イノベーションで乗り越えた」などの話です。これらの物語は、組織の強さや結束力、問題解決能力を強調します。
これらの物語タイプは、肯定的バージョン(組織の成功を称える)と否定的バージョン(組織の失敗を伝える)の両方が存在します。例えば「障害克服」の物語でも、組織が困難を成功裏に乗り越えた事例と、失敗した事例が対照的に語られることがあります。
なぜ多くの組織で、これほど共通する物語のパターンが見られるのでしょうか。これらの物語は組織が普遍的に直面する「基本的ジレンマ」を反映しています。例えば、平等と不平等、安全と不安定、統制と統制の欠如といった対立は、様々な組織が抱える基本的な緊張関係です。物語はこうした緊張関係をドラマチックな形で表現し、組織がそれにどう対処するかを見せます。
組織は自らの過去を「自己奉仕的」に合理化する傾向があります。成功は組織自身の努力によるものとし、失敗は外的要因に帰属させるのです。この傾向は多くの組織に共通しており、それが物語のパターンの類似性を生み出します。また、物語は社員が自らを組織と同一視したり、距離を取ったりするための手段となります。肯定的な物語は組織への一体感を強め、否定的な物語は距離感を生み出します。この機能もまた、多くの組織に共通するものです。
「ユニークネスのパラドックス」は、組織が自身のユニークさを強調しつつも、実際には共通した物語パターンを採用している点にあります。このパラドックスは、組織が自身の望ましい特性を強調しようとする際に、一般的な理解や共感を得るために広く共有されたパターンを採用することによって生じます。完全に独自であることを目指すよりも、既存の認識枠組みや価値観を共有する方が、組織の価値観やメッセージを伝えやすいのです。
脚注
[1] Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D. D., and Sanders, G. (1990). Measuring organizational cultures: A qualitative and quantitative study across twenty cases. Administrative Science Quarterly, 35(2), 286-316.
[2] Pettigrew, A. M. (1979). On studying organizational cultures. Administrative Science Quarterly, 24(4), 570-581.
[3] Jermier, J. M., Slocum, J. W., Fry, L. W., and Gaines, J. (1991). Organizational subcultures in a soft bureaucracy: Resistance behind the myth and facade of an official culture. Organization Science, 2(2), 170-194.
[4] Martin, J., Feldman, M. S., Hatch, M. J., and Sitkin, S. B. (1983). The uniqueness paradox in organizational stories. Administrative Science Quarterly, 28(3), 438-453.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。