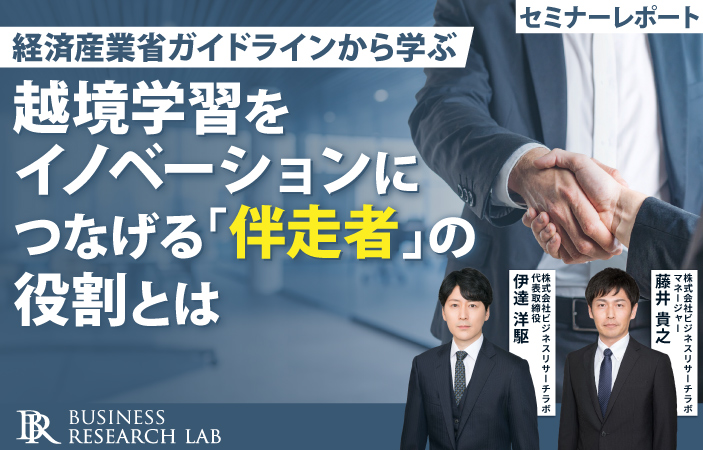2025年8月22日
越境学習をイノベーションにつなげる「伴走者」の役割とは:経済産業省ガイドラインから学ぶ(セミナーレポート)
株式会社ビジネスリサーチラボは、2025年7月にセミナー「越境学習をイノベーションにつなげる「伴走者」の役割とは:経済産業省ガイドラインから学ぶ」を開催しました。
近年、企業において注目されている「越境学習」。自社の枠を超えてスタートアップや異業界などで活動し、新たな視点を得る取り組みです。
この越境学習を組織変革やイノベーション創出につなげるための指針として、経済産業省は2025年3月に「越境学習を支える伴走者のための実践ガイドライン」を策定しました。この度、ビジネスリサーチラボでは、本ガイドライン策定に携わった当社代表取締役 伊達洋駆とマネージャー 藤井貴之が講師となり、越境学習の実践ノウハウを掘り下げるセミナーを開催しました。
セミナーでは、越境前・越境中・越境後の各段階で起こりやすい課題と、それを支える「伴走者」の役割に焦点を当てました。越境学習者が組織間の壁を超えて成長し、その学びを組織全体のイノベーションにつなげるためには、適切な支援が不可欠です。しかし、支援しすぎると主体性が損なわれ、放置すると孤立するという難しいバランスをどう取るべきか。具体的な事例を交えながら解説しました。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
越境学習ガイドラインの意義と活用
藤井:
近年、越境学習(組織の枠を越えて他組織で学ぶ経験)に注目が集まり、持続的なイノベーションを生み出すには、人材や技術などの「イノベーション資源」を社外に開き、組み合わせる機会を増やすことが重要だと考えられています。特に人材の流動化策として、社外での学びである越境学習を企業に普及させる取り組みが進められています。
こうした流れの中で、「越境学習を効果的に実践するにはどうすればいいか」「どんな支援体制を整えればいいか」という声が企業から上がってきました。ただ社員を他社や他分野に送り出すだけでは、期待した成長やイノベーションにつながらない場合もあります。そこで重要になるのが、越境学習を支える「伴走者」と呼ばれる存在――送り出す企業側の上司や人事担当者、受け入れ先のメンターやコーディネーターなど――の支援です。
経済産業省から発行されている「越境学習を支える伴走者のための実践ガイドライン[1]」(以降、「ガイドライン」と記載)は、越境学習の成功を支える伴走者の役割やスキルを体系立てて整理し、誰もが活用できる指針を示しています。ビジネスリサーチラボも作成に携わり、私は実際に越境学習を支援した経験を持つ「伴走者」の方々にインタビューでお話をうかがう機会もいただきました。そうした中で得られた知見も踏まえつつ、ガイドラインの作成の背景やプロセス、そこから得られた実践的な観点や示唆についてもご紹介していきます。
越境学習について
まず、越境学習にはどんな価値があるのでしょうか。一言で言えば、越境学習は個人と組織の両方に革新をもたらす学びの形です。個人にとっては、普段の環境から飛び出し「アウェイ」の世界に飛び込むことで、新たな視点やスキルを獲得できる貴重な機会になります。
異業種・異文化の現場で働く中で、自分の当たり前が通用しない経験をし、視野がぐっと広がります。また、自分は何を大切にしているのか、何にワクワクするのかといった内省も深まります。日常業務から離れるからこそ、自分のキャリアや価値観を見つめ直すきっかけになるわけです。一方、送り出す組織にとっての価値も見逃せません。越境学習で得た知見やネットワークを社員が持ち帰ることで、新規事業のヒントが生まれたり、組織文化に新風を吹き込んだりする可能性があります。
実際、経済産業省が行った調査のなかで「越境学習は単なる人材育成にとどまらず、事業面・組織文化面でもイノベーションを生み出す」ことが示されています[2]。現場の常識に染まりきった組織に、社外の風穴を開ける効果があるわけです。また、社員自身が越境学習を通じてキャリア自律のマインドを高めることで、組織全体の活性化にもつながります。越境学習は、個人の成長と組織の変革を同時に促すポテンシャルを持っているのです。
さらに、越境学習の大きな特徴は「往還型の学習」である点です。異動や転職のように一方向で終わりではなく、「ホーム(自社)からアウェイ(受け入れ先)に行き、そしてまたホームに戻ってくる」という往復のプロセスです。つまり、行って学びを得ることはもちろんですが、戻ってきてから何を生み出すかということも越境学習の価値を決める鍵なのです。新しい環境で学ぶだけでなく、「そこで得た学びを自社でどう活かすか」まで含めて越境学習が完結すると言えます。
この点を踏まえると、組織として越境学習の成果を受け止める仕組みがいかに重要かがお分かりいただけるでしょう。
越境学習のガイドライン作成プロセス
ガイドライン作成にあたり、調査の設計段階では現場の声を徹底的に拾い上げることを重視しました。具体的には、実際に越境学習を支援した経験を持つ多くの伴走者の方々へのインタビューを中心に据えました。これは、机上の理論だけでなく現場ならではの課題や工夫をリアルに捉えるためです。送り出し企業の人事担当者・上司、受け入れ先で直接指導するメンター、さらに両組織に属さない第三者の支援者や事務局担当者――こうした多様な立場の伴走者にお話を伺い、越境前・越境中・越境後の各段階で何が起こりやすいのか、どんなサポートが効果的だったのかなど、実践的な知見を幅広く収集しました。
ここではまず、ガイドライン作成の具体的なステップをご説明します。大きく3つの段階を踏んで進められました。
構成案の作成:
初めに、事前の調査や有識者の意見をもとに、インタビューの骨子となる質問構成案を作りました。そこでは、越境学習の流れを「越境前」「越境中」「越境後」のフェーズに分け、それぞれの段階で生じる課題を広く伺えるようにインタビューの質問を構成しました。
伴走者へのヒアリング:
次に、先ほど触れたように、様々な企業・立場の伴走者の方々にインタビューを実施しました。ヒアリングでは構成案に沿って質問を投げかけ、実際のエピソードや意見を伺っています。「越境前の準備で苦労したことは」「越境中に支援者としてどんな工夫をしたか」といった問いかけに対し、具体的な事例や困難に感じたことなどをお話いただきました。
知見の整理とガイドライン化:
最後に、集めた知見を体系立てて整理し、ガイドラインという形に落とし込みました。インタビューで得られた多彩なエピソードやそこで得られた示唆を、先ほどのフェーズ区分(越境前・中・後)に沿って整理統合し、伴走者の具体的な役割と必要なスキルとして紹介しています。ただ事例を羅列するのではなく、誰もが理解しやすいようにポイントをまとめ、実践しやすい形にガイドラインとして構成しました。そして、最終的な内容については、プロジェクトメンバー内でのレビューや有識者からのフィードバックもいただいて完成させています。
越境学習の課題と伴走者の役割
素晴らしい効果が期待できる越境学習ですが、実際に運用する際にはいくつかの課題もあります。ガイドラインでは、越境「前」「中」「後」の各段階で起こりがちな課題を整理しています。ここでは代表的なものをいくつか共有しましょう。
まず越境前の課題です。社員を送り出す段階で、「何のために越境するのか」が不明確なままだと、その後の学びもぼやけてしまいます。本人の目的意識が希薄なままでは、せっかく外に出ても受け身になりがちです。
そこで重要になるのが目的と期待値の明確化です。ガイドラインでも、越境開始前に伴走者が関わって「なぜ越境するのか」「越境先で何を得たいのか」を内省させ、言語化するプロセスを設けることを推奨しています。このひと手間により、学習者は主体的な目標を持って越境に臨めるようになります。
次に越境中の課題です。全く新しい環境に飛び込むわけですから、学習者は戸惑いや孤立感を味わうことがあります。受け入れ先で期待した役割が与えられなかったり、文化の違いにストレスを感じたりと、「ホームとアウェイのギャップ」に直面するのです。ここで適切な支援がないと、せっかくの挑戦が挫折の体験になりかねません。また、忙しさに追われてしまい内省の時間が取れず、「学び」が言語化・蓄積されないという問題も起こりえます。
この段階で重要なのは、孤立の防止と内省の支援です。具体的には、定期的に話を聞いてくれる存在や、週報を書く仕組みなどがあると、学習者は自分の経験を振り返りながら進むことができます。ガイドラインでも、越境中は週次のレポート提出や月次の1on1面談を通じて学習者の状況を把握し、必要に応じて課題の対処やメンタルサポートを行うことが推奨されています。こうしたサポートがあれば、学習者は困難に直面しても乗り越えやすくなり、学びを深めていけるでしょう。
そして越境後の課題です。実は「戻ってきてから」が越境学習のハイライトと言えます。ここでありがちなのが、せっかく得た知見やアイデアを組織に持ち帰ってもうまく活かせないというケースです。帰任直後に本人が意気込んで提案しても、受け入れる側の上司や同僚がピンと来ずにスルーしてしまったり、元の業務に忙殺されてアイデアを温める時間が取れなかったりします。これでは越境学習の効果が組織に還元されません。
ガイドラインでは、この課題に対応するために計画的なフォローアップを提唱しています。例えば、復帰後は人事や上司と面談し、新しい知見を活かせるポジションやプロジェクトを検討すること、復帰後3ヶ月程度は月1回の伴走者との面談を続けて「学びの活用」を後押しすることなどです。報告会も復帰直後ではなく、実務に多少取り組んだ数ヶ月後に改めて開催することで、学びが形になるまで見守る工夫も有効です。要は、「学びっぱなし」にしない体制作りが大切なのです。
では、そこで伴走者はどのような役割で越境学習者を支えることができるでしょうか。大きな役割としてガイドラインでは以下の内容をあげています。
- 目的の明確化とミスマッチの予防
- 越境学習者の不安を軽減する
- 越境先との連携・調整を助ける
- 所属組織内の関係者との連携を支援する
伴走者の役割を一言で表すと、学習者が越境先で最大限学び、そしてその学びを組織に繋げるための「橋渡し役」と言えそうです。
以上のように、伴走者には多面的な役割が求められます。このような伴走者に必要なスキルとは何でしょうか。ガイドラインでは伴走者のスキルセットを整理して提示していますが、その中でも印象的なポイントをお伝えします。
異なる世界を知る経験:
「複数の現場を知る経験」は伴走者にとって大きな武器です。大企業とスタートアップ、異業種など、異なる文化で働いた経験がある人は、越境学習者と受け入れ先企業の双方の気持ちを理解することができます。逆に自社一筋で来た人だと、アウェイ環境での戸惑いを想像しづらいかもしれません。多様な現場を知っていることは、伴走者として共感力を発揮し適切にアドバイスする土台になります。
他者の成長を支援したいという意欲:
伴走者には人の成長を心から喜び、サポートしたい気持ちが欠かせません。傾聴やコーチングのスキルは訓練で高められますが、「この人の力になりたい」「一緒に成長を喜びたい」というマインドは何より重要です。伴走者自身が思いやりや利他的な考えを持っていることは、支援が効果的に行われることにおいて望ましい適性の一つと言えそうです。
柔軟性(橋渡し力):
越境学習では、場合によっては学習者個人の「やりたいこと」と企業側の「求めること」をすり合わせる必要が生じます。伴走者にはこの両者を上手に橋渡しする柔軟性が求められます。状況に応じて現実的な調整を図ったり、逆に学習者の意思を汲んで組織の考えを動かしたり、といったバランス感覚も必要です。ガイドラインでも、硬直的ではなく双方向に働きかけられるしなやかさが重要だと指摘されています。
対話力・観察力:
学習者の話を深く聴く力、気づきを促す質問力、さらには言葉にならないサインを読み取る洞察力も重要です。特にメンタリング場面では「行間を読む力」が求められるといいます。学習者が出す週報の文面や表情の変化から、モチベーションの浮き沈みや隠れた葛藤を察知するような繊細さです。これは現場経験もさることながら、日頃から相手に関心を持って注意深く見る姿勢で磨かれるスキルでしょう。
このように多面的なスキルが挙がりました。お聞きになって「こんな人材がどこにいるんだ…」と思われたかもしれません。その通りで、すべてを完璧に備えた伴走者をすぐに見つけるのは難しいというのも現実です。
だからこそガイドラインでは、社内外で候補者を確保しつつ伴走者を育成する仕組みの重要性も提言しています。例えば社内の若手マネージャー層に対してコーチング研修を行い、将来の伴走者候補を育てるとか、外部メンターの知見を社内に共有してもらう仕掛けを作る、といったことが考えられます。
越境学習を全員で支える文化へ
最後に、越境学習の取り組みを「制度」や「個人の努力」にとどめず、組織全体で支える文化へと昇華させていくための視点をお伝えしたいと思います。
越境学習とは、言い換えれば「組織の常識を一度手放し、新しい視点を受け入れること」です。これは、学習者にとってだけでなく、受け入れる側の組織文化にも変化を求めるプロセスです。したがって、「越境学習は人事の施策だ」「メンターが頑張ればいい」と切り離すのではなく、組織全体で支える文化をどう醸成していくかが非常に重要になってきます。
今回のガイドラインのメッセージの一つは、「伴走者は一人ではない」ということです。ある一人の支援者が全てを担うのではなく、それぞれの立場に応じてできる範囲で支援に関わっていくことが、越境学習を「組織の力」に変えていく鍵となります。
例えば、越境前には上司が目標設定を支援し、越境中は受け入れ先が現場での気づきを引き出し、越境後には同僚が学びを活かす機会を提供する。こうした多角的な関わりがあることで、越境学習者は孤立することなく、安心して挑戦と変化を続けることができるでしょう。さらに、こうした支援の中で、支援者側自身も学び、成長していきます。伴走者自身が「支援を通じて育つ」存在でもあるということは、ガイドラインの中でも強調されている点です。
また、支援の文化はイノベーションを育てる土壌のように考えることができます。越境学習がイノベーションの種を外から持ち帰ってくるプロセスであり、その「種」が組織の中で育ち、花を咲かせるためには、周囲の理解と土壌づくりが欠かせないという具合です。
越境学習から戻った社員が新しいアイデアを語ったとき、「それってうちでは無理だよ」と即座に否定されてしまうと、せっかくの挑戦は萎んでしまいます。でも、「面白そう、やってみよう」と声をかけられたら、学びは行動に変わり、やがて組織の変化を起こす原動力になるはずです。そのような、挑戦を歓迎し支援を惜しまない文化こそが、越境学習の成果を最大化し、イノベーションを育てる環境となります。
越境学習が日常的な取り組みとして根付き、越境してきた人の声が自然と組織の中に溶け込む、そんな文化が根付いていけば、越境学習はイノベーションの特別な「きっかけ」ではなく、当然の「日常」になるかもしれません。皆さんの組織でも、ぜひ越境学習を制度としてだけでなく、皆で成功を目指す「自分たち」の学びの機会として、組織の文化として根づかせる取り組みに目を向けていただければと思います。
支援か剥奪か?:イノベーションを育む「葛藤の伴走者」
伊達:
組織の壁を越えて新たな知見や価値観に触れる「越境学習」は、個人の成長を促し、組織にイノベーションをもたらす体験として注目されています。しかし、その成功は、越境学習者を支える「伴走者」の存在なくしては語れません。伴走者は、慣れない環境で奮闘する越境学習者の道標であり、精神的な安全基地となります。
しかし、その支援が「良かれ」という善意のもと、いつしか越境学習者の自律性を奪う「過剰」なものへと変質してしまうパラドックスが存在します。これが「伴走過剰」の問題です。支援が統制となり、配慮が干渉となるとき、学習の機会は失われていきます。本講演では、この伴走過剰という問題の構造を解き明かすとともに、その弊害を乗り越え、越境学習者を力づける伴走のあり方を考えます。
伴走過剰という罠
伴走過剰は、いくつかの典型的なパターンとなって現れます。
第一の罠は、ガイドラインを「先回り」して完璧に実行しすぎることです。例えば、越境中に、伴走者が成功への最短ルートをすべてお膳立てし、起こりうる文化的な衝突や業務上の意見の相違も、問題になる前にすべて調整してしまいます。その結果、越境学習者は自ら道を切り拓く経験を奪われます。越境学習者が本来経験すべき試行錯誤の「余白」が失われ、依存心が助長されるという弊害を生みます。
第二の罠は、マイクロマネジメントで越境学習者を「統制」しようとすることです。例えば、越境後にこの罠が発動すると、越境学習者が立ち上げた実験的なプロジェクトに対して、伴走者がその進捗を逐一管理し、些細な意思決定にまで承認を求めるようになります。
このような過剰な管理は、越境学習者を「勝手に動いたら怒られるかもしれない」と萎縮させ、リスクを取った挑戦から遠ざけます。イノベーションの源泉であるはずの自律的な活動が「やらされ仕事」に変質し、モチベーションを著しく低下させます。
第三の罠が、ガイドラインを「チェックリスト化」し、機械的に実行することです。越境中には、伴走者が越境学習者一人ひとりの状況や心の変化に目を向けず、「面談でAからEの項目をすべて確認した」という事実を作ることが目的化してしまいます。帰任後も、例えば「報告会を実施した」「振り返りシートを提出させた」というタスクをこなすだけで満足し、越境学習者が持ち帰ったアイデアを事業化するための支援や、組織内での障壁を取り除くための働きかけを何もしない、といったケースがこれにあたります。
このような形式的な伴走は、「やった感」だけが先行し、越境学習者の深い気づきや組織への貢献にはつながりません。
「葛藤の回避」がイノベーションを阻害
伴走過剰がもたらす深刻な弊害は、越境学習者から「葛藤」の機会を奪い去ってしまうことにあります。イノベーションとは、既存の常識や秩序から「逸脱」し、新しい価値観や方法に触れる経験から生まれるものです。この「逸脱」には、必然的に周囲との軋轢や、自らの内面におけるジレンマといった「葛藤」が伴います。
しかし、伴走過剰は、良かれという善意から、この重要な葛藤を未然に防ぎ、越境学習者を無菌状態に置こうとします。問題が起きないように先回りして調整し、失敗しないように細かく管理することは、一見すると越境学習者を守っているように思えます。しかし、その実態は、越境学習者が自らの力で困難を乗り越え、そこから深い学びを得てイノベーションを実現するという、越境学習の核心的な価値を奪う行為に他なりません。
葛藤なき越境学習は、予定調和の「お勉強」でしかなく、組織の常識を揺るがすような新しい価値創造にはつながりません。イノベーションの源泉となるのは、葛藤のただ中で悩み、考え抜き、それでも前進しようとする格闘です。伴走過剰の最大の問題は、この格闘の場そのものを消し去ってしまうことにあるのです。
「葛藤の伴走者」という役割
伴走過剰の罠を避け、越境学習者の挑戦を意味あるものにするために、伴走者は自らの役割を再定義する必要があります。それは、問題を取り除く「管理者」ではなく、越境学習者が葛藤と向き合うのを支える「触媒」としての役割です。
第一に、伴走者の役割は、(肯定的な意味での)逸脱者である越境学習者の背中を押し、あえて葛藤の渦中に飛び込んでもらうことです。安全な場所から越境学習者を導くのではなく、未知への挑戦を勇気づけ、一歩を踏み出すきっかけを作ります。
第二に、越境学習者が葛藤の中で精神的に潰れてしまわないよう、セーフティネットとしての役割を果たします。葛藤に飲み込まれそうになったときには心の支えとなり、孤立させないよう注意を払います。しかし、それは問題を肩代わりすることではありません。
第三に、葛藤から安易に退却しないよう働きかけます。越境学習者が困難に直面したとき、すぐに解決策を与えるのではなく、共に悩み、問いを投げかけることで、越境学習者が「健全な形で葛藤の中に居続ける」こと(葛藤に飲み込まれすぎず、かといって離れすぎない状態)をサポートします。
これらを実現するために重要なのは、伴走者が単なる評価者やアドバイザーではなく、越境学習者の挑戦の成否にコミットする「利害関係者」になることでしょう。距離をとって意見を言う評論家とは違い、資源面のスポンサーとなり、熱心な応援者となるのです。例えば、帰任した越境学習者が周囲の無理解という葛藤に直面したとき、その提案の価値を経営層に説いて予算を確保したり、反対勢力との対話の場を設けたりします。
このような当事者としての関わりが、越境学習者との深い信頼関係を築きます。越境学習者にとってみれば、逸脱の中でも支えてくれた伴走者は、かけがえのない「恩人」となり得ます。
おわりに
本講演で見てきたように、「伴走」とは、越境学習者の前を歩いて道を切り拓くことでも、後ろから細かく指示を出すことでもありません。越境学習者の横に立ち、その挑戦がもたらす「葛藤」から逃げずに向き合えるよう、勇気と安心感を与える繊細な営みです。
「伴走過剰」は、良かれという善意から生まれやすい問題だからこそ、伴走者は自らの役割を常に問い直す必要があります。越境学習者を無菌室に入れるのではなく、葛藤という荒波に漕ぎ出す船の、信頼できる「利害関係者」となり、時には「恩人」と呼ばれる存在になる。その覚悟が、越境学習をイノベーションへとつなげる鍵となります。
Q&A
Q:講演でご紹介いただいた、越境学習者を支える「伴走者」に求められるスキルは、非常に高度なものであると感じました。特に、スタートアップの経営に携わった経験など、自社とは全く異なる世界の経験を持つ人材は、社内にはごく少数しかおりません。このような特殊なスキルや経験を持つ伴走者を、計画的に育成していくことは可能でしょうか。それとも、まずは適性を持つ希少な人材を社内で見つけ出すことが中心的なアプローチになるのでしょうか。
藤井:
「適性を持つ人材の発掘」と「計画的な育成」を同時に、そして並行して進めていくのが望ましいでしょう。多様な経験を持つ人材が社内にいれば、まずはその方々を中心に役割を担っていただくのが現実的です。しかし、長期的に見れば、伴走者に求められるスキルを定義し、研修などを通じて計画的に育成する仕組みも求められます。
ただし、一人の人間が全てのスキルを完璧に備えるのは困難です。スーパーマンを求めるのではなく、「Aさんは対話が得意」「Bさんは調整力が高い」というように、それぞれの強みを活かしてチームで学習者を支える、という発想が大切になります。
伊達:
伴走者の候補として有力なのが、「越境学習の経験者」です。一度でも自社の外に出て、異なる文化や価値観に触れ、そこで悩み、学んだ経験を持つ人は、これから越境学習に挑む人の気持ちを理解できます。越境学習を経験した人が、次の学習者の伴走者となり、その経験を通じてさらに成長し、また次の世代を育てる。このような「好循環」を生み出すことが、組織に伴走者を根付かせる上で有効なアプローチです。
Q:当社では、会社の制度として越境学習や大学院での学び直しにかかる費用を補助していますが、学習を終えて会社に戻ってきた社員が、比較的すぐに退職・転職してしまうケースが見受けられます。会社への還元が行われないまま人材が流出してしまうことを防ぐための方法や、この状況の捉え方についてアドバイスをいただけますか。ちなみに、当社に伴走者はいません。
藤井:
これは多くの企業が抱える課題ですね。前提として、「なぜ彼らが会社を去るのか」という原因を丁寧に把握することが出発点となります。その上で、例えば社員一人ひとりがキャリアに何を求めているのかを事前に把握しておくことが有効です。もし、「新しい事業を立ち上げたい」といった変革志向の強い社員が離職しやすい傾向があれば、それは会社が彼らの熱意や能力を活かせるだけの挑戦的な「活躍の場」を提供できていない、というサインかもしれません。その場合は、新規事業の責任者といった役割を社内に設計していくことが、一つの対策となり得るでしょう。
伊達:
この場合の離職の原因の一つに、越境学習のプロセスに必然的に伴う「ある現象」があります。学習者はアウェイの中で葛藤し、「自社を良くしたい」という意欲を持って帰ってきます。しかし、その前向きな提案が、周囲から「前例がない」「余計なことをするな」と反発されたり、無視されたりすることが少なくありません。時に「迫害」に近い扱いを受け、孤立感を深め、「この会社は変わる気がないのか」と失望し、会社を去っていくのです。
こうした悲しい結末を避けるために不可欠なのが「伴走者」です。もし彼・彼女の隣に、提案に真摯に耳を傾け、実現のために一緒に悩み、人脈などのリソースを提供してくれる伴走者がいれば、状況は変わっていたはずです。学習者が持ち帰った「変化の種」を組織の中で芽吹かせるために、伴走者は重要な役割を担っています。
Q:そもそも、「伴走者」という存在がいかに重要であるかを、組織の上層部や周囲の社員に理解してもらうためには、どのように説明すれば良いでしょうか。
藤井:
「伴走という役割は、学習者を支援するためだけのものではなく、伴走者自身の成長にもつながる貴重な機会である」という点を強調することです。学習者を支えるプロセスを通じて、伴走者自身もまた、多様な価値観に触れ、視野を広げ、マネジメント能力を高めることができます。越境学習という取り組みは、学習者本人だけでなく、伴走者、ひいては組織全体にとっても成長の機会をもたらす「一石三鳥」の投資になることを説明しましょう。
伊達:
「ガイドライン」を活用していただくと良いかもしれません。「ガイドラインにおいて、伴走者の重要性がこのように指摘されています」と、客観的な根拠を示しながら説明することで、説得力は増すはずです。ガイドラインでは、伴走者を「越境学習の効果を引き出し、投資を無駄にしないために不可欠な存在」であると位置づけています。ぜひご活用ください。
Q:学習者が抱える「葛藤」に寄り添う中で、「このまま見守るべきか」、それとも「葛藤に飲み込まれてしまう危険があるため介入すべきか」を、どのように見極めればよいのでしょうか。
藤井:
これは伴走者が直面する難しい判断の一つです。見極めのヒントとして、「葛藤の種類」を意識することが役立ちます。その葛藤は、本人の成長にとって不可欠な「成長痛」のようなものでしょうか。それとも、自信を奪い、無力感や強い心理的ストレスにつながってしまうような、危険な葛藤でしょうか。前者の場合は、本人の力を信じてじっくりと見守ることが本人の成長を促しますが、後者の場合は伴走者が積極的に介入し、本人が一人で抱え込まないようにサポートする必要があります。
伊達:
まず、学習者と定期的かつ継続的に対話し、信頼関係を築くことが不可欠です。その上で、介入すべきかどうかを判断するための観点を二つ紹介します。
一つ目は、「学習者自身に、何かやりたいことがあるか」。明確な目標に向かう中での葛藤なのであれば、健全な成長痛である可能性が高いでしょう。二つ目は、「その葛藤が、多くの学習者が経験する典型的なものか」。ガイドラインにも記載されているような「誰もが通る道」なのであれば、本人の力で乗り越えるのを見守るというスタンスで良いでしょう。しかし、非常に個人的で独自性の高い問題で深く悩んでいるような場合は、何か特別な事情が隠されている可能性があるため、注意深く状況をヒアリングし、丁寧な介入を検討する必要があります。
Q:伴走者は非常に重要な役割であると理解できた一方で、その難易度の高さも痛感しました。越境学習の経験者を、さらに優れた伴走者として育成していくためには、どのような機会やスキル育成が効果的でしょうか。
藤井:
効果的な育成機会として、「経験者同士が対話し、学び合える場」を設けることをお勧めします。互いの経験を共有することで、多様な状況に対応できる引き出しが増えます。また、どのスキルから伸ばすかという点では、テクニカルなスキル以前の「スタンス」が重要です。特に「相手の成功を心から喜べる」といった他者への貢献意欲や共感性は、後から教えるのが難しい部分です。もともとそうした心を持つ方にお願いすることが、結果的に、学習者との間に良好な関係を築き、支援が長続きする秘訣ではないかと考えています。
伊達:
伴走の難しさの本質は、私は「心理的なハードル」にあると考えています。組織の常識から「逸脱」しようとする学習者に対し、反発を感じるのは人間として自然なことです。重要なのは、ネガティブな感情が湧いた時に、「自分は今、反発している」と客観的に認識し、「一息ついて冷静になる」ことです。なぜ反発を感じるのか、そのメカニズムを理解していれば、一歩引いて状況を捉えられます。この「一息つく」スキルこそが、伴走者として重要なトレーニングです。その上で、一人で全てを背負わずに「役割分担」するという考え方も、心理的ハードルを下げるために有効です。
脚注
[1] 越境学習を支える伴走者のための実践ガイドライン(経済産業省)
[2] 越境学習をイノベーション創出につなげるために―越境学習グッドプラクティス―(経済産業省)
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。

藤井 貴之 株式会社ビジネスリサーチラボ マネージャー
関西福祉科学大学社会福祉学部卒業、大阪教育大学大学院教育学研究科修士課程修了、玉川大学大学院脳情報研究科博士後期課程修了。修士(教育学)、博士(学術)。社会性の発達・個人差に関心をもち、向社会的行動の心理・生理学的基盤に関して、発達心理学、社会心理学、生理・神経科学などを含む学際的な研究を実施。組織・人事の課題に対して学際的な視点によるアプローチを探求している。