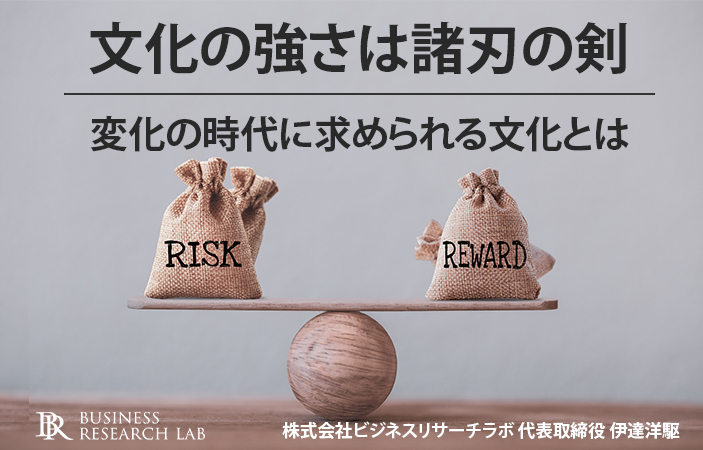2025年8月21日
文化の強さは諸刃の剣:変化の時代に求められる文化とは
企業の成功を左右する要素として、技術力や市場戦略と並んで、組織文化の重要性が認識されるようになっています。組織文化とは、ある企業で共有される価値観や行動規範、思考様式のことを指します。それは目に見えにくいものでありながら、企業の意思決定や日々の業務遂行に根ざしています。
組織文化が企業業績に関わることは多くのビジネスリーダーが感覚的に理解していますが、どのような組織文化が望ましいのかについては、単純に「強い文化が良い」とは言い切れません。なぜなら、組織文化の有効性は、その企業が直面する環境や状況、追求する目標によって変わってくるからです。
本コラムでは、組織文化の「強さ」と「条件適合性」という二つの側面から、組織文化と業績の関係性について考えていきます。強い文化とは組織内で一貫して共有された価値観や行動規範を指し、条件適合性とは企業が置かれた環境や状況に適した文化のあり方を意味します。両者のバランスをどう取るかが、企業の持続的な成功には求められます。
組織文化がどのようなメカニズムで企業の業績や有効性に影響を及ぼすのか、複数の研究成果を紹介しながら掘り下げていきましょう。文化という見えない力を深く理解することは、自らの職場環境を見直し、より良い組織づくりに参加するための手がかりとなるはずです。
強く適応的な文化を持つ企業ほど業績が良い
企業経営において、組織文化が業績に及ぼす影響について多くの議論がなされてきました。興味深いのは、単に「強い文化」を持つだけでなく、「適応的な文化」も併せ持つ企業が優れた業績を達成する点です。
米国の生命保険業界11社を対象とした7年間にわたる縦断的研究では、組織文化の強さと適応性が企業業績に及ぼす影響が調査されました[1]。この調査では、組織文化を測定するために、経営幹部へのアンケートを実施し、戦略の明確性、リスク志向、情報共有、成果重視などの8つの要素を評価しました。
調査結果からは、文化の強さと企業業績の間に相関関係が認められました。とりわけ、保険料成長率という業績指標においては、強い文化を持つ企業が高い成長を達成していました。ここでいう「強い文化」とは、組織内で価値観や行動規範が一貫して共有され、従業員の行動や意思決定に影響を与えている状態を指します。
しかし、文化が強いだけでは十分ではなく、外部環境への適応性も重要です。適応性に関する尺度、具体的には革新性やリスクテイキングを評価する項目は、将来的な企業業績と正の相関を示しました。外部環境の変化に柔軟に対応できる文化を持つ企業ほど、長期的には良好な業績を達成していたのです。
この研究では、特定の価値観に過度に集中することの危険性も指摘されています。調査対象企業の中で、ある一つの価値観だけを極端に重視する企業は、むしろ業績の低下が見られました。これは、一つの価値観に固執することで組織の柔軟性が失われ、環境変化への対応力が低下するためと考えられます。
例えば、「顧客第一」という価値観だけを極端に重視すると、短期的には顧客満足度が向上するかもしれませんが、従業員の満足度やイノベーションが犠牲になり、長期的な競争力を損なう可能性があります。同様に、「効率性」だけを追求すれば、短期的なコスト削減は実現できても、組織の創造性や適応力が低下し、市場環境の変化に対応できなくなるでしょう。
組織文化のマネジメントにおいては、「強さ」と「適応性」のバランスが肝心です。強い文化は企業内部の一貫性や効率性を高め、適応的な文化は外部環境の変化への対応を可能にします。両者を兼ね備えることで、企業は短期的な業績と長期的な持続可能性の両方を実現できます。
強い文化は業績を安定させるが、環境変化に弱い
強く適応的な文化を持つ企業ほど業績が良いという研究結果を見てきました。組織文化の強さが業績の「安定性」にはどのような影響を与えるのでしょうか。また、その影響は産業環境の変動性によってどう変わるのでしょうか。
アメリカの大企業を対象とした研究では、強い組織文化が企業業績に及ぼす影響について、業績の平均値だけでなく、その変動性(安定性)にも焦点を当てて分析が行われました[2]。ここでも「強い組織文化」とは、企業内で価値観や規範が広く共有され、強く維持されている状態を指します。具体的には、次の3点から評価されました。
- 社内で共通した行動スタイルが存在する
- 企業が明確な価値観を提示し、経営陣がそれを強く推進している
- 長年にわたり一貫したポリシーに基づき経営されている
調査の結果、強い組織文化を持つ企業は業績の「安定性」が高いという仮説が支持されました。投資資本利益率(ROI)やキャッシュフローといった業績指標において、強い文化を持つ企業は変動が少なく、安定した業績を示しました。強い文化が企業内部での一貫した行動や意思決定を促進することで、業務遂行の予測可能性や信頼性を高めるためと考えられます。
しかし、この「安定化効果」は、業界の変動性によって左右されることも判明しました。安定した業界環境では、強い文化の業績安定化効果は顕著に現れましたが、業界の変動性が高まるにつれて、この効果は減少し、最終的にはほとんど消失しました。
なぜでしょうか。強い組織文化の持つ「両刃の剣」的な性質がここに現れています。強い文化は内部の一貫性や効率性を高める一方で、外部環境が大きく変化するときには柔軟な適応を難しくする可能性があります。組織文化が強すぎると、新しい環境に適応するための革新的な試み、すなわち「探索的学習」が阻害される恐れがあります。
この現象は、組織学習の観点から「探索(exploration)」と「活用(exploitation)」のジレンマとして説明できます。「活用」とは既存の知識や能力を効率的に使って成果を上げることであり、「探索」とは新しい可能性や機会を模索することです。強い組織文化は「活用」を促進しますが、「探索」を抑制します。安定した環境下では「活用」による効率性が優位に働きますが、変動的な環境では「探索」による革新性が重要になるのです。
例えば、長年安定した業績を上げてきた企業が、急激な技術革新や市場構造の変化に直面したとき、強い組織文化が逆に足かせになることがあります。「我々はこれまでこうやってきた」という共有された価値観や行動様式が、新たな発想や変革への抵抗につながるからです。
ビジネスの歴史を振り返れば、かつて業界をリードしていた企業が環境変化に適応できず衰退した例は少なくありません。それらは強い文化が環境変化への適応を妨げた典型例と見ることができるでしょう。
この研究が示唆するのは、組織文化の強さが企業にもたらす恩恵は環境条件によって変わるということです。安定した環境では強い文化が業績の安定化に貢献しますが、変動的な環境ではその恩恵が減少し、場合によっては障害にもなりうるのです。
組織の有効性は文化タイプで異なる影響を受ける
組織文化と組織の有効性の関係を考える上で、文化の「強さ」だけでなく「タイプ」も重要です。組織文化は一様ではなく、様々なタイプに分類できます。そして、文化のタイプによって、組織のどのような側面が強化されるかが異なってきます。
競合価値フレームワーク(Competing Values Framework, CVF)という理論モデルは、組織文化を2つの軸(内部志向 vs 外部志向、柔軟性 vs 統制性)で分類し、4つのタイプに整理しています。この枠組みを用いたメタ分析の研究では、84の先行研究(合計880の相関係数)を統合的に分析し、各文化タイプが組織の有効性にどのような影響を与えるかを検証しました[3]。
CVFでは、組織文化を次の4つのタイプに分類しています。
- クラン文化:内部志向・柔軟性重視で、協調や信頼、チームワークを大切にする文化
- アドホクラシー文化:外部志向・柔軟性重視で、創造性やイノベーションを重んじる文化
- マーケット文化:外部志向・統制性重視で、競争力や目標達成を追求する文化
- ヒエラルキー文化:内部志向・統制性重視で、規則やプロセスの一貫性を重視する文化
メタ分析の結果、各文化タイプは組織の異なる側面に対して、それぞれ固有の影響を及ぼすことが判明しました。
従業員の態度(満足度やコミットメント)に関しては、クラン文化が最も強い正の関連を示しました。これは、クラン文化が人間関係や信頼、協力を重視するため、従業員の心理的満足感や組織への帰属意識を高める効果があるためでしょう。従業員が「家族の一員」のように感じられる職場は、モチベーションの維持や長期的な定着に貢献します。
一方、業務パフォーマンスについては意外な結果が得られました。イノベーションとの関連が最も強かったのは、当初予想されたアドホクラシー文化ではなく、マーケット文化でした。マーケット文化は競争意識と成果主義を重視するため、従業員の創造性を刺激し、革新的なアイデアの実現を促進する可能性があります。ただし、アドホクラシー文化もクラン文化よりはイノベーションと強い関連を示しており、創造性を育む効果は確かにあります。
製品やサービスの品質については、マーケット文化とクラン文化が同程度の正の関連を示しました。マーケット文化は市場での競争力を高めるために品質向上を重視し、クラン文化は顧客満足を含めた関係性の質を大切にするため、どちらも品質に良い影響を与えると解釈できます。
財務パフォーマンスについては、主観的評価(認識されている業績)においても客観的指標(実際の利益や成長率)においても、マーケット文化が最も強い正の関連を示しました。ただし、客観的な財務パフォーマンスについては、アドホクラシー文化との差は統計的に有意ではありませんでした。競争や成果を重視するマーケット文化と、革新や変革を重視するアドホクラシー文化は、どちらも財務的な成功に寄与する可能性があるということです。
この研究で興味深いのは、CVFの理論では対角に位置する文化タイプ(例えばクラン文化とマーケット文化)は互いに対立的だと仮定されていたのに対し、実際のデータ分析では各文化タイプ間に強い正の相関が見られたことです。現実の組織では様々な文化要素が混在し、対立的というよりむしろ補完的に機能している可能性があります。
組織が目指す成果に応じて、意識的に文化のタイプを形成または強化できるかもしれません。例えば、従業員の満足度や定着率を高めたい場合はクラン文化的要素を、市場での競争力や財務成果を追求したい場合はマーケット文化的要素を強化するといったアプローチが考えられます。
文化の特性ごとに組織の有効性への影響は異なる
組織文化を理解する別のアプローチとして、文化を構成する「特性」に着目する方法があります。文化の「タイプ」が全体的な傾向を表すのに対し、「特性」は詳細な要素に分解して考察するものです。
アメリカの大企業を対象とした研究では、組織文化を4つの主要な文化特性に分類し、それぞれがどのように組織の有効性に影響するかを分析しました[4]。この研究の特徴は、定性的なケーススタディと定量的な調査を組み合わせた混合的手法を用いている点にあります。5つの企業の詳細なケーススタディを行い、その後764の企業を対象とした大規模調査で仮説を検証するというアプローチが取られました。
この研究で着目された4つの文化特性は次の通りです。
- 関与(Involvement):従業員の参加や貢献を促し、オーナーシップを育む特性
- 一貫性(Consistency):組織内の行動や意思決定の安定性と予測可能性を高める特性
- 適応性(Adaptability):外部環境の変化に対応し、学習と革新を促進する特性
- ミッション(Mission):組織の目的や方向性を明確にし、従業員に意味を与える特性
ケーススタディからは、これらの特性が実際の企業でどのように現れるかが明らかになりました。例えば、医療機器メーカーのMedtronicは高い「関与」の文化を持ち、人間主義的な価値観を大切にすることで、従業員の積極的な参加と貢献を引き出していました。この企業では、組織の目標と個人の目的を統合することで高いパフォーマンスを実現していました。
一方、消費財メーカーのProcter & Gambleは強力な「一貫性」を特徴とする文化を持ち、明確な規範と内部的な秩序に基づいて運営されていました。この一貫性が安定した品質と信頼性をもたらし、長期的な成功につながっていました。
航空会社のPeople Express Airlinesは「適応性」の高い文化を持ち、社員の自発的関与と柔軟な対応を重視していました。これにより急速な成長を遂げましたが、一定の規模を超えたところで組織の制御が難しくなるという課題も生じました。
エネルギー会社のDetroit Edisonは伝統的で官僚的な性質が強く、変化への「適応力」が低い一方で、明確な「ミッション」によって一定の安定性を保っていました。明確な目的意識が従業員の方向性をそろえ、組織の一体感を維持する役割を果たしていました。
金融機関のTexas Commerce Bancshares(TCB)は、「ミッション」志向が強く、組織文化が強固な数値目標と統制によって特徴づけられていました。そのため環境変化への適応には課題を抱えていましたが、明確な方向性と数値目標によって高い財務パフォーマンスを達成していました。
これらのケーススタディを踏まえた定量調査の結果、各文化特性が組織の有効性の異なる側面に影響することが確かめられました。
「関与」と「適応性」の特性は、組織の柔軟性や顧客志向性を高め、結果として成長や売上増加といった指標に関連していました。従業員が主体的に参加し、外部環境の変化に敏感に対応できる組織は、市場機会を捉えて拡大する能力が優れています。
対して、「一貫性」と「ミッション」の特性は、内部統制と方向性の明確さをもたらし、収益性や組織の安定性といった指標に関連していました。内部プロセスが安定し、全員が同じ方向を向いて進む組織は、効率的な運営と安定した収益を生み出しやすいと言えます。
特に「ミッション」は、総合的な組織パフォーマンス(資産収益率:ROA)に対して最も強い相関を示しました。明確な目的や戦略的方向性を持つことが、組織全体の成果に貢献することを意味しています。
4つの文化特性はすべて組織の有効性にプラスの影響を与えるものの、それぞれが異なる側面に作用します。しかも、これらの特性の間にはトレードオフの関係もあり、すべてを同時に最大化することは難しいのです。
例えば、高い「一貫性」を追求すると、内部の安定性は高まりますが、「適応性」が低下する可能性があります。同様に、「関与」を重視して従業員の自律性を高めると、「ミッション」の統一性が損なわれる恐れもあります。
組織が直面する環境や戦略的優先事項に応じて、これらの文化特性のバランスを調整することが課題です。安定した市場で競争する企業は「一貫性」と「ミッション」を、急速に変化する環境で革新を追求する企業は「関与」と「適応性」を相対的に強化するといった選択が考えられます。
また、企業の成長段階によっても、重視すべき文化特性は変化するでしょう。創業期には「適応性」と「関与」が重要かもしれませんが、成熟期には「一貫性」と「ミッション」の強化が必要になるかもしれません。
脚注
[1] Gordon, G. G., and DiTomaso, N. (1992). Predicting corporate performance from organizational culture. Journal of Management Studies, 29(6), 783-798.
[2] Sorensen, J. B. (2002). The strength of corporate culture and the reliability of firm performance. Administrative Science Quarterly, 47(1), 70-91.
[3] Hartnell, C. A., Ou, A. Y., and Kinicki, A. (2011). Organizational culture and organizational effectiveness: A meta-analytic investigation of the competing values framework’s theoretical suppositions. Journal of Applied Psychology, 96(4), 677-694.
[4] Denison, D. R., and Mishra, A. K. (1995). Toward a theory of organizational culture and effectiveness. Organization Science, 6(2), 204-223.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。