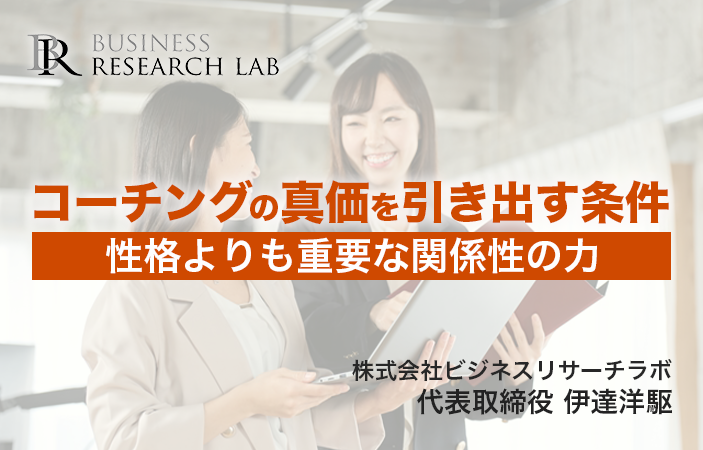2025年8月19日
コーチングの真価を引き出す条件:性格よりも重要な関係性の力
コーチングとは、対話を通じて相手の気づきや学びを促し、自発的な行動変容を支援するプロセスです。多くの企業がコーチングを導入していますが、その効果には差があることが分かっています。同じコーチングでも、ある条件下では顕著な成果を生み出す一方で、別の条件下ではほとんど変化が見られないこともあります。
コーチングが高い効果を発揮するためには、どのような条件が必要なのでしょうか。この問いに答えるために、本コラムでは複数の実証研究を参照しながら、コーチングの効果を高める要因について考察します。コーチングの成果を左右するのは、コーチの技術だけでしょうか。それとも、コーチとコーチを受ける側との相性でしょうか。あるいは、組織的な支援体制や評価方法との組み合わせが鍵を握るのでしょうか。
これらの問いについて、研究知見を紐解きながら、コーチングが効果を発揮する条件について検討します。コーチングに携わる人はもちろん、人材開発や組織開発に関心のある人にとって、本コラムが新たな視点や気づきをもたらすものとなれば嬉しく思います。
コーチング併用で他者評価が向上
コーチングの効果を高める第一の条件として、他の評価手法との併用が挙げられます。「360度フィードバック」と「体系的なコーチング」を組み合わせることで、管理職の自己認識が高まり、職場全体の態度改善につながることが明らかになっています。
360度フィードバックとは、上司、同僚、部下など多方面から評価を受ける手法です。この評価方法は多くの組織で導入されていますが、単独では十分な効果を発揮しないことが問題視されていました。評価の情報量が多すぎて処理しきれなかったり、自己評価と他者評価の差が大きく受け入れられなかったりするケースが少なくありません。
この研究では小規模製造業の企業で、管理職20名と従業員67名を対象に調査が行われました[1]。調査では、管理職の行動能力、対人能力、個人的責任感という3つの要素から構成される「管理職フィードバックプロファイル」を用いて評価が行われました。行動能力には問題解決能力や職務遂行能力が、対人能力には質問対応能力や意見傾聴能力が、個人的責任感には自分の行動への説明責任や信頼性が含まれています。
体系的コーチングでは、評価結果をもとに、自己評価と他者評価の差異の認識とその原因理解、改善すべき行動の具体化、実際の職務における適用方法の明確化に焦点が当てられました。評価結果を視覚的に示したチャートを用いて、「どの行動をどう改善するか」を対話を通じて具体化したことが、この研究の特徴です。
調査の結果、体系的コーチングを実施する前は自己評価と他者評価の間に有意な差がありましたが、コーチング後にはこの差が解消されました。このとき見られた変化で特徴的だったのは、管理職自身が自己評価を下げるのではなく、他者評価が向上することで差が埋まったという点です。管理職は実際に行動を改善し、周囲からの評価が高まったと解釈できます。
加えて、コーチング実施後には管理職と従業員の双方で、職務満足度が向上し、組織コミットメントが強まり、離職意図が低下するという態度変化が見られました。職務満足度は仕事内容、上司との関係、同僚との関係のすべてにおいて向上したことが確認されました。
これらの結果から、360度フィードバックに体系的コーチングを併用することで、評価結果の提示以上の効果が得られることが分かりました。管理職が評価結果を理解し、行動変容につなげるためには、コーチングという手段が必要だったということです。
この研究の意義は、コーチングが他の手法と組み合わされることで、その効果が増幅される可能性を示した点にあります。ただし、研究自体には対照群がなく、理想的な実験設計ではないという限界があります。そのため、観察された効果が本当にコーチングによるものなのか、あるいは別の要因によるものなのかを完全に区別することはできません。
コーチングは360度評価と併用で効果が高まる
コーチングと360度フィードバックの併用効果について、さらに検証した研究があります。エグゼクティブ・コーチングと360度フィードバックがリーダーシップの効果にどのような影響を与えるかが調査されました[2]。
この研究は、アメリカの企業に勤務する281人の管理職を対象に行われました。参加者は3つのグループに分けられました。第1グループはコーチングのみを受ける45名、第2グループは360度フィードバックのみを受ける85名、そして第3グループはコーチングと360度フィードバックの両方を受ける151名です。
調査ではリーダーシップ行動尺度と目標達成率という2つの指標が用いられました。リーダーシップ行動尺度は管理職のリーダーシップ行動を評価するもので、目標達成率は自己評価および他者評価によるリーダーシップの有効性を測る指標です。これらの指標を用いて、コーチングや360度フィードバックの前後で測定を行い、その変化が分析されました。
調査の結果、3つのグループすべてにおいて、事前測定から事後測定にかけてリーダーシップ行動尺度に統計的に有意な改善が見られました。しかし、コーチングと360度フィードバックを併用したグループが、単一手法のグループよりも大幅に高い改善度を示しました。
また、リーダーシップの有効性(目標達成率)についても、グループごとに異なる変化が観察されました。コーチングのみを受けたグループでは、自己評価の改善が最も高かったものの、他者評価における改善は比較的限定的でした。一方、360度フィードバックのみを受けたグループでは、自己評価よりも他者評価における改善が高い傾向が見られました。そして、コーチングと360度フィードバックを併用したグループでは、自己評価と他者評価の両方において大きな改善が確認されました。
これらの結果は、コーチングと360度フィードバックがそれぞれ異なる効果をもたらすことを示しています。コーチングは主に自己認識や自己効力感を高めるのに効果的ですが、他者との相互作用に関する認識については必ずしも直接的な改善をもたらさない可能性があります。一方、360度フィードバックは他者視点からの認識向上を促進しますが、具体的な行動変容を支援するには追加的な支援が必要かもしれません。
先ほど紹介した研究と合わせて考えると、コーチングの効果を高めるための条件として、360度フィードバックとの併用が浮かび上がってきます。コーチングと360度フィードバックはそれぞれ異なる強みを持ち、両者を組み合わせることで効果を引き出せることが分かります。
コーチングの成果は性格より関係性で決まる
コーチングの効果を高める条件として、評価手法との併用に関する研究を見てきました。では、コーチングプロセス自体の中で、何が成果を左右するのでしょうか。2016年に発表された研究では、コーチングの成果に影響を与える要因として、「コーチとクライアントとの関係性」、「コーチとクライアント間の性格の一致」、「クライアントの自己効力感」の3つに着目し、それらの相対的な貢献度が検証されました[3]。
この研究は34か国から1,895組のコーチとクライアントのペア(合計366名の異なるコーチ)、および92名のスポンサー(人事担当者や管理職)から収集したデータに基づく大規模なものです。合計3,882件のアンケート回答が分析されました。
研究の背景には、心理療法分野で実証されている「共通要因」という概念があります。これは、特定の技法や方法論よりも、援助者と被援助者との関係性やコミュニケーションの質が成果を決定づける要因になるという理論です。コーチング研究においても、「コーチとクライアント間の関係性(Working Alliance)」の質が重要な成果要因として注目されてきました。
研究では、関係性を「タスク(課題の明確さ)」「ゴール(目標の共有)」「ボンド(情緒的な結びつきや信頼感)」という3つの側面から評価しました。また、性格はMBTI(マイヤーズ・ブリッグス・タイプ指標)を用いて測定されました。
研究の結果、コーチとクライアント双方が評価した関係性はコーチングの成果と正の相関を示しました。特に「タスク」と「ゴール」の側面が「ボンド」よりも成果に強い影響を与えることが明らかになりました。これは、心理療法とは異なり、コーチングでは感情的な絆よりも課題や目標の共有がより重要である可能性を示唆しています。
また、クライアントの自己効力感(自分は目標を達成できるという信念)も、コーチングの成果と有意に正の相関がありました。コーチとクライアント間の関係性が自己効力感の影響を一部媒介することも分かりました。特に「ゴール」と「タスク」の側面が自己効力感の影響を強く媒介していました。
一方で、MBTIによるコーチとクライアントの性格の一致・不一致は、コーチングの成果や関係性にほとんど影響を与えませんでした。僅かな例外はあったものの、全体としては性格のマッチングが成果を予測する要因とはならなかったのです。
これらの結果から、コーチングの成果は特定の性格マッチングよりも、関係性の質と目標設定が重要であることが確認されました。コーチングの過程での目標共有が自己効力感を補完できることも示されました。
コーチングの成果はコーチとの関係性で決まる
コーチングの成果における関係性の重要性が大規模研究によって裏付けられたことを見ました。この関係性の大事さについて、詳しく検証した研究があります。この研究では、エグゼクティブ・コーチングにおいて、コーチとクライアントの関係性が成果にどのような影響を及ぼすのかが検証されました[4]。
エグゼクティブ・コーチングは企業においてマネジメントスキル向上のために広く用いられていますが、その有効性を支える要因については実証的研究が不足していました。この研究では、心理療法分野における「作業同盟(working alliance)」という概念をエグゼクティブ・コーチングに応用し、その関係性が自己効力感向上の媒介要因として機能するかどうかを検証しています。
「作業同盟」とは、心理療法分野で研究されてきた概念で、前述の通り、「目標(Goals):両者間で共有される目標」、「課題(Tasks):目標達成のための課題設定に関する合意」、「絆(Bond):両者間の情緒的な信頼関係」という3つの要素を含んでいます。
この研究では、北米の大手製造業企業におけるマネジメントスキル開発プログラムに参加した管理職者73名(クライアント)と、コーチ役を務めた幹部24名を対象に調査が行われました。プログラムは8か月間で、集合研修(8日間)、アクションラーニンググループ(半日×7回)、個別のエグゼクティブ・コーチング(最大14回、各90分)が含まれていました。
調査では、「作業同盟尺度」、「自己効力感尺度」、「転移動機尺度」、「上司からの支援尺度」などの測定ツールが使用され、研修前・研修中間・研修終了後の3回にわたってデータが収集されました。
研究の結果、自己効力感はプログラム前後で有意に向上したことが確認されました。そして、コーチとクライアント間の関係性(作業同盟)が、自己効力感の向上に対して有意な媒介効果を持っていることが示されました。これは完全な媒介効果であり、関係性を考慮に入れると、他の要因の直接的影響は見られなくなりました。
また、コーチング回数が多いほど関係性が強まり、自己効力感が向上するという相関も見られました。これは心理療法の研究結果とも一致しており、関係性の構築には一定の時間と回数が必要であることを示唆しています。
関係性に影響を与える要因としては、コーチのスキルについては「学習と結果を促進する能力」が関係性と強く関連していました。一方、クライアント側の要因では、「転移動機(学んだことを仕事に活かす動機)」、「上司の支援」、「コーチングのセッション数」が関係性を予測しました。
これらの結果から、コーチとクライアントの関係性が、コーチングの効果を発揮するための前提条件であることが実証されました。心理療法とは異なる点として、コーチングではコミュニケーション能力や人間関係能力よりも、具体的な結果達成に導く能力が重視されていることも明らかになりました。
先の大規模研究と合わせて考えると、コーチングの効果を高めるための鍵は、コーチとクライアントの間に構築される質の高い関係性にあることが一貫して示されています。特に、共有される目標や課題に関する合意形成が重要であり、それによって自己効力感が高まり、最終的な成果につながることが分かります。
脚注
[1] Luthans, F., and Peterson, S. J. (2003). 360-degree feedback with systematic coaching: Empirical analysis suggests a winning combination. Human Resource Management, 42(3), 243-256.
[2] Thach, E. C. (2002). The impact of executive coaching and 360 feedback on leadership effectiveness. Leadership & Organization Development Journal, 23(4), 205-214.
[3] de Haan, E., Grant, A. M., Burger, Y., & Eriksson, P.-O. (2016). A large-scale study of executive and workplace coaching: The relative contributions of relationship, personality match, and self-efficacy. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 68*(3), 189?207.
[4] Baron, L., and Morin, L. (2009). The coach-coachee relationship in executive coaching: A field study. Human Resource Development Quarterly, 20(1), 85-106.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。