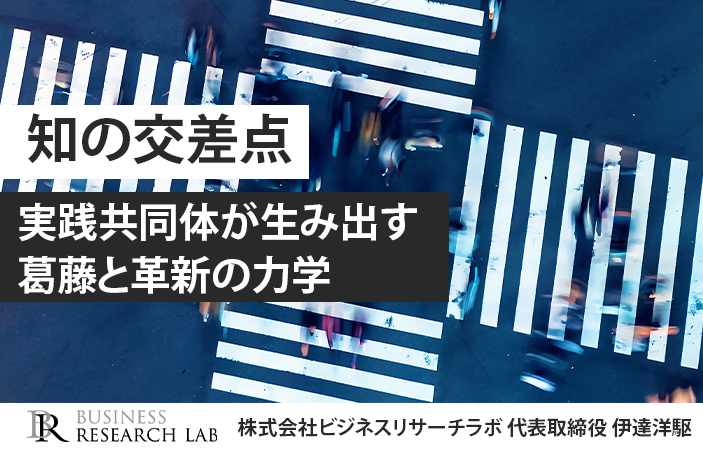2025年8月18日
知の交差点:実践共同体が生み出す葛藤と革新の力学
職場では、日々さまざまな知識や経験が共有され、新たな知恵が生み出されています。この知識の共有と創造の場として近年、「実践共同体」という概念が認識されるようになっています。実践共同体とは、同じ関心や問題などを持ち、相互作用を通じて知識や技能を深めていく人々の集まりです。職場における部門横断的なプロジェクトチーム、同じ専門性を持つ人々のネットワーク、あるいは趣味のサークルなど、様々な形で私たちの周りに存在しています。
しかし、実践共同体は必ずしも平和で調和的な場ではありません。そこには「維持」と「革新」の間の緊張関係が存在します。既存の知識や慣行を保持しようとする力と、新たな知識や実践を生み出そうとする力が拮抗しているのです。
本コラムでは、実践共同体における「維持」と「革新」の揺れ動きに焦点を当て、複数の研究知見をもとに、実践共同体の多面的な姿を探っていきます。実践共同体間の参加と実践の葛藤、進化のプロセス、戦略的な形成、権力関係の埋め込み、そして機能の制限といった視点から、実践共同体の複雑な様相を紐解いていきます。
実践共同体間の参加と実践の葛藤が学習を促す
現代の組織では、一人の人間が複数の集団や共同体に同時に属することが珍しくありません。例えば、ある人は公式の部署に所属しながら、プロジェクトチームのメンバーであり、さらに社内の勉強会にも参加しているかもしれません。このように、私たちは複数の実践共同体にまたがって活動することが多いのです。
実践共同体とは、同じような関心や問題などを持ち、継続的な相互作用を通じて専門知識や技能を深めていく人々の集まりです。これまでの研究では、実践共同体における学習は「参加」「アイデンティティ」「実践」という三つの概念を通じて理解されてきました。
「参加」とは、物理的に共同体の活動に加わるだけでなく、社会的なコミュニティの中で実践に能動的に関与するプロセスです。例えば、新入社員が職場の習慣や規範を学び、徐々にベテラン社員と同じように考え、行動するようになる過程がこれにあたります。この参加は常に平和的とは限らず、共同体内の権力関係や葛藤の中で行われます。
「アイデンティティ」は、「私は誰であり、どのコミュニティに属するのか」という自己理解です。学習とは知識の習得だけでなく、このアイデンティティの形成を含むプロセスです。組織においては、公式な規制(管理職からの期待など)と個人のアイデンティティ形成努力(自分らしさを保とうとする試み)の相互作用によって、職業的なアイデンティティが形成されていきます。
「実践」は、歴史的・社会的文脈の中で意味を持つ社会的な行為です。実践を通じて人々は共同体内の道具、言語、規範、価値観などを学び、自分の行動様式を構築・変容させていきます。新人は熟練者の行動を観察し模倣しながら、徐々に自分独自の実践スタイルを築いていきます。
しかし、複数の実践共同体に同時に所属する場合、それぞれの共同体で求められる参加の形やアイデンティティ、実践が異なることがあります。例えば、研究開発部門では創造性が重視される一方、製造部門では標準化された手順の遵守が求められるでしょう。このような相違が、個人の中で緊張や葛藤を生み出します。
ある研究では、複数コミュニティへの参加に伴う緊張や葛藤こそが、深い学習を促す可能性があると指摘されています[1]。異なる共同体間を移動する際、私たちは自分のアイデンティティや実践を調整・交渉する必要があります。この過程で、私たちは自分の知識や前提を問い直し、新たな視点を取り入れ、より柔軟で創造的な思考を発展させることができます。
実践共同体間の境界における参加は、必ずしも容易ではありません。異なる言語や価値観、実践方法の違いに戸惑うこともあるでしょう。しかし、この「境界体験」がもたらす認知的な不協和や緊張が、新たな学習や知識創造の源泉となり得ます。
実践共同体は進化するほど組織に革新をもたらす
実践共同体は静的なものではなく、時間とともに発展し変化していきます。それでは、実践共同体はどのように成長し、進化していくのでしょうか。そして、その進化は組織にどのような変化をもたらすのでしょうか。IBMグローバル・サービスの事例から、実践共同体の進化過程とその組織的価値について考えてみましょう[2]。
IBMグローバル・サービスでは、社員間の知識共有や知識創造を促進するために、1995年にナレッジマネジメントプログラムを導入しました。このプログラムの中心となったのが、「ナレッジ・ネットワーク」と呼ばれる実践共同体です。これは世界規模で専門知識を持つ社員同士をつなぎ、知識共有を促進するネットワークでした。
ある研究では、約5年間に渡って観察された60以上のナレッジ・ネットワークの進化パターンが分析され、実践共同体の進化モデルが構築されました。このモデルでは、実践共同体の発展段階が5つのステージに分けられています。
- 第一段階は「潜在(Potential)」の段階です。これは共同体が形成されつつある初期段階で、メンバー間での最初の接触や個人的なつながりが形成されています。例えば、同じような問題意識を持つ社員が集まり、情報交換を始める時期がこれにあたります。この段階では、電子メールやオンラインフォーラムなどの基本的なコミュニケーションツールが活用されます。
- 第二段階は「構築(Building)」です。この段階では、共同体が明確に定義され、運営原則が作られます。メンバーは互いをよく知るようになり、共通の専門用語や規範を形成し始めます。知識の分類・保存といった基本的な知識管理活動も始まります。実践共同体の中には、この段階で停滞したり消滅したりすることもあります。環境変化に対応できず、活動が形骸化してしまうのです。
- 第三段階は「関与(Engaged)」です。ここでは、共同体の活動プロセスが定着し、改善が進みます。メンバー間の信頼が構築され、コミュニティへのコミットメントが高まります。新メンバーを迎え入れ、社会化させるプロセスも整備されます。この段階では、ポータルサイトや多言語翻訳ツールなど、より高度なテクノロジーが活用されることもあります。
- 第四段階は「活発(Active)」です。共同体の活動がビジネス価値として認識される段階です。メンバーは具体的なビジネス課題を協働で解決するようになり、グループでの問題解決や意思決定プロセスが確立されます。他のコミュニティとの統合も進み、電子会議や高度な分析ツールなどのテクノロジーも活用されます。
- 最終段階は「適応(Adaptive)」です。この段階に達した実践共同体は、環境変化に対応し、革新や新たなビジネスを生み出す力を持ちます。メンバーはビジネス環境を変える革新的な活動を展開し、先端技術の試験導入や外部技術との統合にも取り組みます。研究では、この最終段階に達する共同体は極めて稀であり、通常はその前段階で組織に吸収されるか、ビジネスユニット化されることが多いと指摘されています。
IBMの事例分析からは、実践共同体の進化には「人」「プロセス」「テクノロジー」の3つの要素がバランスよく統合されることが重要だということがわかります。「人」の要素では、メンバー間の信頼関係や相互理解、「プロセス」の要素では、知識の共有・創造・活用の方法、「テクノロジー」の要素では、コミュニケーションや協働を支援するツールなどが、各段階で異なる形で必要とされます。
実践共同体がより高い段階へと進化するにつれ、その活動は情報交換から、知識の体系化、問題解決、そして最終的には組織の変革や新事業創出へと発展していきます。このように、実践共同体は進化するほど、組織にとって価値をもたらす可能性があります。
実践共同体は戦略的に形成されイノベーションを促す
実践共同体は自然発生的に形成されると考えられがちであり、それも一つの側面ですが、組織が戦略的に構築し、イノベーションを促進するために活用できることをご存知でしょうか。医療分野における革新的技術導入の事例を通じて、実践共同体が戦略的に形成され、イノベーションを推進する過程を分析した研究があります。
この研究では、国際的な医療企業(研究では「Medico」と仮称)が前立腺がん治療の技術「ブラキセラピー」を導入するプロジェクトを調査しました[3]。ブラキセラピーは、外科手術や放射線療法に代わる新しい治療法であり、多くの専門家グループ(医師、マーケティング担当者、科学者など)が関与する複雑なプロジェクトでした。
従来の実践共同体研究では、共同体は同じような実践に従事する人々が自然に集まって形成されると考えられてきました。しかし、この事例研究からは、実践共同体が組織のイノベーション戦略を実現するために、意図的かつ戦略的に構築されうることが明らかになりました。
Medico社のマネジャーたちは、「コミュニティ」という言葉を修辞的に活用し、異なる専門分野や利害関係を持つグループを結集させる戦略を取りました。「コミュニティ」という言葉には、協力や共有といった肯定的なイメージがあります。このイメージを利用して、異なる背景を持つ専門家たちを共通の目的に向かわせることができました。
また、非公式なネットワーキングがプロジェクト推進の鍵となりました。Medicoの営業担当者やプロジェクトマネジャーは「知識の仲介役」として機能し、専門職間や組織間の境界を越えた情報流通を可能にしました。彼ら彼女らは多様な参加者を引き込み、公式の組織構造を越えた非公式なコミュニティを構築したのです。
このプロセスで見逃せないのは、コミュニティ形成における「政治性」です。コミュニティ形成は純粋に自然発生的な現象ではなく、むしろ戦略的で政治的な行為でした。異なる専門家グループの間には利害の対立も存在し、それらを調整するために権力関係の管理が必要でした。
例えば、医師たちは新技術の導入に慎重な姿勢を示す一方、企業側は早期の市場導入を望んでいました。また、放射線医と泌尿器科医の間には専門的な領域をめぐる緊張関係もありました。これらの異なる利害や視点を調整するために、プロジェクトリーダーは様々な戦略を用いました。
彼ら彼女らは公式の会議だけでなく、非公式な場での対話も重視しました。各専門家グループの専門性を尊重しつつも、プロジェクト全体の目標を共有することで、一体感を醸成しようと努めました。さらに、「患者への貢献」といった共通の価値観を強調することで、異なる専門家間の協力を促進しました。
実践共同体での学習は権力関係に埋め込まれる
私たちがチームやグループで働く際、しばしば「みんなで協力して学び合おう」といった言葉を耳にします。しかし、実践共同体における学習は、常に平等で調和的な過程として進むわけではありません。実践共同体における「権力関係」の重要性を指摘し、私たちの学習がどのように権力の影響を受けているのかを明らかにした研究を見ていきましょう[4]。
実践共同体における学習を考える上で基本となるのが「状況的学習論」です。この理論は、学習を個人の内面的な認知過程としてではなく、社会的・歴史的な文脈の中で生じる「参加」を通じた現象として捉えます。重要なのが「正統的周辺参加」という概念で、これは新人が共同体の活動に周辺的な参加者として入り込み、徐々に中心的な参加者へと変化していくプロセスを指します。
しかし、研究では、この理論が権力関係を十分に考慮していないと批判しています。組織内での学習は常に一定の社会的・政治的・経済的文脈(権力関係)に埋め込まれており、これらを無視することは現実の学習過程を単純化してしまうことになります。
具体的に権力はどのように学習に関わるのでしょうか。初めに、権力は「何が学ばれるべきか」を決定します。例えば、ある組織では効率性に関する知識が重視され、創造性に関する知識は軽視されるかもしれません。また、「誰が学ぶことを許されるか」も権力によって規定されます。特定のグループや個人は、研修や重要なプロジェクトへの参加機会を多く与えられる一方、別のグループはそうした機会から排除されることがあります。
言語やコミュニケーションのあり方も権力関係を反映し、再生産します。特定の専門用語や表現を使いこなせるかどうかが、共同体内での発言力や地位に影響することがあります。例えば、経営幹部が使う経営用語を理解し使いこなせる社員は、そうでない社員より「有能」と見なされ、昇進の機会を得やすくなることがあります。
この研究は、組織内の技術者たちの実践を事例として、学習や参加がいかに権力関係に埋め込まれているかを示しています。例えば、技術者がマニュアルを無視して独自のやり方を用いる行為は、単純な慣習ではなく、組織による「効率化」や「マニュアル化」の押しつけへの抵抗としての側面を持ちます。この抵抗行動は、組織側の権力に対する応答として解釈できます。
学習における「排除」の側面も見逃せません。学習に伴う参加は一部のメンバーに限定される場合が多く、それは暗黙の権力構造に基づいています。例えば、非正規雇用者は正社員と同じ業務を行っていても、公式の研修や重要な意思決定プロセスから排除されることがあります。
組織的文脈においては、「情報の貯蔵」も見られます。知識や情報は必ずしも惜しみなく共有されるわけではなく、むしろ戦略的に隠されたり、限られたメンバーの間だけで共有されたりすることがあります。情報や知識の共有・非共有は、権力の表現なのです。
この研究の中では、状況的学習論が権力関係を「外部要因」ではなく、「学習の状況性そのものの本質的要素」として扱う必要性を強調しています。権力関係は共同体の境界線を設定し、何が「正統的」であるかを決定します。学習のプロセスにおいて、誰が参加可能であるかという境界を設定し、これが学習の内容・方法・結果を規定します。
実践共同体は権力や信頼の問題で機能が制限される
実践共同体は知識共有や創造の場として理想的に語られることが多いですが、実際にはさまざまな制約や限界があります。実践共同体の概念とその適用における限界点が分析された研究を取り上げましょう。
この研究では、実践共同体における課題として、先ほどの研究と同じく「権力」の問題を指摘しています[5]。実践共同体内では意味が交渉されるとされていますが、そこには権力関係が伴います。組織内の階層構造や専門家の影響力により、立場の弱いメンバーは意味交渉に積極的に参加できないことがあります。
例えば、管理職と一般社員が同じ実践共同体に属している場合、管理職の意見が優先される傾向があるでしょう。また、長年の経験を持つベテラン社員の意見は、新人の革新的なアイデアよりも重視されるかもしれません。このような権力の不均衡は、新しい知識の創造や多様な視点の統合を妨げることがあります。
「信頼」の問題も課題です。実践共同体はメンバー間の信頼を前提としていますが、組織内の管理スタイルがこの信頼を損なうことがあります。過度に競争的な組織文化や、厳しい業績評価システムは、メンバー間の協力や知識共有を阻害する可能性があります。
信頼関係が乏しい環境では、メンバーは自分の知識や経験を共有することに消極的になります。「知識は力である」と考えると、自分の貴重な知識を他者と共有することは、自分の競争優位性を失うことにつながりかねないからです。このような状況では、実践共同体は表面的な情報交換の場にとどまり、深い知識創造には至りません。
さらに、実践共同体の規模や空間的範囲が拡大すると、新たな課題が生じます。多国籍企業のような大規模で地理的に分散した組織では、メンバー間の直接的な相互作用が制限されます。オンラインツールを使った遠隔地間のコミュニケーションは可能ですが、対面での相互作用に比べると、暗黙知の共有や信頼関係の構築が難しくなります。
「コミュニティ」という概念自体の曖昧さも問題です。個人主義的な社会では、コミュニティの概念が適用しにくいことがあります。また、ビジネス環境の加速化により、信頼構築や長期的な関係性が必要な実践共同体は発展しにくくなっています。現代の組織では、プロジェクトベースの「高速コミュニティ」が形成・解散を繰り返すことが多く、伝統的な実践共同体が育つ余地が限られています。
このように、実践共同体には多くの制約や限界があり、そのポテンシャルを発揮するには、権力や信頼の問題に真摯に向き合い、組織の特性や文化的背景に合わせた適切な運用が必要となるのです。
脚注
[1] Handley, K., Sturdy, A., Fincham, R., and Clark, T. (2006). Within and beyond communities of practice: Making sense of learning through participation, identity and practice. Journal of Management Studies, 43(3), 641-653.
[2] Gongla, P., and Rizzuto, C. R. (2001). Evolving communities of practice: IBM Global Services experience. IBM Systems Journal, 40(4), 842-862.
[3] Swan, J., Scarbrough, H., and Robertson, M. (2002). The construction of “communities of practice” in the management of innovation. Management Learning, 33(4), 477-496.
[4] Contu, A., and Willmott, H. (2003). Re-embedding situatedness: The importance of power relations in learning theory. Organization Science, 14(3), 283-296.
[5] Roberts, J. (2006). Limits to communities of practice. Journal of Management Studies, 43(3), 623-639.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。