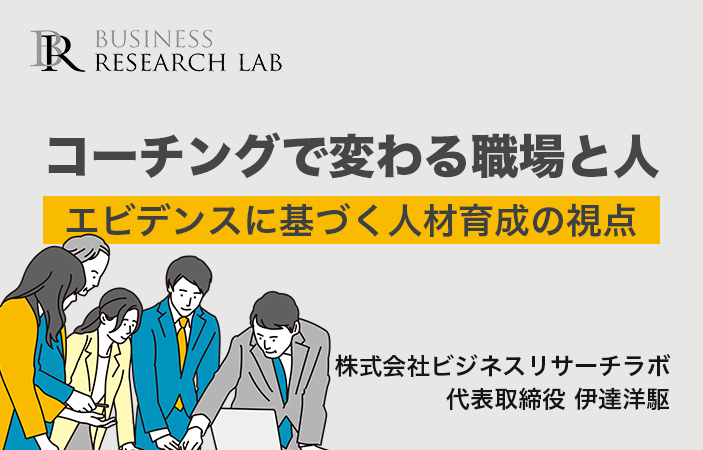2025年8月15日
コーチングで変わる職場と人:エビデンスに基づく人材育成の視点
人材開発の手法としてコーチングが広く活用されるようになりました。コーチングとは、対話を通じて相手の気づきや学びを促し、自律的な成長や問題解決を支援するプロセスです。多くの企業がリーダーシップ開発や業績向上のためにコーチングを導入していますが、その効果に関する社会的な理解は必ずしも十分ではないでしょう。
コーチングには多様な形態があります。外部の専門家によるエグゼクティブ・コーチング、管理職が部下に対して行うマネジャー・コーチング、あるいは組織内の専門スタッフによるインターナル・コーチングなど、様々なアプローチが存在します。しかし、それらが実際にどのような効果をもたらすのか、どのような条件でより良い成果が得られるのかについては、疑問が残る部分もあります。
本コラムでは、コーチングの意義について学術的な視点から掘り下げていきます。職場における成果への効果、組織変化時の目標達成への貢献、評価方法による効果の違い、そしてコーチングプロセスの重要性について、研究結果を基に考察します。これらの理解を深めることで、職場の人材育成や組織開発において価値を持つ方法として、コーチングを捉え直す機会となれば幸いです。
コーチングは職場の成果に効果がある
職場におけるコーチングは効果があるのでしょうか。この素朴な疑問に答えるため、多くの研究が行われてきました。ここでは、複数の研究を総合的に分析したメタ分析の結果から、コーチングの効果について見ていきましょう。
職場でのコーチングの有効性を検証したメタ分析では、17の研究(合計2,267人の対象者)を分析しました[1]。この研究では、コーチングがもたらす成果を3つのカテゴリーに分類しています。1つ目は情動的成果で、自己効力感や自信、満足感、職場でのウェルビーイングなどの心理的要素が含まれます。2つ目はスキルに基づく成果で、リーダーシップスキルや職務スキル、コンピテンシーなどの実務能力が該当します。3つ目は個人レベルの成果で、具体的な職務パフォーマンスや生産性の向上などが含まれます。
分析の結果、コーチングは全ての成果指標において良い効果を示していることが明らかになりました。詳しく見ると、情動的成果では中程度の効果、スキルベース成果では小~中程度の効果、個人レベルの成果では非常に大きな効果となっています。
この結果で目を引くのは、個人レベルの具体的な成果への効果が大きい点です。コーチングが職場でのパフォーマンス向上に直接的に貢献できることを示しています。実際の業績に変化をもたらすことができるのです。
また研究では、コーチングの効果に関わる要因についても調査しています。例えば、360度評価の使用有無による効果の違いを分析したところ、意外にも、フィードバックが使用されない場合の方が効果が大きいという結果が出ました。考えられる理由としては、多方面からのフィードバックによって注意が分散してしまったり、コーチングの焦点がぼやけてしまったりするのかもしれません。
コーチの種類による効果の違いも検証されました。内部コーチと外部コーチを比較すると、内部コーチの方が効果が高い結果になりました。内部コーチは組織の文化や状況をよく理解しているため、より的確な支援ができるのでしょう。一方、外部コーチは組織内の情報が不足していることが効果を減じる一因となっている可能性があります。
コーチングの実施方法については、対面のみで行う場合と、対面と電話を併用する混合型の場合とでは、どちらも同程度の効果があることがわかりました。現在ではオンラインミーティングも普及していますので、必ずしも物理的に同じ場所にいなくてもコーチングの効果は得られると考えられます。
コーチングの回数や期間については、長期間・多数回のコーチングが必ずしも効果を高めるわけではないことが示されました。短期間でも少数回でも、効果的なコーチングは可能であることが分かります。時間やコストの制約がある中でも、適切に設計されたコーチングであれば、十分な効果が期待できます。
コーチングは組織変化時の目標達成を促進する
組織が大きな変化に直面する時期は、リーダーにとって挑戦の時です。新しい戦略の導入、組織再編、合併・買収など、変化の過程では不確実性が高まり、リーダーは通常以上のプレッシャーにさらされます。このような状況下で、コーチングはリーダーにどのような支援を提供できるのでしょうか。
オーストラリアのグローバルエンジニアリング・コンサルティング企業の管理職を対象とした研究では、組織変化期におけるエグゼクティブ・コーチングの効果が検証されました[2]。この研究は約4か月間にわたり、31名の管理職に対して計4回(各90分)の個別コーチングセッションを実施し、その前後での変化を測定しました。
コーチングでは認知行動療法的および解決志向的なアプローチを用い、各セッションで具体的な目標設定、現状分析、行動計画策定を行いました。最終セッション後には、上司や人事担当者を交えたレビューを行い、行動変容を定着させる工夫もなされています。
この研究で測定された主な項目は以下の通りです:目標達成度、解決志向思考、変化対応能力、リーダーシップ自己効力感、レジリエンス(回復力)、そして抑うつや不安、ストレスの軽減です。またコーチングが職場外(家族関係や私生活)にも波及するかも調査されました。
その結果、コーチングによって最も大きく改善したのは目標達成でした。コーチングが具体的な目標の明確化と達成をサポートする上で有効であることを意味します。
次に効果が大きかったのは解決志向思考です。解決志向思考とは、問題の分析だけでなく解決策を生み出す思考スタイルのことで、困難な状況を乗り越えるために有用です。コーチングはこの思考スタイルを促進することが示されました。
変化対応能力、リーダーシップ自己効力感、レジリエンス、抑うつの低下にも一定の効果が認められました。一方で、不安やストレス、職場満足度には統計的に有意な変化はありませんでした。これはベースラインの段階で既に正常範囲内であったためと考えられています。
定量的な数値だけでなく、参加者自身の言葉による評価も行われました。自由記述を分析したところ、リーダーシップ能力の向上(自己認識、明確な思考、キャリアの見通し、コミュニケーションスキルの向上)や個人生活の改善(ワークライフバランス、家族関係の改善、人生の目的の明確化)などが報告されています。
これらの結果は、組織変化期におけるコーチングの多面的な価値を示しています。コーチングは職場における目標達成を強力に支援するだけでなく、変化に対応するための思考や能力を育み、心理的な安定にも寄与します。職場だけでなく私生活にまで良い変化が波及するという点も見逃せません。
組織変化期のコーチングが効果を発揮する理由としては、3つの心理的メカニズムが考えられます。第一に、自己認識の促進です。コーチングを通じて自分自身への理解が深まることで、ストレスの軽減や問題への柔軟な対応力が高まります。第二に、目標志向行動の強化です。明確な目標設定と実践により、自己効力感とウェルビーイングが向上します。第三に、レジリエンスと自己調整能力の向上です。困難な課題にも粘り強く対応できるようになります。
この研究からわかるのは、変化の時期こそコーチングの価値が高まるということです。不確実性やプレッシャーが高まる中で、コーチングは管理職やリーダーに安全な内省と成長の場を提供します。特に解決志向的な思考スタイルを強化することで、問題に囚われるのではなく、解決策を見出す力を養うことができます。
コーチングの効果は自己評価で最も高い
コーチングの効果を測定する際に直面する課題の一つが、「誰がどのように評価するか」という問題です。エグゼクティブ・コーチングのような高度な人材開発手法の場合、その効果をどう捉えるかによって評価が異なることがあります。コーチングの評価方法と、自己評価と他者評価の違いについて考察します。
エグゼクティブ・コーチングの効果に関する研究では、22本の先行研究を収集し、その中から統計的に分析可能な6本の研究を対象にメタ分析が行われました[3]。この分析から見えてきたのは、評価者の視点によって効果の捉え方に差があるという事実です。
具体的には、コーチングを受けた本人による自己評価では、効果量が大きな値を示しました。顕著な改善があったと本人が感じていることを意味します。一方、上司や部下、同僚などの他者による評価(他者評価)では、効果量は中程度にとどまりました。
このギャップはどのように解釈すべきでしょうか。一つの可能性は、コーチングを受けた本人が実際以上に改善を感じている「過大評価」です。自分に投資された時間とエネルギーを正当化するため、あるいはコーチとの良好な関係から、主観的な評価が高くなる場合があります。
しかし別の見方もあります。コーチングの過程で自己認識が深まり、内面的な変化が起きていても、それがすぐに外部から観察可能な行動変容として現れるとは限りません。内面の変化が外部に現れるには時間がかかることもあります。また、他者は変化の全てを観察できる立場にはなく、一部の側面しか評価できないという制約もあります。
詳しい分析として、コーチングの満足度や効果に関する回顧的研究10本のコンテンツ分析も行われました。その結果、コーチングを受けた経営者の満足度は非常に高く、行動変容にも一定の成果があったことが報告されています。また企業レベルでの成果として、生産性や従業員満足度の向上も報告されました。
コーチング評価を適切に行うための要素として、次の点が挙げられています。初めに、評価の目的を明確にする必要があります。総括評価(Summative)はコーチング終了後に全体的な効果を測定するもので、形成評価(Formative)はコーチングの過程で継続的に進捗を評価し調整を行うものです。目的に応じて評価方法を選ぶことが大事です。
続いて、評価基準の選定です。ROIのような定量的指標は分かりやすいものの、エグゼクティブ・コーチングの複雑な価値を十分に捉えられない場合があります。コーチングの具体的な目標に合わせた評価基準を設定することが現実的でしょう。
評価の厳密性も重要です。実務では前後比較が現実的ですが、360度評価を用いる場合、評価者の変動や評価基準の変化が問題となることがあります。例えば、コーチングによって自己認識が高まった結果、自己評価が厳しくなるというパラドックスが生じる場合もあります。
コーチングの種類によっても評価は異なります。「改善型」(問題行動を修正するためのコーチング)と「成長型」(さらなる能力開発を目的とするコーチング)では目的も成果も異なります。特に「改善型」は抵抗感が強く成功しにくい可能性が示唆されており、その点を考慮した評価が必要です。
コーチング内容に関しては、スキルや知識の習得など明確で具体的な目標は達成度が測定しやすいのに対し、個人の価値観や深層的な変容は測定が難しいという特徴があります。目に見える変化だけでなく、内面的な変化もどう評価するかが課題となります。
これらの要素を考慮すると、コーチングの評価はROIのような単一の指標ではなく、プロセスや多様な成果指標を用いた多面的評価が必要であることが分かります。自己評価と他者評価の両方を組み合わせ、短期的効果と長期的効果を区別し、定量的評価と定性的評価を統合することで、より包括的な評価が可能になるでしょう。
コーチングの成果は結果より過程が重要
コーチングが職場の成果に効果があること、組織変化時の目標達成を促進すること、そして効果の評価方法によって捉え方が異なることを見てきました。コーチングの成果を考える際に、「結果」(destination)だけでなく「過程」(journey)にも目を向けることの重要性について探っていきます。
エグゼクティブ・コーチングの成果に関する110本の学術研究を体系的にレビューした調査によると、多くの研究が「コーチングが効くか」(Does it work?)という問いに焦点を当てる一方で、「なぜ・どのようにして効くのか」(How and why it works?)というプロセスへの理解が不足していることが指摘されています[4]。
この調査では、84本の方法論的に厳密な研究を深く分析し、コーチングがもたらす成果とそれに影響を与える要因を包括的に明らかにしています。調査によると、コーチングによってもたらされる主な成果は次の11のカテゴリーに分類されます。
- 自己認識の向上
- リーダーシップ行動の変容
- 業績の向上
- 自己効力感や自信の向上
- 人間関係・コミュニケーションの改善
- ストレスの軽減、レジリエンスの向上
- キャリア満足度の向上
- 組織コミットメントの増大
- 戦略的視野の拡大
- 組織の業績向上への貢献
- コーチ自身の成長
これらの成果は、個人の内面的な変化から対人関係の改善、さらには組織全体への貢献まで、多岐にわたります。ただし、成果が常にポジティブとは限らず、次のような課題や限界も認識されています。
- コーチングへの期待が過度であったり、目的設定が現実的でなかったりする場合、期待された効果が得られないことがある
- コーチングの実施方法や期間が不適切であれば、十分な成果が出ないこともある
- コーチとクライアント間、または組織との関係性が良好でなければ、効果が限定されることがある
ここで重要なのは、これらの成果や課題を「結果」として捉えるのではなく、「どのようなプロセスを経てそうなったのか」という視点です。コーチングの成果に影響を与える要因は、大きく5つのカテゴリーに分けられます。
- 介入の特性(Intervention):コーチングの期間、頻度、具体的手法など
- 組織要因(Organization):組織内のサポート、組織文化、リーダーシップ開発方針
- クライアントの特性(Coachee):クライアントの性格、モチベーション、役職
- コーチの特性(Coach):コーチの経験、背景(心理学的、ビジネス的背景など)、性格
- ステークホルダー間の関係性(Stakeholder Relationships):クライアント・コーチ・スポンサー(組織側)の目的共有、信頼関係
これらの要因がどのように相互作用し、コーチングのプロセスを形作るかを理解することが、コーチングの価値を捉える鍵となります。例えば、同じコーチング技法を用いても、クライアントのモチベーションや準備状態によって成果は異なります。また、組織の文化がコーチングを支持するものであるか否かも、コーチングの効果に影響します。コーチとクライアントの関係性が信頼に基づくものであれば、困難なテーマにも取り組むことができますが、そうでなければ表面的な対話に終始してしまうかもしれません。
脚注
[1] Jones, R. J., Woods, S. A., and Guillaume, Y. R. F. (2015). The effectiveness of workplace coaching: A meta-analysis of learning and performance outcomes from coaching. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 89(2), 249-277.
[2] Grant, A. M. (2014). The efficacy of executive coaching in times of organisational change. Journal of Change Management, 14(2), 258-280.
[3] De Meuse, K. P., Dai, G., and Lee, R. J. (2009). Evaluating the effectiveness of executive coaching: Beyond ROI? Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 2(2), 117-134.
[4] Athanasopoulou, A., and Dopson, S. (2018). A systematic review of executive coaching outcomes: Is it the journey or the destination that matters the most? The Leadership Quarterly, 29(1), 70-88.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。