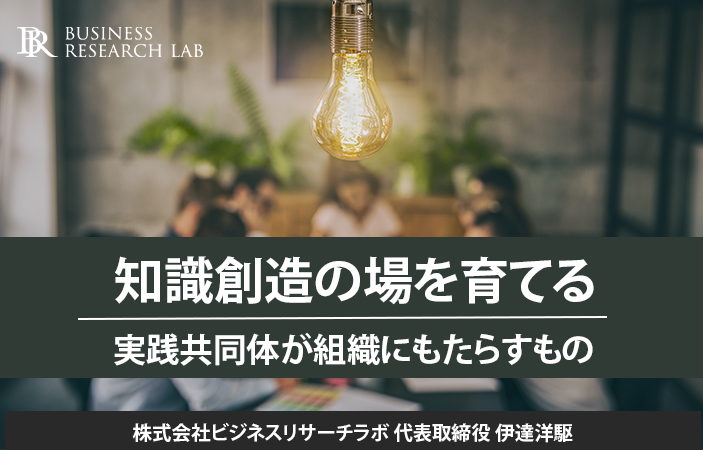2025年8月14日
知識創造の場を育てる:実践共同体が組織にもたらすもの
組織内外での知識の共有と創造は企業の競争力を維持するために欠かせません。この知識共有と創造の場として注目されているのが「実践共同体(Communities of Practice)」です。実践共同体とは、共通の関心や目的を持った人々が集まり、継続的な交流を通じて知識やスキルを深め合うコミュニティのことを指します。例えば、同じ技術分野のエンジニアが集まって問題解決の方法を共有したり、異なる部署の社員が特定のテーマについて意見交換を行ったりする場がこれにあたります。
実践共同体は1990年代から研究が進み、今日では多くの企業が構築・支援するナレッジマネジメントの手法として活用されています。しかし、すべての実践共同体が成功するわけではありません。中には活動が停滞したり、形骸化したりするケースもあります。実践共同体がその本来の機能を発揮し、組織に価値をもたらすためには、どのような要素が必要なのでしょうか。
本コラムでは、実践共同体の効果を高める要因について、様々な研究成果をもとに探っていきます。マネジャーの役割、組織からの適切な支援、メンバー間のつながり、明確な目標設定、そして組織の境界を越えた交流など、実践共同体の成功を支える多様な側面に光を当てていきます。
実践共同体ではマネジャーが組織間の知識共有を促す
実践共同体は、従来、自然発生的で非公式なコミュニティとして捉えられてきました。しかし、近年では組織が意図的に設計し、目的を持って運営する実践共同体も出てきています。特に組織の境界を越えた知識共有を目的とする場合、そこにはマネジャーの存在が重要な意味を持ちます。アイルランドで行われた研究では、4つの意図的に作られた実践共同体を対象に、マネジャーの役割を調査しました[1]。
この研究での実践共同体は約30週間という期限付きで作られ、教育機関や企業、労働組合など多様なバックグラウンドを持つメンバー7~10名程度で構成されていました。各実践共同体には目的があり、フォーマルな構造とリーダーシップを備えていたことが特徴です。
調査の結果、実践共同体のマネジャーは主に3つの領域で重要な働きをしていることが見えてきました。
- 1つ目は「意味の交渉」です。マネジャーはメンバー間の共通理解を促進するために、様々な戦略を用いていました。例えば、メンバーが実際の経験を通じて問題を定義し理解を深める「実践を通じた学習」の機会を設けたり、実践共同体の目的や全体像を把握させることで共通認識を形成したりしていました。また実践共同体の目的を具体的な目標に落とし込み、組織間の意見の不一致や誤解を明確化して再構築する働きも担っていました。
- 2つ目は「信頼と協働の促進」です。実践共同体が30週間という限られた期間で成果を出すためには、メンバー間の信頼関係と協働が不可欠です。マネジャーはメンバーのスキルや知識を迅速に把握してタスクを割り当て、実践共同体の内部での相乗効果を創出していました。また個人の動機づけに焦点を当て、それぞれのメンバーに適した課題を設定することで、全員が主体的に参加できる環境を整えていました。
- 3つ目は「権力関係の管理」です。異なる組織から集まったメンバーの間には、立場や専門性の違いによる権力の不均衡が生じることがあります。マネジャーは会議のルールや行動規範を明確化し、メンバー間の対立を建設的な方向に導く調整役を務めていました。また対面でのミーティングを重視し、個人的な関係性を構築することで、組織間の壁を取り払う努力も行っていたことが分かりました。
この研究が明らかにしたのは、意図的に設計された実践共同体において、マネジャーの存在が実践共同体の理念と矛盾するものではなく、むしろその目的達成を促進するということです。短期間で成果を求められる実践共同体や、組織の境界を越えた知識共有を目指す場合には、マネジャーの役割が重要になります。
マネジャーに求められる資質としては、明確なビジョンを持ち、それをメンバーと共有できる力、メンバー間の交流をファシリテートする能力、そして多様なバックグラウンドを持つメンバーとの信頼関係を構築する能力が挙げられます。これらの能力を持つマネジャーが存在することで、実践共同体は組織間の知識共有という本来の目的を達成しやすくなります。
実践共同体は適度な構造支援で知識交流が活発化
実践共同体の運営において、組織からどの程度の支援や介入が必要なのか、これは多くの企業が直面する課題です。過度の介入は実践共同体の自発性を損なう一方、支援が少なすぎると活動が停滞する恐れもあります。この疑問に答えるための知見を提供しているのが、実践共同体における構造的要素と認識論的要素の相互作用に関する研究です。
この研究では、「WorldSystems」という仮名の組織内にある「e-future」というウェブデザイン部門を事例として取り上げています[2]。ここでは実践共同体の形成と発展を支援するために、いくつかの意図的な介入が行われました。研究者は観察とインタビューを通じて参加者の行動やコミュニティ内の相互作用を分析しました。
調査の結果、組織による介入には大きく2種類あることが明らかになりました。1つ目は「シーディング構造」と呼ばれる非強制的な支援です。これは自由な職場環境(ビリヤード台や自由な会議スペース、芸術的な展示物など)の提供や、オンラインコミュニケーションツールの導入、共有の創造的プロジェクトの設置などが含まれます。これらの支援は参加者が自発的に交流を深め、協力関係を築くための基盤を形成しました。
対照的なのが「コントロール構造」と呼ばれる強制的な介入です。個人の成果を厳格に評価する「ベンチ制度」や、「ベストプラクティス」の強制適用、短期間での大量の新規メンバー投入などがこれにあたります。これらの強制的な介入は、参加者の自発性を抑制し、コミュニティの創造的な交流を妨げる結果となりました。長期的には実践共同体の活力を奪ってしまったのです。
この研究が提案するのは、実践共同体が健全に発展するための2つのパラメータです。1つ目は「構造的パラメータ」です。実践共同体が成長するためには、一定の構造的な支援(シーディング構造)が必要ですが、過度なコントロール構造は逆効果になります。組織は参加者が自由に交流し、新たなアイデアを共有・生成できる環境を整備することが望ましいのです。
2つ目は「認識論的パラメータ」です。実践共同体内での知識交流(認識論的交流)が内向きになりすぎると、外部環境から孤立してしまい、活動が組織全体から理解されなくなる恐れがあります。そのため、外部環境との交流バランスを維持することが重要です。
この研究の意義は、実践共同体への適切な支援のあり方を明確に示した点にあります。組織が実践共同体を効果的に支援するには、シーディング構造をうまく導入し、コントロール構造は最小限に抑えることが肝心です。さらに、実践共同体が内部の交流だけに集中しすぎないよう、外部との健全なコミュニケーションを促進することも大切だと分かりました。
実践共同体の効果は仕事との関連性やつながりで高まる
実践共同体が組織にとって本当に価値をもたらすのか、またどのような条件でその効果が高まるのかについて、米国の大手損害保険会社State Farm Insurance Companiesを舞台にした興味深い実証研究があります。この研究では18の実践共同体に参加する579名を対象に調査が行われ、204名から回答を得ました[3]。
調査では実践共同体の全体的有効性、メンバー自身の仕事への影響、メンバーのコミットメント、メンバー間の信頼、コミュニティへのつながり、リーダーシップの質、コミュニティへの満足度といった多角的な側面から評価が行われました。分析の結果、実践共同体の効果を高める要素がいくつか浮かび上がってきました。
第一に、メンバー自身の仕事への影響が、実践共同体の全体的な効果と強く関連していることが分かりました。実践共同体での活動が参加者の日常業務を直接的に改善するほど、その共同体は組織全体にとっても有効だと評価されるのです。
この「仕事への影響」を左右する要因としては、実践共同体のリーダーシップの質、メンバー間のつながり、そしてメンバーのコミットメントが重要でした。優れたリーダーシップのもとで、メンバー同士が密接につながり、高いコミットメントを持って参加している実践共同体ほど、メンバーの仕事に対してポジティブな影響を与えていました。
第二に、メンバー間のつながりの強さが、実践共同体の満足度に最も強く影響していることも明らかになりました。メンバーが互いに親密な関係を築き、活発に交流することで、参加者は実践共同体での経験に満足感を得ていました。
実践共同体はメンバーの仕事の質を高める有効な手法であることが確認されました。ただし、その効果を最大化するためには、仕事に直接関連する活動を重視することが重要です。抽象的な議論だけでなく、日常業務の具体的な課題解決に結びつく活動を取り入れることで、実践共同体の価値が高まります。
また、メンバー同士のつながりやアイデンティティを高める取り組みも欠かせません。交流機会の創出や、メンバー間の相互理解を深める活動が、実践共同体の満足度と効果を向上させるのです。
実践共同体は明確な目標と運営支援で成功する
実践共同体が成功する要因と失敗する要因について、欧米企業における57の事例を分析した包括的な研究があります。この調査は、Siemens、Oracle、IBM、Daimler、World Bank、国連、CERNなど、様々な業種・規模の組織を対象に実施されました。研究者たちは質問紙調査とインタビューを通じて、成功した実践共同体(45件)と失敗した実践共同体(12件)を比較分析しました[4]。
この研究が明らかにしたのは、成功する実践共同体に共通する10のガバナンス・メカニズム(統治の仕組み)です。これらは「実践共同体統治の10の戒律」と名付けられました。
- 1つ目は「戦略的目標に忠実であること」です。明確で測定可能な目標を設定することで、メンバーの積極的な参加が促されます。漠然とした目標ではなく、具体的な成果指標を持つことが重要です。
- 2つ目は「目標を副項目に分類すること」です。大きな目標をサブテーマに分け、活動を明確化することで知識共有が促進されます。この細分化によって、メンバーは自分が貢献できる領域を見つけやすくなります。
- 3つ目は「ガバナンス委員会を組織すること」です。実践共同体の支援者(スポンサー)とリーダーが定期的に会合し、活動が組織の戦略に沿っているかを確認します。この連携が組織全体との整合性を保つ鍵となります。
- 4つ目は「スポンサーとリーダーがベストプラクティスの管理者となること」です。時間節約、品質向上、コスト削減などのパフォーマンス基準を設定し、定期的に評価することが求められます。
- 5つ目は「外部専門家を定期的に招くこと」です。外部の知識を取り入れることで、既存の実践を改善・革新することができます。外部視点は新たな発想をもたらす触媒となります。
- 6つ目は「他の組織内外のネットワークへのアクセスを促進すること」です。内外のベンチマーキングを行い、実践の質を向上させることが大切です。この開放性が実践共同体の視野を広げます。
- 7つ目は「リーダーが推進者として積極的に機能すること」です。実践共同体を細分化して明確に整理し、メンバーが知識にアクセスしやすくする工夫が求められます。
- 8つ目は「階層的圧力を克服すること」です。実践共同体を自由で階層が存在しない安全な学習空間として維持することが肝心です。組織の肩書きや立場に縛られない対等な関係性が創造性を引き出します。
- 9つ目は「測定可能な成果をスポンサーに報告すること」です。実践共同体活動の成果を定量化し、経営層の継続的支援を得ることが重要です。目に見える成果が次の活動を支えます。
- 10番目は「成果を具体的に示してメンバーの参加意欲を高めること」です。成功事例をメンバーに共有し、活動の有効性を明確にすることで、さらなる参加を促します。
一方、実践共同体が失敗する主な原因としては5つの要素が特定されました。
- 初めに「中核メンバーの欠如」です。活動を牽引する中心的なメンバーが存在しないと、持続性が低下します。
- 続いて「メンバー間の1対1の交流が少ないこと」です。交流不足によりメンバーの関与が薄れてしまいます。
- 3つ目は「コンピテンスの硬直性」です。メンバーが他者の実践を受け入れず、自身の専門性に固執すると発展が阻害されます。
- 4つ目は「実践共同体への帰属意識の低さ」です。メンバーが活動に意味を見いだせないと、参加意欲が低下します。
- 最後に「実践の非可視性」です。実践を具体的に示せないと、共有や学習が難しくなります。
これらの知見をもとに、研究者たちは成功する実践共同体の運営モデルとして「操縦輪(Steering wheel)」モデルを提案しています。このモデルは明確な目標設定、スポンサーによる支援、優れたリーダーシップ、境界を越えた情報交換、階層のない安全な環境、活動成果の測定という6つの要素から成ります。
この研究が示唆するのは、実践共同体が成功するには自発性と明確なガバナンスのバランスが必要だということです。完全に自由放任でも、過度に管理されたものでもなく、適切な支援と明確な方向性を持った実践共同体が効果的だということが分かりました。特にスポンサー(通常は経営層)とリーダーの緊密な連携、そして階層を超えた自由な知識交流の創出が、成功の鍵を握っています。
実践共同体は境界を越えた交流で社会的学習を促す
実践共同体に関する研究の第一人者である、ウェンガーによる研究では、実践共同体が「社会的学習システム」としてどのように機能するかが理論的に検討されています[5]。ウェンガーは、組織の成功は自らを社会的学習システムとしてデザインし、そうしたシステムへの参加を促進する能力に依存すると論じました。ここでいう「社会的学習システム」とは、人々が共通の関心や目的のもとで交流を通じて学びを深める仕組みのことです。
「知る」という行為は個人の頭の中だけで起きるのではなく、社会的参加を通じて生まれるものです。学習とは共同体への参加を通じて、社会的・歴史的に定義された能力を獲得するプロセスなのです。
この社会的学習への参加には3つの形態があります。1つ目は「関与(Engagement)」で、直接の相互作用や共同活動に参加することを指します。2つ目は「想像(Imagination)」で、自分自身やコミュニティをイメージし、その一員であると認識することです。3つ目は「整合(Alignment)」で、活動や目的を調整し、共通の目標に向けて活動することです。これらが適切に組み合わさることで、効果的な社会的学習が生まれます。
実践共同体は、この社会的学習システムの「構成要素」として位置づけられます。実践共同体は個人の学習を支えるだけでなく、社会的なアイデンティティ形成や組織の知識蓄積も支える重要な場です。
ウェンガーは実践共同体の運営には6つの要素が必要だと提案しています。「イベント」は共同体の交流や共有を促す集会です。「リーダーシップ」は共同体をまとめ、活動を調整する役割を担います。「つながり」はコミュニティ内部での交流を活発化する仕組みです。「メンバーシップ」は参加者間の信頼関係を形成し、参加意欲を高める仕組みです。「学習プロジェクト」は共同体が集中的に取り組むべきテーマです。そして「成果物」は共同体が共有・蓄積する知識や文書などのリソースです。
この研究で印象的なのは、共同体の「境界」に対する新たな視点です。一般的に「境界」は障壁や分断のイメージがありますが、ウェンガーは境界こそが重要な学習の源泉だと指摘します。境界とは、ある実践共同体が他の共同体や組織外と接する領域のことです。
境界には3つの重要な側面があります。まず「境界は学習の機会を生む」ということです。異なるコミュニティ間の交流は新たな知識や視点を提供し、イノベーションを促します。次に「境界オブジェクト」の存在です。これは複数のコミュニティを結びつける共通の道具や概念のことで、例えば共通のプロジェクト、専門用語、または共有された問題意識などが該当します。最後に「境界を横断する活動」の重要性です。異なるコミュニティの交流が深い学習をもたらします。
実践共同体への参加を通じて人々は社会的なアイデンティティを形成します。これが組織内での知識共有の動機づけとなります。アイデンティティには3つの特徴があります。「アイデンティティの多面性」は、人が複数の共同体に同時に所属し、異なるアイデンティティを持つことを指します。「アイデンティティの軌跡」は、個人の学習経路やキャリア形成が共同体参加によって形づくられることです。「アイデンティティのフラクタル構造」は、大小の共同体が入れ子構造を形成し、多層的な帰属意識を作り出すことを表しています。
ウェンガーは結論として、非公式な学習システムである実践共同体は、正式な組織制度では達成できない柔軟な学習を促進すると強調します。組織はインフォーマルな交流を促す環境を整えることで競争力を維持できます。
脚注
[1] Garavan, T. N., Carbery, R., and Murphy, E. (2007). Managing intentionally created communities of practice for knowledge sourcing across organisational boundaries: Insights on the role of the CoP manager. The Learning Organization, 14(1), 34-49.
[2] Thompson, M. (2005). Structural and epistemic parameters in communities of practice. Organization Science, 16(2), 151-164.
[3] Hemmasi, M., and Csanda, C. M. (2009). The effectiveness of communities of practice: An empirical study. Journal of Managerial Issues, 21(2), 262-279.
[4] Probst, G., and Borzillo, S. (2008). Why communities of practice succeed and why they fail. European Management Journal, 26(5), 335?347.
[5] Wenger, E. (2000). Communities of practice and social learning systems. Organization, 7(2), 225-246.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。