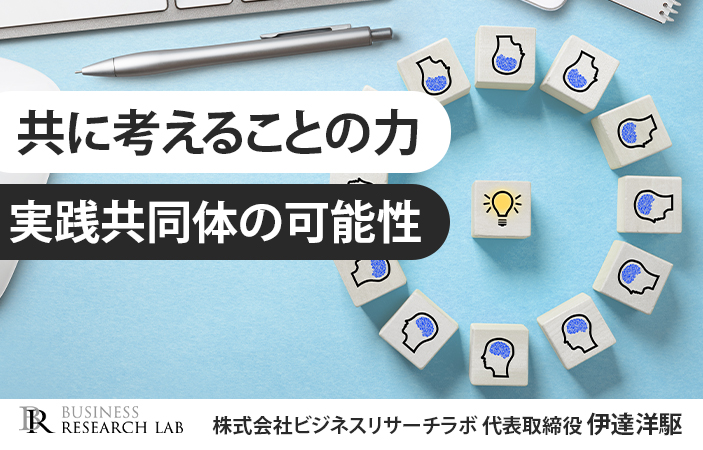2025年8月12日
共に考えることの力:実践共同体の可能性
私たちは仕事を通じて多くのことを学びます。しかし、その学びはどのようにして生まれるのでしょうか。教科書や研修だけで十分でしょうか。現実には、職場での日々のやりとりや同僚との交流から得られる知識が、私たちの成長に寄与しています。このような学習プロセスが起こる場を「実践共同体」と呼びます。実践共同体とは、同じ関心や課題を持つ人々が集まり、日常的な交流を通じて学び合い、知識や経験を共有する場のことです。
職場における実践共同体は、組織内の知識創造や問題解決に有用な存在です。例えば、新入社員が先輩の働き方を観察して学んだり、休憩時間に同僚と業務上の悩みを相談し合ったりする場面があります。このような何気ない交流が、組織にとって貴重な学びの機会を生み出しています。
しかし、実践共同体の価値は見えにくく、その仕組みも十分に普及しているとは言えません。本コラムでは、実践共同体がどのように形成され、どのような効果をもたらすのかについて考えていきます。職場における学びや知識共有を促進するためにも、実践共同体について理解することは意義深いことでしょう。
日々の実務を通じ状況的に学習する
職場における学びといえば、研修やマニュアルなどの公式な教育を思い浮かべるかもしれません。しかし実際には、日常の業務を通じて得られる学びの方が、深く豊かなものとなることがあります[1]。
この現象を説明するのが「状況的学習論」です。この理論によれば、学びとは個人の頭の中だけで起こる認知的なプロセスではなく、特定の文脈や状況の中で社会的に生じるものとされます。私たちは他者との関わりの中で、実際の仕事を通じて学んでいるのです。
例えば、建設現場の管理者は、どのようにして必要な知識や技能を身につけていくのでしょうか。一つの調査では、イタリアの建設業界において、現場管理者の学習過程を観察しました。その結果、彼らはマニュアルや正式な訓練ではなく、実際の現場での問題対応や、同僚・部下との日常的なやりとりを通じて実務的な知識を習得していたことが分かりました。
このような学習は「状況的カリキュラム」と呼ばれることもあります。状況的カリキュラムとは、事前に設計されたものではなく、日々の実践から自然に生まれる学習内容や過程のことです。例えば、労働者との関係構築の方法や、予期せぬトラブルへの対処法などは、実際の状況の中でしか学べないものです。
状況的カリキュラムにはいくつかの特徴があります。
- 学習の内容は体系的に整理されたものではなく、その時々の状況や問題に応じて非線形的に展開します。
- 多くの知識は言葉で明確に説明されるものではなく、現場での観察や実践の繰り返しを通じて暗黙のうちに習得されます。
- 学びは職場の社会的関係の中で形作られます。上司と部下の関係や、同僚との非公式なネットワークが、何をどのように学ぶかに関わってきます。例えば、信頼関係のある先輩からは多くのことを学べますが、そうでない場合は学びが限定的になることもあります。
このような状況的な学習を理解するためには、実践共同体という概念が助けになります。実践共同体とは、同じ実務や関心を共有する人々の集まりであり、その中で人々は互いに学び合い、実践的な知識を深めていきます。新人はまず周辺的な参加から始めて、徐々に中心的なメンバーへと進んでいきます。この過程は「正統的周辺参加」と呼ばれます。
状況的学習の視点から見ると、職場での学びは単なる知識の獲得ではなく、実践共同体への参加度合いが深まっていくプロセスと言えます。人々は日々の業務を通じて、その分野の「やり方」だけでなく、考え方や価値観も習得し、その分野の専門家としてのアイデンティティを形成していきます。
このような学びの形は、従来の教育訓練とは異なります。教室での講義や形式的な訓練だけでは、実務に必要な暗黙知や文脈に依存した知識を十分に伝えることはできません。それらは、実際の状況の中でこそ習得されるものなのです。
実践共同体が社会関係資本を生み組織成果を高める
実践共同体は学習の場にとどまらず、組織にとって様々な価値をもたらします。その価値を理解する上で役立つのが「社会関係資本」という概念です。社会関係資本とは、人と人とのつながりや関係性から生まれる資源のことを指します。実践共同体はこの社会関係資本を形成し、それが組織の成果につながります[2]。
社会関係資本は主に3つの側面から成り立っています。一つ目は「構造的側面」で、これは人々の間のネットワークや情報が流れる経路に関するものです。二つ目は「関係的側面」で、信頼や互恵性など人間関係の質に関わります。三つ目は「認知的側面」で、共有される言語や共通理解など、コミュニケーションを促進する基盤を指します。
実践共同体はこれら3つの側面を強化することで、組織にとっての価値を創出します。例えば、金融機関、製造業、製薬会社、ソフトウェア企業など多様な分野の企業を対象とした調査では、実践共同体が組織に次のような貢献をしていることが判明しました。
- 新入社員の学習期間の短縮です。新入社員は実践共同体を通じて、経験豊かな先輩や必要な情報源に素早くアクセスできるようになります。わからないことがあっても、誰に聞けば良いのかがわかり、組織文化への順応や業務の習得が早まります。
- 顧客ニーズや問い合わせへの迅速な対応が挙げられます。実践共同体のメンバーは、過去の経験や対応事例を共有することで、顧客からの質問や要望に素早く対応できるようになります。
- 重複作業の削減も実践共同体の恩恵です。既に誰かが解決した問題を、別のメンバーが一から取り組むという無駄を防ぎます。実践共同体では、過去の成功事例や失敗事例が共有されるため、「車輪の再発明」を避けることができるのです。
- 新製品やサービスのアイデア創出も実践共同体の価値です。メンバー間の交流は、組織の壁を越えた対話を生み出します。互いの専門知識や経験を組み合わせることで、良質なアイデアが誕生します。
これらの価値は、社会関係資本の3つの側面と密接に関わっています。例えば、実践共同体内のネットワーク(構造的側面)によって、必要な知識や情報へのアクセスが容易になります。メンバー間の信頼関係(関係的側面)は、率直な意見交換や協力を促進します。そして、共通の専門用語や理解の枠組み(認知的側面)は、効率的なコミュニケーションを可能にします。
実践共同体は社会関係資本を生み出すことで、組織の様々な面でポジティブな結果をもたらします。それは知識の共有にとどまらず、新しい知識の創造や問題解決能力の向上、さらには組織の革新につながります。
共に考えることで暗黙知が共有される
実践共同体の魅力的な側面の一つが、「暗黙知」の共有を可能にすることです。暗黙知とは、言葉や文書では表現しにくい知識のことです。例えば、自転車の乗り方や料理の味加減など、言葉での説明が難しいけれども、経験を通じて身につける知識がこれにあたります。
職場においても、マニュアルには書かれていない「コツ」や「勘所」が存在します。顧客対応の微妙なニュアンスや、複雑な機械の調整方法など、長年の経験から培われる知恵は、簡単に言語化できないものです。このような暗黙知をどのように共有し、伝えていくかは、組織にとって課題です。
実践共同体における暗黙知の共有において鍵となるのが、「共に考えること(thinking together)」というプロセスです[3]。これは同じ場所にいることや情報交換をすることではなく、共通の課題に対して心を合わせて取り組むことを意味します。
この「共に考えること」の概念を理解するために、「内在化(indwelling)」という考え方が役立ちます。内在化とは、ある知識分野と自分自身が融合し、その分野が自己の一部になることを指します。例えば、熟練した職人が道具を使うとき、その道具はもはや外部の物体ではなく、自分の身体の延長のように感じられます。同様に、エキスパートは自分の専門分野に内在化し、その領域の知識や経験が自分の一部となっています。
「共に考えること」は、この内在化の状態を他者と共有するプロセスです。同じ課題に取り組む人々が、それぞれの内在化した知識や経験を持ち寄り、共同で問題解決に取り組むことで、言葉だけでは伝えきれない暗黙知が間接的に共有されるのです。
この現象を示す事例として、ある病院での敗血症治療チームの例があります。敗血症は早期発見と迅速な処置が不可欠な深刻な疾患です。この病院では、敗血症専門のチームが病院内の様々な部署と連携していました。チームは情報提供するだけでなく、現場でのメンタリングやトレーニングを通じて、敗血症の微妙な兆候の見分け方や、緊急時の対応手順を共有していました。
このチームの興味深い点は、「共に考える」環境を自然に作り出していたことです。メンバーは現場の医師や看護師と一緒に患者を診察し、リアルタイムで判断や対応について話し合いました。この過程を通じて、マニュアルには書かれていない微妙な兆候の読み取り方や、患者の状態に応じた柔軟な対応方法など、暗黙知が共有されていきました。
対照的に、同じ病院内で構築された認知症ケアのオンラインコミュニティは、あまり成功しませんでした。このコミュニティはトップダウンで設計され、主に情報提供の場として機能していました。しかし、メンバー間の活発な交流や「共に考える」プロセスが欠けていたため、表面的な情報交換にとどまり、暗黙知の共有には至りませんでした。
この対比は、実践共同体の成功には「共に考えること」が必要であることを示しています。同じ関心を持つ人々を集めて情報共有の場を設けるだけでは不十分です。実践共同体が活性化するためには、メンバーが実際の問題解決に共に取り組み、その過程で暗黙知を自然に共有できる環境が求められます。
「共に考えること」を促進するためには、いくつかの条件があります。
- メンバーが共通の課題や関心事を持っていることが大切です。
- その課題に対する継続的な関与が必要です。一度きりの交流ではなく、時間をかけて共に考え続けることで、暗黙知の共有が進みます。
- メンバー間の信頼関係も重要です。安心して自分の考えや疑問を表現できる環境があってこそ、深い対話が生まれます。
実践共同体は分野で異なり、医療では効果は未実証
実践共同体は様々な業界や分野で形成されていますが、その特徴や機能は分野によって異なります。特にビジネス領域と医療領域では、実践共同体の捉え方や活用方法に違いが見られます。また、医療領域においては、実践共同体の効果に関する実証的なエビデンスがまだ十分に確立されていないという現状もあります[4]。
ビジネス領域では、実践共同体の概念は1990年代半ばから広がり始めました。当初は徒弟制度的な教育を中心としていましたが、次第に非公式な学習グループや学際的チーム、バーチャルコミュニティなど多様な形態へと発展していきました。ビジネス領域の実践共同体の特徴として、メンバー間の社会的交流に時間と資源を投資する傾向があります。
一方、医療領域では実践共同体という用語が普及し始めたのは2000年代初頭からであり、その捉え方もビジネス領域とは異なります。医療領域では、社会的学習というよりも、専門職の教育や継続的な能力開発のためのマネジメントツールとして実践共同体が位置づけられています。
医療領域の実践共同体は、ビジネス領域と比べて職場や業務中心の交流に焦点があり、個人的な社会活動は比較的少ない傾向にあります。これは医療現場の特性、例えば緊急性の高い業務や厳格な専門職の境界、時間的制約などが影響していると考えられます。
両分野の実践共同体に共通する特徴としては、次の4つが挙げられます。
- 初めに「社会的交流」で、これは対面またはオンラインを通じた交流を指します。
- 続いて「知識共有」で、関連情報を共有することです。
- 「知識創造」として、新しい方法や問題解決法を開発することがあります。
- 最後に「アイデンティティ構築」があり、これは専門的なアイデンティティを形成していくプロセスです。
成熟した実践共同体ではこれら4つの特徴がすべて見られますが、初期段階のグループでは社会的交流や知識共有が中心で、知識創造やアイデンティティ構築はまだ弱いかもしれません。例えば、新設された病院の看護師グループは、最初は勤務スケジュールや基本的なケア方法の情報交換が中心ですが、時間の経過とともに独自のケア方法を開発したり、その病院の看護師としての独自の文化やアイデンティティを形成していったりします。
両分野において、実践共同体の成功にはファシリテーターの存在が重要とされています。しかし、そのファシリテーターの役割や責任については明確な定義がなく、グループの成功や失敗がファシリテーターの能力や関与の度合いに左右されることも指摘されています。
医療領域における実践共同体の効果については、現時点で定量的な研究が不足しています。医療領域での実践共同体が本当に効果的であるかを実証した研究はまだ少ないのが現状です。この背景には、医療現場の複雑性や、多様な要因が絡み合うことで純粋な効果測定が難しいという事情があります。
実践共同体が感情労働の苦痛を集団で緩和
サービス産業では、従業員が自分の感情を管理しながら顧客に対応する「感情労働」が重要な役割を担っています。例えば、コールセンターのオペレーターが怒りを抑えて丁寧に対応したり、看護師が患者に対して思いやりを示したりすることが求められます。このような感情労働は、従業員に精神的負担をかけることがあります。ここで注目したいのは、実践共同体が「対処の共同体」として機能し、この感情労働の苦痛を和らげる働きをしているという点です[5]。
「対処の共同体」とは、感情労働による心理的な負担や顧客からの攻撃的態度などに対して、同僚同士が相互にサポートし合う非公式なグループのことです。職場での感情的なストレスを共有し、共に乗り越えていくための場として機能します。
この現象を理解するために、オーストラリアと米国の複数のコールセンターで行われた調査を見てみましょう。これらのコールセンターでは、オペレーターたちは日常的に顧客の怒りや不満に直面していました。企業側は「顧客満足」を最優先し、どのような状況でも穏やかで共感的な対応を従業員に求めます。しかし、一方で彼ら彼女らが経験する感情的な負担については十分な配慮がなされていないことが多いのです。
このような状況の中で、オペレーターたちは自然と「対処の共同体」を形成していました。例えば、休憩室での会話や、シフト交代時の短い立ち話、時には勤務後の集まりなど、様々な機会を通じて感情的なサポートを互いに提供し合っていました。
このような「対処の共同体」は、次のような方法で感情労働の苦痛を緩和しています。
- 感情のガス抜きの場を提供します。顧客対応中は常に感情をコントロールすることが求められますが、同僚との間では本音を吐露することができます。怒りや挫折感、時には涙を流すこともあるでしょう。このような感情表現が許される場があることで、精神的な圧力が軽減されます。
- 共感と理解を得られる場となります。同じような経験をしている同僚だからこそ、説明しなくても理解してもらえることがあります。「あの状況では誰でも同じように感じるよ」という共感は、自分だけが弱いわけではないという安心感をもたらします。
- 具体的な対処法や助言が共有される場でもあります。例えば、「あのようなクレームには、こう対応するとうまくいった」といった実践的なアドバイスが交換されます。これは感情的サポートを超えて、実務的なスキルアップにもつながります。
- ユーモアを通じたストレス解消の場ともなります。困難な状況を笑い話に変えることで、感情的な負担を軽減する効果があります。例えば、理不尽なクレームに対して、後で仲間内で冗談めかして再現することで、ストレスを発散することができます。
このような「対処の共同体」は、公式な組織構造の中では見えにくい存在かもしれませんが、従業員のメンタルヘルスや仕事の継続において重要です。しかし、管理者側がこうした「対処の共同体」の存在やその価値を十分に認識していないこともあります。むしろ、休憩時間の雑談や業務外の交流を生産性を下げるものとして否定的に捉えるケースもあります。
これは「対処の共同体」が単純な息抜きの場ではなく、感情労働を持続可能なものにするための要素であることを示しています。実践共同体としての「対処の共同体」は、表面的には見えにくいけれども、サービス業の質と持続性を支えます。
脚注
[1] Gherardi, S., Nicolini, D., and Odella, F. (1998). Toward a social understanding of how people learn in organizations: The notion of situated curriculum. Management Learning, 29(3), 273-297.
[2] Lesser, E. L., and Storck, J. (2001). Communities of practice and organizational performance. IBM Systems Journal, 40(4), 831-841.
[3] Pyrko, I., Dorfler, V., and Eden, C. (2017). Thinking together: What makes communities of practice work? Human Relations, 70(4), 389-409.
[4] Li, L. C., Grimshaw, J. M., Nielsen, C., Judd, M., Coyte, P. C., and Graham, I. D. (2009). Use of communities of practice in business and health care sectors: A systematic review. Implementation Science, 4(1), 27.
[5] Korczynski, M. (2003). Communities of coping: Collective emotional labour in service work. Organization, 10(1), 55-79.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。