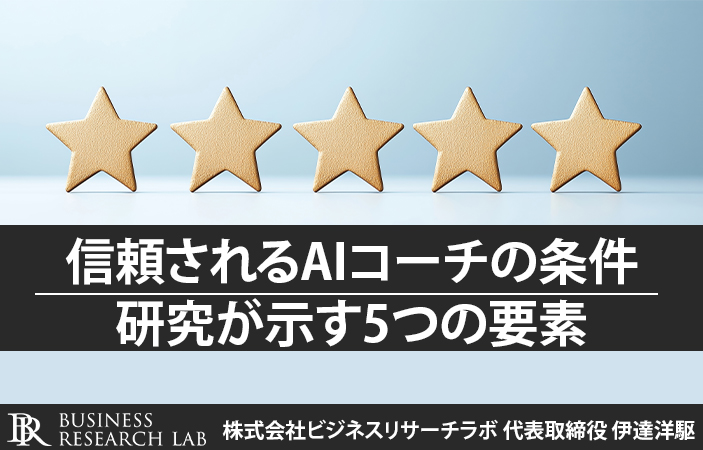2025年8月7日
信頼されるAIコーチの条件:研究が示す5つの要素
デジタルトランスフォーメーションの波は、コーチングの世界にも変化をもたらしています。AI技術の急速な進化により、かつては想像できなかった形で個人の成長や能力開発が支援されるようになりました。教育現場からビジネス環境、健康管理まで、AIは従来の人間による支援を拡張し、新たな可能性を切り開いています。この潮流の中で注目を集めているのが「AIコーチング」というアプローチです。
伝統的なコーチングの世界では、経験豊かな人間のコーチが一対一で対話しながら、目標設定から実行、振り返りまでの過程を支えてきました。しかし、その恩恵を受けられるのは、時間的・経済的余裕のある一部の人々に限られていた現実もあります。AIコーチングの登場は、この制約を打ち破り、質の高い個別指導を民主化し得ます。
しかし、AIコーチングの価値を引き出すためには、最新技術を導入するだけでは不十分です。効果的なAIコーチングを実現するために必要な条件とは何でしょうか。本コラムでは、この問いについて研究成果に基づいて検討します。
インターフェース設計の最適化、AIの人間性の適切な表現、データ駆動型の介入戦略、視覚情報の効果的活用、そして双方向音声コミュニケーションの可能性。これらの要素がAIコーチングの効果を左右する条件となります。本コラムで紹介する知見は、AIコーチングを実践・導入しようとする組織や個人にとって参考情報となるでしょう。
AIコーチングは記述型が信頼感を高める
AIコーチングを設計する際、最初に考慮すべき要素の一つが「対話方式」です。AIとのコミュニケーション方法は大きく分けて、選択肢から選ぶ「クリック型」と自由に文章を入力する「記述型」の二つがあります。このどちらを採用するかによって、AIコーチングの効果は変わることが分かってきました。
ドイツで行われた研究では、試験不安を抱える学生を対象に、クリック型と記述型の二種類のコーチングチャットボットを比較する実験が行われました[1]。この実験では、コーチングの効果を決める要素である「作業同盟」(コーチとクライアントの間で形成される協力関係)に焦点を当てています。
作業同盟は、「ゴール」(目標の合意)、「タスク」(目標達成のための作業の合意)、「ボンド」(信頼や尊重を含む人間関係的なつながり)の三つの要素から成ります。実験の結果、記述型チャットボットはユーザーとの間に強い「ボンド」(信頼感・親密さ)を形成する点で優れていることが明らかになりました。
なぜ記述型の方が信頼感を高められるのでしょうか。その理由は、自由に文章を書くことでユーザーがより深い自己開示や自己反省を行う機会が増えるからです。自分の考えや感情を言語化するプロセスそのものが、問題への理解を深め、AIコーチとの心理的な距離を縮める効果をもたらします。
一方で、クリック型チャットボットは「タスク合意」の面で高い評価を得ました。選択肢が明確に示されることで、ユーザーは何をすべきかが分かりやすく、目標達成のための具体的なステップを理解しやすくなります。また、技術的な面では、クリック型の方がトラブルが少なく、初心者でも利用しやすいという利点があります。
記述型のチャットボットには課題もあります。自然言語処理技術の限界から、ユーザーの入力を正確に理解できないことがあり、そのような場合はユーザー体験が損なわれる可能性があります。実験でも、記述型チャットボットでは技術的なトラブル(AIの学習不足による理解ミス)が報告されました。
これらの知見から、理想的なAIコーチングシステムは「記述型」と「クリック型」の両方の利点を組み合わせた「ハイブリッド型」であることが示唆されています。例えば、コーチングの初期段階では選択肢を提示して方向性を明確にし、徐々に自由記述の要素を増やしていくことで、ユーザーの自己反省を深めながらも、分かりやすさと使いやすさを両立させることができるでしょう。
人間らしさの調整が重要である
AIコーチングの効果を高めるための二つ目の条件は、AIの「人間らしさ」をうまく調整することです。AIチャットボットをどの程度人間に似せるべきか、または人間との違いを明確にすべきか、という問題は、AIコーチングの設計において重要です。
組織的なコーチングにAIを適用するための設計フレームワーク(DAICフレームワーク)を提案した研究によれば、AIコーチの人間らしさには「適切なバランス」が必要であることが明らかになっています[2]。あまりにも人間に近すぎるAIは逆効果となる可能性があるのです。
この現象は「不気味の谷(Uncanny Valley)」と呼ばれています。人間に非常に似ているけれども、完全には人間と同じではないAIに対して、人々は不快感や違和感を覚えることがあります。例えば、あまりにも人間のような表情や言葉遣いをするAIチャットボットは、かえってユーザーに不信感や抵抗感を与えます。
DAICフレームワークでは、AIコーチの設計において次の5つの原則を考慮することを推奨しています。
- まず、「人間らしさの適切なレベルの設定」です。AIが人間のように振る舞いすぎない程度に設計し、むしろAIならではの特性を活かします。例えば、感情表現は控えめにしつつも、データ処理の速さや一貫性といったAIの長所を前面に出すことが望ましいでしょう。
- 次に「能力期待の管理」です。AIコーチには限界があることを明確にし、ユーザーの期待を現実的なレベルに保つことが重要です。例えば、AIが対応できない質問や状況があることを事前に説明しておくことで、ユーザーの失望を防ぐことができます。
- 三つ目は「挙動の変化に対する透明性」です。AIが学習によって変化することをユーザーに伝え、その変化のプロセスを透明化することで信頼感を高めることができます。
- 四つ目は「信頼性と失敗の管理」です。AIが間違えたり失敗したりした場合には、誠実に対応し、継続的な改善を行うことが必要です。完璧を装うのではなく、限界を認めた上で改善していく姿勢がユーザーの信頼を得ることにつながります。
- 最後に「AIであることの開示」です。AIが人間ではないことを明確に伝えることで、ユーザーの期待を管理し、信頼関係を構築することができます。「私はAIアシスタントです」といった自己紹介を最初に行うことで、ユーザーの心理的な準備を整えることができるでしょう。
これらの原則に加えて、DAICフレームワークでは、AIコーチを設計する際に人間のコーチングの効果性に関する4つの原則も考慮することを提案しています。それは、「コーチ・クライエント関係の重要性」「エビデンスに基づく理論モデルの使用」「倫理的な実践」「狭いコーチングの焦点」です。
とりわけAIコーチングでは、人間のコーチのように広範囲の問題に対応することは難しいため、特定の狭い範囲の課題(例えば目標達成や行動変容など)に焦点を絞ることが有効です。AIの限界を認識し、得意分野に特化することで、より質の高いコーチングを提供することができるでしょう。
通話分析で指導を効率化する
AIコーチングの効果を高める三つ目の条件は、AIの分析能力を活用してコーチングの対象を効率的に選定することです。組織内でのコーチングにおいて、誰に、いつ、どのようなコーチングを提供するかという点は重要です。AIの分析力を活用することで、コーチングのタイミングと内容を見極めることができるようになります。
その好例が、コンタクトセンターにおけるAIを活用した通話分析システムです[3]。「AI Coach Assist」と呼ばれるこのシステムは、オペレーターの通話内容を自動的に分析し、コーチングが必要な通話を推薦する機能を持っています。
コンタクトセンターでは、オペレーターのスキル向上のために定期的なフィードバックやコーチングが有効です。しかし、日々膨大な数の通話が行われる中で、どの通話を評価し、どのような点をコーチングすべきかを人手で選ぶのは時間がかかります。このような課題に対して、AIによる通話分析が役立ちます。
AI Coach Assistは、自然言語処理(NLP)と高度な言語モデルを用いて、通話の書き起こしテキスト(トランスクリプト)を分析します。システムはマネージャーが設定した評価基準に基づいて、各通話が「コーチングが必要か否か」を判定し、コーチングの優先度が高い通話を自動的に推薦します。
例えば、「オペレーターは顧客を名前で挨拶したか」「本人確認を適切に行ったか」「問題解決のために必要な情報を収集したか」といった様々な基準に基づいて、各通話を評価します。オペレーターのパフォーマンスが基準を下回る通話が「コーチングが必要」と判断され、マネージャーに推薦されます。
実際の研究では、DialogLEDとDistilBERTという2種類の言語モデルが比較されました。より複雑なDialogLEDモデルの方が高い精度(70%超)を示し、特に「挨拶」や「本人確認」といった基本的な項目での判定精度が高いことが明らかになりました。一方で「行動的要素」や「問題解決」など複雑な評価項目では、まだ課題が残されています。
このようなAI通話分析システムの導入によって、コーチングが必要な通話を効率的に見つけ出し、オペレーターに的確なフィードバックを提供することができます。ランダムに通話を選んでいた従来の方式に比べ、コーチングが必要な場面に焦点を当てることで、限られた時間とリソースを最大限に活用することができます。
このように、AIの分析能力を活用することで、コーチングの効率と効果を飛躍的に高めることができます。AIと人間のマネージャーが協力しながら、組織全体のパフォーマンス向上を図ることが、これからのAIコーチングの方向性の一つかもしれません。
画像効果が個人差で異なる
AIコーチングの効果を高める四つ目の条件は、視覚情報の効果的な活用です。テキストによるコミュニケーションだけでなく、画像を併用することでAIコーチングの効果が高まる可能性があります。ただし、画像の効果は一律ではなく、個人によって異なることが分かってきました。
コーチングチャットボットにおける画像の効果を調査した研究では、テキストのみのチャットボット(TextBot)とテキスト+画像のチャットボット(ImageBot)を比較する実験が行われました[4]。この実験では、ユーザーの目標達成度や技術採用(チャットボットの受け入れ度合い)に加えて、ユーザーの視覚的・言語的情報処理の好み(個人差)が結果にどう影響するかを検証しています。
まず全体的な結果として、両方のチャットボットともに1週間後の目標達成度が向上したものの、テキスト型と画像付き型の間で有意な差は見られませんでした。また、技術採用に関する多くの指標(パフォーマンス期待や楽しさなど)でも、両者の間に明確な違いは見られませんでした。
しかし、この研究で最も興味深いのは、ユーザーの個人的な認知特性によって画像の効果が異なることが明らかになった点です。
例えば、「想像力(Imagination)」が低い人は、画像付きチャットボット(ImageBot)を利用する際に高い努力を要し、使用意図が低下する傾向がありました。これは直感に反するようにも思えますが、想像力が低い人にとっては、提供される画像と自分自身の目標や状況を結びつけることが難しく、かえって認知的負荷が増す可能性があります。
一方、「正しい言語使用(Correct word usage)」を重視する人は、テキストのみのチャットボットをあまり楽しく感じない傾向がありました。言語的な正確さを求める人にとっては、チャットボットのテキストだけのコミュニケーションが不十分と感じられるのかもしれません。
これらの発見は、「二重符号化理論(Dual-code Theory)」と呼ばれる理論とも関連しています。この理論によれば、人間の情報処理は「言語的処理」と「視覚的処理」の二つの独立したシステムで行われており、両方を組み合わせることで理解や記憶、問題解決が促進されるとされています。しかし、この研究結果は、その効果が個人の認知的特性によって左右されることを示唆しています。
これらの知見から、AIコーチングにおいては画像の一律な追加が必ずしも効果的ではなく、ユーザーの個人特性に合わせたカスタマイズが重要であることが分かります。例えば、想像力が豊かな人には抽象的な画像を、言語処理を好む人には詳細なテキスト説明を、といったように、個人の認知スタイルに合わせた情報提供が効果的でしょう。
音声対話で運動を促進する
AIコーチングの効果を高める五つ目の条件は、双方向性のコミュニケーションが可能な音声対話の活用です。特に健康促進や行動変容を目的としたコーチングでは、音声を介したAIとの対話が効果をもたらすことが分かってきました。
過体重または肥満で運動不足のがんサバイバー(主に乳がんサバイバー)を対象にした研究では、身体活動を促進するための2種類のAIコーチング介入が比較されました[5]。一つはスマートスピーカー(Amazon Echo)を通じた音声対話型のAIコーチ「MyCoach」、もう一つは自動テキストメッセージを用いたAIコーチ「SmartText」です。これらは、健康情報提供のみを行ったコントロール群と比較されました。
4週間の介入の結果、音声対話型のMyCoach群は1日あたりの平均歩数が3,618歩も増加し、コントロール群よりも平均3,568.9歩、SmartText群よりも平均2,160.6歩多い結果となりました。また、1日10,000歩以上を達成した割合もMyCoach群が61%と最も高く、SmartText群の41%、コントロール群の28%を大きく上回りました。
なぜ音声対話型のAIコーチが効果的だったのでしょうか。研究者たちは、その理由として「双方向性(bidirectional)」のコミュニケーションが重要だと考察しています。
音声対話型のMyCoachでは、ユーザーが自分の望むタイミングで能動的に対話を求めることができます。「Alexa、マイコーチを開いて」と呼びかければ、いつでもAIコーチと対話することができるのです。この能動的な参加が、モチベーションの維持につながったと考えられます。
一方、テキストメッセージ型のSmartTextは一方的に送信されるメッセージであり、ユーザーの主体性を十分に活用できませんでした。確かに初期には歩数の増加が見られましたが、その効果は時間とともに薄れていきました。
音声対話には他にもいくつかの利点があります。まず、手を使わずに対話できるため、運動中や家事をしながらでも利用しやすいという実用性があります。また、人間の自然な会話に近い形でコミュニケーションできるため、親しみやすさも高まります。さらに、声のトーンや間合いなどを通じて、テキストよりも豊かなコミュニケーションが可能です。
脚注
[1] Mai, V., Neef, C., and Richert, A. (2022). “Clicking vs. Writing”? The impact of a chatbot’s interaction method on the working alliance in AI-based coaching. Coaching | Theorie & Praxis, 8(1), 15-31.
[2] Terblanche, N. (2020). A design framework to create artificial intelligence coaches. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 18(2), 152-165.
[3] Laskar, M. T. R., Chen, C., Fu, X.-Y., Azizi, M., Bhushan, S., and Corston-Oliver, S. (2023). AI Coach Assist: An automated approach for call recommendation in contact centers for agent coaching. In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 5: Industry Track) (pp. 599-607). Association for Computational Linguistics.
[4] Terblanche, N. H. D., and Prywes, Y. (2025). An exploration of the role of visuals and users’ imagery and verbal preferences on goal attainment and coaching chatbot adoption. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 23(1), 205-221.
[5] Hassoon, A., Baig, Y., Naiman, D. Q., Celentano, D. D., Lansey, D., Stearns, V., Coresh, J., Schrack, J., Martin, S. S., Yeh, H.-C., Zeilberger, H., and Appel, L. J. (2021). Randomized trial of two artificial intelligence coaching interventions to increase physical activity in cancer survivors. npj Digital Medicine, 4, 168.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。