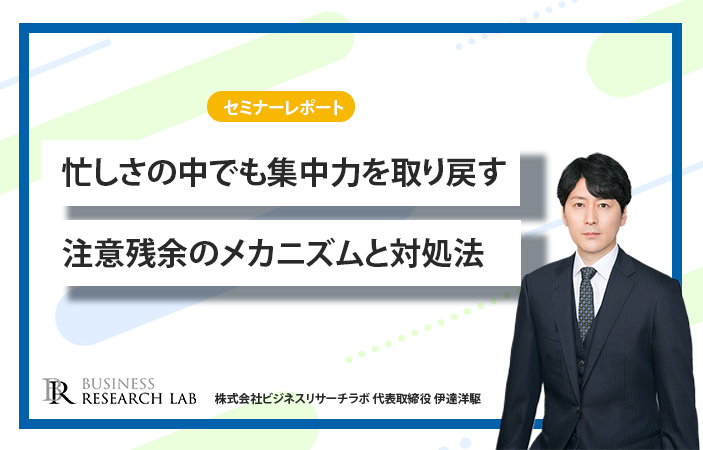2025年8月6日
忙しさの中でも集中力を取り戻す:注意残余のメカニズムと対処法(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年7月にセミナー「忙しさの中でも集中力を取り戻す:注意残余のメカニズムと対処法」を開催しました。
メール確認、会議、電話対応など、様々な業務の切り替えや中断が日常的に発生しています。このような環境で「頭がすっきりしない」「次の作業に集中できない」という状態に陥ったことはありませんか。
これは、心理学的には「注意残余」と呼ばれる現象です。一つの業務から次の業務へ移行する際、前の作業の記憶や思考が残り続け、新たな業務への集中力や生産性を低下させています。
本セミナーでは、ビジネスリサーチラボ代表取締役の伊達洋駆が、注意残余のメカニズムとその影響について、最新の研究知見をもとに解説しました。なぜ作業の中断や未完了のタスクが私たちの認知機能を低下させるのか、マルチタスクが生産性と正確性にどのような影響を与えるのか、そして職場での中断やタスク切替がもたらすストレスと睡眠への影響について理解を深めることができます。
組織全体の生産性向上と社員のメンタルヘルス維持の両立は重要な課題です。本セミナーでは、注意残余を軽減するための職場環境デザインやタスク管理についても考えました。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
従業員の集中力は、生産性や創造性を左右する重要な経営資源です。しかし、絶え間なく届く通知、頻繁な会議、そして複数の業務を同時にこなすことが常態化した働き方は、この貴重な資源を蝕んでいます。なぜ、私たちはこれほどまでに集中を妨げられるのでしょうか。
本講演では、この問いに答えるため、認知科学や心理学の研究知見を基に、集中力を奪う「作業中断」や「注意残余」といった現象のメカニズムを掘り下げます。従業員のパフォーマンスを最大化し、ウェルビーイングを向上させるための打ち手を考える一助となれば幸いです。
現代の働き方と集中力の危機
私たちの仕事は、今、驚くほど細切れになっています。ある観察調査では、情報労働に従事する人々は、平均してわずか3分ごとに異なる作業へと切り替えているという実態が報告されました[1]。これは、アナリストや開発者、マネージャーといった専門職の従業員を対象に、研究者が背後から一日中の行動を記録するという手法で明らかになった事実です。さらに、共通の目的を持つ一連の活動のまとまりである「ワーキングスフィア」と呼ばれる、より大きな仕事の単位でさえ、平均12分で別のものに切り替わっていました。
興味深いのは、作業が中断される原因です。調査によれば、同僚からの声かけや電話といった「外的中断」と、自らの判断で別の作業に移る「内的中断」の発生頻度は、ほぼ同じでした。この事実は、集中力の問題を個人のスキルや意識だけの責任に帰すことの危うさを示唆しています。過剰な業務量や不明確な役割、あるいは「いつ邪魔が入るかわからない」という不安感が、従業員を自ら作業を切り替える行動へと駆り立てている可能性もあるからです。
このような割り込みは、私たちの生産性と精神面に影響を及ぼします。ある実験研究では、主たる課題の途中で割り込みを受けると、タスクを完了するまでの時間が長くなり、特に複雑な課題でその悪影響が顕著になることが示されました[2]。
頻繁な割り込みは、全体のエラー数を約2倍に増加させることもわかっています。これは、割り込みそのものだけでなく、「いつ割り込まれるかわからない」という予期不安が、私たちの注意力を削いでしまうためです。心理的にも、作業途中の割り込みはイライラといった不快感を増大させ、実験後にも続く不安感を高めることが確認されています。
一方で、割り込みがある環境では、逆説的に作業スピードが上がるという現象も報告されています。別の実験では、割り込みにさらされた参加者は、より速く、より短いメールを書くといった戦略をとることで、課題完了時間を短縮させました[3]。
しかし、その代償は大きく、精神的な負荷やストレス、フラストレーションは増加していました。これは、短期的な反応速度と引き換えに、仕事の質と従業員の精神的健康という、より重要なものを犠牲にしている状態と言えるでしょう。人事マネジメントは、この見えにくいコストを認識し、集中力を守るための環境設計に目を向ける必要があります。
中断が奪う時間と生産性
「少し中断しただけ」のはずが、なぜか仕事が思うように進まない。多くの人が日常的に抱くこの感覚は、決して気のせいではありません。ある調査では、情報労働者が経験する作業の切り替えは週に平均50回にものぼり、一度中断されてから再開されたタスクは、中断なく進められたタスクに比べて、完了までに平均で2倍以上の時間を要することが明らかになりました[4]。これは、証券ブローカーから大学教授まで、多様な職種の人々を対象とした調査で得られた結果です。
なぜ、中断後の作業再開はこれほどまでに困難なのでしょうか。その背景には、私たちの認知的な負担があります。作業を中断すると、私たちは「後で何をしようとしていたか」を思い出す「将来記憶」に頼らざるを得ませんが、頻繁な中断はこの記憶の失敗を招きます。さらに、元の作業に戻るためには、以前の思考の文脈、例えば「どの資料のどの部分を、どういう意図で編集していたか」といった複雑な状況を脳内で再構築する「再オリエンテーション」というプロセスが必要となり、これが大きな認知的負荷となるのです。
多くの職場では、タスクの所要時間を見積もる際に、この「中断・再開コスト」という巨大な見えないコストが見過ごされがちです。プロジェクトの遅延や恒常的な残業の原因は、従業員の能力不足ではなく、計画段階におけるこの構造的な楽観主義にもあるかもしれません。
この問題は、タスクを切り替える瞬間の脳の働きを調べる実験研究によって、深く理解できます[5]。ある認知課題から別の課題へ切り替える際には、反応時間の遅延やエラー率の増加といった「切替コスト」と呼ばれるパフォーマンスの低下が発生します。これは、私たちの脳が、前の課題を実行するために形成していた特定の心的態勢、すなわち「認知セット」を一旦抑制し、新しい課題のための認知セットを活性化させる「認知の再構成」というプロセスを必要とするためです。この認知の再構成には、どうしても時間と精神的なエネルギーが費やされてしまいます。
事前に「次は別のタスクです」と準備する時間があれば、この切替コストはある程度は減少します。しかし、研究が示すのは、どれだけ準備をしてもコストは決してゼロにはならないという厳しい現実です。課題が複雑であればあるほど、認知セットの再構成に要する資源は増大し、切替コストは大きくなります。
「5分だけいいですか」という短い中断が、実際には認知の再構成という見えない時間を奪い、タスクの完了を10分以上も遅らせる可能性があるのです。
中断の「質」を考える
すべての作業中断が、等しく有害なわけではありません。中断がもたらすダメージの大きさは、その「質」によって左右されます。どのような中断が特に破壊的なのでしょうか。
ある実験研究は、作業再開の妨害度を決定づけるのは、割り込みの時間の長さよりも、その「類似性」と「複雑さ」であると結論づけています[6]。例えば、記憶力が求められる作業の最中に、別の記憶課題で中断されると、脳内で似た情報処理が混乱しあう「認知的干渉」が起こり、元の作業への復帰が困難になります。同様に、割り込みタスク自体が複雑な思考を要するものであればあるほど、主作業に戻るための認知的負荷は増大します。
中断の「予測可能性」も重要です。予告なく突然タスクが切り替わると、直後の反応速度は大幅に遅れ、エラー率も増加することが実験で示されています[7]。締め切りが迫るような高い時間的プレッシャーのもとでは、参加者は速度を優先するあまり精度を犠牲にする「スピードと精度のトレードオフ」に陥りやすくなります。
また、このような予期せぬ切替時には、古いルールを新しいタスクに誤って適用してしまう「侵入」や、新旧のルールを混ぜてしまう「混同」といった特有のエラーが観察されます。これは、古いタスクの認知セットが完全に抑制されず、新しいルールと競合するために起こる現象です。
では、次にどのタスクを行うかが完全に予測可能であれば、問題は解決するのでしょうか。残念ながら、そうではありません。たとえ次にやるべきことがわかっていても、タスクを切り替える行為そのものには、避けられない「残余的切替コスト」が存在することがわかっています[8]。
準備時間が長ければコストは減りますが、ゼロにはなりません。これは、タスク切替のプロセスが、意識的に準備できる「目標の再設定」段階と、実際の刺激(例えば、画面に表示される課題)を見てからでないと完了できない「刺激依存的再構成」段階の二つに分かれているためです。頭でいくら準備をしても、脳のシステムが完全に切り替わるには、実際の行動がトリガーとなるのです。
さらに、中断される「タイミング」も重要です。「あと少しで終わる」という目標達成間近のタイミングで中断されると、私たちの衝動や欲求をコントロールする「自己制御資源」が激しく消耗されることが、一連の実験で実証されています[9]。目標達成が近づくほどタスクへの意欲が高まる「目標勾配」という現象により、私たちは終了間近の作業を続けようと強く思います。その強い動機を無理に抑えつけて中断を受け入れるために、多大な精神的エネルギーが消費され、その後の注意力や粘り強さが低下してしまいます。
一度中断された作業効率は、すぐには元に戻りません。研究によれば、中断後の回復には一定のパターンがあり、最初の反応は非常に遅く、そこから徐々に元のスピードへと回復していきますが、完全に安定するまでには時間がかかります[10]。この回復プロセスは、中断によってバラバラになった思考の文脈を、一つひとつ連想的に記憶から取り戻していく「累積プライミング」というモデルで説明されています。
これらの知見は、人材マネジメントが管理すべきは目に見える時間だけでなく、「見えない認知コスト」であり、中断の「量」だけでなく、その破壊的な「質」を見極め、制御する必要があることを示唆しています。
マルチタスクの神話
これまでのところでは、主に外部からの「割り込み」が集中を妨げる状況を見てきました。しかし、私たちの集中を阻むのは、外的な要因だけではありません。むしろ、自ら複数のタスクを同時にこなそうとする「マルチタスク」も、現代の働き方を象徴する光景であり、多くの職場では効率性や能力の証として賞賛されています。しかし、その認識は本当に正しいのでしょうか。効率性の代名詞ともいえるマルチタスクの裏に隠された、意外な真実を探っていきます。
ある研究は、この通説に疑問を投げかけました[11]。日常的に複数のメディアを同時に使用する「メディアマルチタスク」を頻繁に行う人々(HMM)と、そうでない人々(LMM)の認知能力を比較しました。その結果、複数の情報を巧みに操っているはずのHMMの人々ほど、実際には、①環境の中の無関係な情報を無視すること、②記憶の中の無関係な情報による干渉を抑えること、そして③異なる課題間をスムーズに切り替えること、のすべてが苦手だったのです。マルチタスクの実践は、その能力の向上につながるどころか、基本的な認知制御能力の低さと関連している可能性が示されました。
さらに衝撃的なのは、マルチタスクを頻繁に行う人ほど、実際の能力が低いにもかかわらず、自身のマルチタスク能力を過大評価しているという事実です。ある調査では、参加者の約70%が自分のマルチタスク能力を「平均より上」と信じていましたが、客観的な能力測定の結果と自己評価の間には何の関連も見られませんでした[12]。
では、なぜ彼らは非効率な行動を好むのでしょうか。研究は、その背景に「衝動性」と「刺激追求性」という二つの心理的特性があることを突き止めています。一つのことに集中し続けるのが苦手な人(注意的衝動性が高い人)や、常に新しい刺激を求める人ほど、マルチタスクに陥りやすい傾向があったのです。
マルチタスクは生産性にどのような影響を与えるのでしょう。ある実験では、マルチタスキングの程度と生産性(完了した課題の量)の関係は、中程度で最も高くなる「逆U字型」を描くことが示されました[13]。単一作業の退屈さを防ぐ適度な刺激が生産性を高める一方で、切り替えが多すぎると認知資源を消耗し、かえって生産性が落ちます。しかし、より重要なのは「正確性」です。作業の正確性は、マルチタスクが増えれば増えるほど、一貫して直線的に低下する傾向が見られました。
これらの知見は、私たちに三つの示唆を与えます。第一に、常にオンラインで複数の案件を同時に動かしているように見える従業員は、賞賛の対象ではなく、むしろ非効率な働き方によって注意散漫になっている「要注意対象」かもしれないという、「できる人」の再定義です。
第二に、集中できない環境がマルチタスクを誘発するという視点です。従業員の特性を責めるのではなく、鳴りやまない通知音や頻繁な声かけといった、集中を阻害する環境要因を取り除くことが、本質的な解決策となります。
そして第三に、職務特性に応じた「働き方のポートフォリオ」の必要性です。高い精度が求められる職務ではマルチタスクを徹底的に排除し、逆に迅速な対応が求められる職務ではある程度許容するなど、画一的でない、柔軟な働き方をデザインしていくことが求められます。
「やり残した仕事」の呪縛
作業中の集中をいかに守るか。先ほどまでは、その敵として「中断」や非効率な「マルチタスク」を扱ってきました。しかし、仕事が私たちの心に与える影響は、パソコンを閉じた瞬間に消えてなくなるわけではありません。その日にやり遂げられなかった「未完了の仕事」は、見えない重荷となって私たちの心に残り、休息の時間さえも侵食していきます。ここでは、この「やり残した仕事」という名の亡霊がもたらす「注意残余」のメカニズムと、その呪縛から心を解放する方法を解き明かします。
私たちの心は、一度始めたことを完了させたいという「完了への欲求」を持っています。そのため、タスクを途中で中断せざるを得ないとき、その未完了のタスクは意識下に残り続け、次の仕事への集中力を奪います。この現象は「注意残余」と呼ばれます。ある実験では、最初のタスクを完了させずに次のタスクに移った参加者は、意欲もパフォーマンスも低下することが示されました[14]。未完了の仕事が、貴重な認知資源を消費し続けてしまうのです。
この影響は、職場を離れた後も続きます。ドイツで行われた長期的な調査では、週末に持ち越された未完了タスクが多い人ほど、その仕事について否定的に考え続ける「感情的反芻」に陥りやすく、睡眠の質が悪化することが明らかになりました[15]。特に、この状態が慢性化すると、未完了タスク自体が睡眠障害の強力な原因となり得ます。
これは、休息が単に「何もしない」ことでは得られず、一日の仕事を精神的に「完了」させ、健全に休息へと移行するための「認知的な区切り」がいかに重要かを教えています。
この「やり残した仕事」の呪縛から逃れる術はないのでしょうか。ヒントが示されています。それは「具体的な計画を立てる」ことです。ある一連の実験では、未達成の目標について、それを「いつ、どこで、どのように実行するか」という具体的な計画を立てるだけで、その目標に関する思考が自然と頭に浮かばなくなることが実証されました[16]。さらに、この認知的な負担を軽減する効果は、実際にタスクを完了させた場合とほぼ同程度でした。
このメカニズムは、計画を立てるという行為が、脳に対して「この件は、この手順で処理することが決まったので、もう意識的に考え続けなくても大丈夫だ」という指令を与えるためだと考えられています。目標の追求が、意識的な思考から無意識的・自動的なプロセスへと委ねられるのです。
私たちは計画を、未来の行動を規定するためのツールだと考えるかもしれません。しかし、計画には「現在の心を解放する」という、強力で即時的な機能もあるのです。従業員が未完了の仕事のことで頭を悩ませているとき、必要なのは根性論ではなく、次の一歩を記すための、ほんの数分の時間なのかもしれません。
おわりに
本講演を通じて、集中力の問題が個人の意欲や能力といった資質の問題だけではなく、現代の働き方そのものに根差した構造的な課題であることを、様々な研究知見から明らかにしてきました。3分ごとに思考が分断され、見えない「切替コスト」を支払い続け、退勤後も「注意残余」によって休息を奪われる。これが、多くの従業員が直面している現実です。
私たちに求められる役割は、こうした「見えない認知コスト」の存在を組織全体で認識し、それを管理可能なものへと変えていくことです。それは、コミュニケーションのルールを見直すことかもしれませんし、通知の来ない「集中時間」を制度として導入することかもしれません。あるいは、一日の終わりに「未完了タスクの計画」を立てる数分間を文化として根付かせることかもしれません。
重要なのは、従業員一人ひとりが集中力を維持し、その能力と創造性を発揮できるような環境を、科学的知見に基づいて設計していくという視点でしょう。
Q&A
Q:リモートワークでは同僚からの声かけといった物理的な中断は減りますが、チャット通知などデジタルな中断は増えていると感じます。オフィス勤務とリモートワークとでは、注意が散漫になるメカニズムに違いはあるのでしょうか。
この問題は、本日お話しした内容を基に考察できます。リモートワークでは、周りの人の動きや会話といった「外的中断」は起こりにくくなります。これはリモートワークの利点でしょう。
しかしその一方で、自分自身の内面から生じる「内的中断」は起こりやすくなるかもしれません。オフィスであれば周囲の目があるため、自然と「集中しなければ」という意識が働きます。しかし自宅ではそのプレッシャーが薄れるため、つい仕事と関係のない作業に手を出してしまうことがあります。また、孤独感から無意識に他者とのつながりを求め、不要不急のチャットを送ってしまうなど、自ら集中を妨げる行動を取ることもあります。
Q:私の仕事は1ヶ月サイクルで、案件を一人で抱えるため、常に仕事のことで頭がいっぱいです。この大変さを同僚に理解してもらえず、集中している時に頻繁に声をかけられて困っています。どうすればこの状況を分かってもらえるのでしょうか。
この問題には、ご自身でできる対策と、周囲に協力を求める工夫の二つの側面からアプローチできます。
まずご自身でできる対策として、「計画を立てる」ことが重要です。1ヶ月という大きな仕事をそのまま捉えると、「まだ終わっていない」という感覚がずっと続き、心が休まりません。そこで、仕事を具体的な小さなステップに分解するのです。「今日はここまで」というゴールを決め、完了させることで、脳はそのタスクを心理的に手放すことができます。
次に、周囲に協力を得る工夫です。誰にでも集中を妨げられて困った経験はあるはずなので、「お互いの生産性を高めるために協力しませんか」という前向きな姿勢で伝えれば、理解を得やすくなると思います。
Q:「マルチタスクを好む人ほど、自身の能力を過大評価している」という話に衝撃を受けました。もし部下や同僚にそのような傾向が見られた場合、本人の納得感を得ながら行動を変えてもらうには、どうフィードバックすればよいでしょうか。
相手の納得感を引き出すことが鍵となります。ここで避けるべきなのは、「あなたのやり方は非効率だ」と頭ごなしに否定することです。反発を招くだけで、行動変容にはつながりません。
重要になるのは、主観的な評価ではなく「客観的な事実」に基づいて対話することです。例えば、「AとBのタスクを同時に進めた結果、Aの納期が少し遅れましたね。もしAだけに集中していたら、どうなったと思いますか」というように、本人に内省を促す問いかけをします。これは相手を責めるのではなく、あくまで仮説を一緒に考えるというスタンスです。
そして本人に気づきが見えたら、「次は実験的に、一つのタスクを一気に終わらせてみませんか」と提案します。本人が自ら考え、行動を選択するというプロセスを尊重し、その結果をまた一緒に振り返る。このような対話を繰り返すことで、納得感を伴った行動変容を促せるのではないでしょうか。
Q:やり残した仕事の計画を立てることは有効だと分かりましたが、その計画自体が「守らなければ」という新たなプレッシャーになることはないのでしょうか。
ご指摘の通り、計画が新たなストレス源になる可能性は十分にあります。そうならないためには、計画との向き合い方を変えることが大切です。
計画を「完璧に遂行すべき厳格なノルマ」と捉えると、大きなプレッシャーになります。そうではなく、計画はあくまで「現時点での見通し」であり、「頭の中を整理するための道具」くらいに捉えてみてください。目的は、思考をクリアにして目の前のことに集中することです。明日以降の自分への単なる「引き継ぎメモ」と考えれば、もっと気軽に立てられるはずです。
もし管理職の立場で部下に計画を勧めるなら、プレッシャーを和らげる声かけが重要です。「計画通りに進まなくても問題ないから、まずは明日一番に取り組むことだけ決めてみよう」といった言葉を添えることで、計画が持つプレッシャーを和らげ、有効なツールとして活用してもらえるでしょう。
脚注
[1] Gonzalez, V. M., and Mark, G. (2004). “Constant, constant, multi-tasking craziness”: Managing multiple working spheres. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 113-120). ACM.
[2] Bailey, B. P., and Konstan, J. A. (2006). On the need for attention-aware systems: Measuring effects of interruption on task performance, error rate, and affective state. Computers in Human Behavior, 22(4), 685-708.
[3] Mark, G., Gudith, D., and Klocke, U. (2008). The cost of interrupted work: More speed and stress. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 107-110). ACM.
[4] Czerwinski, M., Horvitz, E., and Wilhite, S. (2004). A diary study of task switching and interruptions. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 175-182.
[5] Rubinstein, J. S., Meyer, D. E., and Evans, J. E. (2001). Executive control of cognitive processes in task switching. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 27(4), 763-797.
[6] Gillie, T., and Broadbent, D. (1989). What makes interruptions disruptive? A study of length, similarity, and complexity. Psychological Research, 50(4), 243-250.
[7] Cellier, J.-M., and Eyrolle, H. (1992). Interference between switched tasks. Ergonomics, 35(1), 25-36.
[8] Rogers, R. D., and Monsell, S. (1995). Costs of a predictable switch between simple cognitive tasks. Journal of Experimental Psychology: General, 124(2), 207-231.
[9] Freeman, N., and Muraven, M. (2010). Don’t interrupt me! Task interruption depletes the self’s limited resources. Motivation and Emotion, 34(3), 230-241.
[10] Altmann, E. M., and Trafton, J. G. (2007). Timecourse of recovery from task interruption: Data and a model. Psychonomic Bulletin & Review, 14(6), 1079-1084.
[11] Ophir, E., Nass, C., and Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(37), 15583-15587.
[12] Sanbonmatsu, D. M., Strayer, D. L., Medeiros-Ward, N., and Watson, J. M. (2013). Who multi-tasks and why? Multi-tasking ability, perceived multi-tasking ability, impulsivity, and sensation seeking. PLoS ONE, 8(1), e54402.
[13] Adler, R. F., and Benbunan-Fich, R. (2012). Juggling on a high wire: Multitasking effects on performance. International Journal of Human-Computer Studies, 70(2), 156-168.
[14] Leroy, S. (2009). Why is it so hard to do my work? The challenge of attention residue when switching between work tasks. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109(2), 168-181.
[15] Syrek, C. J., Weigelt, O., Peifer, C., and Antoni, C. H. (2016). Zeigarnik’s sleepless nights: How unfinished tasks at the end of the week impair employee sleep on the weekend through rumination. Journal of Occupational Health Psychology, 22(2), 225-238.
[16] Masicampo, E. J., and Baumeister, R. F. (2011). Consider it done! Plan making can eliminate the cognitive effects of unfulfilled goals. Journal of Personality and Social Psychology, 101(4), 667-683.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。